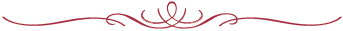戦国武将の評価は、おぼろげなものです。
梟雄としてお馴染みの斎藤道三が、実は親子二代で下剋上を果たしていたことが大河『麒麟がくる』でも描かれたり。
かつてフィクション作品で残虐無道に描かれがちだった織田信長の人間的な側面が見直されたり。
虚構の存在かと危ぶまれていた山本勘助の実在が証明されたり。
史料の発見や見方一つで劇的に変わるものですが、今なお人によって大きく評価の分かれる戦国大名がおります。
大友宗麟(義鎮)――。
キリシタンでお馴染みの宗麟は、九州の半分を制圧した超デキる人と称賛されることもあれば、非道な行為を繰り返し最後は滅亡しかけた暗君だと指摘する声もある戦国大名です。
いったい宗麟とはどんな人物だったのか。
その生涯を追ってみましょう。
お好きな項目に飛べる目次 [とじる]
待望の嫡男だった大友宗麟(大友義鎮)
大友宗麟(大友義鎮)は享禄3年(1530年)1月3日、大友家当主・大友義鑑(よしあき)の長男として生まれました。
母は大内義興(よしおき)の娘。
この母の確かな出自からして、最初から家を継ぐ嫡男として期待されていたようです。
父の義鑑が当時としては高齢の30歳を過ぎてから授かった待望の子宝であり、「御曹司」のような扱いを受けていたとか。
後世の軍記物にみられる宗麟の特徴としては、「武芸を好み、学問には興味を示さなかった荒々しい少年」というような記載が目立ち、よく言えばわんぱく、悪く言えば乱暴な少年像が浮かんできます。
以後、すくすくと成長していった宗麟ですが、天文19年(1550年)、彼の人生を一変させる事件が起きます。
父・義鑑が家臣二名の襲撃によって重傷を負わされ、間もなく死去するという【大友二階崩れの変】が勃発したのです。
父の死によって、嫡男である宗麟が家督を継承することになりました。
通常、父が暗殺されたとあれば、嘆き悲しむのが息子の姿でしょう。ところが、この事件はそう単純なものでもありません。
父の死と家督継承の裏側では、大友家中に渦巻いていた「お家騒動」が関係していたのです。
大友二階崩れの変 その真実は?
実は父の義鑑(よしあき)はその頃、予定通り宗麟に家督を継承させる気を失っておりました。
後から生まれた三男・塩市丸(しおいちまる)をいたく気に入り、宗麟を廃嫡したうえで彼に家督を継承しようと考えていたようでした。
塩市丸の後ろ盾には、側室であった塩市丸の母や家臣・入田親廉らの勢力がおり、義鑑に家督継承を後押ししていたのです。
しかし、この風潮を知った宗麟派の家臣たちは当然黙っていられません。
宗麟の廃嫡に公然と反対した重臣は4人いたと言われ、なんとそのうちの2名が義鑑によって殺害されていたのです。
残された津久井美作守と田口新蔵人両名は、
「このままジッとしていれば俺たちに明日はない」
と考えたのでしょう。
彼らは一か八かの賭けに出ました。
宗麟が湯治のため本拠を離れた隙に義鑑を斬り、かつ塩市丸やその母などをまとめて殺害したのです。
切られた義鑑は息も絶え絶えながら「宗麟に家督継承を継がせる」という遺言を作成し、程なくして亡くなったと伝わります。
大友二階崩れの変は、一般的に「わがままな宗麟が義鑑に嫌われ、聡明な塩市丸が代わりに推挙された」というような説明がされがちです。
しかし実情は、好き嫌いの問題ではなく「大友家の家臣も絡んだ権力闘争」というのが妥当に思えます。
一見すると、宗麟は事件に関与していないようにも見えますが怪しいですよね。
なんせ事件により最も得をした一人が宗麟です。
遺言を含む事後処理などがあまりにもスムーズだったことから、すべて宗麟の手によって仕組まれた事件という指摘も存在します。
叔父・菊池義武の挙兵
血みどろの家督継承争いを制して、大友家の当主となった宗麟。
最初に着手したのは、入田親廉(いりたちかかど)ら塩市丸派を含む反対勢力の一掃でした。
家臣の斎藤鎮実や立花道雪らに命じて入田家の居城を攻めさせると、入田親廉・入田親誠(ちかざね)親子は親戚にあたる阿蘇惟豊(あそこれとよ)を頼って落ちのびようとします。
が、親廉は居城で切腹。あらかじめ宗麟と結んでいた惟豊の手によって親誠も討たれることになりました。
親廉は大友家の中でも重要な役職である加判衆(かはんしゅう)を21年も歴任した重臣であり、宗麟からしてみれば実権を握る敵対的な有力者を首尾よく粛清したことになります。
この流れからして大友二階崩れは宗麟にとって「好ましい出来事」だったことが見て取れますね。
しかし、身内の絡んだトラブルは続きます。
かつて父・義鑑と争い、肥前国へ亡命していた叔父の菊池義武が、二階崩れ後の混乱に乗じて挙兵したのです。
当初は菊池勢に押される展開となるものの、家臣らの活躍や敵方の内応によってこれに勝利。
敗北した義武は親戚である相良氏を頼って落ちのびますが、天文23年(1554年)に宗麟から「和睦」と称して呼び出され、自害に追い込まれた(あるいは殺害された)と伝わります。
なにやら血生臭い――そうした状況はまだ続きます。
隣国・大内家でクーデター勃発
かくして着実に反対勢力を排除していく宗麟。
そのころライバルだった中国地方の雄・大内家でも御家を揺るがす大事件が起きていました。
天文20年(1551年)、当主の大内義隆が家臣・陶晴賢によるクーデターで滅ぼされたのです。

-
西国一の戦国大名だった大内義隆がなぜ滅んだ?45年の生涯まとめ
続きを見る
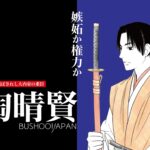
-
戦国大内家の重臣・陶晴賢はなぜ下剋上を起こし毛利に滅ぼされたか
続きを見る
【大寧寺の変】と呼ばれ、この一件は大友家にも非常に影響がありました。
宗麟の弟・大友晴英(はるひで)を大内家の当主にしないか?
と、陶晴賢から打診されたのです。
大友晴英の母は大友義興の娘(宗麟と同じ)であるからして、大内家にとっても深い繋がりがあり、過去にも「大内家の跡継ぎにならないか」という話がありました。
その話も一度はご破算になっていたのですが、陶晴賢のクーデターにより事情が一変。君主不在となった大内家へ再び要請されたのです。
宗麟は当初、この申し出に反対でした。
理由は極めて単純。陶晴賢が欲しているのはお飾りとしての大内家当主であり、弟の晴英が大内家に入っても操り人形になることが明白だったからです。
それでも当の晴英本人が「たとえ一時であっても大内家を継ぎたい!」と強固に主張したため、最終的には宗麟もこれを許し、晴英は名前を「大内義長」に変えて大内家へと入りました。
結論からいえば、宗麟の危惧通り弟の義長は晴賢の傀儡となってしまいます。
しかしメリットも大きいものでした。
大内氏から攻撃される懸念が激減したことで他の敵対勢力排除に注力することができたのです。
宗麟は天文22年(1553年)、少弐氏が衰退していたことを上手く利用して、彼らの治めていた肥前国守護職を得たほか、他にも家内の内紛を上手く鎮圧して統率力の強化を成し遂げました。
毛利と盟約を交わし弟を見捨てた?
新たに肥前守護となった宗麟は、続いて豊前・筑前といった北九州に攻略の矛先を向けました。
このころ中国地方では大内氏に代わって毛利氏が勢力を拡大させており、宗麟の弟・義長は毛利元就の侵攻に苦しんでいました。
続きを見る

毛利元就の手腕鮮やか!どんな策や合戦で中国地方8カ国を支配した?
当然、兄に対し救援を懇願します。
「大内が危ないです。助けてください!」
ところが宗麟は、あえて大掛かりな援軍を行いません。
結果、弘治元年(1554年)に陶晴賢が【厳島の戦い】で敗死し、追い込まれた大内義長も弘治3年(1557年)、自害を余儀なくされました。
続きを見る

毛利軍が奇襲!厳島の戦いで元就が陶晴賢を破り中国地方の覇者へ
宗麟にしてみれば、弟の治める領国が奪われるのは歓迎すべき事態ではありません。
それでも彼を救わなかった理由としては、元就との間に「義長討伐を邪魔しなければ、大友の豊前・筑前攻略も邪魔しません」という盟約が交わされていたためだと言われます。
悪く言えば「弟を売った」とも見れるわけです。
しかしながら、宗麟が相手にしていたのはあの元就です。表向きは手出しをしないように見せかけ、その実、豊前・筑前の国衆らに調略を仕掛けて一揆を扇動しました。
結果、山田隆朝や秋月文種といった勢力が宗麟の前に立ちはだかり、反対勢力の一掃に追われます。
8か国の守護&九州探題に就任!絶頂期を迎える
弘治3年(1557年)には山田隆朝が反発の構えをみせたため、宗麟も「息子を人質として差し出せば許してやらんこともない」と説得にかかります。
しかし隆朝はこの誘いに乗らず、宗麟も討伐を決意。
たちまち城を攻め落とすと、一族郎党の首を片っ端から刎ねるという手法で山田氏を殲滅しました。
続いて、筑前で独立勢力として力をつけていた秋月文種(あきづきふみたね)の討伐に乗り出し、古処山城(こしょさんじょう)に籠る彼らを大友家臣の吉弘鑑理(あきまさorあきただ)らに攻撃させます。
古処山城は標高1,000メートル近い場所に位置する山城で、正面からの攻略は難しいとされていました。
そこで鑑理は一計を案じ、城内に内通者を出して文種の殺害に成功。
宗麟は豊前・筑前を支配下に収め、この支配は幕府にも追認されました。
以前から幕府に対し莫大な献金工作を図っていたことも相まって、宗麟は永禄3年(1559年)に周防・長門の守護職までをも与えられます。
結果、宗麟は北九州を中心に計8か国の守護となり、加えて九州探題の名誉も手にする【九州の支配者】となりました。
こうして戦国大名としての大友氏、ならびに自身の生涯における絶頂期を迎えた宗麟には、今後さらなる躍進が待っている……かに思われました。
人生初の「挫折」33歳の若さで出家
名実ともに九州の覇者となった宗麟は、その後、獲得した領地の維持や反乱鎮圧に追われました。
彼らの躍進を妨害したのは毛利元就であり、大友配下の家臣や国衆を巧みに引き入れ、北九州へ手を伸ばします。
もちろん宗麟も黙ってはいません。
永禄2年(1558年)、門司城をめぐって毛利氏との合戦に及び、以降、この城は大友と毛利が占領と奪還を繰り返す激戦地となりました。
永禄4年(1561年)には、尼子氏攻略に専念していた元就に代わって、その三男・小早川隆景が送り込まれ、海上封鎖で宗麟を追い込みます。
続きを見る

元就の三男・小早川隆景はキレ者ぞ~王佐の才は毛利や秀吉に重宝され
大友軍は門司城の奪還をひとまず諦めて撤退しましたが、隆景の巧みな追撃により撤退中に大損害を被ったと言われています。
この門司城における敗北は、宗麟に大きなショックを与えました。
これまで宗麟は、特段の苦労をすることなく8か国の守護に上り詰めており、人生初の「挫折」であったという指摘もあるほどです。
そして、彼はこのショックを払しょくするため33歳の若さで出家。
名を「宗麟」と改め(以前は義鎮)、豊後府内の統治を長男・大友義統に任せて自身は臼杵の地に城を築き、移住しました。
毛利との激しい攻防に追われ
仏道に専心して気力を養った宗麟は、毛利氏に占領された豊前への再遠征を決断します。
永禄5年(1562年)には立花道雪・吉弘鑑理を中心とした遠征軍を組織し、敵の拠点である豊前松山城および香春岳城を攻撃しました。
続きを見る
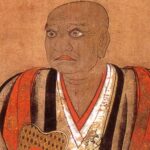
戦国大友家を躍進させた立花道雪の何が凄い?勇将の下に弱卒無し
ところが、この豊前松山城は非常に攻めづらい城であったようで、大友選りすぐりの猛将たちでも落とすことができません。
彼らは豊前松山城の包囲を継続しつつ、並行して因縁の地・門司にも進行していきました。
この地での合戦では大きな戦果を挙げたものの、やはり門司城を落とすまでには至らず……。
戦が長期化していく中で、両陣営は講和を模索するようになります。
特に毛利氏は尼子氏との抗争に手いっぱいであり、大友軍に構っている暇はありませんでした。そもそも今回の大友vs毛利の戦は、尼子氏が宗麟に要請して始まったものですから、ここは尼子氏の作戦勝ちといったところでしょう。
ところが元就は、ただ粛々と講和を受け入れはしません。
彼は交渉の傍ら、引き続き豊前・筑前の国衆へ挙兵を促しており、中々まとまらない交渉にイラ立つ宗麟の様子が確認できます。
最終的に将軍・足利義輝の仲立ちで永禄7年(1564年)に講和は成立しますが、その後も毛利の工作は止まらず、早くも交渉成立の二か月後には「元就が約束を守っていない!」と大友方が抗議する事態に発展します。
続きを見る
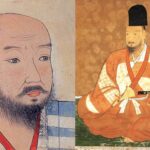
刀を握ったまま斃れる壮絶な最期~足利義輝13代将軍の生涯30年まとめ
苦しいはずの毛利がなぜそんな真似を?
というと実はこのころ「尼子氏との抗争」が片付き、大友と戦う余力ができていたと見なせます。
元就が執拗に進めてきた国衆への調略が実を結び始めており、大友方から離反者が続出する事態になっていたことも大きいでしょう。
毛利による狡猾な外交は、徐々に確実に、大友家を蝕んでいたのです。
離反者が続出し四面楚歌に陥る
実は和平締結の2年前、大友家臣として秋月文種の征伐などに功績を挙げていた高橋鑑種(あきたね)が、ひそかに毛利への内通を決意。
彼の裏切りについては軍記物などで様々な理由が述べられていますが、個人的には毛利と大友を天秤にかけた結果、生き残り戦略として毛利を選択したと思われます。
鑑種の裏切りは、戦略面だけでなく精神面でも宗麟に大きなショックを与えました。
「信頼していたし、可愛がって育ててきたのに、その恩を忘れて裏切るとは…(´・ω・`)」
そんな風に心情を吐露したとも伝わります。
毛利による裏切り工作は和平締結後も公然と行われ、もはや宗麟も黙っていられません。講和の取り決めを無視してふたたび毛利氏との戦を決意します。
永禄8年(1565年)、尼子氏を追い詰めるため家臣を総動員し、毛利の守りが手薄になったことを知った宗麟は、毛利方に内通した国衆を成敗する形で反撃に出ました。
ところが、コトはそう簡単に進みませんでした。
翌年、尼子氏との合戦がひと段落した毛利氏は、ついに全力を投じて豊筑攻略に乗り出したのです。
毛利の動きに呼応する形で高橋鑑種も挙兵し、さらに周辺エリアの敵対勢力だった筑紫広門・龍造寺隆信・秋月種実らも行動を起こしました。
まるで信長包囲網のように宗麟を取り囲む元就。
四面楚歌のピンチに追い込まれた大友軍は、勇猛な家臣たちの働きでどうにか一進一退の攻防を繰り広げます。
しかし、ついには筑前一国を失いかける情勢となり、さらには立花鑑載(あきとし)という家臣が高橋方に与してしまうという危機的状況に陥りました。
そこで奮起したのが勇将として知られる立花道雪。
立花城を占領し反旗を翻す立花鑑載に対し、永禄11年(1568年)に同城を急襲。総攻撃の末に鑑載を敗走させます。
それでも戦況は好転しません。
同年には豊前松山城で合戦が勃発し、ここで優位に立った毛利軍は立花城の奪還を目指して攻め込みました。
大友軍もよく粘りましたが、最終的には戦いに敗れ、城を明け渡して兵をいったん城外まで撤退。
停滞した状況を崩すべく両軍共に調略工作を進めていると、これまで幾度も毛利と大友の命運を左右してきた尼子氏がまたもや動くのです。
永禄12年(1569年)、毛利氏に敗れ京都に隠れていた尼子勝久を要して、山中鹿介(山中幸盛)が挙兵、出雲へ乱入して尼子再興を目指し暴れまわりました。
続きを見る
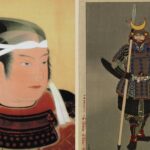
山中鹿介(幸盛)は戦国一の忠義者?七難八苦に立ち向かった生涯とは
尼子に加えて、毛利に敵対する国衆や大内氏の関係者も呼応し、ついに毛利氏は九州攻略を断念します。
こうして、長年にわたる大友対毛利の「北九州ラウンド」は、宗麟の判定勝ちで幕を閉じたのでした。
ただし、依然として門司城は毛利の手中にあり、ひとまず恭順を表明した高橋鑑種も隙あらば裏切りの構えを見せるなど、完全に安心できない情勢にあったことも事実です。
西からは龍造寺 南からは島津
これまで宗麟を苦しめてきた毛利氏も、この後は九州に影響を及ぼすことができなくなっていきました。
新勢力の台頭――織田信長です。
続きを見る

史実の織田信長ってどんな人?生誕から本能寺まで49年の生涯まとめ
東海地方から畿内にかけて勢力を急拡大させている織田軍が西国への侵攻をジワジワと進めてきました。
しかも元亀2年(1571年)には元就が亡くなり、以後は家の存亡を賭して信長との対峙に追われます。北九州どころの話ではなくなっていました。
こうなると俄然大友の有利。宗麟もさぞかしほくそ笑んだろう……と思いきや、天正年間に入って病気がちになってしまいます。
大友家では嫡男の大友義統が政務に携わる機会が増え、遅くとも天正4年(1577年)までには息子への家督継承と宗麟の隠居が進められました。
ただし、家督継承後も宗麟が実質的な支配権を得ており、現役を完全に退いたわけではありません。
以後は病気をおしながら政治に携わっていたと考えられています。
そうまでして働かねばならない理由は、九州西部と南部にありました。
急成長を遂げる竜造寺家と、悲願の薩摩統一を成し遂げた島津家が、迫ってきていたのです。
毛利という厄介な相手に戦いを強いられていた大友家は、新たな敵対勢力への対処が遅れてしまいました。
しかも致命的でした。
島津家との間で【耳川の戦い】に発展し、大友の歴史に残るような大惨敗を喫してしまったのです。
続きを見る

九州最強島津軍が「耳川の戦い」で大友軍に釣り野伏せ&フルボッコ!
キリスト教に傾倒しすぎて……
耳川の戦い以降、有力な家臣を次々と失った大友勢力はかつての勢いが見る影もないほど衰退し、九州の覇権争いから脱落しました。
残された家臣らの中でも裏切りが頻発し、その対処に追われる日々です。
病気がち、かつ家臣団の離脱に心を悩ませたのか。
この頃から宗麟は仏教に見切りをつけ、キリスト教に傾倒していったと言われます。
もともと御曹司として育ち、挫折を味わったときも心許ない行動が指摘された宗麟。
日向国に「キリスト教国家」を樹立しようと構想していたことも指摘されており、こうした過度なキリシタン思想が、家臣や息子・義統との分裂を招く一因になったという説もあります。
残念なことに後継者である義統に当主としてのセンスがなかったらしく、重臣らが宗麟の現役復帰を願っていたという記録が宣教師ルイス・フロイスによって残されています。
キリスト教保護に熱心な宗麟を擁護するのは、フロイスにとってビジネス的な意味合いもあったでしょうが、家臣団が分裂しかけているのは間違いなかったことでしょう。
続きを見る

戦国や信長を描いたルイス・フロイス『日本史』には何が記されていた?
急激に崩壊しつつある大友帝国。
薩摩からの九州北上をはかる島津氏は、急伸していた龍造寺氏さえも打ち破り、その勢いはとどまるところを知りません。
もはや脅威は眼前。大友氏の滅亡は時間の問題かに思われました。
秀吉によって窮地を救われ、滅亡を免れて生涯を終える
続発する国衆や家臣らの反乱。
日の出の勢いの島津氏。
まさに危機的状況を迎えていた大友氏ですが、そこに救いの手を差し伸べた人物がおりました。
天下人として大坂に君臨していた豊臣秀吉です。
続きを見る

ド派手すぎる豊臣秀吉の逸話はドコまで本当か?62年の生涯まとめ
天正13年(1585年)、秀吉は、大友義統と島津義久、毛利輝元に停戦を命じ、従わない場合は征伐も辞さない構えを見せました。
圧倒的劣勢の大友家にとっては願ってもない命令であり、天正10年(1582年)ごろから津久見に隠居し、ひっそりとキリスト教生活を送っていた宗麟も自ら大坂へ出向き、秀吉と面会します。
一方、島津義久は「こんな猿に命令される覚えはないわ!」と停戦令をはねのけ、
続きを見る

戦国九州の統一に迫る島津義久(四兄弟の長男)戦い続けた生涯79年とは
秀吉は九州征伐を決意。
まず手始めに九州へ上陸させた仙石秀久らの豊臣四国連合軍は、島津氏によって返り討ちにされますが【戸次川の戦い】、その後、豊臣秀長らの本隊が登場すると状況は一変します。
苦戦が続いていた大友義統らも、秀吉軍の到着によってなんとか危機を脱し、最終的に豊後一国と豊前の一部を保証され、豊臣臣下の一将として地位を認められたのです。
御家の危機回避を見届けたことで緊張から解放されたのでしょうか。
宗麟は天正15年(1587年)、図ったかのように生涯を終えました。
享年58。
宗麟は名君なのか、暗君なのか
良くも悪くも強烈な存在感を放った大友宗麟の生涯は、同時代および後世でさまざまな評価を下されます。
興味深いのは、良いものから悪いものまで多種多様な点でしょう。
中には性格や能力だけでなく身体の特徴までもが180度異なるような記述がみられることです。
例えば、江戸時代前期に編纂された歴史書『豊府紀聞』では「政道理にかない、国を治め民を服した」と、彼が名君であったという描かれ方になっています。
一方、彼は実に好戦的で野心を抱く独裁君主としての一面も確認できるなど、いかにも「戦国大名」というイメージを与えられます。
しかし、江戸時代中期の『大友記』では、「他人の妻に手を出すほど好色な人物で、酒池肉林におぼれ家を崩壊に導いた暗君」として描かれているのです。
さらに、彼が生前関わった宣教師たちの証言を見てみると、上記とはまた異なった人物像が確認できます。
宣教師らによれば、宗麟は敬虔な信徒にして実に聡明であり、「東洋の名君」と評されています。加えて「体質が弱く、虚弱であった」という指摘もなされており、やはり前述の人物像と相違する点は多いです。
前述のように宣教師たちが宗麟を「持ち上げる」のは当然であり、高評価は割り引く必要もあるでしょう。
続きを見る
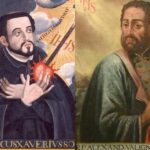
外国人宣教師から見た戦国ニッポン 良い国or悪い国or鴨ネギな国?
以上のような話を整理して見えてくること。
それは宗麟が「対面する人の立場や出会った時期によって、大きく評価の変わる人物」ということではないでしょうか。
例えば、8か国の守護に就任した絶頂期であれば、彼は好戦的で野心家な人物に見えるでしょうし、家を崩壊させた後であれば、家中をまとめきれなかった暗君になるでしょう。
同時に、若かりし頃は仏教を積極的に庇護していた一方、晩年はキリスト教に傾倒したという事実からも評価が一変します。
特に、晩年の彼は「寺社を破壊しキリスト教にかまけた暗君」と言われがちです。
が、寺社の破壊活動については誇張されている点が多いほか、キリスト教の精神に基づいて府内に民衆用の病院を築くなど、ホスピタリティを感じさせる先進的な部分がみられたのも事実です。
今後も、彼の評価は時代や社会に左右されるのかもしれません。