前回に続き、今回は「幕末・明治維新の真相」に関する記事を書いていこうと思います。皆さんは「幕末・明治維新」というとどういったイメージを思い浮かべるでしょうか?「坂本龍馬に代表される幕末の英雄による壮大な国家大改革」、「文明開化、日本の近代化の幕開け」、「身分制度の撤廃による民主主義の台頭」等々、肯定的な印象が強いのではないでしょうか?結論から言いますと、こういった大多数の人が思い描いている明治維新の観念は嘘八百であります。事実は全くの正反対であり、明治維新こそ「彼ら」の「彼ら」による「彼ら」のための日本支配体制が確立された「日本転覆クーデター」なのです。「彼ら」にとって大変喜ばしい「日本転覆クーデター」を、さも「日本人にとって素晴らしい善なる民主主義革命であった」と日本人を洗脳するために、学校教育やマスゴミや御用作家による歴史小説等が使われて来たのです。こういった洗脳媒体を通して大多数の日本人が、「坂本龍馬は日本を改革した偉大な英雄だ」、「明治維新のおかげで日本は世界に誇る近代国家になれたんだ」と思い込んでいます。全く真実が分っていないバカが多すぎます。そういった人間は、「自分が洗脳されている事実にも全く気付いていない」から救いようがないのです。実際問題、皆さん少し考えても見てください。地方の一介の下級武士がいくら弁舌がうまくても、いくら頭が切れて行動力があったとしても、いくら人望があったとしても、個人のこういった能力・才覚のみで薩長を結びつけ徳川幕府を倒すことが出来たと思いますか?
そんなことが出来るわけがないでしょう。龍馬のバックには龍馬を操る勢力が蠢いていたのです。その代表となるのがジャーディン・マセソン商会の代理人であり、武器商人であるトーマス・グラバーです。長崎に行かれた方なら誰もが訪れる観光名所であるグラバー園には隠しもしないでフリーメーソンのマークが刻まれた門柱があります。龍馬はグラバーの代理人に過ぎなかったのです。龍馬とグラバーの武器売買に関わっていたのが日本初の株式会社である亀山社中です。亀山社中を見てみます。
亀山社中(海援隊)(ウィキより抜粋)
海援隊(かいえんたい)は、江戸時代後期の幕末に、土佐藩脱藩の浪士である坂本龍馬が中心となり結成した組織である。1865年から1868年まで3年余りに亘り、私設海軍・貿易など、薩摩藩などからの資金援助も受け、近代的な株式会社に類似した組織、商社活動としても評価されている。運輸、開拓、本藩の応援、射利、投機、
教育(修行科目 政法・火技・航海・汽機・語学等)等、隊の自活運営、政治・商事活動を行った。出版も手掛け和英通韻伊呂波便覧、閑愁録、藩論などがある。中岡慎太郎が隊長となった陸援隊と併せて翔天隊と呼ばれる。1865年閏5月、幕府機関である神戸海軍操練所の解散に伴い、薩摩藩や商人(長崎商人小曽根家など)の援助を得て長崎の亀山(現在の長崎市伊良林地区・
北緯32度44分55.52秒 東経129度53分12.53秒北緯32.7487556度 東経129.8868139度)において前身となる亀山社中(かめやましゃちゅう)が結成され、当初は、貿易を行い、交易の仲介や物資の運搬等で利益を得ながら、海軍、航海術の習得に努め、その一方で国事に奔走していた。神戸海軍操練所時代に考えていた実践でもあり、目的はこれらの活動を通じて薩長の手を握らせることにもあった。
グラバー商会などと取引し、武器や軍艦などの兵器を薩摩藩名義で購入、長州へ渡すなどの斡旋を行い、険悪であった薩摩と長州の関係修復を仲介する。1866年3月、薩摩の西郷隆盛(吉之助)・長州の木戸孝允(桂小五郎)を代表とする薩長同盟の締結に大きな役割を果たす。1866年6月の第二次幕長戦争(第二次長州征伐)においては長州藩の軍艦ユニオン号で、下関海戦に参加、幕府軍を相手に戦い、長州の勝利に大きく貢献する。
倒幕運動に奔走するが大政奉還、内戦回避の坂本と薩摩・長州の武力倒幕では意見が相違した。 同年11月15日(12月10日)、京都・近江屋で坂本が陸援隊隊長の中岡とともに暗殺されると求心力を失って分裂し戊辰戦争が始まると長岡謙吉らの一派は天領である小豆島などを占領し菅野覚兵衛らは佐々木高行とともに長崎奉行所を占領し、また小豆島も治めた。長岡兼吉が慶応4年4月土佐藩より海援隊長に任命されたが、同年閏4月27日(6月17日)には藩命により解散される。土佐藩士の後藤象二郎は海援隊を土佐商会として、岩崎弥太郎が九十九商会・三菱商会・郵便汽船三菱会社(後の日本郵船株式会社)・三菱商事などに発展させる。
武器商人グラバーと龍馬・薩長の関わりがよく分かりますよね。そして忘れてはいけないのが、これらの関係から三菱が誕生した、という事実ですね。龍馬が個人の能力のみで明治維新を成し遂げたのではないのと同様に、岩崎弥太郎個人のビジネス才覚のみで三菱が誕生したのではないことは言うまでもないことです。そして龍馬を操ったグラバーはスコットランドの出身で、長崎に着いた時はまだ21歳でした。21歳の若造が個人の考えで遠く離れた外国の政治体制を転覆させることが出来ると思いますか?グラバーも所詮「彼ら」の使用人に過ぎないのです。グラバーを見てみます。
トーマス・ブレーク・グラバー
トーマス・ブレーク・グラバー(英: Thomas Blake Glover、1838年6月6日 - 1911年12月16日)はスコットランド出身の商人。武器商人として幕末の日本で活躍した。スコットランド・アバディーンシャイアで沿岸警備隊の1等航海士トーマス・ベリー・グラバー(Thomas Berry Glover)とメアリー(Mary)の間に8人兄弟姉妹の5人目として生まれる。ギムナジウムを卒業した後、1859年に上海へ渡り「ジャーディン・マセソン商会」に入社。同年9月19日(安政6年8月23日)、開港後まもない長崎に移り、2年後には「ジャーディン・マセソン商会」の長崎代理店(グラバーの肩書きは「マセソン商会・長崎代理人」)として「グラバー商会」を設立し、貿易業を営む。当初は生糸や茶の輸出を中心として扱ったが八月十八日の政変後の政治的混乱に着目して薩摩・長州・土佐ら討幕派を支援し、武器や弾薬を販売。亀山社中とも取引を行った。また、薩摩藩の五代友厚・森有礼・寺島宗則、長澤鼎らの海外留学、長州五傑のイギリス渡航の手引きもしている。明治維新後も造幣寮の機械輸入に関わるなど明治政府との関係を深めたが、武器が売れなくなったことや諸藩からの資金回収が滞ったことなどで1870年(明治3年)、グラバー商会は破産。グラバー自身は高島炭鉱(のち官営になる)の実質的経営者として日本に留まった。1881年(明治14年)、官営事業払い下げで三菱の岩崎弥太郎が高島炭鉱を買収してからも所長として経営に当たった。また1885年(明治18年)以後は三菱財閥の相談役としても活躍し、経営危機に陥ったスプリング・バレー・ブルワリーの再建参画を岩崎に勧めて後の麒麟麦酒(現・キリンホールディングス)の基礎を築いた。
長州ファイブのイギリス渡航の手引きもしてますね。三菱とキリンにも関わっていますね。そして、造幣寮(今の造幣局)に関わっているのも見逃せませんね。グラバーを操ったジャーデン・マセソン商会を見てみます。
ジャーデン・マセソン商会(ウィキより抜粋)
ジャーディン・マセソン(Jardine Matheson Holdings Limited, 怡和控股有限公司)は、香港にヘッドオフィス(登記上の本社はバミューダ諸島・ハミルトン)を置くイギリス系企業グループの持株会社。ロスチャイルド系であり、米誌フォーチュン誌の世界企業番付上位500社のランキング「フォーチュン・グローバル500」(2009年度版)では世界411位。創設から170年たった今日でも、アジアを基盤に世界最大級の国際コングロマリット(複合企業)として影響力を持っている。
前身は東インド会社で、元は貿易商社。1832年、スコットランド出身のイギリス東インド会社元船医で貿易商人のウィリアム・ジャーディンとジェームス・マセソンにより、中国の広州(沙面島)に設立された。設立当初の主な業務は、アヘンの密輸と茶のイギリスへの輸出。同じロスチャイルド系の香港上海銀行(HSBC)は、ジャーディン・マセソンなどが香港で稼いだ資金をイギリス本国に送金するために設立された銀行である。清とイギリスとの間で1840年から2年間にわたって行われたアヘン戦争に深く関わっている。アヘンの輸入を規制しようとする清朝政府とイギリスの争いが起こった際に、当時のアヘン商人の一つであるジャーディン・マセソン商会のロビー活動により、イギリス本国の国会は9票という僅差で軍の派遣を決定した。1859年(安政6年)、上海支店にいたイギリス人ウィリアム・ケズィック(ウィリアム・ジャーディンの姉の子)が横浜(旧山下町居留地1番館、現山下町一番地)に「ジャーディン・マセソン商会」横浜支店を設立。日本に進出した外資第1号としても知られる。後に吉田茂の養父・吉田健三が一時期、同社横浜支店長を勤めていた。鹿島によって建設された横浜初の外国商館である社屋は、地元民から「英一番館」と呼ばれた。跡地には現在シルクセンター(国際貿易観光会館)が建っている。1863年(文久3年)、ウィリアム・ケズウィックは井上聞多、遠藤謹助、山尾庸三、野村弥吉、伊藤博文の長州五傑のイギリス留学を支援する。彼らの英国滞在は、ジェームス・マセソンの甥にあたるヒュー・マセソン(ジャーディン・マセソン商会・ロンドン社長)が世話した。一方長崎でも、1859年9月19日(安政6年8月23日)に幕末・明治期の重要人物であるトーマス・ブレーク・グラバーが「ジャーディン・マセソン商会」長崎代理店として「グラバー商会」を設立。現在はグラバー園として公開されている。グラバーは、五代友厚(薩摩)、坂本龍馬(海援隊)、岩崎弥太郎(三菱財閥)等を支援した。
ジャーデン・マセソン商会はアヘン貿易をしており、ロスチャイルド系です。そして、「前身は東インド会社である」というのが最大のポイントである。ジョン・コールマンは、「世界を支配している闇の勢力「300人委員会」の前身は東インド会社だ」と述べている。ということは、「東インド会社=300人委員会=ジャーデン・マセソン商会=ロスチャイルド=「彼ら」」ちゅーわけですナ。はい!これで皆さんもご理解いただけたのではないかと思います。「明治維新を操っていた黒幕は誰なのか」ということを。その黒幕がやっていた“商売”はアヘン貿易であり、武器売買であったということを。「そんなヤバイ“商売”をしている勢力が裏で操っていた「明治維新」というものが「善良なる民主主義革命」であるわけがない」ということは、善悪の判断がつくようになった子供でも理解できることでしょう。そして、「吉田茂の養父・吉田健三が一時期、ジャーディン・マセソン商会横浜支店長を勤めていた。」という事実を我々は覚えておく必要があるでしょう。吉田茂は言うまでもなく麻生太郎の祖父であり、側近がCIAに情報提供していたことが暴かれている人物である。この「どす黒い血脈」が現在も続いていることは偶然でしょうか?必然でしょうか?外国人である「彼ら」が直接日本の政財界のトップとして君臨しだしたら、さすがに“洗脳されやすい”日本人も「彼ら」に支配されていることに気付き、次第に暴動が起きるでしょう。しかし一般の日本人を装った、出自の怪しい特殊な地域出身者を中心とした傀儡を「彼ら」の代わりにトップに据え置くことで、「彼ら」は日本を秘かに間接支配することが出来るのです。「彼ら」の間接支配が明治維新から平成の現代まで続いていることを、しっかりと理解しておいて下さい。最後に、「彼ら」の傀儡は維新勢力だけではなかったことを述べておきます。このことは次回書こうと思います。 |
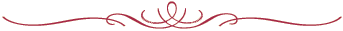
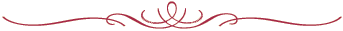
![]()
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)