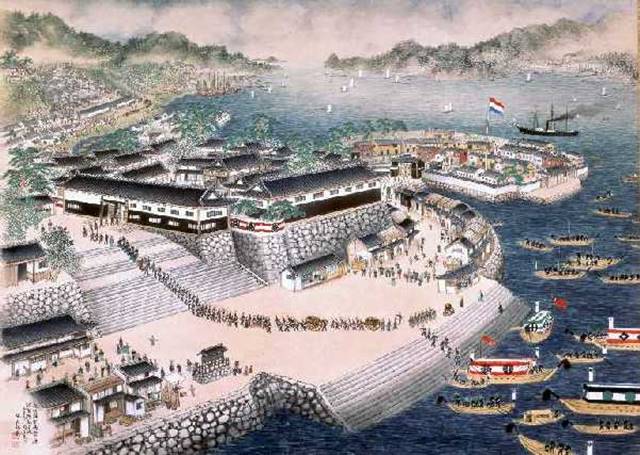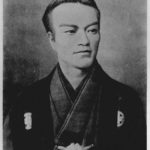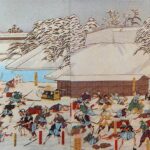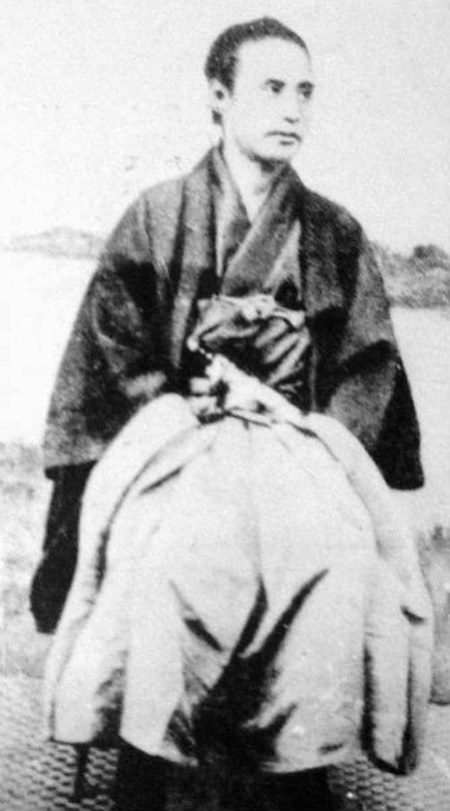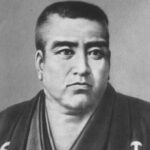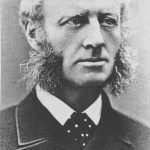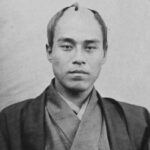幕末舞台のドラマや漫画では、必ず重要な局面で登場する男・勝海舟――。
坂本龍馬や西郷隆盛に大きな影響を与えながらも、幕府に仕える幕臣という異色な存在が魅力的なのでしょう。
では、彼の生い立ちなどをご存知ですか?
明治維新後はどうしていたの?
なんて尋ねられると、案外、答えにくいフシギな一面も持っている――。
そんな“勝海舟の一生”を追ってみましょう。
※名前は勝海舟で統一
お好きな項目に飛べる目次 [とじる]
両国生まれの江戸っ子・勝
勝海舟といえば、べらんめえ口調で喋る、江戸っ子という印象があります。
実際、生まれは、江戸情緒の濃い両国(現在の東京都墨田区亀沢)。
文政6年(1823年)に生誕しております。西郷隆盛が1827年生まれですから4つ年上になりますね。
父は旗本の勝小吉で、母はお信。
小吉はもともと、旗本・男谷彦四郎の三男で、勝家に養子入りしたのでした。
※なお、勝が生まれた場所は、男谷彦四郎邸。つまりお祖父ちゃんの家になります
勝家は、将軍に御目見得できる“旗本”の身分とはいえ、知行はわずか41石でした。
ほとんど御家人(将軍の御目見得はムリ)に近い存在で、父の小吉も就ける職はなく、細々とした暮らしを送っています。
ただ、博徒や侠客とも親しくつきあいがあり、顔の利く男でして。
息子の勝も、自然と火消したちとは昵懇の間柄となりました。父の代(あるいはそれ以前)からの人脈だったのでしょう。
勝は7才まで男谷家で過ごし、のちに赤坂に引っ越します。
少年時代の逸話といえば、9才の時に狂犬病の野犬に睾丸を噛まれて、片方を失ったというもの。
彼はそのせいで二ヶ月以上寝込んだそうですが、狂犬病ならば、その程度で済んで幸運だったでしょう。
つまり江戸の無血開城の話し合いをゴシップ的に捉えると、
「睾丸肥大の西郷と、睾丸が一つしか無い勝の会談」
だったわけでもあります。
西郷の睾丸肥大化と狂犬病については、歴女医・馬渕まり先生の記事に詳しくありますので、そちらをご参照ください。
なお、睾丸というのは片方なくなっても案外平気なものです。
勝は多数の妾を囲い、使用人にも手を出しました。しかも平然と妻妾との同居をしていたのです。
そのため妻子からは、大層あきれられております。
この怪我の後遺症があるとすれば、生涯を通して犬嫌いとなったことでしょう。

勝海舟/wikipediaより引用
3千ページの辞書『ドゥーフ・ハルマ』を2部写す
成長した勝は、幕臣の子らしく剣術修行に励みます。
直心影流の免許皆伝で、山鹿流も習得。
しかし、勝は性格的に血なまぐさい場面が大嫌いで、それよりも勉学について才能を発揮するようになります。
オランダ語の習得は、天保13年(1842年)に開始し、翌年には文章を書けるまでになりました。
妻・たみと結婚した翌年の弘化3年(1846年)には、本所から赤坂田町に移り、このころからますます蘭学の修得に打ち込みます。
勝は、3,000ページもある蘭和対訳辞書『ドゥーフ・ハルマ』を筆写しました。
この辞書は蘭学を学ぶ者にとってマストバイな一冊ですが、幕府は出版を禁じていたのです。
貧しい勝には、筆写本すら手が出ません。
そこで勝は、損料(レンタル料)10両を支払い、筆写本を借りました。
そして弘化4年(1847年)から一年間、寝る間も惜しんで2部の写し作業を完了。
一部は売り払ってレンタル料にあて、一部は手元に置いたわけです。
この過程で、いかほどオランダ語の勉強に繋がったか。
ハイスペックな頭脳のほどが現代の我々にもわかりましょう。
阿片戦争後、危機感を抱く勝
当時、知識人たちは社会情勢に強い危機感を抱いていました。
日本よりはるかに大きな清国が、阿片戦争でイギリスに敗北していたからです。

アヘン戦争/Wikipediaより引用
勝は考えました。
「これからは蘭学と軍学で、この国を強くしなきゃいけねぇ」
阿片戦争から10年。
嘉永3年(1850年)に、勝は蘭学と兵学の塾を開きました。
この時点で、黒船来航、3年前のこと。彼の名声は高まり、入塾者はどんどん増えてゆきます。
「勝先生、これからは火縄銃というわけにはいかんでしょう。ひとつ、小銃や大砲を作ってみてはくれませんか」
そんな依頼をする藩もあったそうです。
実は黒船来航を待つまでもなく、日本国内は外圧を控えて沸騰していました。
「講義ならいくらでもできるが、大砲を作るとなるたぁ……」
勝はオランダの書物を見ながら設計図を引き、鍛冶屋や鋳物師に頼んで、作ることにしました。
「勝先生は、大砲こしらえてたんまり金儲けているらしいぜ」
そんな噂が立ちましたが、実際は逆。
なんせ初めてのことですから、試行錯誤を繰り返してともかく金がかさみます。評判の塾を経営しているとはいえ、収入は常にカツカツでした。
鋳物師が手抜きをしようと賄賂を持って来ても、勝は断固として断りました。
そんなこともあって勝の名声は広まっていたようです。
黒船来航以前に、もし西洋から船が来航したらどうすべきか、書物に書いてまとめていました。
その先進性――常に一歩先をゆく男でした。
黒船来航後、老中・阿部に見いだされる
嘉永6年(1853年)、ついに幕府が恐れていた事態がやってきます。
黒船の来航です。
時の老中・阿部正弘は、慣例を破り、譜代大名と幕臣以外の外様大名を含め、様々な層に意見を求めました。
幕臣も、幕府に上書を出すことができるようになったのです。
こうした上書は実に700にのぼり、しかしその大半が役に立たないものばかり。
根性論で「攘夷をしてしまえ」みたいなものもたくさんあるわけです。
そんな中、蘭学と軍学を学んだ勝の上書は、後の明治政府の方針にもつながるような構想であり、各方面から注目を集めました。
具体的には以下のようなものです。
・将軍の御前で外交・内政の討論をする
・軍艦をつくるとともに、貿易を行う
・敵が上陸した際の、江戸防衛計画
・西洋式軍隊に改め、教練学校を作る
・火薬製造に必要な資源を調達する方法
阿部正弘もまた有能で知られた人物。
有事にあたり、幕政改革に取り組むには、身分にとらわれない有能な人材の登用に真剣でした。
上書も素晴らしく、経営していた塾も既に評判だった勝。
目付・海防掛の大久保一翁(忠寛)も、強く推しています。
安政2年(1855年)、勝は異国応接掛附蘭書翻訳御用に抜擢されます。
貧しい旗本の子に過ぎなかった男は、かくして幕政に参加できるようになっていくのでした。