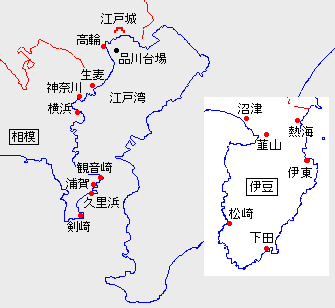4隻の艦隊は、旗艦サスケハナ号(USS Susquehanna)(2450トン、10インチ砲3門、8インチ砲6門)、ミシシッピ号(USS Mississippi)(1692トン、10インチ砲2門、8インチ砲8門)の2隻が蒸気軍艦。サラトガ号(USS Saratoga) (882トン、8インチ砲4門、32ポンド砲18門)、プリマス号(USS Plymouth) (989トン、8インチ砲8門、32ポンド砲18門)が帆走軍艦。翌年の来航時は7隻の艦隊で、旗艦ポーハタン号(2415トン)以下、サスケハナ、ミシシッピ両蒸気軍艦と帆走軍艦4隻。
ペリー艦隊が合衆国東海岸のチェサピーク湾ノフォークを出航したのは1852年11月24日(嘉永5年10月13日)。大西洋のマディラ島、セントヘレナ島からアフリカ南端のケープタウンを回り、セイロン、シンガポール、香港、上海、琉球、小笠原諸島に寄港し、相模浦賀沖に碇泊したのは1853年7月8日午後5時頃。ペリーは日本との交渉と共に、小笠原諸島を調査している。日本からの帰路、琉球に寄って貯炭所を設置している。太平洋横断航路の開発の為の石炭補給地を見つけ、貯炭所を確保するのがペリーの主任務の一つであった。
ペリー艦隊は突然日本に現れたのではなく、前年にオランダ政府に対して、艦隊派遣の斡旋を依頼し、長崎のオランダ商館長を通して幕府に連絡していた。「近くアメリカが日本に艦隊を送る準備をしている」という情報に対し、幕府は対策を取ることなく老中の間で握りつぶし、外交担当者にも知らせていなかったと伝えられている。
ペリー一行は第14代アメリカ大統領ピアース(1853.3.4日就任)の親書(「フィルモア大統領親書」とも記されている)を携えており、その態度は強硬で、ペリー国書の受理を要求し、幕府が対応に苦慮 する間に江戸湾に進入して測量を行なう等、武力を背景として開国を迫った。フィルモア大統領の日本皇帝宛て国書は次の通り(「ペリー艦隊の来航」より)。
| 「余が志、二国の民をして交易を行わしめんと欲す。これを以て日本の利益となし、また兼ねて合衆国の利益となさんことを欲してなり。余さらにペルリ提督に命じて、一件の事を殿下に告明せしむ。合衆国の船、毎年角里伏尓尼亜より支那に航するもの甚だ多し。又鯨猟の為、合衆国人日本海岸に近づくもの少なからず。而してもし台風あるときは、貴国の近海にて往々破船に逢うことあり。もしこれ等の難に遇うに方っては、貴国に於いてその難民を撫恤(ぶじゅつ)し、その財物を保護し、以て本国より一舶を送り、救い取るを待たんこと、これ余が切に請う所なり。日本国に石炭甚だ多く、又食料多きことは、余が會て知れる所なり。我国用うる所の蒸気船は、その大洋を航するに当て、石炭を費やすこと甚だ多し、而してその石炭をアメリカより搬運せんとすれば、その不便知るべし。これを以て余願わくは、我が国の蒸気船及びその他の諸舶、石炭食料及び水を得んが為に、日本に入ることを許されんことを請ふ」。 |
この時、従軍ユダヤ教ラビが日本に向って激烈な呪文を唱えた、と後年公刊された乗組員の日記に報告されている。(この情報につき出典元が分からない。懸命に探しているので強力求める)
6.4日、浦賀奉行与力・香山栄左衛門と中島三郎助、通詞堀達之助が交渉に当たり、ペリー提督を応接し長崎回航を求めたがけ入れなかった。ミシシッピ号が示威行動のため、江戸湾奥に向かう。同日、佐久間象山が米艦隊を視察するため浦賀へ行き、吉田松陰らと会見している。
6.9日、浦賀奉行戸田氏栄、井戸弘道が久里浜でペリーと会見。アメリカの国書を受け取る。吉田松陰は佐久間象山等と現場でこの状況を見ていた。艦隊4隻は江戸湾を周回する。
6.12日、東インド艦隊が再来を約して、那覇へ向けて江戸湾を離れる。その後、香港へ戻る。
6.15日、幕府(阿部老中)が、ペリー来航を朝廷に上奏する。
江戸幕府第3代将軍・徳川家光の時代以来、鎖国を国是としてきた幕府にとって、このペリー来航は幕府内や諸大名間に衝撃を走らせた。老中阿部正弘はとりあえず国書を受け取り、ペリーを退却させた。