1858(安政5)年、日英修好条約を締結するために来日したエルギン卿使節団の一員で、フリゲート艦の艦長だったオズボーンと、エルギンの個人秘書だったオリファントは、日本をバラ色に描いている。オズボーンは最初の寄港地長崎の印象をこう述べている。『この町でもっとも印象的なのは(そしてそれは我々全員による日本での一般的観察であった)、男も女も子供も、みんな幸せで満足そうに見えるということだった』。オリファントも云う。『個人が共同体のために犠牲になる日本で、各人がまったく幸福で満足しているように見えることは驚くべき事実である』。オリファントの場合、熱狂は既に長崎で始まっていた。今次々と展開しつつあるこんなすばらしいプログラムを、上海を出発するときには予想だにしていなかったと言いつつ、彼は次のように話す。『我々の最初の日本の印象を伝えようとするには、読者の心に極彩色の絵を示さなければ無理だと思われる。シナとの対照が極めて著しく、文明が高度にある証拠が実に予想外だったし、我々の訪問の情況がまったく新奇と興味に満ちていたので、彼らのひきおこした興奮と感激との前に我々はただ呆然としていた。この愉快きわまる国の思い出を曇らせるいやな連想はまったくない。来る日来る日が、我々がその中にいた国民の、友好的で寛容な性格の鮮やかな証拠を与えてくれた。それまでセイロン、エジプト、ネパール、ロシア、中国など異国についての豊かな見聞をもち、そのいくつかについては旅行記もものしてきたこの29歳の英国人が、快いくるめきに似た感動をたっぷりと味わっていることだけはよく伝わってくる。彼は日本において、前もって与えられていた予想をただ再強化したのではない。日本の事物は彼にとって『予想外』だったのである。彼は日本訪問を終えたのちに書いた母親への手紙で、『日本人は私がこれまで会った中で、もっとも好感のもてる国民で、日本は貧しさや物乞いのまったくない唯一の国です。私はどんな地位であろうともシナへ行くのはごめんですが、日本なら喜んで出かけます』と述べるほどの日本びいきになっていた。
あの『ヤング・ジャパン』の著者であるブラック(1826~1880)は『思うに、他の国々を訪問したあとで日本に到着する旅行者達が一番気持ちのよい特徴の一つと思うに違いないことは、乞食がいないことだ』と断言している。
陽気な人びと
19世紀中葉、日本の地を初めて踏んだ欧米人が最初に抱いたのは、『この国民はたしかに満足しており幸福である』という印象だった。ときには辛辣に日本を批判したオールコックでさえ、『日本人は色々な欠点をもっているとはいえ、幸福できさくな、不満のない国民であるように思われる』と書いている。ペリーは第2回遠征の際、下田に立ち寄り、『人々は幸福で満足そうだ』と感じた。ペリーの4年後に下田を訪れたオズボーンには、町を壊滅させた大津波のあとにもかかわらず、再建された下田の住民の『誰もがいかなる人びとがそうでありうるよりも、幸せで禍から解放されている』ように見えた。
ティリーは1858年からロシア艦隊に勤務し、1859年、その一員として訪日した英国人であるが、函館での印象として『健康と満足は男女と子供の顔に書いてある』という。1860年、通商条約締結のため来日したプロシアのオイレンブルク使節団は、その遠征報告書の中でこう述べている。『どうみても彼らは健康で幸福な民族であり、外国人などいなくてもよいのかもしれない』。
1871年(明治4年)に来朝したオーストリアの長老外交官ヒューブナー(1811~1892)は云う。『「封建的制度一般、つまり日本を現在まで支配してきた機構について何といわれようが、ともかく衆目の一致する点が一つある。即ち、ヨーロッパ人が到着した時からごく最近に至るまで、人々は幸せで満足していたのである』。
オズボーンは江戸上陸当日、『不機嫌でむっつりした顔にはひとつとして出会わなかった』というが、これはほとんどの欧米人観察者の眼にとまった当時の人びとの特徴だった。
ボーヴォワルは云う。『この民族は笑い上戸で心の底まで陽気である』、『日本人ほど愉快になり易い人種はほとんどあるまい。良いにせよ悪いにせよ、どんな冗談でも笑いこける。そして子供のように、笑い始めたとなると、理由もなく笑い続けるのである』というのはリンダウ(1830~1910)だ。オイレンブルク使節団報告書の著者ベルクの見るところも変わらない。『彼らは、話し合うときには冗談と笑いが興を添える。日本人は生まれつきそういう気質があるのである』。
1876(明治9)年、来日し、工部大学校の教師をつとめた英国人ディクソン(1854~1928)は、東京の街頭風景を描写したあとで次のように述べる。『ひとつの事実がたちどころに明白になる。つまり上機嫌な様子がゆきわたっているのだ。群衆のあいだでこれほど目につくことはない。彼らは明らかに世の中の苦労をあまり気にしていないのだ。彼らは生活のきびしい現実に対して、ヨーロッパ人ほど敏感ではないらしい。西洋の群衆によく見かける心労にひしがれた顔つきなど全く見られない。頭をまるめた老婆からきやっきゃっと笑っている赤児にいたるまで、彼ら群衆はにこやかに満ち足りている。彼ら老若男女を見ていると、世の中には悲哀など存在しないかに思われてくる』。むろん日本人の生活に悲しみや惨めさが存在しないはずはない。『それでも人々の愛想のいい物腰ほど外国人の心を打ち魅了するものはないという事実は残るのである』。
ボーヴォワルは日本を訪れる前に、オーストラリア、ジャワ、シャム、中国と歴訪していたのだが、『日本はこの旅行全体を通じ、歩き回った国の中で一番素晴らしい』と感じた。その素晴らしい日本の中でも、『本当の見物(みもの)』は美術でも演劇でも自然でもなく、『時々刻々の光景、驚くべき奇妙な風習をもつ一民族と接触することとなった最初の数日間の、街や田園の光景だ』と彼は思った。『この鳥籠の町のさえずりの中でふざけている道化者の民衆の調子のよさ、活気、軽妙さ、これは一体何であろう』と、彼は嘆声をあげている。彼にとって真の見物は、この調子のいい民衆だったのである。
水田の中で魚を追っている村の小娘たちは、自分と背丈とあまり変わらぬ弟を背負って、異国人に『オハイオ』と陽気に声をかけてくる。彼を感動させたのは、『例のオハイオやほほえみ』、『家族とお茶を飲むように戸口ごとに引きとめる招待や花の贈り物』だった。『住民すべての丁重さと愛想のよさ』は筆舌に尽しがたく、たしかに日本人は『地球上最も礼儀正しい民族』だと思わないわけにはいかない。日本人は『いささか子どもっぽいかも知れないが、親切と純朴、信頼にみちた民族』なのだ。
リンダウも長崎近郊の農村での経験をこう述べている。『私はいつも農夫たちの素晴らしい歓迎を受けたことを決して忘れないであろう。火を求めて農家の玄関先に立ち寄ると、直ちに男の子か女の子があわてて火鉢を持って来てくれるのであった。私が家の中に入るやいなや、父親は私に腰掛けるように勧め、母親は丁寧に挨拶をしてお茶を出してくれる。‥‥もっとも大胆な者は私の服の生地を手で触り、ちっちゃな女の子がたまたま私の髪の毛に触って、笑いながら同時に恥ずかしそうに、逃げ出していくこともあった。いくつかの金属製のボタンを与えると、『大変ありがとう』と、皆な揃って何度も繰り返しお礼を言う。そしてひざまずいて、可愛い頭を下げて優しく頬笑むのであったが、社会の下の階層の中でそんな態度に出会って、全く驚いた次第である。私が遠ざかって行くと、道のはずれまで見送ってくれて、ほとんど見えなくなってもまだ、『さよなら、またみょうにち』と私に叫んでいる、あの友情の籠もった声が聞こえるのであった』」。
● まだ未完成です(完成率60%)。このあとに随時追加していきます。(なわ・ふみひと) このコメントを編集する場合は以下のURLをクリックしてください。
<http://app.f.cocolog-nifty.com/t/app/weblog/post?__mode=edit_comment&id=110438295&blog_id=14400
34>
このコメントを削除する場合は以下のURLをクリックしてください。 <http://app.f.cocolog-nifty.com/t/app/weblog/post?__mode=list_comments&confirm_delete=1&confirm_id=
110438295&blog_id=1440034>
--
ココログ
http://www.cocolog-nifty.com/
|
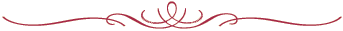
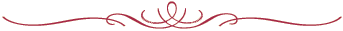
![]()
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)