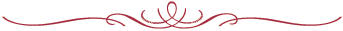
| 筆坂の日共党中央批判/考 |
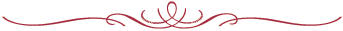
(最新見直し2006.5.30日)
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| 日共の政策委員長として権勢を振るってきた筆坂が失脚し、離党後半年余こたび「日本共産党」の題名の著作を発刊した。2006.4.20日初版であるが、実際には数日前に発売された。セクハラ事件については、既に「筆坂失脚事件考」で考察している。これに日共党中央は久方に大仰な対応で反論体制を敷いた。早速の4.19日に不破議長が、4.20日、幹部会副委員長・浜野
忠夫が、4.21日、志位委員長が反論を赤旗に掲載した。 おかしなことに今のところ「さざなみ通信」でさえ、関連の投稿がさほど為されていない。2チャンネルに「筆坂秀世『日本共産党』(新潮新書)を読む」のスレッドが立ったが、内容のある議論が為されていない。寒いことである。例によって、れんだいこが斬り込むことにした。 2006.4.22日 れんだいこ拝 |
![]()
| れんだいこのカンテラ時評その160 | れんだいこ | 2006/04/20 | |||
| 【れんだいこの書評「筆坂秀世著『日本共産党』」】 れんだいこは、「左往来人生学院掲示板」での2006.4.17日付投稿「れんだいこのカンテラ時評第159」で次のように記した。
早速書店に行き、筆坂著「日本共産党」(新潮文庫、2006.4.20日初版)を購入して中身を確認した。れんだいこの予想通りの日共党中央の腐敗を内情暴露しており、いわば内部告発本となっている。(実際には筆坂は離党しているので、正しくは内部告発というより内情告発と云うべきだろう) 筆坂は、日共党中央からの迫害が予見される危険を顧みず、何故敢えて我が身に引き受けたか。ここに関心がもたれる。 れんだいこは、次のように推理する。その1の理由として、筆坂は、宮顕ー不破ラインの不倒翁執行部による党中央の腐敗が一般に予想されている以上に酷いものであり、自身の人生の過半を投じた党活動履歴の自負に賭けてこれを告発せざるを得なかった。その2の理由として、宮顕ー不破ラインの不倒翁執行部の腐敗は、もはや自浄能力を欠いているどころか養分を吸い尽くした後の立ち枯れ木状態にあり、むしろ筆坂の駄目押しを期待していると読んだ。その3の理由として、その2に関連して、党中央にはもはやかっての宮顕御用的特務機関の威力が無く、彼らも党中央の腐敗を持て余しており、故に迫害されない。迫害されるほどの力が無い。 筆坂は以上のいずれかの読みから「日本共産党」を出版したものと思われる。れんだいこに云わせれば、筆坂の告発は、党中央に居合わせた者からの宮顕ー不破ライン執行部の際限の無い腐敗暴露という点で希少価値がある。その威力は、袴田の「昨日の友へ」以来のものであろう。袴田が宮顕を、筆坂が不破を告発したことになる。願うらくは、筆坂は、知りえた情報をもっと公開し、歴史に遺さねばならない。それは、党中央潜入スパイ派の実態を暴露する意味で貴重なドキュメント証言となろう。 彼らは、能力の不足により党指導を歪めたのではない。党の換骨奪胎を狙う異分子故に能力を党指導を歪めるように使う。御身保全だけでは理解できない数々の反革命的悪行に手を染めている。筆坂が暴露すればするほど、れんだいこのこの指摘の正しさが確認されることになるだろう。故に、筆坂は口封じされる運命にある。永遠にか金銭でか、それは分からない。 筆坂の告発は、日共の現綱領、現路線を概ね肯定的に捉えた上で、派生的腐敗を告発するというスンタスに特徴がある。故に、不破ー志位執行部は逆に反撃し辛(づら)い。党内事情の酸いも甘いも、手の内を知り尽くした相手であるだけに、これまでと同じような批判を浴びせる訳にはいかない。そういう意味で、当面様子見の黙殺以外に手の施しようが無いと思われる。 れんだいこの診るところ、筆坂の政治能力は宮顕ー不破イデオロギーにかなり深く洗脳されており、その分詰まらない。如何にうまく使われ、使い捨てにされたのかの両面に於いて、使い捨てにされたことによる反発から事を為している様子は伝わるが、如何にうまく使われたのかの分析がまるで出来ていない。 筆坂が正気に戻るにはもう少し日数がかかるのかも知れない。付言すれば、かっての新日和見事件の被害者達の心情もそのようなものであった。彼らは決して日共の路線批判にまでは向わない。その分物足りない。 以上が、筆坂の内情告発に対するれんだいこの総合感想である。以下、個別に検討してみたい。 まず、宮顕観について見ておく。筆坂は次のように述べている。
「筆坂の宮顕観」は、拵えられた通説に過ぎない。れんだいこは、宮顕論でそのウソを告発し抜いている。にも拘わらず何の弁証も無くこれを無視し続け、通説の俗説に固執するのはいわば「サバの頭」を信仰しているに過ぎない。そう思いたい故に我はそう思う、という手合いに漬ける薬は無いので処置無しと云える。 れんだいこ史観によれば、宮顕が「12年間も牢獄につながれながら非転向を貫いた」という神話自体のウソさ加減に思い至らない頭脳では政治指導者としてそれだけで失格であろう。逆に、「即時虐殺された幹部が居る中で、何故宮顕だけが非転向を貫けたのか」を問うことこそが事態の核心に迫ることのできる道である。 実際には、数々の資料と証言を付き合わせれば、宮顕は監獄内で放し飼い状態にあり、特段の拷問も受けていないと理解すべきである。従って、「仮に宮本さんのような弾圧を受けたら黙秘で頑張ることができるか」などと問い、恐れおののく必要は無い。「黙秘で頑張ることができる」などという事は在り得ない。それが在り得たという事は、宮顕と当局が共同して拵えた神話であり、ここに疑惑を持たねばならない。 何なら、当時の特高の誰それに確認すればよかろう。「当時、黙秘で、取調べを頑張り通すことが出来ましたか」と。れんだいこの結論は「有り得ない」。故に、それを在り得たとするのは、陰謀により生み出されたフィクションでしかない。 故に、筆坂の「宮本氏の卓越した政治的眼力とリーダーシップ」を高く評価する見識もいただけない。実際は、日共を今日の如く役立たずにしてしまった路線を敷いた張本人であり、それも意図的故意に「闘う日共解体戦略」に基づき持ち込まれたものに過ぎない。もうこれぐらいにしとこ。 次に、筆坂が、数々の疑惑追及につき国会で追求したことを次のように自画自賛している。
筆坂が思いつくままに挙げた「日本共産党が抜きん出た調査力を発揮した汚職・腐敗事件」は曲者である。れんだいこの観るところ、日共の疑惑追及は背後で操作されたような訴追の仕方が多く、むしろそこをこそ詮索すべきであろうに、筆坂は今に至るまで無自覚なようである。 時に特ダネを飛ばすが、不自然に入手された特ダネが多い点を気にかけるべきだろう。特に、政府自民党内のタカ派とハト派の抗争に於いて、専らハト派の不祥事追求に精力的になる癖の原因を解明すべきだろう。中曽根ー小泉系譜のシオニスタン系タカ派の汚職・腐敗事件例えばFX選定事件、ダグラス・グラマン事件、リクルート事件等々に関して、誇るほどの訴追をしなかった原因をこそ探るべきだろう。 筆坂はその他、幹部会、党財政、政党助成金、民主集中制、党勢拡大運動、選挙総括、党内選挙、党内人事、党指導部、党員、拉致事件、自衛隊、皇室、民主連合政府等々に関わる諸問題での党中央の対応を批判している。それぞれの論点を列挙すればキリが無いので割愛するが、宮顕ー不破ー志位党中央の恐るべき空疎な指導ぶりを明らかにしている。 要するに、「至らない者が至ろうとして生起させた諸問題ではなく、党中央が党をわざと至らせない為に仕組んだ数々の不祥事問題」として受け止めない限り理解できない、ということである。ここを見抜かずにマジメそうに注進する者が後を絶たないが、党中央は分かった上で意図的故意にやっているという認識に立つ必要がある。たとしたら、注進者より役者が上ということになろう。このことが分からない下手な役者の正義ぶりが多過ぎる。 2006.4.20日 れんだいこ拝 |
|||||
| 【不破議長の反論】 | ||
2006.4.19日、赤旗は、不破議長の「筆坂秀世氏の本を読んで」を掲載した。これは貴重な反論ゆえ転載しておく。
|
| Re:れんだいこのカンテラ時評その161 | れんだいこ | 2006/04/22 |
| 【不破の筆坂の党批判反論をれんだいこが駁す】 筆坂の内情告発「日本共産党」を読んで、不破議長はよほど頭にきたらしい。至るところに配慮を欠いた反論をしていることが透けて見えてくる。れんだいこが筆坂になり代わって反論しておこう。 不破は、「筆坂秀世氏の本を読んで」(http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-04-19/2006041925_01_0.html)で次のように反論している。早くも例の茶坊主が不破反論に沿ってヨイショし始めている。馬鹿馬鹿しいから取り上げない。今のところ、れんだいこのように筆坂の方がまだしもましという観点から立論する者はいないようである。この後は分からないが。 不破は、筆坂が「日本共産党への『弔辞』」と題する「特別手記」(2005.9.29日号週刊新潮)、「日本共産党」(新潮新書、2006.4.20日初版)により、「党に敵対する立場を明確にしました」と云う。それはそうだろう。問題は、不破が、筆坂の訴えに聞く耳をどれだけ持つことが出来るのかにある。 不破は、「ここまで落ちることができるのか」という見だしで次のように述べている。早速例のセクハラ事件に反論し、今更冤罪と云うのなら、「なぜ、そのとき、正々堂々と自分の態度を説明しなかったのか」と批判している。 不破よ、すり代えるな。筆坂は、著書の中で「不自然な経緯」の方に重点を置いて弁明している。お前が為すべきは、「不自然な経緯」に対する否定弁論である。特に、記者会見をしたかったと述べている。不破の指示で直前にキャンセルされたと述べている。これを釈明してみ。 「筆坂氏の語る「真相」とは……」という見だしで次のように述べている。冒頭、「私は、ある週刊誌にこの本の予告的な報道記事が出たとき、それを読んで目を疑った」と述べている。これは、事前のゲラ刷りのことであろう。不破はそういうものが手に入るようである。 筆坂の宮顕引退時の経緯に関する記述に触れて、事実と齟齬していることを縷々聞かせる。しかし、筆坂のそれは、末尾が「ように聞いている」とあり、伝聞ということを明示している。そんなものを「事実と齟齬している」と批判しても意味が無かろう。 筆坂の宮顕引退時の経緯に関する要点は、不破が宮顕に引導を渡したこと、それにより宮顕の法皇的地位を不破が継承したことを示唆していることにある。不破よ、批判するのなら、それが事実と違うのかどうかを弁明してみ。 お前はこたび、「宮本さんの退任の問題について、二人での話し合いを始めた」、「一致した結論にいたるまでには、時間がかかったが、九月に入って間もなく、話し合いがまとまった」、「私と志位書記局長(当時)の二人が宮本さんと会い、二人が議長退任の申し出を受けた」ことを明らかにした。十分すぎるほど、筆坂の指摘を裏付けているではないか。「この日程を見ていただければ、筆坂氏のいう『真相』など、入り込む余地がまったくないことがお分かりいただけるだろう」と反論したつもりのようだが、俗に云うヤブヘビになっているではないか。 「自分でつくった「ガセネタ」を自分で流す」という見だしで次のように述べている。「自分が『真相』として宣伝するものが、小泉首相の用語法にならえば『ガセネタ』であることを重々承知していたはずである」という反論もヤブヘビだ。今日の政治状況で、小ネズミが粗雑に使用した「ガセネタ」用語を使う神経が、お前の親小ネズミぶりを思わず吐露している。普通には、政敵の愛用語は安易に借用しないものだ。れんだいこはそう思う。 「不破議長時代の罪と罰とは……」という見だしで次のように述べている。筆坂の不破批判が、「拉致問題での外交交渉を論じた党首討論(二〇〇〇年十月)」と「民主連合政府のもとでの自衛隊の扱いについてのテレビ討論での発言(同年八月)」の「二つの点しかない」と捻じ曲げた上で次のように云う。 「私が日本共産党の議長をつとめたのは、第二十二回大会(同年十一月)から第二十四回大会(二〇〇六年一月)までの五年二カ月だが、その全期間を筆坂式で調べても、この二つの問題点しか見つからなかったのだろうか。しかも、二つの問題点なるものは、どちらも私が議長になる以前のことであって、それを「委員長時代」ではなく、「議長時代」の「罪」に数え入れるのは、「看板に偽りあり」ということになろう」。 これこそ、極め付きの詭弁、すり替え、歪曲であろう。筆坂の不破批判は総花的にあれこれ述べている。決して、拉致問題や自衛隊問題を廻る対応の拙さだけを批判しているのではない。実際に著書を読めば分かることだ。 次に、「委員長時代ではなく議長時代の罪に数え入れるのは看板に偽りあり」とはどういう意味か。お前が委員長であろうが議長であろうが一貫して党の最高指導者であったお前の指導を批判しているのだろうが。委員長と議長の区別をして難癖つけて何か事態が変るのか。お前はいつもこういう小手先の批判逃れをする。 「提起されている二つの問題点については、どちらも、ここに「罪」を求めるのは筆坂氏の独断にすぎない」という見だしで次のように述べている。筆坂の批判を「まったくの曲解」だとか、「私たちの政策のこうした発展のプロセスは、公開された形で明らかになっていることで、筆坂氏の“内幕”話などが入り込む余地は、なんら存在しない」と述べることで反論したつもりのようだが、何も云っていないに等しい。 筆坂はかって党の政策委員長の立場にあった。離党して初めて党の利益を逃れて公平な立場から当時の政策のあれこれを見直す機会を得た。見えてきたものを日本人民大衆に告げる責務を感じた。これが筆坂の偽らざる気持ちであろう。その気持ちに応えるお前の対応は、スピッツがキャンキャン吼えているような代物で、党の最高指導者の風格のそれではない。お前が慌てて感情的に反論したにせよ、そういうことが透けて見えてくるだけの話でしかない。 最後に伝えておく。この種の論争の場合、最低限必要なことは、当の筆坂の著書に当ることである。その上で、不破の反論を精査することである。当の著書を読まずに読んだ気にされ、不破の反論で事足れりとするのは、いつもながらの煙巻き論法に巻かれるだけのことであろう。 もう一つ最後に気にかかることを記しておく。筆坂は何気なく次の事実を明らかにしている。2004.11.17日、日共の不破夫妻が、東京元赤坂の迎賓館で、デンマークのマルグレーテ2世女王夫妻招待の夕食会に招かれ参列した。日本側の主賓は天皇皇后夫妻で、夕食会への参加は、日本の政党関係では不破夫妻だけだったとのこと。不破は、見知っている人として俳優の岡田真澄氏や外務省から宮内庁に移っていた役人がいたと伝えている。 これは何なんだ。政界関係者の中でなぜお前だけが選ばれてこういうところへ出向いたのだ。妙に引っかかるものがある。 2006.4.22日 れんだいこ拝 |
||
| 【浜野副委員長の反論】 | |
2006.4.20日、赤旗は、筆坂問題を廻る幹部会副委員長・浜野忠夫の「筆坂秀世氏の本の虚構と思惑」を載せた。これを転載しておく。
|
| 【志位委員長の反論】 | |
2006.4.21日、赤旗は、筆坂問題を廻る志位委員長の記者会見での「筆坂氏の本について 誤りの合理化が転落の原因」を載せた。これを転載しておく。
|
| 【赤旗の反論】 | |||
2006.4.26日、赤旗は、筆逆告発に関連して「『週刊朝日』編集子の不見識」(http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-04-26/2006042604_04_0.html)なる新たな反論を掲載した。これを転載しておく。
|
| 【赤旗のマスコミ抗議】 | ||||
2006.4.28日、赤旗は、筆逆告発に関連して日本共産党広報部名で、「筆坂本の一方的宣伝は不当 朝日ニュースターに抗議」(http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-04-28/2006042802_03_0.html)なる新たな記事を掲載した。これを転載しておく。
|
| Re:れんだいこのカンテラ時評その165 | れんだいこ | 2006/04/28 |
| 【日共の執拗な元党員攻撃が続いている。あきれはてるのはれんだいこだけか】 不破は、筆坂の告発によほど頭にきたらしい。赤旗で執拗に攻撃しており、この問題を採りあげた出版社やマスコミに圧力かけ始めている。しかし、やればやるほど馬鹿さ加減が浮き彫りになるだけであろうに、それさえ分からないらしい。 考えてみれば、筆坂に至るまで過去何人の元大物党員がこういう形で罵倒されたことだろう。何事もやり過ぎると食傷されるということも分からないみたいだ。 最新の赤旗は、このところ癖になっているマスコミ恫喝を恥ずかしげも無く記事にして嫌らしい形で正義ぶっている。それほどガセネタだと云うのなら、採りあげたことがけしからんというのではなしに、公開討論会を挑まんかい。できるだけたっぷり時間を取って、筆坂が告発した箇所の隅々までガセネタぶりを論えば良い。 日共よ、お前達の論法から引き出されるべきはそういう態度を採ることである。そこを急に捻じ曲げて、筆坂批判、新潮社批判、テレビ局批判に耽るというのは姑息である。特に、マスコミに権力的容喙をするとなると、日頃の民主主義云々に照らして、云っていることとやっていることが違うがな。 日共が避けている論点は次のところである。筆坂が、秘書と婦人と焼肉店へ行き、その後カラオケボックスで婦人とディェットし、腰の辺りに手を回した。あるいは撫でた。それは事実であるがそれがどうしたというのだ。それぐらいのことで何で党の政策委員長を辞めさせられ、議員辞職までさせられねばならないのか。それこそ公党暴力ではないのか。どうせ裏の事情があったのだろうが度が過ぎて一線を越えていよう。 れんだいこには、それが当たり前だという神経が分からない。世間はそのことを問題にしているのだろうが。お前達はそれぐらいのことでかくも制裁を科すほど本当に潔癖か。不破も含めて過去を顧みて述べてみ。 次のことも云っておく。お前達は、「日本共産党の名誉を傷つける行為」であろうが無かろうが、甘んじて報道の自由を守るべきではないのか。それとも、「公党の名誉を傷つけてはならない」という新法でも出来たのか。日本共産党の名誉をそれほど気にするのなら、他党の名誉も同じように守ってやれや。手前らだけは除外つうのは虫が良すぎよう。 お前達が、「報道は、事実を客観的かつ正確、公平に伝え、真実に迫るために最善の努力を傾けなければならない」との放送倫理基本綱領を引き合いに出すのなら、筆逆告発が事実かどうか、討論番組でやりおうたらどうか。「すみやかな謝罪・是正を求める」などは姑息で、バトルテーブルを用意せよと云うのが本筋だろうが。 お前達はいつも問題を逆に解決しようとする。選挙に負けた時の責任の取り方もそうだ。責任は誰でも取れる。この後に責任を取るのが真の責任のとり方だと上手に口を動かしては、負けばかりしている。こうして永遠に執行部が維持されるという仕掛けだ。 エエカゲンにしておかないと最後には閻魔さんに舌を引っこ抜かれるぞ。 2006.4.28日 れんだいこ拝 |
||
| 【「週刊朝日の5/5・5/12号の筆坂秀世氏と有田芳生氏の対談末尾」】 | |
週刊朝日の5/5・5/12号の筆坂秀世氏と有田芳生氏の対談末尾に、次のように記されている。
これは何を意味しているのだろうか。週刊朝日誌の質問状に対する回答が「答える必要がない」だと。これは、「さざなみ通信」の「組織論・運動論討論欄」の風来坊氏による2006.4.27日付投稿「週刊朝日の筆坂秀世氏と有田芳生氏の対談について」が伝えている。 赤旗は、筆坂告発を小ネズミ首相ばりにガセネタ呼ばわりしており、赤旗だけ読めばそういう気分にさせられてしまうが、事実は、「事実確認などのための質問状」に対する回答拒否しており、いわば「云い得云い勝ち」という不当なキャンペーンを続けていることになる。当然ながら、事実確認すれば不利になるという事を踏まえての対応であろう。それにしても腐敗である。宮顕ー不破の宿アの体質を又も見させられていることになる。 2006.5.4日 れんだいこ拝 |
| 【薄幸ダイオード氏の「共産党にとって、国会議員は共産党の単なる派遣社員に過ぎない」の指摘考】 | |||
「さざなみ通信」の「一般投稿欄」の薄幸ダイオード氏の2006.5.25日付投稿「共産党は本当に護憲勢力なのか?」は、問題の核心を射ているので転載しておく。
|
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)