|
都知事選における敗因は脱原発派の分裂にあり、その元凶は共産党のセクト主義にある(その1)(2013/3/2 )
(1)、はじめに
都知事選の結果は、予想されたこととはいえ、奇跡的などんでん返しは起こらず、口先男の舛添の勝利に終わった。何ともはや、やりきれない気分だが、自説の検証とネット上に見られる主な批判への応答はしておくことにしよう。 ネット上の論調をみると、宇都宮支持派が細川に勝ったと意気軒昂であり、主敵が誰であったかを忘れたような高揚ぶりが目につく。この現象はここ10年以上にわたって負け戦続きであったゴリゴリの共産党員の鬱憤晴らしか、あるいは福島原発事故後に政治に目覚めた経験不足の若者達の存在を示すものであるが、他方では同じ社会事情が極右の田母神の61万票をも生み出している。また、「ノーサイド」の声もあるものの、半世紀にわたる原水禁運動の分裂が何をもたらしたかということを念頭に置く時、宇都宮派、特にその本隊である志位ら共産党の誤りを明確にしておくことはやはり必要なことである。
(2)、主要な論点の概略
長くなりそうなので、先に総論的なところを書いておこう。その第一は細川と宇都宮の得票を合計すると194万票もあり、細川・小泉拒否派の石頭の連中の票を除いても、細川で一本化できれば、生活の党の小沢も言うように、脱原発派にも十分な勝機があったということがひとつ。なぜ細川なのかと言えば、国民の脱原発政策支持率は約7割あり、脱原発政策を掲げながら、左翼嫌いの中間・保守層の脱原発票を取り込めるのは細川だからである。事実、前回と比較すると、脱原発票は宇都宮の97万票だけだったものが、今回は194万票へと拡大している。この194万票は投票総数493万票の約40%にすぎず、まだまだ、有権者を呼び込める「伸びしろ」があったのであるが、出口調査(朝日2月10日付)では、舛添に脱原発票の3割(100万票)が流れている。
|
 (私論.私見) (私論.私見) |
| ここまでは良い論評のように思えるが、選挙結果に於けるムサシマシーンの不正選挙操作の可能性を問わないのは片手落ちだろう。 |
| 第二は、宇都宮票が細川票より26535票多かったことをもって、一本化するならば宇都宮での一本化が正しく、細川での一本化論は誤りであるという主張についてである。どこかの共産党系の大学教授は、得票数の多い宇都宮は細川より当選可能性が高かったとまで言っているようであるから、熱心な宇都宮派にはこの得票差が金科玉条のようにみえるのであろう。しかし、このような主張は得票差を単純に比較しただけの視野狭窄、全く馬鹿げた見解なのであって、何のための一本化論議であったのかがすっかり忘れられている。200万票の基礎票を持つ舛添に勝つための戦術なのであって、その戦術の目的からすれば、単なる得票差ではなく、総投票数との関係で見なければ意味はない。
その得票差26535票は総投票数との比較では0.54%の差でしかないのであって、この程度の差は、当日の天気次第で容易に変動する得票差に過ぎない。当日が大雪で、投票率が46.1%と下から3番目に低い投票率であったために、全国動員をかけてまで注力した共産党の基礎票が若干の効果を発揮しただけである。26535票の差は、吹けば飛ぶようなわずかな得票差であって、その差に有意性はない。実際の比較でも、舛添票211万票(得票率43.4%)に対して宇都宮の98万も細川の95万もダブルスコアの負けであって、宇都宮票と細川票の比較は「どんぐりの背くらべ」にすぎない。その「どんぐりの背くらべ」をさも重大事のように云々しているのが、宇都宮派の主張なのである。
この選挙の敗北の意味するところは重大で、「ファナティック」な宇都宮派が細川に勝ったと「ぬか喜び」している間に悪政はどんどん進んでいく。今後の2年半のフリーハンドを得た安倍政権は原発の再稼働を旺盛に進めるであろうし、また「戦後レジームからの脱却」、ヒトラーの知恵を拝借した「改憲なしの憲法の停止」(特定秘密保護法や集団的自衛権の解釈変更など)へのアクセルをつよめるであろう。
|
 (私論.私見) (私論.私見) |
| ムサシマシーンによる不正選挙操作の可能性を問わなければ、こういう論評になると云う良い意味での見本である。 |
| 第三は、細川陣営最後の街頭演説で、大雪の中、長く浜岡原発訴訟をやってきた老弁護士が言っていたことである。これまで反原発運動は、左翼や環境派、様々な市民運動などが半世紀近くもやってきたが、結局、止めることはできなかった。そして54基もつくられてしまった。相手は実に強大であり、原発を止めるにはどうしても脱原発に目覚めた保守と手を結ばないことには絶対にできない、ということである。政策がより良いとかで宇都宮を推した政治経験の乏しい若者はこのことがわからない。どこの国の政治世界にもよくあることだが、偏狭な理想主義のもつ無分別が彼らの運動の目的とは正反対の結果をもたらす。 500億円の買収資金を積まれても、稲嶺が勝利した沖縄・名護市長選をみてもそうである。本土では社共が強いからと想像しがちだが、そうではない。いわゆる草の根保守が反基地だから勝利できたのである。26人の名護市議のうち、共産党は1名にすぎない。社会大衆党も社民党の名前も見あたらない。 |
 (私論.私見) (私論.私見) |
| ここはこれで良い。 |
| 第四は、敗因についてである。言うまでもなく、敗因は脱原発陣営の分裂である。共産党が脱原発陣営分裂の張本人であり、昨年の都議選、参議院選での復調の流れを強めるために、宇都宮を先行的に担ぎ出して「準」自前候補として、自由に党活動(党勢拡大の運動)ができるように都知事選を利用したということである。例によって、共産党の後天的本能となっている党勢拡大至上主義=セクト主義が暴発して、12月28日の宇都宮による「いの一番」の出馬表明をもたらしたのであり、この「フライング」こそが分裂の芽を胚胎させることになったのである。
問題はなぜ、この「フライング」が起きたのか?である。宇都宮が「いの一番」に手を挙げ、共産党が社民党と同時にではあれ、早々と推すということになると、宇都宮は左翼候補と見なされるのは必定で、これでは200万票の基礎票を持つ舛添に勝つ戦略を放棄したも同然である。両党の合計基礎票はMAXで90万票(70+20万票)、それなのになぜ宇都宮は早々と立候補したのか? しかも、前回、トリプルスコア以上の大差でボロ負けた候補がである。普通の政治センスの持ち主ならば、候補者には不向きな「玉」と自覚して、推されても辞退するのが当然であったろう。ところが宇都宮は違った。なぜか?
宇都宮が「隠れ共産党員」なら話は早い。そうでないのなら、どこかの時点で、宇都宮と共産党は「握って」おり、宇都宮に「魔が差した」のである。右であれ左であれ、人は変わる。政治の激動期に、その渦中に身を投ずればなおさらである。
前回の反省に経って、いち早く選挙準備を始めることの何が悪いと言う向きは、偽善者か経験不足の者の言うこと。革命政党の名を掲げながら90年も政権を襲ったこともなく、生きながらえても国政選挙でいまだ10%の得票率さえ確実に得られない政党が、早期に選挙準備に入ったところで高が知れている。得票が基礎票の3倍にも4倍にもなるわけがないのだ。それだけ国民の評価は確定しているし、評価に十分な時間もあったのである。かつて共産党は、ソ連が崩壊した時、ソ連を世界の社会主義運動や進歩的政治運動の障害物と批判したが、今では、同じことを日本の共産党が国内でやっている。反省亡き者の因果は巡る。
|
 (私論.私見) (私論.私見) |
| 原氏は共産党の変調対応を鋭く衝いている。しかし、「れんだいこ式日共論」を確立していないので、共産党がなぜこのような拙劣な対応をするのかが理解できない。共産党の拙劣対応が意図的故意のものであったなら原氏的批判は馬耳東風にされるだろう。れんだいこは、毎度の意図的故意の拙劣対応とみなしているので「例によって共産党の後天的本能となっている党勢拡大至上主義=セクト主義の暴発」などとは見なさない。「宇都宮に魔が差した」などとは見なさない。日共と宇都宮を結びつける黒い霧があると見立てる。 |
|
都知事選の候補一本化論について。丸氏への回答(2013/3/22 )
さざなみ通信の論客が、前回の議論への反論に応えています。
原氏の前回の議論
http://www.asyura2.com/14/senkyo162/msg/489.html
への反論は
http://www.geocities.jp/sazanami_tsushin/readers/readers.html
で見ることができます。
が、議論の体をなしているようには見えません。そこで、原氏の前回の議論の補足として以下を転載しておきます。
http://www.geocities.jp/sazanami_tsushin/readers12/1403/r1403b.html
(1)、はじめに
私の言う細川への一本化論は、脱原発派を都知事選で勝たせようとする選挙戦術であって、脱原発政策を左翼の専売特許とそのイメージから救い出し、左翼嫌いの脱原発派の保守・中間層をも取り込もうとねらうものであった。しかしながら、共産党は1月27日に「全都幹部活動者会議」を開き、「細川はこれまでの都政の継承者だ」(「赤旗」1月28日付)と規定し、石原都政とその継承者猪瀬の同類だと主張していた。この同類論は共産党お得意の「同じ穴のムジナ」論の一種であるが、細川の脱原発政策(即時原発ゼロ、再稼働阻止)を敢えて無視する点で驚愕すべき頑迷・偏狭ぶりを発揮した。2011年、「維新」の橋下が府知事を辞めて大阪市長選に立候補した時は、用意した自前候補を降ろし、政策協定も結ばず、勝手連風に、自・民が推す現職の平松に相乗りしたのだが、その「柔軟性」(?)と比較すると、今回の都知事選をめぐる動きはまったく対照的であった。そのせいか、左翼には頑迷・偏狭ぶりは伝播しやすいのか、小泉・細川嫌いが触媒になっているのか、日頃は共産党にも距離を置き、孤高の地位に留まっていた丸氏が宇都宮陣営に投じて私の一本化論を批判している。
|
 (私論.私見) (私論.私見) |
| 共産党の対応が、大阪市長選の時には用意した自前候補を降ろし、政策協定も結ばず勝手連風に自・民が推す現職の平松に相乗りすると云う柔軟さを見せたのに対して、都知事選の時の硬派的対応を無原則的と批判している。これはその通りで、分かり易い比較だろう。 |
(2)、丸氏による一本化論批判・その1
原は宇都宮を政策が総花的で脱原発に熱意がない、と言うのであるから、宇都宮が出馬したところで細川とバッティングしないじゃないか、「宇都宮の立候補はほとんど障害にはなり得ないはずである。」と主張している。しかし、これは奇妙な理屈である。私は宇都宮の政策メニューが脱原発も福祉も並列的で総花的であると指摘しているが、宇都宮が脱原発(原発即時ゼロ)政策を主張していない候補だと言っているわけではない。前回も今回も宇都宮は脱原発を主張する候補であり、選挙戦の実際も、大方の予想どおり、細川と脱原発票を真っ二つに二分し、安倍政権に安眠の枕を提供したのである。だから、私は脱原発派の敗因はその分裂にあると言っているのである。
(3)、丸氏による一本化論批判・その2
また、丸氏に言わせると、一本化で共産党が細川支持になれば、細川は「とんでもないハンデを背負わされることになっていたであろう!あくまでも原氏の主張に従うなら、それが論理的帰結である。」と言うのである。「とんでもないハンデ」とは、細川に共産党の支持が来れば、脱原発政策を左翼の専売特許イメージから救うことも、保守・中間層の取り込みも難しくなると言うのである。この「とんでもないハンデ」がどうして「論理的帰結」になるのかわからないが、心配ご無用。庶民の政治意識は、丸氏の「論理的帰結」(?)より多様であって、細川・小泉の元首相連合の印象はやはりそれなりに強烈で、都民の感覚・印象からすれば、細川が左翼候補になるのではなく、逆に、脱原発政策が左翼専売特許のイメージから救い出されたと見てよいだろう。「首都圏反原発連合」の呼びかけ人ミサオ・レッドウルフも同様の感想を述べていたはずである。
その目安としては前回の都知事選と比較して、左翼専売特許イメージに取り憑かれていたはずの脱原発票が2倍に増えたことである。この悪しきイメージの付着は、細川への一本化如何に関わらない既存の事実であったことを想起してもらいたい。にわか脱原発派には実感できないであろうが、長く反原発運動に関わってきた者には痛感されてきたイメージなのである。呪われた脱原発政策は細川・小泉連合の咆哮で呪いが解かれ脱原発票が新たに出て来たのであって、共産党がやって来ても、もはや、解かれた呪いは元には戻らないというのが、むしろ、「論理的帰結」なのである。
(4)、脱原発政策に架けられていた呪いは解かれた
前回はただ一人脱原発を言う一本化候補でありながら、宇都宮票は96万票にすぎず、そのほとんどは左翼票(社共の基礎票だけで7~80万票)であった。今回もその9割方の票が宇都宮に行ったと推測されるのであるから、細川票96万票の大半は新規に掘り起こされた保守・中間・無党派層の脱原発票である。時事通信の出口調査によれば、自民支持層の9%、民主の39%、維新の21%、社民の21%、無党派の25%、共産の8%が細川に投じている。宇都宮票との比較で見れば、宇都宮に投じたのは民主支持票の25%、維新の12%、自民の4%、無党派の26%である。自民・民主・維新から奪った票でみれば、細川は宇都宮にほぼダブルスコアに近い差をつける健闘ぶりであることがわかる。また、読売の出口調査(2月10日付)によれば、重視した政策で投票動向を見ると、宇都宮の支持層は「14%」しか「原発などエネルギー問題」を重視していないのに対し、細川支持層ではそれが「62%」に跳ね上がる。この両者の違い、細川の「62%」は、有権者の投票動向の歴史的新段階とでも規定して格別に重視されて良いのだが、ここでは触れない。
大雪で史上3番目の低投票率の中で、しかも、都民の身の回りの直接的生活利害からは遠いにもかかわらず、これだけの脱原発票が新たに出現したのである。宇都宮票と合わせて194万票にもなり、舛添の211万にそれほど見劣りしない脱原発票数が出たのだから、脱原発政策が都知事選を境に市民権を得たと言っても良いだろう。細川を共産党が支持しても脱原発票は減らない。むしろ、共産党のためには、細川を支持した方がその柔軟性が注目され、保守・中間層からも見直しの気運が出たのかもしれないほどである。
(5)、「ドン引き」する丸氏の敗因論
さて、私は以上のように反論したわけであるが、丸氏は上記に紹介したふたつの一本化否定論から、真の敗因、その元凶は悩んだ末に細川支持を表明した「『脱原発都知事を実現する会』『脱原発都知事選候補に統一を呼びかける会』」だと言うのである。これはまた面妖な、と思うのだが、どうしてそんなことになるのかと言うと、これらの会に名を連ねる人たちが「左翼以外の何者にも見えないであろう人物ばかりである」からなのだそうだ。つまり、私が取り込もうとねらう保守・中間層が「ドン引き」しちゃったと言うわけである。かくて、例によって、丸氏にかかると次のような大層な結論に行き着くのである。「都知事選における脱原発派の敗因とその元凶を宇都宮と共産党に求める原氏の見解は、原氏自身の主張によって内在的に破綻、ないし完全な自家撞着となっているのである」。
こんな丸氏の文章を読むと、まじめに反論を書く自分がアホらしくなってくるが、次のように回答しておこう。丸氏の言う左翼丸出し顔の面々が細川支持を打ち出しても、また短期間で、選対の混乱など準備不足があったにもかかわらず、細川は宇都宮票に匹敵する96万票を新たに掘り起こしたのであり、その事実こそ、「ドン引き」はなかった証拠なのである。だからまた、共産党がやって来てもウェルカムである。しかも、この掘り起こし票の「62%」は脱原発政策を重視する有権者なのであって、宇都宮票の「14%」とは格段の差があった。 |
 (私論.私見) (私論.私見) |
| 原氏はまじめに丸氏論を俎上に乗せて批判しているが、この御仁が党中央擁護の任務を帯びて登場しており、この任務に添って意図的故意に立論しているとすれば、批判も役に立たないだろう。 |
(6)、行方久生の「重回帰分析」なるもの・その1
私の一本化論への丸氏の批判は以上のようなものであるが、一本化論に関連して丸氏が自説の補強に引用している「行方久生・文教大学教授」による「重回帰分析」なるものを検討しておこう。この行方の論は前に一見したことがあるが、改めて調べてみると、宇都宮支持派が拡散に熱心なようであり、当人もバリバリの宇都宮派で一本化論者は「頭を丸めて、四国のお遍路さんをやってほしい」と言うほどであるから、こちらも遠慮は無用なようだ。
丸氏の引用文から孫引きして紹介すると、次のような要旨になる。細川と宇都宮の支持層では、「所得の状況によって、投票する対象がかなり鮮明に異なっているという事実」があり、「仮に一本化しても、もともと、投票する人たちが異なるので、その効果は、極めて限定的なものであったというのが事実である」。どういうことかというと、当人の日本語能力に問題があるようで解説が必要なのだが、所得水準に規定されて宇都宮であったり細川になるのだから、一本化しても「その効果は、極めて限定的」、一本化は効果がないから一本化は無意味だ、と主張しているわけである。これが統一戦線思想それ自体の否定論であることは指摘するだけに留めておこう。
さて、この行方「重回帰分析」なるものは、その結論(解釈)が我田引水で完全に間違っているのである。大学教授であっても、ある種の政治的意図を持って専門外の選挙分析などをやるからこういうことになる。丸氏は行方「重回帰分析」なるものを受け売りするだけで、自分でその内容を検討していない。
(7)、行方久生の「重回帰分析」なるもの・その2
「重回帰分析」なる分析手法はそれほど難しいものではなく、「ウィキペディア」を見れば、何だ、こんなことか、と簡単な英単語の事例で説明があるので、そちらを参照してもらうとして、行方の分析は用語も丸めて要点を簡単に言うと次のようになる。まず、東京23区の区・別一人当たりの平均所得を官庁統計から取り出す。次に23区における宇都宮と細川の得票差を取り出す。私の手元資料では最大7611票(世田谷区・細川のプラス)、この二つの数値を、縦軸に得票差(ゼロ点を中心に、上が宇都宮のプラス差、下が細川)、横軸に平均所得(左端をゼロ円とし右端が900万円)、そして各区をこのマップ上のピンポイントとして記入する。例えば、低所得の板橋区でみると、平均所得375万円(2006年)で宇都宮の得票が細川より6076票多いのであるから、板橋区のピンポイントは左上に来る。こうした作業を23区全てについてやる。そうすると、ピンポイントの密集するところをねらって、左上から右下にかけて一本の直線を引くことができる。この直線は簡単な数式で表現できるが、ここでは省略。また、当たり前のことであるが、この直線上に23区のピンポイントがきれいに並ぶわけではない。
(8)、行方久生の「重回帰分析」なるもの・その3
さて、このピンポイントマップとそこに引かれた直線から、どういうことがわかるかというと、23区のうち、平均所得水準の低い区で宇都宮票のプラス分が多く出ていることがわかり、細川では平均所得水準が高い区でプラスの得票差が出ているということである。しかし、この程度のことは、こんな分析をしなくても、およそわかっていることである。宇都宮98万票のうち80万票は社共の票であるから、どちらかと言えば所得の上では下層が多いから、平均所得水準の低い区では相対的に宇都宮が強い。細川票は宇都宮より保守・中間層の比率が高いのだから相対的に所得水準が高いところで強いと推定できる等々。そして、この程度の分析から上記引用の行方主張が言えるのか、と言うことである。すなわち「所得の状況によって、投票する対象がかなり鮮明に異なっているという事実」があり、「仮に一本化しても、もともと、投票する人たちが異なるので、その効果は、極めて限定的なものであったというのが事実である」。
(9)、行方久生の「重回帰分析」なるもの・その4
まず、「所得の状況によって」と言うものの、そこで上げられているのは区・別の平均所得(行方論では「総所得金額等」)だけなのだから、たとえば、低い方の板橋区375万円(2006年)はどういう性格の所得なのか? 労働者階層なのか中間層なのか? 実際は金持ちから失業者まで含んだ平均が375万円なのだから、「所得の状況によって、投票する対象がかなり鮮明に異なっているという事実」なんて言えるわけがないし、わかるわけもない。こんなことを言うためには、平均所得ではなく、出口調査で有権者にその所得と投票した候補者をもれなく聞かなければならない。
仮に平均所得が375万円なのだから板橋区は労働者階級で代表させるとして、そのせいで宇都宮票は細川より6076票(私の調べ)多いのだ、と主張すれば笑われるであろう。全国一の港区の平均所得1006万円(2006年)では、金持ち階層で代表させ、それで細川票が6824票多いのだと納得できるであろうか。港区の有権者の実際の投票動向は舛添34808票、田母神12738票、細川19792票、宇都宮12968票で、何と金持ちが宇都宮に13000票も! と解釈すれば、これはもう悪い冗談で、学者がやることではないだろう。どの区でもそうだが、ある平均所得を得ることは計算上できるが、実際の有権者は金持ちから失業者までおり、それぞれの人が誰に投票したかを所得水準ごとにグループ化するには、区ごとの平均所得を取り出すだけではできないのである。以上のようなわけであるから、もうこれ以上、行方「重回帰分析」の解釈にお付き合いする必要はないだろう。 |
 (私論.私見) (私論.私見) |
| ここでも原氏はまじめに行方論を俎上に乗せて批判しているが、この御仁が党中央擁護の任務を帯びて登場しており、この任務に添って意図的故意に立論しているとすれば、批判も役に立たないだろう。 |
(10)、遅れてやってきた小沢一郎の新弟子
最後に私の一本化論に対置する丸氏の選挙戦術を見ておこう。「一点突破全面展開とばかりに一回の選挙でどうにかしようという発想は、現実に成り立った試しがない。田中角栄が言い、小沢一郎が引き継いだ選挙の鉄則は、"戸別訪問3万軒、街頭演説5万回"であった。~~これぐらいの地道で持続的な活動こそが、脱原発派には求められているのではないか?」。
• いやはや、人は変わるものである。丸氏の変貌ぶりは瞠目してよい。かつて、6、7年前、私と論争した時は、無党派層への不信感を吐露していたのだが、角栄の秘蔵っ子・小沢一郎も丸氏のような新しい弟子を得たことを喜ぶであろう。どんな選挙であれ、コツコツと地道に有権者との対話を積み重ね、有権者の信頼を勝ち取ることは選挙運動の基本であり、そのことを私は否定したことはないし、国策捜査で弾圧された小沢を支持してもきたのである。問題は選挙運動一般の話ではなく、2月9日に行われた都知事選でどういう選挙戦術を採るべきであったのか、ということである。この選挙では特筆すべき事件=細川・小泉連合の脱原発派が登場したことであって、この存在への対処をぬきに「街頭演説5万回」と言っても、都合の悪いことは見ないと言うに等しい思考停止である。
細川は原発即時ゼロ、再稼働阻止と明言していたのであるから、どうして脱原発へ向けた一歩前進の芽を利用しようとしなかったのかである。おそらくは細川・小泉連合への猜疑心がそうさせたのであろう。旧来の左翼は大半がその旺盛な猜疑心のために自縄自縛に陥っており、とばっちりを受けるのは庶民である。分裂した一方の宇都宮がバラ色の政策メニューをいくら並べても当選できないのだから、絵に描いた餅にすぎず、そんな選挙戦を共産党は半世紀以上もやってきて、国政選挙では相変わらず10%の得票率さえ安定的に確保できないのである。この事実は、「街頭演説5万回」をやっても、誰でもが庶民の信頼を得られるわけではないことを示しているのである。 |
 (私論.私見) (私論.私見) |
| 「一点突破全面展開」は無謀な時もあれば有望な時もある。こたびの都知事選での原発政策からの急速転換ろを掲げての撤退は「一点突破全面展開」は有効であった。この時に、これに棹差す論調は不明としか云いようがないが、意図的故意にそう立論する者には通じまい。丸氏が「田中角栄が言い、小沢一郎が引き継いだ選挙の鉄則は、"戸別訪問3万軒、街頭演説5万回"」を引き合いにして反論しているのはお笑いでしかない。かなりズレており、何の意味もない持ち出しであり、これは意図的故意の立論としか考えようがない。 |
  都知事選における敗因は脱原発派の分裂にあり、その元凶は共産党のセクト主義にある(その3)(2013/3/29) 都知事選における敗因は脱原発派の分裂にあり、その元凶は共産党のセクト主義にある(その3)(2013/3/29)
(4ー1)、430万票都知事の突然の辞任
宇都宮の選対総括(「素案」)があまりにひどかったので、澤藤ブログ(「憲法日記」)に寄り道してしまったが、本論に戻って、まず、本稿(その1)の第四に指摘したところ、すなわち共産党のセクト主義の問題から検討する。本稿(その2)については、いつもの批判者から「ご都合主義的つまみ食い」なる論難が寄せられているが、どちらが「つまみ食い」をしているかは読者の判断にお任せしよう。まず、突如、選挙戦が行われることになった今回の都知事選当時の政治情勢を一瞥しておこう。猪瀬が徳州会から5000万円を借りた事件は検察によるリークが発端だとも言われているが、1年前に史上最多の430万票を獲得して当選し、2020年に東京オリンピックの招致に成功した都知事であるから、1年やそこらでの辞任はやはり、突然の印象が強い。猪瀬が東京電力に協力的でなく、また、招致したオリンピックの組織委員会を東京都主導でやろうとしたことが、「原子力ムラ」や自民党の反感を買い、政治的に追い落とされたとする見方もあるが、いずれにしても、体制側は430万票の都知事を追い落としても、微動だにしないような強力な政治体制を築いていたことが第一にあげられる。
|
 (私論.私見) (私論.私見) |
| 猪瀬の史上最多の430万票獲得をムサシマシーンによるものと見立てる視点がない。 |
|
(4-2)、都知事選当時の政治情勢=改憲勢力の大躍進
共産党勢は2013年の参議院選での復調に浮かれて、見るべきものも見えていないので、ここでおさらいをしておこう。2012年末の総選挙の結果は政権に復帰した旧勢力の歴史的な圧勝であった。自民党の圧勝(119から294議席へ)、与党連合の公明党の議席回復(21から31議席へ)、これだけで絶対多数を得ていたところに、与党の右に位置する石原・維新(11から54議席へ)、さらには前安倍政権で特命担当大臣を務めた渡辺・みんなの党(8から18議席へ)という具合である。与党・改憲勢力という線引きで見ると、480議席中397議席を占める状態である。これに野田政権で壊滅的惨敗を喫した民主党の改憲勢力を加えれば、優に4百数十議席、改憲勢力による衆議院独占状態という未曽有の政治情勢が生まれている。しかも、「アベノミクス」なる日銀による野放図な資金放出で、円安・株高が演出され、政権は平均的に60%代の支持率を維持してもいた。この基本的特徴=与党勢力の圧勝は2013年の参議院選でも同じである。
(4-3)、左派・中道左派の大幅後退
一方の野党勢力は政権を転落した民主党を除いて見ても、左派・中道左派の勢力は大きく後退した。日本未来の党(61から9議席へ)、共産党(9から8議席へ)、社民党(5から2議席へ)、新党大地(1から1議席)、合計すると76議席から20議席への惨敗である。共産党にあっては、9から8議席への後退であるから、それほどの敗北には見えないが、21世紀に入ってからの低迷の中でも維持してきた岩盤の9議席を1議席減らし、かつ得票数が368万票と基礎票の400万票台を割り込み、得票率も半世紀前の水準6.1%へと沈没する状況であった。このような改憲勢力の大躍進と護憲勢力の壊滅的後退、老舗護憲政党の社共にいたっては、合わせて衆議院10議席という歴史的な惨状の事態が出現したのである。
(4-4)、2013年参議院選でも大状況は同じ
共産党が復調を見せた2013年の参議院選でも、ここでのべたような国政の大政治状況はまったく変わっていない。2013年の参議院選での自民・公明・維新・みんなの議席増が改選議席数121議席中の43議席、合計議席数が115+20+9+18=162。定数242議席に占める比率は67%、これに民主党の参議院59人中の改憲派を合わせれば、参議院でも改憲派が優に2/3を突破する事態となっている。一方、民主党を除く左派・中道左派の野党はどうであったかというと、共産党が改選3から8への5議席増があるだけで、社民党が改選2から1への減少、生活の党が改選6から0への6議席減、みどりの風が改選4からゼロへ、全体では改選議席総数15が9議席へと減少している。 こうした全体の政治状況の中では、民主党の複数擁立による共倒れミスにも支えられた共産党の3から8議席への復調など、当事者達の喜怒哀楽を除けば、採るに足りない政治のエピソードに過ぎない。
|
 (私論.私見) (私論.私見) |
| 各種選挙戦結果をムサシマシーンによる操作と見立てない点が不満であるが、それを除けば良い評論であろう。 |
(4-5)、共産党の妄想癖・カルト化(その1)
ところが、共産党にあっては、不思議なことに、この政治の大状況が目に入らないのである。日本共産党が革命政党と自称しなければ、私もそれほど厳しい注文をつける気はないのだが、如何せん、革命政党と自称しているのだからやむを得ない。革命政党ならば、自党の選挙結果だけをみて、増えた減ったと喜んだり落胆したりしているヒマはないはずで、先憂後楽の思想がありそうなものである。政治の大状況を押さえた上で、自党の選挙結果を大状況の中に正しく位置づけて評価しなければならないはずである。弱小政党であれば、少しでも似た政策を掲げる他の野党との連携を模索し、庶民の要求をどれだけ実現できたか、連携の広がりにどう貢献したか等々を検証してみなければならない。
(4-6)、共産党の妄想癖・カルト化(その2)
しかし、共産党の場合はそうではない。今年の1月に、4年ぶりに第26回党大会が開かれたが、その大会決議冒頭の第1章は「『自共対決』時代の本格的な始まりと日本共産党」となっており、第1章の小見出しには「(3)日本共産党の不屈の奮闘がこの時代を切り開いた」と書かれている。我が目を疑うような文章である。共産党が言う「この時代」とは、通常ならば、誰が見ても、すでに見てきたような政治の大状況(改憲派の国会占拠状態)を指すはずなのであるが、「日本共産党の不屈の奮闘がこの時代を切り開いた」というのであるから、この大状況を共産党は歓迎していると解釈するほかない。護憲政党にしてはまったく倒錯した政治情勢認識である。志位指導部はその成立以降、15年にわたる後退のなかですっかり妄想癖が身に付きカルト化してしまったようである。
(4-7)、共産党の妄想癖・カルト化(その3)
この政治の大状況を共産党が歓迎する理屈をもう少し詳しく見てみよう。支配勢力は共産党つぶしのために、自・民などの2大政党制づくりや、中間政党を絶えず作り上げてきたのだが、「しかし、今回は、そうした『受け皿政党』が存在しない。『自共対決』という政党地図が、かつてない鮮やかさをもって、浮き彫りになっている」。この理屈では中間政党は共産党つぶしの鉄砲弾か、あるいは邪魔者扱いであって、それがいなくなって大歓迎だというわけなのである。自己都合このうえない極端に一面的な政治情勢の見方が出現している。しかも、さらに進んで次のように言う。「2013年7月の参議院選挙では、~~野党のなかで日本共産党がただ一つ躍進を果たした。日本共産党の躍進は、1961年に綱領路線を確立して以来、1960年代終わりから~の”第一の躍進”、90年代後半の”第2の躍進”に続く、”第3の躍進”の始まりという歴史的意義をもつものになった」。
「第3の躍進」と言うのであれば、もう2、3回大型選挙で大躍進してからにしてもらいたいものだが、いかにも気が早い。というより、どうみてもピンチな大状況の中で、他の野党が潰れれば共産党の大躍進の時代がやってくると考えているのであるから、これはもう、妄想以外のなにものでもない。自分と同じような政策を掲げた生活の党やみどりの風、社民党が負け戦を強いられているのに、どうして「第3の躍進」を想像できるのであろうか?
(4-8)、共産党の妄想癖・カルト化(その4)
共産党が躍進した70年代の前半、第2期美濃部都政が1971年に361万票で圧勝した時代は社会党が健在であり、民社党や公明党までが美濃部支持を打ち出すほど革新勢力に求心力があったものだが、今はその片鱗もない。共産党の裸単騎の「躍進」など先の参議院選同様に、ミニ躍進で政治情勢には何の変化を及ぼすこともない。ここに直近の明白な前例がある。中道左派の大幅な後退の中で、共産党だけが大躍進し、その躍進で政治の大状況を転換できると考えることは妄想以外のなにものでもない。何事にも中道好みの日本人の大方の気質を考慮すれば、妄想癖にしても度が過ぎる。このように、中道左派との連携や切磋琢磨で政治の大状況を変えていこうとするのではなく、逆に、これらの似たもの政党は中間政党で、それが潰れることは自党躍進の肥やし、というのでは、これはもう志位らが盛んに言う「一点共闘」とやらも怪しいもので、要するに、スターリン以来の共産党に伝統的な社民主要打撃論がむきだしになっているわけである。中間政党不在という一面的な政治情勢認識から、今の政治の大状況を歓迎し、躍進の時代がやってきたと小躍りする共産党の姿はもはや妄想に踊るカルトそのものというべき様相を見せ始めており、中道左派の後退を邪魔者の消滅と同一視し歓迎するのであるから、そのセクト主義も頂点に達しているとみるほかなかろう。このような政党が都知事選で宇都宮陣営の中核を形成していたのである。
|
 (私論.私見) (私論.私見) |
| 「共産党の妄想癖・カルト化」を批判するのは良いが、これがどこから生まれているのか、意図的故意のものと見なす見立てがないからカルト批判になってしまう。 |
都知事選における敗因は脱原発派の分裂にあり、その元凶は共産党のセクト主義にある(その4)(2013/4/5)
前回(その3)、今年1月の共産党の大会決議をとりあげた。そこには中間政党の衰滅を両手を挙げて歓迎し、「第3の躍進」、「自共対決」時代の本格的到来と奮い立つ姿があった。マルクス主義の一般理論からすれば、確かに中間政党の衰滅はひとつの法則的なものと把握されるところであるが、社会が単純に二大階級に収斂するわけではなく、現実には、社会の複雑化に伴い所得階層も複雑になり、それに対応して新たな社会層とその利害を反映した諸政党の誕生もまた法則的なのである。その両面的把握から統一戦線思想が生まれてくるのであるが、共産党の場合、前者があって後者が抜け落ちてしまっており、統一戦線思想の片鱗もない倒錯したセクト主義満開の政治情勢認識になってしまっている。このようになってしまった政党が、党大会の開催と同じ時期に、倒錯したセクト主義とは無関係に、国政選挙に準ずる大型選挙=都知事選に取り組めるはずがないのである。
(6)、宇都宮擁立へ一直線の共産党
90年の党史を誇る「老舗」政党なのであるから、都知事選に勝利するためには政権与党の基礎票200万票を上まわる選挙戦略が求められていたことくらいはわかっていたはずである。12月28日の宇都宮の立候補表明では「倍返しで200万票取って 都知事選に勝利しよう」と言っていたのであるから、与党側の基礎票200万票は十分意識されていたはずである。では与党の基礎票200万票を上まわる構想が模索されたのであろうか? その形跡はまるでない。猪瀬辞任表明の翌日である12月20日には前回都知事選の宇都宮の確認団体である「つくる会」の緊急運営委員会が開かれ、本稿(その2)で述べたような運営委員会の即解散、宇都宮と中山への一任、澤藤排除、河添の恫喝、「新」運営委員会(23日開催)という急展開が行われ、28日には宇都宮の立候補表明となるのであるから、誰が見ても、ジグザグの試行錯誤とは見えないのである。前回も、今回も、宇都宮の支持団体に名を連ねた有力政党は社民党と共産党だけである。社民党は一時は細川との一本化を模索したところであり、また今回は共産党が格段の注力ぶりであったところからすれば、ここに示した「つくる会」の急展開を裏で支え、猪瀬辞任直後から宇都宮の線で行く方向をゆるぎなく持っていたのは共産党だけであったと決めつけてもそれほど不合理ではあるまい。
(7)、勝利の展望なき宇都宮擁立
宇都宮にとっても弁護士連合会会長の選挙や前回の都知事選を経験しているのであるから、有力な支持団体の支援を事前に確保することなしには立候補表明のあるはずもない、と見るのが自然であろう。その有力な支持団体とは、時間をかけた大衆討議が必要な大衆組織ではありえず、執行部の判断で即決できる有力組織、すなわち、そういう政党、一時は候補一本化も検討した社民党や組織力のない新社会党やみどりの党ではありえず、つまりは共産党なのである。それだから、本稿(その1)で、宇都宮と共産党はどこかの時点で手を握ったと書き、12月28日の立候補表明の時点では、都知事選「共闘」が成立していたと見るのが合理的なのである。しかし、この「共闘」には200万票を獲得する展望があったのかと言えば、根拠なき願望以外はまるでなかったはずである。安倍自民の政権復帰、維新やみんなの党が幅を効かせる政治的右傾化の時代に、宇都宮のフライング立候補で、宇都宮に左翼候補イメージが付いてしまうリスクを犯してまで立候補したのではどうにもならない。
70年代の美濃部都政の時代にあっては、社会党のような大政党(72年総選挙1147万票)の支持があったのに比べれば、現在の社民党は142万票(2012年)にすぎないのだから、社共共闘も様変わりで、美濃部都政よ、もう一度、というような夢を見るわけにはいかない。そのうえ、1年前には統一候補・宇都宮で闘って、96万票、猪瀬の430万票の前に惨敗し、候補者の魅力に不足があることは実証済みである。共産党とて2012年総選挙では369万票(6.1%)、美濃部時代には550万票(1972年総選挙、得票率10.49%)と大躍進した頃と比べると見る影もない。「躍進」と喜ぶ昨年の参議院選でさえ、比例の得票が515万票となっているが、それでも得票率は10%には届かず、9.68%どまりである。
(8)、フライング立候補の真相(その1)
このように見てくると、宇都宮と共産党の「共闘」があったにしても、もう少し、うまい立ち回り方があってもよさそうなものである。何と言っても,宇都宮は前回の統一候補だったのだから、脱原発派の中では飛び抜けて有利な位置にあったはずで、他に適任の候補が見あたらなければ、自ずと候補者は宇都宮に落ち着くはずである。「待てば海路の日和あり」である。そうなれば、フライング立候補よりよほど広範な諸団体の支持が期待できたであろうし、前回支持の諸団体とも摩擦を起こさずに済んだかも知れない。宇都宮選対の選挙総括案(「素案」)でも、フライング立候補により、「無所属・リベラル派の区議・市議の方々」の支援が「大幅に減りました。」(「素案」7ページ)とある。ところが、「やせ馬の早駆け」とばかりに「いの一番」の立候補表明であるから、早駆けせざるを得ない事情が持ち上がっていたと考えるべきだろう。思い当たることはふたつある。ひとつは河添の恫喝に怒った弁護士・澤藤によるブログにおける公然たる告発(「憲法日記」)である。日が経てば、告発の内容は広がる可能性がある。もうひとつは、猪瀬の辞任ムードが濃厚になってきた12月下旬に、永田町に流れ始めた細川出馬といううわさである。
(9)、フライング立候補の真相(その2)
本稿(その2)で触れた宇都宮選対の選挙総括案(「素案」)には次のような記述がある。「私たちが元首相の細川護煕氏を擁立する動きがあることを知ったのは、1月7日の朝刊に~~記事が掲載された時点です。」(「素案」11ページ) しかし、1月7日ではいかにも遅い。素人なみである。20日に緊急の運営委員会を開き強行突破の途についた選対としては如何にも情報感度が鈍い。これはウソである。「日刊ゲンダイ」の1月4日付の記事で、すでに「仰天情報・細川元首相急浮上」というのがあるくらいである。 本命はこちらであろう。「素案」にはこういう記述もある。「瀬戸内寂聴氏は、12月26日に細川夫人から選挙についての挨拶があったことを新聞への寄稿で明らかにしています。」(同11ページ) 世俗を解脱した尼僧への挨拶が26日にあるくらいだから、永田町では、それ以前に、すでにかなりの情報が流れていたと見るべきで、この26日という日付も意味深長で、28日の緊急出馬ぎみのフライング立候補をリアルなものにする材料になる。
(10)、 フライング立候補の真相(その3)
おそらくは、宇都宮のフライング立候補の真相はこういうことであろう。都知事候補者・宇都宮ということで宇都宮と共産党との合意はあったものの、予想外に早く猪瀬辞任に発展したことや細川出馬のうわさもあり、「つくる会」の新体制づくりを急いだのだが、拙速さのあまり、恫喝まで飛び出し、予定外の告発も受け、年末には脱原発候補・細川出馬が濃厚になってきたことから、統一候補擁立の気運を待っていたのでは細川に脱原発候補をさらわれるとの恐れが生まれ、支持広がりのリスクを犯してでも、急遽、年内立候補へと突き進んだということである。細川で脱原発派候補の一本化ということになると、野心家に変身した宇都宮にとっても不本意であろうし、共産党にとっては存在感を示す選挙戦にできないことになり、セクト主義の頂点にある党指導部の現状ではとうてい受け入れがたかったのである。
(11)、野心家・宇都宮の発言
残るは宇都宮の野心家への変身についてである。野心家に変身することを一概に非難するわけにはいかないのは当然のことであるが、その野心故に庶民の政治的利害の実現が阻害されたということになると、話は別である。本稿(その2)で、宇都宮は12月20日の緊急運営委員会で、当日の運営委員会議長でありながら、河添による恫喝を制止もせず傍観したことをもって、私は都知事候補としては失格であると判断したのであるが、付け加えて、ここでは宇都宮の野心家ぶりを示しておくことにしよう。12月28日の立候補表明演説(講演)が、宇都宮の確認団体であろう「希望の町、東京をつくる会」のサイトに載っている。そこでの宇都宮の発言を見ると、こういうものがある。「市民の候補者というのは、市民運動の中からスターを生み出して育てていかなければなりません。どこかから取ってくる候補者ではダメなのです」。「どこかから取ってくる」という口ぶりに、細川のイメージがすでにちらついているようにも見えるのだが、それは棚に上げておこう。また、自分自身が元日弁連会長ということで、「取って」こられた都知事候補者であったことを忘れていることや、宇都宮が言及する美濃部都政でさえ、学者の美濃部が「取って」こられたし、黒田革新府政でさえ同様であったことも不問にしよう。この主張で宇都宮が言っていることは、前回はボロ負けしたが、おれ(宇都宮)を「スター」に「育て」ろということである。この発言には驚いた。他人が、ボロ負けした宇都宮を再登板させようとして推薦の弁としてやるならわかるが、しかし、ボロ負けした当人が言う言葉ではないだろう。宇都宮は、自分から「スター」になりたいのだと言っている。ここに立派な紳士であったはずの宇都宮の変身ぶりが赤裸々に露呈されているのである。彼は立候補の時点で、すでに十分な野心家に成長・変貌しているのである。
(12)、最後に、福島原発事故の認識が問題なのだ
これまで、ネット上での議論を様々見てきたが、一本化論を分ける分水嶺は福島の原発事故をどうとらえるかということに帰結する。その象徴が福祉も脱原発も重要だと並列的に政策を並べる共産党・宇都宮陣営、対する細川での一本化論者は脱原発政策の最重要性を強調する。少し考えればわかることだが、脱原発政策は福祉政策などとは同じ次元で論じることはできない。ひとたび、過酷な原発事故が起これば、「国破れて山河あり」どころではないからである。山河が残れば、福祉も医療も雇用も成り立ちうるのに対し、山河さえ残らない。山河も故郷も一族も家族も我が身も、すべてがこれまでの境涯から一変してしまうのである。このような惨害と比較しうるものは大戦、いやそれ以上のものでさえある。しかも、かかる惨禍は広範囲に及ぶ。日本政府はデータを誤魔化し、安全基準を改悪し、情報を隠蔽したり過小評価して事態の沈静化に努めているが、一説には、EUで出されたある研究報告では34000平方キロ(国土の27%)がチェルノヴイリ基準で言う「徹底的な放射能監視必要区域」にあたり、該当する地域には首都圏が丸々含まれているというほどである。福島県における青少年の甲状腺ガンの広がりは氷山の一角に過ぎない。地球上に占める面積からすれば1%にも満たない日本列島に地球上の大地震の20%が集中し、しかも、専門家の意見では、東日本大震災以降、日本は地震の活動期に入ったと言われ、アメリカ基準では活断層との関係で1基も原発を作れないはずのものが54基も存在するのである。現在は、稼働中の原発がゼロなのだから、再稼働阻止は最優先課題であり、そのためには、都知事選といえども、再稼働阻止で当選できる可能性を1%でも多くもっている候補者を探しだし、そこへ投票を集中させる選挙戦術が必要だったのである。 |
 (私論.私見) (私論.私見) |
結局、長文な割には急所を射る評論にはなっていないな。れんだいこの宮顕論、不破論、日共論を読んでいないから事態の深刻さの認識に欠けている。そういうことになる。
2014.4.7日 れんだいこ拝 |
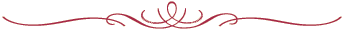
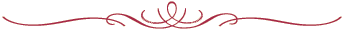
![]()
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)