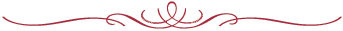
| お筆先執筆年代考 |
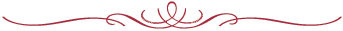
(最新見直し2015.10.25日)
| 【お筆先の御執筆】 |
|
1869(明治2)年正月、「お道」立教の年より数えて32年目のこの頃、教祖は、お筆先をお書き始めになられた。この頃、世の中は幕末の時代から明治の世へと代替わりの最中であり、こうした時節に教祖は「筆、筆、筆をとれ」との急き込み為され、何かに執り憑かれるように筆を執った。筆が走れば時間にも制限がなく、夜となく昼となく暗闇の中でも自動的に動き、しかもその執筆に乱れがなかった、と伝えられている。 |
| 【「理」考】 |
|
「理」の考察をしておく。漢和辞典には次のように記されている。1・おさめる。治、修。イ.みがく、ロ.ただす、ハ.さばく、ニ.はからう、ホ.つくろう、ヘ.区別する、ト.かざる。2・おさまる。3・きめ。イ.玉の筋、ロ.木の木目、ハ.肌のきめ。4・すじ。5・みち。6・ことわり。7・わけ。8・宇宙の本体。9・天性。 |
| 【「お筆先」の御執筆年代について】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
お筆先の執筆年代は、「おつとめ」が整備されて行った年代と一致する。ご執筆の年次とお歌数は次の通りである。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
これをみれば、お書き下されている「お歌」の数は、毎年毎年数の上で平均しているのではなく、驚くばかり不揃いである。明治2年は2号誌されたものの、明治9、10、12、13、14、15年の各年は各1号ずつである。明治3、4、5、6、11年の5年間はご執筆なく、これらの年は教祖のみちすがらの上から見ても特筆すべき事実はなかった。明治7、8年の2カ年に精力的にご執筆されており、お筆先全号の半分以上がお書きになられている。 お筆先の過半数をお書き下された明治7、8年の両年は、「おつとめ」の整備という上から見れば、「かぐら面」が出来たり、「ぢば」を定めて「つとめの場所」を明らかにされたり、「かんろだい」の据え付けを目標にされる等、「おつとめ」を整えていかれる上での眼目とでも申すべき、親神の思召しを次から次へと明かされていった年である。 これに応じて、「おつとめ」のよってきたる、この世の元を明らかにしなければならぬし、お話は勢い根本教理に触れて、口でも説けば、筆にも誌すという具合に、「お筆先」のご執筆量も増えていくこととなっている。してみれば、お筆先は、「つとめの理」を教えることを主軸にして、親神様の思し召しを説くという体裁で「お道」と道人の歩むべき方向を指し示されたものと拝察し得るであろう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
他に「号外」句が3首存在する。それは以下の3首である。仮にこの3首を号内の1711首に足すと合計1714首ということになる。
|
| 【「お筆先」の外冊(げさつ)について】 |
| お筆先1711種を仮に「正冊」とすれば、「外冊」(げさつ)と云われるものがある。現在確認されているのは、全17号のうち、第2号、第6号、第10号、第11号、第16号の5冊を除く、第1号、第3号、第4号、第5号、第7号、第8号、第9号、第12号、第13号、第14号、第17号である。 |
|
|
|||||||||||||||
|
「お筆先」は、「み神楽歌」第4節「よろづよ八首」を冒頭に書き誌すことから始められていることに象徴されるように、「み神楽歌」教義を踏まえて、親神様の思し召しを更に詳しく誌すという構図で、道人に「お仕込み」を為すという立場からご執筆されているように拝察させていただくことができる。
とあるように、お筆先の眼目は、しっかりと「理」を思案することのできるようにとの親心で親神の思し召しを「筆」により説きあかすことにより、道人に「お仕込み」を為すことにあった。併せて道人の成人を促されたものと拝察させて頂くことができる。これをお遣しくだされたればこそ、我々は今日でも、じかに教祖の教えに触れることができるという有り難いこととなった。
|
| 「おふでさき三号解釈 その一 (1〜4)」その他を参照する。 | |
| お筆先3号が書かれた時期は表紙に「明治七年戌年一月ヨリ」とあることで判明する。これは、前年の明治6年に改暦された陽暦で、陰暦では明治6年11月13日である。お筆先3号には、明治7年6月18日(陰暦5月5日)、教祖が前川家へ神楽面を取りに行った時、お筆先4号と共に差し出されたものがある。これは外冊と呼ばれて1から47までのお歌が記されている。その何ヶ所かに日付が書かれている。この日付は陰暦で教祖ご自身が書かれたものである。5番のお歌の右上に、「十月三日」とあるのが最初で、42番のお歌のところに「十八日」とあるのが最後である。「十月三日」は、明治6年で陽暦では11月22日になる。これにより、お筆先3号の表紙には陽暦「1月」とあるが実際に書き始められたのは前年の陽暦11月からであることが判明する。ちなみに、どのお歌がいつごろ書かれたかに関しては、「3−109、このものを 四ねんいせんに むかいとり 神がだきしめ これがしよこや」と、3年3月15日死亡のお秀さんが4年前に亡くなったと記していることから、109番のお歌は、陰暦の明治6年中に書かれたことが分る。ちなみにお筆先の年数の数え方は「数え」(かぞえ)である。陰暦7年正月元旦は陽暦7年2月17日で、3号は149番まであり、また4号の表紙には「4月」とあるから、3号は陽暦6年11月22日以前に始まり、陽暦7年2月までに3分の2ほどが書かれ、4月頃には書き終えていたことになる。 明治6年11月4日に、お屋敷(庄屋敷村戸長仲山秀治宅)で、石上神社の教導職によって「三条の教則」の内容を国民に徹底させるための説教が150名の聴衆を集めおこなわれたという記録「明治七年七月/巡回説教聴衆扣/石上神社」(天理図書館収蔵史料)なる史料が公表されたことで、お筆先の解釈に大きな影響を及ぼした。天理大学の池田士郎氏が、「教祖とその時代」のP178「原典成立とその時代」で、それをもとに3号1−4、3号148−149の新たな解釈を行なっている。それによれば、当時のお屋敷内で150名もの人が入れる場所とは「つとめ場所」をおいて他にないと判じている。「つとめ場所」には、既にお筆先1、2号が書かれた明治2年当時も、吉田神祇管領からもらった祭具を祀り、中臣の祓いなどが行われていた。明治6年の11月、教祖は、お筆先3号の最後のお歌「3−148.高山の せきゝよきいて しんしつの 神のはなしを きいてしやんせ」、「3−149.にち/\に 神のはなしを たん/\と きいてたのしめ こふきなるぞや」と記されている。これは、教祖の「高山の説教会議」批判と受け取るべきだろう。教祖は、「高山の説教」に対して、「教祖の語る神の話」こそが「こふき」(古記、口記、鴻基)であるとしてアンチテーゼしている、ことになる。 お筆先3号1−4も検証されるに足りる。「3−1.このたびハ もんのうちより たちものを はやくいそいで とりはらいせよ」、「3−2.すきやかに そふぢしたてた 事ならば なハむねいそぎ たのみいるそや」、「3−3.しんぢつに そふぢをしたる そのゝちハ 神一ぢよで 心いさむる」、「3−4.だん/\と せかいの心 いさむなら これがにほんの をさまりとなる」。ここの下りの「たちもの」、「そふぢ」をどう解釈するのかに諸見解がある。池田士郎氏の新見解は次の通りである。教祖が、3号1のお歌で語りたかったことは、「たちもの」は具体的な建物ではなく、「神道的国民教化の教説」、「高山のせきゝよ」である。3号2、3に出てくる「そふぢ」が、「1号29.このたびハ やしきのそふじ すきやかに したゝてみせる これをみてくれ」、「1−30.そふじさい すきやかしたる 事ならハ しりてはなして はなしするなり」、「1−31.これまでの ざんねんなるハ なにの事 あしのちんばが 一のさんねん」と通じている。してみれば、ここで云う「そふぢ」の対象は「あしのちんば」即ち秀司にあったと理解できる云々。 これまでの解釈は次の通りである。お筆先出版史及びその都度の解釈を確認しておく。 大正5年、大平隆平氏が簡単な註を付けた「評註御筆先」が出版された。これが嚆矢となる。この本は、お筆先本文は原本と同じかな書きで、ほぼ現在の本部版と同内容である。ただ番号は付されていない。そして、若干の註がお歌の横に書かれている。 大正10年、天理教同志会編の「御筆先訳文」が出されている。何刷りかされている。これは、お筆先本文が漢字交じり文になっており、「評註御筆先」と同じように、ところどころに註が付いている。本文、註とも総ルビである。 1928(昭和3)年、のお筆先刊行時に「お筆先註釈」が付せられ、それが現在でもお筆先解釈の基本とされている。「註釈」が作られる経緯について、「改訂天理教事典」(1997年、道友社)は次のように記している。
「改訂天理教事典」が云うところの「信者の中に誤った原典解釈が流布する危険が出て来た」というのは、「評註御筆先」、「御筆先訳文」の2冊のことを指しているのだろうか。それで、本部の解釈が必要になったというのも一因で史料集成部が作られ、昭和3年に本部から註付の公刊本が出される。戦前につけられた註は、「当時の国情に基づく非本来的な見解も散見される」として戦後修正が行われている。主に「にほん」、「から」といった部分の解釈である。3号1−4の註では、4の註として、「親神の真意が人々の心に行きわたって」という文が、追加されている。 |
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)