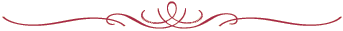
| 日本寓話「十五夜お月さんの論理」について |
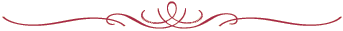
更新日/2021(平成31→5.1栄和改元/栄和3)年.1.15日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここで、「十五夜お月さんの論理」について記す。 2007.10.12日 れんだいこ拝 |
![]()
| その一 |
| 面白いことに気づいたので書きつけてみようと思う。「十五夜お月さんの餅つき話」を子供の頃に聞かされ、満月のお月さんを見ながら、何とかして餅つきの図に読み取ろうとした記憶がある。見ようによればウサギが餅つきしているようにも見えた。少し違うなとも思いながらも。そのことの詮議をするのが本稿のテーマではない。1969年7.21日、米国製有人宇宙船アポロが初めて月面着陸に成功した。恐らく、テレビのあるところ地球上の隅々で人が釘付けになったと思われる。れんだいこもその一人であった。今日、「アポロの人類初の月面着陸映像はウソだった」論議も生まれているようだが、そのことの詮議をするのが本稿のテーマではない。れんだいこが思案しようとしているのは、あのアポロの快挙によって、それより後の人々に「十五夜お月さんの餅つき話し」の伝承が萎えてしまったことについてである。その功罪を問いたいというのが本稿の狙いである。こんなことを考える人は珍しいのかも知れないが、れんだいこは至ってマジに愚考している。この問いの奥は深いと考えている。 今日、「十五夜お月さんの餅つき話」を真剣に語る者がいたとしたら、我々はお笑いで遇するだろう。しかし、当人がそれでも真剣に語り続けたとしたらどうなるのだろう。それも、「アポロの人類初の月面着陸映像はウソだった」という観点からでなく、それを史実として快挙と思い且つそれでも「十五夜お月さんの餅つき話し」を語り続ける人がいたとしたら、我々はどう遇するべきか。要するに、今日の時点で、「十五夜お月さんの餅つき話し」を語ることが罪なのか益なのか、という問になる。これについて、皆さんはどう思われるだろうか。れんだいこはこれを愚考しようとしている。そして、廻らした思案は次のようなものになった。 「十五夜お月さんの餅つき話し」は今なお生命力を有している。というか、引き続き語り続けなければならない。それは何故か。一つは、想像力を掻き立てる為である。この想像力がなくば人生が面白くないと気づく故にである。この想像力は、よしんば科学の知見と齟齬しても、独立して成り立つべき脳内占有権を持ってしかるべしと思う。むしろ、科学が脳内から想像力の座を狭めるのなら、それは科学の行き過ぎと思う。というか、科学自体には罪はないのかも知れないので、科学的知見を受け止める我々の弁えについて、どこか至らないところがあるのではないかと思う。 むしろ、最近の科学万能社会は、これをどの範囲で受け入れるのか明らかにするよう、我々に迫っているのではないのか。このことを顧慮せず、我々が科学万能社会に追随することはむしろ危険なのではないのか。考えてもみよう。科学は常に発展途上である。現在から過去を見れば、過去の時代とは何と科学的知識の不足していた時代であったことよと思うであろう。今現在も後世からすれば過去であり、その後世という未来から見れば、今現在は何と科学的知識の不足していた時代であったことよと思うであろう。科学とはそういうものであろう。時代とはそういうものであろう。 だから、科学万能社会論は何一つ物事を解決しない。その時代の知見というものがひけらかされているに過ぎない。そう認識すべきではなかろうか。もっとも、この知見が過去の誤謬を訂正するのだから有益さは論をまたない。但し、それを常に限定的に語るべきで、科学という名を被せれば、それで万事解決済みという如意棒にはならないという弁えを持つべきだろう。科学という名を被せて優越に浸るなどは、云い得云い勝ちの子供騙しの論であるに過ぎない。単に言葉に酔っているだけの、言葉に弱い系の人種間に通用する独善議論作法でしかあるまい。具体的に誰のことを指して云っているのか、本稿の品を落とすので差し控えておくことにする。 さて、科学主義論のことはこれぐらいにして、「十五夜お月さんの餅つき話し」に戻そう。「十五夜お月さんの餅つき話し」には、極めつきの善さがある。このことが知られねばならない。どういう意味かというと、幼児、子供向けの童話ないし御伽噺(おとぎ)話しと比較してみれば分かるが、中にはかなりキワモノのものも多い。正直の善さを説くのに懲らしめが代償にされていたり、希望を持つよう説くのに、それが安易に時の権力者に見初められるだけの話しであったり、親孝行説くのに金銀財宝を暴力的に取ってくるだけの話しであったりする構図のものが多い。 それを思えば、「十五夜お月さんの餅つき話し」には害がない。むしろ、月面を眺めて、ウサギが石臼と杵と相和して突き合う姿の想像を掻き立てるうちには、何ともいえない妙味さえあるというべきだ。れんだいこは、人生に於いてこの妙味の部分をもっと大事にしたいと考えている。月面に実際にウサギがいなくても構わない。居たとしたらという仮定で思いを練り、そこにメルヘンがあり、そのことに害がなければ、十分に検討されるに値する話しだとする姿勢を持ちたい。以上が、れんだいこ式「十五夜お月さんの餅つき話し」の前段になる。さて、これからが値打ちものになる。乞うご期待。 2003.8.26日 れんだいこ拝 |
| その二 |
| 「十五夜お月さんの餅つき話しには害がない」という良さがあることを既に指摘した。ところで、「十五夜お月さんの餅つき話し」は絵だけのような短文であるが、これにもう幾分か肉付けストーリー化され、そこそこの長文になった場合はどうなるのだろう。それが結構面白い話しになっていたとしたら。ついでに面白いだけでなく為になる話しが満載されていたらどうだろう。懲らしめでもなく、権力者への迎合でもなく、安逸な立身出世物語でもなく、我々の人生とか世の中の仕組みとか今後の歴史の流れとかについて啓発的な寓意になっていたとしたらどうなるか。 科学的社会主義屋は、これを荒唐無稽として罵詈雑言するのだろうか。アポロの話しを持ち出して否定に躍起になるのだろうか。仮にそうなるとしたら、その姿勢を批判したいというのが、れんだいこが本稿を書きつけてみたいと思うようになった動機である。もし、マルクス主義者にして、アポロ話しを持ち出してナンセンス呼ばわりする者がいたなら、その人はマルクス主義の何たるかを根本的に理解し損なっていると思う。 なぜなら、あり得べきマルクス主義の根幹には、世界の社会主義的改造へ向けての「十五夜お月さんの餅つき話し」的童話性があるからである。そういう感性まで含めて理論化しているのがマルクス主義であり、童話性を排除した科学的社会主義屋の如きな教説は何らマルクス主義のものではない。干乾びた現実を客観的に筆で晒したからといって、それだけでは所詮二束三文的な値打ちにしかならない。この理屈が分からない分かろうとしないマルクス主義屋が多い。 考えても見よう。マルクス主義的未来社会論は、「十五夜お月さんの餅つき話し」にある童話性と相似していないだろうか。典型的には、「各人の自由な発展が万人の自由な発展のための条件となるような、一つの協働体としての社会主義社会」、「各人はその能力に応じて、各人はその必要に応じて受け取る共産主義社会」なる概念であるが、これは人類が深く願望するユートピアそのものではなかろうか。 マルクス主義に宿るこのメルヘン気分を理解せず、マルクス主義以外のユートピア教説のあれこれを批判して得意がっているマルクス主義者が多い。そういう御仁は、己の能力の甲羅に合わせて潜り込んでいる亀が、己の甲羅を自賛しているに過ぎない。肝心なことは、その御仁の甲羅の特性である。まだしもそれが開放系のものになっておれば良いのだが、排他的独善的なものになってゲバ棒を振り回し始めたら始末が悪い。れんだいこは、このような甲羅主義者も科学的社会主義屋もお仕置き屋も好まない。 なぜなら、そこには現実から何を期待しようとするのか、変革するのかについて夢がない単なる批判に堕しているからである。人は一般に、金銭欲、異性欲、見栄、名誉、権力を求める。この五欲はそのどれ一つとっても生涯を通じて叶えるのに困難なものであるが、だからといってこの五欲に没頭すれば良いのかというと、やはり味気なさが残る。能うるならば五欲を超えたいと思う。むしろこの五欲はちょぼちょぼで良いのだ。但し、このちょぼちょぼさえ困難な社会情勢に於いては第一に闘う精神、気概を養うべきだ。その際には、自己奮闘と社会変革とを不即不離に捉えて合一せねばならない。陽明学という学問があるが、その精髄はそのようなことを述べている点で卓見である。我々は、その過程で同類を寄せ集め、苦しみを分かち合いつつ助け合うべきだ。 しかし、それは第一歩であり、そこから先「十五夜お月さんの餅つき話し」に向かわねばならない。五欲は自己目的すべきものではなく、その先に人はかくあるべし論を持たねばならない。その話しが未熟だったり荒唐無稽過ぎるならば、何度も書き直して然るべきものに書き換えればよい。いずれにせよ、「十五夜お月さんの餅つき話し」が不要ということにはならない。人はこれを大義とも云う。この大義がなければ味気ないのが人間の性(さが)ではなかろうか。大義とは「錦の御旗」と云われるものである。「錦の御旗」の内実は局面局面でころころ変わるものであるが、この伝播性はかなり強く、それだけに疎かにすべきものではない。否、もっと磨くべき種のものではなかろうか。 考えてみれば、今の世の中は賢こぶるものが多すぎて「十五夜お月さんの餅つき話し」が萎え過ぎている。しかし、それはおかしなことなのだ。歴史は、誰かのシナリオの「十五夜お月さんの餅つき話し」が育まれ、時にそのシナリオ同士が相争いつつ、相互に味付けが為されつつ変遷してきていると思えるから。もし、今現在の「十五夜お月さんの餅つき話し」が不満だとすれば、我々用の「十五夜お月さんの餅つき話し」を対置して行けば良い。そうする必要があるのではなかろうか。それがいつか現実になる。これに経済的な裏づけとそれに基づく相互の人間関係の在り方を踏まえればより有効なものになるだろう。「十五夜お月さんの餅つき話し」に耳を傾ける精神がなければ、この営為そのものが生まれてこない。故に、「十五夜お月さんの餅つき話し」を銘々が創造せねばならない、読み合わせしてどんどん書き込んで書き直していかなければならない、これが「十五夜お月さんの餅つき話し」にまつわるれんだいこ見解である。 ところが、驚いたことに、この営為が不要という科学的社会主義屋の指導者がいる。青写真を作ると手足が縛られるだと。何というあきれ果てるべき御仁だろう。故に、この御仁の云うこと為すこと全体が干乾びている。膨大な文章を得意がって書きつける癖があるが、読んでも何がいいたいのかさえ分からない。あちこちが玉虫色でさっぱり要領が得ない。この手合いの口車に乗せられると、我々は次第に痴呆症患者の症状を呈することになろう。結局、思想性のない、何も思わず単に唯々諾々するだけのペット人間あるいは病床人間にされてしまう。この虚構を突破せよ。これがれんだいこが「十五夜お月さんの餅つき話し」を語らざるを得ないゆえんである。 2004.2.6日 れんだいこ拝 |
| その三 |
| れんだいこは、何故「十五夜お月さんの餅つき話し」に拘るのか。実は、とても素敵な「十五夜お月さんの餅つき話し」調の諭し話しを知っているからである。マルクス主義ユートピア論よりも気に入っている。ズバリ云おう。それは天理教開祖の中山みきが説いて聞かせた人類創世記譚「元の理」である。「元の理」は「泥海古記(口記)」とも云われる(以下、「元の理」と記す)。それを一言で要約すれば、人類史を俯瞰した上での人の生きる道の指針教説である。れんだいこは、何の因縁か27歳頃この話しを聞き魅せられた。以来、今もって虜(とりこ)になっている。 れんだいこの見るところ、「元の理」は、天理教のみならず日本のみならず人類全体に及ぶ貴重な財産である。その説話の創世記物語はキリスト-ユダヤ教圏内の旧約聖書数行の記述よりも長い。完成度も高い。そして、人たる者として人類誕生の元一日の謂われ(因縁)を知り、創造主神の御心に叶う生き方をすべきことを示唆している。その圧巻は、人の生きる目的を諭して、親神が「泥海だけの世は味気ない。一つ人間と云うものを拵えて、その人間が陽気に明るく勇んで助け合って生きる様を見て共に楽しみたい」との思いで創造した以上、創造された側の人間の生きる目的は、この親神の思いに適うことである。しかしてそれが陽気暮らし、陽気勤めの助け合い生活であるとしている。これを延々と説き分ける「元の理」教説の例え話しが無茶苦茶に面白い。 「元の理」の科学的根拠は分からない。検証しようもない。但し、荒唐無稽かというとそうでもない。親神による人類創造でありながら、進化論的にも齟齬しない知見が披歴されている。その逐条が現在の科学的知見においてさえ裏付けられるような内容になっており、今後に於いてもますます違背しないのではないかと思われるほどの卓見的示唆で散りばめられている。教祖中山みきが、この口述を何に依拠して宣べたのかは分からない。教義的には、神が入り込み宣べた思惑を高弟が筆写したものであるから、間違いのあろう筈がないという訳になるのだが、れんだいこはそこまでは同調しない。しかしながら、「元の理」の秀逸さを誰にも引けをとらないほど畏敬している。 れんだいこは何故「元の理」に拘るのか。それは、21世紀の人類が陥っている悲劇に対して、みきの諭した「元の理」こそ救済になっているのではないかと思うからである。それは、この世にもしサタニズム論理とそれを信奉する勢力が邪悪な意思で地球及び人類改造を企図しているとするなら、「元の理」」こそそれを覆す論理と知力と運動のつまりは理論的且つ実践的な生命力を持っているのではなかろうかと思うからである。これが、初期の天理教教団が弾圧された真の理由ではなかろうかと思っている。 そのような内容を持つ「元の理」について詳しく知りたければ「教義原型『元の理』」で考察しているので、興味のある方は読まれてみるが良い。今日のものは無論、将来の科学でも跡づけられない、しかし何れの日にか凄いと判明させられる超科学的教説であるように思っている。江戸幕末に突如登場した一介の主婦中山みきは、知る人ぞ知る知らぬ人は知らない天理教教祖であるが、彼女の叡智が世界的に賛辞される日が必ずやって来るだろう。 さて、ここで「十五夜お月さんの論理考」に戻る。れんだいこは、「元の理」話しが真実であろうがなかろうが、全く害のない有益至極な理念話しであり、然しながらその思想は深い。科学的社会主義屋の精神からは何の意味もない「元の理」譚ではあるが、「十五夜お月さんのおとぎ話し」を大人版にしたものと拝することができ、その効能は絶大と評価絶賛している。とりわけて、地球文明的気を迎えている21世紀に於いては、その混迷を打破する有り難い指針書足りえているのではないかと思っている。パレスチナの悲惨と中近東の騒乱悲劇を思うたびに、双方が「元の理」の精神で親和する以外に解決しないのではなかろうかと案じている。その他その他然りである。 ここまで述べれば、「十五夜お月さんの論理考」はほぼ完結である。後は、気ままに肉付けしていくことにする。 2005.3.8日 れんだいこ拝 |
| その四 |
| ネット検索で、「『宇沢弘文と語る』を聴講して」に出くわした。れんだいこが意訳すると、次のような話しを伝えている。 2010年現在、いつノーベル賞を取ってもオカシクナイとされている万年候補の宇沢博文・政治経済学者が旧制中学の4年生の頃、いろいろの事情があって新潟の禅寺(曹洞宗)に身を寄せることになった。禅寺の住職は、宇沢に「嘘をつきなさい。人びとを幸せにする嘘を沢山つきなさい」と教えたと云う。住職は、晩飯になると宇沢少年を呼んで一緒に食事をしようと誘った。未成年なのを承知で酒も用意されていた。宇沢少年相手にいろいろの話しをしてくれ、そのなかの話しの一つが「嘘をつきなさい」だった。 宇沢教授は、「今から考えるとわたしの経済学の考え方の根源になっているような気がする」と述べている。この教話の力点は前段の「嘘をつきなさい」にあるのではない。後段の「人びとを幸せにする」というところにある。「嘘」と云う言葉も教説上の方便で、学問も含めた全ての知が「嘘」の範疇に入ると云う認識を元にしている。「学問といい、科学的知見といい、宗教の教義といい、それらはどこまでいってもひとつの仮説にすぎない。つまりは『嘘』の一種なのだから、どうせ『嘘』をつくなら『人びとを幸せにする嘘』をつきなさい」という禅宗特有の寓意である。 宇沢青年をして数学から経済学に向かわしめ、経済学をして、人を計数的物量として扱う近代経済学に対して、生身の人間の生活的与件を絶対的基礎とする「社会的共通資本」なる概念を生ましめ、やがて公共経済学を発想せしめることになるが、その背後に去る日の住職の「嘘をつきなさい。人びとを幸せにする嘘を沢山つきなさい」の教話があったと云う。これを知り、れんだいこ流に解釈すれば、宇沢弘文政治経済学教授は、「十五夜お月さんの餅つき話」を解する立派な知識人だと云うことになる。 2010.11.4日 れんだいこ拝 |
| その五 |
| 「十五夜お月さんの餅つき話し」執筆動機の背後に天理教教祖の口述人類創世記譚「元の理」があったことを種明かししたが、ついでに天理教教祖に纏わる「存命の理」についても記しておく。「存命の理」とは、天理教教祖中山みき逝去後も生身の身体としては死亡したが生命は生前同様に存命しており、今も人類救済の為に働き続けているとする教説である。こういう教祖存命説は何も天理教でのみ云われるのではなく、他の宗派でも同様の説を持つところもあるように思われる。 さて、この「存命の理」をどう寓すべきか。既にここまで「れんだいこの十五夜お月さんの餅つき話し」をお読みいただけた者には得心できよう。「存命の理」を科学的知見で批判するのはいとも簡単である。その種の口角泡を飛ばし士に尋ねるが、或る宗派が教祖を死後も「存命の理」として待遇し、教祖を敬慕したとして何か害があるだろうか。天理教では、「存命の理」のままに教祖の着替えを日々行い、拝殿の奥に鎮座されているとして日々諸事の伺いを立て報告申し上げている。口角泡を飛ばし士がこれを茶番と云うのは勝手である。しかし、れんだいこは、素晴しい没後対応であるとして逆に評価している。 教祖中山みきは生前、人間の寿命は115歳までの定命(じょうみょう)を与えられているとして教説していた。これを説いていた頃は80歳代後半の頃である。そのみきは80歳の頃より十数次にわたって検挙され、その取り調べも次第に暴力的になった。「最後の御苦労」が1886(明治19)年2月、89歳の身で厳寒の獄舎に入れられた。一説によると、この時の老婆虐待は凄まじく、にも拘わらず教祖は差し止めさせられていた教義を説くのにひるまなかった。15日間後に釈放されたが、もはや立つこと叶わぬ息絶え絶えの身になっていた。その後は床に臥す日々となり、「最後の御苦労」の一年後に逝去している。亨年90歳。教内では、「115歳定命説」に違う教祖の逝去に対する動揺が走った。 この時、霊能を分与されていた後の本席・飯降伊蔵が指図したのが、「さあさあわからん。わからん、なにもわからん。115才、90才、これもわからん。25年不足であろう。どうであろう。これもわからん。どうしてもこうしてもすっきり分からん。故に25年を縮め、助けを急ぎ、扉を開いて世界をろくぢに踏み均(な)らしに出た。神でのうてこの自由自在は出けようまい。止めるに止められまい。神は一寸(ちょっと)も違うた事は云わん。よう聞き分けてくれ。これから先というは、何を聞いても、どのよの事を見ても、皆な楽しみばかり。楽しみや。よう聞き分け。追々刻限話しをする」、「さあさあこれまで住んで居る。何処へも行てはせんで、何処へも行てはせんで。日々の道を見て思案してくれねばならん。(中略) 姿は見えんだけやで、同んなじ事やで、姿がないばかりやで」なる啓示であった。かく「存命の理」が打ち出され、教内の動揺は治まった。これが「存命の理」の歴史的事情である。これに照らす時、飯降伊蔵の啓示はむしろ何とも鮮やかと云うべきではなかろうか。 「十五夜お月さんの餅つき話し」から始まりマルクス主義のユートピア思想、天理教の「元の理」、「存命の理」へと辿り着いたが、この思索の旅が面白かったのは一人れんだいこだけだろうか。本稿はこれでひとまず完結とする。 2012.09.19日 れんだいこ拝 |
| れんだいこのカンテラ時評№1062 投稿者:れんだいこ 投稿日:2012年 9月21日 |
| 「十五夜お月さんの論理」についてその1 面白いことに気づいたので書きつけてみようと思う。「十五夜お月さんの餅つき話」を子供の頃に聞かされ、満月のお月さんを見ながら何とかして餅つきの図に読み取ろうとした記憶がある。見ようによればウサギが餅つきしているようにも見えた。少し違うなとも思いながらも。 そのことの詮議をするのが本稿のテーマではない。1969.7.21日、米国製有人宇宙船アポロが初めて月面着陸に成功した。恐らく、地球上の隅々でテレビのあるところ人は釘付けになったと思われる。れんだいこもその一人であった。今日、「アポロの人類初の月面着陸映像はウソだった」論議も生まれているようだが、そのことの詮議をするのが本稿のテーマではない。 れんだいこが思案して見ようと思うことは、あのアポロの快挙によって、それより後の人々に「十五夜お月さんの餅つき話」の伝承が萎えてしまったことを廻ってである。その功罪を問いたいというのが本稿の狙いである。こんなことを考える人は珍しいのかも知れないが、れんだいこは至ってマジに愚考している。この問いの奥は深いと考えている。 今日、「十五夜お月さんの餅つき話」を真剣に語る者が居たとしたら、我々はお笑いで遇するだろう。しかし、当人がそれでも真剣に語り続けたとしたらどうなるのだろう。それも、「アポロの人類初の月面着陸映像はウソだった」という観点からでなく、それを史実として快挙と思い且つそれでも「十五夜お月さんの餅つき話」を語り続ける人が居たとしたら、我々はどう遇するべきか。要するに、今日の時点で、「十五夜お月さんの餅つき話」を語ることが罪なのか益なのか、という問になる。これについて、皆さんはどう思われるだろうか。れんだいこはこれを愚考しようとしている。そして、廻らした思案は次のようなものになった。 「十五夜お月さんの餅つき話」は、今なお生命力を有している。というか、引き続き語り続けなければならない。それは何故か。一つは、想像力を掻き立てる為である。この想像力がなくば人生が面白くないと気づく故にである。この想像力は、よしんば科学の知見と齟齬しても、独立して成り立つべき脳内占有権を持ってしかるべしと思う故にである。むしろ、科学が脳内から想像力の座を狭めるのなら、それは科学の行き過ぎと思う故にである。というか、科学自体には罪はないのかも知れないので、科学的知見を受け止める我々の弁えについて、どこか至らないところがあるのではないかと思う故にである。 むしろ、最近の科学万能社会は、これをどの範囲で受け入れるのか明らかにするよう、我々に迫っているのではないのか。このことを顧慮せず、我々が科学万能社会に追随することはむしろ危険なのではないのか。考えてもみよう。科学は常に発展途上である。現在から過去を見れば、過去の時代とは何と科学的知識の不足していた時代であったことよと思うであろう。今現在も後世からすれば過去であり、その後世という未来から見れば、今現在は何と科学的知識の不足していた時代であったことよと思うであろう。科学とはそういうものであろう。時代とはそういうものであろう。 だから、科学万能社会論は何一つ物事を解決しない。その時代の知見というものがひけらかされているに過ぎない。そう認識すべきではなかろうか。もっとも、この知見が過去の誤謬を訂正するとすれば、その際の有益さは論をまたない。但し、それを常に限定的に語るべきで、科学という名を被せれば、それで万事解決済みという如意棒にはならないという弁えを持つべきだ、ということが云いたい訳である。 科学という名を被せて優越に浸るなどは云い得云い勝ちの子供騙しの論であるに過ぎない。単に言葉に酔っているだけの、言葉に弱い系の人種間に通用する独善議論作法でしかあるまい。具体的に誰のことを指して云っているのか、本稿の品を落とすので差し控えておくことにする。 さて、科学主義論のことはこれぐらいにして、「十五夜お月さんの餅つき話」に戻そう。「十五夜お月さんの餅つき話」には極め付きの善さがある。このことが知られねばならない。どういう意味かというと、幼児、子供向けの童話ないしおとぎ話と比較してみれば分かるが、中にはかなりキワモノのものも多い。正直の善さを説くのに懲らしめが代償されていたり、希望を持つよう説くのに、それが安易に時の権力者に見初められるだけの話であったり、親孝行説くのに金銀財宝を暴力的に取ってくるだけの話であったりする構図のものが多い。 それを思えば、「十五夜お月さんの餅つき話」には害がない。むしろ、月面を眺めて、ウサギが石臼と杵と相和して突き合う姿の想像を掻き立てるうちには、何ともいえない妙味さえあるというべきだ。れんだいこは、人生に於いてこの妙味の部分をもっと大事にしたいと考えている。月面に実際にウサギがいなくても構わない。居たとしたらという仮定で思いを練り、それに害がなければ十分に検討されるに値する話だとする姿勢を持ちたい。以上が、れんだいこ式「十五夜お月さんの餅つき話」の前段になる。さて、これからが値打ちものになる。乞うご期待。 |
| れんだいこのカンテラ時評№1063 投稿者:れんだいこ 投稿日:2012年 9月21日 |
| 「十五夜お月さんの論理」についてその2 「十五夜お月さんの餅つき話には害がない」という良さがあることを既に指摘した。ところで、「十五夜お月さんの餅つき話」は確か短文であるが、これがもう幾分か肉付けされたり、ストーリー化されてそこそこの長文になった場合はどうなるのだろう。しかもそれが結構面白い話になっていたとしたら。ついでに、面白いだけでなく為になる話が満載されていたらどうだろう。懲らしめでもなく、権力者への迎合でもなく、安逸な立身出世物語でもなく、我々の人生とか世の中の仕組みとか今後の歴史の流れとかについて啓発的な物語になっていたとしたらどうなるか。 科学的社会主義屋は、これを荒唐無稽として罵詈雑言するのだろうか。アポロの話を持ち出して否定に躍起になるのだろうか。仮にそうなるとしたら、その姿勢を批判したいというのが、れんだいこが本稿を書きつけてみたいと思うようになった動機である。もし、マルクス主義者にして、科学的社会主義屋の如きアポロ話を持ち出す者が居たなら、その人はマルクス主義の何たるかを根本的に理解し損なっていると思う。 なぜか。それは、有り得べきマルクス主義の根幹には世界の社会主義的改造へ向けての「十五夜お月さんの餅つき話」的童話性があるからである。そういう感性まで含めて理論化しているのがマルクス主義であり、童話性を排除した科学的社会主義屋の如きな教説は何らマルクス主義のものではない。干乾びた現実を客観的に筆で晒したからといって、それだけでは所詮二束三文的な値打ちにしかならない。しかし、この理屈が分からない分かろうとしないマルクス主義屋が多い。 考えても見よう。マルクス主義的未来社会論は、「十五夜お月さんの餅つき話」にある童話性と相似していないだろうか。典型的には、「各人の自由な発展が万人の自由な発展のための条件となるような、一つの協働体としての社会主義社会」、「各人はその能力に応じて、各人はその必要に応じて受け取る共産主義社会」なる概念であるが、これは人類が深く願望するユートピアそのものではなかろうか。 マルクス主義に宿るこのメルヘン気分を理解せず、マルクス主義者にして世の中のユートピア教説のあれこれを批判して得意がっている者が多い。そういう御仁は、己の能力の甲羅に合わせて潜り込んでいる亀が己の甲羅を自賛しているに過ぎない。肝心なことは、その御仁の甲羅の特性である。まだしもそれが開放系のものになっておれば良いのだが、排他的独善的なものになっていたら始末が悪い。 れんだいこは、このような甲羅主義者も科学的社会主義屋も好まない。なぜなら、現実から何を期待しようとするのか、変革するのかについて夢がないからである。人は一般に、金銭欲、異性欲、見栄、名誉、権力を求める。この五欲はそのどれ一つとっても生涯を通じて叶えるのに困難なものであるが、だからといってこの五欲に没頭すれば良いのかというと、やはり味気なさが残る。 この五欲はむしろちょぼちょぼで良いのだ。但し、このちょぼちょぼさえ困難な社会情勢に於いては第一に闘う精神、気概を養うべきだ。その際には、自己奮闘と社会変革とを不即不離に捉えて合一せねばならない。陽明学という学問があるが、その精髄はそのようなことを述べている点で卓見である。我々は、その過程で同類を寄せ集め、苦しみを分かち合いつつ助け合うべきだ。 しかし、それは第一歩であり、そこから先「十五夜お月さんの餅つき話」に向かわねばならない。五欲は自己目的すべきものではなく、願うならば人はかくあるべし論を持たねばならない。その話が荒唐無稽ならば何度も書き直して然るべきものに書き換えればよい。いずれにせよ、「十五夜お月さんの餅つき話」が不要ということにはならない。人はこれを大義とも云う。この大義がなければ味気ないのが人間の性(さが)でもあることが知られねばならない。大義とは、「錦の御旗」と云われるものである。「錦の御旗」の内実は局面局面でころころ変わるものであるが、この伝播性はかなり強く、それだけに疎かにすべきものではない。否、もっと磨くべき種のものである。 考えてみれば、今の世の中は賢ぶるものが多すぎて「十五夜お月さんの餅つき話」が萎え過ぎている。しかし、それはおかしなことなのだ。歴史は、誰かのシナリオの「十五夜お月さんの餅つき話」が育まれ、時にそのシナリオ同士が相争いつつ、相互に味付けが為されつつ変遷してきていると思えるから。もし、今現在の「十五夜お月さんの餅つき話」が不満だとすれば、我々用の「十五夜お月さんの餅つき話」を対置して行けば良い。そうする必要があるのではなかろうか。それがいつか現実になる。これに経済的な裏づけとそれに基づく相互の人間関係の在り方を踏まえればより有効なものになるだろう。 そもそも「十五夜お月さんの餅つき話」に耳を傾ける精神がなければ、この営為そのものが生まれてこない。故に、「十五夜お月さんの餅つき話」を銘々が創造せねばならない、読み合わせしてどんどん書き込んで書き直していかなければならない、これが「十五夜お月さんの餅つき話」にまつわるれんだいこの見解である。 ところが、驚いたことに、この営為が不要という科学的社会主義屋の指導者がいる。青写真を作ると手足が縛られるだと。何というあきれ果てるべき御仁だろう。故に、この御仁の云うこと為すこと全体が干乾びている。膨大な文章を得意がって書きつける癖があるが、読んでも何がいいたいのかさえ分からない。あちこちが玉虫色でさっぱり要領が得ない。この手合いの口車に乗せられると、我々は次第に痴呆症患者の症状を呈することになろう。結局、思想性のない、何も思わず単に唯々諾々するだけのペット人間又は病床人間にされてしまう。この虚構を突破せよ。これがれんだいこが「十五夜お月さんの餅つき話」を語らざるを得ないゆえんである。 |
| れんだいこのカンテラ時評№1064 投稿者:れんだいこ 投稿日:2012年 9月21日 |
| 「十五夜お月さんの論理」についてその3 れんだいこは、何故「十五夜お月さんの餅つき話」に拘るのか。実は、とても素敵な「十五夜お月さんの餅つき話」調の諭し話を知っているからである。マルクス主義ユートピア論よりも気に入っている。ズバリ云おう。それは天理教開祖の中山みきが説いて聞かせた人類創世記譚「元の理」(「泥海古記(口記)」とも云われる。以下、「元の理」と記す)である。それを一言で要約すれば、人類史を俯瞰した上での人の生きる道の指針教説である。れんだいこは、何の因縁か27歳頃この話を聞き魅せられた。以来、今もって虜(とりこ)になっている。 れんだいこの見るところ、「元の理」は、天理教のみならず日本のみならず人類全体に及ぶ貴重な財産である。その説話の創世記物語は旧約聖書数行の記述よりも長い。完成度も高い。そして、人類誕生の元一日の謂われ(因縁)を知り、創造主神の御心に叶う生き方をすべきだと示唆している。その圧巻は、人の生きる目的を諭して、親神が「泥海だけの世は味気ない。一つ人間と云うものを拵えて、その人間が陽気に明るく勇んで助け合って生きる様を見て共に楽しみたい」との思いで創造した以上、創造された側の人間の生きる目的は、この親神の思いに適うことである。しかしてそれが陽気暮らし、陽気勤めの生活であるとしている。これを延々と説き分ける「元の理」教説の例え話が無茶苦茶に面白い。 「元の理」の科学的根拠は分からない。検証しようもない。但し、荒唐無稽かというとそうでもない。親神による人類創造でありながら、進化論にも齟齬しない知見が披歴されている。その逐条が現在の科学的知見において裏付けられるような内容になっており、今後に於いてもますます違背しないのではないかと思われるほどの卓見的示唆で散りばめられている。 教祖中山みきが、この口述を何に依拠して宣べたのかは分からない。教義的には、神が入り込み啓示した思惑を、みきが筆写ないしは口述したのであるから神の言であり、これに間違いのあろう筈がないという訳になるのだが、れんだいこはそこまでは同調しない。しかしながら、「元の理」の秀逸さを誰にも引けをとらないほど畏怖している。 れんだいこは、何故「元の理」に拘るのか。それは、西欧的思弁的知性とは別系の東洋的日本的知性の知恵を感ずるからである。人の生きる目的を尋ねて延々と思索の道に分け入るのは自由ではあるが、日本的知性は割合と早くに見限って、むしろ授かった生命の燃焼の仕方の方に価値を見いだしていた観がある。何事も寿命との相談として、寿命の折節でのパフォーマンスを重視しているように思う。結構な知恵であり分別ではなかろうか。 「元の理」の効能はそれに止まらない。21世紀の人類が陥っている悲劇に対して、みきの諭した「元の理」こそ救済になっているのではないかと思うからである。それは、この世にもしサタニズム論理とそれを信奉する勢力が邪悪な意思で地球及び人類改造を企図しているとするなら、「元の理」」こそそれを覆す論理と知力と運動のつまりは理論的且つ実践的な生命力を持っているのではなかろうかと思うからである。これが、初期の天理教教団が弾圧された真の理由ではなかろうかと思っている。 そのような内容を持つ「元の理」について詳しく知りたければ「教義原型『元の理』」で考察しているので、興味のある方は読まれてみるが良い。今日のものは無論、将来の科学でも跡付けられない、しかし何れの日にか凄いと判明させられる超科学的教説であるように思っている。江戸幕末に突如登場した一介の主婦中山みきは、知る人ぞ知る知らぬ人は知らない天理教教祖であるが、彼女の叡智が世界的に賛辞される日が必ずやって来るだろう。 さて、ここで「十五夜お月さんの論理考」に戻る。れんだいこは、「元の理」話しが真実であろうがなかろうが、全く害のない有益至極な理念話しであり、然しながらその思想は深いと思っている。科学的社会主義屋の精神からは何の意味もない「元の理」譚ではあるが、「十五夜お月さんのおとぎ話し」を大人版にしたものと拝することができ、その効能は絶大と評価絶賛している。とりわけて、地球文明的危機を迎えている21世紀に於いては、その混迷を打破する有り難い指針書足りえているのではないかと思っている。パレスチナの悲惨と中近東の騒乱悲劇を思うたびに、双方が「元の理」の精神で親和する以外に解決しないのではなかろうかと案じている。その他その他然りである。 ここまで述べれば、「十五夜お月さんの論理考」はほぼ完結である。後は、気ままに肉付けしていくことにする。 |
| れんだいこのカンテラ時評№1065 投稿者:れんだいこ 投稿日:2012年 9月21日 |
| 「十五夜お月さんの論理」についてその4 ネット検索で、「『宇沢弘文と語る』を聴講して」に出くわした。れんだいこが意訳すると、次のような話を伝えている。 2010年現在、いつノーベル賞を取ってもオカシクナイとされている万年候補の宇沢博文・政治経済学者が旧制中学の4年生の頃、いろいろの事情があって新潟の禅寺(曹洞宗)に身を寄せることになった。禅寺の住職は、宇沢に「嘘をつきなさい。人びとを幸せにする嘘を沢山つきなさい」と教えたと云う。住職は、晩飯になると宇沢少年を呼んで一緒に食事をしようと誘った。未成年なのを承知で酒も用意されていた。宇沢少年相手にいろいろの話をしてくれ、そのなかの話の一つが「嘘をつきなさい」だった。 宇沢教授は、「今から考えるとわたしの経済学の考え方の根源になっているような気がする」と述べている。この教話の力点は前段の「嘘をつきなさい」にあるのではない。後段の「人びとを幸せにする」というところにある。「嘘」と云う言葉も教説上の方便で、学問も含めた全ての知が「嘘」の範疇に入ると云う認識を元にしている。「学問といい、科学的知見といい、宗教の教義といい、それらはどこまでいってもひとつの仮説にすぎない。つまりは『嘘』の一種なのだから、どうせ『嘘』をつくなら『人びとを幸せにする嘘』をつきなさい」という禅宗特有の寓意である。 宇沢青年をして数学から経済学に向かわしめ、経済学をして、人を計数的物量として扱う近代経済学に対して、生身の人間の生活的与件を絶対的基礎とする「社会的共通資本」なる概念を生ましめ、やがて公共経済学を発想せしめることになるが、その背後に去る日の住職の「嘘をつきなさい。人びとを幸せにする嘘を沢山つきなさい」の教話があったと云う。 これを知り、れんだいこ流に解釈すれば、宇沢弘文政治経済学教授は、「十五夜お月さんの餅つき話」を解する立派な知識人だと云うことになる。 もう一つ。「十五夜お月さんの餅つき話」執筆動機の背後に天理教教祖の口述人類創世記譚「元の理」があったことを種明かししたが、ついでに天理教教祖に纏わる「存命の理」についても記しておく。「存命の理」とは、天理教教祖中山みき逝去後も生身の身体としては死亡したが生命は生前同様に存命しており、今も人類救済の為に働き続けているとする教説である。こういう教祖存命説は何も天理教でのみ云われるのではなく、他の宗派でも同様の説を持つところもあるように思われる。 さて、この「存命の理」をどう寓すべきか。既にここまで「れんだいこの十五夜お月さんの餅つき話」をお読みいただけた者には得心できよう。「存命の理」を科学的知見で批判するのはいとも簡単である。その種の口角泡を飛ばし士に尋ねるが、或る宗派が教祖を死後も「存命の理」として待遇し、教祖を敬慕したとして何か害があるだろうか。天理教では、「存命の理」のままに教祖の着替えを日々行い、拝殿の奥に鎮座されているとして日々諸事の伺いを立てるなり報告を申し上げている。口角泡を飛ばし士がこれを茶番と云うのは勝手である。しかし、れんだいこは、素晴しい没後対応であるとして逆に評価している。 教祖中山みきは生前、人間の寿命は115歳までの定命(じょうみょう)を与えられていると教説していた。これを説いていた頃は80歳代後半の頃である。教祖は、「115歳定命説」を我が身で体現しつつあった。そのみきは80歳の頃より十数次にわたって検挙され、その取り調べも次第に暴力的になった。「最後の御苦労」が1886(明治19)年2月、89歳の身で厳寒の獄舎に入れられた。 一説によると、この時の老婆虐待は凄まじく、にも拘わらず教祖は差し止めさせられていた教義を説くのにひるまなかった。15日間後に釈放されたが、もはや立つこと叶わぬ息絶え絶えの身になっていた。その後は床に臥す日々となり、「最後の御苦労」の一年後に逝去している。亨年90歳。教内では、「115歳定命説」に違う教祖の逝去に対する動揺が走った。 この時、霊能を分与されていた後の本席・飯降伊蔵が指図したのが、「さあさあわからん。わからん、なにもわからん。115才、90才、これもわからん。25年不足であろう。どうであろう。これもわからん。どうしてもこうしてもすっきり分からん。故に25年を縮め、助けを急ぎ、扉を開いて世界をろくぢに踏み均(な)らしに出た。神でのうてこの自由自在は出けようまい。止めるに止められまい。神は一寸(ちょっと)も違うた事は云わん。よう聞き分けてくれ。これから先というは、何を聞いても、どのよの事を見ても、皆な楽しみばかり。楽しみや。よう聞き分け。追々刻限話しをする」、「さあさあこれまで住んで居る。何処へも行てはせんで、何処へも行てはせんで。日々の道を見て思案してくれねばならん。(中略) 姿は見えんだけやで、同んなじ事やで、姿がないばかりやで」なる啓示であった。 かく「存命の理」が打ち出され、教内の動揺は治まった。これが「存命の理」の歴史的事情である。これに照らす時、飯降伊蔵の啓示はむしろ何とも鮮やかと云うべきではなかろうか。 「十五夜お月さんの餅つき話」から始まりマルクス主義のユートピア思想、天理教の「元の理」、「存命の理」へと辿り着いたが、この思索の旅が面白かったのは一人れんだいこだけだろうか。本稿はこれでひとまず完結とする。 |
宇沢氏の情報が入ったので転載しておく。
|
![]()
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)