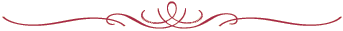
| みかぐらうた(御神楽歌)その1、悪しき祓いの地歌/座りづとめ |
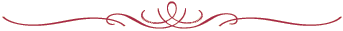
更新日/2020(平成31→5.1栄和改元/栄和2)年.3.12日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここに、「御神楽歌」全文(但し、れんだいこ翻訳文)を誌す。れんだいこは、「御神楽歌は、日本宗教史上最高の傑作中の傑作の和歌教歌」と評価させていただく。おさしづ(明治33年9.9日)に「ひと言説いたら百巻の書物にできる」と諭してあるように、全編が神示となっている。信仰の流れ的には、入信から講の結成の道筋、自己助かりから世界助けへの理論と実践の道筋、その為のつとめ、その精華としての甘露台神楽づとめ、陽気暮らしの思想を芯とせよとの思し召しを、日本古来よりの伝統的な和歌形式で説いているところに特徴が認められる。 これをもう少し詳しく説明すると、人生のよろず悩みを抱えての入信から始まり、身情事情解決の道筋の悟り、互い助け合い思想の確立、用木(ようぼく)としての「お道」の歩み、講の結成、この経緯での道人の心構え等々につき実にやさしく且つ内容豊かに歌い上げている。道人がこの教えに一筋にもたれて通るなら、人生に豊かな実りが約束され、難渋が救われ、遂には謀反と病の根を切り、更に世界助けに向かうことにより国々所々が治まり、平和な世の中になることを詠っている。まさに教祖流の世直し論であり、「人々の心の入れ替え、胸の掃除を通じての世の立て替え(社会の再創造)」を指針しているところに特徴が見られる。今日定式されているこの形式が教祖の教えたそれであったかどうかとは別であるが、原型は維持されていると考えるべきではなかろうか。御神楽歌の凄さは、お道の発展のみならず、あらゆる組織、事業体の形成経営に資する普遍的な教示となっているところにある。心して学ぶべしではなかろうか。ここでは、「みかぐらうた(御神楽歌)その1、悪しき祓いの地歌/座りづとめ」と「よろづよ八首」について確認する。 2011.04.14日再編集 れんだいこ拝 |
![]()
| 【神楽づとめの地歌】 | |||||
| 「座りつとめ」で表現される際の御歌である。 | |||||
|
|||||
|
|||||
|
| 【十一通りのおつとめ】 | |
| 教祖は、他にも十一通りの特別な守護をお願いする「おつとめ」を教えている。 1、をびやづとめ(安産の祈願)。2、一子のつとめ。3、ほうそづとめ、4、ちんばのつとめ。5、はえでのつとめ(豊作の祈願)。6、肥のつとめ。7、雨乞いつとめ。8、雨さずけのつとめ。9、虫払いのつとめ。10、みのりのつとめ。12、むほんづとめ、である。 教学者の上田嘉成氏は、「この中で一番肝心なのは、むほんづとめである」(上田1980)としている。この「つとめ」の地歌は以下の通り。
「改訂・天理教事典」によれば、この「おつとめ」の手振り(踊りの振り付け)には、刀をさすような動作がある云々。現在、十一通りのおつとめのうち「をびやづとめ」と「はえでのつとめ」を行っているだけで、「むほんづとめ」はもう行われていない。 |
| 【「ようし、ようし」考】 | |
教祖伝逸話篇109「ようし、ようし 」。
|
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)