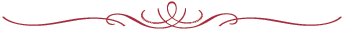
| 二つ一つの理 |
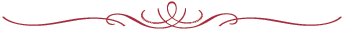
更新日/2019(平成31→5.1栄和改元)年.10.29日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここで、お道教理としての「二つ一つの理」教理を確認しておく。 2003.8.29日 れんだいこ拝 |
![]()
| 【二つ一つの理】 | ||||||||
| お道教理では「二つ一つが天の理」(以下、「二つ一つ理論」と表記する)と云う。これは、二つの相反する対照的なものが、抗争しあるいは拮抗しながら調和して働くところに生成発展の元がある、生産的な力が現れると見なす理法である。これは、二つのものが同一のものに合体するということではない。それぞれが独自性(異なる働き)を持ちながら、助け合い、補い合い、支えあって活動している、世の中の全てのものが「相対する二つの要因が互いに補足し合い、共に他を成り立たせる働きかけにおいて、自らの存在を得ている」と云う理法に基づいている、と見做している。これを「天の理」と云い、これが親神の守護の理であり、宇宙秩序、自然世界、人間社会、人間身のうちに貫通しているとも見做している。
たとえば「元初まりのお話」において親神は「月様」「日様」としてお現れになっているとか、「地と天とを象りて」とか、相対する働きによって、親神の守護の理が説かれている。この理を簡単に表現するために「二つ一つ」または「二つ一つの理」または「月日の理」という言葉が、教理書において使われることがある。 「おさづけ」の「おかきさげ」に、「さづけ」を授けられた人への教訓として、「所に一つ成る程(なるほど)の者というは、第一には家業、親孝心、二つ一つが天の理という」(明治22.10.9 補遺)のように、家業と親孝心(親孝行)と二つをあげている。 例えば、両方の手足を思えば良い。片方がかけると色々と不便で、通常支えあっていることが分かる。両者相関のこれを「二つ一つ理論」と悟らせていただく。昼と夜、月と太陽の関係も然りである。両者は一見して火と水、天と地のように相反する事象のように思える。が、一見両立し得ないような両者ではあるが、昼と夜がなければ作物が育たない、月と太陽がなければ生命が育まれない。火と水はお互いを相殺する(火は水を蒸発させ、水は火を消すなど)働きがあるが、火と水がお互いを立て合ってお湯を造り出すこともある。天地の関係で言えば、天に地の働き(雨を蓄えたり、作物を育むようなこと)はできず、地も天の働き(雨を降らせたり、雪を降らせたりするようなこと)ができない。この両者が両立相関しつつ天地の事象を司どっている。これらの働きすべてが天の理であり親神様のご守護であるとも教えられる。 「二つ一つ」、「二つ一つの理」という言葉は、お指図の中で次のように宣べられている。
これらの意味するところは「二つまたは いくつかの事柄が、たとえば、誠の心のような人間の精神とか、または親神の守護によって一つに治まること。あるいは、両立しがたいものでも両立し得る道があり、それが天の理、すなわち親神の守護である」ということと理解される。 |
| 【お道の「二つ一つ理論」とマルクス主義的矛盾論との違い考】 |
| この「二つ一つ理論」は、マルクス主義の唯物弁証法的闘争理論としての矛盾論とは似て非なるものである。世上の男女同視的同権理論とも違う。「二つ一つ理論」は、「相対立する両者が、対立の真奥で相補しつつ拮抗している点を重視する。その上で、お互いに相手の主体性、自由、個性を認めつつ、立場の相違を踏まえた上で、抗争すべきところは抗争し、且つお互いに救け合っている面も認め、結果として釣り合いのとれたところで調和している」と見做すのが「二つ一つ理論」である。お道の「二つ一つ理論」は、マルクス主義の唯物弁証法的闘争理論としての矛盾論を稚拙に排撃して事足れるとするのではなく、マルクス主義のそれより深いところまで認識しており、理論的により優れているのではなかろうかと思わせていただく。ここに値打ちがあるように思われる。 |
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)