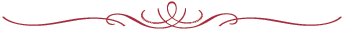
| 信仰観、諭し悟りの道その5、談じ合い練り合いの理 |
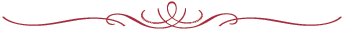
更新日/2019(平成31→5.1栄和改元)年.10.5日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここで、お道教理としての「信仰観、諭し悟りの道その5、談じ合い練り合いの理」を確認しておく。 2003.8.29日 れんだいこ拝 |
![]()
| 【談じ合い、練り合い論】 | ||||
| 本部教理では打ち出しが弱くされているが、本来のお道教理では「談じ合い、練り合い」が重視される。これは、親神様が人間を創造される時に道具雛型となったものたちと談じ合い練り合ったことに由来すると思われる。道具衆は、親神の諭しで始まる人間創造の「元の理」に添って話し合い練り合いすることが大事とされており、天理教信仰の型となっている。この型によって、親神と道具衆の「談じ合い、練り合い」はお道の組織原理にスライド適用される宿命を持つ。即ち、最終的に「教会長と教会氏子」の関係へ、更に「理の親と理の子」の関係へと適用されて行くべきことになる。本来はかく、お道教理の「談じ合い、練り合い」を芯としていることを窺うべきで、これより「談じ合い、練り合い、助け合い」をワンセット教理を生みだすべきだろう。 み神楽歌、お筆先は次の通り。
|
||||
昭和18年②月号みちのとも「朝起・正直・働き」の梶本宗太郎「人と打ち解けるには」。
|
||||
お指図教理。
|
||||
| この道の神は、「諭し談じの神」である。これを確認しておく。教理的には「元の理」全編で説かれている。このことが如何に重要なことであるかが案外と理解されていない。それは、ユダヤ/キリスト教のエホバ神との比較をすれば違いがはっきりと見えてくる。ユダヤ/キリスト教のエホバ神も天理教の天理王の命もどちらも神話上の天地創造神であるが、そのありようがかくも違うことに驚かされよう。 |
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)