明治19年9.10日、式上郡笠間村講元加見兵四郎「少々家業さして被下度(下されたく)御願い」。【註】当おさしづは、現行「七巻本」未収録。〔みちのだい第33号「教祖特集号」40頁〕
| さあさぁ尋ねる事上(事情)/\は、赤き道、白き道、黒き道に諭しおこう。 これでわかろまい、 赤き道は神の道一寸はかり(ちょっと解り)かけた事、白き道は世界並み、黒き道はわが身の思案。世界のものからつけた徳は、世界からはおとさん(落とさん)、わが心でおとさぬ(落とさぬ)よう。さあさぁいばらぐろう(茨畔)も、がけ(崖)道も、つるぎ(剣)の中もと云ふてあろ、どうせこうせは云わん、心と心で思案(しやん)してみるがよい。 |
|
| 「ただこうきという。それぞれのところより刻限、赤きは赤き、黒きは黒き者に連れられ、さあさぁ段々早や/\」(明治20.3.19日)。 |
明治20年11.2(旧9.17日) 本席おさしづ。【註】当おさしづも「七巻本」未収録。
| 心迄に一寸噺して置に依テ(心までにちょっと話しておくによって)、よふしやん(よう思案)。 赤キ道、黒キ道、白キ道、是デハわかろまい(これでは分かろまい)。あか(赤)き道とゆふは、わかりかけた心、赤キ道也(なり)。黒キ道とゆふは、何事もわがしやんの心、黒キ道也(なり)。白キ道とゆふは、世界なみの心、是ヲ(これを)白キ道と云う也(「根のある花・山田伊八郎」222頁)。
|
これによれば、赤き道とは「神の道・神意・教えの理が解りかけた心」で、 黒き道とは「何事も自分中心に考える『わが身思案・ほこり』の心」で、 白き道とは「世界並みの心」と説明されている。
|
| 名々身上處(ところ)分からん。ほんに色もの、白黒が分からん残念(明治20.12.2日)。 |
| どういう事も改める/\/\、十分改める。白きものは白きと言えば分かる(明治22.4.17日)。 |
| 赤きもの赤きと言えば、鮮やかであろう。白きもの白きと言えば、鮮やかであろう(明治22.10.9日)。 |
| 先の理の話、これまで一つの理、思いも軽い理も分かる、黒き赤き理も分かる(明治25.2.1日)。 |
| 元々から用いりて、取り立ててくれにゃならん。持ちてる物 離してなりと運んでくれにゃならん。白きもの白きに見る、赤きもの赤きに見る、黒きもの黒きに見るは皆世界の事情(明治26.2.5日)。 |
| どう思うてもならんで/\。悩み/\身の難儀、赤い黒いも分からず、そもそもの心を吹き出し、段々事情と言えば、これも十分の心とは言えようまい(明治26.5.18日)。 |
| 夜と昼とが分からねばならん。白いものと黒いものと分からねばならん(明治26.10.5日)。 |
| 縁談話理が分かりよう處(ところ)分け。白きもの白き理、色の話、どんな話、大変間違う。…白き話、白きものを以(もっ)て、理を以て理聞く(明治27.3.6日)。 |
| 春風のようなそよそよ風の間は何も言うことはない。神も勇んで守護する。なれど今の事情はどうであるか。黒ほこり、泥ぼこり立ちきってある。この黒ほこり、泥ぼこりの中で、どうして守護できるか。又(また)守護したところが、世界へどう見えるか。よう聞き取れ。大変口説き話である程に/\(明治30.2.1日)。 |
| 鏡やしき濁りた心は持たん。黒きは黒き、白きは白き、赤きは赤きが映る(明治30.7.7日)。 |
| そこで内々事情、屋敷の中という。あちらから黒ぼこりこちらから黒ぼこり、年限ようよう一寸(ちょっと)事情、払うて/\どうでも払い足らん。まだもう一段払い足らん。…神の自由(じゅうよう)して見せても、その時だけは覚えて居る。なれど一日経つ、十日経つ、三十日経てば、ころっと忘れてしまう。大ぼこり/\、提げ出す、担い出す。積もる。後向いても、どっこにも橋がない。神が除いて了(しも)たら是非がないで。どれだけ塵(ちり)を溜めておいても、払うて了(しも)うたら、もう一遍(いっぺん)どうしようと思ても行こまい(明治31.5.9日夜)。 |
| あちら話しこちら話し、白いものと言うて売っても 中開けて黒かったらどうするぞ(明治32.7.23日)。 |
| 何ぼ(なんぼ)言うて聞かしたてならん。我(わ)が身仕舞(じま)いではならん。それでは灯火(ともしび)消えて、今一時点(つ)けようと言うたて行きやせん。暗闇と言う。聞き分け。今日の指図は容易ならん指図である程に。心に含んで言わんと居るは、真実はほんの上面(うわっつら)だけ。今日の一つ指図下(く)だすは、憎うて下(く)だすやない程に。可愛一条(
かわいいちじょう)で下だすのやで(明治33.10.14日)。 |
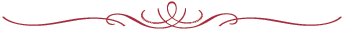
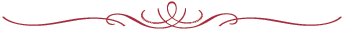
![]()
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)