|
宗太郎(そうたろう)父が、昭和二十六年「復元 第十八号」に「教祖様の思〈ひ〉出〈その他〉」として出しておられますうちより、二つ三つ、抜き書きさせて頂きました。
〇私は「教祖に物をもろうた」というようなことだけ覚えている。教祖は、蜜柑(みかん)を下さった。蜜柑の腹の方の筋を取って、背中の方から指を入れて、「トンビトートー、カラスカーカー」というのにして、『指を出せ』と仰るので指出すと、その上へのせて下さるので喜んでる、私は七つくらいやった。また、蜜柑の袋もろて(もらって)、こっちも真似(まね)して指にさして、教祖のところへ「ヒョー」っと持って行くと、教祖が召し上がって下さった。
〇神殿(つとめ場所)の方で、お菓子でもいただいたら、子供同士遊んでて、遊びながらいただいて、なくなったら、また教祖のところへ走って行って、手を出すと、下さる。食べてしまって、なくなると、また走って行く。どうで(どうせ)〈自分が〉、「おばあちゃん、またくれ」とでも言うたのやろ。三遍も四遍も行ったように思う。それでも、「今やったやないか、というようなことは一度も仰らん」。また、「うるさいから一度にやろう、というのでもない」。 食べるだけ/\下はった(くだはった)。白せんこ(はくせんこう/白雪糕/はくせつこう)か、ボーロか、飴のようなものやったと思う。
大体、教祖は子供が非常にお好きやったらしい。山澤の母に聞くとそうや。櫟本の梶本へは、チョイチョイお越しになった。そのたびに、内の子にも、近所の子にもやるように、お菓子を袋に入れて持ってきて下さる。その巾着(きんちゃく)は、端切れを継ぎ合わせて巾着にしてある。角にして継ぎ合わせてある。赤も黄もある。そしてその紐(ひも)は、鉋屑(かんなくず)。それも、スーッと紙のようにして作ったのを、コヨリ(紙縒り)にして紐にしてある。それが巾着の紐や。「それは教祖が鉋屑で作らはったんや」と聞いた。その巾着は、今も中山家の蔵にある。山澤の母(ひさ)に、この説明は聞いた。
〇私は曽孫(ひまご)のなかでは男での初や。女ではおもとさんがいる。それで、
『早う、一人で来るようになったらなあ』と仰ってくれはったという。
〇島村(父の弟/宗太郎の弟、国治郎)が生まれた時、『色の白い、きれいな子やなあ』と言うて抱いて下された。それは山澤の母にも、うちの母(ウノ)にも、よく聞いた。
〇吉川〈万次郎〉と私と二人、教祖の背中に同時に負うてもろうたことがある。そして、東の門長屋(もんながや)の所まで、お出で(おいで)下はったことがある。藤倉草履(ふじくらぞうり)みたいなもの履いて。
〇教祖のお声は、優しいお声やった。スラリとしたお姿やった。顔は面長(おもなが)で、お政さん(教祖のご長女)は、ちょっと円顔(まるがお)やが、口元や、顎(あご)はそのままや。お政さんは、頑丈(がんじょう)の方(ほう)、教祖は、やさしい方(ほう)やった。腰は曲がってなかった。
〇教祖は、生の薩摩芋(さつまいも)の皮を剥(む)いて、「わさびおろし」で擦(す)って召し上がった。分量は、お齢を召していたから少しと思うが、時々召し上がった。時によると、煮たもの〈は〉召し上がらずに、そんなもの召し上がった。私は子ども心に見ていた。おいしそうに召し上がるので、櫟本の家に帰ると、真似して、お茶碗に一杯ぐらい食べた。
〇お隠れの時は、箱枕(はこまくら)やった。私は、お隠れになった時、亡骸(なきがら)の所へ連れて行ってもろた。そして、手を当てたらハッとした。冷たかった。その時、
「息引き取ったら、こんなに冷たいものか」と思うた。それが、私にとっては初めての印象や。その時には、飯降〈政甚〉さんも、裏の叔父さん(梶本楢治郎)も、同じこと言うてる。真柱さんが、いちいちお呼びになったのやろ。
× × ×
教祖が御身をお隠しになりました時、宗太郎父は八才でしたので、「お仕込み頂いた思い出はない」と申しておりました。
みちのだい第33号「教祖特集号」30-31頁
|
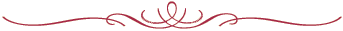
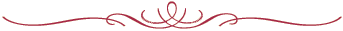
![]()
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)