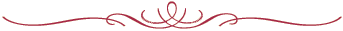
|
古老より聞いたはなし ⑻、
|
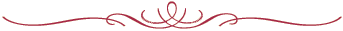
更新日/2019(平成31→5.1栄和改元)年.9.25日
| (れんだいこのショートメッセージ) | |
| ここで、「天理教教理を学び神意を悟る」の「古老より聞いたはなし」の「古老より聞いたはなし ⑻ 」を確認しておく。
2006.1.23日、2012.9.18日再編集 れんだいこ拝 |
![]()
| 【 |
|
深みゆく大和(やまと)の秋景色のなかでも、特に一葉々々と散りゆく柿の木になる色鮮やかな実が、いっそう大和の秋の趣きを深めております。わけても古い農家には、御所柿(ごしょがき)が、門の内ら(内側)の屋根に覆いかぶさるように立っているのが大和らしい姿です。教祖ご誕生にゆかりある、三昧田の前川家の内庭にも、古い柿の木が植わっています。
私の家でも、信仰の初代、儀三郎(ぎさぶろう)祖父(別名:左右衛門/さえもん)の時代からあったという、古い御所柿の木が前庭にあり、ある年には「虫」のため、二つ三つ、申しわけ程度の時もあり、また、枝が折れんばかりに、たわわに実る年もあります。
【註】御所柿…現奈良県御所(ごせ)市周辺原産の完全甘柿品種。 この古い柿の木と調和するように、奥まった所に、これまた百年はゆうに過ぎた古家があります。初代当時からのもので、真っ黒に煤(すす)けきった天井や柱に、文久の初めから教祖にお救け頂き、手塩にかけてお導き頂いた、初代の信仰の息づかいが秘められているようです。
その昔、年代ははっきりしませんが、教祖が、庄屋敷村から歩いても五、六分とかからない豊田村の、この屋敷へ来られて、『しっかり踏み込め/\、末代までも、しっかり踏み込め/\/\』とお言葉を下されたそうです。 祖父は、この尊い親心のにじみ込んだ屋敷を、末代永く子孫に伝えんがため、二代、三代に、くどくど言い伝えておりました。そして信仰とは、その場限りの、一代限りの短いものではなく、生涯末代に続くものであることを、敷地の地固めをすることによって、お教え下さった教祖の御心を、今日も新たに私たちは味あわせて頂いています。
教祖は晩年、十八回にも及ぶ獄舎へのご苦労のお道すがらがございますが、 明治十九年の櫟本分署での最後のご苦労中、朝方になってもランプの灯が点いていたので、教祖は、つと立って、ランプの灯を吹き消されたお話がありますが、やはり、監獄ご苦労中のこと、教祖ご自身、使い古した罫紙(けいし)を差し入れさせられて、それで紙縒り(こより)を作られ、一升瓶(いっしょうびん)ぐらいの入る網を作られたのを、祖父に下されました。この網袋(あみぶくろ)を見させて頂くにつれ、「お齢を召された教祖が、よくもまあ、こんな細かい細工物を作られたなあ……」と、改めて感嘆させられるのでありますが、『どんな小さいものでも、大切に生かして使う』という、温かい心遣いが偲ばれるのであります。 いづれも中田家に、いんねん結んで下されたればこそ。 今日も教祖の御心が実感として味あわせて頂けることに、喜びをいっぱいに感じさせて頂いております。 みちのだい第33号「教祖特集号」29-30頁 |
|
【参考】「逸話篇」四一 末代にかけて
あるとき教祖は、豊田村の仲田儀三郎の宅へお越しになり、家のまわりをお歩きになり、 『しっかり踏み込め、しっかり踏み込め。末代にかけて、しっかり踏み込め』 と、口ずさみながらお歩きになって後、仲田に対して、『この屋敷は、神が入り込み、地固めしたのや。どんなに貧乏しても手放してはならんで。信心は、末代にかけて続けるのやで』
と仰せになった。
後日、儀三郎の孫、吉藏(きちぞう)の代に、村からの話で、土地の一部を交換せねばならぬこととなり、話も進んできた時、急に吉藏の顔に面疔(めんちょう/おでき)ができて、顔が腫れあがってしまった。それで、家中の者が驚いて、いろいろと思案し、額を寄せて相談したところ、年寄りたちの口から、 「教祖が地固めをして下された土地」であることが語られ、早速、親神様にお詫び申し上げ、村へは断りを言うたところ、身上の患いは鮮やかに、すっきりとお救け頂いた。 註「年寄りたち」とは、中田しほと、その末妹、上島かつの二人である。しほは、儀三郎の長男の嫁。
「天理教教祖伝逸話篇」69-71頁
|
| 一三八 物は大切に 教祖は、十数度も御苦労下されたが、仲田儀三郎も数度、お伴させて頂いた。そのうちのある時、教祖は、反故(ほご)になった罫紙を差し入れてもらって、コヨリ(紙縒り)を作り、それで、一升瓶を入れる網袋をお作りになった。 それは、実に丈夫(じょうぶ)な、上手に作られた袋であった。教祖はそれを、監獄署を出て、お帰りの際、仲田にお与えになった。そして、『物は大切にしなされや。生かして使いなされや。すべてが神様からのお与えものやで。 さあ、家の宝にしときなされ』とお言葉を下された。 「天理教教祖伝逸話篇」230頁 |
| 【参考】「道のさきがけ 教祖伝にみる人物評伝」 仲田儀三郎
天保二年(1831年)五月二十五日、豊田村(現天理市豊田町)に生まれる。
左右衛門(さえもん)といい、「さよみさん」の名で親しまれた(明治になって改名)。
文久三年(1863年)二月、妻かじの産後の肥立ちが悪く、教祖を訪ねたのが信仰の始まり。のちに、初期の信仰者の総代的存在となる。教史の重要な場面には、必ずと言っていいほど彼の名が出てくる。
義太夫(ぎだゆう)の心得があって、警察に連行される時でも、身ぶり手ぶりで語って周囲を笑わせた。教祖とともに拘留された事もしばしば。 明治十九年の、いわゆる「最後の御苦労」にも一緒に拘留され、三十年振りの厳寒の中、櫟本警察分署に十日間留置、檻に入れられた。この年の六月二十二日、五十六歳で出直した。 教祖のお話を書き記したものは、 「棺(ひつぎ)に納めて埋めてしまった」 と言われている。
「道のさきがけ」25-27頁〕参照 |
|
教祖お手製「紙縒り(こより)の網袋」
写真は明治10年に、増井りん先生が
頂戴したものだが、仲田儀三郎先生が
頂戴したものも同様のものと思われる
「おやさま 天理教教祖と初代信仰者たち」
89頁より謹写
|
 御所柿(ごしょがき)
上下に平たい甘柿の典型であり代表格
|
| カテゴリなしの他の記事 |
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)