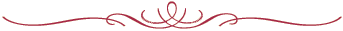
| 古老より聞いたはなし ⑷、 |
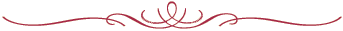
更新日/2019(平成31→5.1栄和改元)年.9.25日
| (れんだいこのショートメッセージ) | |
ここで、「天理教教理を学び神意を悟る」の「古老より聞いたはなし」の「古老より聞いたはなし ⑷
2006.1.23日、2012.9.18日再編集 れんだいこ拝 |
![]()
| 【 |
| 「『お屋敷に居る者は、よいもの食べたい、よいもの着たい、よい家に住みたいと思うたら、居られん屋敷やで。よいもの食べたい、よいもの着たい、よい家に住みたい、とさえ思わなかったら、何不自由ない屋敷やで。これが世界の長者屋敷やで』と、教祖がお屋敷住まいについて、こう仰せ下されたのや」と母から聞かして頂きました。 |
|
〇腹立ちについて
これは伊三郎父と、おさめ母が、教祖のお仲人で結婚をさせていただかれまして、それからのことでございます。父伊三郎が、教祖の御前に出られました時、『伊三郎さん。あんたは外では優しい、なかなか人付き合いのいい人やけど、家に帰って、わが女房の顔を見ては、ガミガミ腹を立てて怒ることは、これは一番いかんことやで、これは今日よりやめておきなさいや』と教祖が、父にお仕込み下されました。するとこの時も、「私がいない時に、おさめが教祖に、こんなこと話しに来たのやないか」と思うて、やっぱり腹が立ちました。けれど、よくよく考えてみると、「おさめが教祖にこんなこと言いに来るはずもない」と思案した時、「自分の腹立ちの心が悪いのや。これを教祖がお仕込み下されているのや」と気付いて、その時その場で教祖に、「今後は決して腹を立てません」と、固く精神を定められました。すると、それからというものは、父が家に帰って母の顔を見ても、ちょっとも腹が立たん。母の顔は変わらん同じ顔であるが、「わが心に、腹の立つようなことが映ってこんのや」と言うて、「お父さんが腹立ちの因縁切ってもらわれて、それからというものは、それはそれは優しいお父さんになられたのや」という話を聞かせて頂きました。 これはまた、おきく祖母に教祖がお聞かせ下された話であります。『人の腹というものは、腸(はらわた)というて、やわらかい腹を貸してあるのやで。腹の立つような腹を貸してあるのやないで。立つ理は、皆めんめん(銘々)我が心にあるのやで』 とお仕込み下されたという話も、この腹立ちの話をされました時に、母が聞かせてくれました。そして、「教祖のお話というものは、ちょっとも無駄にはできない正味のお話やで。これをしっかりそのまま心に守って通らせてもろうたら、わが身結構に、わが身の因縁も切って頂いて、救けて頂くこともできる、ありがたいお話やで」と、母が聞かせてくれました。
〔みちのだい第33号「教祖特集号」26頁〕 |
| 【参考】「逸話篇」七八 長者屋敷 教祖が、桝井キクにお聞かせ下されたお話に、 『お屋敷に居る者は、よいもの食べたい、よいもの着たい、よい家に住みたい、と思うたら、居られん屋敷やで。よいもの食べたい、よいもの着たい、よい家に住みたい、とさえ思わなかったら、何不自由ない屋敷やで。これが、世界の長者屋敷やで』と。
〔「天理教教祖伝逸話篇」134-135頁〕 |
|
【参考】「正文遺韻」
今までの長者というは、金持ちが長者や。長者一夜にも倒れるで。これからの長者は、ころりと違うで。
〔諸井政一「正文遺韻」119頁〕 |
| 【参考】「おさしづ」 この道始め 家の毀ち初め(こぼちぞめ)や。やれ目出度い(めでたい)/\と言うて、酒肴(さけさかな)を出して内に祝うた事を思てみよ。変わりた話や/\。さあ/\そういう處(ところ)から、今日まで始め来た/\。世界では長者でも今日から不自由の日もある。何でもない處から大きい成る日がある。家の毀ち初めから、今日の日に成ったる程と、聞き分けてくれにゃなろまい。
〔おさしづ 明治33.10.31〕 どれだけの長者も、一夜の間に無くなる、という理 諭(さと)したる。これ聞き分け。今日は十分と思えども、明日は分からん。この理を聞き分けにゃならん。理を心に意味を含んでくれ/\。取り損(とりぞこな)いあっては、踏み被(ふみかぶ)らにゃならん。何よの事も天然と言うて諭し掛けたる。天然という順序聞き分け。
〔おさしづ 明治34.2.10〕
|
|
【参考】「逸話篇」 一三七 言葉一つ
教祖が、桝井伊三郎にお聞かせ下されたのに、『内で良くて外で悪い人もあり、内で悪く外で良い人もあるが、腹を立てる、気侭癇癪(きままかんしゃく)は悪い。言葉一つが肝心。吐く息引く息一つの加減で内々治まる』と。また、『伊三郎さん、あんたは外では、なかなか優しい人付き合いの良い人であるが、我が家へ帰って、女房の顔を見て、ガミガミ腹を立てて叱ることは、これは一番いかんことやで。それだけは、今後決してせんように』と仰せになった。 桝井は、「女房が告げ口をしたのかしら」 と思ったが、「いやいや神様は見抜き見通しであらせられる」と思い返して、「今後は一切腹を立てません」と心を定めた。すると不思議にも、家へ帰って女房に何を言われても、ちょっとも腹が立たぬようになった。
〔「天理教教祖伝逸話篇」228-229頁〕 |
| 【参考】桝井孝四郎「教祖様のお言葉」 これはまた別の場合でありまするが、おきくのお祖母さんが、教祖様(おやさま)から斯様(かよう)にお聞かせ頂いた。『なあ、おきくさん。腹というものはな、腸(はらわた)と言うて、柔らかいもの神様が貸して下さってあるのやで、立つ、立たんは、めんめんの心の理が立つのやで』と仰った。誠にこの通りではありませんか。「はらわた」、上手いことを教祖様(おやさま)は仰るじゃありませんか。ところが、なんぼ柔らかい袋でも、中に棒を入れたら立つのです(笑声)。立てるのは、こちらにあるのです。だからして、埃というものは、銘々の我心にあるのです。我心の掃除、心の入れ替えなし、そして喜びの世界を見せていただくのであります。すなわち、救けて頂くことができるのでございます。 〔「天理青年教程」第3号 119-120頁〕 中山正善「ひとことはな志」161頁より謹写 最終見直し 2016.7.31 15:00 |
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)