〔みちのだい第33号「教祖特集号」25-26頁〕
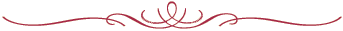
| 古老より聞いたはなし ⑶、梅谷四郎兵衛 |
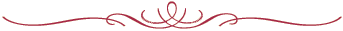
更新日/2019(平成31→5.1栄和改元)年.9.25日
| (れんだいこのショートメッセージ) | |
| ここで、「天理教教理を学び神意を悟る」の「古老より聞いたはなし」の「古老より聞いたはなし ⑶、梅谷四郎兵衛」を確認しておく。
2006.1.23日、2012.9.18日再編集 れんだいこ拝 |
![]()
| 【 |
|
〔みちのだい第33号「教祖特集号」25-26頁〕 |
|
【参考】「逸話篇」一〇七 クサはむさいもの
明治十五年、梅谷タネがおぢばへ帰らせて頂いた時のこと。当時、赤ん坊であった長女タカ(註、後の春野タカ)を抱いて、教祖にお目通りさせて頂いた。この赤ん坊の頭には、膿を持ったクサが一面にできていた。教祖は早速、『どれ、どれ』と仰せになりながら、その赤ん坊を自らの手にお抱き下され、そのクサをご覧になって、『かわいそうに』と仰せ下され、自分のお座りになっている座布団の下から、皺(しわ)を伸ばすために敷いておられた紙切れを取り出して、少しづつ指でちぎっては唾を付けて、一つ一つベタベタと頭にお貼り下された。そして、『おタネさん、クサは、むさいものやなあ』と仰せられた。タネはハッとして、「むさ苦しい心を遣ってはいけない。いつも綺麗な心で、人様に喜んで頂くようにさせて頂こう」と、深く悟るところがあった。それで教祖に厚く御礼申し上げて大阪へ戻り、二、三日経った朝のこと。ふと気が付くと、綿帽子をかぶったような頭に、クサがすっきりと浮き上がっている。あれほどジクジクしていたクサも、教祖に貼って頂いた紙に付いて浮き上がり、ちょうど帽子を脱ぐようにして見事にご守護いただき、頭の地肌には、すでに薄皮ができていた。 「天理教教祖伝逸話篇」184-186頁「静かなる炎の人 梅谷四郎兵衛」73頁 |
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)