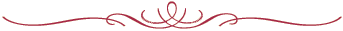河内国柏原村の山本利三郎は、明治三年秋二十一才の時、村相撲を取って胸を打ち、三年間病の床に臥(ふ)していた。医者にも診せ、あちらこちらで拝んでももらったが、少しもよくならない。それどころか、命旦夕(めいたんせき)に迫ってきた。 明治六年夏のことである。その時、同じ柏原村の「トウ」という木挽屋へ、大和布留から働きに来ていた「熊さん」という木挽がにをいをかけてくれた。それで父の利八が代参で、早速おぢばへ帰ると教祖から、
『この屋敷は、人間はじめ出した屋敷やで。生まれ故郷や。どんな病でも救からんことはない。早速に息子を連れておいで。おまえの来るのを、今日か明日かと待っていたのやで』、と結構なお言葉を戴いた。戻ってきて、これを伝えると利三郎は、「大和の神様へお詣りしたい」と言い出した。家族の者は、「とても大和へ着くまで持たぬだろう」と止めたが、利三郎は、「それでもよいから、その神様の側へ行きたい」とせがんだ。あまりの切望に戸板を用意して、夜になってから秘かに門を出た。けれども途中、竜田川の大橋まで来た時、利三郎の息が絶えてしまったので一旦は引き返した。しかし家に着くと、不思議と息を吹き返して、「死んでもよいから」と言うので、水盃の上、夜遅く提灯を点けて、また戸板を担いで大和へと向かった。その夜は、暗い夜だった。 一行は、翌日の夕方遅く、ようやくおぢばへ着いた。すでにお屋敷の門も閉まっていたので、付近の家で泊めてもらい、翌朝、死に瀕している利三郎を、教祖の御前へ運んだ。すると教祖は、『案じる事はない。この屋敷に生涯伏せ込むなら、必ず救かるのや』、
と仰せ下され、続いて、『国の掛け橋、丸太橋、橋がなければ渡られん。差し上げるか、差し上げんか。荒木棟梁々々々々』、と、お言葉を下された。それから風呂をお命じになり、『早く風呂へお入り』、と仰せ下され、風呂を出てくると、『これで清々したやろ』、と仰せ下された。そんな事のできる容態ではなかったのに、利三郎は少しも苦しまず、かえって苦しみは去り、痛みは遠ざかって、教祖から戴いたお粥を三杯、美味しく頂戴した。こうして教祖の温かい親心により、利三郎は六日目にお救け頂き、一ヶ月滞在の後、柏原へ戻ってきた。その元気な姿に、村人達は驚嘆したという。