風姿花伝(ふうしかでん)は室町中期(1400年頃)に成立した能楽書です。全七巻からなり、作者は能役者の世阿弥(ぜあみ)です。 世阿弥の父である観阿弥(かんあみ)の教訓をもとに書かれたもので、下記の七巻の伝書からなります。略称を”花伝”や”花伝書”ともいいます。その高度な芸能論は現代のアーティスト達にも根強く愛されています。
| 【風姿花伝の構成】
|
1.風姿花伝第一 「年来稽古条々(ねんらいのけいこのじようじよう)」
|
|
|
|
2.風姿花伝第二 「物学条々(ものまねのじようじよう)」
|
|
|
|
3.風姿花伝第三 「問答条々(もんどうのじようじよう)」
|
|
|
|
4.風姿花伝第四 「神儀云(じんぎにいわく)」
|
|
|
|
5.第五 「奥義云(おうぎにいわく)」
|
|
|
|
| 6.花伝第六 「花修云(かしゆにいわく)」 |
|
|
|
7.花伝第七 「別紙口伝(べつしのくでん)」 |
|
|
|
「年来稽古条々」では7歳から50歳過ぎまでの年齢に応じた稽古の心得と説き、「物学条々」では男女の演じ分けや鬼の演じ方などが延べられています。「問答条々」ではその名の通り芸道上の心得が問答体で書かれているなど、芸道に通じる様々な事が全七巻に記されています。
風姿花伝の内容
この章では、風姿花伝の内容をピックアップしてご紹介します。
秘すれば花
高校古典の教科書にも出てくる「秘すれば花」の解説です。
原文
秘する花を知ること。秘すれば花なり、秘せずは花なるべからず、となり。
この分け目を知ること、肝要の花なり。そもそも一切の事、諸道芸において、その家々に秘事と申すは、秘するによりて大用あるがゆゑなり。しかれば、秘事といふことをあらはせば、させることにてもなきものなり。これを、「させることにてもなし。」と言ふ人は、いまだ秘事といふことの大用を知らぬがゆゑなり。まづ、この花の口伝におきても、ただ珍しきが花ぞと、みな人知るならば、「さては珍しきことあるべし。」と思ひまうけたらん見物衆の前にては、たとひ珍しきことをするとも、見手の心に珍しき感はあるべからず。見る人のため、花ぞとも知らでこそ、為手の花にはなるべけれ。されば、見る人は、ただ思ひのほかにおもしろき上手とばかり見て、これは花ぞとも知らぬが、為手の花なり。さるほどに、人の心に思ひも寄らぬ感を催す手立て、これ花なり。
現代語訳
秘密にする(ことで生まれる)花を知ること。秘密にすれば花であり、秘密にしなければ花になることはできない、ということなのだ。この(花となるか、ならないかの)分け目を知ることが、「花」について肝心・大切なところである。ところで全てのこと、もろもろの芸道において、その(それぞれの専門の)家々に秘密のことと申しあげるのは、秘密にすることによって大きな効用があるからである。
だから、秘事ということを明らかにすると、大したことでもないものなのだ。これを、「大したことでもない。」と言う人は、まだ秘事ということの大きな効用を知らないからである。
七歳
風姿花伝第一「年来稽古条々」の「七歳」です。
原文
一、この芸において、おほかた、七歳をもてはじめとす。
このころの能の稽古、必ず、その者、自然と為出だす事に、得たる風体あるべし。舞・はたらききの間、音曲、もしくは怒れる事などにてもあれ、ふと為出ださんかかりを、うち任せて、心のままにせさすべし。さのみに、よき、あしきとは教ふべからず。あまりにいたく諫むれば、童は気を失ひて、能、ものくさくなりたちぬれば、やがて能は止まるなり
。ただ音曲・はたらき・舞などならではさせすべからず。さのみの物まねは、たとひすべくとも、教ふまじきなり。大場などの脇の申楽(さるがく)には立つべからず。三番・四番の、時分のよからむずるに、得たらん風体をさせすべし。
現代語訳
一、能楽の稽古は、だいたい七歳の時分に始めるのが良い。
この頃の能の稽古というものは、ともかく自然に任せるという事が肝心である。どんな子でも、それぞれがやりたいようにやらせておくと、その自然に出てくるやり方の中に、必ず個性的な有様が見えてくるものだ。舞いや仕草の中に、また謡いにのせての所作はもとより、更には例えば怒気を含んだ鬼物の所作などの場合であっても、本人が何心もなく思いついて見せる動きなど、みなその子の好きなように、心のままにやらせておくのが良い。この時分には、「こうすると良い」とか「そうしちゃいけない」とか、事細かに教えるのはかえってよくない。あまり口うるさくあれこれと注意すると、子供というものはやる気をなくして、能なんて面倒くさいなぁと思って怠る心が出来るから、すなわちそこで能の進歩は行き止まりとなる。そうして、子供には、謡い、しぐさ、舞い、という基礎的な事だけを教えて、それ以上のことはさせてはいけない。子供の中には、もっと手の込んだ写実的演技などもさせれば出来る者もいるけれど、あえてさようなことは教えぬほうがよいのだ。格の高い大きな場所での脇能(初番の神能)のようなものには出演させてはいけない。
三番目の女の舞いを主眼とした能か、四番目の世話物の能あたりの、ちょうどよさそうな時分に、その子のもっとも得意とする役柄で出してやるのがよろしい。
十二・三より
風姿花伝第一「年来稽古条々」の「十二・三より」です。
原文
この年の頃よりは、はや、やうやう声も調子にかかり、能も心づく頃なれば、次第次第に物数(ものかず)をも教ふべし。まづ童形なれば、なにとしたるも幽玄なり。声も立つ頃なり。二つのたよりあれば、わろき事は隠れ、よき事はいよいよ花めけり。おほかた、児(ちご)の申楽(さるがく)に、さのみに細かなる物まねなどはせさすべからず。当座も似合はず、能も上らぬ相なり。ただし堪能(かんのう)になりぬれば、何としたるもよかるべし。児といひ、声といひ、しかも上手ならば、なにかはわろかるべき。さりながらこの花は、まことの花にあらず。ただ時分の花なり。さればこの時分の稽古、すべてすべてやすきなり。さるほどに一期(いちご)の能の定めにはなるまじきなり。この頃の稽古、やすき所を花に当てて、わざをば大事にすべし。はたらきをもたしやかに、音曲をも文字にさはさはと当たり、舞をも手を定めて、大事にして稽古すべし。
現代語訳
このくらいの年齢になれば、謡う声もだんだんと能の音階に合わせられるようになり、もう内容的な事もちゃんと理解出来る頃であるから、謡い、舞い、演技とも、順々に少しずつ数多くのことがらを教えてよい。なにぶんにも、華やかな稚児姿なので、何をどのように演じようとも華やいだ美しさがある。しかも、声もよく通るようになっている。この二つの美点があるのだから、欠点は目立たず、良いところはますます華やかに見えてくる。とはいえ、概してこうした稚児たちの申楽には、あんまり細密な写実演技などさせるものではない。そういうのは、目の当たりに見ていてもいっこうに似つかわしいとは思えないものだし、また将来上達がとまるもといである。ただし、この年代の子供の中には、どうかするととても達者になんでも出来る者がある。そういう稚児は、何をどう演じてもよろしかろう。なにしろ、姿はお稚児の華やかさ、声も朗々と響く、しかも上手に演ずる子とくれば、そりゃ何をやっても悪かろうはずがない。とはいいながら、この花は本物の花ではない。
言ってみれば、ちょうど良い年齢ゆえの花であるに過ぎないのだ。かかる花が備わっているからして、この時分の稽古はなんでも容易に出来てしまうところがある。だからといって、この時分の稽古で達成したことが一生の芸の格として身につくというわけでもない。したがって、この時分の稽古は、年齢相応のやりやすいところを舞台で華やかに見せるようにして、一方、一つ一つの基礎的な技を丁寧に稽古することが肝心である。すなわち、動作を確実にし、謡いは発音を正しく明瞭にするように心がけ、舞いも一つ一つの所作をきちんと守って、大事に大事に稽古しなくてはいけない。
十七・八より
風姿花伝第一「年来稽古条々」の「十七・八より」です。
原文
この頃は、またあまりの大事にて、稽古多からず。
まづ声変はりぬれば、第一の花、失せたり。
体も腰高になれば、かかり失せて、過ぎし頃の、声も盛りに、花やかに、やすかりし時分の移りに、手だてはたと変はりぬれば、気を失ふ。
結句(けつく)見物衆(けんぶつしゆ)も、をかしげなるけしき見えぬれば、恥づかしさと申し、かれこれ、ここにて退屈するなり。この頃の稽古には、ただ指をさして人に笑はるるとも、それをば顧みず、内にては、声の届かんずる調子にて、宵・暁の声を使ひ、心中には願力を起こして、一期の境ここなりと、生涯にかけて能を捨てぬよりほかは、稽古あるべからず。ここにて捨つれば、そのまま能は止まるべし。総じて調子は声によるといへども、黄鐘(おうしき)・盤渉(ばんしき)をもて用ふべし。調子にさのみかかれば、身なりに癖出で来るものなり。また声も、年寄りて損ずる相なり。
現代語訳
この年頃はまた、なんとしても難しい時期で、稽古をしすぎてはいけない。まず声変わりということがある。これによって少年期の艶めかしさは失せる。また体つきも、手足が伸びて変に腰高な風情になるので、見ていて不安定な感じがする為に第一姿が悪くなる。それまでは声も朗々として美しく、姿は華やかであってなんでも自在にできた時期であったけれど、そのあとでなにもかもがぱたっと一変してしまうわけだから、どうしてもここで気力が萎えてしまう。
その結果、見物の人たちも、ありゃ変だなあと思っているらしい様子がそれとなく分かるので、やっぱり恥ずかしいし、それやこれやでこの年齢の頃に挫折してしまう事が多い。だから、この時期の稽古は、舞台では指さしして嘲られることがあろうとも、それは気にかけないこと、そして家に帰ってからは、あまり無理な高声など使わずに、そこそこ届く程度の高さの声で、宵には十分に声を出し、朝にはちょっと控えめにして発声を整える。心の中に神仏かけての願力を奮い立たせて、おのれの一生の分かれ目はここだ、と覚悟し、これから先、生涯をかけて能を捨てずに精進するということの他には稽古の方法もないのである。そうして、この時期に諦めてしまったら、もうそれっきり能は行き止まりとなる。概して、声の高低は生まれつきで決まっているものだが、それでもおおかたの所を申すならば、この変声期の時期には「黄鐘(おうしき)・盤渉(ばんしき)」あたりまでの所の声を使うのがよろしい。調子にこだわって無理に高い声などだそうとすると、その為に体つきに妙な癖がついてしまうことがある。さらには、声帯を傷めて後に中年以後に声が出なくなるというようなことも出来(しゅったい)するので、くれぐれも無理は禁物である。
二十四・五
原文
この頃、一期の芸能の定まるはじめなり。
さるほどに、稽古の堺なり。
声もすでに直り、体も定まる時分なり。
さればこの道に二つの果報あり。声と身なりなり。
これ二つは、この時分に定まるなり。
年盛りに向かふ芸能の生ずる所なり。
さるほどによそ目にも、すは、上手出で来たりとて、人も目に立つるなり。
もと、名人などなれども、当座の花に珍しくして、立合勝負にも一旦勝つ時は、人も思ひ上げ、主も上手と思ひしむるなり。
これ、かへすがへす主のため仇なり。
これもまことの花にはあらず。
年の盛りと、見る人の一旦の心の、珍しき花なり。
まことの目利きは見分くべし。
この頃の花こそ初心と申す頃なるを、極めたるやうに主の思ひて、はや申楽にそばみたる輪説(りんぜつ)とし、至りたる風体をする事、あさましき事なり。たとひ人も褒め、名人などに勝つとも、これは一旦、珍しき花なりと思ひ悟りて、いよいよ物まねをも直ぐに為(し)定め、なを得たらん人に事を細かに問ひて、稽古をいや増しにすべし。
されば時分の花をまことの花と知る心が、真実の花になほ遠ざかる心なり。
ただ人ごとに、この時分の花に迷ひて、やがて花の失するをも知らず。
初心と申すは、この頃の事なり。
一、公案して思ふべし。
わが位のほどをよくよく心得ぬれば、それほどの花は、一期失せず。
位より上の上手と思へば、もとありつる位の花も失するなり。
よくよく心得べし。
現代語訳
このころ、一生の芸能の位が定まる、ちょうどその分れ目の所に当たっている。
だから、稽古もここが肝心かなめの所である。
変声期は既に終わり、体も安定してくる。
しかるに、能という芸能にとっては、二つの幸いがなくてはならぬ。
声と体の二つである。この二つはまさにこの時期に善し悪しが定まると言ってよい。
そうして、これから段々に全盛期に向かっていく本格的芸能の生まれてくる時期がこの頃なのだと言うことが出来るであろう。さあ難しいのはここである。
なにしろこの時期には、第三者から見ても「ややっ、これは上手な役者が出てきたぞ」というような事になって、やたら称賛を浴び、人目に立つということがある。
その為に、たまさか名人と呼ばれるような人と能の立会い菖蒲をして、若造のくせに勝ったりする事もある。これはしかし、叙上の意味でかりそめの物珍しさの魅力で勝っただけなのだが、それでも廻りはチヤホヤするだろうし、勝った本人はすっかり舞い上がって、己はもう上手の位に上がったのだと思いこんでしまう。これは返す返すも本人の為にならぬ。この時分の魅力というものもまた、まことの花ではない。若盛りの美しさと、まだ物珍しさが見るほうにあるための、かりそめばかりの魅力なのだ。そのところを、本当に目の利く人はちゃんと見分るであろう。
この時期の花こそ、芸道にとっては、ようやく「初心」という程度のことなのであるが、もういっぱし芸を窮めたようなつもりになってしまう者もいて、申楽を演ずるにもなにやら変則的なやり方で演じて見せたりして、いわゆる名人気取りの様子をすることは、これまことに浅ましいことと言わねばならぬ。それでたとい人も褒め、立会いの勝負で本当の名人に勝つことがろうとも、それはほんの一時の「物珍しさの魅力」なのだと自らに思い定めて、ますますまっすぐに定式通りの写実演技をするように励み、より高い芸格の役者衆にあれこれと細かなところまで教えを乞い、稽古はさらにいや増しに尽すのがよい。すなわち、こういうことである。一時かりそめの花をほんとうの花だと思いこんでしまう心が、真実の花に遠ざかる心である。そんなふうにして、誰もかれも、この一時かりそめの花を褒められて有頂天になる結果、すぐにその花は失せてしまうのだということも悟らない。「初心」というのは、子供時代のことでない。まさにこの人も褒める若盛りのことなのである。
一、各自内省熟慮して思うべきことがある。
己の芸の格をよくよく心得て勘違いしないようにしていれば、それ相応の花は一生のあいだ失せることがない。しかし、慢心して相応の位よりも上手なのだと思い込んだら最後、それまで持っていた花もすべて消え失せてしまうのだということである。
このあわいをよくよく思っておかなくてはならぬ。
三十四・五
風姿花伝第一「年来稽古条々」の「三十四・五」です。
原文
この頃の能、盛りの極めなり。
ここにて、この条々を窮(きわ)め悟りて、堪能になれば、定めて天下に許され、名望を得つべし。
もしこの時分に、天下の許されも不足に、名望を思ふ程になくは、いかなる上手なりとも、いまだまことの花を窮めぬ為手(して)と知るべし。
もし窮めずは、四十より能は下がるべし。
それ、後の証拠なるべし。さるほどに、上がるは三十四・五までの頃、下がるは四十以来なり。
返すがへす、この頃天下の許されを得ずば、能を窮めたりととは思ふべからず。ここにてなほ、慎むべし。この頃は、過ぎし方をも覚え、また、行く先の手立(てだて)をも覚る時分なり。この頃極めずば、こののち天下の許されを得ん事、返すがへすかたかるべし。
現代語訳
この年ごろの能は、あらゆる意味で全盛で窮める。したがって、この時期に至って、この伝書に書きおく条々をよくよく悟得(ごとく)して、行き届いた芸域に達するならば、かならずや天下の見巧者にも認められて、芸能者として一流の名を得るであろう。反対に、もしこの時期になっても、天下の見巧者には認められず、その結果大した名声も得られないのであれば、一見いかに達者に芸をするように見えても、それはいまだ「真実の花」を会得しているシテ(役者)とは考えがたい。そうして、もうこの年ごろが絶頂の時期なのだから、もしこの頃までに「真実の花」を会得し得なかったならば万事休す、四十を過ぎてからどのように芸が堕ちていくかということを見れば、その者が真実の花を会得していたか否かが分かるというものである。というわけであるから、芸の力が進歩向上するのはせいぜい三十四・五までのこと、そして芸が衰え始める境目が四十のころなのだ。
くれぐれも言っておくが、だからこの三十四・五のころまでに天下に名声を確立出来なかった者は、ゆめゆめ能を窮めたなどと思ってはいけない。この時期には、なお一層自省熟慮しなければならぬことがある。すなわち、自分がそれまでに学んできたあれこれの事を反省し、またこれから先どのような方法で進んでいくべきか、そのことをよく考えるべき時だという事である。重ねて言っておくが、この時分に芸を窮め真実の花を会得していなかったならば、これから先どんなに頑張っても天下に名人の名を許されることはまずありえないのである。
四十四・五
原文
この頃よりは、能の手だて、おほかた変はるべし。
たとひ天下に許され、能に得法(とくほう)」したりとも、それにつけても、よき脇の為手(して)を持つべし。
能は下がらねども、力なく、やうやう年たけゆけば、身の花も、よそ目の花も失するなり。
まづすぐれたらん美男は知らず、よきほどの人も、直面(ひためん)の申楽は、年寄りては見られぬものなり。さるほどにこの一方は欠けたり。
この頃よりは、さのみに細かなる物まねをばすまじきなり。
おほかた、似合ひたる風体を、やすやすと、骨を折らで、脇の為手に花を持たせて、あひしらひのやうに、少な少なとすべし。
たとひ脇の為手なからんにつけても、いよいよ、細かに身を砕く能をばすまじきなり。
なにとしても、よそ目、花なし。
もしこの頃まで失せざらん花こそ、まことの花にてはあるべけれ。それは、五十近くまで失せざらん花を持ちたる為手ならば、四十以前に天下の名望を得つべし。たとひ天下の許されを得たる為手なりとも、さやうの上手は、ことに我が身を知るべければ、なほなほ脇の為手をたしなみ、さのみに身を砕きて難の見ゆべき能をばすまじきなり。
かやうに我が身を知る心、得たる人の心なるべし。
現代語訳
この年ごろからは、能の演じ方ががらりと変わるはずである。
たとい天下に名人の声価を許されて、実際に能の奥義を得悟したとしても、大切なことは、良い助演者を持つということである。前段に言った「真実の花」を会得した名人ともなれば、そうやすやすと技量が下がっていくこともあるまいけれど、ただ年齢というものはいかんともしがたいところであって、だんだんに高齢になっていくにしたがって、身体的な華やぎも、また観客から見た魅力も失せていくのは、避けられない。たとえば、ともかく抜群の美男などは別として、相当の姿よき人であっても、面を掛けずに素顔で演じる演目(直面の能)は、年寄ってからはとうてい見られたものではない。
ということは、すでにこの直面の能という一分野は欠けてしまったということである。
だから、この年齢になってきたら、むやみと細密な写実の演技などはするものでない。
だいたい自分に似合った風体の曲を、さほどな苦労もせずして、さらりさらりと演じつつ、むしろ若い助演者に花を持たせて、自分のほうがかえって助演者みたいな感じで内端(うちわ)内端に演じるのがよろしい。もし優れた助演者が得られないとしても、だからといって、年がいもなく、俊敏に動き回り身を砕くような演目をやるべきでない。
自分ではちゃんと出来ているつもりでも、観客のほうから見れば、なんとしても見た目の花が無くなっているのだから。とはいいながら、本当の名手ならば、この年齢になってもなお見どころ魅力が十分残っているはずで、その失せないで残っている花こそが、本当の花であるにちがいない。
こうした場合、五十近くまでなお残っている花を持っているシテならば、必ずやすでに四十以前に天下の名人の名を許されているはずのところである。そうしてさように天下に名声を得た演者となれば、なおのこと、己というものを良く心得ておいて然るべきものであって、普通の人よりもいっそう十全に助演者を吟味して、その若いものに任せるべきところは任せ、自分はさように身を砕くような写実演技などをして身の衰えを露見せしめるようなまねをするべきでない。
つまり、そういうふうに、己の身の状態をきちんと認識して、今何をすべきかを知る人が、真の芸を会得した本当の名手というべきものである。
五十有余
風姿花伝第一「年来稽古条々」の「五十有余」です。
原文
この頃よりは、おほかた、せぬならでは手だてあるまじ。
「麒麟も老いては弩馬(どば)に劣る」と申す事あり。
さりながらまことに得たらん能者ならば、物数はみなみな失せて、善悪見どころは少なしとも、花は残るべし。 亡父にて候ひし者は、五十二と申しし五月十九日に死去せしが、その月の四日、駿河国浅間(せんげん)の御前にて法楽(ほうらく)つかまつり、その日の申楽、ことに花やかにて、見物の上下、一同に褒美せしなり。
およそその頃、物数をばはや初心に譲りて、やすき所を少な少なと、色へてせしかども、花はいや増しに見えしなり。これ、まことに得たりし花なるがゆゑに、能は、枝葉も少なく、老木になるまで、花は散らで残りしなり。
これ、目のあたり、老骨に残りし花の証拠なり。年来稽古 以上。
現代語訳
こういう年齢になったら、およそ、「何もしない」ということ以外にはこれという手だてもあるまい。
「麒麟も老いては駑馬に劣る」ということわざがある。それはいかんともしがたい現実ではあるが、とは申しながら、真実奥底深く能を会得した者ならば、次第に演じる曲目も技ももうすっかり失せに失せて、いかにも見どころが少なくなってしまっていたとしても、それでもなにがしかの「花」は残っているであろう。亡父観阿弥と申すものは、五十二歳という年の五月十九日に死去したが、その同じ月の四日の日に、遠く駿河の国、浅間神社の宝前で奉納の能を奉った。
その日の申楽能は一段と華やかで、見物の皆々身分の高きも賤しきも等しくこれを称賛したということがある。亡父は、およそその頃には、もうあれもこれもほとんどの演目を私ども若いものに譲ってしまって、自身は体に無理のないところを、動きは内端に内端に舞いながら、しかし、しっとりとした彩りを込めて演じたので、老いてなお花はいよいよ盛りに見えたものであった。この花は、亡父がまことに会得した真実の花であったために、実際の動きは最小限で、あたかももう枝も葉も少なくなった老木のようになっていても、それでも花は散り失せずに残っていたのである。これが、私が目の当たりにした「老いてなお残っていた花」のなによりの証拠である。
年来の稽古については、以上である。 |
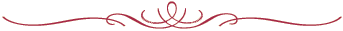
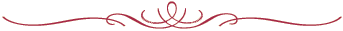
![]()
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)