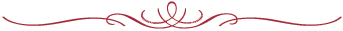
| 前編第1の3(10から12) |
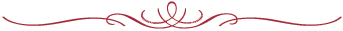
更新日/2021(平成31.5.1栄和改元/栄和3)年.7.16日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここで、「暗夜行路前編第1の3(10から12)」を確認する。 2021(平成31.5.1栄和改元/栄和3)年.7.16日 れんだいこ拝 |
![]()
| 【暗夜行路前編第1の3(10から12)】 |
| 十 |
| 半月ほど、つけ怠っていた日記に謙作はこんな事を書いた。この考えはこの間中(あいだじゅう)から漠然彼の頭に往来していた考えであった。実際、彼には今の人間が総て何かはつきりしない目的の為に焦りぬいているように思われた。何か知れない大きい意志に追い立てられている。芸術でも宗教でも科学でも総てにこれが種々(いろいろ)な形で現れている。そう思われた。彼は現在の自身に就いてもそう感じられた。謂われなく苛々と焦り立つ時に彼は何かそういうものに追い立てられるのを感じた。彼は亢奮から部屋の中を歩き廻っていた。 「謙さん。謙さん」。段々の下でお栄の声がした。「お昼はどう?」。彼は一寸夢から覚めたように感じた。朝寝の習慣から謙作は大概朝と昼とを兼ねた食事をしていた。しかしその日は信行に起され、珍しく九時前に朝飯(あさはん)を食っていた。「そうだな」と、彼は少し不機嫌に云った。「空いてもいないが、行きましょう」。暫くして彼は階下(した)へ降りて行った。食事中、お栄は「不良少年なんて、一人で出掛けて心配ないの? 竜岡さんに一緒に行って頂く方がよかないの?」と心配そうに云った。彼はそうそうと思った。そして、「大丈夫です。不良少年というほどでもなさそうだし」と云いながら、しかし先の出ようでは割りにかっとする性質の自分に一寸不安を感じた。食過ぎたので、彼は消化剤を飲んで、そして二階へ上がると、机の下にあった籐(とう)の紙屑籠を枕にして、横になった。亢奮し過ぎた後の淋しい気分が来た。 間もなく宮本が来た。「竜岡さんの送別会は何処がいいかね。早く決めないともう日がないから」と云った。宮本がその世話をする事になっていた。「まだ決めてないのか?」。謙作は非難するように云った。「一週間ないじゃないか。何処でもいいから、竜岡の空いている日を聞いて、早く決めたらいいじゃないか」。「日は聞いてあるんだよ。だけど場所がまだ決まらないんだ。清賓亭とか西緑とか、そう云う家でない方がいいだろう?」。宮本は少し気をひくように云った。「無論、そんな家でない方がいい」。「そう。そう君に聞けば安心なんだよ」と宮本は笑い出した。「ああいう家も悪くはないが、送別会は一寸いやだろう? でも君達に無断でよしちゃあ悪いような気がしたから」。二人は笑った。「僕は富士見軒か三縁亭にしようと思っているんだ。料理はどうだか知らないが、何となく昔の洋行のようでいいだろうと思うんだ。それから写真屋も少し旧い家でね、富士見軒なら武林(たけばやし)か何かを呼ぶといいと考えてるんだ」。宮本は彼ら仲間での所謂趣味家だった。 謙作は妹に手紙を寄越した青年のある事を話した。「一緒に行って見る気はないかい?」。「可恐(こわい)。もしピストルでも出された日にはこれだからね」と宮本は両手を挙げて見せた。「そんなら待ってたまえ」。二時になった。丁度雨は止んでいたが、謙作は蝙蝠傘(こうもりがさ)を突いて一人、二三町離れた氷川神社へ出かけて行った。常には近所の子供の遊び場だが、雨で、今日は一人もいなかった。只神楽堂の裏に二十二三の顔色のよくない痩せた若者が石に腰かけ、この寒空に薄汚れた白がすり一枚で身を縮め、物怯(ものお)じしたような眼で謙作の方を見ていた。「あれではない」。そう思いながら謙作はその辺を一通り歩いてみた。額堂(がくどう)に茶店を出している男が、客がないので床几(しょうぎ)を積み重ねていた。その他は誰も居ない。彼は暫く、ぶらぶらと歩いていた。時々境内を通り抜けて行く人があった。しかしそれらしい男は来なかった。 その内不図、やつれはてた清玄の連想から、彼はその見すぼらしい若者をもしやと云う気になった。信じたほけではないが、先刻から同じ処に凝っとしている。その様子が人を待っていると見れば見られる気がしたからであった。彼は若者の方へ行ってみた。大きな銀杏があって、濡れた地面へその黄色い葉が落ち散っていた。彼は蝙蝠の先で銀杏の落ち葉を一つ一つ刺しながら二三度若者の前を往ったり来たりした。若者は不安そうに、時々眼だけで彼の方を見た。 到頭謙作は前へ行って、「誰か待ってるのか?」と訊いてみた。若者は直ぐ返事ができない程の恐怖を現わした。その急にキョトキョトし出した様子で、謙作は矢張りこの男だな、と云う気になった。「何故、此処に居るんだ」。「まま待って---」と息を切らしながら、頭を振る事で後をおぎないながら、「いるんじやない」と漸く続けた。自然に身体が震えている。眼がおびえ切っていた。二寸くらいに延びた薄い髪の毛は栄養不良から、まるで光沢(つや)がなく、手や足の皮膚はカサカサになって、白い粉を吹いていた。「家はあるんです。箪笥町十九番地です」。若者は謙作の怒ったような顔を凝っと見上げながら、あえぎあえぎ云った。そして殆ど無意識に親指のささくれをむしり出した。ささくれからは血がにじみ出ていた。それでも痛さを感じないように尚無闇とむしつた。若者は浮浪罪に問われる事から、すつかりおびえて了ったのだ。謙作を刑事と思ったのだ。「失敬しました」。こういって謙作は一寸頭は下げたが、まだ怒ったような顔をしていた。 彼は鳥居の側(わき)へ来て立っていた。謙作は若者が恐る恐る神楽堂の裏からそっと此方を覗いているのを見た。十八九の学生らしい若者が帽子も被らず着流しで、本を一冊持って、時々それを見ながら歩いて来た。何か暗記物をしている風だ。謙作はこれかなと思った。暗記物をしている風を粧(よそお)って、誰か他の人の来る場合に用心しているのかも知れないと思った。じろじろ見ているので青年の方でも拘泥していた。訊いて見るより仕方がないと思って彼は近寄って行った。前で凝りていたから今度は丁寧に云った。「失礼ですが、君は人を待っているんですか?」。青年は至極穏やかな顔をしていた。そして、「いいえ」と答えた。生意気なところがなく如何にも良家の子弟らしかった。「そう」。謙作は頭を下げた。 とにかく、三時まで待つ事にして、額堂の茶店へ入った。そして毛布も何も掛けてな積み残しの床几に腰を下ろしたが、茶店の主は客扱いにする気がないらしく、「いらっしやい」と云って、そのままの溶岩を組み合わせて作った庭石の間に散り込んだ落ち葉を草箒(ぼうき)で丹念に掃き出していた。謙作は秋らしい静かな気持ちになって、煙草を吸っていた。手紙の主と会うには丁度いい気持ちだと思った。三時まで待って、来なかったら帰るつもりで、時々時計を見ていた。先刻の見すぼらしい若者はまだ腰かけている。血が出るまでに無闇とむしったささくれが痛んでいるだろうと思うと、何とか云って慰めてやりたい気がした。しかし何故あんな風に何時までも凝っとしているのかしら。病人でもない、乞食でもない若者が十一月の寒い日に白地の単衣(ひとえ)一つであんな事をしている。そういう人の生活が彼には一寸見当がつかなかった。 余り長くいるので、茶店の主は茶と菓子を持って来た。もう来そうもない、そう思って彼は智や題を置いて立ち上がろうとした時に石段をあがって来るお栄の姿が見えた。何という事なし両方で微笑した。「此方から帰りましょう」。彼は直ぐ往来へ出られる小さい門の方へ足を向けた。彼は一寸先刻の若者に言葉をかけて行きたい気がしたので、その方へよって行くと、若者は急に首根を堅くして、顔を反向けて了った。謙作は言葉をかける事をやめ、そのままお栄と一緒に往来へ出た。「先が分かっているのだから手紙で云っておやりなさい」。「そうしましょう」。 帰ると直ぐ彼は宮本に待って貰って手紙を書いた。松山とは子供からの友達だと云うような事も書いて置いた。宮本は不意に、「不良少年もいいなあ。不良少年になろうかしら」と云って笑い出した。謙作も釣られて一緒に笑ったが、何だか不快な気がした。宮本が不良少年と云う言葉を使って自分たちに共通な一つの要求を露骨な調子で指摘したような気がしたからである。 又霧のような雨が降り出した。二人は将棋をさした。そして五六度さして、もう疲れ盤の上も薄暗く、少し不愉快になった時に電気が来た。暫く考えて、いい考えも出ずにいた謙作は「よそうか」と云った。「よそう」。宮本も直ぐ手の駒を盤の上へ投げ出した。そして倒れるようにそのまま仰向けに寝てしまった。用意ができていたので、食事を済まして、二人は直ぐ戸外へ出た。謙作は風邪をひきやすかったから、二重廻しを抱えて行った。溜池から電車に乗って、新橋から銀座へ出た。街燈と並んで立った柳の細い枝が風に揺られながらキラキラと美しく光っていた。 宮本は袋物に興味を持って、そういう店の前へ来ると、必ずショウ・ウィンドウに額をつけ、根気よく眺めた。「近頃は荒物趣味の方はどうだい?」。「勿論あるよ」と宮本は答えた。袋物は本統に凝った物だと、どうしても古物で、前にどんな奴が使ったか知れない物だから、よくても或る意味では甚だ不潔だが、荒物の方はどれもこれも新しく安く、その割に趣味があって清潔だからいい。よごれたら直ぐ捨てて惜しくないところもいい。歩きながら宮本はこんな説をはいていた。「今度の旅でも大分(だいぶ)買って来た。その内朝鮮へも行こうと思うんだ。朝鮮のは中々いいんだよ」などと云った。 台湾喫茶店の前を通る時、謙作は何となく緒方が居そうな気がした。そして実際奥の方に帽子のふちを下ろし、雨外套(あまがいとう)を着たままのその姿を見た。「緒方がいる」と注意すると、宮本は少し後もどりして入口から近視の眼を細くして見ていた。「寄ろうか」。「よそう。蜘蛛猿が来てるよ。それより緒方さんを呼び出そうよ」。そう云って宮本は給仕女に緒方を呼び出して貰った。出て来た緒方は直ぐに承知した。そして又入って、ステッキを取って出て来た。三人はそのまま京橋の方へ歩いた。「君は蜘蛛猿が嫌いなのかい。謙遜ないい奴じやないか」と緒方がいった。「別に嫌いでもないがネ。何だか閉口じゃないか」。「どうも君達は一体に気難しくていかんな」。尾張町の乗換場(のりかえば)へ来た時、「あすこはどうだい?」。緒方は向う側のカッフェを指した。「蜘蛛猿より閉口なのが居そうだな」と又宮本がいった。「どうしたんだい。大変気難しいんだネ。酒はいやかい?」。「酒はいいんだよ。だけど、何だか急に人が可恐(こわ)くなっちゃって---」と宮本は笑った。「人が居なくて、酒だけあるとこなんかないね」。結局、引き返して清賓亭へ行く事にした。 二階の小さい室(へや)のカーテンを下ろし、三人は其処へ落ち着いた。お鈴は階下(した)の掛りで余り出て来なかった。其処にはお加代の他にお牧という余り美しくない女中がいた。謙作はその日割に靜かな気持ちでいた。酒を飲むのもいやだった。お加代も幾ら緒方が勧めても飲もうとしなかった。「理由(わけ)があって、お酒は断っちゃったのよ。---本統に散々叱られちゃったわ」。そう腹立たしそうに附け加えた。「又お酒で失策(しくじり)をしたんですの」。「又なんて、ひどいよ、お前(まい)さん」。お加代は多少下品な調子でいって、お牧の肩を突いた。そして、「出世前の者はお酒なんか飲むもんじゃないのよ」と独りで云った。 謙作は前日自家(うち)で不図お加代が一皮眼か二皮眼かというような事を考えて、それを緒方への端書の端に書いてやった、それを憶い出した。ところがそれと同時に緒方がその事を云い出した。「おいおいお加代さん。時任がね、君の眼が一皮か二皮か考えたそうだよ。一寸見せてやり給え」。今まで少しむっとしていたお加代は急に媚びるような眼をして謙作の方を向いた。「両方あるのよ。ね、此方が一重(ひとえ)でしょう? 此方が二重(ふたえ)」。「あべこべだ」。「おや、そうかしら」。お加代は指の先で眼瞼(まぶた)を擦(さす)りながら、眼をぱちぱちさした。「そうだわ」。そしてお加代はもう一度、嬉しそうな変に誘惑的な眼を向け、黙って、微笑した。居ない所で一皮か、二皮かを考えたと云う事は偶然効果の多すぎるお世辞になっていた。 しかしその夜(よ)はとかく話が絶えがちだった。謙作は氷川神社へ行った時の話をしようかとも思ったが、後で客との話の種にされても困る気がしてやめた。皆が黙っていると、お加代とお牧は勝手に自分達の話をしていた。「ほら、運送屋の横丁さ」。「運送屋って、あのいい男の坐ってる家かい?」。「ああ」。こんな事をいつていた。「怪しからんな。いい男がどうしたんだい」。緒方は興味のない気持ちで無理にそんな事をいった。お加代は直ぐ剣突(けんつく)らしく答えた。「いい男の話じやない事よ。いい男のいる横丁の話しよ」。「横丁なら尚怪しからん」。緒方は出鱈目を言って、つまらなさそうに笑った。「この辺はそりゃあ、いい男が多いんですよ」とお牧が云った。「つまり君達の岡惚れだな」。「Оさん、この間ね」といってお加代は笑い出した。「お清さんが露月町(ろげつちょう)の方にそれはそれはいい男の散髪屋さんが居るって云うのよ。それを又、よくきかずにこの人と出かけちゃったものよ。ところがどうしても家が知れなくて、一軒/\散髪屋を覗いて歩いちゃった---」。女二人は横眼を見合わせ、顔を真っ赤にして笑った。その時のお加代の顔には、変に下等な感じが出ていた。謙作は或る不安から宮本の方を見た。宮本も謙作の方を見ていた。その顔には意地悪いような同情するような笑いを浮かべていた。 お加代とお牧は図に乗って界隈の「いい男」の噂を始めた。運送屋の番頭もその一人だった。八百屋の息子と云うのもあつた。自動車の運転手と云うのもあつた、それを聴きながら宮本は露骨ににがにがしい顔を女達に見せていた。お加代は毎日昼前十時頃銭湯に行くと丁度空(す)いている時で、誰もいないと両方に留桶(とめおけ)を抱えてよく泳ぐというような話をした。「この人はそりゃあ上手なんですよ」と傍からお牧が云った.肉づきのいいこの大きな女が留桶を抱えて風呂の中で泳ぐ様子が謙作には可成り不格好な形で想像された。そしてその不格好さがいやに肉感的に感じられた。お加代は瓦斯会社の工夫が大きな脚立(きゃたつ)を流しへ持ち込んで、損じた瓦斯燈が直ってからも何時までも愚図/\しているので湯槽(ゆぶね)を出られなかったというような話を自身でも興味を持って話していた。謙作は最初からお加代を品のいい女とは考えなかった。只投げやりな生き生きとしたところや、変にコケティッシュなところなどに惹きつけられていたが、今日の事がある。そしてその余りに安価な感じから、すつかり気持ちを冷やされた。近寄れば近寄るほどこの感じは強くなりそうに思われた。この点では初めて会った時が一番よかった。 間もなく三人は其処をでた。そして直ぐ別れ別れに家へ帰った。翌日起きると、前日出した手紙の返事が来ていた。平詫(ひらあやま)りに詫った手紙だった。実は御妹様は写真で拝見したばかりで、自分にはそれほどの考えはなかったのですがT病院の看護婦〇〇に勧められてあんな手紙を差し出しました。もしこの事が松山様に知れでもしましたら私一身にとり由々しき事に相成るべく御慈悲を以て何卒/\御海容下されたく云々。T病院というのには一年程前咲子が入っていた事がある。そしてその看護婦は謙作も覚えている。一寸美しい女だった。謙作は簡単に前日の事を書き、その手紙を同封して信行へ出した。そしてそのお男へは松山には決してに云わないと云う約束をした手紙を出してやった。 |
| 十一 |
| 謙作が自分から放蕩(ほうとう)を始めたのはそれから間もなくであった。或る曇った薄ら寒い日の午前の事だ。彼は現在に少しもそう云う衝動なしに、寧ろ決めた事を決行するような心持で、深川のそう云う場所に一人で出かけて行った。その二年ほど前に木場(きば)からその辺、それから砂村を通って中川べりに出た事がある。それ故、道は大概分かっていた。彼は永代橋を少し行った所で電車を降りると、沈んだ不愉快な顔をしながら八幡前の道を歩いて行った。どれほど陰鬱な、そしてどれほど醜い顔つきであるか、自身でも感じられた。道行く人が皆、彼の目的を知っているように彼には思えた。彼はそれらの人々に淡い一種の敵意さえ感じた。そして急いだ。時々空つばを呑み込み彼は急ぎ足で歩いて行った。幾つ目かの小さい橋を渡って右へ折れると直ぐ、泥をへだててむそういう家々が見えた。彼は今更に到頭来たと思った。登喜子のいる場所へ行く時とは目的が異うだけに彼の気持ちはぎごちなかつた。寧ろ非常に不愉快だった。それでいながら、中止しようと云う気にはならなかった。 彼方(むこう)から前どよなしに母衣(ほろ)だけをかけた車が来た。その上の人が黒眼鏡をかけていた。それが却って彼の注意を惹(ひ)いた。田島という彼よりも三つ上の級にいた男で、こう云う場所で会うにしてはその職業からも誠に思いがけない人だった。謙作は一寸迷った。二三間歩く間彼はその男から眼が放せなかった。彼方でも見ているらしかったが、眼鏡の中でよくわからなかった。間もなく彼は眼を反(そ)らした。その道は先の養魚場でなければ、曲輪(くるわ)からの一本道だった。無論曲輪から出て来たのだと彼は思った。普段使わない黒眼鏡で尚そう思われた。これはお互いにいやな所を見たものだと思った。彼は苦々しい、腹立たしい気持ちになった。しかし自分はまだ中へ入っているのではないと思った。このまま養魚場を抜けて砂村の方へ出て了えば、それとも西緑のような家へ行ってそのまま帰って了えば、というような考えも一寸浮んだ。しかしそれは田島が曲輪を出て来たのではない場合はいいとしても、それを知りつつそういう事をするのは何かしら卑劣な気がした。そして、どうせ今日入らないにしろ、屹度自分は又来るに違いないと彼は思った。 二時間ほどして彼は往(ゆ)きとは全く異った気持ちで曲輪を出て来た。自身でも不思議なほど気安い気持ちだった。悔ゆるというような気持は全くなかった。女は醜い女だった。青白くて、平ったい顏の、丁度裏店(うらだな)のかみさんのような女だった。実に鈍く善良な女だった。彼はもう二度とその女を見たいとは思わなかったが、何かで、これからも好意を示したい気が仕切りにした。為替(かわせ)で寄付金をしてもいいと考えた。女は一人の客毎に雇い主から五銭ずつを受取るのだと云う事を彼は聞いた。 彼は放蕩を始めてから変にお栄を意識しだした。これは前からも無い事ではなかったが、彼の時々した妙な想像は道徳堅固にしている彼に対し、お栄の方から誘惑して来る場合の想像であった。その想像では常に彼はお栄に説教する自分だった。そう云う事が如何に恐ろしい罪であるか、その為に如何に二人の運命が狂い出すか、そんな事を諄々と説き聴かす真面目臭い青年になっていた。しかも、そう云う想像をさす素振りがお栄の方にあったわけではなかったが、彼は時々そんな風な想像をした。 それがこの頃になって変って来た。夜中悪い精神の跳梁(ちょうりょう)から寝つけなくなると、本を読んでも読んでいる字の意味を頭が全(まる)で受け付けなくなる。只淫蕩な悪い精神が内で傍若無人に働き、追い退けても追い退けても階下に寝ているお栄の姿が意識へ割り込んで来る。そう云う時彼は居ても起ってもいられない気持ちで、万一の空想に胸を轟(とどろ)かせながら、階下へ下りて行く。お栄の寝ている部屋の前を通って便所へ行く。彼の空想では前を通る時に不意に襖(ふすま)が開(あ)く。黙って彼はその暗い部屋に連れ込まれる。---が、実際は何事も起らない。彼は腹立たしいような落ち着かない気持ちになって二階へ還(かえ)って来る。しかし、段々の途中まで来て又立ち止まる。降りて行こうとする気持ち、還ろうとする気持ちが彼の心で撃ち合う。彼は暗い中段に腰を下ろして、自分で自分をどうする事もできなくなる。 彼の放蕩は少しずつ烈しくなつて来た。その癖気持ちは少しも所謂放蕩者らしくならなかった。そうなれないところに放蕩しながら常に不愉快がついて廻った。本統に夢中になれる女がいそうに思いながら、彼は却々(なかなか)そう云う女に出会わなかった。一寸そんな気持ちになっても常に長持ちしなかった。自分も悪いし、対手(あいて)も悪いのだと彼は考えた。登喜子やお加代のいる所へも前ほどは行かなくなったが、それでも緒方や宮本と一緒になるとよく行った。登喜子に対しても或る落ち着きからは進みも退きもしなかった。寧ろ進む事が段々困難になった。 或る程度に執着する事はあっても、それは登喜子の場合のように、或いはお加代の場合のように、されでなければ又他の場合のように、彼の気持ちはいつも逸れて行った。手軽く深入りできる女は別として、そうでない女では或る程度に深入りしてからなら却って夢中になれそうに彼には思えた。しかし執着すると妙に、彼は深入りしようとかるにはそれ程の熱情が自分にないという気がした。これでは何時まで経っても駄目だと思っても、そう思って敢えて進めるのは如何にも図々しいような、不自然なような気がした。感情が一番先立ちになっていてくれなければ、彼ではそれは不自然だった。誰とも夢中になれそうもないと思うと、時々彼は自己嫌悪に陥入った。しかしそんな気持ちでいながら、身体だけは、彼は益々放蕩の深みへ堕として行ったのである。 生活が乱れるにつれ、頭が濁って来るにつれ、彼のお栄に対する悪い精神の跳梁は段々烈しくなった。彼はこのままの状態を続けて行ったら、自分達はどうなる事か知れないという気がした。殆ど二十も年の違う、その上祖父の長い間の妾(めかけ)だったお栄とのそう云う関係は何かの意味で自分を破滅に導くだろうと云う考えの前に彼は立ちすくんだ。彼のお栄に対する衝動は、それは悪夢のようなものだった。白昼、気楽な気持ちで対坐している場合、そんな気持ちになる自分が不思議な気がした。そして悪夢でなくて何であろうと思われるのだ。が、実際ではその悪夢は段々頻繁に彼を襲った。 或る夜彼は夢を見た。寝ているところに宮本が変な笑い顔をして入って来た。そして、「阪口が旅先で死んだよ」と云った。謙作は寝たまま、「ああ到頭死んだか」と思った。阪口が誰にも知らさず、家出同様に一人旅に出た事を夢として彼は知っていた。そして、彼は阪口が旅先でそういう死に方をしそうな気が何だかしていたのだ。彼が黙っていると、「播摩(はりま)をやったんだそうだ。---到頭やったネ」と重ねて云って宮本は妙な笑い方をした。「やはりそうか」と謙作は思った。播摩とはどう云う事をするのか彼は知らなかった。しかしとにかくそれは命がけの危険な方法で、阪口はそれを以前大阪で教わって知っていると云う事だけを彼は知っていた。そして宮本は阪口から聴いて知っている筈だった。 阪口は淫蕩の為にはあらゆる刺激を求めて来たが、到頭その播摩まで堕ちたかと思うと謙作は身内が寒くなるような異様な感動を覚えた。播摩の恐ろしい事を百も千も承知の上で、遂に其処まで突き詰めた阪口の淫蕩は彼の自由意思の外(ほか)のものだったに違いないと思われた。「播摩と云うのはどうするのだ」。謙作はもう少しでこう訊きかけて口を噤(つぐ)んだ。聴けば屹度自分もやる。この考えでぞっとした。死なずに済むかも知れない。しかし大概は死んで了う。こう云う恐ろしい方法でも、百に一つ、千に一つ死なずに済む機会が与えられてある以上、悪い精神の跳梁に打ち克てない場合は全く恐ろしいものになると思った。知らぬが仏で、知ったが最後だと思った。 宮本は彼がこれを屹度訊くだろうと思うように意地悪い笑いを見せながら黙っている。謙作は訊かなかった。そして夢から覚めた。気味悪いいやな気持が残った。それを云いに来た宮本が既に化物のような気がした。宮本の形を借りた化物のように思われた。---彼は便所へ立って行った。(それが又夢だったのである)便所の窓が開いていて、戸外は静かな月夜だ。木の葉一つ動かない。しんとした夜景色で、広い庭には(彼の家の庭より、それは余ほど広い庭だった)屋根の形が山形にくっきりと映っている。彼は不図その地面で何か動いたように思った。映った屋根の棟(むね)でそれが動いていた。彼は先刻、どーんという鈍い響きで何かが自分の寝ている屋根の上へ飛び下りたような気がした事を憶い出した。 それは七八歳の子供くらいの大きさで、頭だけが大きく、胴から下がつぼんだように小さくなった。恐ろしいよりは寧ろ滑稽な感じのする魔物だつた。それが全く声もなし、音もなしに、一人安っぽく跳(おと)っている。彼から影を見られている事も知らずに、上を見、下を見、手を挙げ、足を挙げ、一人ではしゃいでいるが、動くものはその影だけで夜は前にも書いたようにしっとりと月光の中に静まり返っていた。彼はこれが跳っている間、その棟の下にいる者は悪い淫蕩な精神に苦しめられるのだと思った。淫蕩な精神の本体がこんなにも安っぽいものだと思う事は却って何となく彼を清々(すがすが)しい気持ちにした。そして今度は本統に眼を覚ました。 |
| 十二 |
| 仔山羊だと思っているうちに僅か二三カ月の間に何時か角も三寸ほどになり、頤(あご)の下からは先の尖った仔細らしい髭が生えていた。「この頃山羊が変に臭いの。洗ってやったら、どうでしょう」と茶の間で一緒に食事をしている時にお栄は顔をしかめながら云った。「洗っても駄目でしょう?」。「そうかしら。それに段々気が荒くなって、由(よし)なんか可恐(こわ)がって中へ入れないのよ。突っかかるものがないと、餌さ函をひっくりかえしたり、棒杭と押しっこしたり、一人で怒っているの」。「何処かへやりましょうか」。「鳥清(とりせい)? 鳥清なら幾らかで引き取ってくれるかも知れないのね」。「鳥清でもいいが、あすこへやれば屹度伝染病研究所へ売るから、殺しにやるようなものですね」。「それもいやあね。---おかみさんを持たしてやればいいのかしら」。「しかし何処かへやった方がいいでしょう。何故ならもしかしたら僕は暫く旅行しようかと思ってる」。「何処へ?」。お栄は一寸意外な顔をした。「はつきり場所をきめてないんですが、半年か一年、何処か地方へ行って住まおうかと思うんです」。「又、どうして不意にそんな事を考え出したの?」。「そうだな、そうはっきりした理由もないが、とにかく僕はもう少し生活をどうかしなければ駄目なんです」。「私も一緒に行くの?」。「いいえ」。 お栄は一寸不快な顔をした。謙作は何と説明していいか、わからなかった。少時(しばらく)して、「信さんへはもうお話したの?」。「まだしません」。「だけども---全体何故なのかしら? 此処じゃあ、勉強ができないんですか?」。「そうあんまり問い詰められると困るが、そんな事でもして気を更(か)える必要があるんですよ」。「そう。そんなら仕方がないけど。半年か一年したら屹度帰って下さるんですか?」。「そりゃあ帰りますさ。此処が自家だもの」。「気を更えるだけなら一月(ひとつき)かそこらでも充分だと思うけど---」。「長い仕事を持って行くんです。それを書き上げるまでいるんです」。二人は暫く黙った。「じやあ、ここはどうするの? 私一人だと、こんな家を借りてるのは無駄ね」。「そんな事ないさ。僅か一年ばかり」。「何か理由(わけ)があるんじやないの?」。「理由と云えば、今僕が云っただけの事です」。「何だかはつきりしないのね」。お栄は少し厭味らしく云って笑った。お栄は彼が女でも連れて行って同棲する心算(つもり)ではないかと疑う風だった。 「一言(ひとこと)にいえば純粋に一人になりたいんですよ。友達からも自家の人からも、それから誰からも」。彼はわざと貴女(あなた)という代りに自家の人と云う言葉を使った。それだけでも多少お栄にはいい感じがした。そして笑いながら、「淋しくなりませんか?」と云った。「それは淋しくなるかも知れないが、何しろ勉強しますよ」。「私は随分淋しくなるわね。あんまり淋しくなったら家をたたんで出かけますよ」。謙作は苦笑した。それから彼は前日から考えていた多分山陽道の何処か、海に面した処で、簡単な自炊生活をする事等、幾らか具体的な計画を話した。「気楽でいいのね」と云って、お栄は「本統に気楽な人だ」と云うような、いい眼つきをして凝っと謙作の顔を見た。 その晩彼は電話で信行の在宅を確かめてから本郷の家へ行った。「一寸羨ましいな」。信行は直ぐこんなに答えた。「尾の道へ行くといい。尾の道はいい処だよ」。「そうかね。何処でもいい処ならいいが、船のつく処だね」。「そうだ。お前は汽車が嫌いだから、それもいいかも知れない。いっそ、横浜から船で行くと云い」。謙作はそれも面白いと思った。そして最近に出る船を調べて貰って、切符を買う事を信行に頼んで、そして翌日又会う約束をして別れて来た。 翌日(あくるひ)午後四時少し前、彼は三越の角で、近くの火災保険会社から出て來る筈の信行を待っていた。年の暮れ近い夕方の忙(せわ)しい室町通りで、電車は北からも南からも絶えず来てはその前で留まり、車掌が同じ事を云って、又動いて行った。車、自動車、荷馬車、自転車、それからその間々を縫って人間が四方へ勝手な速さで歩いていた。犬も通った。彼は鼻先をかすめて通る男の肩の風を顔に受けながら、もう直自分は前に海を見晴らす遠い静かな処へ行くのだと思った。楽しみでもあり、一寸淋しい気持ちもした。彼はぶらぶら日本銀行の方へ歩き出した。小さい郵便局の前を通る時に丁度四時が鳴っていた。間もなく、広場を三方から囲んでいる三井の建物から吐き出されるように大勢の人々が出て来た。杖を小脇へ挟んで、巻煙草に火をつけている者がいる。先へ行く仲間を小走りに追いかけて行く者がある。見る見る広場はこの連中で賑わった。日本銀行からも出て来た。正金銀行からも、その他からも出て来た。そして三々伍々ぞろぞろと通る。彼は直ぐ、その内に信行を見出した。信行は五十恰好の品のない肥った男と何か話しながら来る。信行は笑いながら、片手に丸めて持った雑誌で他の手の掌(ひら)を叩きながら、しきりに何かいっている。太った男は時々それに応じて点頭(うなず)いていた。 信行は謙作を見つけると、足を早めて近づいて来た。「待ったかい?」。「いや」。背後(うしろ)から、「じゃあ、失礼します」と太った男は声をかけて、中折れの帽子の縁(ふち)に手だけかけて、脱がずに一寸頭を下げた。「君は此方へ帰るんじゃないのかい?」。「今日は一寸」。「そう。それじゃあ、今の事ね、僅かな事だから、僕の方はどうでもいいから、あんまり露骨にならないようにお願いいします」。「承知しました」。こういって、もう一度頭を下げて太った男は外濠(そとぼり)の方へ引き返して行った。電車通りへ出ると、「とにかく、向う側へ渡ろう」と、信行は厚い外套の肩で、謙作の背中を押すようにして線路を越した。「何を食う」。「何でもいい」。「鳥はどうだい?」。「鳥でもいい」。日本橋の仮橋(かりばし)へ来た。土台を築くために囲いをした、その中へ浸み込む水を石油エンジンで絶えず汲み出している。亜鉛板(とたんいた)の変に反(そ)りかえった屋根から、細いのと太いのと日本の煙突が出ていて、細い方はスポッスポッと勢いよく蒸気を吐く度震えていた。そして太い方は赤さびて、その頭から元気のない煙を僅かにたてている。セメントに小砂利を混ぜたのをモツコで陸(おか)から運ぶ者がある。頬髯のいかめしい土方がそれをシャベルでならしている。一方ではその上へ蓆(むしろ)を敷いて、向かい合った二人が、堂突きで、よいさよいさと突いていた。背広に日本脚絆(きゃはん)をはいた男が測量をしている。その彼方で、丸太を二本立て、それへ貫き板をX字なりに打ちつけている者がいる。そして、その下の油のギラギラ浮いた水溜(たま)りで顔を洗っている女労働者があった。 二人は一寸立ち止まって欄干へ倚(よ)り、それらを眺めた。そして又それを離れて歩き出した。「働く事がその日その日の食う手段になっている奴はまだいいがね。俺のしている事なんかそれだけの必然さもないからね」。突然信行はこんな事を云い出した。「時々変な不安な気持ちになって仕方がない」。謙作は一寸不思議な気持ちがした。信行にもそう云う事があるというのが思いがけない気がした。「会社をよす気があるの?」。「うん」と信行は首肯(うなず)いた。「俺は自分のしたい事がもう少し分明(はっきり)したら、直ぐよす心算(つもり)だ」。「先によしたっていいだろう」。「それでもいいが---」。こういって信行は一寸不快な顔をして上を向いた。謙作は少し云い過ぎたと思った。信行には弱い気持ちがあった。放蕩などから父にも義母(はは)にも随分心配かけながら、彼は妙に親孝行の気質(かたぎ)が強かった。それだけに愛されてもいたが、こう云う決心をするにも父を苦しめる事、父を失望さす事は妙に恐れた。「どう云う事をするつもりなの?」。こう謙作は訊いたが、信行ははつきりした返事をしなかった。 二人は間もなく或る小さい鳥屋に入って行った。「先刻俺と話していた男があったろう?」と信行が云った。「俺の方の勧誘だが、今日あの男に聴いて、中々ひどい奴があるものだと驚いたよ。二月(ふたつき)ばかり前だが河合という年寄りの矢張り勧誘が、仲間の野口というのが家族で病気で弱っているから、六カ月で五十円貸して貰えないかと俺にいうんだ。その爺さんはいやな奴だが野口というのは人のいい一寸勧誘なんか向かない方の奴なんで、子供が病気だという事も聞いていたし、貸してやったんだ。その時利子の事をいうから、それは要らないと云うと、証書を書かせるというから、それも要らないと云って、そう云う男だから、返せない時、此方へ気兼ねをして、会社へ出られなくなっても困るから、君からとして、僕の名を出さずにやつてくれと云ったんだよ。ところがどうだね。河合はその金を天引き12円の高利で、その弱ってる野口へ貸しつけたもんだ。えにい事をやるじゃあないか」と信行は笑った。「今日あの太った男と野口の噂をしている内に不図わかったんだが、勿論野口の方はとうにその金は使って了つて、五十円の証書だけが河合の手へ渡ってるわけだ。今日の奴は河合をなぐります、とかひどく憤慨しているんだが、なぐったところで始まらないから、証書と天引きした金だけ取り上げて、なるべく穏やかにするように云っといたがネ。又そう云う奴だから契約は中々よく取って来るんだよ。追い出すわけにも行かないんだ」。 謙作は信行の寛大な気持ちを面白いと思った。自分ならばもっと腹を立てて、多分その年寄りを呼びつけて、逃路(にげみち)のないように追い詰めるかも知れないと考えた。「一度思い切って油を絞ってやるといいんだ」。「信さんはそんな風に考えて、よく諦めていられるね。腹は立たないかい?」。「腹は立よ。しかしそんな事をしたって、結果が何にもならないと分かっていれば怒る気もしなくなる」。「そうかな。それはその方が本統かも知れないが、僕なら中々それでは落ち着けないな」。「しかし追及すれば、するだけ不愉快になりそうだからね」。「それが分かっていても、初めから赦(ゆる)す気になれない」。「其処は俺が呑気にできているからかも知れないよ」。一時間ほどして二人は其処を出た。銀座まで歩いて、其処で信行は駱駝の襟巻を買って、謙作への餞別とした。 |
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)