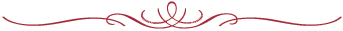
| 第4章の4(後編8)(16から20) |
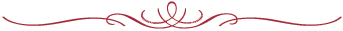
更新日/2021(平成31.5.1栄和改元/栄和3)年.8.10日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここで、「暗夜行路第4章の4(後編8)(16から20)」を確認する。 2021年.8.10日 れんだいこ拝 |
![]()
| 【暗夜行路後編第4章の4(後編8)(16から20)】 |
| 十六 |
| 旅の出がけに謙作は、手紙持たぬように、便りがなければ無事と思っていていい、といい置いて来た。そしている所を知らせなかったから、直子からの便もなかったわけだが、今日お由から竹さんの話を聴くと、急に手紙を書く気になった。出発前と同じ自分を直子に考えさせて置く事が可哀想になり、且つ、それはよくないことに思われて来た。悲し気な眼つきをしながら、子供のように首を傾け、「本統に、もう僻(ひが)まなくていいのね」という直子の姿を憶(おも)い、彼は不憫にもなるが、不愉快な気持にもなる。直子はどうしても完全に赦されたという自信が持てない。仮令(たとえ)赦されても自分だけは赦されたと思ってはならぬと思っている。赦されたと安心すれば、その時、不意に謙作から平手で顔を叩かれるような事が起ると思っている。これは謙作の寛大になりきれない気持が直子にそう思わせるので、謙作自身にとってはこの意識は苦しかった。直子がつい犯した過失に対し、それ程執拗に拘泥するのはつまらない。その為、更に二人が不幸になるのは馬鹿気ている。しかしそう思うのは功利的な気持も含まれていて、謙作自身としては愉快でなかった。又直子からいえば、それでは本統に安心する事ができないのだ。しかし腹から寛大になれないなら、せめて、これより仕方がないではないかと、謙作は腹立たしく思うのだ。そして、こういう自分の気持を純化するのが、この旅の目的だったが、幸いにも、それが案外早く彼に来たのだ。 「皆御無事か、御無事の事と思っている。手紙出さぬようにいったが、急に出したくなって出す。私は旅へ出て大変元気になり、落ち着いている。此所(ここ)へ来た事は色々な意味で、大変良かった。毎日読んだり、何かしら書いたりしている。雨さえ降らねば、よく近くの山や森や河原などへ散歩に出かける。私はこの山に来て小鳥や虫や木や草や水や石や、色々なものを観ている。一人で叮嚀に見ると、これまでそれらに就いて気がつかず、考えなかった事まで考える。そして今までなかった世界が自分に展(ひら)けた喜びを感じている。お前に話したかどうか忘れたが、数年来自分にこびりついていた、想い上った考えが、こういう事で気持よく溶け始めた感がある。尾道に一人いた頃そういう考えで独り無闇に苛々したが、今は丁度その反対だ。この気分本統に自分のものになれば、自分ももう谷化に対し、自分に対し危険人物ではないという自信が持てる。とにかく謙遜な気持から来る喜び(対人的な意味ではないが)を感ずるようになった。今思えばこれは旅に出る時から漠然望んでいたもので、思いがけなく来た変化ではないが、案外早く、自然にその気持に入れた事を大変嬉しく感じている。 お前に対しても今までの自分はあれで仕方がなかった。後悔してもお互いに始まらない事だ。しかしこれからはお互いに安心したい。お前も二人の間に決して不安を感じて貰いたくない。一人で山にいて遠く自家(うち)の事を考えると、この気持は一層強い。これからは私も怒り、お前を困らす事もあるだろうが、それにはもう何の根もない事を信じて貰いたい。そんな事は決してないつもりだが、山を下りると又元の木阿弥になるようではつまらない。私はこの気持をもっと確(しっか)り摑(つか)み、本物にしてお前の所へ還るつもりだ。それもそう長い事ではない。そしてお前には色々な意味で本統に安心して貰いたい。実際これまでの事も馬鹿馬鹿しいという事はよく知っているのだが、病気のように一ㇳ通りの経過をとらねば駄目なものだ。今の私は本統にその経過をとり終った。もう何の心配の種もない。 赤ちゃんの事は時々憶い出している。病気させぬよう充分注意。この寺にもうち*のより半年早生まれの赤坊(あかんぼ)いるが、乱暴な育て方をしている。医者も薬屋もない山だから、ひと事ながら心配な事もある。此所の飯の不味(まず)い事、大閉口(おおへいこう)。炊き方が悪いのではなく、米自体が悪いのだ。こんな経験初めてだ。手紙来ていたら送るよう。信さんから便りあるか。お栄さんには尾道の時とは大異違(おおちが)い故、御心配無用といって貰いたい。お前も身体を気をつけるよう。私も身体は元気だが、食い物悪く、知らず知らず減食する結果となり、少し瘠せたようだ。しかし何も食物は送らぬよう」。彼は机に凭(もた)れたまま開け放しの書院窓をとおしてぼんやり戸外(そと)を眺めていた。座敷の前、三間ほどの所が白壁の低い土塀で、それから下が白っぽい苔の着いた旧い石垣で路(みち)、路かせ更に二三間下がって金剛院という寺がある。朝からの霧が未だ晴れず、その大きな萱屋根が坐って居る彼の眼の高さに鼠色に見えている。 彼はまだ何か書き足りないような気がした。それよりも直子には寝耳に水で何の事か分らぬかも知れぬという不安を感じた。急に自家が恋しくなり、発作的にこんな手紙を書いたと思われそうな気もした。彼は洋けい紙の雑記帳を取り、その中から三枚ほど破って、余白に「こんなものを時々書いている」と書き、手紙に同封した。二三日前この書院窓の所で蠅取蜘蛛(はえとりぐも)が小さな昆虫を捕り、到頭、それが成功しなかった様子を精しく書いて置いたものだった。自分の生活の断片を知る足しになると思ったのだ。彼は買置きの煙草が断れたので、それを買い旁々(かたがた)、今の手紙を出しに河原を越し、鳥居の所まで行った。霧で湿ったバットをよく買わされるので、新しい函を開けさせ、その一つを吸って見てから幾つか買い、又同じ道を引還して来た。何となく、晴々した気持になっていた。彼は自分の部屋の窓から余分の煙草を擲(なげ)込んで、今度は今行った方向とは反対の方へ出かけた。杉の葉の大きな塊(かたまり)が水気を含んで、重く、下を向いて幾つも下がっている。彼はその下を行った。間からもれて来る陽が、濡れた下草の所々に色々な形を作って、それが眼に眩(まぶ)しかった。山の臭いが、いい気持だった。路傍(みちばた)に山水を引いた手洗い石があり、其所だけ路幅が広くなっている所で、竹さんが仕事をしていた。枝を拡げた大きな水楢(みずなら)がその辺一帯を被い、その葉越しの光りが、柔らかく美しかった。竹さんは短く切った水楢の幹から折板(へぎ)を作っている。既にできた分が傍(わき)に山と積んであった。彼を見ると、竹さんは軽いお辞儀をした。「そんなに要るのかね」。「どうして、この三倍ぐらいは要るんですよ」。「材料から拵えてかかるのだから大変だな」。謙作は其所に転がしてある、幹の一つに腰を下ろした。「第一こんな立派な木を無闇と伐(き)って了うのは勿体ない話しじゃないか。やはりこの辺にある奴を伐るのかね」。「まあ、なるべく人の行かないような所から伐って来るんです」。「それにしても、そう木の多い山ではないから惜しいものだね」。「水屋の屋根にするぐらい、知れたもんですよ」。竹さんはよく桶屋が使っている、折れた刀の両端に柄をつけたような刃物を、傍(わき)に置くと、カーキ色の古い乗馬ズボンのポケットからバットを出して吸い始めた。「こんな大木を伐るのは、自分でやるのかしら」。「これは本職でないと駄目だね。本職の木挽(こびき)が挽(ひ)いて、持って来てくれるんです」。「そうだろうね」。「それはそうと、山へはいつ登ります?」。「僕は何時でもいいよ。竹さんの都合のいい時でいい」。「実は明日の晩、一ㇳ組案内を頼まれているんだがね。学生四五人という話で、それと一緒にどうです?」。「うん、いいよ」。「中学生なんか、却って、無邪気でいいでしょう」。「そうだ」。 濡れて、苔の一杯ついた手洗石のふちに何か分らない、見馴れない虫がウヨウヨ這い廻っている。桜にいる毛虫より小さく、黒い地肌の見える、毛の少ない奴で、何千だか何万だか、重なり合って、脈を打っている。群をなしているのが堪らなかった。虫もこういうのに会っては興醒(きようざ)めだと思った。「やはり毛虫の類かね」。「昨日は一匹もいなかったが、今日急に出て来たね」。「普通の奴とは大分異うが、やはり、毛虫の類だろうな」。「---寺を十二時に出て、ゆっくり登って、頂上で御来迎(ごらいこう)を拝む事になるんだが、月があると楽なんだが、この頃は宵のうちに入って了うね」。「そうかな。月がないとすると提灯をつけていくのか」。「はれてさえいれば星明りで充分ですよ。登り出せば木がないからね。尤もその用意だけはして行くが」。「少し昼寝をしておかないと弱りそうだが、そいつができないんで困る」。「よる、早く寝ておけばいい。いい頃に行って、私が起して上げましょう」。「そのまた、早寝も習慣でできないんだ」。「そりゃあ、困ったね」と竹さんは笑い出した。竹さんは煙草を喫(す)い了ると、足で踏み消し、又仕事にかかった。謙作はいつも行く阿弥陀堂の方を廻って帰って来た。今日の手紙は早くて、明後日(あさって)、隔日しか登って来ない郵便脚夫が今日来なければもう一日遅れて直子の手に入るわけだと思った。彼は机に向い、読みかけて、そのままになっていた、元三大師(がんさんだいし)の伝を読み始めた。よく田舎家の入口などに貼ってある元三大師鬼形(きぎょう)の像のいわれを面白く思った。上野にある両大師の一人がこの元三大師たせという事も初めて知った。 その時、彼は玄関に聴き馴れない男の声を聴いたが、自分に客のある筈もなく、庫裏への客が間違えているのだろうと少時(しばらく)そのままにしていたが、又、同じ声がしたので、出て行った。四十前後の坊主が如何にも慇懃(いんぎん)な様子で立っていた。「ちょっとお邪魔致してもお差支えございませんか」。何か間違いだろうと思ったが、謙作は書院と玄関とのあいだの間(ま)に通した。坊主は具合悪そうに奥の間、玄関の間などを見廻していたが、本の積んである床の間に眼をやると、「何か御研究でもなさっておいでですか」と云った。「いいえ」。謙作は坊主の何となく俗な感じがいやだった。間違いでないとすれば、どうせろく*な用ではないだろうと思い、故意に不愛想に黙っていた。「早速ですが、私はこの山の下の赤崎という所の、万松寺という寺の住職でございますが、金剛院で明日から十日間禅の講習会を催しますので、もし禅に多少とも興味をお持ちのようでしたら、御参会を願いたいと思いまして---それをお勧めにあがったのですが、---」。「貴方が御講義をなさるのですか」。「いや、私ではございません。実は小学校の教員方の御希望で、私は只、主催者としてお手伝いをしておりますので、師家(しけ)は天竜寺の峨山(がざん)和尚に就いて修行せられた方です。---私は禅宗とは、宗門違いなのであります」。峨山の事は前に信行から聴いていたから、その弟子で一ㇳ通りの坊主ならば、面白いかも知れぬという気にちょっとなった。「提唱はどういうものをなさるのですか」。「臨済録をされる筈です」。「その本なら丁度今、持ってはいるが---」。こういうと、坊主がちょっと意外な顔をしたので、謙作は続けて、「鎌倉の寺に通っている兄があって、それがくれたのです」と云った。「いや。それでは貴方様も禅の方はよほど御修行になっておられるのでしょう」。「いいえ、全然知りません」。「そんな事はございますまい。しかしそれはとにかく、臨済録をお持ちならば是非一つ御参会を願いたいもので---」。「公案もあるのですか」。「そうでございます」。 公案は師匠の坊主が余程できていなければ無意味だというような事を前に信行から聴いたように思った。そして彼は少時(しばらく)黙っていたが、「考えてから御返事します」と云った。謙作は今、眼の前に坐って居る坊主とこれから十日間も交渉を持つ事を考えると、もう厭になっていた。「余り堅くお考えにならんで、どうぞ一つ---何しろ、十日間の講習で、皆初めての方ばかりで、つまり禅とは如何なるものかと云う事を朧気(おぼろげ)なりとも分って頂ければよい程度で---、むつかしくお考えにならずに是非御参会をお願いしたいものです。臨済録をお持ちだと云うのも、因縁でありますから---」。「あとで御返事します」。「そう仰有(おっしゃ)らんで是非---」。謙作は返事をしなかった。坊主はちょっと具合悪そうにしていたが、急に改まった調子で、「実はそこで一つお願い致したい事があるのでありますが---」と云い出した。話の要領は、下の金剛院には離れがなく、師家と講習生とが襖一枚で隣り合っている為、一人一人に授ける公案が他に漏れて了う。それが困るので、もし謙作が講習生の一人になり、他の人々と合宿してくれれば、この離れを師家の為に使う事ができる。もしそうして貰えれば非常に好都合なのだ、幸い禅に理解があり、公案がどういうものかを御存知なので、お願いするにも仕易く、大変幸いであった。---こういう話だった。 謙作はすっかり腹を立てて了った。坊主の話に幾らか釣られた形だったので尚腹を立てた。「最初から、それを云うのなら、考えようもありますが、おだてるような事を貴方は云われた。それでは貴方に乗せられる事になる」。謙作は腹立ちから、こういう言葉を繰返した。「それは誤解です。私は最初からそんな目的で伺ったのではないのです。一人でも多く、求道(ぐどう)の道を得たいと思いまして、それで、お勧めに伺ったのですが、伺うて初めて、この離れが師家に大変好都合な御部屋だと考えたので、甚だ不躾(ぶしつけ)とは思いましたが、ついお願いして見たまでで、最初から此所を空渡して頂きたい---そんな考えで伺ったのではないのです。この点をよく御諒解戴(いただ)かんことには私が如何にもずるい人間かなぞのようで---」。「それは嘘だ!」。到頭、謙作は怒鳴った。「どうしてですか」。坊主もちょっと調子を変え、青い顏をした。「そんな見え透いた嘘をいっても駄目だ」。二人は黙って暫く睨(にら)み合っていた。そのうち、坊主は不意に衣の袖(そで)をぱっと両方へ拡げると、可笑しいほど平蜘蛛(ひらぐも)になって、「御海容(ごかいよう)を願います」と云った。その急な変り方に謙作はちょっと呆気(あっけ)にとられた。結局、静かな部屋を他に探してくれれば此所を空渡してもいい、必ずしもこの寺でなけねばならぬという事はないのだから、と謙作も云い、坊主ももしそうして貰えればありがたい事だ、と云って帰って行った。謙作は下らぬ事で、折角の静かな気分を打ち壊した事を馬鹿馬鹿しく思った。しかしそれに余り拘泥しない事にした。 |
| 十七 |
| 夕方、想いがけない話をお由から聴き、謙作はすっかり不快(いや)な気持になった。竹さんの女房が痴情の争いで、情夫と一緒に重傷を負い、危篤だという知らせがあり、竹さんは倉皇(そうこう)、今、山を下って行ったというのだ。「可哀想ですわ、竹さんはそんな悪いおかみさんでも少しも憎んでいないのですからね、きっとこんな事になると思っていた、と泣いていたそうです」。「気持の悪い話だな」。「斬った方は竹さん以前からおかみさんと関係のあった人で、斬られたのも竹さんのお友達で、一緒に山へ来た事のある人だそうです」。「その細君と云うのは、助かりそうなんですか」。「竹さんの帰るまで持たないだろうと誰かが云ってまとたわ」。「もし助かっても、そんなの、もう駄目だな」。彼は吐き捨てるように云った。「それが、竹さんには、そういかないらしいですわ」。謙作は不思議な気がした。しかしそういう竹さんだから、その渦に巻き込まれなかったのだ、と思った。「実は先刻(さっき)会って、明日の晩、山を案内して貰う約束をして来たばかりなんだ」。「そうそう。お母さんが云ってました。---でも、代わりの人があるそうです」。 叡山に次ぐ天台の霊場などいわれる山に来て、猶(なお)且つ、こういう事を聴かねばならぬと云うのは如何にも興醒めだった。只竹さんが、完全に事件の圏外に居て、その災厄(さいやく)を逃れた事はよかった。彼はその朝、お由さんから竹さんの話を聴き、竹さんが多少、変態なのではないかしらと思ったが、今はそれより、竹さんのはその女房を完全に知る為の寛容さであったかも知れぬと思った。性質と、これまでの悪い習慣を完全に知る事で、竹さんは自分の感情を没却し、赦していたのだ。さっき気楽に話し合っていた、恐らくその頃、山の下ではそんな血塗(ちまみ)れ騒ぎが演じられていたのだ。如何に超然たる竹さんでも、今頃は参っているだろう。女を憎んでいないとすれば、恐らく悲嘆に暮れているかも知れないと、彼は思った。謙作は母の場合でも直子の場合でも不貞というよりむしろ過失と云いたいようなものが如何に人々に祟(た)ったか。自分の場合でいえば今日までの生涯はそれに祟られとおして来たようなものだった。総ての人が竹さんのように超越できれば、まだしも、---その竹さんとても不幸である事に変りはないが。---そうでない者なら、何かの意味で血塗騒ぎを演ずるような羽目になるのだ。謙作自身にしても、もし自恃(じじ)の気持がなく、。仕事に対する執着がなかったら、今頃はどんな人間になっていたか分らなかった。「恐ろしい事だ」。謙作は思わずこんな事をいった。「本統に恐ろしい事ですわ」とお由は謙作とは別な気持で答えた。そして、「でも、私には竹さんのおかみさんの気持が分りませんわ」と云った。「そんな女を少しも憎めない竹さんも変っている」と謙作はいった。 翌日はよく晴れ、山登りには好適な日であったが、謙作は昨日(きのう)の暗い気分が滓(かす)で残っていて、妙に億劫(おっくう)で、気が進まなかった。とにんく、その晩の山登りは止める事にした。午後彼は阿弥陀堂へ行き、その縁で1時間ほど、凝然(じっ)としていた。子供から母を憶(おも)う時、よく一人、母の墓へ出かけたが、同じ気持ちで、此所へ来る事を彼は好んだ。人は殆ど来ず、代りに小鳥、蜻蛉(とんぼ)、蜂、蟻、蜥蜴(とかげ)などが沢山其所には遊んでいる。時々、山鳩の啼き声が近い立木の中から聴えて来た。帰途、不二(ふじ)門院という荒れ寺へ行った。見上げる大きな萱屋根が更に大きな杉の木の間に埋まっている。久しい空き寺らしく、閉めた雨戸の所々、板が剥(はぎ)取られてあった。彼は下駄穿(は)きのまま入って見た。正面には本尊も何もない大きな仏壇があり、その両側が一間ほどずつ開け放しの押し入れのようになっていて、何十とも知れぬ大きな位牌がほこりにまみれ、立ったり倒れたりしていた。代々の住職、大檀那(だんな)という人達の位牌らしく、桃山建築にあるような唐破風(からはふ)のついて黒塗り金字の大きな位牌が算を乱しているのは余りにいい気持ではなかった。恐らく野鼠(のねずみ)、木鼠の仕業だろう。 暗い庫裏の長い土間に大きなながし*があり、その上に畳一畳ほどの深い水溜(みずため)の枡(ます)があった。半分は屋内に、半分は屋外に出ていて、筧(かけひ)から来る山の清水が、それから滾々(こんこん)と溢(あふ)れていた。杉の枝を漏れる夏の陽が山砂の溜まった底の方まで緑色に射込(さしこ)み、非常に美しく、総てが死んで了ったようなこの寺で、此所だけが独りいきいきと生きていた。彼は又、反対側の書院の方へも行って見たが、荒れ方が甚(はなはだ)だしく、周囲四五町、人家のない森の中の淋しい所ではあるが、住めれば住んで見てもいいような気で、見に来たが、その事は断念した。彼が又寺に帰って来た時、赤児を抱いたお由が石段の上に立っていた。「留守に昨日の人は来ませんでしたか」。「来ませんわ。それにそんな都合のいい所なんて他にあるわけがありませんわ」。お由はその坊主に反感を現わして云った。「来なければ丁度いい。実は今、不二門院へ行って見たが、荒れ方があまり甚いので---」。「ほう、とても、とても」とお由は首を振った。上が一直線のような妙な形をした握拳(にぎりこぶし)を口一杯に入れていた赤児が、涎(よだれ)に濡れた手を謙作の方に差出し、身体を弾ませながら大きな声をあげ、尚、抱かれるつもりか身体を無闇に彼の方へ屈(ま)げて来た。「この間、コンデンス・ミルクを嘗めさしたんで、味をしめたな」。謙作は笑いながら、「駄目だ、駄目だ」と、そのまま自分の部屋へ入って行った。 |
| 十八 |
| 二三日経ったが、竹さんの家の消息は分らなかった。そして、下の坊主もそれきり顔を出さなかった。一度「喝(かつ)」という大きな声が下の寺から聴こえて来た。「喝」の講義らしかった。場合によっては臨済録の提唱だけ聴きに行ってもいいと思っていたが、むこうがそれきりなので謙作も行くのをやめた。そして毎日の天気続きに彼は彼方此方(あっちこっち)とよく一人散歩に出たが、竹さんの居なくなったのが少し淋しかった。これまでも別にそれ程の間柄ではなかったが、竹さんの仕事を見ながら一服する事がないだけでも何となく物足らなかった。いつもの所には、やりかけた仕事がそのまま路傍(みちばた)に積んであった。手洗い石に群(むらが)っていた気味悪い毛虫は今は一匹も居なくなり、其所に白い鶺鴒(せきれい)が遊んでいた。謙作は竹さんの帰るのを待って山登りしようと思っているのではなかったが、竹さんとの約束が駄目になると、つい億劫な気持で、延(のば)していたが、こう天気続きで今度降り出すと又降り続きそうにも思われ、今の間に山登りをして了おうと思った。そして帰ると、彼は早速寺のかみさんに山の案内者を頼んだ。「連れはどうでもいいから、なるべく、明日(あした)の晩という事にして下さい」。「そうですか? 一人に一人の案内人は無駄なようにも思いますが、天気が変ると、あの時出かければよかったというような事になるかも知れませんからね。---まあとにかく、案内人の都合を訊き合せして見ましょう。いいお連れがあるかも知れないし」。「そうして下さい」。 庫裏の土間に立って、二人がこんな事を云っているところに、戸外から巻脚絆(まききやはん)に草鞋(わらじ)穿きの若い郵便脚夫が額の汗を拭きながら入って来た。彼は尻餅をつくようにかまち*に腰を下ろし、紐で結んだ一ㇳ束の手紙を繰り、中から二三通の封書を抜き取り、其所へ置いた。「どうもご苦労さん。今日あたりはえらい*だろうね。お茶がいいかね。水がいいかね」。「水を頂きましょう」。「砂糖水にしようか」。「すみません」。謙作は郵便脚夫が手紙の束を繰る時、ちょっと眼で直子の字を探したが、勿論まだ返事の来る筈はなかったので、「それじゃあ、連があってもなくても、なるべく明日の晩と云う事にして下さい」。台所に行く上(かみ)さんにこう声をかけ、自分の居る離れの方へ引き還そうとした。「そうそう」。郵便脚夫は急に何か憶い出した風で、上着のポケットを一つ一つ索(さぐ)って、皺になった電報を取出すと、「ええと---時任さんは貴方ですね」と云った。謙作はドキリとし、不意に、直子が死んだと思った。自殺したが、居所が分らず、今まで知らす事ができなかったのだ。彼は自分の動悸(どうき)を聴いた。「お宅からですか?」。コップを載せた盆を持って出た上さんがこう云った。その如何にも暢気(のんき)そうな調子が謙作を一層不安にした。「オフミハイケン、イサイフミ、アンシンス、ナオ」。「ありがとう」。謙作は郵便脚夫に礼を云い、無意識にその電報を幾つにも畳みながら、自分の部屋へ還って来た。 何故、そんなにドキリとしたか自分でも可笑しかった。彼は電報の返事を全然予期しなかった事が一つ、それに手紙を出して了うと、もっと早く云ってやるべきだった、というような事をこの二三日切(しき)りに考えていた。更に竹さんの家の不快(いや)な出来事が彼の頭に浸み込んでいた。その聯想が電報で一遍に彼の頭に閃(ひらめ)いたのだ。何れにしろ、馬鹿げた想像をしたものだと彼は心に苦笑したが、「とにかく、これでよし」と、彼は急に快活な気分になった。そして何度か電報を読み返した。その晩、彼は蚊帳の中の寝床を片寄せ、その側(そば)に寝そべって、久しぶりに鎌倉の信行に手紙を書いた。彼は自分がこの山に来てからの心境について、細々(こまごま)と書いてみるのだが、これまでの自分を支配していた考えが余り空想的であるところから、それから変化した考えも自分の経験した通りに書いて行くと、如何にも空虚な独りよがりを云っているようになり、満足できなかった。そういう事を書く方法を自分は知らないのだとも思った。そしてそれよりも直子かお栄の手紙で自分の旅立ちを知り、心配しているかも知れない信行を安心さすだけのり手紙を書く方がいいと思い直し、五六枚書いた原稿紙の手紙を二つ折りにして、傍(わき)のポート・フォリオへ仕舞い込んだ。 「もうおやすみですか」と襖の外から声をかけ、寺の上さんが顔を出した。丁度いい連があり、明晩十二時頃から頂上行きをするからと、それを知らせに来たのた。「どうもありがとう。そうしたら、明日はせいぜい朝寝をするから、戸を開けないようにして下さい。昼寝ができないから、なるべく寝坊をしておくのです」。「承知しました」。寺の上さんは尚、敷居際に膝をついたまま、声を落し、「それはそうと、竹さんのお上さんは到頭死んだそうですよ」と云った。「そうですか。---そしてその男の方は?」。「男の方は助かるかも知れないと云う---」。「それから、竹さんの事は何か聴きましたか」。「その竹さんですが、---殺した奴が覗(ねら)いはしないかと皆(みんな)大変心配しているそうですわ」。「変な話だな。殺した奴はまだ捕(つか)まらないのですか」。「そうなんです。山へ逃げ込んだらしくてね」。謙作は不快(いや)な気がした。「しかし竹さんを覗(ねら)う理由は何にもないじやありませんか。そんな馬鹿な事はないでしょう」。「そんな奴はもう気違いみたようなものですからね。やはり、竹さんも油断はしない方がいいですよ」。「それはそうに違いないが、竹さんは大丈夫ですよ」。「ああいう人ですから、そりやあ大丈夫とは思いますけど---」。謙作は腹立たしい気持になった。そして、「この上竹さんが、又やられる---そんな馬鹿な事があって堪るものか」と思った。 翌日(あくるひ)、謙作はできるだけ朝寝をするつもりだったが、癖で、いつも通り、七時過ぎると眼を覚ました。前夜、信行への手紙を書き、少し晩(おそ)くなったところに、竹さんの不快(いや)な話を聴き、又一方では、自分の手紙を見た直子の事など、それからそれと考えると彼は寝つかれなくなった。遠く鶏の声を聴き、驚いて時計を見ると、二時少し廻っていた。彼は眼は覚めたが、このまま起きて了っては恐らく四時間も眠っていないと考え、無理に眼を閉じ、もう一度眠ろうとしたが、只うつらうつらとするだけで、本統には眠れず、それでも十時頃漸く床を離れた。頭が疲れ、身体もだるかった。今晩の山登りは弱るに違いない。しかしこの調子なら却って昼寝ができるかも知れないと思った。 |
| 十九 |
| 山登りの連(つれ)というのは大阪の会社員たちで、大社参りの帰途(かえり)、この山に寄った連中だった。謙作は二三時間の昼寝で睡気(ねむけ)の方は良かったが、昼飯に食った鯛にあたったらしく、夕方烈しい下痢をして、妙に力が脱(ぬ)け、元気がなかった。どうしようかちょっと迷ったが、六神丸(ろくしんがん)を定量の倍ほど呑んだら、どうやらそれも止まったので、やはり思い切って出かける事にした。十二時頃寺を出た。提灯を持った案内者は五十近いおやじだった。会社員たちは若かったが、彼らは一週間の休暇をできるだけ享楽したい気持で、殊更(ことさら)元気だった。洋服に地下足袋、それから茶代返しに違いない小さなタウルを首に巻き、自然木(ぼく)の長い金剛杖(こんごうづえ)をてんでについていた。「おっさん、その一升瓶を破(わ)らんように気をつけてや。おっさんにも御馳走(ごっつお)するさかいな」。ひんな事を後ろから大声に云う者があった。「何遍いうのや。そんなに心配なら、自分で担いで行け」。「お前らも飲むものを一人で担いで行けるか。阿呆(あほ)」。 皆が元気なだけ、謙作はその夜の自分の体力に不安を感じた。一緒に行って途中で自分だけ弱る事を考え、負けまいと意地を張る事で尚苦しい想いをし、同年輩と云う事、そして自分だけが関東者だという事で下らぬ競争意識など持ちかねないと思うと不安を感じた。「山にはもうよほど久しゅうおいでですか」。肩を並べて歩いていた男が話しかけた。謙作が一人別だという事を気の毒に思うらしく、この男は努めて対手(あいて)になるようにしているらしかった。「半月ほどいます」。「よう厭きられんですな。この山に二日凝然(じっ)としてれ云われても私共には、よう我慢でけまへんな」。前に歩いていた太った男が、振り返り、「聞かしとるな。うまいこと惚気(のろけ)とるぞ。---この男は旅行に出た晩から、帰りたがっとるです。最近、彼は妙齢の夫人と結婚したであります」といって、大きな声で笑った。「こらッ」。その男も仕方なく、照れ隠しに太った男の背中を強く平手で叩いた。 竹さんがよく仕事をしていた場所から十町ほど進むともう木はなく、左手は萱(かや)の繁った山の斜面で、空は晴れ、秋のような星がその上に沢山光っていた。路傍(みちばた)に風雨に晒された角材の道しるべが少し傾いて立っていた。それが登山口で、両方から萱の葉先の被(おお)いかぶさった流れの底のような凸凹路(でこぼこみち)を、皆は一列になって、「六根清浄、お山は晴天」こんな事をいいながら、身体を左右に振りながら登って行った。前に四人、後(うしろ)に二人いると、皆と同じ速さで歩かないわけにゆかず謙作は、段々疲れて来た。彼はそれでも我慢して登るつもりであったが、少し不安になった。一時間ほど登ると大分高い所へ来た感じがした。夜でもそれが分った。そしてその辺りで、とにかく、一ㇳ休みする事にした。謙作は疲れた。気持にも身体にももう張りがなかった。これ以上同じ速さで皆について行く事は到底できそうに思われない。彼は案内者に、「身体が本統でないから、私は此所から帰る。二時間ほどすれば、明るくなるだろうし、それまで此所で休んでいる」と云った。「そうですか。それはいけませんな」。そういって案内者は、「どんな具合ですか」と訊いた。謙作は大した事ではなく、只、下痢の後で、体力が衰えているだけ故、心配せずに残して行ってくれと云った。「さあ、それにしても、どうしたらいいかね」。「本統に心配しなくていいんだ。遠慮せずに登って下さい」。「我慢出けまへんか。---なあ君、まだ大分あるんかね」。「今の倍以上登らんなりませんな」。「降りる方はいいが、これ以上登るのは自信がない。どうか心配しないで残していって下さい」。 皆が慰めるような事を云うのに一々答えるのも少し億劫になった。結局、彼一人残る事になったが、謙作への遠慮か、暫くして皆は黙り勝ちに登っていった。謙作は用意して来たスエーターを着、それを包んで来た風呂敷を首に巻き、そして路から萱の生えた中へ入り、落着きのいい所を探して、山を背に腰を下ろした。彼は鼻で深い息をしながら、一種の快い疲れで眼をつむっていると、遠く上の方から、今登って行った連中の「六根清浄、お山は晴天」という声が二三度聴こえて来た。それからはもう何も聴えず、彼は広い空の下に全く一人になった。冷々(ひえびえ)した風が音もなく萱の穂を動かす程度に吹いていた。疲れ切ってはいるが、それが不思議な陶酔感となって彼に感ぜられた。彼は自分の精神も肉体も、今、この大きな自然の中に溶け込んで行くのを感じた。その自然と云うのは芥子粒(けしつぶ)ほどに小さい彼を無限の大きさで包んでいる気体のような眼に感ぜられないものであるが、その中に溶けて行く、---それに還元される感じが言葉に表現できないほどの快さであった。何の不安もなく、睡い時、睡(ねむり)に落ちて行く感じにも多少似ていた。一方、彼は実際半分睡ったような状態でもあった。大きな自然に溶け込むこの感じは彼にとって必ずしも初めての経験ではないが、この陶酔感は初めての経験だった。これまでの場合では溶込むというよりも、それに吸込まれる感じで、或る快感はあっても、同時にそれに抵抗しようとする意志も自然に起るような性質もあるものだった。しかも抵抗し難い感じから不安も感ずるのであったが、今のは全くそれとは別だった。彼にはそれに抵抗しようとする気持は全くなかった。そしてなるがままに溶込んで行く快感だけが、何の不安もなく感ぜられるのであった。 静かな夜で、夜鳥(よどり)の声も聴えなかった。そして下には薄い靄(もや)がかかり、村々の灯(ひ)も全く見えず、見えるものといえば星と、その下に何か大きな動物の背のような感じのするこの山の姿が薄く仰がれるだけで、彼は今、自分が一歩、永遠に通ずる路に踏出したというような事を考えていた。彼は少しも死の恐怖を感じなかった。しかし、もし死ぬならこのまま死んでも少しも憾(うら)むところはないと思った。しかし永遠に通ずるとは死ぬ事だと云う風にも考えていなかった。彼は膝に臂(ひじ)を突いたまま、どれだけの間か眠ったらしく、不図、眼を開いた時には何時か、四辺(あたり)は青味勝ちの夜明けになっていた。星はまだ姿を隠さず、数だけが少なくなっていた。空が柔らかい青味を帯びていた。それを彼は慈愛を含んだ色だと云う風に感じた。山裾の霧は晴れ、麓の村々の電燈が、まばらに眺められた。米子の灯も見え、遠く夜見ケ浜の突先にある境港の灯も見えた。或る時間を置いて、時々強く光るのは美保の関の燈台に違いなかった。湖のような中の海はこの山の陰になっている為めまだ暗かったが、外海(そとうみ)の方はもう海面に鼠色の光りを持っていた。 明け方の風物の変化は非常に早かった。少時(しばらく)してろ、彼が振り返って見た時には山頂の彼方(むこう)から湧き上がるように橙色(だいだいいろ)の曙光(しょこう)が昇って来た。それが見る見る濃くなり、やがて又褪(あ)せはじめると、四辺(あたり)は急に明るくなって来た。昔は平地のものに較べ、短く、その所々に大きな山独活(やまうど)が立っていた。彼方(あっち)にも此方(こっち)にも、花をつけた山独活が一本ずつ、遠くの方まで所々に立っているのが見えた。その他、女郎花(おみなえし)、吾亦紅(われもこう)、萱草(かんぞう)、松虫草なども萱に混じって咲いていた。小鳥が啼きながら、投げた石のように弧を描いてその上を飛んで、又萱の中に潜り込んだ。中の海の彼方(むこう)から海へ突き出した連山の頂が色づくと、美保関の白い灯台も陽を受け、はっきりと浮び出した。間もなく、中の海の大根島にも陽が当り、それが赤エイを伏せたように平たく、大きく見えた。村々の電燈は消え、その代りに白いけむりが所々に見え始めた。しかし麓の村はまだ山の陰で、遠い所より却って暗く、沈んでいた。謙作はふと、今見ている景色に、自分のいるこの大山がはっきりと影を映している事に気がついた。影の輪郭が中の海から陸へ上って来ると、米子の町が急に明るく見えだしたので初めて気付いたが、それは停止することなく、袷度(ちょうど)地引網のように手繰られて来た。地を嘗めて過ぎる雲の影にも似ていた。中国一の高山で、輪郭に張り切った強い線を持つこの山の影を、そのまま、平地に眺められるのを稀有の事とと、それから謙作は或る感動を受けた。 |
| 二十 |
| 彼は十時頃、漸く寺へ帰って来た。よく途中で、参って了わなかったと思う程、彼は疲れ切っていた。玄関の板敷で赤児を遊ばせていたお由が、入って来た謙作の様子を見、謙作に声をかけるよりも、驚きから、「お母ァさん、お母ァさん」と家の中に向って、大声に呼び立てたほど、謙作の様子も顔色も悪かった。寺の上さんも驚いた。直ぐ離れに寝かせたが、熱が高く三十九度、---暫くすると、それが四十度に昇った。頭を氷で冷やす一方、直ぐ麓の村へ医者を呼びにやり、ついでにその使いに京都への電文を持たせてやった。それは謙作が譫言(うわごと)にたびたび直子の名を呼んだからでもあった。村の医者が来たのは夜八時過ぎだった。上さんとお由とはそれまで幾度(いくたび)、戸外へ出て見たか知れない。日が暮れると、殆ど人通りのない所で、それが、いつもと全く変りない静かな夜である事が、恰(あたか)も不当な事ででもあるように二人には腹立たしかった。要するに二人共、親切者には違いなかったが、女二人だけの所で、もし謙作に死なれでもしたら大変だと思うのだ。とにかく、早く医者に来て貰い、この重荷を半分持って貰いたい気持で一杯だったから、提灯と鞄を持った使いを先に、巻脚絆草鞋穿(は)きといういでたちの年寄った小さな医者の着いた時には、二人の喜び方は一ㇳ通りではなかった。「先生が見えましたよ。もし!先生が見えましたよ」。 先に一人走って来たお由が、彼の枕元に良手をつき、顏で蚊帳を押すようにして、亢奮しながら、こう叫んでも、謙作は薄く眼を開いただけで、何の返事もしなかった。しかし医者が入って来て、容態、経過を訊ねた時には、声は低かったが、案外はっきりそれに答えていた。鯛の焼物---五六里先から、夏の盛りに持って来るのだから、最初から焼いてあるのを又焼直して出す、---それが原因らしいという事は、側(そば)に寺の者のいる事を意識してか、少し曖昧に云っていた。医者は一ㇳ通りの診察をした後、特別に腹のあちこちを叮嚀に抑え、「此所は---?」、「此所は---?」と一々訊ねて痛む場所を探した。結局急性の大腸カタルで、その下痢を六神丸で無理に止めたのが不可(いけな)かったと診断した。そしてヒマシ油と浣腸で悪いものを出して了えば、恐らく、この熱も下がるだろうといった。下痢の事は使いの者に聞いていたので、医者はそれらを鞄の中に用意していた。浣腸は殆ど利目(ききめ)がなかった。ヒマシ油の方が三四時間のうち利くだろうし、とにかくそれまでこの離れにいて見よう、出た物を調べる必要もあるからと云う医者の言葉だったので、寺の上さんは早速医者と使いの男へ出す、酒肴の用意をする為、庫裏の方へ行った。 「何をされる方ですね」。医者は次の間へ来て胡坐(あぐら)をかき、其所に置いてあった既に冷えた茶を一口飲んで、お由に訊いた。「文学の方をされる方ですわ」。「言葉の様子では関東の人らしいな」。「京都ですわ」。「京都? ほう そうかね?」。医者とお由がこんな話をしているのを謙作はそれが自分とは全(まる)で関係のない事のように聴いていた。「---どうですやろ」。小声になってお由が訊くと、医者も一緒に声を落し、「心配はない」と答えた。謙作は半分目覚めながら夢を見ていた。それは自分の足が日本共胴体を離れ、足だけで、勝手にその辺を無闇に歩き廻り、うるさくて堪らない。眼にうるさいばかりでなく、早足でどんどん、と地響きをたてるので、八釜しくて堪らない。彼は日本の足を憎み、どうかして自分から遠くへ行かそうと努力した。夢と云う事を知っているから、それができると思うのだが、足は却々(なかなか)自分のまわりを離れてくれない。彼の考えている「遠く」というのは靄(もや)の中、---しかも黒い靄で、その中に追いやろうとするが、それは非常な努力だった。段々遠退いて行く、遠退くにつれ、足は小さくなって見える、黒い霧が立ち込めている、その奥は真っ暗な闇で、其所まで、足を歩かせ、闇にきえさせて了えば、それを追い払えると思うと、もう一ㇳ息、もう一ㇳ息という風に力を入れる、それには非常な努力が要った。そして、一っぱいにそれが張ったところで、恰度(ちょうど)張り切ったゴム糸が切れて戻るように、消える一歩手前で、足は一遍に又側(そば)へ戻って来る。どんどん、どんどん、前と変らず八釜しい。彼は何遍でもこの努力を繰返したが、どうしても、眼から、耳から、その足を消して了う事はできなかった。 それからの彼は殆ど夢中だった。断片的には思いのほか正気のこともあるが、あとは夢中で、もう苦痛というようなものはなく、只、精神的にも肉体的にも自分が浄化されたということを切りに感じているだけだった。翌朝早く年とった医者は帰り、代りに午頃(ひるごろ)、食塩注射の道具などを持った余り若くない代診が来たが、その時は、熱は下がったが下痢するものが米の磨ぎ汁のようで、手足の先が甚く冷え、心臓の衰弱から、脈が分らないぐらいになっていた。大人の急性腸カタルとしては最も悪い状態で、代診はもしかしたらコレラではないかと心配していた。とにかく、早速強心剤の注射、それと食塩注射、太い針を深く股(もも)に差し、ポンプで徐々に食塩水を流し込むのだが、その部分だけが不気味に脹(は)れあがり、謙作は苦痛から涙を出していた。 直子が着いたのはそれから間もなくだった。しかし寺の上さんは謙作が直子の到着を切りに心待ちにしている事を知っていたから、不意に会わし、もし気のゆるみから、どうかあってはという心配で直ぐ会わす事に反対した。謙作はそれ程衰弱していた。医者も注射した食塩水が吸収されれば、もっと脈もしっかりして来るから、その時にして貰いたいと云ったので、直子は吃驚(びっくり)して了った。直子は色々悪い場合を想像しては来たが、恐らく想像するよりは屹度(きっと)軽いに違いない、「電報なんか打ったから驚いたろう?」。こんな事を云って微笑する謙作まで考え、それを希望として来たから、現在の容態が、想像以上なので、すっかり驚いて了った。そしてそんなに衰弱した謙作を見るのが恐ろしくもなった。何故なら炎天下の三里の登り道を急いだ彼女は疲労と亢奮とから、自分自身にも自信がなかったから、会って、余りの変り様に、もし気を取乱したりしては病人の為にも悪いと思うと、医者の云うように暫く様子を見てから二するのが本統かも知れぬと思った。寝不足と、夜汽車の煤(すす)と、汗とで顔色の悪く見える直子に寺の上さんは小声で頻りに入浴を勧めたが、直子は却々尻をあげなかった。「浴衣(ゆかた)に着更えなされませ」とも上さんは云った。「ありがとう、そんなら、顔だけ洗わして頂きます」。直子は湯殿を案内して貰い、漸くそれだけをし、其所にあつた小さい鏡台の前で乱れた引結(ひつつめ)の髪を撫でつけ、還ろうとすると、庫裏の炉を挟み、医者と上さんとが何か小声で話し込んでいるのを見た。二人は足音で一せいに直子の方を見たが、医者が、「奥さん、どうぞ、ちょっと」と云った。 「---」。直子はどきりとしながら、其所へ入って行った。「脈は大分よくなりました。今、眠って居られますが、今度眼が覚めた時、なるべく静かにお会いになったらいいでしょう」。「随分危険な容態なのでございましょうか?」。「はっきりは申し兼ねますが、とにかく、急性の大腸カタルに違いないので、子供の場合とか、余程不健康な人の場合は別ですが、普通には、そう恐ろしい病気ではないので---御心配なさらんでいいと思いますが、---実は今、此所の奥さんとも御相談していたのですが、一度米子の〇〇病院の院長さんに診てお貰いになってはどうかと思いまして---」。「是非お願い致します」。直子は早口にそれを云った。「どうか直ぐ、そうお願い致します。様子によっては鎌倉に居ります兄にも知らせなければなりませんので---」。「いや、いや。まだ、そんな容態とは私は思いません。とにかく、それでは早速、使いを出して、電話か電報で、〇〇博士にお願いして見ます。勿論今日というわけには行きませんが、明日午後には屹度来て貰えるでしょう」。「それからその時、看護婦さんを一人お願いしたいのですが---」。 お由が入って来た。お由は「驚いた」と云った調子で、「奥さんの来ていられる事を知っていられますわ」と、三人を見廻すようにして云った。「そうかね?」と医者はことさら首を傾け、それを疑問にしながら、「夢を見たのだよ、それは」と云った。「そんな事ありませんわ。会われるのをお母さんが止めた事まで、よく知っていられますわ」。直子はもう中腰になり、黙って、医者の顔を見ていた。それと気がつくと、医者はお由に訊いた。「それで、奥さんに来て欲しいと云われるのかね?」。「へえ、そう云っていられます」。医者は炉の炭火から煙草に火を移し、一口、それを深く吸込んでから、「なるべく感情を刺激せんように、貴女御自身も泣いたりせんようにしてお会いになったらいいでしょう」といった。直子はちょっと頭を下げ、お由と一緒に離れの方へ行った。「どうでしょう?」。寺の上さんは眉間に深い皺を作って、今まで恐らく何遍か、訊いたに違いない事を繰返した。「さあ、うちの先生は何といわれたか知りませんが、私にはどうもはっきりした事は云えませんよ。実はコレラかという心配もあったが、そんな事はないらしい。腹と尻を充分に温め、強心剤で持たしておれば、余病の出ない限り、大概直ると思うんだが------」。「何しろ家の人が留守なので、留守中そんな事があると、私も実に困るんですよ」。「もう先方(むこう)の奥さんが来たのだから、貴女はそうやきもき*せんでもいいでしょう」。「私はどうも様子が悪いように思われて---」。「心臓が甚く衰弱して了ったので、私も本統の所、何方(どっち)とも云えないんだが---」。「どうも様子が悪い」。そう繰り返し、寺の上さんは大袈裟に溜息をついた。医者は黙って、只煙草を喫(の)んでいた。 直子は胸を轟(とどろ)かせ、しかし外見はできるだけ平静を装うたつもりで入って行ったが、やはり亢奮から、眼を大きく見開き、見るからに緊張していた。謙作は仰向けに寝たまま、眼だけを向け、そういう直子を見た。直子も亦、眼のすっかり落ち窪んだ、頬のこけた、顔色も青黄色くなった。そして全体に一ㇳまわり小さくなったような謙作を見て胸が痛くなった。彼女は黙って、枕元に坐り、お辞儀をした。謙作は聴き取りにくいしゃがれた声で、「一人で来たのか?」と云った。直子は点頭(うなず)いた。「赤ちゃんは連れて来なかったのか?」。「置いて参りました」。大儀そうに、開いたままの片手を直子の膝のところに出したので、直子は急いで、それを両手で握り締めたが、その手は変に冷たく、かさかさしていた。謙作は黙って、直子の顔を見、眼で撫でまわすように只視ている。それは直子には、未だかって何人にも見た事のない、柔らかな、愛情に満ちた眼差しに思われた。「もう大丈夫よ」。直子はこう云おうとしたが、それが如何にも空々しく響きそうな気がして止めた程、謙作の様子は静かで平和なものに見えた。 「お前の手紙は昨日届いたらしいが、熱があったので、まだ見せてくれない」。直子は口を利くと、泣き出しそうなので、只点頭いていた。謙作は尚、直子の顔をしきりに眺めていたが、暫くすると、「私は今、実に云い気持なのだよ」と云った。「いや!そんな事を仰有(おっしや)っちゃあ」。直子は発作的に思わず烈しく云ったが、「先生は、なんにも心配のない病気だと云っていらっしゃるのよ」と云い直した。謙作は疲れたらしく、手を握らしたまま顔をつむって了った。穏やかな顔だった。直子は謙作のこういう顔を初めて見るように思った。そしてこの人はこのまま、助からないのではないかと思った。しかし、不思議に、それは直子をそれ程、悲しませなかった。直子は引き込まれるように何時までも、その顔を見詰めていた。そして、直子は、「助かるにせよ、助からぬにせよ、とにかく、自分はこの人を離れず、何所までもこの人に随(つ)いて行くのだ」というような事を切に思い続けた。 |
| 【暗夜行路後編第あとがき】 |
| 「暗夜行路」は今日までの私にとっての唯一の長篇だが、長篇を書き慣れない故(せい)もあって、中々完成しなかった。終り近くなって、書けなくなって、十一年抛(ほ)って置いたのを今度全集を出すについて、何でもかでも書き上げる事にしたが、主人公の気持に本統に自分が入れるか、書き出すまではそれが甚だ心元なかった。しかし幸いに本気になって、入り込む事ができ、出来栄えに就いても或る程度に満足した。しかし一方では、それわりも人から訊かれれば書くつもりだと毎時(いつも)答えながら、どうしても手がつけられずにいた未完の小説を遂に完成したという事で私の気持は非常に楽になった。長年何となく気にかかっていたものから自由になった事が嬉しかった。 私は作品によって、楽にできる事もあるが、時々随分手古摺(てこず)る事がある。『暗夜行路』は中でも手古摺った物と云えるが、本統に手古摺ったのは、『暗夜行路』の前身である『時任謙作』という所謂私小説の時だった。大正元年の秋、尾の道にいた頃から書き出し、三年の夏までかかって、どうしても物にならなかった。夏目さんからの手紙で、東京朝日新聞に出すように勧められ、その気で書いていたが、新聞の続き物故(ゆえ)豆腐のぶつ切れは困るから、その心算(つもり)で書くようにというような夏目さんからの注意があり、これには困った。夏目さんには敬意を持っていたし、自分の仕事を認めてくれた事ではあり、なるべく、豆腐のぶつ切れにならぬよう書くつもりでも、それまでが白樺の同人雑誌で何の拘束もなしに書いて来た癖で一回毎(ごと)に多少の山とか謎とかを持たせるような書き方は中々できなかった。夏目さんはその年の春頃から、『心』という小説を朝日新聞に出していた。私のものはそれが終ったところで直ぐ連載する筈で、私は松江に行ってそれを書いていた。一緒に行っていた里見と昼は舟遊び水泳などをしてよく遊んだが、夜は明け方まで、それにかかっていた。『心』には「先生の遺書」という傍題があり、こういうものが幾つか集まって『心』という長篇になるものとばかり考えていたが、『心』の方は一日一日進んでいるのに、私の長篇はどうしても思うように捗(はか)らない。私は段々不安になって来た。もし断るなら切羽詰まらぬ内と考え、到頭、その為め上京して、牛込の夏目さんを訪ね、お断りした。ところが、『心』は「先生の遺書」だけで終るもので、私が切羽詰まらぬ内と考えていたのはあて違いだった。夏目さんは考え直すよう、そしてもしその小説が書けないなら、書けない気持を小説に書けないものかと云われた。私はその時考えて見ましょうとは答えたが、書けそうな気はしなかった。翌日早速お断りの手紙を出した。そうしたら夏目さんから、書けた時には必ず朝日新聞に出すようにという大変懇篤(こんとく)なる手紙を頂いた。 私の出すべき長篇小説の空地はその頃の私ぐらいの若い連中の中篇小説幾篇かで埋める事になったが、義理堅い夏目さんに迷惑をかけた事を大変済まない事に感じ、何時かいい物を書いて、朝日新聞に出そうと思ったのが、他にも理由はあったが、それから四年程何も作品を発表できなかった原因の一つであった。その四年間にも私は未完成の長篇を時々書き続けようとし、それができるまでは別の短篇を書いても他の雑誌へ出すことは遠慮しようと思っていたのだ。ところがその間に夏目さんは亡くなられた。新聞社からの直接交渉は一度もなかったので、夏目さんが亡くなられた事で、私のこの気持は自然解放されたが、その後、初めて発表した『佐々木の場合』という小説は亡き夏目先生にデディケートして僅かに自分の止むを得なかった不義理を謝した。 『暗夜行路』の前身『時任謙作』は永年の父との不和を材料としたもので、私情を超越する事の困難がもしかしたら、書けなかった原因であったかも知れない。しかし間もなく私は『和解』という小説に書いたような経緯で、大変気持のいい結果で父と和解をした。和解してみれば『時任謙作』という小説に対する私の気持も変化して来た。ことに父との不和を『或る男、その姉の死』という、弟の立場でそれを見ると云う、比較的公平に批判できる形で書いて了うと、『時任謙作』を今更書き続けなければならぬという気持が段々なくなって来た。長篇を書きたい気はあっても、今までの主題には興味がなくなって来た。 ところで話がとぶが、前に尾の道でその長篇を書きつつあった頃、讃岐へ旅行をして屋島に泊った晩、寝つかれず、色々考えている内に、もしかしたら自分は父の子ではなく、祖父の子ではないかしらという想像をした。私が物心つかぬ頃、父は釜山(ふざん)の銀行へつとめていた事があり、又金沢の高等学校の会計課につとめていた事があり、しかもその時私の母は東京に残っていた。それに、私が十三の時に三十三で亡くなった母の枕頭(ちんとう)で、祖父が「何も本統に楽しいと云う事を知らさず、死なしたのは可哀想なことをした」と声を出して泣いた。父はその時泣かなかった。この印象は後まで私に残っていて、父に対する反感になっていたが、自分がもしかしたら祖父の子ではないかしらと云う想像をすると、こう云う記憶が急に全く別な意味を持って私に甦(よみがえ)って来た。十六で嫁入って来た私の母は、父一人で子のなかった祖父母に実の娘のように愛されていたのだ。「母の死と新しい母」という小説にも書いたように祖母は母の死後、いつまでも私と一緒に泣いていた程、私の母を愛していた。月夜の屋島の淋しい宿で、寝つかれぬままに私がした想像などは如何にも馬鹿気たものだった。翌朝起きた時には自身それを如何にも馬鹿馬鹿しく感じたが、私は安孫子(あびこ)で今は用のなくなった書きかけの長篇を想いながら不図この事を想い出し、そういう境遇の主人公にして、それを主人公自身だけ知らずにいる事から起る色々な苦しみを書いて見ようかと想いついた。この想いつきが『時任謙作』から『暗夜行路』への移転となった。私は祖父を尊敬した。私は肉親という私情を除いても自分のこの世で出会った三四人の最も尊敬すべき人の一人として祖父を尊敬している。それ故、『暗夜行路』の主人公の祖父にはこの祖父と思いきり類似点のない人間を書かねば気が済まなかった。当時、我孫子で自家に出入りしていた植木屋の親爺をモデルにした。昔は所謂好男子であったろうというような老人だった。その為め身を持ちくずし、今は息子に使われている。そういう意気地のない老人、---私はこの老人を嫌いだった。---それを頭に置いて書いた。 しかし、『暗夜行路』も私には却々(なかなか)上手く書けなかった。そして、或る時は一っそ短篇で幾つも書き、それらを纏めて一つの長篇となるようなものにしようかと思った事もある。序詞とした『謙作の追憶』とか、前篇の終り辺を『憐れな男』という題をつけて別に発表したのも、そういう気持からであった。『暗夜行路』前篇に書かれた描写の方面は大体、前の『時任謙作』中にあるもので、一度苦しんで書いたものはそのまま捨て難い気持もあり、できるだけ『暗夜行路』の中に生かす算段をした。後篇の方は『時任健作』ではまだ書かれていない部分だったから、これは純粋に『暗夜行路』のために書いたもので、前篇、後篇の書き方には自然そういう相違ができたわけだ。前篇後篇統一を欠いたわけだが、仕方ない事だった。『暗夜行路』を発表する場合の経緯(いきさつ)と『暗夜行路』という題をつけた事などは前に『暗夜行路』覚書というのを書いたので繰返さない。『暗夜行路』という題もつけた当時は自分でも余り感心しなかつたが、こう年代が起つと今はいやとも感じなくなった。 モデルに就いて。主人公謙作は大体作者自身。自分がそういう場合にはそう行動するだろう、或いはそう行動したいと思うだろう、或いは実際そう行動した、というような事の集成と云っていい。祖父は前に云ったようなもの、母は序詞に出て来るだけだが、私の実際経験ではこれは祖母だった。父も序詞だけだが、父と角力(すもう)をとって、負けて非常に口惜しく感じた経験はある。本文中の陰になっている父も私の父らしいところが多少ある。お栄と云う女は性格的には全然モデルなしに終った。お栄の境遇は或る女から聴いたその女の経験をできるだけ利用したが、性格の方は全然見本なしだった。それが自分でも少し不安だったので、長与(ながよ)に話したら、書いて行く内うち自然に決まるだろうと云われた。長篇では長与の方が先輩だから、そういうものかと思っていた。お栄は後篇にも出て来るが、この女の境遇は自分の小説には少し風変わりで、興味を感じていたが、人間は型に終ったような気がしている。信行と云う主人公の兄はこれもモデルなしである。主人公との関係は私と四つ上の叔父との関係にちょっと似ているが、性格は故(わざ)と叔父とは丁度反対の人物にして、尚、一面では主人公とも対照さすようにしたが、その効果は自分ではよく分らないが、或る程度には成功しているようにも思っている。直子はなるべく自分の家内にならぬよう、最初は体格など全(まる)で別の人物に書いてみたが、いつか段々家内に近い人物になって来た。しかし自分では、あれはあれで一人の別な人物のつもりでいる。境遇はお栄の場合と反対に全然作りものだ。私の家内は自身に似た人物の出て来る小説を見るのをいやがり、未だに『暗夜行路』を読んでいない。細君が自殺する事を書いた『邦子』という小説を読んで懲(こ)りているのだ。 その他、何人かの人物が出て来るが、見本のあるものもあり、ないのもあり、色々である。景色の描写は前篇ではそれを見た当時、或いはその時に近く書いたものだが、後篇の最後の大山の朝景色は二十四年前行ったきりの場所で、うまく書けるかどうか、書くまでは不安であった。もし季節が同じなら、もう一度見に行ってもいいと思ったが、小説では夏なのに書いていた時は冬だった。高い山の雪景色では仕方がなかった。しかし書いて見たら、前の印象が深かった為か、案外はっきり頭に浮かんでくれたので大いに助かった。とにかく、気持がそれにすっかり入り込めたのは大変嬉しかった。 主題は女のちょっとしたそういう過失が、---自身もその為め苦しむかも知れないが、---それ以上に案外他人をも苦しめる場合があるという事を採りあげて書いた。仏蘭西とかウィーンの小説が人妻のそういう事を余りに気楽に扱っている。読者は自身を姦通の対手(あいて)の男の立場に置いて鑑賞するから、そういう不道徳も中々魅力があるわけだ。『クロイツエル・ソナタ』のような小説もあるが、シュニッツレルなどをそういう意味でもし面白いと感ずるなら、恥ずべき事であり、少し馬鹿げていると思った。主人公は母のその事に祟(たた)られ、苦しみ、漸くそれから解脱したと思ったら、今度は妻のその事に又祟られる、---それを書いた。しかしこういう事はたまにその反対の人物、或いは場合もある事と認めるので、これも少し極端ではあったが、『雨蛙』という短編を『暗夜行路』の前篇と後篇との間で書いて見た。 『暗夜行路』は外的な事件の発展よりも、事件によって主人公の気持が動く、その気持の中の発展を書いた。筋を初めから決めてかかり、大体そのように運んだつもりだが、筋が決まっているだけに、先に起る事に伏線を幾つか張ったが、中途で書く事が二三度途絶えたりしたので、伏線倒れに終るのではないかしらという多少の不安を感じた事もある。が、通読して見て、それ程でなかったので満足している。『暗夜行路』を恋愛小説だと云った小林秀雄、河上徹太郎氏の批評がある。私には思いがけなかったが、そういう見方もできるという事はこの小説の幅であるから、その意味では嬉しく思った。所謂恋愛小説というものには興味がなく、恋愛小説を書きたいとは少しも思わなかったが、『暗夜行路』がもし恋愛小説になっているとすれば、それも面白い事だと思った。昭和十三年五月十二日 |
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)