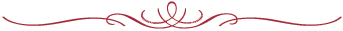
| 第4章の3(後編7)(11から15) |
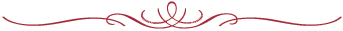
更新日/2021(平成31.5.1栄和改元/栄和3)年.8.10日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここで、「暗夜行路第4章の3(後編7)(11から15)」を確認する。 2021年.8.10日 れんだいこ拝 |
![]()
| 【暗夜行路後編第4章の2(後編6)(6から10)】 |
| 十一 |
| 謙作はいよいよ旅へ出る事にしたが、普通の旅とは心構えが異うだけに出発際(たちぎわ)が何となく妙だった。「何時でもいいんだ。どうせ一日で山までは行けないんだから---」。彼はできるだけ暢気(のんき)らしい風をしてこんな事を云っていた。彼は旅行案内を見ながら、「三時三十六分鳥取行か。もしそれに遅れたら五時三十二分の城崎(きのさき)行でもいい」。「缶詰や何かお手紙下されば、直ぐ明治屋から送らせますから---」。「まあ、なるべく、そう云うものを取寄せずに、むこうの物で間に合わそうよ。なまじ、都の風が吹いて来て、里心がついては面白くない。そう云う意味で、なるべく用事以外、お互いに手紙のやり取りはよそうじやないか」。「ええ。---それでももし貴方に書く気がおでになったら下さればいいわね。もしそう云う気におなりになった時には」。「そうだ。それはそれでいい訳だが、そんな事を云って了うと、お前がそれを待っていそうでやはり窮屈になるね」。「それなら、どうでもいいわ」。「お前は俺の事なんか何にも考えなくていいよ。お前は赤ちゃんの事だけ考えていればいいんだ。俺も赤坊(あかんぼ)が丈夫でいると思えば、非常に気が楽だよ。迷わず成仏(じょうぶつ)できると云うものだ」。「亡者(もうじゃ)ね、まるで」と直子は笑い出した。「実際亡者には違いないよ。その亡者が、仏様になって帰って来るんだ」。「たち際(ぎわ)に縁起の悪い事を仰有るのね」。「これほど縁起のいい事はないさ。即身成仏、と云ってこのまま仏様になるんだ。帰って来ると俺の頭の上に後光(ごこあ)がさしているから---。とにかく、俺の事は心配しなくていいよ。お前は自分の身体に気をつけるんだ。それから赤ちゃんを特に気をつけて」。「つまりおんばさんになった気でね」。「おんばさんでも母親でもいい。とにかく、暫く細君を廃業した気になっていて貰いたい。未亡人になつた気でもいい」。「貴方はどうしてそういう縁起の悪い事を云うのがお好きなの?」。「虫が知らすのかな」。「まあ!」。 謙作は笑った。実際彼は今日の出立(しゅったつ)を「出家」ぐらいの気持でいたのだが、そういう気持をそのまま現わして出るわけには行かなかった。丁度いい具合に話が笑談(じょうだん)になったのを幸い、そろそろ出かける事にした。花園駅から鳥取行に乗る事にした。「もう送らなくていいよ。なるべく簡単な気持で出かけたいから」。お栄が茶道具を持って出て来た。「三時に家を出ます。---それからお前、仙に車を云わしてくれ。三時」。「もう少し早くしてご一緒に妙心寺辺まで歩いちゃ、いけない?」。「この暑いのに歩いたって仕方がないよ」。「------」。直子はちょっと不服な顔をして、台所へ出て行った。「又、先(せん)みたように瘠(や)せこけて帰って来ちゃあ、いやですよ」。お栄は玉露を叮嚀に淹(い)れながら云った。「大丈夫。何もかも卒業して、人間が゜変わって還(かえ)って来ますよ」。「時々お便りを忘れないようにね」。「今も云ったところだが、まあ便りはしないと思っていて下さい。便りがなければ丈夫だと思ってようござんす」。「今度は三人だから淋しくはないが」。「赤坊を入れて四人だ」。「そうそう。赤ちゃん一人で二人前かも知れない」。「鎌倉へは手紙を出しませんからね。あなたから、できるだけ何気なく書いて出しといて下さい。余計な事を書かずに」。お栄は点頭(うなず)いた。謙作は茶を味わいながら、柱時計を見上げた。二時を少し廻っていた。直子が赤児(あかご)を抱いて出て来た。まだ眠足りない風で、顔の真中を皺にしながら、眼をまぶしそうにしている。「お父様のご出発で、今日は感心に泣かないわね」。「その顔はどうしたんだ」。謙作は笑いながら指先で赤児の肥(ふと)った頬を突いた。「もう少し、機嫌のいい顔をしてくれよ」、赤児は無心に首をぐたりくだりさしていた。「医者は如何なる場合にも病院のを頼めよ。近所の医者は直謙(なおのり)の時でこりごりした」。「ええ、そりやあ大丈夫。第一病気になんぞさせない事よ」。「今のうちはお乳だけだから、心配ないが、来年の夏あたりは何でも食べるようになるから余程気をつけないとね」。お栄は直子に茶をつぎながら云った。謙作は風呂場へ行って水を浴び、着物を更えた。そして暫くすると、車が来たので、大きなスーツケースを両足の間に立て、西へ廻った暑い陽(ひ)を受けながら一人花園駅へ向った。 嵐山(らんざん)から亀岡までの保津川の景色は美しかった。が、それよりも彼は青々とした淵(ふち)を見ると、それに浸(つか)って見たかった。川からきりたった山々の上に愛宕(あたご)が僅かにその頂を見せていた。彼はいつも東から見る山をもう西から見ていた。そして彼の頭には瞬間衣笠の家が遠く小さく浮んだ。綾部、福知山、それから和田山へ来て、漸く夏の日が暮れた。彼はその晩、城崎へ泊る事にして、豊岡を出ると、、車窓から名高い玄武洞を見たいと思っていたが、暗い夜で、広い川の彼方に五つ六つ燈火(あんり)を見ただけだった。城崎では彼は三木屋というのに宿った。車で見て来た町の如何にも温泉場らしい情緒が彼を楽しませた。高瀬川のような浅い流れが街の真中を貫いている。その両側に細い千本格子(ごうし)のはまった、二階三階の湯宿が軒を並べ、眺めは寧ろ曲輪(くるわ)の趣に近かった。又温泉場としては珍しく清潔な感じも彼を喜ばした。一の湯というあたりから細い路を入って行くと、桑木細工、麦藁細工、出石焼、そう云う店々が続いた。殊に麦藁を開いて貼った細工物が明るい電燈の下に美しく見えた。宿へ着くと彼は飯よりも先ず湯だった。直ぐ前の御所の湯というのに行く。大理石で囲った湯槽(ゆぶね)の中は立って彼の乳まであった。強い湯の香りに、彼は気分の和らぐのを覚えた。出て、彼は直ぐ浴衣(ゆかた)が着られなかった。拭いても拭いても汗が身体を伝わって流れた。彼は扇風機の前で暫く吹かれていた。傍のテーブルに山陰案内という小さな本があったので、彼はそれを見ながら汗の退(ひ)くのを待った。 大乗寺、俗に応挙寺というのがあった。それは城崎から三つ先の香住(かすみ)という所にある。彼は翌日其の所へ寄って見ようと思った。子供から応挙の名を聞いていたが、その後、狗子(くし)や鶏や竹などの絵を見て彼は少しも感服しなかった。第一円山派というものに殆ど興味を持たなかったが、再びこの辺へ来るかどうか分らぬ気がしたので、寄って見る気になった。此所が暑いのか、その晩が暑いのか、何しろ蒸し暑くて彼は寝つかれなかった。この湯は春秋、或いは冬来て却っていい所かも知れぬと思った。翌朝起きたのは六時頃だった。彼は寝不足のぼんやりした頭で芝生の庭へ出て見た。直ぐ眼の前に山が聳え、その山腹の松の枯れ枝で三四羽の鳶(とび)が交々(かわねがわる)啼いていた。庭に、流れを引き込んだ池があり、其所には青鷺(さぎ)が五六羽首をすくめて立っていた。彼はまだ夢から覚めないような気持だった。十時頃の汽車で応挙寺へ向う。香住駅から車で行った。 応挙の書生時代、和尚が応挙に銀十五貫を与えた。応挙はそれを持って江戸に勉強に出た。その報恩として、後年この寺ができた時に一門を引き連れ、寺全体の唐紙へ揮毫(きごう)したものだという。応挙が一番多く描いていた。その子の応瑞(おうずい)、弟子では呉春、芦雪(ろせつ)もあり、それぞれ面白かった。応挙は書院と次の間と仏壇の前の唐紙を描いていた。書院の墨絵の山水が殊によく思われた。如何にも律儀な絵だった。次の間は郭氏儀(かくしぎ)、これには濃い彩色があり、もう一つは松に孔雀だった。呉春の四季耕作図は温厚な感じで気持ちよく、芦雪の群猿図(ぐんえんず)は奔放で如何にも芦雪らしく、八枚の右の二枚は構図からも描法(びょうほう)からも、為事(しごと)を投げ出して了ったような露骨な破綻を見せていた。酒に酔った芦雪が眼に浮び、呉春との対照が面白かった。応挙の模写と云う禅月大師の十六羅漢が未完成のまま庫裏(くり)の二階に陳列してあった。沈南ピンの双鷲図(そうしゅうず)、浪の間に頭を出している岩の上に雌鷲(めわし)が足を縮め、両翼を開き、脊を低く首をめぐらし、雄鷲(おわし)を見上げながら立っている。上の岩に真直ぐに立つて雄鷲が強い眼差(まなざ)しでそれを見下ろしている。雌鷲の子を産む為の本能が如何にも露骨に描き出され、そしてそれを上から強く見下している雄鷲の態度も謙作には興味があつた。「もう他には---?」。謙作は背後(うしろ)に立っている小坊主を顧みた。「まあ、絵はこんなものですが、この他に左甚五郎が彫った竜というのが屋根にあります」。二人は庫裏から下駄を穿いて、戸外へ出た。戸外は何時の間にか曇っていた。二人は本堂を左へ廻った。石段から一間ほど登った所にちょっとした平地(ひらち)がある。其所から、入母屋破風(はふ)に置かれた大きな丸彫の竜を望んだ。竜の写実だと思い、彼は軽い可笑味(おかしみ)を覚えた。「これは実物大ですね」。そう云って笑ったが、小坊主には通じなかった。「おお、降って来た」。仰ぎ見た謙作の顔に大粒な雨があたった。「この竜が雨を呼んだのだ」。彼はこんな笑談(じょうだん)をいいながら又庫裏の方へ還って来た。 |
| 十二 |
| その晩、謙作は鳥取に向った。此所では幅一里長さ七里に亘(わた)る海岸の砂原にあると云う大擂鉢(おおすりばち)、小擂鉢のというもの、それから多鯰ケ池(たねがいけ)というその砂原に添うた小さな湖の見物を勧められたが、南里かを車に揺られて行くのが、もう億劫で、絵葉書を買って済ました。晩飯の給仕に出た若い女中は多鯰ケ池の伝説、湖山長者(こやまちょうじや)伝説などを彼に聞かせた。多鯰ケ池の話ではお種という娘が大蛇になってその池に住んでいたが、或る時、鳥取の侍を追いかけ、侍が家へ逃げ込んで門を閉めたのを口惜しがり、自身の鱗(うろこ)を三枚門の扉に貼り付けて帰って行った。その鱗は最近までその家に伝えられてあったという事を真面目に話していた。謙作は翌日の天気模様を気にしながら寝た。もし雨になればもう一日何所かへ泊らねばならぬのが今は少し面倒になっていた。東郷池の東郷温泉なども面白そうに思われたが、それよりも早く、涼しい大山に登り、延び延びした気持になりたかった。夜中、驟雨(しゅうう)の音を聞いて、彼はこれならば却ってあしたはいいかも知れぬと思った。翌日は果たしていい天気だった。ジリジリと照り付けられる一日が想われるような朝だった。彼は九時頃の汽車に乗ったが、又前日のように何十というトンネルをくぐる事が、おもいでもあった。 彼は前夜、町で買って来た帝国文庫の高僧伝を開き、元三(がんさん)大師の条(くだり)を少し読んで見たが、直ぐ疲れて了った。湖山池の景色は良かった。湖山長者が田植えの日暮れに日輪を呼び返した罰で、その持田(もちだ)が一夜にこういう池になつて了ったという伝説はこの池としてよくできていると思った。低い山と山との間の如何にも耕地として適(ふさ)わしい広い場所が、一面の水をたたえている様は、出水(しゅっすい)の田圃(たんぼ)と見れば見られる眺めたった。この辺の伝説をよく書いた小泉八雲の物にこれはないかしら---そう云えばハーンの物を少し持つて来ればよかったと彼は思った。東郷池は故山池に較べ、何の趣もない湖だつた。伝説があるかどうか彼は知らなかったが、恐らくないだろうと思った。とにかく人口に膾炙(かいしゃ)される伝説を持った場所は何かの意味でそういう趣きを具(そな)えているものだと思った。 上井(あげい)、赤崎、御来屋(みくりや)。彼は汽車の窓から飽かず外の景色を眺めて来た。盛夏の力と云うようなものが感ぜられ、彼は近頃に珍しく元気な気持になった。二尺程に延びて密生した稲が風もないのに強い熱と光の中に揺れて見えた。「ああ稲の緑が煮えている」。彼は亢奮しながら思った。実際稲の色は濃かった。強い熱と光と、それを真正面(まとも)に受け、押合い、へし合い歓喜の声をあげているのが、謙作の気持には余りに直接に来た。彼は今更にこう云う世界もあるのだと思った。人間には穴倉の中でいがみ合っている猫のような生活もあるかわりに、こう云う生活もあるのだと思った。今日の彼にはそういう強い光が少しも眩(まぶ)しくなかった。大山という淋しい駅で汽車を下りた。車夫を呼んで訊くと、大山までは尚六里あるとの事だった。それも車で行けるのは初めの三里で、後は徒歩で歩くのだという。「それじゃあ、この荷物はどうするかね、馬にでもつけて行くのか?」。「俺(わし)が背負(しょ)つて行きます」。車夫は五十余りの瘠せた男だった。「本が入っているから却々(なかなか)重いぜ」。「なに、このくらいは---」。車夫はそれをもう一度、さげて見て笑った。「お前はもう飯は済んだのか」。「旦那は?」。「私は汽車で弁当を食って来た」。「それじゃあ直ぐ出かけましょう。俺(わし)は分けの茶屋で何か食わして貰えばいい」。これから六里の道を一緒に行くと云う事が既に彼らを幾らか親(ちか)しくしている感じだった。謙作は車に乗った。「日は長えが、何しろ半分からはずっと登りだからね」。前に遠く、線の立派な大山を眺めながら謙作はこの炎天にこの車夫があすこまで荷を運ぶかと思うと不思議な気がした。「上はよほど涼しいだろうね」。「そりゃあ涼しい。昔はこの辺の水と云やあ、みんなあの山の雪を持って来たものだ。冬、積み重ねて置いたのを夏になって、切り出して来るのだ。俺は若い頃、その人足をやっていた」。 狭い通りで子供達が騒いでいた。人取りのような遊びで、子供達はそれに夢中で、却々(なかなか)車をよけなかった。老車夫は丁度其所に落ちていた細い竹の枝を拾うと、子供達の頭をちょいちょいと叩きながら行った。「老いぼれ」、「阿呆」。子供達は毒づいていたが、老車夫は笑いながら、手の届く子供の頭は一々叩いた。間もなく、その狭い通りから急に広い道へ出た。路幅は六七間、両側に軒の低い家が並んでいた。それが一層この道を広々と、又明るい感じに見せた。三又(みつまた)に竹竿を渡し、それへ白い無闇と長い物が一杯掛けてあった。片側半分ほどは軒並みそれだつた。干瓢(かんぴょう)だという。「干瓢にしちゃあ幅が広いな」。「まだ乾かねえからさ」。「名物にでもなつているのか」。「なに、名物という程じゃあない」。馳(か)けたり、歩いたり、二人は気楽にこんな話をしながら行った。三里来て、其所からはもう車は通わなかった。老車夫は車を百姓家に預け、麻縄で荷を背負った。謙作は麻帷子(あさかたびら)の裾を端折(はしょ)った。道から細い坂を登ると、上は広々とした裾野だった。最近まで軍馬養成所になっていたとか、広々した気持のいい場所だった。一体大山は馬市でも名高い所だと云う。二人はゆるい傾斜の原をゆつくり歩いて行った。 |
| 十三 |
| 竜胆(りんどう)、撫子(なでしこ)、藤袴(ふじばかま)、女郎花(おみなえし)、山杜若(やまかきつばた)、松虫草、吾亦紅(われもこう)、その他、名を知らぬ菊科の美しい花などの咲き乱れている高原の細い路を二人は急がず登って行った。放牧の牛や馬が、草を食うのを止め、立って此方を眺めていた。所々に大きな松の木があり、高い枝で蝉が力一杯啼いていた。空気が澄んで山の気が感ぜられたが、登り故に却々暑かった。そして背後に遥か海が見え出すと、二人は所々で一服しながら行った。「さあ、もう一ㇳ息だ」。「荷は思ったより重いだろう」。「うむ、ずっしりといやに重いね。こりゃ本かね」。「辛いようなら、その茶屋で少し出して行ってもいい。ついでの時に運んで貰うとして」。「なに大丈夫だ。分けの茶屋で飯を一つよばれよう。そうすりゃあ元気が出らあね」。「お前は酒を飲むか?」。「たんとはいけないね」。「其所で少し飲んだらいいだろう」。「直しを一杯御馳走になるか。旦那はどうだね」。「私は駄目だ」。「全然(まるで)いけないという事はないだろう。直しを一杯やつて、一時間ばかり昼寝をして行っちゃあどうだ」。「昼寝はともかく、ゆっくり休んで行こう」。「もう三四町だ。其所は分けの一つ家(や)といって、一里四方人家のない所だ。昔は恐ろしい爺(おやじ)がいて、よく旅人の物を盗(と)ったりしたものだ」。「何時頃の話だ」。「俺(わし)の若い頃の話さ。大山の蓮浄院(れんじょういん)へ竹槍を持って押込みをやったのが知れ、茶屋の前で攻め木にかけられているのを見た事がある。海老(えび)攻めと云うので見ていられなかったね。真っ白い長い髪を振ってわあわあ云う奴を段々にしめて行くのだ。俺は丁度雪を背負(しょ)って、其所を通りかかって見たのだが、海老攻めというのはえらい拷問だね。身体をぎゅうぎゅう海老のように曲げちまうんだから」。車夫は尚、その時の話を精しくした。頬被りをした強盗が住職を嚇(おど)している間に、気の利いた小坊主が本堂の鐘を乱打した。それが火事その他不時の場合を知らす撞(つ)き方なので、他の寺々でも応じて鐘を撞き出したが、静かな真夜中だけに森や谷にこだましてごんごんごんごんそれが響いた。或る僧が戸外に出ていると恰度(ちょうど)月の入りで、森の中を真っ白な髪を振り乱しながら逃げて行く老人の姿を遥かに見たと云う。「山には竹はないが、その頃一つ家の前だけに竹藪があった。そこで藪を探すと、捨てて行った竹槍にすつきり切り口の合う株が見つかった。これには如何に強情な爺(おやじ)も恐れ入ったそうだ。調べ上げると他にも色々悪い事をしてたのが分って、間もなく米子(よなご)で死刑になったよ」。 やがて、二人はその茶屋に着いた。屋根の低い広々とした平家(ひらや)だった。軒前(のきさき)の大きな天水桶にはなみなみと水がたたえてあり、その下で襷(たすき)をかけた六十ばかりの婆さんが、塩びきの鮭(さけ)を洗っていた。「暑い暑い」。車夫は其所の縁台に重い荷を下ろした。広い平家は真中に土間が奥まで通ってい、その左が住まい、右が客用の間になっていた。そしてその客用の間の真中に八十近い白髪の老人が立てた長い脛(すね)を両手で抱くようにして、広い裾野から遠く中の海、夜見ケ濱(よみがはま)、美保の関、更にそと海まで眺められる景色を前に、静かに腰を下ろしている。老人は謙作達が入って来たのも気附かぬ風で、遠くを眺めていた。「車屋にめしと酒」。謙作は婆さんに云った。「私には菓子と、それからサイダーを貰おうか」。「お爺さん。お爺さん」。婆さんは立って濡れ手を前へ下げたまま老人を呼んだ。「私は手が臭いからお客様に菓子とサイダーを上げて下さい」。老人は黙って立った。脊が高く丁度風雨にさらされた山の枯木のような感じがした。「菓子と何だね?」。「お爺さん、サイダーは俺が持って来る。菓子だけ出しておくれ」。車夫はそういい、自身流しの方へそれを取りに行った。「此方の方が冷えているのかね」。爺さんは棚から硝子(がらす)の皿を取り、石油缶から駄菓子を手で摑(つか)み出し、それを謙作の前へ持って来た。そして「おいで---」。こういってちょっと頭を下げると、又元いた場所へ還って腰を下ろした。「これ食べるかね」。婆さんは塩びきを切りながら車夫に云った。「結構だね」。車夫は胸に流れる汗を拭きながら答えた。謙作は扇を使いながら、サイダーを飲み、それから遠い景色を眺めた。そして彼は二三寸にのびた白髪頭の老人を背後(うしろ)から眺め、今、車夫に聞いた昔の爺(おやじ)とを想い較べ、それらが同じ場所に住んでいるだけに如何にも面白い対称に感じた。この老人にすればこれは毎日見ている景色であろう。それを厭(あ)かずこうして眺めている。一体この老人は何を考えているのだろう。勿論将来を考えているのではない。又恐らく現在を考えているのでもあるまい。長い一生、その長い過去の色々な出来事を老人は想い出しているのではあるまいか。否(いな)、それさえ恐らく、今は忘れているだろう。老人は山の老樹のように、或いは苔むした岩のように、この景色の前に只其所に置かれてあるのだ。そしてもし何か考えているとすれば、それは樹が考え、岩が考える程度にしか考えていないだろう。謙作はそんな気がした。彼にはその静寂な感じが羨ましかった。 老人のいる左手の壁に寄せて、米俵が幾つか積み上げてあつた。その後ろで先刻(さっき)から何かゴソゴソ音がしていたが、不意に一匹の仔猫(こねこ)が其所から米俵の上へ現れた。仔猫は両方の耳を前へ向け、熱心に今自分の飛び出して来た所を覗き込んでいた。そして身体は凝(じ)つとしているが、長い尾だけが別の生き物のように勝手に動いていた。すると、下からも丸い猫の手がちょいちょい見えた。「旦那も直しを一杯どうだね」。車夫は今、自分がそれを注(つ)いで貰ったコップを持って謙作に勧めに来た。「直しと云うのは飲んだ事がないから」。「まだ口をつけないから、これを一ㇳ口やって御覧なさい」。「まあよそう」。「そうかね。夏はこれにかぎるがね」。そう云って、車夫はそれへ口をつけながら、自分の膳へ還って行った。「あの猫は此所で生まれたのか?」。「あれは此所で生まれたのかね?」。車夫が取次いで婆さんに訊いた。「去年貰ったのが、生んだのだよ」。「そうか。早いもんだな。雄(おん)もいるのかね」。「なに雄は居ないのだが、何所かで子種を貰って来たよ」。「一里四方人家のない所で、何所から貰って来たかな」。「二日ほどいなくなったが、〇〇あたりまで行ったかも知れない」。老人は置物のように尚皆の方へ背を向けたままでいた。二匹の仔猫は俵の上で上になり下になりふざけていたが、そのうち誤って一匹が俵から下へ落ちた。落ちた子猫は急に興ざめのしたキョトンとした様子で哀れっぽい声で二タ声三声啼いた。何所からか急いで親猫が出て来て仔猫の身体を嘗めてやった。 乗馬ズボンに巻脚絆(まききゃはん)をした三十余りの男が入って来た。「やあ」。そういってかまち*の所で後ろ向きになると、股を開き両手を腿(もも)に、さも疲れたようにドスンと腰を下ろした。「山田を探して山まで行ったが、居(お)らなんだ。お婆さん、今日此処を通らんかったかね?」。「誰が」。「山田が」。「見かけなかったね」。「又御来屋(みくりや)へでも出掛けたかな」。「昨日足を折った馬はどうしたかね」。「それで山田を探しているんだが、居(い)にゃあ仕方がない。殺して埋めちまおう」。「山田さんの馬かい」。「そうだ」。「えらい損害だね」。「時に、今日は肴(さかな)は何だい」。「鮭の塩びきは?」。「塩びきか---。それよりするめでも焼いて貰おうか」。婆さんは酒をつけ、するめを焼きながら、「今年は山でも蚊が出たそうだね」。「そんな事も聴かなかったが、そうかね」。「此処らは月初めから蚊帳(かや)を釣ってるよ」。親猫はするめの臭いで、五月蠅(うるさ)くその辺を立廻り、婆さんの裂いたするめの皿へ鼻をつけそうにしてはその度、頭を叩かれ、眼を細くし、耳を寝かせていた。 暫くして謙作と車夫とはこの茶屋を出た。三十分ほど歩く内に謙作は又喉(のど)が乾いて来た。車夫はもう少し行くといい流れがあるからと云った。しかし行って見ると、流れは涸(か)れて底の砂が干(ひ)割れていた。「昨晩、鳥取では大分降ったが、この辺は降らなかったかな」。謙作は腹立たしそうに云った。車夫はもう十町ばかりで、鳥居の所に冷水がひいてあるからと慰め顔に云った。そして、「寺は何所にするかね。景色はないが、さっき話した蓮浄院の離れが空いていると、勉強にはいいと思うがね」。「とにかく、行って見た上にしよう」。「暫く滞在するのかね?」。「気に入れば永くいたいと思うのだ」。「永いと云っても夏だけの所だよ。秋になりゃあ、下にも幾らもいい温泉場があるから、山に居たってつまらない。第一ろくな食い物がないから、余り永くは居られないよ」。「寺は精進か?」。「いや、生臭(なまぐさ)でも何でも食わすよ。梵妻(だいこく)もいるし、開けたもんだ。坊主は馬の売り買いばかり熱心にやっていらあね」。謙作は叡山に次ぐ天台の霊場というように聞いていただけにこの話にはいささか落胆(がっかり)した。丹塗(にぬ)りの剥げ落ちた大鳥居の傍(わき)に宿屋がある。二人は其所で漸く冷水にありついた。車夫は寺まで尚五六町あると云い、「この宿は気に入らないかね?」と小声で訊いた。謙作は黙って首を振った。車夫は少し荷に参って来たらしい。約束よりは賃金を増してやろうと謙作は思った。絵葉書と巻煙草を買って出た。 大山神社への道から右へ降り、石のごろごろした広い河原へ出た。河原はかなりの傾斜で森と森の間を裾野の方へ下っている。。「地蔵の切分け」というので、川の流れ出た所が恰(あたか)も切りさいたように断崖が二つに分れていた。二人は河原を越し、急な坂路を薄暗い森の中へ登って行った。右が金剛院、左が一段高くなつて蓮浄院だつた。庫裏の土間に入り車夫が声をかけると、四十前後の顔の角張った女が出て来て、謙作と荷とを見較べながら、「暫く御滞在ですか」と云った。庫裏の炉端で白い単衣(ひとえ)を着た若い和尚が、伯楽(ばくろう)風の男を相手に酒を飲みながら高声(たかごえ)に話合っているのが見えた。「暫く御厄介になりたいんです」。女は心元ない風で後ろを向き、「ちょいと、どうです?」と和尚へ呼びかけた。「ようこそ」。酒で赤い顔をした和尚が出て来て、立ったまま取ってつけたようなお辞儀をした。「泊めて頂けますか」。「お泊めせん事もございませんが、この寺の先住が少し悪いと云うので、実は明日江州(ごうしゅう)の坂本まで出掛ける事にしているのですが、人手が足らんので、------が、とにかくお上がり下さいませ。もしお世話できんようでしたら、他の寺をご紹介しますで」。謙作は離れに通された。それは書院作りの座敷、次の間、折れて玄関と云う、何れも四畳半ばかりの家だった。先々住の隠居所に建てたもので、長押(なげし)から長押へ竹竿を渡し、それに縁(ふち)のない障子が何枚も重ねてある。それは寒中(かんちゅう)、その高さに障子で座敷をくぎる、一種の暖房装置だった。小さな座敷の書院作りは少し重苦しい感じもしたが、結局三間共に貸してくれるとの事で謙作は満足した。車夫はこの寺に一泊し、翌朝還って行った。 |
| 十四 |
| 永年、人と人と人との関係に疲れ切って了った謙作には此所の生活はよかった。彼はよく阿弥陀堂という三四町登った森の中にある堂へ行った。特別保護建造物だが、縁など朽ち腐れ、甚く荒れはてていた。しかしそれが却って彼には親しい感じをさせた。縁へ登る石段に腰かけていると、よく前を大きなヤンマが十間程の所を往ったり来たりした。両方に強く翅(はね)を張って地上三尺ばかりの高さを真っ直ぐに飛ぶ。そして或る所で向きを変えると又真直ぐに帰って来る。翡翠の大きな眼、黒と黄の段だら染め、細くひきしまった腰から尾への強い線、---みんな美しい。殊にその如何にもしつかりした動作が謙作にはよく思われた。彼は人間の小人(しようじん)、---例えば水谷のような人間の動作とこれと較べ、どれだけかこのり小さなヤンマの方が上等か知れない気がした。二三年前京都の博物館で見た鷹と金鶏鳥(きんけいちょう)の双幅(そうふく)に心を惹かれたのも要するに同じ気持だったろうと、それを憶い出した。彼は石の上で二匹の蜥蜴(とかげ)が後足で立ち上がったり、跳ねたり、からまり合ったり、軽快な動作で遊び戯れているのを見、自らも快活な気分になった。彼は又此所に来て鶺鴒(せきれい)が馳(か)けて歩く小鳥で、決して跳んで歩かないのに気がついた。そう云えば鳥(からす)は歩いたり、跳んだりすると思った。よく見ていると色々なものが総て面白かった。彼は阿弥陀堂の森の真中に黒い小豆(あずき)粒のような実を一つづつ載せている小さな灌木(かんぼく)を見た。掌(てのひら)に大切そうにそれを一つ載せている様子が、彼には如何にも信心深く思われた。 人と人との下らぬ交渉で日々を浪費して来たような自身の過去を顧み、彼は更に広い世界が展(ひら)けたように感じた。彼は青空の下、高い所を悠々舞っている鳶の姿を仰ぎ、人間の考えた飛行機の醜さを思った。彼は三四年前自身の仕事に対する執着から海上を、海中を、空中を征服して行く人間の意志を賛美していたが、不知(いつか)、全(まる)で反対な気持になっていた。人間が鳥のように飛び、魚のように水中を行くという事は果たして自然の意志であろうか。こういう無制限な人間の欲望がやがて何かの意味で人間を不幸に導くのではなかろうか。人智におもいあがっている人間は何時かその為め酷い罰を被(こうむ)る事があるのではなかろうかと思った。かってそういう人間の無制限な欲望を賛美した彼の気持は何時かは滅亡すべき運命を持ったこの地球から殉死させずに人類を救い出そうという無意識的な意志であると考えていた。当時の彼の眼には見るもの聞くもの総てがそう云う無意識的な人間の意志の現われとしす感ぜられなかった。男と云う男、総てその為め焦っているとしか思えなかった。そして第一に彼自身、その仕事に対する執着から苛立ち焦る自分の気持をそう解するより他はなかったのである。然るに今、彼はそれが全く変っていた。仕事に対する執着も、その為め苛立つ気持もありながら、一方遂に人類が地球と共に滅びて了うものならば、喜んでそれも甘受できる気持になっていた。彼は仏教の事は何も知らなかったが、涅槃(ねはん)とか寂滅為楽(じゃくめついらく)とかいう境地には不思議な魅力が感ぜられた。彼は信行に貰った臨済録など少しずつ読んで見たが、よく分らぬなりに、気分はよくなった。鳥取で求めて来た高僧伝は通俗な読み物ではあったが、恵心僧都(えしんそうず)が空也上人を訪ねての問答を読みながら彼は涙を流した。「穢土(えど)を厭(いと)い浄土を欣(よろこ)ぶの心切なれば、などか往生を遂げざらん」。簡単な言葉だが、彼は恵心僧都と共に手を合わせたいような気持がした。 彼は天気が良ければ大概二三時間は阿弥陀堂の縁で暮らした。夕方はよく河原へ出て、夏蜜柑(みかん)ぐらいの石を河原の大きな石に力一杯投げつけたりした。かあんと気持よく当って、それが更に他の石から石と幾度にも弾んで行く。それがうまく行った時は彼はわけもない満足を覚えながら帰って来るが、どうしても、うまく行かない時は意地になってこんきく投げた。 彼は大山の生活には大体満足していたが、たた寺の食事には閉口した。彼は出掛けに食料品を送る事を断ったぐらいで、粗食は覚悟していたが、其所まで予期できなかったのは米の質が極端に悪い事だった。彼はそれまで米の質など余り気にする方ではなかったが、食うに堪えない米で我慢していると、不知(しらず)減食する結果になり身体が弱ってくるように思われた。寺の上(かみ)さんは好人物で彼の世話をよくした。山独活(やまうど)の奈良漬を作る事が得意で、それだけはうまかった。鳥取へ嫁入った寺の娘が赤児を連れて来ていた。十七八の美しい娘だった。座敷へは余り入って来なかったが、彼の窓の下へ来てよく話した。「やや児のような者にやや児ができてどうもなりません」。娘はこんな事を云って笑った。人から云われたのをそのまま真似をして云っているとしか思われなかった。母親一人で忙しく働いているのに娘はいつも赤児を抱いてぶらぶらしていた。謙作はこの娘に対して別に何の感情をも持たなかっだ、娘がよく窓の外へ来て立ち話をして行く気持には、娘ながらに、既に人妻となったという事で男を恐れなくなったのだと思った。そして彼は直子の過失も直子がまだもし処女であったら、或いはああいう事は怒らなかったのではなかろうかと考えたりした。 或る日、寺の上さんが手紙を持って謙作の所へ相談に来た。四五十人の団体の申込みだった。「どうしましょう」。しかし謙作には分らなかった。「炊事はできるんですか」。「できん事はありません」。「そんなら引受けたらどうですか。---尤(もっと)も私はなんにも手伝えないが」。上さんは尚迷うらしく少時(しばらく)考えていたが、遂に引き受ける事に決心した。そして独り言のように、「お由(よし)がもう少し役に立つといいんだけど」と云った。「赤ちゃんが居るから------それより竹さんをお頼みなさい」。竹さんというのは麓(ふもと)の村の屋根屋で、大山神社の水屋の屋根の葺き替えに来ている若者だった。板葺きの厚い屋根で、山の木で、その折板(へぎ)から作ってかかるので一人為事(しごと)では容易な業(わざ)ではなかった。寝泊り食事は寺の方にして貰って、その労力を奉納するのだという話だった。謙作はこの人に好意を持ち、仕事をしているところで、よく話し込むことがあった。謙作は引受ける返事の端書を書かされた。二三日して謙作は机に倚(よ)り、ぼんやりしていると、下の路から上さんが「来ました、来ました」とせかせか石段を馳登(かけのぼ)って来た。 如何にも大事件らしいその様子が可笑しかった。珍しくもなさそうな事を何故こんなに騒ぐのかと思った。しかしいつもは和尚も働くらしく、上さん一人ではそれは大分重荷だったに違いない。上さんは午後になって何度か坂の上まで見に行ったが、今、四五十人の人がぞろぞろ河原を渡って来るのを見、そんなに興奮しているのであった。間もなく団体の連中が着くと、寺の方は急に騒がしくなった。謙作は手伝えるものならば手伝ってやりたいと思ったが、できないので、そのまま散歩に出た。日が暮れ、彼が還って暫くして漸く晩飯が赤児を抱いた娘の手で運ばれた。「自分でつけるから構いませんよ」。「どうせ何もしないんですから」。そして娘は笑いながら、「今夜は旦那さんの傍(わき)に寝させて貰います」と云った。謙作はちょっと返事に困った。勿論傍と云うのはこの離れの玄関の間の事だろうとは思ったが、きっと蚊帳などは足りなくなっているに違いないので、多少紛らわしい気もするのであった。その夜、謙作はいつものようにして寝た。娘はそれきり顔を出さなかった。それで当り前なのだが、彼は娘が何故不意にそんな事を云い出したか不思議な気がした。 |
| 十五 |
| その夜、謙作は妙な夢を見た。神社の境内は一杯の人出だ。ゆるい石段を人に押されながら登って行くと、遠く石段の上に大社造りの新しい社(やしろ)が見える。今、其所で儀式のような事が始まっている。しかし彼は群集に隔てられ、容易に其所へは近寄れなかった。石段には参詣人(さんけいにん)の腰ほどの高さに丸太を組んで板を敷いた別の通路ができている。儀式が済むと生神様(いきがみさま)が其所を降(くだ)って来るという事が分っていた。群集がどよめき立った。儀式が済んだのだ。白い水干(すいかん)を着た若い女---生神様が通路の端に現れた。そして五六人の人を従え、急ぎ足に板敷の上を降って来た。身動きならぬままに押され押され少しずつ押上げられていた彼はこの時、もっとぐんぐん其方(そっち)へ近寄って行きたい衝動を感じた。 生神様は湧立(わきた)つ群集を意識しないかのように如何にも無造作な様子で急いで板敷の路を降って来る。それは今鳥取から帰っているお由だった。彼はそれを今見て知ったのか、最初から知っていたのか分らないが、とにかくその女の無表情な余り賢い感じのしない顔は常の通りだった。そしてそれは常の通りに美しくもあった。尚それよりも生神様に祭り上げられながら少しも思いあがった風のないのは大変いいと彼は思った。彼はお由が生神様である事に少しも不自然を感じなかった。むしろこの上ない霊媒者である事を認めた。お由は殆ど馳けるようにして彼の所を過ぎて行った。長い水干の袖が彼の頭の上を擦って行った。その時彼は突然不思議なエクスタシーを感じた。彼は恍惚としながら、こうして群集はあの娘を生神様と思い込むのだ---そんな事を考えていた。夢は覚めた。覚めて妙な夢を見たものだと思った。群集は前日の団体が夢に入って来たに違いない。唯(ただ)あの不思議なエクスタシーは何であろう。そう考えて、夢ではそう感じなかったが、今思うと、それには性的な快感が多分に含まれていたように思い返され、彼は変な気がした。そんな事とは遠い気分でいる筈の自分がそんな夢を見るのは可笑しな事だと思った。 翌朝(あくる朝)、軒に雨だれの音を聴きながら眼を覚ました。彼は起きて、自ら雨戸を繰った。戸外(そと)は灰色をした深い霧で、前の大きな杉の木が薄墨色にぼんやりと僅かにその輪郭を示していた。流れ込む霧が匂った。肌には冷々(ひえびえ)気持が良かった。雨と思ったのは濃い霧が萱(かや)屋根を雫(しずく)となって伝い落ちる音だった。山の上の朝は静かだった。彼は楊枝(ようじ)と手拭(てぬぐい)とを持って戸外へ出た。そして歯を磨きながらその辺を歩いていると、お由が十能(じゅうのう)におき火を山と盛って庫裏から出て来た。「夜前(やぜん)は彼方(むこう)へ寝て往生しました。団体の人達が騒ぐので、やや児が眠られんのですわ」。「少しは考えたが、此方(こっち)はそんなにも八釜しく思わなかった」。「よっぽど引越ししょう思うて来て見ましたが、ようやすんでられる風じやでやめました」。謙作の夢の中のお由とは大分異(ちが)っていた。 「昨晩あなたが生神様になってる夢を見た」。「生神様て何ですの。そんなものありますの」。「天理教の何とか婆さんと云うのを知ってますか? 天理教を始めた人です。あなたがそう云う人になってるんだ。尤もあなたは婆さんじゃあなかった。あなたは若くて、そして私もどうやら信者の一人になってるらしいんだ」。「ふん」。お由はちょっと肩をすぼめて笑ったが、さて返事の為(し)ようもないと云う風で、少時(しばらく)黙った後、「竹さんのお父さんはその天理教で家をつぶした人です」と云った。「そう、---それで竹さんだけがこの山の信者なんですか」。「代々そうだったのをお父さんが天理教で家をつぶしたのですから、その方はよっぽど懲りたでしょう」。「尤も屋根の葺き替えを奉納するなどは幾らか天理教臭いところもあるけど---」。「------ですけど、本統に感心な人ですわ」。「そうらしい。毎日よく働いている」。「村でもあの人は別ものらしいです」。「どこか老成したようなところがある。それだけに若々しいところも少ないが」。「色々苦労があるからね」。「苦労------?」。「お父さんに家をつぶされたのは竹さんが子供の時ですからね、それだけでも大変なのに近頃又、人にも云えない苦労があるらしい噂です」。「へえ、そんな人なのかな。---それはそうと、昨日から手伝いに来てるんですか?」。「いいえ。お母さん、頼まんかったらしいです」。 彼が朝飯の膳についた時、お由は竹さんの人にも云えない苦労と云うのを話した。竹さんには三つ年上のまだ子供を産まない嫁がある。生来の淫婦(いんぶ)で、竹さん以前にも、以後にも、また現在にも一人ならず、情夫と云うような男を持っている女だった。そして竹さんは亭主と呼ばれるだけの相違で、事実は何人かの一人に過ぎなかった。それを承知で結婚した竹さんではあるが、やはりその為め大分苦しんだ。人からは別れろと云われ、自分でも幾度(いくたび)かそれを考えた。しかし竹さんには何故か、この女を念(おも)い断(き)る事ができなかった。意気地がないかにだ、そう思い、又実際にそれに違いないが、竹さんはどうしてもこの女を憎めなかった。絶えず面倒な事が起った。それは竹さんを入れた所謂(いわゆる)三角関係ではなく、竹さんを除いたそう云う関係で、面倒が絶えなかったのである。竹さんは女の不身持ちよりもこの面倒を見る事に堪えられなくなった。さりとてきっぱり別れようとはしなかった。「それはお話にならんですわ。男が来て嫁さんと奥の間にいる間、竹さんは台所で御飯拵(ごしらえ)えから汚れ物の洗濯まですると云うのですから。時には嫁さんに呼びつけられ、酒買いの走り使いまですると云うのですから」。「少し変わってるな。それで竹さんが腹を立てなければ、よっぽどの聖人か、変態だな。一種の変態としか考えられない」。 謙作は竹さんを想い浮べ、そう云う人らしい面影を探して見たが、分らなかった。しかし彼にもそう云う変態的な気持は想像できないことはなかった。「竹さん自身はどう云ってるんです」。「自家(うち)のお母さんなどには何か愚痴を云ってるらしいです」。「うむ」。「もう諦めてるんでしょう」。「諦められるかな」。「どうせ、そう云う嫁さんらしいです。で、それは諦めても狭い土地の事で、人の口がうるさいから、一つはそれで山に来ているらしいんです」。「苦労した人と聴けばそんなところも見えるけど、現在そう云う事がある人とはとても考えられませんね。よく松江節を唄いながら木を割っているが、そんな時の様子が如何にも屈託なさそうで羨ましい気がした」。「時々は沈んでいる事もありますわ」。「そう。それが本統だろうけど、あの人の顔を見て、そんな事があろうとはき全く想像できなかった」。「誰だって」。お由は急に笑い出した。「顏だけ見て、その人が間男されているかどうかは、分らんでしょうが」。「そうだ。それは正にそうだ」。謙作も一緒に笑った。「そこで私の顔を見て、あなたはどう思う。そういう事があると思うか、どうですか」。「ハハハハハハ」。 この時謙作はふと、留守を知って又要が衣笠村を訪ねていはしまいかという不安を感じ、胸を轟(とどろ)かした。しかし直子が再び過失を繰返すとは思えなかった。---思いたくなかった。そしてそう信じているつもりではあるが、それでもまだ何所かに腹からは信じきれない何か滓(かす)のようなものが残った。あの女は決して盗みをしない、これは素直に信じられても、あの女は決して不義を働かない、この方は信じても信じても何か滓のようなむものが残った。女と云うものが弱く、そう云う事では受身であるから、そう感ぜられるのか、それとも彼の境遇がそういう考え方をさせるのか分らなかった。が、とにかく、直子にはもうそういう事はあり得ない、彼は無理にも信じようとした。唯、要の方だけはその時は後悔しても、若い独身者の事で自分の留守を知れば心にもなく、又訪ねたい誘惑にかられないとは云えない気がするのであった。お栄と云う女がもう少し確(しっか)りし、且つ賢い女ならとにかく、人がいいだけで、そんな事には余り頼りにならないのを彼は歯がゆく思った。 |
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)