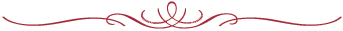
| 第4章の2(後編6)(6から10) |
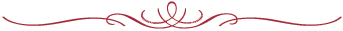
更新日/2021(平成31.5.1栄和改元/栄和3)年.8.10日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここで、「暗夜行路第4章の2(後編6)(6から10)」を確認する。 2021年.8.10日 れんだいこ拝 |
![]()
| 【暗夜行路後編第4章の2(後編6)(6から10)】 |
| 六 |
| 翌日謙作は一条通を東へ急ぎ足に歩いていた。南風は生暖かく、肌はじめじめし、頭は重かった。天候の故(せい)もあり、勿論寝不足の故もあったが、その割には気分が冴え、気持は悪くなかった。つまり彼はしん*で興奮していた。只、落ち着いて物が考えられなかった。断片的に色々な事が恰(あたか)もそれが廻転(かいてん)しているもののようにチラチラと頭にひらめくばかりだった。「直子を憎もうとは思わない。自分は赦(ゆる)す事が美徳だと思って赦したのではない。直子が憎めないから許したのだ。又、その事に拘泥する結果が二重の不幸を生む事を知っているからだ」。彼は前夜直子に云った事を又頭の中で繰返していた。「赦す事はいい。実際それより仕方がない。------しかし結局馬鹿を見たのは自分だけだ」。 下の森から京電に乗る習慣で、その方へ行ったが、丁度北野天神の縁日で、その辺は大変な人出だった。彼は武徳殿の裏から終点の方へ行った。しかしそこも大変な人で、飴売り、風船売り、玩具屋(おもちゃや)、あ水クリーム屋などで馬場の方まで賑わっていた。覗(のぞ)き絡繰(からくり)が幾つか鳥居の前の広場に並んでいた。「八百屋お七」が「金色夜叉(こんじきやしゃ)」や「不如帰(ほととぎす)」に更(かわ)っているだけで、人物の眼ばりをした緞帳(どんちょう)くさい顏や泥絵具の毒々しい色彩まで昔と少しも変らなかった。彼は千本通から市電に乗るつもりで上七軒(かみしちけん)へ入って行った。 「つまり、この記憶が何事もなかったように二人の間で消えて行けば申し分ない。---自分だけが忘れられず、直子が忘れて了って、---忘れて了ったような顔をして、---自分だけが忘れられず、直子が忘れて了って、---忘れて了ったような顔をして、---いられたら---それでも自分は平気で居られるかしら?」。今はそれでいいように思えたが、実際自信は持てなかった。お互いに忘れたような顔をしながら、憶い出している場合を想像すると怖ろしい気もした。「自分は又放蕩を始めはしないだろうか」。彼は両側の掛行燈(かけあんどう)の家々を見ながら、不図、こんな事も想った。彼は今日の自分が変に上ずっているように思えて仕方なかった。末松に今日は何事も話すまい。もしきりだして了ったら、恐らく下らぬ事まで饒舌(しゃべ)るに違いない。「そうだ、末松へやる土産物(みやげもの)を忘れて来た」。彼は帽子を脱ぎ、額の汗を拭(ぬぐ)った。千本の終点からは楽に乗れた。(その頃其処が終点だった) 戸外も夕方のように灰色をしていたが、電車の中は一層薄暗く、その上、蒸々(むしむし)して、長くいると、吐気(はきけ)でも催しそうに思われた。 実際暫くすると、彼は湿気と人いきれ*からたえられなくなった。そして烏丸の御所の角まで来ると、急いで電車を飛び降り、其所の帳場から人力に乗り換えた。岡崎の下宿では玄関に立つと、偶然二階から馳け降りて来た末松と向かい合った。「やあ。---上らないか」。「直ぐ出よう」。「とにかく、上がらないか。見せたい物がある」。「そいつはこの次にしよう」。謙作は今日ちょっとでも水谷とは顔を合したくなかった。末松は不思議そうな顔をした。「---じやあ、着物を更える間、待ってくれないか」。「動物園の前で待っている。---人を連れて来ちゃあ困るよ」。末松は解って急に笑い出した。「生憎(あいにく)、今、居ないよ。しかし直ぐ行く」。謙作はその路次を出た。道の正面に近く見える東山は暗く霞(かす)み、その上を薄墨色の雲が騒がしく飛んでいた。変に張りのない陰気臭い日だった。公園の運動場で自転車競争の練習をしている若者があった。赤色のシャツ、猿股の姿で、自転車の上に四ッ這いになり、頭を米搗(つ)き機械のように動かしながら走っていた。向い風では、上体を全体右に左に揺り動かし、如何にも苦しそうだが、再び追い風に来ると、急に楽になり、早くなる。謙作は往来端(おうらいばた)に立ち、少時(しばらく)それを眺めていた。 間もなく末松が来て、二人は歩きながら話した。「ちよっと見て貰えばよかったな。なんでも藤原時代の盛花(もりばな)をする器だというんだが、二三日前松原のきたない道具屋で見つけた。その内持って行くから見てくれないか」。「俺にも分らないよ、そんなもの」。大津からの電車に乗る事にし、広道の停車場で、其所のベンチに二人は腰を下ろした。「下らない奴を遠ざけるのは差支えないが、時任のように無闇と拘泥して憎むのはよくないよ」。末松は突然こんな風に水谷の事を云い出した。「実際そうだ。それはよく分っているんだが、遠ざける過程としても自然憎む形になるんだ。悪い癖だと自分でも思っている。何でも最初から好悪の感情で来るから困るんだ。好悪が直様(すぐさま)此方(こっち)出は無善悪の判断になる。それが事実大概当るんだ」。「それは当ったように思うんだろう」。「大概当る。人間に対しそうだし、何か一つの事柄に対してもそうだ。何かしら不快の感情が最初に来ると、大概その事にはそういうものが含まれているんだ」。謙作は昨夜水谷が停車場へ来ていた事、それが不愉快で、知らず知らず糸を手繰(たぐ)って行った自身の妙な神経を想った。「そういう事もあるだろう。しかしそれを過信していられるのは傍の者には愉快でないな。何となく脅かされる。---少なくともそれだけに手頼(たよ)るのはいかんよ」。「勿論、それだけには手頼らないが---」。「気分の上では全く暴君だ。第一非常にイゴイスティックだ。---冷たい打算がないからいいようなものの、傍の者はやっぱり迷惑するぜ」。「-----」。「君自身がそうだと云うより、君の内にそう云う暴君が同居している感じだな。だから、一番の被害者は君自身と云えるかも知れない」。「誰にだってそう云うものはある。僕と限った事はないよ」。しかし謙作は自身の過去が常に何かとの闘争であった事を考え、それが結局外界のものとの争闘ではなく、自身の内にあるそういうものとの争闘であった事を想わないではいられなかった。「つまり人より著しいんだ」と末松が云った。 謙作はこれまで、暴君的な自分のそういう気分によく引き廻されたが、それを敵とは考えない方だった。しかし過去の数々の事を考えると、多くが結局一人角力(ずもう)になるところを想うと、つまりは自分の内にあるそういうものを対手に戦って来たと考えないわけには行かなくなった。直子の事も解決は総て自分に任せてくれ。お前は退(ど)いていてくれ。今後顔出しするのは邪魔になる。---自分が直ぐこれを云ったのは知らず知らず解決をやはり自身の内だけに求めていた事に初めて気がついた。実際変な事だと思った。---「自身の内に住むものとの争闘で生涯を終る。それぐらいなら生れて来ない方がまし*だった」。そんな意味を云うと、末松は「しかしそれでいいのじゃないかな。それを続けて、結局憂いなしという境涯まで漕ぎつけさえすれば」と云った。 大津からの電車は中々来なかった。謙作はぼんやり前の東山を見上げていたが、ふと異様な黒いものが風に逆らい、雲の中に動いているのに気がついた。そして彼は瞬間恐怖に近い気持に捕えられた。風で爆音が聴こえなかった為と、こんな日に如何にも想いがけなかった為と、その姿が雲で影のように見えていたためとで彼の頭にはそれが直ぐ飛行機として来なかったのだ。機体は将軍塚の上あたりを辛うじて越すと、そのまま、段々下がって行き、仕舞いには知恩院の屋根とすれすれにその彼方へ姿を隠して了った。「きっと落ちたぜ、円山へ落ちた。行って見ようか」。陸軍最初の東京大阪間飛行で、二人共新聞では知っていたが、今日はまさか来まいと思っていた。それが来たのだ。二人はそのまま粟田口の方へ急ぎ足に歩いて行った。 |
| 七 |
| 二人は円山から高台寺の下を清水の方へ歩いて行った。何処でも飛行機の噂をしているものはなかった。朝の新聞でもしそれを見ていなければ謙作は先刻の機体を自分の幻視と思ったかも知れない。それ程それは朧気(おぼろげ)にしか゜見えなかったし、又それ程彼の頭にも危なっかしいところがあった。彼は甚く空虚な気持で、末松に前夜の事を話そうか話すまいか、迷いながら、絶えず他の事を饒舌(しゃべ)り続けていた。実は話すまいと彼は決心しているのだ。しかしその決心している自身が信用できなかった。 彼は前にも尾道でちょっとこれに近い気持になった事がある。それは自分が祖父と母との不純な関係に生まれた児だという事を知った時であるが、その時はそれを弾(は)ね返すだけの力が何所かに感ぜられた。そして実際弾ね返す事ができたのだが、今度の事では何故かそういう力を彼は身内の何所にも感ずる事ができなかった。こんな事では仕方がない、こう思って、踏ん張って見ても、泥沼に落込んだように足掻きがとれず、気持は下へ下へ沈むばかりだった。独身の時あって、二人になって何時かそういう力を失って了った事を思うと淋しかった。少時(しばらく)して二人は二年坂を登り、其所の茶屋に入った。謙作は縁の籐椅子に行って、倒れるように腰かけたが、今は心身の疲労から眼を開いていられなかった。節々(ふしぶし)妙に力が抜け、身動きもできぬ心持だった。これは病気になったのかも知れぬと彼は思った。そして、「茶が来たよ。そっちへやろうか」。末松にこう声を掛けられた時には謙作は不知(いつか)眠りかけていた。「どうしたんだ」。「寝不足なんだ。それにこの天気でどうにもならない」。 謙作は物憂い身体を漸く起こすと敷居際(ぎわ)から這うような格好で、自分の座布団へ来て坐った。「大変な参り方じゃあないか」。「実は君に話したい事があるんだ。しかしそれを話すまいと思うんで尚いけない」。末松はちょっと変な顔をした。「------」。「持て余しているんだ。僕の気持の上の事だが」。しかし謙作はまだ云うまいと思っている。云えばきつと後悔する事が分っていた。「気持の上の事?」。「ああ、丁度今日の天気見たように不愉快な気持なんだ」。「どういうんだ」。「何(いず)れ話す。しかし今日は云いたくない」。「ふむ」。「---話は別だが君の所謂(いわゆる)赤切符はその後どうなのかしら?」。「------」。この不意な質問に末松は云い渋って具合悪そうな微笑を浮べていた。そして「------四条の額じゃないが、雨奇(うき)晴好(せいこう)ぐらいな気持かな」と笑った。謙作が結婚した頃、末松はその女の事でよく苛々していた。当時謙作は離れ離れな気持から、深入りして訊きもしなかつたが、水谷の口から、別れたとか、又会っているとか、二三度そんな噂を聞いただけで、その後はどうなっているか、少しも知らずに来たのである。末松は嫉妬からよく苛々していた。彼が愛している割りに女の方は気楽な気持だったし、それに他の関係も多く、「てっぱる」場合もよくあり、百も承知の事ながら、その度末松は一人苦しんでいた。「しかしその関係でいまだに続いているんだね?」。「そうだ」。「気味の気持はそれで落ち着いていられるのかね」。「一ㇳ口で云えば気持が冷めて来たのかも知れない。対手にないものは望まなくなった。しかしそれで調子はとれて来た。疑っていた日にはきり*がないからね。田舎亭で君を弱らした事がある。覚えているかしら?」。謙作は点頭(うなず)いて見せた。「あんな事はもうないよ」。そう云って末松は笑った。そして、「君のもああ云う種類の気持なのか?」と云った。「------」。謙作はちょっと考えてから、「幾らか近い気持だ」と答えた。 末松は少時(しばらく)黙った。それから又こんな事を云った。「よくは分らないが、そういう事は十中の七八は疑心暗鬼を作っている場合が多いらしいな。そんな事ではないのかね」。「疑心暗鬼ではない。しかし事件としては何もかも済んでいて、迷うところは少しもないのだ。只、僕の気持が落ち着くところへ落ち着かずに居るんだ。それだけなんだ。それは時の問題かも知れない。時が自然に僕の気持を其所まで持って行ってくれる、それまでは駄目なのかも知れないんだ。が、とにかく今は苦しい」。「------」。「しかし一方ではこうも思っている。今直ぐ徹底的に僕が平和な気持になろうと望むのは却って、自他共に虚偽を作り出す事だとも。その意味で、取らねばならぬ経過は泣いても笑っても取るのが本統だと云う考えもあるんだ」。「------」。「抽象的な事ばかり云っているが、そうなんだ」。「大概分ったような気がする。そしてそれは水谷に関係した事なのか?」。「いや、直接関係した事ではない。露骨に云えば水谷の友達で直子の従兄(いとこ)がある。それと直子が間違いをしたんだ」。「------」。「それも直子自身に少しもそういう意志なしに起った事で、僕には直子が少しも憎めないのだ。再びそれを繰返さぬように云って心から赦しているつもりなのだ。実際再びそういう事が起るとは思えないし、事実直子には殆ど罪はないのだ。それで総てはもう済んだ筈なんだ。ところが、僕の気持だけがどうしても、本統に其の所へ落ち着いてくれない。何か変なものが僕の頭の中でいぶつている」。「それは君の云うように時の経過を待つより仕方ないかも知れない。現在(いま)は寧ろそれが自然だよ」。「それより仕方のない事だ」。「無理な註文かも知れないが、事件として解決のついた事なら、余り拘泥しない方がいい。拘泥したところで、いい結果は生れないから。つまらぬ犠牲を払うのは馬鹿馬鹿しい」。「只、当事者となると、よく分っている事で、その通り気持が落ち着いてくれないのが始末に悪いのだ」。「ほん統にそうだ。しかし意志的にも努力するのだな。そうしなければ直子さんが可哀想だ。感情の問題には相違ないが、君のように事件が十二分に分っているとすれば、感情以上に意志を働かして、それを圧(おさ)えつけて了うのは人間としても立派な事だと思う」。 「君の云う事に間違いはない。しかし僕としてはそれは最も不得手な事だからね。それと仮令(たとえ)直子に罪がなかったとは云え、僕達の関係から云えば今まで全然なかったもの、或いは生涯ないとしていたものが、できた点で、今までの夫婦関係を別に組み変える必要があるような気がするんだ。極端な事を云えば仮に再び同じ事が起っても動かないような関係を。---もっとも、こんな事を云うのからして、君の云う事を本統に意志してない証拠かも知れないが」。「まあ、それは無理もないと思うけじ---」。「密雲不雨(みつうんふう)と云う言葉があるが、そういう実にいやな気持がしている」。「それはそうだろう。しかしとにかく、君にとって、これは一つの試練だから、そのつもりで充分自重すべきだな」。「ありがとう。この上、不用意から不幸を積み上げた日には、それこそ、馬鹿馬鹿しい。それは気をつけるつもりだ」。「事件そのものが分らずに引廻されるのは仕方ないが、君のはよく分っているんだから」。「ありがとう。話したんで大変気持がよくなった」。「直子さんはどうしてる?」。「僕が出る時には頭痛がするとか云って寝ていた」。「早く帰って上げる方がいいな」。謙作はふと末松に直子を慰めて貰おうかしら、と考えたが、直ぐ「それは厭だ」と思い返した。往来を馳(か)ける号外売りの八釜(やかま)しい鈴の音が聞こえた。間もなく二人はその茶屋を出たが、出る時、末松は入口に落ちていた号外を取上げ、「やはり先刻(さつき)の飛行機は深草へ下りたんだね」と云った。しかし他の一機は無事に大阪へ着いた事もそれに出ていた。二人はそれからダラダラ坂を東山松原の停留所の方へ下りて行った。 |
| 八 |
| その後、衣笠村の家では平和な日が過ぎた。少なくも外見だけは思いの外、平和な日が過ぎた。お栄と直子との関係も謙作の予想通りによかった。それから謙作と直子との関係も悪くはなかった。しかしこれはどういっていいか、---夫婦として一面病的に惹(ひ)きあうものができたと同時に、其所にはどうしても全心で抱合えない空隙(くうげき)が残された。そして病的に惹き合う事が強ければ強いほど、あとは悪かった。妻の過失がそのまま肉情の刺激になるという事はこの上ない恥ずべき事だ、彼はそう思いながら、二人の間に感ぜられる空隙がどうにも気になるところから、そんな事ででも尚、直子に対する元通りなる愛情を呼び起したかったのである。病的な程度の強い時には彼は直子自身の口で過失した場合を精しく描写させようとさえした。直子が又妊娠した事を知ったのは、それから間もなくだった。彼は指を折るまでもなく、それが朝鮮行き以前である事は分っていたが、いよいよ直子との関係も決定的なものになったと思うと、今更、重苦しい感じが起って来た。謙作の心は時々自ら堪え切れないほど弱々しくなる事がよくあった。そういう時、彼は子供のようにお栄の懐に抱かれたいような気になるのだが、まさかにそれはできなかった。そして同じ心持で直子の胸に頭をつけて行けば何か鉄板(てついた)のようなものをふと感じ、彼は夢から覚めたような気持になった。 夏が過ぎ、漸く秋に入ったが、依然謙作の心の状態はよくなかった。それは心の状態と云うより寧ろ不摂生(ふせっせい)から生理的に身体をこわして了ったのだ。彼はこんな事では仕方ないとよく思い思いしたが、だらしない悪習慣からは却々(なかなか)起きかえる事ができなかった。彼は甚く弱々しいみじめ*な気持になるかと思うと、発作的に癇癪(かんしやく)を起こし、食卓の食器を洗いざらい庭の踏石に叩きつけたりした。或る時は裁縫鋏(さいほうばさみ)で直子の着ている着物を襟から脊中まで裁(た)ち切ったりした事がある。こんな場合、彼ではその時ぎりの癇癪なのだが、直子は直ぐその源(みなもと)を自身の過失まで持って行き、無言に凝(じ)っと、忍んでいるのだ。そしてその気持が反射すると、謙作は一層苛立ち、それ以上の乱暴を働かずにはいられなかった。お栄は前から謙作の癇癪を知っていたが、そんな風にそれを実行するのは余り見た事がなく、僅か一二年の間に何故、謙作がそれ程に変ったか、分らないらしかった。 或る時謙作は鎌倉の信行から、その内遊びに行くと云う便りを貰った。そして謙作は直ぐ返事を書いたが、後で、それはお栄が手紙で信行を呼んだのだという事に気がついた。彼は追いかけに直ぐ断りの手紙を出して了った。しかし又、彼は折角来るという信行をそんなにして断った事が気になりだした。彼は来て貰うかわりに此方から出掛けようかとも迷ったが、それを断行するだけの気力はなかった。そして会えば必ず総てを打明けるだろうと思うと、それだけでも今は会いたくなかった。末松は自分も一緒に行くからと、切(しき)りに旅行を勧め、二人共まだ知らない山陰方面の温泉案内などを持って来て、誘ったが、彼は却々(なかなか)その気にならなかった。末松の好意はよく分っていながら、そうなると意固地になる自身をどうする事もできなかった。そしてとにかく自分で自分を支配しなければならぬ、そう決心するのだ。彼は久しく遠退いていた、古社寺、古美術行脚(あんぎや)を思い立った。高野山、室生寺(むろうじ)、など、二三日がけの旅になる事もあった。丁度晩秋で、景色も美しい時だった。そして彼は少しずつ日頃の自分を取り戻して行った。 秋が過ぎ、出産が近づいた。彼は総てで幾らかの自制ができて来ると、直子に対し、乱暴する事も少なくなった。自分の乱暴が胎児に及ぼす結果を考えると、彼は無理にも苛立つ自身を圧(おさ)えつけるよう心掛けた。出産はその暮れ、---延びて、正月の七草前と云う事で、彼は前の例もあるので、直子の軽挙(かるはずみ)には八釜(やかま)しく云っていた。そして今度はお栄もいるし、万事手抜かりなくやるつもりだったが、正月になり、十日過ぎてもまだ産がないと、少し心配になって来た。そして彼は今度は病院で産をして、一ㇳ月ぐらいは其所で養生する方がいいとてうような事を云い出したが、医者に相談すると、これだけの事でがあればその必要はあるまいと云った。その上、直子もそれを望まなかった為、入院の話はそのまま沙汰止みとなった。謙作はもし一ㇳ月の数え違いではないかと云う不安を感じた。二月に入って産があり、月を逆算してそれが自分の朝鮮旅行中にでもなっていたらと思うと、慄然(ぞっ)とした。しかし一月末の或る日、彼は大和小泉にある片桐石州の屋敷に出掛け、それから歩いて法隆寺へ廻り、夜に入って帰って来ると、自家では赤児が生まれていた。充分に発育し、その為、前より遥かに産が苦しかったという丸々とした女の赤児を見て、彼は何かなし、ほっと息をついた。彼が丁度法隆寺にいた頃生れた児ゆえ、一字をとって隆子と命名した。 |
| 九 |
| 謙作は毎年(まいねん)春の終りから夏の初めにかけきっと頭を悪くした。殊に梅雨(ばいう)期のじめじめした空気に打ち克てず、肉体では半病人のように弱る一方、気持だけは変に苛々して、自分で自分をどうにも持ちあつかう事が多かった。或る日、前からの約束で、彼は末松、お栄、直子らと宝塚へ遊びに行く事にした。その朝は珍しく、彼の気分も静かだった。丁度彼方(むこう)で昼飯になるよう、九時何分かの汽車に乗る事にした。出がけ、直子の支度が遅れ、彼は門の前で待ちながら幾らか苛立つのを感じたが、この時はどうか我慢した。末松とは七条駅で落ちあった。暫く立ち話をしている内に改札が始まった。彼はふと傍(わき)に直子とお栄の姿が見えない事に気がつくと、「便所かな」とつぶやいたが、「乗ってからやればいいのに馬鹿な奴だ」と直ぐ腹が立って来た。二人は便所の方へ行こうとした。その時彼方からお栄一人急ぎ足で来て、「二人の切符を頂戴」と云った。「どうしたんです。もう切符切ってるんですよ」。「どうぞお先へいらして下さい。今あかちゃんのおむつを更えるの」。「何だって、今、そんな事をしてるのかな。そんなら、貴方は末松と先へいって下さい」。謙作は苛立ちながら、二人の切符を末松へ渡し、その方へ急いだ。「有料便所ですよ」。背後(うしろ)からお栄が云った。直子は丁度赤児を抱き上げ、片手で帯の間からがま口を出しているところだった。「おい。早くしないか。何だって、今頃、そんな物を更えているんだ」。「気持悪がって、泣くんですもの」。「泣いたって関(かま)わしないじゃないか。それよりも、皆もう外へ出てるんだ。赤ん坊(あかんぼ)は此方(こっち)へ出しなさい」。彼は引ったくるように赤児を受取ると、半分馳けるようにして改札口へ向った。プラットフォームではもう発車の号鈴が消魂(けたたま)しく鳴っていた。 「一人後から来ます」。切符を切らしながら振り返ると、直子は馳足とも急ぎ足ともつかぬすり足のような共馳け方をして来る。直子は馳けながら、いま更えた襁褓(むつき)の風呂敷包みを結んでいる。「もつと早く馳けろ!」。謙作は外聞も何も関(かま)っていられない気持で怒鳴った。「どうでもなれ」。そう思いながら彼は二段ずつ跨(また)いでブリッジを馳け上がったが、それを降りる時は流石(さすが)に少し用心した。汽車は静かに動き始めた。彼は片手で赤児をしつかり抱き〆めながら乗った。「危ない危ない!」。駅夫に声をかけられながら、直子が馳けて来た。汽車は丁度人の歩くくらいの早さで動いていた。「馬鹿! お前気もう帰れ!」。「乗れてよ、ちょっと掴(つか)まえて下されば大乗で乗れてよ」。段々早くなるのについて小走りに馳けながら、直子は憐れみを乞うような眼つきをした。「あぶないからよせ。もう帰れ!」。「赤ちゃんのお乳があるから---」。「よせ!」。直子は無理に乗ろうとした。そして半分引きずられるような恰好をしながら漸く片足を踏台へかけ、それへ立ったと思う瞬間、殆ど発作的に、彼は片手でどんと強く直子の胸を突いて了った。直子は歩廊へ仰向けに倒れ、惰性で一つ転がり又仰向けになった。前の方の客車でそれを見ていた末松が直ぐ飛び下りた。謙作は此方へ馳けて来る末松に大声で、「次の駅で降りる」と云った。末松はちょつと点頭(うなず)き、急いで直子の方へ馳けて行った。「まあ、どうしたの?」。お栄が驚いて来た。「私が突き飛ばしたんだ」。「------」。「危ないからよせと云うのに無理に乗って来たんだ荷」。謙作は亢奮を懸命に圧(おさ)えながら、「次の駅で降りましょう」と云った。 「謙さん。まあ、どうして------?」。「じぶんでも分らない」。直子が仰向けに倒れて行きながら此方を見た変な眼つきが、謙作には堪えられなかった。それを想うと、もう取り返しがつかない気がした。次の駅で二人は降りた。駅には丁度電話がかかっていて、謙作は直ぐそれへかかった。出ているのは末松だった。「軽い脳震盪(のうしんとう)を起こしたらしい。しかし怪我はない。直ぐ医者が来る事になっている。まあ大した事はなさそうだ」。「十五分程で上りが来るから、それで還(かえ)る。で、其方は何処にいるんだ」。「駅長室だ」。「どうなの?」。傍(わき)からお栄が心配して訊いた。謙作は受話機をかけながら、「怪我はなかったらしい」。「まあ、よかった。本統に吃驚(びつくり)して了った」。間もなく京都行の列車が着いて、二人は直ぐ同じ路(みち)を還って来た。謙作はどうしてそんな事をしたか自分でも分らなかった。発作と云うより説明のしようがなかった。怪我がなく済んだのはせめてもの幸いだったが、直子との気持ちの上が、どうなるか、それを想うと重苦しい不快(いや)な気持がした。「謙さん、何か直子さんの事で気に入らない事でもあるの? 貴方は前と大変人が変ったように思うけど---」。謙作は返事をしなかった。「それは元から苛立つ性(たち)じやああったが、それが大変烈しくなったから」。「それは私の生活が悪いからですよ。直子には何も関係のない事です。私がもっとしっかりしなければいけないんだ」。「私が一緒にいるんで、何か気不味(まず)い事でもあるんじやないかと思った事もあるけど---」。「そんな事はない。そんな事は決してありません」。「そりゃあ私も実はそう思ってるの。直子さんとは大変いいし、そんな事はないとは思ってるんだけど、他人が入る為に家が揉めるというのは世間にはよくある事ですから羅ね」。「その点は大丈夫だ。直子も貴方を他人とは思っていないんだから」。「そう。私は本統にそれを有難いと思ってるのよ。だけど近頃のように謙さんが苛立つのを見ると、其所に何かわけがあるんじゃないかと思って---」。「気候のせいですよ。今頃は何時だって私はこうなんだ」。「それはそうかも知れないが、もう少し直子さんに優しくして上げないと可哀想よ。直子さんの為ばかりじゃあ、ありませんよ。今日みたいな事をして、もしお乳でも止まったら、それこそ大変ですよ」。赤児の事を云われると謙作は一言もなかった。 駅長室では末松と直子と二人ぼんやりしていた。直子は脚の高い椅子に腰かけ、まるで訊問(じんもん)前の女犯人とでもいうような様子で凝(じ)っとしていた。「まだ医者が来ないんだ」。末松は椅子を立って来た。直子はちょっと顔を上げたが、直ぐ眼を伏せて了った。お栄が傍へ行くと、直子は泣き出した。そして赤児を受取り、泣きながら黙って乳を含ませた。「本統に吃驚した。大した事でなく、何よりでした。---おつも*、どう?。水か何かで冷やしたの?」。「------」。直子は返事をしなかった。直子は自分の身体よりも心に受けた傷で口が利けないという風だった。「どうも、あれが実に困るんです。乗り遅れると云って、四十分で直ぐ出る列車があるんですから、少しも狼狽(あわ)てる必要はないんですが、僅か四十分の為に命がけの事をなさるんで---。しかしお怪我がないようで何よりでした」。「大変御面倒をかけました」。謙作は頭を下げた。「嘱託の医者が留守で、町医者を頼めばよかったのを、直ぐ帰るというので、そのままにしたのですが、どうしましょう。近所の医者を呼びましょうか?」。「どうなんだ」。謙作は顧みて云った。「少しぼんやりしておられるようだが、却って、直ぐ此方から医者へ行った方がよくはないか」。「それじゃあ、折角ですが、私の方で、連れて行きます。大変御厄介をかけ、申し訳ありません」。末松は車を云いに行った。謙作は直子の傍(わき)へよって行った。彼は何と云おうか、云う言葉がなかった。何を云うにしても努力が要(い)った。直子の決して寄せつけないと云うような態度が、謙作の気持の自由を奪った。「歩けるか?」。直子は下を向いたまま点頭(うなず)いた。「頭の具合はどうなんだ」。今度は返事をしなかった。末松が帰って来た。「車は直ぐ来る」。謙作は直子の手から赤児を受取った。赤児は乳の呑みかけだったので急に烈しく泣き出した。謙作はかまわず泣き叫ぶまま抱いて、駅長と助役にもう一度礼を云い、一人先へ出口の方へ歩いて行った。 |
| 十 |
| 直子の怪我は大した事はなかったが、腰を強く撲(う)っていて、二三日は起き上がる事ができなかった。謙作は一度直子とよく話し合いたいと思いながら、直子が変に意固地になり、心を展(ひら)いてくれない為にそれができなかった。直子の方は彼がまだ要との事を含んでいると思い込んでいるらしいのだが、謙作から云えば、苛々した上の発作で、要との事なぞその場合浮ぶだけの余裕は全くなかったのだ。「お前はいつまで、そんな意固地な態度を続けているつもりなんだ。お前が俺のした事に腹を立て、あんな事をする人間と一生一緒に居る事は危険だとでも思っているんなら、正直に云ってくれ」。「渡し、そんな事ちっとも思っていないことよ、只腑に落ちないのは貴方が私の悪かった事を赦していると仰有(おっしゃ)りながら実は少しも赦していらっしやらないのが、つらいの。発作、発作って、私が気が利かないだけで、ああいう事をなさるとはどうしても私、信じられない。お栄さんにも前の事、うかがって見たけれど、貴方があれ程病的な事を遊ばした事はないらしいんですもの。お栄さんも、近頃は余程変だと云っていらっしたわ。前にはあんな人ではなかったとも云っていらした。そんな事から考えて貴方は私を赦していると仰有って、実はどうしても赦せずにいらっしやるんだろうと私思いますわ。貴方は貴方が御自分でよく仰有るように私を憎む事で尚不幸になるのは馬鹿馬鹿しいと考えて、赦していらっしゃるんだと思う。その方が得だと云うお心持で赦そうとしていらっしゃるんじゃないかと思われるの。それじゃあ、私、どうしてもつまらない。本統に赦して頂いた事には何時まで経ってもならないんですもの。それぐらいなら一度、充分に憎んだ上で赦せないものなら赦して頂けなくても仕方がないが、それでもし本統に心から赦して頂けたら、どんなに嬉しいか分らない。今までのように決して憎もうとは思わない、拘泥もしない、憎んだり拘泥したりするのは何の益もない話だと云う風に仰有って頂くと、うかがった時は大変ありがたい気もしたんですけれど、今度のような事があるとやはり、貴方は憎んでいらっしゃるんだ、直ぐそう私には思えて来るの。そしてもしそうとすればこれから先、何時本統に赦して頂ける事か、まるで望みがないように思えるの」。「それだから、どうしたいと云うんだ」。「どうしたいと云う事はないのよ。私、どうしたら貴方に本統に赦して頂けるか、それを考えてるのて」。「お前は実家(さと)に帰りたいとは思わないか」。「そんな事。又どうして貴方はそんな事を仰有るの?」。 「いや。只お前が先に希望がないような事を云うから訊いて見ただけだが---とにかく、お前が今日ぐらいはっきり物を云ってくれるのは非常にいい。お前が変に意固地な態度を示しているので、此方から話し出す事が今までできなかった」。「それはいいけれど、私の申し上げる事、どう?」。「お前の云う意味はよく分る。しかし俺はお前を憎んでいるとは自分でどうしても思えない。お前を憎んだ上に赦してくれと云うが、憎んでいないものを今更憎むわけには行かないじやないか」。「------貴方は何時でもきつと、そう仰有る」。直子は怨(うら)めしそうに謙作の眼を見詰めていた。謙作はそれは直子の云うように実際もう一度考えて見る必要があるかも知れないと思った。「---それにしてもこの間の事をそう云う風に解すのは迷惑だよ。とにかく、俺達の生活がいけないよ。そしていけなくなつた原因には前の事があねかも知れないが、生活がいけなくなつてから起る事がらを一々前の事まで持って行って考えるのは、それはやはり本統とは思えない」。「私は直ぐ、そうなるの。僻(ひが)み根性かも知れないけど。それともう一つは貴方はお忘れになったかも知れませんが、蝮(まむし)のお政(まさ)とかいう人を御覧になった話ね。あの時、貴方が、云っていらした事が、今、大変気になって来たの」。「どんな事」。「懺悔(ざんげ)と云う事は結局一遍こつきりのものだ、それで罪が消えた気になっている人間よりは懺悔せず一人苦しんで、張りのある気持で居る人間の方がどれだけ気持がいいか分らない、そう仰有ったわ。その時、何とか云う女義太夫(ぎだゆう)だか芸者だかの事を云っていらした」。「栄花か」。「その他あの時、まだ色々云っていらした。それが今になって、大変私につらく憶い出されるの。貴方はお考えでは大変寛大なんですけど、本統はそうでないんですもの。あの時にも何だか貴方があんまり執拗(しつこ)いような気がして恐ろしくなりましたわ」。 謙作は聞いているうちに腹が立って来た。「もういい。実際お前の云う事は或る程度には本統だろう。しかし俺から云うと総ては純粋に俺一人の問題なんだ。今、お前がいったように寛大な俺の考えと、寛大でない俺の感情とが、ピッタリ一つになってくれさえすれば、何もかも問題はないんだ。イゴイスティックな考え方だよ。同時に功利的な考え方かも知れない。そういう性質だから仕方がない。お前と云うものを認めていない事になるが、認めたって認めなくたって、俺自身結局其所へ落ち着くより仕方がないんだ。何時だって俺はそうなのだから---。それにつけても生活をもう少し変えなければ駄目だと思う。もしかしたら暫く別居してもいいんだ」。「------」。直子は一つ処を見詰めたまま考え込んでいた。そして二人は暫く黙った。「------別居と云うと大袈裟に聞こえるが」。謙作は幾らか和らいだ気持で続けた。「半年ほど俺だけ何所(どこ)か山へでも行って静かにしてて見たい。医者に云わせれば神経衰弱かも知れないが、仮に神経衰弱としても医者にかかって、どうかするのは嫌だからね。半年と云うが或いは三月(みつき)でもいいかも知れない。ちょっとした旅行程度にお前の方は考えていい事なのだ」。「それは少しも僻まなくていい事なのね」。「勿論そうだ」。「本統に僻まなくていい事ね」。直子はもう一度確かめてから、「そんならいいわ」と云った。「それでお互いに気持も身体も健康になって、又新しい生活が始められればこの上ない事だ。俺はきつとそうして見せる」。「ええ」。「俺の気持分ってるね」。「ええ」。「暫く別れているという事は、決して消極的な意味のものじゃないからね。それ、分ってるね」。「ええ。よく分っています」。 その晩謙作は暫く家を離れる事をお栄に話した。お栄は大不賛成だった。お栄は尾道行きの前例から云っても、そんな事は何にもならないと云った。そして幾ら今の生活が悪いからと云って、夫婦が別居して、更にいい生活に入れる筈がないではないかと云った。謙作は説明に弱った。「第一尾道行とは動機が幾らか違うですがね。あれはできない仕事を無理にやろうとして失敗したが、今度は仕事は第二で自分の精神修養とか健康回復とかいうのが目的なんだから、別居と云うと大袈裟に聞こえるが、何も別に家を持つというのではなく、保養に旅へ出たぐらいに思って貰えば丁度いいんですよ」。「何処へ行く気なの?」。「伯耆(ほうき)の大山(だいせん)へ行こうと思うのです。先年古市の油屋で一緒になった鳥取の県会議員がしきりに自慢していた山だ。天台の零場とかで、寺で泊めてくれるらしい。今の気持からいうとそう云う寺なんか却っていいかも知れない」。 |
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)