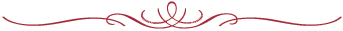
| 第4章の1(1から5)(後編5) |
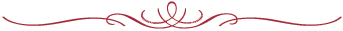
更新日/2021(平成31.5.1栄和改元/栄和3)年.8.10日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここで、「暗夜行路第4章の1(1から5)(後編5)」を確認する。 2021年.8.10日 れんだいこ拝 |
![]()
| 【暗夜行路後編第4章の1(1から5)】 |
| 一 |
| 謙作はその冬、初めての児を失い、前年とは全(まる)で異(ちが)った心持で、この春を過ごして来た。都踊りも八重桜も、去年はそのまま楽しめたが、この春はそれらの奥に何か不思議な淋しさのある事が感ぜられてならなかった。彼は今後に尚何人かの児を予想はしている。しかしあの子供はもう永遠に還(かえ)っては来ないと思うと、その実感で淋しくさせられるのだ。次の児が眼の前に現れて来れば、この感情も和らげられるに違いない。が、その時までは死んだ児から想いを背向(そむ)ける事はできなかった。散々になやまされ、しかも、それが何から来るか分らなかった自身の暗い運命、それを漸く抜け出し、これから新しい生活に踏み出そうと云う矢先だけにこの事は甚(ひど)くこたえた。丹毒は予防しようもない。むしろ偶然の災難だ。普通ならばそう思って諦めるところを、彼は偶然なこと故に、却ってそれが何かの故意のよう考えられるのだ。僻み根性だ、自らそう戒めもするが、直ぐ、と、ばかりも云えないという気が湧いて来る。彼はこういう自身に嫌悪を感じた。しかしそういう自分をどうする事もできなかった。 直子は思い出してはよく涙を流した。それを見るのが彼はいやだった。そして殊更ひき入れられない態度を見せていると、「貴方は割りに平気なのね」と直子は怨み言を云った。「いつまで、くよくよしたって仕方がない」。「そうよ。だから私も他人(ひと)には涙を見せないつもりですけど、仕方がないで忘れて了っちゃあ、直謙(なおのり)が可哀想よ」。「まあいい」。謙作は不愉快そうに云う。「あなたはそれでいいよ。しかしこっちまで一緒にそんな気になるのは御免だ。実際仕方がないじゃあないか」。「------」。「それより僕は近頃お栄さんの事が少し心配になって来たんだ。此方(こっち)には全(まる)で便りを寄越さないし、前の関係から云って信さんに任せっきりというわけには行かないから、その内一度朝鮮へ行って来ようと思うんだ」。直子はちょっと点頭(うなず)いたまま、返事をしなかった。小時(しばらく)して謙作は、「その間、あなたは敦賀へ行っていないか」と云った。「泣言でもいいに行くようでいやあね」。「泣言を云って来ればいいじゃないか」。「それがいやなの。貴方にならいいけど、実家の者にはそれは云いたくないの」。「何故。---一緒に行ってあなただけ置いて来よう」。「いいえ、結構。どうせ、十日か半月ぐらいなら仙と二人でお留守番しててよ。あんまり淋しいようだったら、その時勝手に一人で出かけるわ」。「それができれば一番いい。家で悲観しているようだと、こっちも旅へ出て気が楽でないからね」。 しかしこんな事を云いながら却々出かけられなかった。西は厳島(いつくしま)より先を知らなかった。それで京城(けいじょう)までが甚く大旅行のよう思われ、億劫(おっくう)だった。一つはお栄の方にも差し迫ってどうという事もなかったから、出掛けるにも気持に踏みきりがつかなかった。直子ができ、お栄に対する彼の気持も幾らか変化したのは事実だった。が、少年時代から世話になった関係を想い、又、一時的にしろお栄への一種の心持---今から思えば病的とも感ぜられるが、とにかく結婚まで申込んだ事を考えると、差迫った事がないとしても、こう愚図愚図、ほって置く事が、如何にも自分の冷淡からのよう思われ、心苦しかった。或る日、鎌倉の信行から書留で手紙が届いた。それに信行宛てのお栄の手紙が同封してあった。「不愉快な出来事から、最近、警部の家を出て、今は表記の宿で暮らしております。私もほとほと自分の馬鹿には呆れました。この年になり、生活の方針たたず、その都度お手頼(たよ)りするのは本統にお恥ずかしい次第ですが、他に身寄りもなく、偶々(たまたま)力になって貰えると思ったお才さんは私が思ったような人でなく、どうしても、又お願いするよりございません。精しい事情はここで申上げのせん。又申上げられるような事でもございません。私は一日も早く内地に帰りたく、今はその心で一杯でございます」。 こんな意味だった。つまり宿の払いと旅費を送って貰いたいと云うのだ。謙作は読みながら、信行の手紙にもちょっと書いてあったように、前には大連(たいれん)で盗難に会い、直ぐ帰るよう、金を送っても帰らず、勝手に京城に行き、今、又そんな事を言って金を請求して来る。もしかしたら植民地らしい不検束(ふしだら)な生活から変な男でもでき、それが背後(うしろ)で糸を引いているのではないかしらというような疑問も起こした。謙作は一緒に暮らしていた頃のお栄を想うと、こういう推察は不愉快だった。しかし、又、病的にもしろ、自分がそういう感情を持ったお栄には何かまだそういう誘惑を人に感じさせるものが残っているに違いなく、且つ話に聞いたお栄の過去が過去であるだけ、この推察も必ずしもあり得ないとは思えなかった。お栄が精しい事情を書かない点からも何か色情の上の出来事らしく感ぜられた。信行も、今度は行って連れて来るより仕方あるまいと書いて来た。その日はもう銀行が間に合わないので、彼は翌晩の特急でたつ事にし、その事を京城と鎌倉とに電報で知らせた。 |
| 二 |
| お栄の天津(てんしん)での失敗はお才に瞞(だま)されたとは言えないまでも、わざわざ金を持って内地から出掛けた者に対し、それを勧めたお才としては、やり方が少し無責任だった。悪気はないにしても親切気がなかった。お才も後でこの事は幾らか気になったらしく、お栄が大連へ引き上げてからも再三、手紙で、又来るよう勧めて来た。が、お栄はもうお才を信じなかった。仮にそう勧めてくれる親切は信じられても、それがどれだけ続くか、信じられなかった。お栄はその度、当り障りのない文句で断った。鉄嶺(てつれい)ホテルの女あるじ、増田というのは、男勝りのしつかり者だという噂はお栄もかってお才から聞いていたが、この女が最近土地の検番と喧嘩し、一つは意地から自力で別に検番を作る事にし、前から多少知り合いだったお才へ手紙でその事をいって寄越した。お才はそれを直ぐお栄の方へ知らして来た。 四五人の芸者に間に合うだけの衣装を持ち、それをもとでに何処かで芸者屋を開こうとしているお栄には、実に渡りに船の話だった。勿論二つ返事で乗って来るものとお才は思っているに違いなかったが、お栄はそれも断って了った。これが大連とか京城(けいじょう)とかの話ならば嬉しいのだが、近頃のように病気をしていると一層気が弱くなり、鉄嶺まで入り込んで行くのが、益々内地と縁遠くなるようで心細い、折角の親切を無にするようだが、鉄嶺へは行きたくない。そしてこの大連も今のところいい話もなさそうなので、そのうち京城へ行こうと思う。少しでも内地に近づきたく、もし京城の方にいい話でもあったら、その時は是非知らして貰いたい、と書いた。その後又お才から、もし京城に行くなら警部で野村宗一と云う知り人がある。それに頼めば万事便宜を計ってくれるだろう。もし行く場合は此方から手紙を出しておこうと言って来た。 お栄は早速その手紙を出して貰う事を頼んだが、隔日に瘧(おこり)の発作がキニーネで漸く治めている時で旅行はまだ暫くはできそうもなかった。そして愚図愚図している内に盗難に会い、唯一のもとでとしていた芸者の衣装幾行李(こうり)かを荷造りのままそっくり持って行かれて了ったのである。お栄はその時落胆もしたが、何となく清々(せいせい)とした気持にもなった。もう内地に帰るより仕方なく、信行に頼んで旅費を送って貰い、直ぐ帰るつもりだったが、もう再び来る事はないと思うと、少しは見物もしたく、朝鮮を廻って帰る事にした。一つは船の長いのもいやだった。十月に入って病気は余ほどよくなった。お栄は予定の如く朝鮮を廻り、京城まで来たが、お才の手紙にあった野村宗一を訪ねると、「内地に帰ってもいい仕事でもあるんなら別だが、此所でもう一度商売をして見たらどうです」と勧められた。警部の野村が何故こんな事を云ったかよく分らない。仕舞いに腕力でお栄を自由にしようとした、その下心がその時からあったのか、或いは単に軽い親切気からそんな風に勧め、同居している内にそういう気になったのか、お栄の話では謙作には見当がつかなかった。が、とにかくお栄はそれで又其所へ腰を下ろして了ったのだ。 「食料は払っていたんですけど、とにかく厄介になっていると思うから、町のお使いもなるべく私が行くようにしていましたし---京子という五つになる女の児があって、小母(おば)さん小母さんってよく懐(なつ)いているもんですから、私も可愛くなって、お使いの時はいつでも連れてって、玩具(やもちや)やお菓子なんか買ってやってたんですけど、それがどうでしょう。---野村がおかみさんの留守に私に変な事をしようとして、仕舞いには腕ずくでかかって来たから、私は野村を突き飛ばしてやったんです。すると、丁度其所へ入って来た京子が、何にも分らない癖に、小母ちゃん、馬鹿馬鹿、畜生畜生って泣きながら二尺差しを持って私をぶちに来るんです。それが一生懸命なの。その時は私も何だか、情けなくなって涙が出ましたわ。あんなに可愛がってやり、むこうもよく懐いていて、やはり他人は他人ですわね。そういう時には本気になって親の加勢をしようとするの。腹が立つやら、可笑しいやら、情けないやら---。でも親子というものはいいものだと私は自分がその味を知らないせいか、つくづくそう思いましたよ」。お栄は自分の年にも恥じたし、よくしてくれる野村の妻にも気の毒で、事を荒立てる気にはならなかった。そして翌日なるべく静かにこの家を去った。 謙作はお栄の話を聴きながら何となく愉快でなかった。近頃の自分の生活とは折り合わぬ調子が気持をかき乱した。彼は放蕩をしていた頃にも、そういう場所の空気に半日以上浸(ひた)っていると、いつも息苦しくなり、憂鬱になり、もっと広々とした所で澄んだ空気を吸いたいという欲望にかられた。今彼は丁度そういう気持になった。切(しき)りと京都の家---直子の事が想われた。彼はお栄が不検束者(ふしだらもの)になっていなかった事を嬉しく思った。要するに、いい人なのだ、只人間にしつかりしたところがなく、その時々の境遇に押し流されるのが不可(いけな)いのだ、そういうお栄を一人放してやった自分が無責任だったとも顧みられた。かって彼はお栄の止めるのも諾(き)かず、一人尾の道に行き、幾月かして、からだも精神もヘトヘトになって帰って来た時、お栄から、「瘠せましたよ。もう、これから、そんな遠くへ一人で行くのはおやめですね」と云われた。その同じ言葉を今彼はお栄に云ってやりたかった。そして彼はそれを彼自身の言葉で云った。「貴女は馬鹿ですよ。少しも自分を知らないんだ。一本立ちでやって行こうなんて、柄でもない考えを起こしたのが間違いの原(もと)ですよ」。しかしお栄の将来をどうしていいか、彼には分らなかった。自分が結婚を申込んだという事さえなければ、当然自家へ引き取り、一緒に暮らしたかった。又、その事があったとしても直子が意に介さないなら、そうしたかった。しかし少しでも直子がそれに拘泥するようなら、きっと面白くない事が起りそうだ。多少でもそういう点で絶えず直子が何か思うようなら、それは避けねばならぬ事だと考えた。 謙作は朝鮮では余り歩かなかった。開城(かいじょう)から平壌(へいじょう)へ一泊で出かけた以外は、或る晴れた日、お栄と清涼里(せいりょうり)の尼寺に精進料理を食いに行ったくらいのものだった。途中山の清水の湧いている所で朝鮮人の家族がピクニックをしているのを見かけた。白髯(はくぜん)の老人が何か話している。囲(まわ)りの人々が静かにそれに聴き入っている。長い物語でもしているらしかった。昔ながらの風俗らしく、見る者に何か親しい感じを与えた。南山(なんざん)から北漢山(ほくかんざん)を望んだ景色が好きで、彼は二度其所へ出かけて行った。景福宮(けいふくきゅう)、昌徳宮(しょうとくきゆう)、それから夜は一人で鐘路(しょうろ)の夜店あさりをした。古い螺鈿(らでん)の鏡台があり、欲しかったが、毀(こわ)れている割りに値が高かった。彼は美しい華革張(かかくば)りの文函(ぶんこ)を直子の為に求めた。これも今出来でなく、いい味があった。平壌への汽車の中で、彼は高麗焼きの窯跡を廻っているその方の研究家と一緒になり、色々そういう話を聴いた。謙作とは殆ど同年輩の人だったが、話しぶりにも老成したところがあり、朝鮮統治などにも一角(ひとかど)の意見を持っていた。 謙作はこの人から或る不逞(ふてい)鮮人の話を聞いた。びん徳元(とくげん)という若い両班(やんぱん)で、その地方では相当勢力のある金持だったが、鉄道敷設の計画で、その方の役人から相談を受け、一手に敷地の買占めを引き受けた。絶対秘密で、安く買上げるつもりだったが自分の土地は総て抵当とし、親類縁者からも金の出る所は総て出さし、益々買占めの手を拡げて行く内に何時かこの噂も評判となった。人々はびん徳元を裏切者として憎んだ。しかし彼は自分は単に親日主義者なのだといっていた。しころで、いよいよ鉄道敷地の買上が始まって見ると、それはびん徳元が役人から指定され、買占めて置いた土地とは三里も四里も離れた所だった。敷設計画が何時の間にか変更されていたのだ。びんはそれを少しも知らなかった。前に相談を持ち込んだ役人がそれをびんに教えなかったのだ。その役人も好んでびんを窮地に陥れる気ではなかったが、勧めた手前、既にかなり買占めのできたびんにそれが打明けにくくなったに違いない。しかしびんにとってはこれは甚い打撃だった。自分が無一物になったばかりでなく、親類縁者からも甚く怨(うら)まれ、土地の者からは裏切者のいい見せしめとして笑われた。立場が全くなくなった。役人の言葉を簡単に信じたところに自分の手落ちはあるにしても、そちらから勧めて来た話である以上、この行違いに対し、誰か責任を持ち、どうかしてくれる者があってもいい筈だ。見すみす自分一人が見殺しにされる。 びんはこの事を云って再三再四、総督府に談判した。しかし誰も取り合ってくれる者はなかった。責任者を出してくれといつても、勧めた役人は今は内地に還(かえ)って、いないという風で、その真偽は別として、彼に対し気の毒だったというだけの誠意さえ見せなかった。びんがこの不合理に就いて熱すれば熱する程、役人の方は冷たく取扱った。そしてそれ以上に熱するようなら不逞鮮人と認めるような気配さえ見せた。結局びんは泣寝入りより仕方がなかった。その後、一二年して、びん徳元は札つきの不逞鮮人になった。彼は何かの意味で日本に復讐してやろうと決心した。朝鮮の独立という程の事は彼には考えられなかった。それは殆ど不可能な事に思えていたし、その夢想は彼にはなかったが、それより彼では自分から総ての物を奪って了った者に対する復讐だ。絶望的な復讐心だった。彼は近年あらゆる悪い事に関係していた。「多分この間死刑になった筈ですが、四五年前例の窯跡探しで、案内して貰った時など、何だか非常に静かでそんなになろうとは夢にも思えないような若者でした」。 |
| 三 |
| 謙作は十日目にお栄を連れ、帰って来た。蒸々(むしむし)暑い日中の長旅で、汽車の中は苦しかった。下関から電報を打ったので、直子が大阪あたりまで出迎えているかも知れないと謙作は思った。「お帰りの時は何所かまでお迎い出ようかしら」。そんな事を直子がいっていたのを彼は想い出していた。で、彼は神戸でも、三ノ宮でも、汽車の止まる度、プラットホームに下り立って見た。大阪では列車が駅へ入る前から首を出していたが、此所まで来ると、その賑わしさが彼にやっと帰って来たという気をさした。彼はプラットホームの人込みの中に直子の姿を探したが、見えなかった。彼は何か軽い失望を感じながら、いっそ、はっきり出て来るよう、云ってやればよかったと思った。お栄は腰掛に横向きに坐って、うつらうつらしていた。一年半、---一年半にしては多事だった。---そして漸く帰って来たという事は何人にも感慨深くありそうな事だが、お栄はもうそれさえ想わない程、疲れて見えた。謙作にはお栄の感情がそれ程乾いたように思われた。「いらっしゃいませんか」。居ずまいを直しながらお栄は物憂そうに袂(たもと)から敷島の袋を出し、マッチを擦(す)った。お栄は久しく止めていた煙草をこの一年半の間に又吸い始めた。 謙作の方は僅か十日の旅でも、帰って来た事がいやに意識された。今乗り込んで来た連中は何(いず)れも見知らぬ顔だったが、それが皆、知人(しりびと)かのよう思われるのだ。彼は今度は間違いなく出ている直子の晴れやかな顔を想い浮べ、汽車の遅い速力を歯がゆく思った。九時何十分に汽車は漸く京都駅へ入った。謙作は直ぐ群集から少し後ろに離れて直子と、それに附き添って水谷が立っているのを見つけた。彼は手を挙げた。水谷は直ぐ人を押分け、駆け寄って来た。そしてまだ動いている列車について走りながら、荷を受取ろうとした。謙作は末松なら分っているが、水谷が迎いに来ている事が何となく腑に落ちなかった。自分とのそれ程でない関係からいって何か壺を外れた感じで漠然不愉快を感じた。彼は小さい荷物を水谷に渡しながら、「赤帽を呼んでくれ給え」といった。「いいですよ。ずんずんお出しなさい」。さう云いながらお栄の出す荷物も一緒に水谷は忙(せわ)しくおろしていた。直子はちょっと羞(はにか)んだ微笑を浮かべながら近寄って来た。「お帰り遊ばせ」。そしてお栄の方にも頭を下げた。「とにかく赤帽を呼んで来ないか」。彼は直子に云った。「いいですよ。奥さん」。水谷は自分の働きぶりを見せる気なのか、又そういった。謙作は苛々しながら、「いいですって、君、これだけの荷が持って行けるかい」と云った。大きなスーツケースが三つ。その他信玄袋や、風呂敷包が幾つかある。水谷はそれらを眺めて今更に頭を掻(か)いた。そして、「じゃあ、僕が呼んで来ましょう」と、急いで赤帽を探しに行った。謙作は忘れ物のない事を確(たしか)め、お栄を先に列車から下りた。彼は簡単に、「直子です」とお栄に紹介した。「栄でございます、何分よろしく---」。二人は叮嚀に挨拶を交わしていた。 「どうぞお先へいらして下さい」。こういいながら水谷が赤帽と一緒に還(かえ)って来た。「毀(こわ)れ物があるんだが、それだけ持って行こう」。「どれです。これですか?」。「僕が持って行くよ」。謙作は高麗焼(こうらいやき)を少しばかりと李朝の壺を幾つか入れた一ト包みを取上げた。「大丈夫です。僕が持って行きますよ」。水谷が奪うようにそれを取った。一体そういうところのある水谷ではあるが、今日はそれが謙作には五月蠅(うるさ)く思われた。彼はお栄と直子を連れ、改札口を出、そこに立って赤帽等を待った。「どうして水谷が来てるんだ」。彼は直子に訊いてみた。「今日自家へいらしたの。この間要(かなめ)さんが来て、三晩ばかり泊って、その時水谷さんや久世さんもいらして、お花で夜明かしをしたんですの」。「何日(いつ)」。「四五日前に」。「要」さんは何日帰った。末松は来なかったのか?」。「末松さんは一度もいらっしゃいません。要さんの帰ったのはさきおとついです」。「敦賀へ帰ったのか」。「九州り製鉄所へ見学に行くとかいっていました」。「八幡だね」。「ええ」。謙作は何となく不愉快だった。直子の従兄(いとこ)が、来て泊る事に不思議はないようなものの、自分の留守に三日も泊り、その上、自身の友達を呼んで夜明かしで花をしたというのは余りに遠慮のない失敬な奴らだと思った。又、直子も直子だと思った。 僅か十日間ではあるが、結婚してこれが初めての旅だった。彼は直子がその間、淋しさに堪えられないだろうと思い、敦賀行きを勧めたぐらいで、自分も朝鮮でそう気楽にしている事が直子に済まない気がし、且つ自身も早く帰りたく、彼は直子に会う事にかなり予期を持って帰って来たのだ。しかし会った最初から、何か、直子の気持がピタリと来ない事が感ぜられ、それに水谷の出ていた事がちょっと彼を不機嫌にすると、それが直ぐ直子にも反射した為か、直子の気持も変にぎごちない風で、不愉快だった。水谷が毀れ物の風呂敷を下げ、赤帽についてニコニコしながら出て来た。「チッキの荷もあるんでしょう? 直ぐとらせましょう」。謙作はそれに答えず直接赤帽に云った。「市内配達があるだろう」。「御座ります」。「衣笠村だけど届けるかね」。「さあ、市外やと、ちょっと、遅れますがな」。「そう。じゃあ一緒に持って行こう」。謙作は側で何かいっている水谷には相手にならず、割符(わりふ)を赤帽に渡した。荷共車四台で行く事にした。謙作の不機嫌に幾らか気押され気味の水谷は、それでも別れ際に、「二三日したら末松君とお伺いします」と云った。「それより末松にあした行くと云ってくれ給え」。「承知しました。明日は末松君も僕も学校は昼までですから、お待ちしています」。「少し用があるから一緒に出たいと末松にいってくれ給え」。 謙作は苛々した。車は烏丸(からすまる)通りを真直ぐ北へ走って行った。電車が幾台も追い越して行った。謙作は一番後ろから大きな声で前に行くお栄に東本願寺を教えた。それを引き取って年を取ったお栄の車夫が何か説明していた。六角堂でも車夫は駆けるのを止(や)め、歩きながら、説明した。「夜とはいえ、電車通りをお練(ね)りで行くのは少し気が利かなかったな」。彼は一つ前の直子にこんな事を云った。彼は自分は今はそれ程不機嫌でない事を示したかった。直子は何かいったが謙作には聴き取れなかった。彼は直子が何となく元気がないのが可哀そうになった。そして彼は、「水谷に荷を宰領さして皆で電車で行けばよかった」。心にもないこんな事をいつた。衣笠村の家へ帰ったのは十一時頃だった。眼刺しの仙が馴れた飼犬のような喜び方で玄関に迎いに出た。謙作にはそれが直子の気持よりもずっと近く来たのが、変な気がした。直子は自分の留守にそういう連中と遊んでいた事を後悔し、それで心の自由を失っているのだ。しかしそれを今は何とも思っていない事を早く示してやらねば可哀想だと彼は思った。 家の中はよく片附き、風呂が沸いていた。「いいお住まいね」。お栄は座敷で茶を飲み了(おわ)ると、立って、台所から茶の間と見て廻った。「お栄さんの寝る所は何所にした?」。「分らないから、今晩だけとにかく二階の御書斎にとらしておきました」。「うん」。そして彼はお栄に、「今晩は疲れているから早く寝るとよござんすね。風呂へ入って直ぐお休みなさい」と云った。「私は後で頂くから、謙さんお入んなさい」。「瀬戸物の荷を解(ほ)どくから僕はゴミになるんです。今日だけ先に入って下さい」。謙作は玄関の間で藁(わら)に巻いた壺や鉢をほどいて出した。「高麗焼の方は少し怪しいのもあるようだ」。直子は辰砂(しんしゃ)の入った小さい李朝の十角壺(じっかくつぼ)を取上げ、「これ、綺麗だこと---」と云った。「お前には華皮張(かかくばり)の綺麗な函(はこ)を買って来た。しかしそれも欲しければやってもいい」。「ええ頂きたいわ」。直子は両手で捧(ささ)げ、電燈の下でそれに見入っていた。「何でしょう。べたべたするのね」。「さあ、油でも塗ってあねかな」。「お栄さんがおでになったら、お風呂一緒に入っていい?」。「そうしよう」。「この壺を洗ってやるの」。「折角いい味になっているのを無闇に洗っていいかな」。「いいのよ。これじゃあ、きたなくて仕方がない。シャボンとブラシですつかり洗ってやるわ。もう頂いたんだから、いいでしょう? 私の物になったらもう骨董じゃあないのよ」。謙作は日頃の直子らしくなったと思った。 二人はそれらを座敷へ運び床の間に並べた。「私の壺が一等ね」。「李朝の物ではそれはいいよ」。「惜しくなっても、もうお返ししませんよ」。謙作は異(ちが)う荷から華革張りの函を出して来てやった。直子はそれも喜んだが、所々少しはがれかけた所などを気にした。それを見て謙作は云った。「お前には今出来を買ってくればよかった。何でも見た眼が綺麗ならいいんだから」。「そう軽蔑するものじゃあ、ないわ」。「実際そうじゃあないか」。「段々分って来てよ」。謙作は直子が湯上りの化粧を済まして来るのを待ち、お栄のこれからに就いて相談した。直子はこの家に一緒に住みたいと云った。謙作はそれがどれだけ考えがあっての返事か余り信用しなかったが、変な事を云われるよりは遥(はる)かに気持がいいと思った。「お前がそう云うのは、それは大変いい」。「いいも悪いも、それが当り前じゃあありませんか」。「子供から世話になった人で、実際はそうだが、お前とは全(まる)で異う境遇で来た人だからね。そんな点でもし合わないようでは面白くない。世話するとして、必ずしも一緒に住まねばならぬという事はないのだから、近所に小さい家を借りてもいいと思ったんだ」。「却って困るわ。そんな事」。「お前が差支えなければ、それでいいんだ。もし望まないようならそうしてもいいと考えたまでなんだ」。「私嬉しいわ。何でもこれからはご相談できて」。謙作は両方ともそう癖のある性質ではなくて、案外折合いがいいかも知れぬと考えた。実際お栄は過去は過去として新しい境遇にも順応する方だった。 謙作は自分の留守中の事を直子が少しも云い出さないのを少し変に思った。自分のちょっとした不機嫌がそれ程直子にこたえたのかしら。しかし、直子がその事を悔い、触れたがらないのはいいとして、此方も一緒に全く触れないようにしていると、却ってそれがその事に拘泥(こだわ)っている事にもなりそうなので、簡単に話せたら話して了いたいと思った。そして今後はそういう事にはもう少し気を附けるよう云いたかった。しかし、彼は却々気軽にそれが云い出せなかった。折角互いに機嫌よく、お栄の話も気持よくいっている時、それを切り出すのは努力が要(い)った。自然、両方が沈黙勝ちになった。「要さんはいつ卒業するんだ」。彼はこんな事から云い出した。「今年卒業したとか、するとかいってましたわ。八幡は見学もですけど、多分其所へ出るようになるんでしょう」。「帰りには又寄るのか」。「どうですか。何しろ来たと思ったら、直ぐ出かけて、翌日は又久世さんや水谷さんとお花でしょう。話しする暇なんかなかった。夜明かしでやって、そのまま又晩の九時か十時まで、三十何年かしたんですもの。人生五十年やるなんて、とてもかなわないから、私途中で御免蒙(こうむ)ったわ」。「それで要さんは翌日たって行ったのか?」。「朝、私がまだ寝ているうちに黙ってたって行って了ったの。本統にひどいのよ。何の為に来たか分りやしない」。 「それは花をしに来たんだ。水谷が手紙ででも誘ったんだろう」。「そうよ」。「予定の如くやったんだ。しかし留守なら少しは遠慮するがいいんだ。水谷の下宿でだってできる事なんだ」。謙作は不知(いつか)、非難の調子になっていた。「------」。「末松はそういう点、神経質だ。水谷はその点で俺はいやだよ」。「それは要さんもいけないのよ」。謙作は不図(ふと)「お前が一番いけないんだ」と云いそうにしたが、黙って了った。「もうこれからは断るわ。実際失礼だわ。御主人の留守に来て、幾ら親類だって、あんまり失礼ね」。「それは断っていいよ。要さんは会わないから、どういう人か知らないけど、従兄(いとこ)としてお前が親しければ尚、はっきり断って差支えない」。「------」。「とにかく、水谷は不愉快だよ。何だって、今日も出迎えなんかに来ていたんだ。それもまるで書生かなぞのようにいやに忠実に働いたりして。ああいうおっちょこちょいでもやはり気が咎めているもんで、あんなにしないではいられなかったのだ」。「------」。「水谷は末松も誘ったに違いないのだが、十日ばかり旅をした者を、わざわざ出迎えるほどの事はないから末松は出て来なかったんだ。その方がよっぽど気持がいい」。云い出すと謙作は泊らなくなった。「------」。「一つは末松は俺が水谷を厭やがっている事を知ってるから尚出て来なかったのかも知れない」。「------」。「水谷にはこれから来る事を断ってやろう」。「------」。「悪い奴とは云わないが、ああいう小人タイプの卑しい感じはかなわない。あいつの顔を見ると反射的に不機嫌になって了う。たまに、機嫌が良くて、一緒に笑談(じょうだん)なんか云って了うと、あと、きっと、自己嫌悪に陥る。何方(どっち)にしても、ああいあ人間と付き合うのは馬鹿気ている。末松は神経質なところがある癖にどうしてあんな奴と付き合っているのかな。あんな奴とつき合ってる奴の気が知れない」。 謙作は明らかに自分が間接に要の悪口を云っている事に気づいたが、却々止められなかった。「本統に悪かったわ。もうこれから気をつけるから赦して」。「お前もいいとは云えないが、俺はお前を責めているわけじゃあない。他の奴が不愉快なんだ」。「私が悪いのよ。私がしっかりしていないから、皆が私を馬鹿にしているんだわ」。「そんな事はない」。「私、もう要さんにもこれから来てくれるのよして貰います。それが一番いい」。「そんな馬鹿な事があるかい。伯父さんとの関係でそんな事できるかい」。「伯父さんは伯父さん、要さんは要さんよ」。謙作はあの上品なN老人を想い、その愛している一人児(ひとりご)に対し、ちょっとした不謹慎、それも学生として、別に悪気もない事に、自分の我が儘な感情から、こんなに思うのは済まないという気もした。N老人の自分に対する最初からの好意に対しても済まぬ事だと思った。彼はこうしたちょっとした感情から、段々誇張され、理不尽に、他人に不愉快を感ずる欠点を自分でもよく知っていた。彼はN老人に済まなく思うと同時に、自分の気持に対しても幾らか不安を感じた。実際考えようによれば何でもない事なのだ。それが、自分の感情で、一方へばかり誇張され、何か甚く不愉快な事のよう思われ、殊に黙っている間はよかったが、一度云い出すと、加速度にそれが、変に堪えられない不快事になって来る。これは自分の悪い癖なのだ。気を滅入らしていた直子に今は不機嫌でない事を示し、直子も折角気持を直したところに又、それを云い出さずにはいられない、実際自分はどうして、こう意地悪くなるのだろうと思った。彼は又気持を直す、その道を探すのに迷って了った。 「しかしもういいよ。他人ならあっさり考えられる事に俺は時々変に執拗(しつこ)くなるんだ。一ト通拘泥(こだわ)ねと自然に又直るんだが、中途半端に見逃せないのだ。今日プラットフォームに水谷の顔が見えた瞬間から不愉快になったんだ。つまり水谷の来るという事が壺を外れた事だ。何か不純なものをそれが暗示している気がしたんだ。そして結局それが当たったようなものだが、もうそれはいいよ。俺の気持ちが分り、これからそういう事に気をつけてくれるなら文句はない。お前も気にする必要はないよ」。間もなく二人は床にはいったが、互いに気持ちよくなった筈で、何だか、白々しい空気の為め溶け合えなかった。当然謙作はそうして弱り切っている直子を自身の胸に抱きしめてやるべきだったが、それがわざとらしくてできなかった。直子は泣きもしなかったが、掻巻(かいまき)の襟を眼まで引上げ、仰向けに凝(じ)っと動かずにいる。それは拗ねているのでない事は分っていながら、謙作はこの変な空気を払い退(の)ける事ができなかった。口では慰めたが、自身の肉体で近寄って行く気にはなれなかった。こうして一夜を明かす事は堪えられないと彼は思った。何か自分の感情を爆発さす事のできる事なら却って直るのも早いのだがと思った。彼はかなり疲れていたが、そういう直子を残し、一人眠入るわけに行かなかった。眠れなかった。彼は手を出し、直子の手を探した。しかし直子はそれに応じなかった。彼はムッとして少し烈しい調子でいった。「お前は何か怒っているのか」。「いいえ」。「そんなら何故そんなにしおれているんだ」。 |
| 四 |
| ふと、或る不愉快な想像が浮んだが、謙作は無意識にそれを再び押し沈めようとした。しかし息が弾み、心にもなく亢奮して来るのを彼はできるだけ抑えて、静かに続けた。「黙っていずに、何でも云えばいいじゃあないか。お前は俺が何か非難していると、そう思うのか?」。「そんなこと---」。「正直に云えば非難じゃないが、俺は非常に不愉快なんだ。停車場で見た瞬間から気持がチグハグになって、少しもぴったり此方へ来ない。抽象的な気持ばかりを云うのは、分らなくて気の毒とも思うが、何か変だよ。---お前は要さんや水谷の事を何時までも拘泥(こだわ)っていると思うかも知れないが、別の事だ、全然別かどうか分らないが、何か気持が抱合わない感じなんだ。其処に不純なものが感じられるのだ。一体どうしたんだ。今までこんな事ないじやないか」。「------」。「二階に聴こえるのはいやだ。此方へ来ないか」。謙作は身をずらして、寝床に空き地を作ってやった。直子は元気なく起きかえって、来て、其処へ坐った。憂鬱な、無表情な、醜い顔をして、ぼんやりと床の間の方へ眼を外(そ)らしていた。其処には先刻(さっき)甚く喜んだ壺や函がある。「坐ってないで横におなり」。直子は動こうともしなかった。二人は暫く黙っていた。謙作の頭の中は熱を持ったようになり、疲れたまま冴えていた。静かな晩だ。寝静まった感じで四辺(あたり)は森々としていた。そして只この座敷だけが熱病にうかされ、其処には「凶」という眼に見えぬ小さなものが無数に跳躍しているよう謙作には感じられるのだ。 「とにかく、もう少し物を云っちゃあ、どうだい。こうこじれて来てはこのままで眠るわけには行かないし。---それともお前は何にも云わないと決心でもしているのか?」。「------」。「はっきり云って、事に依ったら怒るかも知れないが、それでもいいじゃあないか。怒る事なら怒れば直るかも知れないし、ともかくはっきりさして、その上で解決をつければいい。どうなんだい」。「------」。「こうやっていればお互いに段々息苦しくなるばかりだぜ」。直子はやはり返事をしなかった。「---俺は何の為に、こんなにお前を責めているか自分でも分らない。何を云わそうとしてるか少しも分らないんだ。だから、お前も何にもないんなら、ないと、それだけ、はっきり云っていいんだ。---それだけの事ならはっきり云えるだろう? どうだい。ないのか?---ええ? 何にもないのか」。直子は急に眼を堅く閉じ、首を曲げ、息をつめて顏中を皺にした。そしてそれを両手で被うと、いきなり突っ伏し、声をあげて烈しく泣き出した。謙作は不意に自分の顔の冷たくなるのを感じた。彼は起き上がり、何か恐ろしいものに直面したよう、波打つ直子の背中を見下ろしていたが、少時(しばらく)すると彼は自分の心が夢から覚めたよう却って正気づいた事を感じた。彼は直子のこの様子を、どう判断していいかと先ず思った。次に彼はとにかく自分達の上に恐ろしい事が降りかかって来た事を明らかに意識した。 |
| 五 |
| 直子と要との関係は最初から全く無邪気なものとは云えなかった。それはそれ程深入りした関係ではなく、単に子供の好奇心と衝動からした或る卑猥な遊戯だが、それを二人は忘れなかった。色々な記憶の中で、それだけが寧ろ甘い感じで直子には憶い出されるのだ。春、まだ地面に雪の残っている頃だった。小学校から一度帰った要は父の使いで直子の母を呼びに来た。直子は近所の年下の女の児を対手(あいて)に日あたりの縁で飯事(ままごと)をしていた。それが面白く、「お前も要さんとこへ行かんか」と母に誘われたが、断って、遊びに余念なかった。少時(しばらく)すると、もう帰ったと思った要が庭口から入って来て、二人の仲間に入り、金盥に雪を積んで来ては飯にして遊んだ。縁が解けた雪で水だらけになり、皆の手はすっかりかじかんで了った。三人はその遊びをやめ、部屋に入り、炬燵にあたった。要は近所の児を邪魔者にし、「あんた、もうお帰り」。こんな事を切(しき)りに云い出した。しかし女の児は帰らなかった。すると、要は「亀と鼈(すっぽん)」という遊びをしようと云い、直子に赤間関(あかまがせき)の円硯(まるすずり)を出して来さし、その嘘日を二人に教えた。それは硯を庭に隠して置き、子供になった児が硯を探しに来る。そして障子の外から「お母さん亀を捕りました」と云う。直子のお母さんが「それは亀ではありません」と答える。その時、要が大きな声で、「鼈(すっぽん)」と怒鳴ると云う遊びだ。二人には何の事かさっぱり解らなかったが、それをする事にした。 女の児が要の隠した硯を探している間、二人は炬燵に寝ころんでいた。そして漸く見つけ出し、それを持って来た時、要はいきなり、「鼈(すっぽん)」と怒鳴って飛び起き、一人ではしゃぎ、跳(おど)り上がったり、でんぐりがえしをしたりした。この遊びは下男から教えられた。そして、その卑猥な意味は要だけには幾らか分っていたが、直子には何の事か全く分らなかった。只、炬燵で抱合っている間に直子はかって経験しなかった不思議な気持から、頭のぼんやりして来るのを感じた。三人は幾度かこの遊びを繰返した。暫くして、直子の兄が学校から帰って来て、二人は驚き、跳び起きたが、直子は兄の顔をまともに見られぬような、わけの解らぬ恥かしさを覚えた。要と直子との間では二度とこう云うことはなかった。しかしこの事は不思議に色々な記憶の中で、はっきりと直子の頭に残った。 それ故、直子は謙作の留守に要が不意に訪ねて来た時、かすかな不安を感じたが、感じる自身が不純なのだとも考え、殊更、従兄妹(いとこ)らしい明るい気持で対するよう努めた。翌日、水谷や久世が来て、花を始めた時も、こういう第三者が居てくれる事は却っていいと思い、人妻として不都合だと云うような事は少しも考えず、自分も仲間になって夜明かしをしたが、夜が明け、陽の光に尚、遊び続けていると、流石(さすが)に体力で堪えられなくなり、食事の事など総て仙に頼んで、自分だけ裏の四畳半に引き下がり、ぐっすりと寝込んで了つたのである。直子が眼を覚ました時は、もう家の中は暗かった。直子は湯殿へ行こうとし、途中、唐紙の隙間から座敷を覗くと、三人はまだ一つの座布団を囲み、同じ遊びを続けていた。皆、眼をくぼまし、脂(あぶら)の浮いた薄汚いかおをしていた。三人はちょっとした事にもよく笑い、普段それ程でもない久世までがたわいなく滑稽な事を饒舌(しやべ)っていた。 直子は身仕舞を済まし、仙と一緒に夜食の支度をした。三人は食事の間も落ち着かず、人生五十年だけやって、レコードを作ろうなど云っていた。そして、又直ぐ始め、直子も一緒になったが、前日から一睡もしていない三人は下りている間にも、一寸横になると直ぐぐっすりと眠りに落ちて行った。要は肩や首の烈しい凝りで、甚く苦しがっていた。十時頃になり、遂にやめた。三人は一緒に湯に入り、騒いでいたが、間もなく、久世と水谷は帰って行った。要は座布団を折って、それを枕に長々と仰向けに寝ていた。直子は幾度か床にはいるよう勧めたが、「今、行きます」と云い、中々起き上がらなかった。仕方なく、直子は丹前をかけてやり、側で雑誌を読んでいると、暫くして要は不意に起き、「おやすみ」と云い捨て、二階へ上って行った。直子は眠くないので、そのまま其所で雑誌を読み続けていた。そして、どれだけか経った時、直子はふと、二階で要が何か云っているのに気づき、立って梯子段(はしごだん)の下まで行き、其所から声をかけてみたが、要の返事が、寝ぼけ声でよく聴き取れなかった。直子は段を登って行った。「肩が凝って眠れない。按摩を呼んで貰えないかな」。「さあ、ちょっと遠いのよ。それも早ければすまわないが、もう十二時過ぎよ」。要は不服らしく返事をしなかった。「仙も今、丁度寝たとこだし、今から起こしてやるのも可哀想ね」。「そんなら要らない」。「よっぽど凝ってるの?」。「キリキリ痛むんだ。頭がまるで変になっちやって、眠れないんだ」。「私が少し揉んで上げましょうか」。「いいえ、沢山」。「割りに上手なのよ」。直子は部屋へ入って行った。そして要の首から肩の辺りを揉み始めたが、その凝り方は到底女の力ではうけつけそうもなかった。 「少しは利きそう?」。「うむ」。「利かないでしょう?」。「うむ」。「何方(どっち)なのよ。いやな要さんね」。直子は笑い出した。「こうして揉んでる間に、早くお眠りなさい。あしたお起きになる頃、按摩を呼んどいて上げるから」。直子は暫く、そうして揉んでやった。要は少しも口をきかなかった。直子はもう眠ったかしらとも思い、しかし止めて、もし起きていられたら気まりが悪いとも考えた。要が不意に寝返りをした。直子は驚き、手を離したが、要はその手を握り、片手を首に巻いて直子の身体を引き寄せた。要は眼を閉じたままそれをした。直子は吃驚(びっくり)したが、小声に力を入れて、「何をするのよ」と云った。「悪い事はしない。決して悪い事はしない」。こんな事を云いながら、要は力で無理に直子を横たえて了った。直子は驚きから、ちょっと喪心しかけた。そして叱るように、「要さん。要さん」と抵抗し、起き上がろうとしたが、要は自身の身体全体で直子を動かさなかった。そして、「悪い事はしない。決してしない。頭が変で、どうにもならないんだ」。これを繰返した。こう云う争いを二人は暫く続けていたが、仕舞いに直子は自分の身体から全く力が脱(ぬ)け去った事を感じた。それから理性さえ。直子は静かに二階を降りて来た。仙に覚(さと)られる事が恐ろしかった。そして、床に就いたが、何時までも眠られなかった。翌朝、直子が目を覚ました時には、要は出発し、もう家には居なかった。 |
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)