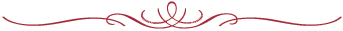
| 第3章の2(6から9)(後編2) |
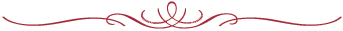
更新日/2021(平成31.5.1栄和改元/栄和3)年.8.10日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここで、「暗夜行路第3章の2(6から9)(後編2)」を確認する。 2021年.8.10日 れんだいこ拝 |
![]()
| 【暗夜行路後編第3章の2(6から9)】 |
| 六 |
| 石本とは横浜で別れ、其所で乗換え、大森へ着いた時は、もう日が暮れていたが、慣れた路で、彼は小さな手さげ一つ下げ、歩いて帰って来た。急いで玄関に出迎えたお栄は何よりも、謙作の今度の話に喜びを云った。それがもう決まったかのように喜んでいるのが、謙作には不安心でもあつたが、とにかく、そう喜んでくれるお栄が嬉しかった。お才という女は丁度東京に出ていて、居なかった。二人は久しぶりで食卓に向い合い、夜の食事をした。「一体まあ、どんな方?」とお栄がいう。「どんなって---」。「知ってる人で云ったら、まあ誰って云うような人?」。「そうね、知ってる人ではちょっと憶い出せないが、高井は鳥毛立屏風(ちりげだちびょうぶ)の美人だといってましたよ」。謙作はその為めわざわざ二階から東洋美術史稿を持ち出して来て、その絵を見せたが、生憎と、それに出ていたのは、何枚かある内の余り似てない一つだった。「これとも異うな、とにかくもっといいんです」。「まあ、大変なのね」。こんな風に二人はその事はよく話し合ったが、しかしお栄自身の方の事は何となく互いに口に出しにくかった。そして余りにそれの出ない事が変になって来た時にお栄は漸く、云い出した。「---でもね、貴方や信さんが賛成して下すったんで、私、本統に安心しました」。 こんなに云った。こう云われると謙作は弱った。彼は信行の伝えた事が嘘でないまでも、自分の気持を本統に伝えていない事を知った。その信行の上手なところがちょっといやな気がした。「あのね、---信さんはどう云ったか知りませんが、本統を云うと、僕は余り賛成してないんです。不賛成がいえないから賛成したので、実はいやいやなんです」。これを聞くとお栄はちょっと意外な顔をした。「この話がうまく行ったとしても、二三年は自家の事を貴女に見て頂きたいんです。そうだと僕には非常にいいんです」。「そう?---それは私だって、今、貴方とお別れするのはつらいのよ。だけども仕方がないと思っている。それに、そう云っちゃあ、何だけれど、私、やっぱり本郷のお父様がこわいのよ。近頃段々そうなって来た。その後はご遠慮して、伺わないけど、こわい眼で何時でも凝然(じっ)とこう睨まれてるような気がして仕方がない」。「そんな事ないさ。それは貴女の気のせいだ。きっと何所か身体が悪いんだ」。「ええ、もしかしたら、そうかも知れない」。「きつとそうだ。第一貴女は本郷のお父さんを恐れる事は何にもないんだ。本郷のお父さんとの事は対僕の問題で、貴女の知った事ではありませんもの」。「そうも云えないわ。お祖父さんのいらした頃から、私はお父さんの嫌われ者でしたわ」。「しかしそれでもいいじゃあ、ありませんか。それより、身体が悪いようなら医者に診て貰って、それから直してかからなければ駄目じゃありませんか。とにかく、こんな事はもっとよく考えてから決める方がよかったんです」。 お栄は今更の反対に当惑していた。そして、愚痴っぽい調子で賛成という事だったからお才にもそう返事をし、その支度で今もお才は東京に出ているのだというような事を云った。謙作の方も最初はそれ程に云う気はなかったが、云い出すとやはり其所まで云って了って、今は幾らか後悔していた。それに、こんな事を云う自分の心持が、自分でもちょっとはつきりしなかった。お栄の為に云っているのか、自分の為に云っているのか、そう考えると、何しろ、お栄に対する、変な未練気(みれんげ)から、こんなにして別れて了うのは、つまらないと云う駄々っ子のような我儘な気持が起っているのであった。お栄の方だって、もう少し自分に執着していい筈だというような不満があった。離れているとそれ程に露(あら)われなかったこういう気持が、会うと急に出て来るのである。しかしこれはいい事ではないと、彼は思った。こういう幼稚な我儘に自身を渡し切ってはならないと考えた。で、彼は今云った言葉を取消すような意味で、ぐずぐずとまずい調子で何か繰返していた。 お才と云う女が大きな風呂敷包を抱え、車で帰って来た。瘠せた背の高い、そして顔に険のある案外年をとった女だった。謙作は最初から不快な印象を受けた。「こちら、謙さん?」。こう一度お栄の方を向いて、「私、才。初めてお眼にかかります」。こういって年に似合わぬ蓮っ葉なお辞儀をした。そしてお才は眼尻に小皺(こじわ)を作り、色の悪い歯ぐきを露わし、笑いかけ、臆面もなく親し気に謙作の顏へ眺め入った。謙作は参った。お才に好意のある事が感じられるだけに尚、彼は一種圧迫を感じた。とにかくお才は彼の想像以上に下品な女だった。彼は自分の好悪感(こうおかん)が、そのままにお栄で、働かない事を歯がゆく思った。余りにそれがお栄にはなさ過ぎる気がした。そしてこんな女と一緒に何かしようというお栄の気が知れなかった。お才は風呂敷包みを解き、何枚かの華美(はで)な女着物を出して見せた。何れも古着らしく、何所か垢染みていた。お才は時々、「これがね---」。こんな風に云って、起って、それを自分の胸に当てて垂らし、お栄に説明した。 謙作は少し疲れていたし、その場に居にくい気持もし、挨拶して一人二階へ上って行った。そして彼は床の中に寝そべりながら、今、抱えて来た、東洋美術史稿の挿絵(さしえ)を見た。古い時代のものが殊になつかしかった。中には今度の旅で見て来たものもあり、今までになく彼はそれらに惹き入れられた。こうして自分には今までになかった世界が展(ひ)らけて来、そして結婚によって新しい生活が始まるだろう、など考えると、彼の胸には静かな幸福な気持が自然に湧き上がって来た。それにつけても、今階下(した)で何か小声で話している二人を想うと、丁度反対な世界が今、お栄に展らけつつあるのではないかという気がし、この儘(まま)にしていていいのだろうか、という気がした。久しぶりで、自分の寝床はよかった。暫くして彼は電燈を消し、快い眠りに沈んで行った。 翌朝、彼が起きた時にはお才はもう東京へ出て、居なかった。古着に就いては、女は彼地(あっち)でも直ぐ呼ぶ事ができるけれど、それに着せる衣装は夏冬一通りの物を揃えて行かねばならぬそうだという事をお栄が話した。総てがお才任せらしかった。こう、どんどんと事が運びつつあるのを見ると今更どうにもならない気がした。彼は自分の方もそろそろ支度をせねばならぬと思い、借りた本を別にし、自分の本を行李(こうり)幾つかにつめてみた。 午後彼は牛込の石本を訪ねた。電話をかけずに行ったので丁度今出たというところへ行った。別に用もなかつたので、彼はそのまま銀座の方へ引き返したが、ふと石本が京都で明後日(あさって)用があると云っていた、それを全く忘れていた事に心附(づ)いた。彼は何となくお才と会いたくなかった。お才は彼がお栄に結婚を申し込んだ事を聞き、それに変な興味を持っていそうな気がした。そして蔭でお栄にどんな事を云っているか、それさえ大概見当のつくような気がした。久しく東京言葉を聴かなかったような気持から、一つはお才と一緒になりたくない気持から、彼は夜になって落語の寄席へ行き、晩(おそ)くなって大森の家へ帰って来た。お栄とお才はまだ起きて、茶の間の電燈の下で何か話し込んでいた。お才はその話で興奮しているらしく、前夜のような世辞も云わず、自分で急須(きゅうす)へ湯をさし、それを茶碗へしたむと、謙作の前へ置いて、直ぐ、話しを続けた。 「それが、お前さん、ちつとも私は知らなかった。その春から、これだったんだ---」。こう荒っぽく云って、お才はその瘠せこけた片手の親指と小指の先をお栄の鼻先で二三度忙(せわ)しく、くっ附けて見せた。お栄は眼を伏せ、黙っていた。「口惜しいっちゃ、ない。旦那も何だけれど、妹の奴、食わして貰っていて、そんな事をしやがるかと思うと、まさか本気でもなかったが、私は出羽包丁を振り廻してやった」。謙作は何だか居たたまらない気持になって来た。茶を飲みながら、腰を浮かしていると、それと察したお栄が急に頭を挙げ、「お菓子でも出しましょうか」と云った。「もう沢山」。こういって起ちかけると、お才も気がついて、「いやな話で、済みません」と殊更に作り笑いをして謙作の方を向いた。「石本さん、いらしたの?」とお栄が云った。「居なかった。今日居ない事は知っていたんですが、すっかり忘れていたんです。仕方がないから、はなしかを聴いて来ました」。謙作は火鉢の方へいって、腰を下ろした。 「謙さんもそう云うものがお好きなんですか。私も好きな方だが、彼地(あちら)じゃあ、いいのが来ませんからね。---ええあれは何て云ったかしら。落語家(はなしか)の方は忘れたが、かみさんが、旭紫嬢(あさひしじょう)という琵琶弾きで、暫く二人共家へ置いてやった事がありますよ。却々いい声で、黎元洪(れいげんこう)に字を書いて貰った琵琶を持っていました」。お才は食卓に両臂(ひじ)を突き、米噛(こめかみ)の所に両の掌(たなごころ)を当て、電燈の光から顔を蔭にしながらそんな話をした。それはそうする事で顏の小皺が見えなくなり、艶を失った皮膚の色が分からなくなる為に幾らか美しく見えた。勿論お才はその効果を十二分に知って、しているので、そして謙作にも実際それが美しく見えた。少なくともこの女が若かった頃は相当に美しかったかも知れないという気を起こさせた。お才は翌朝岐阜の方へ起って行った。岐阜は郷里でもあり、其所に何か用もあるらしく、お栄とは日を決めて、京都で会い、一緒に彼地(あっち)へ行く事にして行った。起ち際に、「お栄さんの事はご心配なく」。こんなに云われても謙作は挨拶ができなかった。停車場へはお栄と女中とが送って行った。 その日午後になって、謙作は鎌倉の信行を訪ねた。其所に昨日(きのう)会えなかった石本が来ていて、そして信行の方は風邪をひき、喉(のど)に湿布をして床へ入っていた。「まだ何とも云ってないよ」。謙作も勿論そう早く返事を聴けるとは思っていないが、石本は彼の顔を見ると直ぐ云った。そしてその事に就いて二人は少し話していたが、信行は熱があるらしく、眼の中がとろんとして、話を聞いているさえ苦しい様子だった。「本郷から誰か呼んだら、どうだい。帰ってそう電話をかけようか」と謙作は少し心配になって聞いて見た。「いいよ。経過が分かってるから、もう二三日こうしていれば直るよ」。「誰か呼ぶ方がいいだろう。そして吸入でもどしどしやって貰う方が早いだろう」。「うむ」。「吸入器もないんだね?」。「そんなら吸入器だけ買って来て貰おうか」。 謙作は早速、町の方へいってその機械を買って来た。信行のうつらうつら眠っている枕元で石本は退屈そうに禅門何とかいう洋綴(ようとじ)の厚い本を拾い読みしていた。謙作は信行に寝たまま、吸入を仕掛けてやった。そして丁度来た大家のかみさんにその仕掛け方を教えて、後を頼み、夕方になって石本と一緒に其所を出た。停車場へ来た。其所には東京へ帰る石本の知った医者がいて、翌日又此方へ来るというので、その人に石本は信行の事を頼んだ。汽車の中では、謙作は一人ぼんやりと薄暮の景色を眺めていたが、気が沈んで仕方がなかった。やはりお栄と別れる事が淋しかったのだ。自身の為にも淋しかったが、お栄の為にも淋しい気がした。窓外の薄暮が彼を一層そういう気持に誘っていた。 |
| 七 |
| 謙作は近く別れねばならぬお栄と一緒にいながら、今までにない一種の気づまりを感じた。こうしている事もそう長くないと思うと、彼はなるべく外出も控えるようにしているのだが、それが不思議に気づまりで、且つ退屈でかなわなかった。第一、一緒にいて、話しの種が急になくなった気がした。お栄の方は、しかし忙しかった。その忙しさからそう云う気持には遠いらしく見えた。お栄は女らしい心持で、謙作の着物は一つでも汚れたものを残したくなかった。それらを洗張りにやり、縫い直し、それに余念なかった。 或る朝、謙作はいつになく早く眼を覚ました。彼は理(わけ)もなく変に落ち着かない気持になって、朝の食事をせずにそのまま自家を出た。停車場へ来たが汽車までは時間があるので、京浜電車の方へいって乗った。そして品川まで行くその間に彼はふと、明け方夢を見ていたという事を憶い出した。そしてその夢が彼の落ち着かない気持の原因だった事は分かったが、それを思い出そうとすると、不安な気持だけが、はっきりしていて、どういう夢だったか、その事実の方は却ってぼんやりしていた。何でも近頃南洋から帰ったTを訪ねたところから始まる。雨中体操場のような雑な大きな建物の中に、丁度曲馬団の楽屋に見る猛獣を入れた檻(おり)のようなものが沢山あって、その一つに何十疋(ひき)という栗鼠(リス)くらいの小さな狒々(ヒヒ)が、目白押しに泊り木にとまっているのが、甚く彼には面白かった。急に不安な気持に襲われると、そわそわとしてTと別れ、上野の博物館の、あの大きい古風な門、あすこへ彼は逃れて来た。遠巻きに何人かの刑事が取り捲(ま)いている事が姿は見えないが分っているのだ。で、彼自身は反逆人という事になっている。彼はそっと扉の陰から外を覗いていると日曜かなんぞのように兵隊が三々五々、前を通り過ぎる。その一人に「君は脱営する気はないか」。こう訊いたらしい。直ぐ承知して二人は扉の陰で、急いで和服と軍服とを取りかえて着た。「これでいい」。彼は思った。両方にいい事を考えたものだと思った。そしてその和服の兵隊と別れ、彼は何食わぬ顔で、兵隊になり済まし、一人淋しい方へ歩いて行った。道幅の狭い両側が堤(つつみ)の様になった所へ来ると、駅長のような制服を着た男が前から来て、いきなり彼を捕えて了った。忽ちに見破られたのである。見破られるのも道理、彼は自分で気がつくと、軍服の着方が全然いけなかった。襟(えり)のホックを一つもかけずに其所がだらしなく展(ひろ)がっている。それからズボンが、ずり下がり、誰の眼にも借り着という事は直ぐ分かる。ひどい格好をしているのである。彼は我ながら余りの不手際に苦笑し、同時に、捕えられた事に戦慄した。大体こんな夢だった。しかし憶い出してよかったと彼は思った。変に落ち着かぬ気持の出所(でどころ)が知れなければ、それだけでも終日いやな気持のする事だった。 はっきりした的(あて)もなしに出て来たが、やはりもしやという気持から、彼は石本を訪ねる事にした。石本は起きたばかりのところらしく、謙作は緑の籐椅子(とういす)で石本の出て来るのを待っていた。少し秋めいた静かないい朝で、苔のついた日本風の庭に朝日が斜めに差していた。軒に下げられた白い文鳥がちょっと濁ったような丸味のある声でしきりと啼(な)き立てた。「御機嫌よう」。石本の六つばかりになる上の娘が長く畳んだ三四枚の新聞を持って来て彼に手渡した。すると、その下の二つか三つの肥った女の児が、一束(ひとたば)の手紙を持ってよちよちと歩いて来て、「はい。はい」。こういって同じようにそれを彼に手渡した。「ありがとう」。彼はその児の頭をなぜてやった。上の児が駆けて行くと、下の児もよちよちと後から帰って行った。彼は新聞を膝(ひざ)の上に置き、手を延べて、そのまだ開封していない石本への手紙を前のテーブルへのせた。一番上になっている子爵石本道隆様としてある厚味のあるのが、S氏からのらしく、何となく彼にはそんな気がした。 水で綺麗に髪を分けた、石本が出て来た。「それはSさんからの手紙じやないかしら?」。謙作は一番上のそれを指して云った。「そう」。石本は直ぐ取上げ、「そうだ」と云った。石本は黙ってそれを読み始めた。謙作はその僅かな間が待ち遠しい気がした。「いい返事だ」。長い手紙を巻き返しながら石本が云う。謙作はそれを受取った。それは実際気持のいい手紙だった。女の人には大分年の異った兄があり、母親があり、それらによく相談して返事をするという事だった。そして何よりも謙作を感動させたのは例の不純な出生に就いて、Nというあの老人が云った言葉で、「---それはその人物の問題にて、却ってその為め奮発する底(てい)の人物なれば左様な事は少しも差支えなきものと信ずる由(よし)申され候」とこう書いてあった事である。尚、謙作の最近の写真と、何か書いたものがあれば、それを早速送って貰いたいと書いてあった。「何しろ、年寄りにしては余ほど、解(わか)った人らしい」。石本はその老人を讃(ほ)めた。「------」。謙作はそれに返事をしなかったが、腹の底では甚(ひど)く興奮していた。涙ぐみそうになるのをできるだけ堪(こ)らえた。 二人が一緒に朝の食事をしているところに用の客があった。それをしおに謙作は直ぐ帰る事にした。別れる時、石本はその手紙を直ぐ信行の方へ廻して置くからと云った。謙作は急ぎ足に歩いた。自然に急ぎ足になった。十中七分通りもう大丈夫だと考えた。そう決めていいと思った。むしろそう決めなければ駄目だと考えた。それ程に珍しく彼は自信が持てた。そして、彼の頭ではその人が急に近くに来ていた。それまで東京へ帰ると同時にお栄の事が余計考えられ、その人の方は不知(いつか)遠退(とおの)いた形であったが、今急にそれが近づき等身大に見えて来ると、結婚後の生活までが不意と断片的に浮かんだりした。いつの間にか町には風が吹いていた。彼はお栄への餞別(せんべつ)の品を見る為に銀座の方へ行った。時計に何か短い、いい言葉を彫らせても面白いと考えたが、そういういい考えが却々浮ばなかった。二三軒時計屋を念入りに見て廻った。そしてその中から割りに気持のいい流行遅れの型の物を選んだが、金を少ししか持っていなかったので、それを届けて貰う事にして、昼頃彼は大森の家へ帰って来た。お栄はS氏の手紙の話を聞き、感動していた。 謙作はその日奈良の高井にその後の事を知らす手紙を書いた。それからS氏へも礼手紙と、それから自分の写真と二三冊の自分のものの載った雑誌とを送った。自分の作物が芸術品としてよりも、もっと実際的な目的で読まれるのだと思うと、余りいい気がしなかった。しかも、これが自分の芸術だと云って見せるにしては、何れも貧弱な気が今更にされるのであった。それが届いたと云うS氏の手紙が来たのは、それから五日ほど後のことであった。それに、もし両三日内に京都へおいでになられるようだと大変に好都合だがと書いてあった。N老人は貴方が何時又当地へ来られるのかという事を再三訊く。それは自分が郷里へ帰る前にもし貴方が当地へ見えるようなら是非お会いして行きたいと云う気らしい。貴方の方の御都合もあること故、強いてとはいえないが、四五日内に老人はたつ筈で、それまでにおいでになれるようだとこの上なく好都合だという意味だった。尚、直子(女の子)さんは昨日(きのう)帰国されたが、写真は兄さんから直接貴方の方へお送りする都合になっている、とも書いてあった。 彼はその手紙をお栄に見せた。そして、「どうするかな」と云った。彼は迷った。「是非いらっしやい」とお栄は云う。「お目見得(めみえ)えに行くようなものだ」。彼は自分の作物を送って見せるさえ多少拘泥したところに、わざわざ自身そう云う風に呼び出されて行く事が何となく自尊心を傷つけた。「どうせ十日程したら、行くところです。今更そんな事に拘泥(こだわ)るのはよくありませんわ。Sさんでも石本さんでも本気で心配していて下さるんですもの」。「うん、---」。それもそうだと謙作は考えた。そして行こうと思った。「しかし僕がいなくても、あと大丈夫ですか?」。「何、云っているの---」とお栄は笑い出した。「此所へ来る時だって、何にも役に立たなかった癖に。謙さんなんか居ない方が、よほど邪魔にならなくっていい」。謙作も笑い出した。「よろしい、それじゃあ、出掛けましょう。邪魔と云う事なら仕方がない」。「ええ、邪魔/\」とお栄は謙作が案外素直に承知した事を喜んだ。謙作の家は一年以上借りる約束で、幾らか家賃が割引してあった。しかし今、一年経たぬ内に引き上げるとなると、その計算をしなければならなかった。毎月女中ばかりやっていたが、彼はそれをしに、自身山王の方の大家の家へ行き、ついでに電話を借りて、翌朝たつ事を石本へ知らせた。 |
| 八 |
| 京都の停車場へはS氏が出迎えていた。前日、「あす朝たつ」と云う電報を打っただけで、そう云う予期を少しもしていなかった謙作はちょっと恐縮し、そして小さい自尊心から色々拘泥していた自分を恥じた。N老人を訪ねるのは翌日という事で、その前にS氏が誘いに来る筈で、彼は壊れ物などを持って来ていたから、其処でS氏とは別れ、一人車で東三本木へ向った。翌日約束の時間にS氏を訪ねて来た。そして二人は直ぐ近い東三楼へ行く事にした。謙作は余りに社交馴れない自分が幾らか不安でもあった。しかし前夜よく眠っていたし、気分は良かった。女中がS氏の名刺を持って入ると、何時も河原からばかり見ていた老人の細君が、その日は常よりいい着物を着て、玄関へ出て来た。「さあ、どうぞ」。細い薄暗い廊下を先へ立って歩きながら、「えらい、むさくろしい所で---」などと云った。一重羽織を着たN老人が河原の方を背にして、きちんと坐っていた。謙作はいつもの癖で袴も穿(は)かずに来たが、それがちょっと気になった。「初めまして、---」。老人は瘠せた身体に似合わぬ幅のある、はっきりした声を出した。「この度はこちらにお住まいやそうで---」。こんな風に云われると、謙作は只、「ええ」と答える。後は大概S氏が要領よく続けてくれるのである。謙作は様子では窮屈らしくなっていたが、気持はもっとずっと楽だった。彼はN老人がそれとなく自分をじろじろと見でもしそうに予想して来たが、そう云うところは少しもなく、むしろそれを避けると思われる程に見なかった。 割りに質素な食事が運ばれ、女中でなく、細君自身お酌をして廻った。が、酒は誰も余り飲まなかった。話は極く普通の世間話しかしなかった。山崎医学士の噂などが出た。敦賀の漁業の話から、昔は大概塩魚にして出したもので、それを貯蔵して置く倉が沢山あって、維新前の事、筑波山(つくばさん)の武田耕雲斎一味のものが、東海道を通れぬ為、北陸を廻って、京都へ入ろうとするところを、敦賀で捕(とら)え、その塩魚を入れる倉へ閉じ込めた事があるというような話を老人はした。日のささぬ、じめじめした倉で、それに塩気が浸み込んでいるから、浪士の人達は皆、しつにかかり、それが身体中に弘まって、その様子が実に見ていられなかった。------ 「おい、ちょっとその袋を持って来い」。N老人は謙作の背後の違い棚を指し、話を少時(しばらく)きった。「御免やす」。細君は謙作のにん)*うしろを廻り、その袋を取って老人の前へ置いた。古代紫という色が、実際いい具合に古びた羅紗(らしゃ)の「火の用心」のような袋だった。老人は中から眼鏡や財布やマッチや小刀(こがたな)などを出してから、「この根付けが、その時の浪士で、佐々木重蔵という磐城(いわき)相馬藩の男でしたが、世話になったというので、記念にくれた物です、---」。こういってその袋を二人の前へ出した。「ははあ------」。S氏はちょっと見て、直ぐ謙作へ渡した。水牛の角にしてはもっと肌理(きめ)の細かい割りに軽い質のもので、応挙の絵に見るような狗児(くじ)を四五疋(ひき)かためて、彫ってある。「その男なぞも話すと、却々(なかなか)しっかりした男でしたが、可哀想に寒さに向って、段々に、皆死んで了いました」。謙作は自分が1週間ほど前に見た夢を憶い起こし、自分の場合幾分、愛興味のある反逆人だったが、それでも覚めてまで変な恐怖が残った事を想い、そういう連中が暗い、じめじめした塩魚の倉で、全身しつに悩まされ、寒さに向って一人一人仲間が死んで行くのを見ている時の気持を考えると、ちょっとかなわない気がした。最初その連中は福井に隠れていて、福井なら大丈夫のつもりでいたのを、そういう時代で福井でもはっきりした態度が取れず、お為めごかしに領内を立ち退かせ、敦賀で捕え、さしたのだという。「あの頃の事を考えると、この先どうなる事か、まるで、分りませんでしたからな」と老人は云った。 その日結婚の話は誰の口からも出なかった。それは謙作にも気持が良かった。そしてS氏が帰りかけた時、老人は、「お近うござります。如何です」と謙作だけを止めた。謙作は老人の好意を嬉しく思った。それは普通のお世辞ではなく、本統にもう少し居て貰いたいらしかったからで、謙作は残る事にした。老人はそれからも維新時分のそういう話を聴かした。無頼漢が寄り集まって尊王論を唱え、金を集めては贅沢(ぜいたく)をしていた。が、間もなく捕えられ、白洲(しらす)で尊皇とはどう云う事かと訊かれ、尊い王様という事だと答えたと云う洋な話などが出た。とにかく、謙作はこの老人夫婦に対し、大変親しい感じを持った。そして暫くして暇(いとま)をつげた。 翌日老人夫婦は世話になった医者その他の礼廻りやら、買物などに忙(せわ)しいらしかった。それでも宿の玄関まで謙作を訪ねることを忘れなかった。その翌日老人たちは敦賀へたった。謙作は停車場まで送った。其所にはS氏、山崎医学士、看護婦、その他見送りの人達が来ていた。老人たちを送って了った謙作は急に用がなくなったような気がした。お栄が来るまでの一週間が待遠しく、その間の何となく落ち着かない無為な日が想われた。高井を誘って橋立(はしだて)か小豆島か左(さ)もなければ伊勢参りでもしようと思った。 翌日、それは気持よく晴れた日だった。彼は高井が何処かへ出掛けぬ内に行くつもりで京都を早く出た。そして奈良の浅茅(あさじ)が原の茶店の離れに居る筈のその友を訪ねたが、高井は既に二三日前、郷里へ引き上げて、いなかった。謙作はちょっとがっかりした。彼は室生寺(むろうじ)へでも行こうかと考えた。只、室生寺が何処で汽車を下り、どう行くのか、そういう事は精しく知らず、それを調べるのも億劫な気がし、で、矢張り一番近い伊勢参りをする事にして、奈良では博物館だけを見て、直ぐ停車場へ引き返した。伊勢参りは思ったより面白かった。神馬(しんめ)という白い馬にお辞儀をさせられるという話を聴いていたが、まさかにそれは嘘だつた。五十鈴川(いすずがわ)の清い流れ、完全に育った杉野大木などを見てみなければわからぬ気持のいい所があった。それから古市の伊勢音頭も面白く思った。 芝居で馴染(なじみ)の油屋(あぶらや)という宿屋に泊り、その伊勢音頭を見に行く事にしていると隣室の客が一緒に行きたいと云い、食事も一緒にしたいからと境の唐紙(からかみ)を開け放さした。「丁度県会の方が暇になったものですから」。こんな風に、その人は云いたがる人だった。鳥取県の人で彼より三つ四つ年上の人だったが、県会議員が、どの程度に自慢の種になる事か全く知らない謙作は県会が出る度(たび)、気の毒なような軽い当惑を感じた。山陰に温泉の多い事、それから、何とかいう高い山が、叡山に次ぐ天台での霊場で、非常に大きなそして立派な景色の所だというような話をした。下座敷(しもざしき)の客も二組一緒に行く事になって、七人程度になった。宿の女中に案内され、夜の遊女屋町を皆(みんな)でその家へ行った。染めたのか、くすぶったのか、とにかく、黒ずんだ、ひどく古風な座敷へ通された。深い大きな床を背にして、皆が段通(だんつう)へ直(じ)かに坐っていると、その前の三宝(さんぽう)に番組ようの刷物と他に菓子か何かが積んで厚保て、前三方は御簾(みす)をへだてて、やがて舞台となるべき花道程の廊下に向っている。 「あなたは偉い、一人でこれを見ようとされたのだから」と鳥取県の人が謙作を顧みて笑った。謙作は別にそういう事を考えずにいたが、成るほどそう云えばこの広い座敷に一人ぽつ然(ねん)としていて、十何人かの女が出て来たら、ちょっと具合の悪い事だったかも知れないと思った。下方(しもかた)が四五人坐り、太棹(ふとざお)とも細棹ともつかぬ三味線を弾きだすと、木が入り、三方の御簾が上がり、電気がつき、廊下が一尺ばかりせり上り、それに低い欄干がつき、そして両方から四人ずつの女が出て来て、至極単調な踊りを、至極虚心に踊るのである。十五分くらいで済んだ。その単調な調子も、その余りに虚心な処も、それから、太とも細ともつかぬ三味線の悠長な音色も面白かった。それに時代離れのした座敷の様子も、総てが謙作にはよかった。これを一人でぽつ然と見ていたら尚面白かったかも知れないと考えた。別の座敷に導かれ、肥った五十くらいの女から、もっと残るように勧められた。が、誰も残らなかった。一緒に又宿の女中について帰って来た。 翌朝、彼は車で内宮から徴古館(ちょうこかん)、それから下宮へ廻った。外宮では林の中の池に何百となく野生の鴛鴦(おしどり)が水面に、又岸の木の水へ差し出した大きな枝に一杯にいるのを見て、夢の中の場面のように思い、興じた。二見(ふたみ)から鳥羽へ行き、一泊して、京都へ帰る事にしたが、その帰途(かえり)、彼は亀山に降り、次の列車までの一時間半ばかりを車で、一通り町を見て廻った。亀山は彼の亡き母の郷里だった。それは高台の至って見すぼらしい町で、町見物は直ぐ済み、それから、神社の建っている城跡の方へ行って見た。広重の五十三次にある大きい斜面の亀山を想っている謙作は、その景色でも見て行きたいと考えたが、よく場所が分からなかった。車を鳥居の前に待たし、いい加減にその辺(へん)を歩いて見た。下の方に古い幽翠(ゆうすい)な池があり、その彼方が又同じくらいの山になっていた。彼はその方へ降り、そして、急な山路(やまみち)をその高台へ登って行った。上は公園のようになっていて、遊びに来ている風の人は一人もいなかったが、身なりの悪い、しかし何処か品のいい五十余りの女が一人、其処で掃除をしていた。彼が登って行くと、その女も掃く手を止(や)めて此方(こっち)を見ていた。その穏やかな眼差(まなざ)しが、親しい気持を彼に起こさせた。そして丁度亡き母と同じ年頃である事が、そして昔の侍の家の人であろうという想像が、彼に何かその女と話して見たいと云う気を起こさせた。 「此所は---」。こんな事を云いながら彼は近寄って行った。「やはりお城の中ですか?」。「そうでござります。こちらは二の丸で、あちらが昔の御本丸でござります」。そう云って女の人は神社のある方を指さした。「昔、此所に居た人で佐伯(さえき)という人を御存知ありませんか」。「佐伯さん。御旧臣ですやろ」。「そうです」。謙作はわけもなく赤い顏をしながら、「佐伯新というんですが、丁度あなたぐらいの年です」。謙作は当然「知っている」という返事を予期しながら少し焦(せ)き込んでいった。「はあ---」とその女の人は呑み込めない顔をして首を傾けた。「お新さんと云われたお方はよう覚えまへんが、お金さんとそのお妹御(いもうとご)でお慶さんといわれるお方はよう存じとりますが」。「女同胞(きょうだい)はないのです。---多分なかったんだろうと思うんです。もっと他にありませんか。佐伯という家は---」。「」さあ、どうですやろ? 私共の覚えているのは御維新(ごいつしん)から後の事ですよって、他(ほか)土地へ出られたお方やと存じませんのやが、今申しました、佐伯さんでお訊ねやしたら、大方知れん事もござりますまい」。 結局謙作の予期に外れた。それに彼はそう云う機会もなく、母の幼時の事などを全(まる)で知らなかった。母が何時から東京へ出て来たのか、母方の親類にどういう家があるのか、第一母の父の名さえ彼は知らなかった。「芝のお祖父(じい)様」で事が足りていたので、その祖父を自家の祖父よりも心から尊敬し愛していたにも拘(かかわ)らず名を知らなかった。女の人はこの土地の佐伯という家を教えてくれたが、彼は別に行く気もなく、礼を云って別れた。彼は自分が余りにそういう事を知らなかった事を---知る機会が自分になかった事を今更に心附いた。夕陽が本丸の森を照らしていた。ぬるでだけがもう紅葉して青い中に美しく目立っていた。「しかしそれでいいのだ。その方がいいのだ。総ては自分から始まる。俺が先祖だ」。こんな事を思いながら、彼はうるさく折れ曲がる急な山道を、既に秋らしく澄んだ池の方へ、トントンと小刻(こぎざ)みに駆け降りて行った。 |
| 九!/\ |
| 京都には謙作の留守の間(ま)に石本が来ていた。「大変いい具合なんだね」と石本が云った。「そうかね」。謙作は何か具体的ないい話でもあったのかとちょっと思った。「老人夫婦は君に随分好意を持っていたそうだ」。「此方(こっち)でも随分好意を持った」。「そう。それはよかった」。「------」。「後へ残って、何か少しはそう云う話をしたの?」。「いや」。謙作はその日の事を簡単に話し、そして今度は珍しく自分でも大丈夫な気がしている事などを話した。「しかし遠い所を度々ありがとう」。こう謙作は礼をいった。「何でもないよ」。「わざほざ本統にありがとう」。謙作はこれまで、こんなにはっきり石本に礼を云った事などなかったような気がした。しかしそれが少しも変でなく口から出た。「まあ、間違いないと見て、これから先の事はどうしよう。君一人ではとても駄目だろう?」。「うん」。「Sにやって貰わないと困る事もあるが、大体、信行と相談して、此方で決めていいかい?」。「そうしてくれ給え」。「決めた事はなるべく君の承認を受けるようにはするが---」。「一々それをして貰わなくていいよ、大変だ。---やはりSさんの方へ返事は来るんだね?」。「そうだ。しかしそれはまあ心配ないよ」。石本の口ぶりではN老人は或る程度に、はっきりした返事をして行ったらしかった。石本はその晩の急行で帰って行った。 先発の荷が着いたので、謙作は人を頼み、入る家を掃除させ、其所で荷造りをほごさせた。福吉町以来の女中は暇を取る事になったので、彼は代りを宿に頼んでおいた。そして間もなくそれが見つかり、その日も謙作から知らせたわけではなかったが、手伝いに来ていた。瘠せた婆さんで、引っ込んだ眼や、こけた頬(ほお)や、それが謙作に目刺しを想わせた。仙と云う名だった。そしてその晩から仙だけ其所へ泊る事になった。それから3日程して、朝、お栄が着いた。お栄は家の方をすつかり片附けて行きたがった。「沢山です」と謙作はいった。「後の荷も着かないし、僕の世話より、ゆっくり見物をなさい。その方が此方も嬉しいんです。幾日ぐらいいられるのですか?」。「四五日したら岐阜から来る筈」。「そんなら尚、引っ越しなんか、どうでもいい。まあ、僕に任せて下さい」。そう云って宿へ落ち着くと、直ぐ彼はお栄を見物に連れ出した。 その前、お栄は旅鞄(たびかばん)から奉書の紙に包んだキャビネの写真を彼の前へ出して、「一昨日(おととい)届いたの」と云った。「うむ、これです。余り鳥毛立(とりげだち)でもないな」と謙作は云った。お栄は愛子と比較してちょっと何か云った。それには古い不愉快に対する女らしい反感が響いていた。それを愛子で云ったのが謙作には不愉快でだったが、しかしやはりあの頃の色々いやな事が憶い浮んで来ると、ちょっと腹立たしい気持にもなり、彼は黙っていた。車で、黒谷(くろだに)、真如堂から銀閣寺、法然院、松虫鈴虫の寺などを廻り、南禅寺北の坊の今度の家へ寄った。そこで車を返し、暫く休む事にした。「本統にいい家だこと」。お栄はしきりに家を讃(ほ)めた。そして「あれは何?」。若王子(にゃくおうじ)の裏のこんもりした松山の上に赤い旗が何本もヒラヒラ動いているのを謙作に訊いた。「茸(たけ)狩りしやはるとこどっせ」。仙が次の間から勝手に答えた。 お栄は東京とは様子の変った、路次のような細長い台所に興味を持ち、仙に説明させ、隈なくその辺を見ていた。法然院の庭などよりもお栄にはこの方が興味が深かった。若王子も永観堂もやめて南禅寺へ行った。謙作はお栄がうるさく思うだろうと自分でも思えるほど、見る物、見る物に説明したくなって弱った。子供らしい気持だと思いながら止められなかった。殊に相手がお栄だと、自然臆面(おくめん)もなく自分の子供らしさが出るのであった。南禅寺の裏山の中腹から、疎水(そすい)の上へ出て、それからインクラインを見、瓢亭(ひょうてい)という家に寄って夜の食事をした。暗くなって二人は宿へ帰って来た。其所には狭い座敷に掛蒲団(かけぶとん)の端(はし)を重ね合して二つの寝床がとられてあつた。出掛けに、それを訊かれ、謙作は何気なく、「いえ、この部屋でかまいません」と答えたのだが、今それを見ると彼は永年一緒に暮らして来て、(極く子供の頃は別として)お栄と二人こう一つ部屋で寝た場合を一度も憶い出せなかった。「少し窮屈だな」。彼はちょっと顔をしかめ、独り言のようにいった。お栄は又それとは全で別な心持で、枕元の僅かな空き地に、疲れた身体を据えるように坐り、「おかげで、思いがけない見物をしました」と、もう見物が皆、済んだような事をいった。「これで、かのいませんか?」。「ええ、結構」。「もう、直ぐ寝るんでしょう?」。「謙さんは?」。「僕は少し町を散歩して来ます」。「そう、それじゃあね、私、昨夜(ゆうべ)汽車でよく眠れなかったから、お先へ失礼します」。「ええ、そんなら直ぐお休みなさい」。 謙作は町へ出れば大概寺町を真直ぐに下がるのが癖のようになっていた。そして今もその道を歩きながら、やはり、彼は無心ではなかった。晩(おそ)くなって帰って来た。お栄は明るい電燈の下でよく眠入(ねい)っていた。最初彼が帰って来た事も知らぬ風だったが、少時(しばらく)して、まぶしそうに薄眼を開(あ)くと、ちょっと醜い顔して、「今、お帰り?」と云い、直ぐ寝がえりを打ってうしろを向いて了った。謙作は誰にしろ、同じ部屋に人が居ると安眠できない方だった。こういう時、疲れ切るまで本を読む癖から、彼は紐を延ばし、電燈を頭の上へ引き、「から騒ぎ」と云う、今、古本屋から買って来た喜劇の本を読み始めた。先日活動写真の「真夏の夜の夢」を面白く思って以来、彼はしきりにそう云う喜劇類を読んだ。それは今の彼にとって、丁度、東洋の古美術が、全く異(ちが)った時代へ彼を連れて行ってくれるように、そしてそれが彼に大きな慰めとなるように、それらの喜劇に接する事が一時的にもせよ、彼を今までとは全く反対な、そういう軽い自由な気分へ誘い出してくれる、それが彼にはありがたかった。とにかく悲劇類は今の彼には閉口だったのである。 半分ほど読んだ。そして彼は電燈を消し、案外早く眠りに沈んで行った。が、どれだけか経って、彼は不意と、丁度人に揺り起されたかのように、暗い中ではつきりと眼を覚まして了った。そしてもう眠れなかった。眠ろうと幾ら努めても眠れなかった。直ぐ側にお栄の安らかな呼吸が聞こえている。それでも頭が疲れて来、ぼんやりと、熱を持ったようになると、実際部屋の空気も濁り、暑苦しくもなっていたが、彼はやはり苦しさから、自分の腕をドサリとお栄の方へ投げ出したりした。翌朝彼が眼を覚ました時には、身仕舞を済ましたお栄が戸外(そと)の景色を眺めながら一人茶を飲んでいた。「お眼覚め?」。謙作が床の中で伸びをすると、お栄はこんな風に声をかけた。「何時ですか?」。「かれこれ九時でしょう。もう起きられるの?」。「起きましょう」。「この座敷は二人じやあ、やはり狭いのね」。「今日変えましょう」。「もし謙さんにお仕事でもあるなら、別に借りてもいい、今どうなの?」。「何にもしてません」。謙作はお栄のこう云う言葉をどう解釈していいか分からなかった。単に云っているだけの意味のものか、もっと考えて云っているのか見当がつかなかった。しかし何(いず)れにしろ、彼は別に困らなかった。前夜の彼の苦しみを知っていて云ってるとしても、お栄に対し、彼は殆(ほとん)ど恥かしいと云う気は起らなかった。それは恥知らずの気持ではなかった。総てを赦(ゆる)していてくれるだろうと云う寧ろ安心からであった。もしそれがお栄に知られたとしても、その為め、お栄は怒りもせず、又自分を軽蔑もしないだろうと云う気がはっきりしていたからであった。「彼方に、もう一つ、ちょっとした小さい座敷があるんです。今夜から其所へいらっしゃい」。「そうしましょう。---昨日行った所は大概此所から見えるのね」。 昼から二人は嵐山へ行った。帰途(かえり)、金閣寺の方へ廻ろうなど云っていたのだが、お栄がもう沢山だといい、時間も少し遅くなって、そのまま帰った。「明日(あした)は奈良へ行きましょう。それから電車で大阪へ廻ってもいい」。謙作は暫く会えないと思うと、こう云う機会にできるだけ色々な所へ案内したい気になるのだ。しかしお栄は遠慮なのか、又実際それ程歩きたくないのか、「もう本統に充分ですわ」とよく云った。「明日ひる通る。間に合うよう」。こういうお才からの電報が翌日来た。自然奈良行きも大阪行きも沙汰止みになって、その日はお栄の買い物に謙作も一緒について歩いた。その翌日二人は時間を早めに停車場へ行った。「多分三等だろうと思うの」。こう云ってお栄は下関までの汽車賃を謙作に渡した。「あの人だけですか」。「岐阜から、こどもを連れて来るでしょう」。「子供があるんですか?」。「本統の子供の事じゃ、ないの---」。お栄は仕方なしに苦笑した。「---京都からも一緒になるのがあるかも知れない」。 年のよく分らない背の低い、眼瞼(まぶた)のたるんだ一人の女が派手ななりをし、大きな男の人形を抱いて、先刻から、その辺りをうろついていた。それに二人の連(つ)れだか見送りだかの女がついていた。謙作は何という事なし、それが京都からのいわゆるこどもに違いないと思った。皆がプラットホームに出ている所に下りの汽車がついた。三等列車の、一つからお才と他の二人の若い女が顔を出していた。そして、眼瞼(まぶた)のたるんだ女は五十余りの女に手を惹かれながらその方へ急いでいた。お栄がこういう連中の一人になる事は謙作にはちょっと堪らない気がした。彼は見知らぬ二人の見送り人と一緒に三等客車の窓の前に一足退(さ)がって変に空虚な心持で立っていた。見送りの若い方の女が一人で、しきりにはしゃいでいた。先年は泣かない約束で来て、泣いて了ったが、今こう自分がはしゃげるのは今度こそ成功なさる前兆だろう、などと云った。こんな話を聴くにつけ謙作はお栄の為に危なっかしい気がした。 「そんな附景気(つけけいき)ばかり云ってないで。ちつと、お前さんの資本を此方へお廻しなさい」。お才はその若い女に揶揄(からか)った。「お前さんの六百円の電話を売って、それだけでもいいから廻しなさい」。つけつけいわれて若い女は不安そうな顔をした。お栄はお才の後ろで、黙って穏やかに微笑していた。そして、それが見かけは大変よかったが、同じような心持でお才から勧められ、それにうまうま乗せられ、これから冬に向って天津くんだりまで金を失いに出掛けて行くのだと思うと、謙作はその若い女よりも「馬鹿だな」と頭ごなしに云ってやりたいような気持になった。眼瞼の女は窓に倚りかかり、その前に立っている五十ばかりの女の手を両手で握り、その甲へ自分の頬をしきりと擦(こす)りつけていた。「ちょいと、これは上へのせた方がいいよ」とお才に云われると無智らしいその女は黙って、その手を離し、大きい男人形を上の網棚へのせ、そして直ぐ又、元のように坐って、年寄った女の手を取上げ、さも、離せないもののように、それへ頬を擦(す)りつけていた。 |
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)