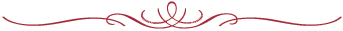
| 後編第3の1(1から5) |
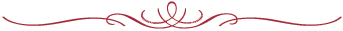
更新日/2021(平成31.5.1栄和改元/栄和3)年.8.10日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここで、「暗夜行路後編第3の1(1から5)」を確認する。 2021年.8.10日 れんだいこ拝 |
![]()
| 【暗夜行路後編第3の1(1から5)】 |
| 一 |
| 謙作の大森の生活は予期に反し、全く失敗に終わった。彼は恐ろしく惨めな気持に絶えず追い詰められ、追い詰められ、そして安々とは息もつけない心の状態で来たが、ふとした気まぐれで、一月ほど前から京都へ来て見て、彼は初めて幾らか救われた気持になった。古い土地、古い寺、古い美術、それらに接する事が、知らず彼をその時代まで連れて行ってくれた。しかもそれらの刺激が今までのそれと全く異なっていた。それが現在の彼には如何によかったか。そして如何によき逃げ場であったか。しかし彼は単に逃げ場としてでなく、これまでそういう物に触れる機会の比較的少なかった自分として、積極的な意味からもこの土地にともかくも暫く落ち着く事は悪くない事だと考えたのである。彼は丁度快癒期にある病人のような淡い快さと、静けさと、そして謙遜な心持を味わいながら、寺々を見て廻った。 それにしても、早く住むべき家を探さねばならぬのであるが、行く先々に何かしら見るに足る寺々のある京都では、貸家探しはいつか寺廻りと変る方が多かった。その日も朝涼(あさすず)の内に嵯峨方面を探すつもりで、天気続きにポクリポクリほこりのたつ白い道を釈迦堂から二尊院、祇王寺の方へ廻り、結局、目的の貸家は一軒も見ず、二尊院の「法然上人足びきの像」と称する偉(すぐ)れた肖像画をその日の収穫とし、満足して午頃、川に望んだ東三本木の宿へ引き上げて来たのである。午後中、彼はその宿の暑い小さい座敷でごろごろして暮らした。やがて、日が入りかけ、宿の女主が風呂を云いに来て、風呂に入り、それから出て、晩の食事に向かった頃には漸く河原を渡って来る風も幾らか涼しく感ぜられた。 食事を終った彼は敷居に腰を下ろし、団扇(うちわ)を使っていた。低い欄干の下を小さい流れが気忙しく流れている。新しくできた河原の広い道で男女の労働者が川底から揚げて来た砂利を大きさに従ってふるい分けている。それから所々、草の生えている賀茂川。それから日の当たった暑そうな対岸の往来、人家、その上に何本かの煙突、そして彼方に真正面に西日を受けた大文字から東山、もっと近く黒谷、左に吉田山、そして更に高く比叡の峰が一眸(いちぼう)の中(うち)に眺められた。「早く秋になるといいな」。彼はそう思った。冷え冷えと身のしまる朝、一人南禅寺から、若王寺(にゃくおうじ)、法然院、あのあたりに杖をひく自身の姿を想い浮べると、彼にはしみじみそう思われるのであつた。 彼は巻煙草に火をつけ、起ち上がって、庭へ下り、流れにかけ橋した一枚板の橋から河原へ出て見た。草いきれのした地面からの温か味が気持悪く裾から登って来る。そして其所には汗と埃で顔に隈取りをした町の児らが甚兵衛一枚の姿でまだ、ばったを追い廻していた。彼はぶらぶらと荒神橋の方へ歩いて行った。軒を並べた河原の家々では、電燈のついた下で、向き合って酒を飲んでいるのなどがと見られた。 その一軒に多分地方から出て来たらしい病人で、近いこの辺りに部屋借りをして大学病院に通っていると云う風の老人がいた。謙作は四五日前から、一人の若い看護婦とその老人の細君らしい五十余りの女の人のいるその家に心づいていた。そして今、彼が何気なくその前へ来ると、毎日は見掛けない若い美しい女の人がその縁で土鍋をかけた七厘(しちりん)の下をあおいでいるのを見た。大柄な肥った、そして火をおこしている為かその豊かな頬が赤く色づいている。それも健康そうな快い感じで彼に映った。彼はその人に惹きつけられた。普段何気なく美しい人を見る時とは、もっと深い何かで惹きつけられ、彼の胸は波立った。それはそれ程にその人が美しかったと云うのとも異う。彼は自分ながら初心者らしい心持になって、もうその方を見られなかった。そして少し息苦しいような幸福感に捕えられながらその前を通り過ぎた。 荒神橋の下まで行って引き返した。彼は遠くから注意した。その人は縁へ立って、流れを隔てた河原の人を見下ろして話していた。河原の人は年とったいつもの女の人で、云う事はわからなかったが、何か云って二人が一緒に身を反らして笑うと、若い人の声だけが朗らかに彼のところまで響いて来た。その快活な響きに思わず彼は微笑する気持へ誘われた。間もなく年取った人は川べりの方へ歩いて行った。湯上りらしく団扇を片手に持っている。そして若い方の人は土鍋のふたをとって中へ入って行った。 その人はたすきがけで働くにしてはいい着物を着ている。その日特別に手伝いに来たらしく謙作には察せられた。そして働き方もいそいそとそれに興味を持っているようなところが、何か小娘の飯事(ままごと)遊びの働き方に似て見えた。彼が前まで来た時に又その女の人は縁へ出て来た。彼は少し堅くなったが、自分でもなるべく何気ない気持になって通り過ぎた。後ろから見られるような気がして身体が窮屈であった。彼は宿へ帰ってからも落ち着けなかった。しかしそれはやはり幸福な気持だった。そしてそれをどうしたらいいのか、そして全体これはどう云う気持なのか、と思った。確かに通り一遍の気持ではなかった。彼は今日もう一度通っておかねば、明日はもう其所に居ないだろうと思った。で、自身玄関の下駄を庭へ廻し、再び暗い草原道へ出て行った。その時は既に暮れ切ってはいたが、河原は却って涼みの人達で賑わった。彼は多少気がひけながらその方へ歩いて行った。 女の人は年取った方の人と縁へ坐って涼んでいた。部屋には蚊帳が釣られ、その上に明るい電燈が下がっていた。並んで川の方を向いている二人の顔は光を背後(うしろ)から受けているので見られない代りに、此方はそれを真正面(まとも)に受けねばならぬので、余り見る事ができなかった。女の人は湯上りらしく白い浴衣(ゆかた)を不格好に角張らして来ていた。そしてその角張った不格好さも亦彼には悪くなかった。二人は団扇を使いながら、しんみりと話し込んでいた。荒神橋まで往ってあがり、今度は対岸を丸太町橋の方へ引き返して来た。遠く影絵のように二人の姿が眺められた。橋の袂(たもと)から、彼は東山廻りの電車に乗った。丁度涼み客の出盛る頃で電車は込んでいた。彼は立ったまま、祇園の石段下まで行って、其所で降りた。 彼は自分の心が、常になく落ち着き、和らぎ、澄み渡り、そして幸福に浸っている事を感じた。そして今、込み合った電車の中でも、自分の動作が知らず知らず落ち着き、何かしら気高くなっていた事に心附いた。彼は嬉しかった。その人を美しく思ったという事が、むそれで止まらず、自身の中に発展し、自身の心や動作に実際それほど作用したという事は、これは全くそれが通り一編の気持でない証拠だと思わないではいられなかった。そして何と云う事なし、あの気高い騎士ドン・キホーテの恋を想い出していた。彼は大森でその本を読み、その時はそれ程に感じなかったが、今自身の心持から、ドン・キホーテの恋も、それを彼が滑稽を演ずる前提とのみ見るべきではない事に考え附いた。勿論トボソのダルシニアと今日の人とを比較するのはいやだった。しかしドン・キホーテの心に発展し、浄化されたその恋は如何に気高い騎士を更に気高くし、更に勇ましくしたか、---彼には変にそれがピッタリと来た。彼は自身のそれをどう進ますべきか、そういう事を考える気もなく、只、彼に今、起っている快い和らぎ、それから心の気高さ、それらに浸っていた。四条通りをお旅まで行き、新京極の雑沓(ざっとう)を人に押されて抜けながらも彼の心は静かだった。そして寺町を真直ぐに丸太町まで歩き、宿へ帰って来た。 この事はどうしたらていいか、彼はそれを考え始めた。このままにこの気持を葬る事は断じてしまいと決心した。しかし只同じ家並(やな)みにいるというだけで、しかも両方が一時的に宿っているのであれば尚、余程にうまい機会を捕らえない限り、この事は恐らく永久に葬られては了わないだろうか。此方から積極的に機会を作って行くなどという事は考えられなかった。同様に自然に或る機会が来るだろうとも考えられなかった。彼は自分が余りに無能な気がして歯がゆかった。彼は彼の或る古い友達が、そういう機会を作る為にその人の家の前で、故意に自分の自転車を動かせない程度にこわし、その家に預かって貰い、翌日下男を連れて取りに行き、段々に機会を作って行った話などを憶い出した。しかし自分の場合ではその前で偶然卒倒でもしない限り、そんなうまい機会は作れそうもなかった。 とにかく、もう一度前まで行って見ようと思い、彼は又庭から河原へ出た。まだ雨戸は開いていたが、電球には緑色の袋がかけられ、中はしんとしていた。町へでも出たか、さもなれりばその人の帰るのを送って出たか。彼はちょっと淋しい気がした。そして、第一、その人は純粋に独身なのか、或いは自身望む人でもいるのではないか、こう云う疑問を起こし高と彼は甚く頼りない気もして来た。 |
| 二 |
| 翌朝、彼が起きた時にはもう陽は大文字の上に昇っていた。彼は顔を洗うと座敷の掃除のできる間又河原へ出た。草の葉にはまだ露があり、涼しい風が吹いていた。彼は余りに明かる過ぎる広い道に当惑した。しかし故意に図々しく、自分を勇気づけ、その方へ歩いて行った。多分もういんいだろう。しかしもし居てくれたら自分には運があるのだ、そう思った。彼方から朝涼り内にきまつて運動するらしい、前にも二三度見掛けたことのある四十余りの男の人が、今日も、身仕舞いを済ませた小さい美しい女の子を連れて歩いて来た。その人達の無心に澄んだ空気を楽しんでいるような、ゆつたりした気持がその時の彼には羨ましく感ぜられた。 そして女の人はやはり前日のように縁に出ていてくれた。彼はドキリとして進む勇気を失いかけた。が、その人は彼の方には全く無関心に、寧ろぼんやりと、箒を持ち、手拭を姉さん被りにし、注意を奪われ切ってその美しい女の児の方を見ているところだった。この事は彼には幸いだった。けれども同時にその人の顔には昨日のような美しさがなかった。彼は多少裏切られた。一々こんな事で裏切られていては仕方がないと自分で自分を食い止めたが、その内女の人は、ふと彼から見られている事を感じたらしく、そして急に表情を変え、赤い美しい顔をして隠れるように急いで内へ入って了った。彼の胸も一緒にどきついた。そして彼はその人のその動作を大変よく思い、いい感じで、その人は屹度馬鹿でないと云う風に考えた。 彼は今日は家探しをやめ、午前中博物館で暮らそうと思った。博物館は涼しかったし、それに来た時見た物は大概陳列替えになつているだろうと考えた。宿へ引き返し、朝めしを済ますと、直ぐ電車で博物館へ向った。博物館の中は例のごとく静かだった。分けてもその日は静かで、観覧者としては謙作以外に一人の姿も見られなかった。そしてこういう静けさが却って謙作を落ち着かない気持に追いやった。制服を着た監視の一人が退屈そうにカッタン、コットン、カッタン、コットン、と故(わざ)と靴で調子を取りながら腰の上に後ろ手を組み、靴の爪先(つまさき)を見詰めながら歩いて来た。そのカッタン、コットンという響きが高い天井に反響し、一層退屈な、そして空虚な静けさを感じさせる。その辺りに掛けられた古い掛け物の絵までが、変に押し黙って、まわりかに凝っと此方を見ているように謙作には感ぜられた。彼は親しみ難い、何か冷たい気持でそわそわと急ぎ足にそれらの絵を見て廻った。しかしふと、如拙(じょせつ)の瓢箪鮎魚図(ひょうたんでんぎょず)の前へ来て、それは日頃から親しみを持っていたものだけに暫く見ている内にその絵の為に段々彼の気持は落ち着いて来た。絵から何か話しかけて来るような感じを受けた。 支那人の絵で南画風の松にも彼は感服した。気持が落ち着くに従って絵との交渉が起って来ると、呂紀(りょき)の虎、それからやはり支那人の描いた鷹と金鶏鳥の大きい双福の花鳥図などに彼は甚く惹きつけられた。泉湧寺(せんやうじ)出陳(しゅっちん)「律宗三祖像」、顔は前日見た二尊院の肖像画に較べて遠く及ばない気がしたが、それでも曲ろく(きょくろく)に掛けた布(きれ)とか袈裟(けさ)などの美しさは感服した。総じて彼がこういうものに触れる場合彼の気分の状態が非常に影響した。興に乗るという事は普通能動的な意味で多く用いられるが、彼では受動的な意味でも興に乗ると乗らぬとでは非常な相違があった。これはこういう美術品に触れる場合、殊に著しく感ぜられる事であつた。そして今日も最初は妙に空虚な離れ離れな気分で少しも興に乗れなかったが、段々にそれがよくなつて行くのが感ぜられた。彫刻では、広隆寺の弥勒思惟像、これは四五日前太秦(うずまさ)まで見に行って、却って此所(ここ)へ出してある事を聞き、この前は見落していた事に気づいたものであった。 少し疲れて来た。いい加減にして其所を出ると、彼は歩いて西大谷(にしおおたに)の横から鳥辺山(とりべやま)を抜け、清水(きよみず)の音羽(おとわ)の滝へ行った。水に近い床几(しょうぎ)に腰を下ろすと彼は何よりも先ず冷たい飲み物を頼んだ。彼は疲れた身体を休めながら、東京からすると一体に華美(はで)な装いをした若い人たちの姿などを見ていた。高台寺(こうだいじ)の中に貸家ができつつあるという話を憶い出し、彼は少時(しばらく)して、その方へ行った。貸家は二階建ての二軒棟割りになった家で悪くなかった。町への出端(でば)もよく、彼は気に入ったが、疲れから大家(おおや)まで行く事が大儀に思われ、そのまま八坂(やさか)神社へ出て四条通りを帰って来た。 四条の橋を渡った所に、川へ突き出しを作った安直な西洋料理屋がある。それへ入った。どのみち風のない日だったので、彼はなるべく陽に遠い空いたテーブルを選んで腰を下ろしたがやはり先ず飲み物が欲しく、椅子へ横向きにかけ、振り返っていたが丁度立て込む時で女中は中々廻って来そうになかった。彼はふと、自分から三つ四つへだたったテーブルで一人、忙しくナイフとフォークを動かしている男に気がついた。のだ食っている内からナイフを挙げて、「オイ、シチウ。---わかりましたか」。こんな事を太い声で云った。やはり高井だった。謙作は自分の麦藁帽子を取上げ、起って行った。「オイ」。こう云ってちょっと肩を突(つつ)くと、高井は不審そうに振向いて眼を見張ったが直ぐ、「オオ」と云って起ち上がった。「うまく会えたね」。「本統に」と高井も嬉しそうに云った。 二人は丁度二年振りで会ったわけである。その頃謙作は五六人の友達と同人雑誌を出そうとした。高井もその一人として、彼が洋画家であるところから、装幀(そうてい)を引き受け、尚、詩や短歌なども出す筈であったが金の事がうまく行かず、一(ひと)先ず雑誌は延ばす事にすると、間もなく高井は胃から来た割に烈しい神経衰弱にかかり水治(すいじ)療法をやる神戸の衛生院に入り、其所に一年近く居て、殆ど全快し、それから但馬(たじま)の方の郷里へ帰っている、という事を謙作は人伝手(ひとずて)に聞いていたのである。「この頃は此方なの?」。「いや、奈良にいる。春からずっと奈良にいるんだが、何処へも御無沙汰している。---で、君は何時来たの?」。謙作はこの地へ住まおうとしている事などを話した。高井は自身のいる奈良へ来る事を勧めた。「奈良でもいいけど、---差し当たりやはり京都へ住みたい」。こう云いながら謙作は自分の問題を高井に打明け、相談して見てもいいと考えた。 暫くして二人は其所を出、連れ立って東三本木の宿へ帰った。そして謙作は前日からの事を割りに精(くわ)しく高井に話した。「随分真剣なんだね」。高井は二十前後の青年かなぞのような初々(ういうい)しい謙作の感情をちょっと意外に感じたらしかった。「僕としては純粋な気持だ。しかしこれからどう進ませるか、それは今のところちょっと見当がつかない。もしこのままにしていると今までの経験では、又、有耶無耶になりかねないが、何となくそうはしたくない気があるんだ」。「積極的にやるのさ、どういう人か調べて、誰かに申込んで貰うんだ」。「そうてきぱき行けばいいが---」。「頼むのさ、誰か人にやって貰うのさ」。「うん」。「僕でもできる事ならやりたいが、こんな書生っぽでは彼方が信用しまい」。「君にやって貰えれば僕には最も嬉しい事だ」。「そう---やれるかしら。やれれば僕も喜んでやるが」。高井はちょっと考えていたが、「その家に部屋があるかね。僕がそれを借りて住む事ができれば---、大概、人の見当はつくが---。もし君に不賛成がなかったら、こんな事も一つの手段だね」と云った。 謙作は賛成した。が、同時に、彼はこんな風にしてどんどん事が進んで行き、又、或るところで不意にそれが破れたりするのではないかという不安を感じた。それが自分の運命だと云う気が近頃の彼には直ぐして来るのである。この反省は自身のいじけた姿を突きつけられる点で二重に彼を暗い気持に誘った。しかし彼の他の心はそれを反発し、殊更、自身をそういう気持から超越させようとした。「今、いるかね?」と高井が云った。「わからないが---」と謙作は微笑しながら「見に行こうか?」と気軽く答えた。「僕だけ見て来よう。その方がいいだろう」。 謙作は精しくその家を教えた。高井は直ぐ庭から河原の道へ出て行った。高井が如何にも何気ない風で歩いて行く、そして、それとなく眼だけでその家を探している様子が背後から見ていて甚く可笑しかった。しかしこうしてこの事がもし順調にいくものとすれば高井のあの可笑しな後姿も只笑ってはいられないと思った。それにつけても自分は自分の出生を少しも隠す事なしに、話し、彼方(むこう)にその事から先ず解決して貰わねば---と考えた。間もなく高井は笑いながら帰って来た。「わからない」。彼はこういって首を振った。「間抜けだな」。謙作も笑った。「そんな筈はない。一緒に出よう」。「何しろ、この一町以内にはそんな人は一人もいない」。「そんなら今いないんだ。とにかく出てみよう」。謙作は下駄を廻し、帽子を被り暑い戸外へ出た。「あの朝鮮すだれの下がっている家だ」。「ふむ。そうか」。「居るじゃあないか」。謙作はその方を少しも見ずに云った。「どれ」。「坐ってる」。彼は今度は叡山の方を向いて云った。「わかった」。一足後(おく)れになった高いが背後から、「通りからでも、どの家か分かるかい?」と訊いた。「帰りに見て行こう」。こう云いながら謙作は振り返って、目標になる三階建ての家から、二軒、三軒、四軒目、と心覚えをしておいた。 二人は荒神橋の袂から往来へ出た。謙作は自分が自分ながら可笑しいほど快活な気分になっている事に気がついた。その人の姿の片鱗を見たというだけでこうも変る自分が滑稽にも亦、幸福にも感ぜられた。こうしてこの事が順調に運び、うまく行けば、今までにない、本統の新しい生活が自分に始まるのだと思った。実際今までは総てが暗闇に隠されていた。その為に、却って恐ろしい黴菌(ばいきん)が繁殖した。総ては明るみへ持ち出される。そして日光にさらされる。黴菌は絶やされる。そして、初めて、自分には、自分らしい本統の新しい生活が始まるのだ。 「それはそうと」と謙作は不意に並んで歩いている高井を顧みた。「君は奈良を引き上げてもかまわないのかい?」。「ああ」。「しかし彼方で何か描いているんだろう」。「あるけれど、それはもう二三日やればいいんだ。それに京都で描きたい所もあるから僕の心配要らないよ」。二人はそれから寺の土塀について左へ折れ、狭い東三本木の通りへ入った。そして少し行くと謙作が目標にしていた三階建ての家があり、それから数えて、その家を直ぐ知る事ができた。「君は先へ帰るだろう」と高井が云った。「今、直ぐか?」。謙作は余りに気が早過ぎる気がしたのでちょつと眼を見張った。「こういう事は愚図/\してない方がいいのだ」。高井は無造作にこう云ったが、謙作にははっきりした理由なしに、それが危ぶまれた。「まあ、帰って待って玉え」。高井は軽く会釈して格子を開け、狭い石畳の路次へずんずん入って行った。 謙作は独り宿へ帰って来たが、帰りながら彼は昔、或るむさくるしいなりをした大学生が上野公園で美しいお嬢さんが車で行くのを見掛け、直ぐそれを追いかけ、車が家へ入ると一緒に主人に面会を求め、結婚を申し込み、その場でうまく話をまとめたという話を憶い出した。これはその大学生の友達だった国語の教師から聴いた話なので、彼は多分本統だろうと思っている。そしてそれを聴いた時彼は随分笑ったものの、何となくその男のやり方に、不快な気持が感ぜられた。一つはそれだけの話ではその男の率直さの程度が本統に感ぜられないからでもあったが、もう一つは彼の行為の上の趣味から云ってそういう奇抜さが嫌いであり、そういう奇抜さに興味を持つ人が好きになれなかったからでもあった。しかし高井のやり方が同じようになる気づかいはないと彼は安心しながら帰って来た。 彼は直ぐ湯殿へいって水で身体を拭いた。其所に高井が苦笑しながら帰って来た。「断られたよ。本統か嘘かわからないが部屋がないそうだ」。謙作も一緒に苦笑した。が、別に落胆はしなかった。「しかし本統かも知れないよ。もし、なんなら、もう一遍この家から訊いて貰う事もできるし」といった。「そうだね。最初からそうする方がよかったかも知れない---とにかくもう一度訊いて貰おうか」。「そうしよう」。二人は部屋へ来た。宿の女主(おんなあるじ)が直ぐ茶道具を持って来た。「東三楼ですかね。この向うにありますね」。高井は直ぐ云い出した。「へえ」。女主は茶を入れながら返事をした。「あすこは、下宿もさせるのですか?」。「へえ、よう大学や私立へ通われる病人さんが宿られるよう聞いとりますが」。「実は今、部屋を訊いて見たんです。---」。「へえ」。「部屋がないと断られたんです。しかしそれがぶっつけに行ったんで、断られたのか、実際ないのかよく分らないんです。本統の事が訊いて貰えると都合がいいんですが---」。「早速訊ねて参じましょう。あのお家は前のお方やと。極く御懇意に願うとりましたが、一昨年代かわりになりまして。まだお馴染みは薄うござりますが、自家の仕出し屋があのお家にも入りますさかい、仕出し屋に訊ねさせましょう」。女主はそういつて立って行った。そして直ぐ又一通の手紙を持って、「えらい済まん事で、お昼頃参っとりましたのを、つい忘れまして」と云い訳して謙作へ渡した。それは鎌倉の信行からの手紙だった。「要事」としてかなりに重みのある手紙だった。 |
| 三 |
| 御無沙汰している。元気の事と思う。お前の先日の便り嬉しく見た。京都気に入った由何より。いい家見つかったか。これから段々よくなる時候で、楽しそうだ。いずれ家でも見つかったら、帰って来る事と思うが、その前にとにかくお前に考えておいて貰いたいからとお栄さんに頼まれたのでこの手紙を書く。実は一昨日(おととい)お栄さんから手紙が来て相談したい事があるから、上京の折り寄ってくれとの事で昨日行ってみた。 お前も知っているだろうがこの頃大森にはお才さんというお栄さんの従妹(いとこ)が来ている。お栄さんはお才さんの前身について余り云いたがらないが、察するにやはり身体で商売をした人らしい。現在もはっきりした事は分からないが、何でも天津(てんしん)で料理屋をしているのだという事だ。料理屋と云っても東京あたりの料理屋とは異った性質のものだろうと思う。それでお栄さんの云う事は、本来ならば、お前との関係もお前にいい嫁さんができ、ちやんと、新しい家庭が作れたところで、身を退くのが本統とは思うが、今となれば本郷の父上のおもわくもあり、どうしたものかと実は迷っていたと云うのだ。これを云い出すと又お前の気を悪くするかも知れないが、お栄さんとしたら尤もだと俺は考える。 其所(そこ)で今度十年ぶりとかでそのお才さんという人が却って来て、できる事なら自分の仕事をお栄さんにも手伝って貰いたいと云うのだそうだ。勿論手助けだけではなく金の方が主なのだろうと思うが、何しろお栄さんの方もそれには大分乗り気らしい。で、お栄さんはこういったからとて、前に話のあった本郷からの金を貰いたいとか、そういう気持は少しもないので、もしこの事にお前でも俺でもが、不賛成でないと云う事なら、幸いお前も今度京都へ住むと云うし、この家を畳み、千何百円かの貯金を持ってお才さんと一緒に天津へ行きたいと云うのだ。まあ簡単に云えばこれだけの事だ。 いずれ精しい事はお前が帰った時に話し合うつもりだが、それまでにお前もこの事をよく考えておいて貰いたい。俺はお才さんという人が、どういう人か、そして一緒にするといってどんな仕事をするのか、そんな事もそのうち、はつきり聞きたいと思っている。金の事も俺は考えているが、これはなるべく俺に一任しておいて貰いたい。お前は何日頃帰れるか。帰りに鎌倉へ寄ってくれると好都合だ。では左様なら。 謙作は読みながらちょっと異様な感じがした。お栄が天津へ行って料理湯をする、この事が如何にも突飛な気もし、一方如何にも有り得そうな気もした。しかしそのお才という女がどんな女か、それにだまされるような事があっては馬鹿馬鹿しいと思った。とにかく、謙作にはその手紙に書かれた事は余りいい気がしなかった。自分とお栄との関係が今後どうなって行くか、それは彼にもはっきりした考えはなかったが、こんなにして、二人が遠く別れて了い、交渉がなくなって了うという事はやはり結局二人は赤の他人であったという---余りにそう云う気のされる事で彼にはそれが淋しく感ぜられた。しかしどうすればいいか、その的(あて)もなかった。 女主が入って来た。東三楼という家にはやはり空間(あきま)がないという返事だった。「今、表にいられます。お年寄りの病人さんが二十日もしたらお国へ帰られます筈やで、そしたら、そのお座敷が空きますがちゅう御返事でござりました」。「ありかどう」。高井はこう云った。「どうも、それでは仕方がない」。女主は帰って行った。「しかし訊いて見てよかったよ」と謙作は云った。「二十日もするとあの老人が居なくなる事がわかっただけでもいい」。「そうだ。それまでにどうかしていい手づるを作るんだ」と高井も云った。「もしかしたら兄貴に来て貰おうかしら。今手紙が来て、自家の方の事で少し話したい事があるし、尤も僕が帰る方が早いかも知れないが、そうしてると、此方が不安心だから」。「うん、それがいいかも知れない。そうし玉え。兄さんは何時でも出て来られるんだね」。「大概来られるだろうと思う」。「早くその人が何所(どこ)の人か、そしてあの老人とはどういう関係の人か、それを確かめるといいね」。「あの人の娘かね?」。「さあ」。「姪かね?」。二人は笑った。「そう観察力が鈍くちゃ仕方がないな」。「眼がくらんでるんだ。---しかし娘じゃあないよきっと」と謙作は云った。「兄さんへ手紙を書くなら遠慮せずに書いてくれ玉え。そしたら僕はちょっと五条まで買物に行って来る」。こういって間もなく高井は宿を出て行った。 謙作は後で信行へ手紙を書いた。お栄の事、それから自分の事、それを書くとかなりに長くなった。どうせ最近会うのにこんなに精しく書く必要はないのだ。そう思い思いやはり惰性的に色々書いて了った。彼が坐り疲れた身体を起し、その手紙を頼みに立って行くと、玄関の狭い廂合(ひあわ)いから差込んで来る西日で、いつもねは薄暗い廊下の縁板が熱くなっていた。彼は少時(しばらく)して湯に入り、又前日のように団扇を持って腰を下ろしていた。遥か荒神橋の方から何気ない真顔で、急ぎ足に帰って来る高井の姿が眼に入った。そして前まで来ると今度は割りに大胆にその方を見ていた。間もなく高井は一枚橋を渡って微笑しながら帰って来た。「よく見た」。「そうだろう。恐らく一度で僕よりよく見たらしい」。「あれは君、鳥毛立屏風(とりげだちびょうぶ)の美人だ」。突然こんな事を高井が云った。この評は割りに適評であり、謙作には大変感じのいい評であった。「ふむ、そうかな」。そう云いながら謙作は自分が赤い顏をしたように思った。 高井は湯へいった。その間に謙作は又ちょっと河原へ出て見た。前まで行く気がせず、遠くからそれとなく気をつけていると、その人の姿は時々見えた。その晩二人は新京極へ活動写真を見に行った。「真夏の夜の夢」を現代化した独逸(どいつ)物の映画を二人は面白く思い、晩(おそ)くなって二人は、東三本木の宿へ帰って来た。 |
| 四 |
| 三日目、それは珍しく明け方から雨になり割りに涼しい朝だった。毎朝雨戸を照りつけられるので寝坊のできなかった謙作はよく寝ていた。其所へ夜行で来た信行がついた。「おい、朝めしがまだだが貰えるかい」。こんな風に挨拶よりも先に、信行がいう。謙作は一体寝起きの不機嫌な方だったが、その日はよく眠ってもいたし割りに愛想よく兄を迎える事ができた。 暫くして二人は雨にけぶる河原の景色を眺めながら朝の食事をした。「お前の方の事をお栄さんに話したら大変喜んでいられたよ。是非ともというような事を仕切りと俺に繰り返していた。それは本統に俺も嬉しい事だし、うまくやりたいもんだね」。信行は続けて、「それでね、お栄さんの方の事を先に話すと、俺はね、その事が本統にお栄さんの為になる事かどうか、はっきりしないんだ。そうかといって、それに不賛成をいって、他にどうという、うまい考えもないとすると、一途に否定するわけにも行かず、又案外それでうまくやって行くかも知れないとも思うし、それからお栄さん自身はそのお才さんにすっかり勧め込まれて了って非常に乗り気なので、この場合俺達が不賛成をいえばよすにはよすだろうが落胆も随分するに違いない。で、俺の考えとしては、お栄さんの考え通りに総てして、つまり、全く自由にして、もし、それで不成功だった場合、あとを此方でどうにでもするようにしたらいいかと思うんだ。一言にいえば又金の話になるが、金は本郷からのと、お前からのがあれば、それを一つにして俺でもお前でもが保管して置く、そんな事にしておいてはどうかと思うんだ」。「全体何をするんだろう?」。 「それが、どうも余り感心しないのだが、お才さんという人が天津で料理屋をしているのだ。其所にいわゆる内(うち)芸者というのがあるそうだ。芸者といっても勿論二枚鑑札だが、それを今までは両方一緒にやっていたが、手が廻りきらない為にその芸者の方一切をお栄さんにやって貰いたいというのだそうだ。つまり、上方(かみがた)でいえば置屋(おきや)見たようなものだ。それが別になっていずに同じ家に一緒にいて資本は別でやつて行こうというのだ」。謙作にも大概見当はついた。「ひどく品の悪い商売じゃないか」。「其所がどうも感心しないが、煙草屋をやる、小間物屋をするといったところで、東京だと家賃はとにかくとして造作とかいうのが非常に高く、それだけで、もう仕入れの金も何にもなくなるくらいだろう」。「そういう事は具体的に云えといわれると一言(いちごん)もないが何かもう少し品のいい商売がありそうなものだ」。 「何といってもお栄さんはやはり水商売の人だね。幾らか昔の経験があるから考えがどうしてもそつちへ入って行くらしい。それでお才さんという人がどういう人か、それが信用できる人なら、一切任せてもいいが、其所がはっきりしない点で、此方で後の余裕を残しておく必要があると思うよ」。「僕にはよく分らない。他に仕事があるものなら勿論他の仕事を探す方が賛成だが、他にないなら仕方がないし、もし又自分で急にそんな事をする必要がないという気になれるようなら、二三年これからも一緒にいて貰って少しも困らないがな。少しセンチメンタルかも知れないが、僕はこんな風にしてお栄さんと別れて了うのは何だか物足らない」。「ふむ------」。「お父さんの方への気兼ねの事もこの間書いてあったが、そんな事は僕がもし結婚すれば問題にはならない事だし---」。「まあ、それは---やはり二三年後に別れるものなら、今別れて了った方がいいと俺は思う。それはセンチメンタリズムだよ。やはり何にでも時期と云うものがあるよ。時期によっては生きる事柄が、それを外して、生きなくなる場合がある」。 「つまり本郷から金を貰う事かい?」。謙作は結局信行はこの事をいつているのだろうという可笑しいような、同時に多少いらいらした心持もして露骨にこう云った。「それも一つだ」と信行は案外真面目な顔をして答えた。「それで、そっちの方は手紙にも書いた通り一切俺に任せる事にして、なるべくお前は立入らん事だ。お前のは強迫観念的に金の事をいうと損をしておきたがる潔癖がある。欲の深いのよりはいいが、利口な事じゃない」。「そんな事あるもんか」。「それはまあ何方(どっち)でもいいが、其所でどうだろう、今いった俺の考えにお前は賛成するか、どうか」。「お栄さんの云い出した通りにするという事かいはてな」。「そうだ」。「そうだな---賛成はできないが、仕方がないな。賛成するといえばいやいやの賛成だな」。「そうか。まあ、それでいいだろう。もしいけなかったら、又その時でどうとでもできるんだから---」。 「何時から行く気なのかしら?」。「きまれば、早いへ方がいいんだろう。なるべくならお才さんという人と一緒に行きたいんだろうが、もう直ぐ、お才さんは行って了うんだろう。何しろ不賛成のない事早く知らしてやる方がいい。あとで電報を打ってやろう」。「------」。「其所でお前の方の事だが、大体、お前の手紙で分かっているが、今でも居るんだね?」。「居るだろう。あんまり通るのも変で少し遠慮しているが、見えたり見えなかったりだ」。「高井君はもうあれっきりかい?」。「ああ」。「俺は一つ考えがあるんだが、お前は山崎を知ってるかね。高等学校でボールの選手をしてた」。「知らない」。「俺の級で三部だが、寮が同じで割りに親しかった。その山崎が、此所の大学病院にいる筈なんだ。何科か分からないが、俺は山崎に頼んで、病院の方から多少でも手蔓(てづる)を作る事ができそうに思う」。 謙作は黙って点頭(うなず)いていた。「うまく行くものなら、そんな事でもうまく行くだろうし。---」。彼はこう云ったような気持だった。彼には自分にいい運の向く事を信ずるのが却々(なかなか)困難だった。半信半疑を、もっと疑問の方を強くしておかないと不安心だった。習慣的にそうなっていた。「俺の手に合わなかったら、石本を頼んでみよう」。信行がこういったのは石本は公卿(くげ)華族で何かと手蔓を作る便宜が多いというつもりなのである。「そんな事いってる内に京都から国へ帰って了う」と謙作は云った。「なに、国によってはもっといい手蔓ができる---それはそうと今日はどうするかな。お前は何か予定でもあるのか?」。「別に」。「そんなら、どうしようか。山崎でも訪ねるか。それとも今日は休養という事にして何かうまい物でも食いに行くか」。「何方(どっち)でも」。「一日でも早く山崎に会う方がいいかな?」。「何方でもいい」。「それじゃあ、やはり山崎に会っておこう、そして晩一緒に何所かへ行こう」。「そう。それなら、そうして貰おう」。 |
| 五 |
| 謙作の結婚の話は案外うまく進みそうになった。それは信行の学校友達の山崎という医学士が丁度、その老人を診ている博士の助手だった事から、急に色々な事がはつきりした。女の人は老人の姪(めい)であると云う事、敦賀の在のいわゆる物持ちの家の人であると云う事、そして、京都へは老人の見舞いを兼ね、冬物の衣装その他を買う為に出て来たのだというような事まで分かった。それからもう一つ謙作の為に幸いだった事はその老人を博士へ紹介して寄越した市会議員のSという人が偶然にも石本のいわゆる旧臣だった事である。この事は東三本木の宿でその人の名が何気なく山崎の口から出た時に女主が「そのお方さんやったら、石本さんの元の御家来やと思うとりますが---」といったので分かった。 ともかくも愚図愚図しない方がいい、こういう事で信行は石本に会う為に帰って行った。謙作は自分のその事に信行が本気で働いてくれるのを心で感謝した。そして石本に対しても、前に「君達にそういう心配はして貰いたくない」とか「そういう老婆心が不愉快なのだ」とか云った自分が一年経たぬ内に結局その事で世話にならねばならなくなった事を彼は面白く感じた。「それ見ろ。あんな立派な口をききながら到頭あたまを下げる事になったろう」。こんな風に石本が思うかも知れない、と考えた。そう思うなら思ってもよろしいと彼は又考えた。結局石本も信行のようにそういう事が謙作に意外に早く来、そしてそれが偶然にしろ、彼自身の手に頼らねばならなくなつた事を心から喜ぶ事が知れていた。それ故、謙作には何の反抗心らしいものも起っては来なかったばかりでなく、もし同じ事で石本でない人に手頼(たよ)らねばならぬ場合を想像すると、それが偶然にしろ石本であった事を彼は一層気持ちよく感じないではいられなかった。要するに自分は不幸な人間ではないと謙作は考えた。自分は全くの我儘者(わがままもの)である。自分は自分の想う通りをしようとしている。それを人は許してくれる。自分は自分の境遇によって傷つけられたかも知れない。しかしそれは全部ではない、それ以上に自分は人々から愛されていたのだ。こんな事を思った。 彼は相変わらず寺廻りをした。そして出入りにはよく河原の道を通った。彼は又家探しもした。彼は南禅寺の北の坊という所に先日高台寺(こうだいじ)で見たよりも、更に気持のいい一軒立ちの草葺(くさびき)屋根の家を見つけた。それは一人住まいの寓居としてはこの上なくいい家だった。結婚するとすれば少し狭過ぎる気もしたが、それを予想して今から大きい家へ入るのもちょっと変な気がしたし、殊に貸家としてでなく建てられたその家が彼には気に入った。で、彼はそれを借りる事に決めた。二三日すると石本が来た。石本は何の厭味らしい冗談も云わなかった。それはよかつたが、そして直ぐ実際の話を始めた時に、「無論彼方の事も精しく訊くつもりだが、此方の事もできるだけ精しく話しておく方がいいだろうね」と石本が云った。「そうしてくれ玉え」。謙作は石本が「此方の事」というのは何(ど)の程度までをいうのか不安心に思った。多分、総てを云ってくれるのだろうとは思ったが、自分さえ近く知った自分の出生を、本統によく石本も知っているかしら? それが疑われた。で、彼は「つまり僕の出生の事も云ってくれるんだね」と云った。彼がこういった心持は、勿論それを云ってくれなければ---というつもりだったが、石本にはそれが反対に響いた。「出生の事も云って了うのか」。こう謙作が弱音を出したようにとった。石本はちょっといやな顔をした。そしてその事は隠さず打明けねばならぬという事をくどくどと云い出した。謙作は心外な気がした。「勿論そうだよ」「初めからそのつもりだつたのだ」こんな事を云ってみても、自分ながらそれが後からの附け足しらしく聞こえ、不愉快な気がした。そして結局石本の長談義を彼は終りまで聴いて了った。彼は多少苛々(いらいら)もしたが、後で信行に云えば分る事と思い、その気持の行き違いは到頭そのままにして了った。 謙作がその事を信行にはっきり云っておかなかった事がこの行き違いを作ったのである。謙作はそれを考え考え遂に云い出さなかった。その事を先ず第一に云うという事が余りに自分らしい気がして厭だった。実際それは余りに彼らしい潔癖に見えたろう。それ故、彼は半ば無意識に、半ば意識しつつそれを云わなかった。そしてこの事が大森の家で信行と石本とお栄との間で話された時に、お栄は何よりもそれを云う事に反対した。反対の理由は簡単で、はっきりしていた。しかし石本はどうしても先ずそれを云わねばならぬと主張した。それでなければ自分は間に入れないと云った。こう石本のいう理由もはっきりしていた。勿論それは謙作も同じ考えであったが、石本は「何故(なぜ)謙作がこの事を第一に信行に云わなかったろう?」。これを疑問にしたらしかった。行き違いは此所から発していた。しかし幸いに謙作はそれに余り拘泥せずに済ませた。この事はそれだけで済んだ。石本は麩屋町(ふやちょう)の行きつけの家へ宿を取っていた。そして二時から宿でS氏と会う筈になっているからと、間もなく帰って行った。 謙作は自分の事を彼方に打明ける一つの方法として、自伝的な小説を書いてもいいと考えた。しかしこの計画は結局この長篇の序詞に「主人公の追憶」として掲げられた部分だけで中止されたが、その部分も何かしら対手(あいて)に感傷的な同情を強いそうな気がして彼はそれを彼方へ見せる事をやめた。そして彼は後になってそれを聴いたが、石本は謙作がその事について尾の道から信行へ出した、最初の手紙を持って来ていて、その中のお栄に関する部分だけを消して先へ見せたと云う事である。お栄に関する事も打明けねばならぬと思いながら、謙作にはこの事の方は、ひどく苦しかった。何故かわからなかった。そんな事を今いうと云う事が、あの美しい人に対し、冒涜である、そんな気持に近かった。石本もそれには触れようとしなかったし、彼も或る時、打明ける機会に隠さなければいいのだと考え、それは殊更には云わない事にした。 日暮れ前だった。謙作はちょっと近所の古本屋を二三軒歩き、河原の路から帰って来ると、手紙を持った石本からの使いが待っていた。「差支えなかったら今夜S氏と会って貰いたい。この車で直ぐ来てくれると好都合だ」。こんな事が書いてあった。彼は直ぐその車に乗って出掛けた。石本は一人で彼を待っていた。「本人に就いての詳しい事は何も分からなかったが、極く大体の事は聴いた」。こう石本は云った。それによると、老人は明治三十年代の代議士だった人でS氏とは同じ政党の関係で前からの知り合いだと云う事、そしてその女の人は老人の妹の娘で、敦賀の女学校を二年前に出て、嫁入り前の支度旁々(かたがた)衣装を買いに来たのだという事、この程度の事だった。で、その晩は、大した意味もないが、S氏の案内で何所かへ一緒に飯を食いに行こうと云うのであった。 間もなくS氏が誘いに来た。S氏は五十余りの額のぬけ上がった痩せた人でその薄い柔らかな髪の毛を耳の上から一方へ一本並べに綺麗になでつけていた。そして石本の事を道隆という名で道様/\と呼んでいた。すっぽん料理へ行く事にして三人はその宿を出た。そして或る所から電車に乗り北野の方へ向った。すっぽん屋は電車通りから淋しい横町へ入り、片側にある寺の土塀の尽きた、突き当りにあった。金網をかけた暗い小行燈(こあんどう)が掛けてあり、そしてその低い軒をくぐると、土間から、黒光りのした框(かまち)の一部屋があり、其所から直ぐ二階へ通ずる、丁度封印切りの忠兵衛が駆け降りて来そうな段々があって、これも恐らく何百年と云う物らしく、黒光りのしている上に、上の二三段き虫に食われてぼつぼつと穴があいていた。それをそのままにしてあつた。これも一つの見得には違いないが、悪くないと謙作は思った。すっぽんも、うまかった。昔このすっぽん屋が、蝦蟇(ひきがえる)を捕りに来たという話を謙作は北野の方の池のある屋敷へ住んでいた人から聴いた事があったが、今はそういう事はないに違いないと思いながら食った。 三人は別に用の事は話し合わなかった。それに謙作の位置が旧い主従関係を忘れずにその調子で話している二人の中へ入ると何となく変だった。S氏も石本に対すると謙作に対すると調子を変えるわけに行かず、甚く叮嚀であった。そして同じように叮嚀にしようとすると謙作は何となくぎごちなくなるので、彼はなるべく話から遠退いていた。それでも石本は、「そうすると、家はもう見つかったんだから、君は最近此方へ引越して来るね」。こんな風に時々謙作を話の中へ連れ出そうとした。その夜、S氏と別れてから、謙作は石本と円山(まるやま)の方を散歩した。「僕は明後日(あさって)用があるので、明日(あした)の夜行で帰るがね」と石本は云う。「そしてSの返事によって、一週間か十日して又来るつもりだ。それでこの事には君の直接する事は何にもないのだから、都合で何時でも帰るといいよ」。「------」。「Sに総て一任してあるが、Sは大概うまく調(ととの)うだろうと云っているが、そう決め込んで駄目だと落胆(がっかり)するからね------」。「僕も明日帰る。朝の急行で帰る」。こう急に謙作は云った。「そんなら一緒に帰ろうか」。「うん」。それに決めて二人は暫くして別れ各々自分の宿の方へ帰って行った。 |
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)