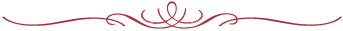
| 「西郷訓補講」 |
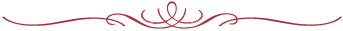
(最新見直し2008.2.9日)
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| 「南州翁遺訓41ケ条」の補講として次のような遣り取りが遺されている。これも確認しておく。「(遺訓)」を参考にする。以下、出航する。 2008.2.7日 れんだいこ拝 |
| 【遺訓1、問答(岸良真二郎の問と4問) 】 |
| (岸良真二郎の問1) |
| 一 事に臨み猶予狐疑して果断の出来ざるは、畢竟憂国の志情薄く、事の軽重時勢に暗く、且愛情に牽かさるるによるべし。真に憂国の志相貫き居り候へば、決断は依て出るものと奉(レ)存じ候。如何のものに御座候哉。
(訳)大事な場面に臨んで、ぐずぐずしたり、疑い深く決心のできないのは、つまるところ、国を憂える心が薄く、事がらの軽重や世の中の情勢について疎く、さらには人情にひかされることによると思います。本当に国を憂える真心を貫ぬいていたら、決心することは、おのずからできるものと思いますが、いかがでございましょうか。 |
|
(南洲の答)
|
|
一 猶予狐疑は第一毒病にて、害をなす事甚多し、何ぞ憂国志情の厚薄に関からんや。義を以て事を断ずれば、其の宜にかなふべし、何ぞ狐疑を容るるに暇あらんや。狐疑猶予は義心の不足より発するものなり。 (訳)ぐずぐずしたり、疑い深いというのは第一の毒で、害を及ぼすことが、きわめて多い。決して国を憂える心の厚いとか薄いとかに関係することではない。正しい道をもって物事を判断すれば、きっと筋道にかなうであろう。どうしてぐずぐずしたり疑い深い心など起こり得ようか。ぐずぐずしたり疑い深いというのは正しい心の不足から起こってくるものである。 |
| (岸良真二郎の問2) |
|
二 何事も至誠を心となし候へば、仁勇知は、其の中に可(レ)有(レ)之と奉(レ)存じ候。平日別段に可(レ)養ものに御座候哉。 (訳)何事も誠を心とすれば、仁(いつくしみ)勇(勇気)知(知恵)すなわち人としての大事な道は、その中で養われるものと存じます。かねて特別に養わねばならないものでしょうか。 |
| (南洲の答) |
|
二 至誠の域は、先づ慎独より手を下すべし。間居即慎独の場所なり。小人は此処万悪の淵籔(えんそう)なれば、放(ほう)肆(し)柔惰の念慮起さざるを慎独とは云ふなり。是善悪の分るる処なり。心を用ゆべし。古人云ふ、「主(トシ)(レ)静(ヲ)立(ツ)(二)人極(ヲ)(一)」(○宋 周藩渓の語)是其至誠の地位なり、不(レ)慎べけんや、人極を立てざるべけんや。 (訳)至誠(この上もない真心)の境地はまず独りを慎むことから手を下すべきである。することもなく、ひまでいることは、すなわち独りを慎むによい場所である。小人(人格の低いつまらない人)にとっては、こういう場所が、すべての悪いことのより集まるところであるから、わがままや、心弱く怠ける思いを起さないことが、独りを慎むということである。ここが善と悪との分かれるところであり、最も心を用いなければならない。昔の人が言っている。「静かで安らかな心で人としてこの上もない道をきわめる」と。これこそその至誠の境地である。慎まないでよかろうか。人としてこの上もない道をきわめるよう努力しないでよかろうか。 |
| (岸良真二郎の問3) |
|
三 事の勢と機会を察するには、如何着目仕可(レ)然ものに御座候哉。 (訳)事がらの勢いと、機会を知るにはどういうところに気をつけたらいいものでしょうか。 |
| (南洲の答) |
|
三 知と能とは天然固有のものなれば、「無知之知(ハ)。不(シテ)(レ)慮(ヲ)而知(リ)。無能之能(ハ)。不(シテ)(レ)学(バ)而能(クス)」(○明、王陽明の語)と、是何物ぞや、其惟(ただ)心之所為にあらずや。心明なれば、知又明なる処に発すべし。 (訳)知恵と才能はおのずから備わったものであるから「たとえ知識がないものでも深く考えることなくしてよく知り、たとえ才能のないものでも、余り学ぶことなくしてよくできる」(明の王陽明の語)とあるが、これはどういうことであろうか。すべての心のなすところではないだろうか。心さえ明らかであったら知恵もまた明らかにおこるであろう。 |
| (岸良真二郎の問4) |
|
四 思設けざる事変に臨み一点動揺せざる胆力を養ふには、如何目的相定、何より入りて可(レ)然ものに御座候哉。 (訳)思いがけない事がらに会い、少しも動揺しない胆力(きもったま)を養うには、どのような目標を定め、何から勉強していったらよいものでしょうか。 |
| (南洲の答) |
|
四 勇は必ず養う処あるものなり。孟子云はずや、浩然之気を養うと。此気養はずんばあるべからず。 (訳)勇気は必ず養わなければならない。孟子が言っているではないか。天地に満ちている何ものにも屈しない勇気を養うと。この勇気はかねて養うところがなければならない。 |
| (南洲の答) |
|
五 事の上には必ず理と勢との二つ必あるべし。歴史の上にては能見分つべけれ共、現事にかかりては、甚見分けがたし。理勢は是非離れざるものなれば、能々心を用ふべし。譬へば賊ありて討つべき罪あるは、其理なればなり。規(き)模(ぼ)術略吾胸中に定りて、是を発するとき、千仞に坐して円石を転ずるが如きは、其勢といふべし。事に関かるものは、理勢を知らずんばあるべからず、只勢のみを知りて事を為すものは必ず術に陥るべし、又理のみを以て為すものは、事にゆきあたりて迫(つま)るべし。いづれ「当(ツテ)(レ)理(ニ)而後進(ミ)。審(ニシテ)(レ)勢(ヲ)而後動(ク)」(○陳龍川、先主論の語)ものにあらずんば、理勢を知るものと云ふべからず。 (訳)物事は何であっても、必ず道理と勢いの二つがある。歴史の上ではこれをよく見分けることができるが、現在目の前の事については、なかなか見分け難い。道理と勢いとは二つとも離すことのできないものだから、よくよく心を用いるべきである。たとえば悪者があって、これを征服しなければならないというのは、そういう道理があってのことである。物の仕組みや、はかりごとが自分の心の中に定まっていて、これを発するとき、ちょうど非常に高いところにいて円い石をころがすようなのは、その勢いといってよいだろう。 |
| (南洲の答) |
|
六 事の上にて、機会といふべきもの二つあり。僥倖の機会あり。又設け起す機会あり。大丈夫僥倖を頼むべからず、大事に臨みては是非機会は引起さずばあるべからず。英雄のなしたる事を見るべし、設け起したる機会は、跡より見る時は僥倖のやうに見ゆ、気を付くべき所なり。 (訳)物事の上で、機会というべきものが二つある。まぐれあたりの機会と、こちらからしかけた機会である。真の男児たるもの、決してまぐれあたりの幸いを頼んではならない。大事に臨んでは、ぜひ機会というものを引きおこさねばならない。英雄といわれる者のなしたことをよく見るがよい。自分で引きおこした機会というものは、後(あと)から見るとまぐれあたりの幸いのようにみえる。これは気をつけねばならないことだ。 |
| (南洲の答) |
|
七 変事俄に到来し、動揺せず、従容其変に応ずるものは、事の起らざる今日に定まらずんばあるべからず。変起らば、只それに応ずるのみなり。古人曰、「大丈夫胸中灑(しゃ)々(しゃ)落(らく)落(らく)。如(ク)(二)光風霽月(ノ)(○一)任(ズ)(二)其(ノ)自然(ニ)(○一)何(ゾ)有(ラン)(二)一毫之動心(一)哉」(○明、王耐軒筆疇の語)と、是即ち標的なり。如(レ)此体のもの、何ぞ動揺すべきあらんや。 (訳)変わったできごとが急に起こった時、心を動揺させることなく、ゆったりと落ちついてそれに対応するという心構えは、まだまだ起こらないときに定まっていなければならない。もし変わったことが起こった時は、ただそれに対処するだけである。昔の人が言っている。「真の男児たるもの、心の中はいつもさっぱりして、雨上がりの風月のようにわだかまりがなく、自然に任せる。どうして、少しでも動揺するような心があろうか」。(明の王耐軒筆疇の語)というのだが、これこそ生き方の目標である。このようなあり様であったら、どうして動揺などすることがあろうか。 |
|
|
| 【遺訓2、(補遺1) 】 |
|
一 誠はふかく厚からざれば、自ら支障も出来るべし、如何ぞ慈悲を以て失を取ることあるべき、決して無き筈なり。いづれ誠の受(じゅ)用(よう)においては、見ざる所において、戒慎し、聞かざる所において恐懼する所より手を下すべし。次第に其功も積みて、至誠の地位に至るべきなり。是を名づけて君子と云ふ。是非天地を証拠にいたすべし。是を以て事物に向へば、隠すものなかるべきなり。司馬温公曰「我胸中人に向うて云はれざるものなし」と、この処に至っては、天地を証拠といたすどころにてはこれなく、即ち天地と同体たるものなり、障(しょう)礙(がい)する慈悲は姑息にあらずや。嗚呼大丈夫姑息に陥るべけんや、何ぞ分別を持たんや。事の軽重難易を能く知らば、かたおちする気づかひ更にあるべからず。 (訳)誠というものは、深く厚くなければ自然にさしさわりも出て来るであろう。どうしてあわれみをかけて失敗するというようなことがあろうか。決してないはずである。これから誠を身につけるためには、人の見ていないところで心を戒め、慎み、人の聞いていないところで恐れかしこむということから、まずはじめるべきである。そうすれば次第にその結果も表われて、至誠(この上もない真心)の境地に至ることができるであろう。このような境地に至った人を君子というのである。 |
| 【遺訓2、(補遺2) 】 |
|
二 剛胆なる処を学ばんと欲せば、先づ英雄の為す処の跡を観察し、且つ事業を翫味し、必ず身を以て其事に処し、安心の地を得べし、然らざれば、只英雄の資のみあって、為す所を知らざれば、真の英雄と云ふべからず。是故に英雄の其事に処する時、如何なる胆略かある、又我の事に処するところ、如何なる胆力あると試較し、其及ばざるもの足らざる処を研究励精すべし。思ひ設けざる事に当り、一点動揺せず、安然として其事を断ずるところにおいて、平日やしなふ処の胆力を長ずべし、常に夢(む)寐(び)の間において我胆を探討すべきなり。夢は念ひの発動する処なれば、聖人も深く心を用ふるなり。周公の徳を慕ふ一念旦暮止まず、夢に発する程に厚からんことを希ふなるべし。夢寐の中、我の胆動揺せざれば、必驚(きょう)懼(く)の夢を発すべからず。是を以て試み且つ明むべし。 (訳)肝っ玉の強くて太いことを学ぼうと思うならば、まず英雄と言われた人のなしたあとをよく調べ、その事業をよく味わって、必ず自分自身で事がらに対処し、心安らかな境地を得なければならない。そうでなく、ただ英雄の資質だけあって、何もなすところがなければ、ほんとうの英雄ということはできない。 |
| 【遺訓2、(補遺3) 】 |
|
三 若し英雄を誤らん事を懼れ、古人の語を取り是を証す。 譎詐無(ク)(レ)方。術略横出(ス)。智者之能也。去(リテ)(二)詭詐(ヲ)(一)而示(スニ)(レ)之(ヲ)以(テシ)(二)大義(テ)(○一)置(イテ)(二)術略(ヲ)(一)而臨(ムニ)(レ)之(ニ)以(二)正兵(ヲ)(○一) 此(レ)英雄之事。而智者之所(レ)不(ル)(レ)能(ハ)(レ)為(ス)矣。(○陳龍川、諸葛孔明論の話)英雄の事業如(レ)此、豈奇妙不思議のものならんや。学んで而して至らざるべけんや。 (訳)もし英雄というものを思い誤ってはと恐れて昔の人の言葉をとってこれを示された。 「相手を偽ること自由自在に、はかりごとをほしいままに出すというのは、知恵ある人のよくすることである。偽りあざむくことをしないで、相手に筋のとおった道理を示し、はかりごとをしないで、正しい兵法をもって対応するというのは、これこそ英雄のすることであって、知恵ある人のとうていできることではない。」(陳龍川の諸葛孔明論の語)と。英雄のなすことは、大体このようなもので、どうして奇妙で不思議なものであろうか。大いに学んでこの境地にぜひ達したいものである。 |
| 【遺訓3】 |
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)