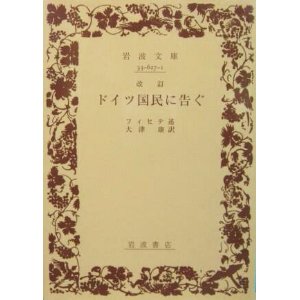http://www.asyura2.com/10/senkyo90/msg/564.html
閉塞感に包まれているこの国はいったいどこで道を誤ったのか──『国家の品格』の著者があえて提言する「自立」「誇り亡を取り戻すために、いま、日本人がなすべきこと
。一八〇七年、ナポレオン占領下のドイツで哲学者フィヒテは、「ドイツ国民に告ぐ」という講演の中で、打ちひしがれた国民に祖国再生の熱いメッセージを送った。熱き想いを共有する私は、フィヒテのひそみに倣い、その柄でもないことを顧ず以下を認(したた)めた。
日本が危危機に立たされている。何もかもがうまくいかなくなっている。経済に目を向けると、バブル崩壊後二十年近くにもなり、その間ありとあらゆる改革がなされてきたがどれもうまくいかない。グローバル化に沿った構造改革も社会を荒廃させただけで、デフレ不況は一向になおらない。財政赤字は世界一となり、なお増え続けている。一人当りGDPもどんどん低下するばかりだ。失業率は増え続け、自殺者数はここ十二年間毎年三万人以上を記録し、世界トップクラスの自殺大国となっている。政治時日を向ければ相変らずの「政治とカネ」ばかりである。自国の防衛さえ自らしようとせず、アメリカへの屈従と引換えに防衛を請う有様である。とても独立国とは言い難いから、中国の首脳にいみじくも「アメリカの妾国」と呼ばれてしまう。そう呼ばれてもさほど恥ずかしいとも思わない。米国債を買わされ続け、すでに世界一、二を争う残高となりながら、売ることさえままならない。なぜかこれについては政府もマスコミも触れようともしない。「年次改革要望書」などという内政干渉に近い要求まで拒めなくなる。郵貯簡保の三百四十兆円をアメリカへ差し出すために行なわれた郵政民営化、世界で最も安定していた日本の雇用を壊した労働者派遣法改正、WHOに世界一と認められていた医療システムを崩壊させた医療改革、外資の日本企業買収を容易にするための三角合併解禁など、みな「年次改革要望書」で要求されたものだった。
誰もがモラルを失いつつある国
よい政治家が必要となるが、選挙の半年前までは国政など考えたこともないような素人が登場し、質は低下するばかりである。政治家の大半は相も変らぬ世襲議員、トップに目を付けられた素人、そしてスポーツやテレビなどで顔の売れた人ということになる。これまでの政党に飽足らない議員がどんな新党を結成してみても、今後どんな政界再編があろうと、質の劣化した政治家連の区分けが変わるだけのことであり、質の向上にはつながらない。濁った水はどう分けても濁ったままである。深刻な少子化が進みつつある。若者が二十代で結婚したがらない。やっと結婚しても産みたがらない。晩婚となれば産んでもせいぜい一人か二人ということになる。ここ五年間の出生率は一・三四程度で、人口維持に必要なのは二・〇八だからある時から相当急激な減少が始まることになる。深刻なのはモラルの低下である。政治家や官僚のモラル不足だけではない。子殺し親殺し、それに「誰でもよかったが殺したかった」という無差別殺人など、かつてありえなかった犯罪が頻(しき)りに報道されるようになった。世界で図抜けていた治安のよさも、かろうじてトップレベルという所まで落ちてきた。子供達のモラルも一斉に崩れ、単級崩壊は日本中の小中学校で広く見られるようになりた。除湿ないじめによる子供の自殺が普通のこととなった。数世紀にわたって恐らく世界一だった子供達の学力は、十年ほど前に首位を滑り落ち、その後も落ち続けている。ケータイ病におかされた子供達は今や、世界でもっとも勉強しない予供達とさえ言われる。身近な幸せに安住し、ケータイやインターネットに興じている。視線が内向き下向きになっている。それに学校にはモンスターペアレンツ、病院にはモンスターぺイシャンツと、不満が少しでもあれば大げさに騒ぎ立て訴訟にまで持ちこむ人々が多くなった。人権をはじめとしてやたらと権利を振りかざす人間が多くなった。
この国の当面するあらゆる困難は互いに関連し、絡み合った糸玉のようになっていて誰もほぐせないでいる。部分的にほぐしたように見えても大ていは‥時的なものに止まり全体の絡みには何の影響も及ぼさない。我が国の直面する危機症状は、足が痛い手が痛い頭が痛いという局所的なものではなく全身症状である。すなわち体質の劣化によるものなのである。漂流し沈下しつつある日本はどうなるのか。日本人は今、深淵に沈み行くことを運命と諦めるか、どうにかせねばと思いながら確たる展望もないままただ徒(いたず)らに焦りもがくばかりである。古くより偉大なる文学芸術を生み、明治以降に偉大なる経済発展をなしとげ、五大列強の一つともなった優秀で覇気に富んだ日本民族は一体どうなったのだろうか。祖国再生の濱はどこにあるのだろうか。
一般に多くの困難を解決しようとする場合、一つ一つ着実に解決しようとするのは、誰でもまず考えることであるが、大ていの場合、労力がかかるばかりで成功しない。多くの困難が噴出しているというのは、それら全てを貫く何か一つの原理が時代や状況にそぐわなくなっているという ことを意味する。従ってこの原理を変えることで諸国難を一気に解決する、というのが最も効果的なばかりか容易でもあるのだ。それでは我が国は戦後、どのような原理で動いて来たのであろうか。それを考えるには日本人とはどういう民族であったかという所から始めなければならない。
独立文明を築いた日本
ハーバード大学の国際政治学者サミュエル・ハンチントン教授は、その一九九〇年代のベストセラー『文明の衝突』の中で世界の文明を七つに分けた。中華文明、ヒンドゥー文明、イスラム文明、日本文明、東方正教会文明(ロシアなど)、西欧文明、ラテンアメリカ文明である。この中で日本文明以外はすべて、多くの国にまたがるものだ。いかなる分野でも、学者が何かを分類しようとする時、なるべく簡明なものにしようとする。複雑な区分けはもはや分類と呼べないからだ?
当然、日本という小国だけに存在する日本文明を、中華文明に組み入れようとする。ところが世界の文明を分類しようとする現代のどの学者も、日本文明を独立したものと見なすのである。一万年も前の縄文時代からあった土着の文明に、西暦二世紀頃から中華文明が混じり、十六世紀末からは西欧文明の影響を受けたものの、主に日本という孤島で独自の発達をとげた文明と見なさざるを得ないからである。明瞭に中華文明に含まれる朝鮮半島などと異なり、日本文明と中華文明は何から何まで余りにも隔っているからである。日本人は古来、新しい進んだ文明に触れると、繊細な民族性だけにすぐに劣等感を持ち、それを見習い取り入れてきた。漢字も仏教も西欧の技術もそうだった。ところが不思議なことに、その劣等感をバネに、それら新文明に必らず独創を加え、自分達独自のものに変えて行くのである。漢字が来れば間もなく万葉仮名、片仮名、平仮名を発明し、漢文の訓読を始める。仏教の方も伝米して間もない奈良時代には神仏習合という離れ技をなしとげ、遣唐使の終了した平安未期の頃から日本独自の仏教を創始した。禅や儒教は中国では庶民にまで広がらなかったが、日本では武士道にとり入れたのを皮切りについには国民精神にまで広めてしまう。鉄砲が種子島に伝えられれば、その三十年後には工夫に工夫を加え、て織田信長が世界最優秀の鉄砲を三千丁も量産していた。先進中国のものであっても君主専制や科挙や官官は取り入れないなど、国柄との適合を念頭に、取捨選択と換骨奪胎(かんこつだったい)を繰り返しながら自らのものとしていたのである。
それでは日本文明とは一体どんな文明なのだろうか。これは難しい問題である。とりわけその中で暮らしている日本人には見えにくい。空気の中で暮らしている人間が空気の存在に気付いたのは、十七世紀になってトリチェリが真空の存在を発見したからであった。人類誕生から数百万年もかかっている。自らの文明は自らは認識しにくく、異質の文明との比較によってようやく見えるものと言ってよい。幸いにして、幕末から明治にかけて来日した欧米人を中心とする多くの論者が様々な考察をしてくれた。
彼等は、長い航海の後、アジアの各地に寄りながら日本までやって来て、「日本人はなぜこうも他のアジア人と追うのか」ということに驚愕しつつ、日本とは何かについて自問自答を繰り返したのである。多くの欧米人が日本を訪れ、新鮮な日で日本を見つめ、断片的であろうと、個人的印象に過ぎないものであろうと、多くの書物に残してくれたことは実に幸運であった。日本文明が成熟を見た江戸時代の直後だった、ということはなおさら幸運であった。
彼等の言葉をいくつか、『逝きし世の面影』(渡辺京二著、平凡社ライブラリー)を引用し参考にしつつ考えてみよう。日米修好通商条約締結のために訪れたタウンゼント・ハりスは、日本上陸のたった二週間後の日記にこう記している。「厳粛な反省──「変化の前兆──「疑いもなく新しい時代が始まる。あえて問う。日本の真の幸福となるだろうか」。彼は「衣食住に関するかぎり完璧にみえるひとつの生存システムを、ヨーロッパ文明とその異質な信条が破壊」することを懸念したのである。ハリスの通訳として活躍したヒュースケンはこう記す。「この国の人々の質撲な習俗とともに、その飾りけのなきを私は賛美する。この国土のゆたかさを見、いたるところに満ちている子供たちの愉しい笑声を聞き、そしてどこにも悲惨なものを見いだすことができなかった私は、おお、神よ、この幸福な情景がいまや終わりを迎えようとしており、西洋の人々が彼らの重大な悪徳をもちこもうとしているように思われてならないし。また日英修好通商条約を締結するため来日したエルギン卿の秘書オリファントはこう記す。「個人が共同体のために犠牲になる日本で、各人がまったく幸福で満足しているように見えることは、驚くべき事実である」。
多くの欧米人がいろいろの観察をしているが、ほぼすべてに共通しているのは、「人々は貧しい。しかし幸せそうだ」である。だからこそアメリカ人のモースは「貧乏人は存在するが、貧困なるものは存在しない」と言ったのだ。
欧米では、裕福とは幸福を意味し、貧しいということは惨めな生活と道徳的堕落など絶望的な境遇を意味するのだが、この国ではまったくそうでないことに驚いたのである。明治六年に来日し、日本に長く生活したイギリス人バジル・チェンバレンはこう記す。「この国のあらゆる社会階級は社会的には比較的平等である。金持は高ぶらず、貧乏人は卑下しない。……ほんものの平等精神、われわれはみな同じ人間だと心底から健じる心が、社食の隅々まで浸透しているのである」。
イギリスの詩人エドウィン・アーノルドなどは、明治二十二年に東京で開かれたある講演で日本についてこうまで言っている。「地上で天国あるいは極楽にもっとも近づいている国だ。……その景色は妖精のように優美で、その美術は絶妙であり、その神のようにやさしい性質はさらに美しく、その魅力的な態度、その礼儀正しさは、謙譲ではあるが卑屈に堕することなく、精巧であるが飾ることもない。これこそ日本を、人生を生甲斐あらしめるほとんどすベてのことにおいて、あらゆる他国より一段と高い地位に置くものである」。
無論ここには詩人らしい誇張も含まれているだろう。しかし実に多くの人々が表現や程度こそ異なれ類似の観察をしているのである。
現代知識人の本能的自己防衛
現代知識人の多くはこのような観察を重要なものと思わない。軽視する。江戸時代とは「士農工商という厳しい身分制度に基づいた封建制度の下や庶民は苦しい生活を余儀なくされていた」、明治とは「猛烈な富国強兵策と不平等条約の戦と庶民は困窮していたLという考えに縛られているからである。彼等は「封建制度は悪」という明治以来の日本を支配した欧米歴史学、あるいは「富国強兵は侵略戦争につながった諸悪の根源」という東京裁判史観に縛られているからである。確かにヨーロッパをはじめ世界の封建制度とは、おしなべて専制君主が人民を圧制下におき農民を農奴のごとくこき使い、搾り取れるだけ搾り取るというものであった。国民のほとんどを占める農民はいかなる希望も持てず、どん底の闇を這いずり回るような生活をしていた。欧米流の歴史学を学んだ現代知識人にと?て、幕末から明治初期にかけて来日した外国人の観察は矛盾に満ちたものに映るのである。日本の封建制度が他国の封建制度とは似ても似つかないものであったとは考えずに、単なるオリエント趣味の発露に過ぎず珍らしい骨董品をほめる程度の他愛ないものと思うのだ。あるいは、当時の西欧で流行していたジャポニズム、という眼鏡を通して形成された美しき幻影にすぎず、日本や日本人の実像を示すものではないと考える。人によっては、そういった観察の底には、抜き差しがたい欧米優位思想があり、日本を称えるのは愛玩動物を愛撫ずるようなもので日本蔑視の一形態に過ぎない、とまで考えるのである。
実は江戸末期に来日した欧米人も同じく、日本の封建制度を見て衝撃を受け、歴史学の常識との矛盾を感じ悩んだのだ。しかし彼らには目の前の現実という「動かね証拠」があったから、日本の封建制度の異質を信じざるを得なかった。現代知識人には「動かぬ証拠」がないからいつまでも疑惑の日を向けるのである。それに、知識人にとって、自己肯定は無知をさらすことであり、自己懐疑こそが知的態度なのだ。と同時に物事を「白」と断ずるのは危険、「灰色」と言うのは安全、ということを知る知識人の本能的自己防衛でもあるのだ。
実はこのような態度は現代知識人に固有のものでもない。英詩人エドウィン・アーノルドが先述の、いささか褒めすぎとも思える絶賛を述べた翌朝の日本の各紙における論説は、アーノルドが日本のやりとげた政治、経済、軍備の躍進に触れず、芸術、自然、人々のやさしさや礼節といったものばかりを賞讃したのは、日本に対する一種の蔑視ではないかと憤ったのである。
また、明治に長年にわたり日本に暮らしたジャパノロジストのチェンバレンはこう書いている。「新しい教育を受けた日本人のいるところで、諸君に心から感嘆の念を起きせるような、古い奇妙な、美しい日本の事物について、詳しく説いてはいけない。……一般的に言って、教育ある日本人は彼らの過去を捨ててしまっている。彼らは過去の日本人とは別の人間、別のものになろうとしている」。
同様のことは明治九年は東大医学部創設期のお雇い教師として来日し日本人と結婚、三十年近くにわたり日本に滞在したドイツ人医師ベルツもこう書いている。「現代の日本人は自分自身の過去については、もう何も知りたくはないのです。それどころか、教養ある人たちはそれを恥じてさえいます」。彼が教養ある紳士達に日本の歴史について尋ねると、ある人は「いや、何もかもすっかり野蛮なものでした」と答え、ある人は「われわれには歴史はありません。われわれの歴史は今からやっと始まるのです」と断言したのである。
明治の頃にせよ終戦後にせよ、何か新らしい価値観に立って進もうとする時、日本人は過去を完全に捨て去り猛進しようとする性向があるようである。終戦後の大ヒット「青い山脈」に「古い上着よさようなら、さもしい夢よさようなら」とあるようにだ。無論それはある意味で仕方ないことだ。その時代の潮流にのり国民一丸となって突き進むことも時には大切だからだ。しかしかつては、そのようなバランスを欠きがちな国民性に歯止めをかける精神、古くは「和魂漢才」、明治には「和魂洋才」などがあった。
ところが戦後のアメリカ化の過程ではついぞ「和魂米才」は耳に入らなかった。あたかも米魂米才を理想として目指しているかの観があった。
外国人を魅了した日本文化の美徳とは何か
それはともかく、幕末から明治にかけて来日した外国人の言葉によると、日本は江戸時代に、今日に至るまで白本以外の世界のどこにも存在しなかった、貧しいながち平等で幸せで美しい国を建設していたのである。こういった見聞録に対する現代知識人の冷笑主義に私は与(くみ)しないが、百歩譲ってその言い分を認め、そのような印象が単なる幻影だったとしても、少くとも当時来日したほとんどの外国人に、そのような幻影を抱かせるような現実が、当時の日本にあったことは間違いはない。
その現実とは何か。明治四年に来日したオーストリアの長老外交官ヒューブナーはこう断言する。「封建制度一般、つまり日本を現在まで支配してきた機構について何といわれ何と考えられようが、ともかく衆目の一致する点が一つある。すなわち、ヨーロッパ人が到来した時からごく最近に至るまで、人々は幸せで満足していたのである」。
貪しいながら人々の顔に表れた幸せと滞足感が余りにも著しかったから、すべての来日外国人がこの想像しにくい状況に瞠目し書き記したのである。
無論、幸せとか満足感に基準はない。当時の欧米は産業革命の真只中でありその歪みも出始めていたが、その頃の自国の人々の表情と比べての印象であることは否めない。
それにしても、表情に表われた幸せや満足感をすべての人々が見聞違うなどということがあり得ようか。人々が健康そうで礼儀正しく正直だったこと、鍵のない部屋や机から何も盗まれなかったこと、街頭や農村で見た人々が子供から人足、車夫に至るまでみな、冗談を言い合っては笑いころげていたこと、これらは現実ではないのか。苛斂誅求(かれんちゅうきゅう)にあえいでいたはずの当時の農村で、人々が貧しいながら皆幸せそうにしていたいと多くの外国人が言う時、「苛斂誅求にあえいでいた」の真偽を疑うことが先決ではないのか。日本をよく見て歩き将軍家定に謁見までしたハリスが、「将軍の服装は質素で、殿中のどこにも金メッキの装飾はなく、柱は白木のままで、火鉢と私のために用意された椅子とテープルの他には、どの部屋にも調度の類が見当たらなかった」と書いたのはハリスの幻だったのか。彼が「日本には富者も貧者もいない。正直と質素の黄金時代を他のどの国よりも多くここに見出す」と書いたのは錯覚だったのか。
世界のどこの地域でもなしとけられなかった、かくも素晴らしい社会を作りた日本人の、卓越した特性をなぜ日本人は誇りに思わないのだろうか。日本以外の国であったら、世界が目をみはった日本文明に関し、歴史教科書で誇り高く詳述するであろう。世界の中で品格をもって生きて行くためにどの国民にとっても必要な、「祖国への誇り」を育くむために活用するだろう。
現代日本の教科書では無論ほとんど一切触れられていない。前述のように歴史家がそれを嫌い、知識人がそれを忌むからである。自らを自慢することはしたくない、という日本人の謙遜もそこには働いている。祖国への誇りを子供に育くむのは軍国主義につながりかねない、愛国教育ではないのか。などと本気で心配したり、近隣諸国条項を考慮したりする。近隣諸国条項とは一九八二年に教科書検定基準として定められたもので、平らたく言うと、「中国、韓国、北朝鮮を刺赦しかねない叙述はいけない」という政治的なものである。歴史的あるいは国際的な客観性より外交を優先するという代物だ。無論、これら三国にそのような滑稽な規定はない。
昨春、私はお茶の水女子大学を定年退官したが、定年前の十数年聞、専門の教学以外に、一年生対象の読者ゼミを年に一コマか二コマ担当していた。よく新入生にこう尋ねてみた。「日本はどういう国と思いますか」。彼女達の答えには、表現の差こそあれ、「恥ずかしい国」「胸を張って語れない歴史をもつ国」などと否定的なものが多かった。理由はほぼこういうものだった。「明治、大正、昭和戦前は、帝国主義、軍国主義や植民地主義をひた走り、アジア各国を侵略した恥ずべき国。江戸時代は士農工商の身分制度、男尊女卑、自由も平等も民重義もなく庶民が虐げられていた恥ずかしい国。その前はもっと恥ずかしい国、その前はもっともっと」。そう習ってきたのである。そう理解することでやっと大学合格にまで漕ぎつけたのである。
私は彼女達がかくもひどい国に生まれた不幸に同情した後、必ず聞くことにした。「それでは尋ねますが、西暦五〇〇年から西暦一五〇〇年までの十世紀間に、日本一国で生まれた文学作品がその間に全ヨーロッパで生まれた文学作品を、質および量で圧倒しているように私には思えますがいかがですか」。これで学生達は沈黙する。私はたたみかける。「それでは、その十世紀間に生まれた英文学、フランス文学、ロシア文学、をひっくるめて二つでいいから拳げて下さい」。学生は沈黙したままだ。私自身、『カン夕べリ寸物語』くらいしか思い浮かばない。
私は学生にさらに問う。「この間に日本は、万葉集、古今和歌集、新古今和歌集、源氏物語、平家物語、方丈記、徒然草、太平記……と際限なく文学を生み続けましたね。
それほど恥ずかしい国の恥ずかしい国民が、よくぞ、それほど香り高い文学作品を大量に生んだものですね」。理系の学生がいればさらにたたみかける。「世界中の理系の大学一年生が習う行列式は、ドイツの大天才ライプニッツの発見ということになっていますが、実はその十年前、元禄年間に関孝和が鎖国の中で発見し、ジャンジャン使っていたものですよ」。学生は完全に沈黙する。毎春の授業風景であった。
これは私の学生のみに見られる傾向ではない。世界数十カ国の大学や研究機関が参加する「世界価値観調査」によると、十八歳以上の男女をサンプルとした二〇〇〇年のデータだが、日本人が「自国を誇りに思う」の項で世界最低に近い。「もし戦争が起こったら国のために戦うか」は一五%と図抜けて世界最低、ちなみに韓国は七四%、中国は九〇%である。恥ずかしい国を救うために生命を投げ出すことなどありえないのである。
アメリカによる巧妙な属国他戦略
いかにして日本人は祖国への誇りをかくも失ったのだろうか。もちろん戦後のことである。
終戦と同時に日本を占領したアメリカの唯一無二の目標は、「日本が二度と立上ってアメリカに歯向かうことのないようにする」であった。それは国務省、陸軍省、海軍省合同で作成した「日本降伏後における米国の初期の対日方針」に明らかである。そのために日本の非武装化、民主化などを行なったが、それに止まらなかった。第一次大戦後、二度と立上がれないほどドイツを非武装化弱体化したが、たった二十年でヨーロッパ最強の陸軍を作ってしまったのをよく知っていたからである。日本人の「原理」を壊さない限り、いつかこの民族が強力な敵国として復活することを知っていたからである。とくに昭和十九年秋に始まった神風特攻隊かも硫黄島、沖縄と続く理性を超越した鬼気迫る抵抗に震撼した直後だけに、なおさらだった。
まず新憲法を作り上げ、前文に「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」と書いた。日本国の生存は他国に委ねられたのである。第九条の「陸海空軍その他の戦カは、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」は、前文の具体的内容である。自分が守らない場合、どこかの国に安全保障を依頼する以外に国家が生き延びる術はない。アメリカ以外にないことは自明であった。すなわち日本はこの時、アメリカの属国となることが決定されたのである。戦争に倦む日本人に対し平和を高らかに謳い上げ、アメリカが平和愛好国であることを印象づけた上で属国化する、という実に巧妙なやり口であった。
さらには念のため、第一条で国民の心の拠り所であった天皇を、元首からただの象徴にした。さらには皇室典範を新たに定め、十一宮家を皇籍離脱させ、万世一系を保つのがいつか極めて困難になるように仕掛けた。国民の求心力の解体を目論んだのである。それくらいで満足するようなアングロサクソンではない。漢字全廃への第一段階として当用漢字を導入したのは、日本の文化を潰し、愚民化するためであった。世界から絶讃されていた教育勅語を廃止した上で作った教育基本法とは、公への奉仕や献身を大事にするという日本人の特性、すなわち底力を壊し、個人主義を導入するためのものであった。これでもまだ足りなかった。
魂を空洞化した言論統制
実はアメリカが日本に与えた致命傷は、新憲法でも皇室典範でも教育基本法でもなかった。占領後間もなく実施した、新聞雑誌放送映画などに対する厳しい言論統制であった。終戦の何年も前から練りに練っていたウォー・ギルト・インフォーメーション・プログラム(WGIP=戦争についての罪の意識を日本人に植えつける宣伝計画)に基づいたものである。自由の旗手を自認するアメリカが、日本人の言論の自由を封殺するという、悪逆無道を働いたのであった。これについては江藤淳氏の名著『閉された言語空間』(文春文庫)に余す所なく記されている。
この根本的狙いは、日本の歴史を否定することで日本人の魂の空洞化を企図したものであった。そのためにまず、日本対アメリカの総力戦であった戦争を、邪悪な軍国主義者と罪のない国民との対立にすり変えようとした。四百万近い国民が米軍により殺致され、日本中の都市を廃墟とされ、現在の窮乏生活がもたらされたのは、軍人や軍国主義者が悪かったのであり米軍の責任ではない。なかんずく、世界史に永遠に残る戦争犯罪、すなわち二発の原爆投下による三十万市民の無差別大量虐殺を、日本の軍国主義者の責任に転嫁し、自らは免罪符を得ようとしたのである。アングロサクソンが日本の立場にあったなら必らず復讐を誓うから、日本の復讐を恐れ軍部のせいにしたという側面もある。
この作為的転嫁すなわち歴史歪曲を実行するため、早くも昭和二十年十二月には学校における歴史地理修身の授業を中止し、「太平洋戦争史」なる宣伝文書を製作し各日刊紙に連載した。「太平洋戦争史」は各学校で教科書としても使われ、NHKラジオでも「真相はかうだ」として十週間にわたり放送された。アメリカによる洗脳が始まったのである。これがうまく行けば、日本人の間に当然ながら渦巻いていた対米憎悪のエネルギーが、アメリカではなく、自分達国民を歎してきたということで徐々に軍部や軍国主義者に向かい、そしていつかは日本の残虐性と好戦性の源ということで伝統的秩序の破壊に向かうだろうとの深い読みであった。マインドコントロールであった。「太平洋戦争史」で教育された人々がこのパラダイムを次の世代に伝えたから、未だに歴史教科書に色濃く残っているのである。GHQは同時に「神道指令」を発令し、神道を弾圧することで皇室の伝統、すなわち日本人の心の拠り所を傷つけようとした。
これらを着実に実行するため、私信までを開封した。私自身、セロテープで閉じられた父あての封筒を幾度となく見ている。さらには雑誌新聞などの事前検閲であった。占領軍や合衆国に対する批判、極東国際軍事裁判(東京裁判)に対する批判、アメリカが新憲法を起草したことへの言及、検閲制度への言及、天皇の神格性や愛国心の擁護、戦争における日本の立場や大東亜共栄圏や戦犯の擁護、原爆の残虐性についての言及、などが厳しく取締られ封印された。細かくは、米兵と日本人女性との交際への言及なども対象となった。日本人数千人の協力の下で、この極秘裏の検閲は数年間にわたりなされたのである。識字率が異常に高く、またお人好しの日本人には有効だった。歴史を否定し愛国心を否定するものであった。WGIPに協力的でない日本人は公職追放されたり圧力を加えられた。余りにも一方的な嘘の不当な押しつけに抵抗する人は多くいたが、そういった人々を含め二十万人もが公職追放されたのであった。
WGIPに協力することは就職口を得ることであり、生き延びることであり、出世につながることとなった。このWGIPは七年近い占領のすんだ後でも日本人に定着したままとなった。ソ連のコミンテルン(ソ連共産党配下の国際組織)の影響下にあった日教組がGHQの方針をそのまま継承し教育の場で実行したからである。
GHQが種をまき、日教組が大きく育てた「国家自己崩壊システム」は、今もなお機能している。特に教育界、歴史学界、マスコミにおいてである。WGIPの禁止条項はなんとアメリカが引揚げて六十年近くたった今も生きているのである。東京裁判への批判、新憲法や教育基本法を押しつけ、検閲により言論の自由を奪い洗脳を進めたアメリカへの批判、愛国心の擁護、原爆や無差別爆撃による市民大量虐殺への批判、などは、すべて正当でありながら、公に語られることは稀である。無論、教科書に載ることはない。ある歴史学者は、「このようなことを口にする者が歴史学科で就職を得ることは今でも難しい」と語っている。
テレビで語られることもほとんどない。かくして日本人は魂を失い誇りを失って行ったのである。
「文藝春秋」六月号の梯久美子氏の記事によると、八十六歳になる建築家の池田武邦氏は、海軍兵学校を出て海軍士官となってからずっと軽巡洋艦「矢矧(やはぎ)」に乗っていたが、昭和二十年四月の沖縄戦で戦艦「大和」とともに海上特攻に出撃し撃沈され九死に一生を得た。彼は昭和三十年代に小学生の息子さんに「お父さんはなんで戦争になんか行ったの」と詰問され、それ以降、戦争のことを一切話さなくなったそうだ。「どんな思いで戦ったのか。戦友はどんなふうに死んでいったのか。艦全体が家族のようだった矢矧のこと。言ってもわかってもらえるはずがないと心を閉ざしてしまった。戦争の話をするようになったのは八十歳を過ぎてからです」と今語る。
四年ほど前に見たあるテレビ番組は、五十歳前後の俳優が八十九歳の父親とベトナム沖の島を訪れるものであった。陸軍大尉だったこの父親がB級戦犯として五年間収監されていた島である。ここで俳優が老いた父親を高圧的に非難するのだった。[戦争は人殺しだよね。悪いことだよね」と、父親の反論に耳を貸さず幼稚な言い分をがなり立てる様にいささか驚いた。軍人だった父親のいる多くの家庭で見られた風景に違いない。「日本がすべて悪かった。日本軍人は国民を欺いて戦争に導いた極悪人だ。自衛戦争も含めすべての戦争は悪だ」という洗脳教育から大多数の国民がまだ解き放たれていないのだ。だからこそ、戦場で涙ながらに老いた父母を思い、新妻や遺される赤子の幸せを祈り、日本に平和の訪れることを願いつつ、祖国防衛のため雄々しく戦った人々は、散華(さんげ)した者は犬死にと嘲られ、かろうじて生き残った者は難詰され罵倒されるという、理解を絶する国となってしまったのである。だからこそこの国から誇りが消えたのである。
法的な根拠を欠くアメリカの言い分
WGIPの作ったマスコミ向け禁止条項を批判することはすべて正当、と書いたがなぜだろうか。まず事前検閲は、ポツダム覚書第七項や合衆国憲法修正第一条に違反し、アメリカ自らのでっち上げた日本国憲法にも違反するものであり、自由の中でもとびぬけて大切な言論の自由を奪うものだから当然許されざるものである。広島と長崎への原爆や日本中の都市に対する無差別爆撃が、人道上の罪であることは言を俟たないが、一九〇七年に結ばれたハーグ条約の第二十二条(無差別の害敵手段を使用してはならない)や第二十五条(防守されていない都市、集落、住宅、建物はいかな手段をもってしても、これを攻撃、砲撃することを禁ず)にも違反している。不法行為である。
新憲法や教育基本法を押しつけ、日本のエリートを壊滅させるべく旧制中学、旧制高校を廃止したのも、「占領者は現地の制度や法令を変えてはならない」という趣旨のハーグ条約四十三条に反している。ハーグ条約に関して付け加えると、アメリカが真珠湾奇襲を「恥ずべき行為」と今だに口汚く糾弾する唯一の根拠は、開戦前の宣戦布告を義務づけたハーグ条約なのである。ハーグ条約以前は、当のアメリカを含めどの国も、戦争を奇襲から始めていた。ハーグ条約以降でさえ、アメリカは一九二ハ年の対ドミニカ戦争で、宣戦布告なしに奇襲占領している。第二次大戦でドイツがポーランドやソ連に侵攻した時も奇襲だった。ハーグ条約における宣戦布告条項は、単に開戦儀礼について言っているもので、誰も重要と思っていなかったのである。現に真珠湾攻撃より先に、日本軍はイギリス領マレー半島への上陸作戦を敢行したが、イギリスは宣戦布告のあるなしなど問題にもしなかった。ルーズベルト大統領だけが「恥辱」とか「破廉恥」などと激昂して見せたのは、モンロー主義による厭戦気分に浸るアメリカ国民を煽動し、ヨーロッパ戦線への参戦を決意させるためだった。
国を愛する心の擁護と育成は世界中どこでも行っていることである。しなければいけないことでもある。家族愛、郷土愛、祖国愛、この三つの愛が健全に育ってはじめて最も崇高な人類愛を持つことができるからである。三つの愛なしの人類愛は砂上の楼閣にすぎない。
WGIPの定めた禁止条項のうち、一つを除いてどれも不当であることを示した。残るのは、東京裁判への批判が不当であるかという問題だ。第二次大戦におけるドイツの戦争犯罪を裁くニュールンベルグ裁判では、ドイツの法曹関係者も裁く側に参加していたが、この東京裁判では日本側は参加を許されなかった。「勝者の裁き」と言われる所以である。また、原爆をはじめとする連合国側の戦争犯罪を不問にしたり、「平和に対する罪」という終戦後に考え出された罪を遡って適用した。証人に偽証罪を問わなかったから、南京での二十万人虐殺などという主張が確たる証拠なしにとび出した。事件の一カ月後の国際連盟で、中国代表の顧維鈞(こいきん)が日本非難のため、日本軍による二万人の虐殺を主張して連盟から否定されたものが、八年余りを経て犠牲者が十倍となって再登場したのである。今ではさらに増え、三十万人以上と当時の南京の人口を超えてしまっている。確たる証拠は今もない。
「日本は挑発挑戦され自衛のために起った」というローガン弁護人のものをはじめ、弁護側の弁明の大部分が却下されたことも法の下の平等を欠く。この辺りは小堀桂一郎編『東京裁判 日本の弁明』(講談社学術文庫)に群しい。まったく一方的で裁判とはとても呼べないものである。当時から現代に至るまで、ほとんどの国際法専門家がこの裁判を否定的に見ているのは当然である。即ち、この裁判はまったく不当なもので単なる復習劇と言って過言でない。
裁判自体が噴飯物というのは明らかだが、それを証明しただけで物事が終るわけではない。罪状が、日本指導者二十八名について、文明の名によって世界征服の責任を裁く、というものだったからである。二十八名は、通常の戦争犯罪に加え、平和に対する罪で起訴された。すなわち日本が侵略戦争を起こしたという非難だったからだ。
日本の犯した一方的侵略戦争、というのがもし真実であったら、東京裁判にとどまらず、終戦後のアメリカによるWGIPをはじめとするありとあらゆる傍若無人な振舞い、度重なるハーグ条約違反は、極悪国家日本を懲らしめその存在を全否定するという、正当な行為における勇み足ほどのものになってしまう。日本が戦争青任のすべてを背負うほどの非人道的行為に走ったのかどうかは避けて通れない大問題である。ここをきちんと抑えなければならない。