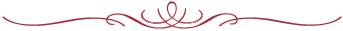
| �������Y�}�l���̂P |
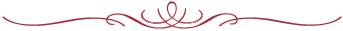
�@�i�ŐV�������Q�O�O�T�D�P�Q�D�R���j
| �@�����Œ������Y�}�l���ׂ��̂́A�������Y�}���g��������悤�Ƃ����̂ł͂Ȃ��B�قړ������ɑn�����ꂽ���{���Y�}�Ƃ̕��݂̈Ⴂ����͂��A�����v���ɐ��������������Y�}�Ƃ��b�ɂ��Ȃ�Ȃ��������{���Y�}�Ƃ̍�����ۗ����������ׂł���B�������̌�̒������Y�}�̕��݂̃W�O�U�O�Ԃ肩��̑�Ȓ��������v���j�̈Ӌ`���ڂ݂��t�ɉߏ��]������X���ɂ��邪�A���h�I�ϓ_����̓i���Z���X�ł��낤�B �@���������v���́A���V�A�P�O���v���ɑ������E�j�I�����j�ł���A���̉��l�����Ȃ��邱�Ƃ������Ă͂Ȃ�Ȃ��B���̌�̕��݂̎��s�͂���͂���ł���A���������Ă͂Ȃ�܂��B�Ƃ����悤�Ȋϓ_����A�ȉ��l�@�ɓ���B �@�Q�O�O�R�D�S�D�Q�R���@������q |
�@�P�X�P�X�D�T���A�T�D�S�^���u���B�������Y�}�̑n���ҁE�ƏG���w�������B��i�K�v���_�Ɋ�Â��u���W�����v���Ƃ��Ĉʒu�Â��Ă����B
�@�P�X�Q�P�N�A������Ŋ��ꂽ�u���Y�}�錾�v���o�ł��ꂽ�B
�@�Q�O�O�Q�D�V�D�P�P���t�������V���������w�����Ői�ޒƏG�����@�����`�̉i�v�v���ҁx�i���X�ؗ́j���
�@�l�V�����^���̢���i�ߣ�A�������Y�}�̑n���ҁA�����g���c�L�Y���^���̎w���ҁ��ƏG�i�P�W�V�X�\�P�X�S�Q�j�B�ߑ㖯���`�̏����ҁB�k����w���Ȋw���i�����̕��w���ɑ�������s���E�j�̐E�ɂ���A�P�X�P�W�N�̌l�V�����^���̗̑��Ƃ��Ċ���B�P�X�Q�O�N�t�}���N�X��`����e�B���N�P�P���������Y�}�n���ɎQ���B��ɂ��̑����L�ƂȂ����B�Q�V�D�S���̏�C�ł̏Ӊ�N�[�f�^�[�ɂ�荑������H���̌���F�����A�����L�����C�B�b�����āA���Y�}�̍����}�ւ̏]�����X�^�[������̖��߂ł��������Ƃ����A�Q�X�N�ɍ��ۍ������Δh��g�D���Ă����g���c�L�[�ɍ����B�R�P�N�Ƀg���c�L�[�h�̒������Y��`�����̑����L�ɏA�C�B�R�Q�N�Ӊ�ɂ��ߕ߂���A�����푈���u������R�V�N�܂œ싞�̍����ɂ������B�č����ߕ�����Ă���́A�g���c�L�[�ƘA�����Ƃ�A���Y�}�A�����}�Ƃ̈�v�R���ׂ̈ɕ������邩�����A�X�^�[�����̑�e��������A��v�����^���A�����`�i���Y�K������j��̎���i���Ȃ���A�S�Q�N�ɕa�v�����B������̃g���c�L�[��ƌĂ��B��̑S���U������Â���A�w�����I�����`�̉i�v�v���ҁx���ł��I�m�ł��낤��i���X�ؗ́E�����w�@�����E�Ȋw�j�E���{�ƏG�������j
�@�P�X�T�Q�N��A�ё̐����x�@�ɂ���ăg���c�L�[�h����đߕ߂��ꂽ�B
|
�g���c�L�[�^��@�������E�����h �y����z�{�e�́A�P�X�R�V�N�V����ḍa�����������������ɖu�������S�ʓI�ȓ����푈���߂����āA�}���N�X��`�҂̂Ƃ�ׂ���{�I�ȑԓx�ɂ��Ė��炩�ɂ������̂ł���B���{�鍑��`�ƒ����Ƃ̐푈�ɂ����āA�}���N�X��`�҂͒����I�ԓx���Ƃ�ׂ��ł͂Ȃ��A�����̌��݂̎w���҂������Ȃ���̂ł��낤�Ƃ��A���{�鍑��`�ɔ����Ē����̖�������푈��S�ʓI�Ɏx������ׂ��ł���Ƃ��Ă���B�i�E�̎ʐ^�͏Ӊ�j �@���̎莆�̌`�����Ƃ����_���̒��ŁA�g���c�L�[�́A�J���ґg�D�̐����I�Ɨ�����ێ����A���̐푈�ɑS�ʓI�ɎQ������ׂ��ł���Ƃ��Ă���B�����A���̎莆�ł́u�R���I�Ɨ����v�ɂ��Ă͍l������Ă��Ȃ��B�����̒����̏��炵�āA�u�R���I�Ɨ����v�Ȃ��Ɂu�����I�Ɨ����v�͂��肦�Ȃ������B�g���c�L�[�́A�v���I�J���҂��Ӊ�̌R���ɎQ�����A�Ӊ�𐭎��I�ɓ]�����鏀��������ׂ��ł���ƍl���Ă������A����͏Ӊ�̌R���̑g�D�\�����炵�Ė����Ȓ����ł������B�ё�������悤�ɁA�Ǝ��̐w�n�A�Ǝ��̌R����g�D���邱�ƂŁA�R���I�Ɨ������܂������Ċm�ۂ��邱�Ƃ��K�v�ł������B�ё̎w�����钆�����Y�}�͂����ΐ����I�Ɨ�����B���ɂ����A���̌R���I�Ɨ����̂������ŁA�P�X�Q�U�`�Q�V�N�̂Ƃ��ƈ���ďӉ�ΌR�ɕ��ӂ���邱�ƂȂ��A�t�ɁA���{�R�ɏ��������̂��̓���ŏӉ�ΌR��s�k�����邱�Ƃ��ł����̂ł���B �@�Ƃ���ŁA���̎莆�̒��ł́A�����ɂ���ƏG���͂��߂Ƃ��铯�u�����̈��S�m�ۂɑ傫�Ȓ��ӂ������Ă��邱�Ƃ͒��ڂɒl����B�����̍������Δh�̒��ł́A���̓����푈���߂����āA�R���푈��D�悳�������}�R�Ɠ�������g�ނׂ����Ƃ���ƏG�h�̗���ƁA�v���I�c���s�k��`���Ƃ�ׂ����Ƃ���ɍ��h�Ƃ��Η����Ă����B���̎��_�ł́A�ƏG�̓g���c�L�[�̌�����m�炸�A�g���c�L�[�͒ƏG�̌�����m��Ȃ��������A���҂̌����͍��{�I�ȓ_�ň�v���Ă����B�̂��Ƀg���c�L�[�͒ƏG�̌�����m��A���̂��Ƃ�傢�Ɋ�i�Q�ƁA�w�g���c�L�[�����x��R�X���j�B �@�{�e�̍ŏ��̖|��́w�g���c�L�[����W 1937-38�x���i�ѐA���[�j�����A�w�g���c�L�[�̒����_�x�i�p�X�t�@�C���_�[�Ёj�����̉p���{�ɂ��������đS�ʓI�ɖȂ�����A�U�����ꂽ�������̌�C������Ă���B �@L.Trotsky, On the Sino-Japanese War, Leon Trotsky on Chaina, Pathfinder Press, 1976. |
�@�����O�H��
�@�����O�́A�W�V�N��c�Ȍ�}���ɐ��͂A�ƏG���E�����a����`�̔ᔻ���ĂP�X�Q�X�D�P�P�D�P�T������������A���̌���p���œ}�̎���������A�P�X�R�O�D�T���A��C�x�O�ő�ꎟ�����\�r�G�g����\�����J�����B�X�ɂU�D�P�P���ɂ͓}���������lj�c�Ţ��Ȃ��邢�͐��Ȃɂ�������I�����̕K�v���͐����ē}�����̐����I�C���Ɋւ�����j�I�Ȍ��c���̑����Ă���B�����A�Ꝅ��`�Ƒ�������Ă��邪�A���Ȃ��邢�͐��Ȃɂ�������I���������_�Ƃ��đS���I�v������}���ē������J�n�������ƂɂȂ�B
�@���̎��̗����O�̏���͎͂��̂悤�Ȃ��̂ł������B��S���E�ɕ��Չ���������Ȍo�ϋ��Q�Ɛ����I��@�ɂ��A��O�̐��E�I�厖�ςƐ��E�I�K�͂̊v���Ɛ푈����X�̖ڑO�ɂ��������Ă���B�����͒鍑��`�̈�̍��{�������ł��W�����ł���s�������n�_�ł���B����̂ɁA���ݐ��E�v���̊�@����s������ɂ������āA�����v�����܂��������A����ɂ���Ă܂����E�v������N���A���E�Ō�̊K���I������\�Ȃ炵�߂���̂ł���B�ł��邩��A���E���{��`�̈�ʓI��@�́A���E���{��`�̑����ŖS���Ӗ�����ɂЂƂ����B�����Ă��̈�ʓI��@�̔��W�́A�s�ύt���������A��ӏ��Ŋv������������Α����S���E�ڊv���̏�ɓ]��������̂ł��飁B
�@�����������P�X�Q�X�N�ȗ���腁��R�ΏӉ�ΌR�Ƃ̐킢�̍Œ��ł���A���̊Ԍ��ɏ悶�A�����ƕ����Ƃ̐�̂�_�����B�U������T�R�������y�ё�W�R�̉�������ɖ����Ė�R���̕��𗦂��Ē����ւ̐i�����J�n�����B�V�D�Q�V��������̂��A���V�D�Q�W�������O����ȂƂ��钷���\�r�G�g���{�����������B�Ƃ��낪�A���ꂽ�R���������鍑��`���̋쒀�͂̏�������ĂW�D�T�������ɓ]�����B�����O�R�͓P�ނ��A�������Ē����\���͂P�O���V���ŏI������B
�@�P�X�R�O�N�H�A�����O�H�������Z�����B�����̎w�����j����ς��邱�ƂɂȂ����B�}�̑�O�Ƃ̌��т����̗v�Ƌ��P�����ꂽ�B
�P�@�Q�����Ƃ��Ă̖ё�
���ꎵ�N�̃��V�A�v���͓s�s�̘J���҂����N���Č��͂�D�悵���B�������Y�}�͐ݗ������̓��V�A�v���̂��������̂܂ܖ͕킵�āA�s�s�̘J���҂�g�D���Ċv���^���������߂悤�Ƃ����B�������A�����̒����ł͋ߑ�I�Y�ƘJ���ҊK���͖��Z�Z���ɂ������A�����̐l�X�Ɉˋ����Ċv���^���������Ȃ����Ƃɂ͑傫�Ȍ��E���������B
���X�N���A��̊v���Ƃ����̓\�A�̌o�����Ή����Ă������A�ё͊����͂₭�A�����v���ɂ����Ă͔_���̖������d�v�Ȃ��ƂɋC�Â����B�����Ŕނ͒n��ɍ�悳��A�n���̂Ȃ��ɂ���_����������Ĕ��R�ɗ��������点���B����A�n��̑��A���͂̑��͕������Ă����������悤�Ƃ���B���������������_���͓G�̕������R�ԕ��ɗU������Ŋe���j����B�������Ēn�呤�̌��͂̎x�z������Ȃ��Ȃ����Ƃ�����u�����v���邢�́u�����n�v�Ƃ����B�l������悩��u����v���ꂽ�n��A�l�����v���̂��߂́u�����Ƃ���n��v�̈ӂł���B
�ё͈���Œn��̓y�n��D���Ĕ_���ɕ��z����y�n�v���̌v��ҁA�g�D�҂Ƃ��āA�����ł͂��̂悤�ɂ��Đ��������������A�����n��h�q���A�g�傷�邽�߂̃Q�����푈�̎w���҂Ƃ��āA�������H�Ȕ\�͂������B���{�ɂ͏��ĂΊ��R�Ƃ����������邪�A�����ł͐�������Ή��ƂȂ�A���s����Α��ƂȂ�i�������s�����j�Ƃ����B�ё͏������Ċ��R�ƂȂ�A���ƂȂ����B
�ё͌Γ�Ȃ̔_���̎q�Ƃ��Đ��܂ꂽ�B�_���̎q���Ȃ��Q������̒B�l�ƂȂ肦���̂��B�ߔN�A�ё̉ƌn�ɂ��Ă̎�����������A���̔閧���Ƃ��J�M������ꂽ�B�ё̈�`�q�̂Ȃ��ɂ͌R�l�̑f�����܂܂�Ă����悤�ł���B
�_���̂Ȃ���
�O�͂ł͖ёA�������̓��}�܂ł̘b�������B�����̒������Y�}�̓��V�A�v����͕킵�āA�s�s�̘J���҂�g�D���A���͂�D�悵�悤�Ǝ��݂��B���̂Ƃ��A��̂ȋ��Y�}�͍����}�ƍ�������������Ȃ����Ƃɂ���Ċv���������߂悤�Ƃ������A�N�ɏӉ�͏�C�N�[�f�^���������A���̓s�s�v���H���͍��܂����B�s�s�ł̊v���^���Ɍ��E���������ё́A�_���̑�C���̂Ȃ��Ɋ��H�����o���A�u�_���œs�s���͂���v�헪��͍����͂��߁A�܂��]���Ȉ䉪�R�ɍŏ��̍����n���������B
�������A���Y�}���̎嗬�h�A���邢�̓��X�N���A��̎w���҂����́A�����V�A�v�����f���ɌŎ����Ă����̂ŁA�嗬�h�ƖёƂ��a瀂͐[�܂����B�嗬�h�͖ё��w��������r���������̂́A�G�̍U�������ނ��邱�ƂɎ��s���A�����n����������S���邱�Ƃ�]�V�Ȃ����ꂽ�B���ꂪ�����ł���B
�s���̓r���Ŗё��w�������Ăъm�ۂ��A�����ɂ��ǂ�����B�����ōR���푈��키���A�R�폟����A����������]�V�Ȃ������B�ނ��蟖k��]�킵�A�D���ȍ����}�R�Ɛ킢�A�Ō�̏������l�������B���ꂪ����푈�ł���B
�ё͂��̉ߒ��Ŗ����Ƃ��ɒ������Y�}�̃i���o�[�����ɂȂ����B�������͓����͖ё̏㋉�ł���Ȃ���A�ё̒D�������������A�݂�����͂����⍲��������ɓO����悤�ɂȂ����B�ǂ̂悤�ȉߒ����ւĂ����Ȃ����̂��B��������̏͂ł������B
�쏹�I�N�ƏH���I�N
����O�N�A�����̗����ɂ��ƂÂ��āA�������삪�����Ȃ��A���Y�}�͍����}�̒��ɐg���B���Đ��͊g��ɂƂ߂Ă����B�����}�̓����Ő������Â��鋤�Y�}�̐��͂ɋ��Ђ��������Ӊ�́A�N�l����C�ŃN�[�f�^�������Ȃ��A���Y�}�g�D�ɉ�œI�ȑŌ������������B
���̊�@�ɒ��ʂ��Ċv�����~�����߁A��̕����I�N���v�悳�ꂽ�B��͓쏹�I�N�A������͏H���I�N�ł���B
�쏹�I�N�͓N��������A�������A�ꗳ�A�t���A�铿�A�������炪�k���R�O���]���Ђ����Č��N�����B�쏹���̂������A�����}�����ɕ�͂���A������ɒ��B�A�������ʂɔs�������B�쏹�I�N�͎��s�������A�����}�����ɂނ����ŏ��̏e���ł���A�ے��I�ȈӖ������B�����Ŕ�����������R�߂��Ȃ킿����R�̑n���L�O���Ƃ��Ă���B
�H���I�N�͋㌎����A�ё炪�_�����w�����ČΓ�A�]���ȋ��ŖI�N�������̂����A�I�N�R�͑傫�Ȕs�k���i�����B�����Ŗё͏㋉����w�����ꂽ�A�Γ�ȏȓs�������U������v���f�O���A�䉪�R�n��ɂ��Ă�����A�����ŏ��̔_���v�������n������Ђ炢���B�u�_���œs�s���͂���v�헪�́A�����ɃX�^�[�g�����B����͓s�s�̘J���҂Ɉˋ����郍�V�A�v�����f���ƑΏƓI�Ȑ헪�ł���B
���N�l���A�铿�A�B��쏹�I�N�g�̕������䉪�R�ɂ͂���A�ё̕����ƍ��̂��A�Q���������n�͈�i�Ƌ������ꂽ�B�����v���̎����͔_���v���ł���A�Ƃ����邪�A�䉪�R�ɂƂ����������ȉ������嗤���Ȃ߂��������̉ƂȂ����B�Ƃ͂����A���̏����܂łɂ́A���N�Ԃɂ킽�錌�Ō���Q�����푈���K�v�ł������B
�ё̓Q��������ŏ��́w�����`�x�⑾���V���R�̋��P�Ȃǂ���܂ȂƂ����邪�A�̂��ɂ̓N���E�[�r�b�c�̐푈�_���������Ă���B�䉪�R����ɂ܂Ƃ߂��Q������̃G�b�Z���X�́u�G���i�߂A��͑ނ��B�G�����i�Ƃ܁j��A��͏�i�������j����B�G������A��͑łB�G���ނ��A��͒ǂ��v�i�������G�i��ށA�G�����A�G���ŁA�G�މ�ǁj���̂ŁA�������Z��������Ȃ�B���{�̂���̓J���^�̂悤�ɁA�ё͂��̈�Z�����ŕ����̓ǂ߂Ȃ��_�������ɐ�p�̋Ɉӂ����������킯���B
�䉪�R����ɖё͔_���R�̋I���������߂Ă���B�s���͎w���ɂ��������B�J���Ҕ_���̂��̂�D��Ȃ��B�G����D�������͈̂�l��߂����A�݂�Ȃ̂��̂ɂ���B���̎O�J���ł���A�����ւ��̓I�ł킩��₷���B����ɘZ�̒��ӎ��������A�̂��Ɂu�����̑O�ő̂���Ȃ��v�u�ߗ��̍��z����D��Ȃ��v�̓�J����������A�l���N��Z���Ɂu�O��I���������Ӂv�Ƃ��ďW�听���ꂽ�B���ꂪ�Q���������̗ϗ��ł���A���̋I���̂䂦�ɍg�R�͖��O�̎x�������邱�Ƃ��ł����B
�Q������̗v���₫�т����R�I���͂������ɐ푈�������ɂ݂��т������͂ƂȂ����B�����A�����œ���ꂽ�̌��ɐ푈�̏I�����������肷�������Ƃ��A�̂��ɖё̔ߌ��ɂȂ��邱�Ƃ��v���A�܂��ɉЕ��͂����Ȃ����̂��Ƃ��A�ł���B
�ŏ��̐ڐG
���N�A�H���I�N�����s���A�ё��������Ђ����Ĉ䉪�R�ɂ̂ڂ����Ƃ��A�䉪�R������ɂ��Ă����Ηѕ����i�ΗтƂ͎R���铐�̂��Ɓj���͕��˂Ɖ����ɘb�����āA�䉪�R�ɂ͂��邱�Ƃ��ł����o�܂�����B�����䉪�R�ɏZ��ł����̂́A��Z�Z�Z�l���炸�̋q�Ƃł���A�͕��˂Ɖ������q�Ƃł������B�ё͂����Ŕނ�Ɛe�����������悤�ɂȂ�A��l�͂܂��Ȃ����Y�}�ɓ��}�����B�������A�����ō]���ȓ}�����ɂ�����]���l�i�{�Ёj�Ƌq�Ɓi�q�S�j�̑Η����������Ȃ�A����͂̂��ɕx�c�����̈���ɂȂ�B
�������͓쏹�I�N�����s�������ƁA�ЂƂ܂��L���o�R�ō��`�ɂ̂���邪�A�Ђ����ɏ�C�ɐ������A�����}�̌������Ď��̂��Ƃŏ�C�Ɏ������������Ă����}�����̎d������������B��C�ƈ䉪�R�A���ꂽ�y�n�ɂ����l�̐ڐG�́A���N�A�����̎���������̏��Ȃɂ���Ă͂��܂�B���̂Ƃ��A�������O�Z�A�ܐl�̐����Ǐ햱�ψ��̈�l�ł���A�}������̓i���o�[�E�c�[�ł���B�R�~���e�����������s�ψ���̌��ψ��ɂ��I��Ă���B����ɑ��Ėё͎O�܍A�q���̒����ψ��ł��邩��A�}������ł͓�K���̍������Ă����B
�u�������M�v�i�����N�����j����C�̎��������N�������̂́A�Q�����������ߏ��]������R�~���e�������̔F�����ӂ܂��āA�铿�A�ёɑ��čg�R�𗣂�A��C�̒��������{���Ɉړ�����悤�����邽�߂ł������B
���̂���ёA�铿�A�B�̂Ђ�����g�l�R��͂́A���N�ꌎ��l���ɍ����}�ɂ���Ĉ䉪�R��ǂ��A�]���E�L���̏ȋ���]�킵�Ă����B���M�̏����ꂽ�����ɁA�g�l�R��͍͂]���Ȑ����k���Œnj������ɑ叟���A�܂��g�������Œn��ōg�R�Ɨ����A��l�c�Ɖ���A���M��[�߂Ă����B�]�풆�̂��߁A�l���O���ɂȂ��Ă悤�₭�A�ё�͎���������J���O�ɏ������w���������Ƃ����B
�ё͒����i�������j�Ɉ��Ă��̂Ȃ��ŁA��C�ւ̈ړ����̈ӂ������\�������B�u�������M�͋q�ϓI�����ю�ϓI�͗ʂɑ��ė]��ɂ��ߊϓI�ȕ]���v�ł���B�铿�A�ё�����𗣂�邱�Ƃ͓K���ł͂Ȃ��B
�Q�����D���Ƃ�����̕ω��܂��āA���������C�����̔F�����ω����A�l�������Ɏ������͐�̓w�����Ƃ�����莆�������āA���̖��͍����~�݂ɂȂ����B�������A���̎��_�Ŏ������͂܂��ё̕ԐM�������Ƃ��Ă��Ȃ������B�@�q�Ȏ������݂͂�������j��]�������̂ł������B�v����ɁA�Q���������̌����m��Ȃ����������R�~���e�����̕��j�������ɁA����̎w���Җё�Ɍ�����u�w���v����������Ƃ����`�ł̂��Ƃ肪�A��l�̍ŏ��̐ڐG�ƂȂ����̂ł���B
�����O�H���Ƃ̑Η�
���N�܌��A�\�A����A���������������g�l�R�̗Վ��R�Ϗ��L����������C�ɂȂ��A�Q�����̈Ӌ`�Â��̖ʂōl�����̂��ƂȂ�ё͍g�l�R�̎w�������O����A�����Ȑ����ŕa��{�����ƂɂȂ����B�Q���������̍s���͊�@�Ɋׂ����B
���̊�@��ŊJ���邽�߁A�Z�������̐����lj�c�Ŏ������͌R����c�̊J�Â��Ă����B����ɂ��ƂÂ��āA�������{�B���䉪�R������āA��C�ɓ������A�������A�����O�A�B���g�l�R�H��ɑ���w���������������B�L���ׂ��Ȏ������̎w�����ӂ܂��ĒB���N�������̂��u���������̍g�l�R�O�ςɈ��Ă��w���M�v�i�㌎���j�ł���B���̎w���M��B�������n�ɂ���������A��ꌎ��Z���A�ё͂悤�₭�g�l�R�w�����ɕ��A���邱�Ƃ��ł����B
�R�~���e�����͂������n�̎���𗝉�����ɂ������Ă��Ȃ��B�����ŎO�Z�N�O���A�������̓R�~���e�����Ƃ̈ӌ������̂��߂Ƀ��X�N���ɕ������i�������A���j�B�������̗���Ɉ�̂���܂������������B�����a�����������O�����������̈ӎv������s�����ƂɂȂ�A�����U���Ƃ����`����`�H�����̑����ꂽ�B���Ȃ킿�Z�����������ǂ͗����O�̕u�V���Ȋv���̍����ƈ�Ȃ��邢�͐��Ȃ̎�揟���v���̑����A��������\�����͂��܂����B
�����O�H���A���邢�͒����̎w���ɒ����ȉ������w���҂Ƃ���{�Аl�i�]���l�j�̓}�������ƁA�ё�ɒ����Ȍ��R���͕��ˁA������̍R���̒��ŁA���������������B�ёA�铿�Ȃǂ��g�l�R���Ђ����ăJ����A�r�����ɉ��������Ԍ��ɏ悶�āA������͗�������������Ă����d�����R�̗͂���āA�͕��˂Ɖ������E�Q���Ă��܂����B�O�Z�N���߂̂��Ƃł���B�ނ炪�ĂюR���ɖ߂�������Ƃ����̂����̗��R�Ƃ��ꂽ���A�ނ������ɂ����Ȃ������B
�x�c�����̑�l��
������]���l�O���[�v�Ƌq�Ƃ���іёƂ̔��ڂ́A���̃��E���h�ɂ��������ꂽ�B���͂Ȗёh�ɑR���邽�߁A������͗����т��w���҂Ƃ��铌�ŁA�����n��̓}�Ǝ�����B�������č]�������n�̎w�������߂���ёƉ����A�����т�̑Η������������B
���ɎO�Z�N������A�ё͑��O�G�ψ���i���L�ёj�̖��ŗ����i�����J�_�v���ψ�����h���j��h�����A�]���Ȃ̓}�@�ցA�\�r�G�g�@�ւ��͂��A���Z�]�����`�a�c�i�A���`�E�{���V�F�r�L�c�j���v�����q�̌��^�őߕ߂���Ƃ����搧�U���ɏo���B
����ɑ��đ��Z�R�̈�R������������N�����A�t�ɈՎ��m�i�������h���j�A���S���i��Z�R�R���j�A�������ߕ߂����B�����͂قړ�Z���ԂÂ����B���̔�����ёw�����̑��O�G�ψ���Ƒ����ʌR���������A�ߕߎҎl�Z�Z�Z�l�ȏ�A���Y�ғ�Z�Z�Z�l�ȏ�Ƃ�����l�������ɔ��W�����B
�x�c�����̒ꗬ�́A�ёH���ƁA�����O�H���𐄐i����]���ȓy�������Ƃ̑Η��ł���B�l���S��ŗ����O�ɑ����Ē����̎������������������ȂǃR�~���e�����h�́A�x�c�����v���\���ƒf�肵���ёh�̍s���F���A�l��������ɐi�߁A���ɂ͍]���ȓy���̊����̂قƂ�ǂ����Y���邢�͍~�i�����ɂ��Ă��܂����B������͍]���n���}�����`�a�c�i�����}�̕ʓ����A�����g�D�j�������O�H�������ƏG�E�g���c�L�[�h�A�Ƃ����s��ȏl���̌��������A�]�������n�݂̂Ȃ炸�A���ׂĂ̊v�������n�ɂ�����l���^���ɓK�p�����B�����烂�X�N���A��̎��w���҂ɂƂ��āA���n�̕����݂͂�����̐��͊g��̐�D�̃`�����X�ł������B�X�^�[�����̒��V��͂������āA�����v���̌�����������悤�Ƃ��Ă����B�܂��Ȃ��r�����A�C�쓇�A��罃R�E�A�^�A��k�Ȃǂ̍����n�ɂ����āA�g���c�L�[�h���邢�͒ƏG�g���c�L�[�h�Ƃ��đ����̊v���Ƃ��l������Ă������B
�������A�v�������n��
�������͎O��N���{�ɏ�C�𗣂�A����ɒ����v�������n�i�����\�r�G�g��j�̒��S�����ɒ������B�N�ȗ��l�N�Ԃɂ킽��u����v�Ƃ�ꂽ�����}�������ɂ�����n�������̐����i���̊ԁA���̃\�A�K����܂ށj�͂���ŏI������B���Ɏ������O�O�ł������B�����A����̖ёA�铿��A�����Ĉꑫ��ɒ����Ă����C�J���A���p�A���ҏ˂�Ɖ�A�����\�r�G�g�撆���Ǐ��L�ɏA�C�����B
����A���������ނ����������\�r�G�g��ł͎O��N�t����Ăɂ����āA�ёA�铿�炪�A�G��[���������肱�ޕ��j�ŏӉ�̑��A��O����͓��������ނ��邱�Ƃɐ������Ă����B
����ɂ��ď�C�̗Վ������́A�㌎����t�w�����Ȃ��\�r�G�g�撆���ǂƍg�R���O�ςֈ��Ăāu�̑�Ȑ����v�Ǝ]�������̂́A�y�n���Ȃǂɂ��Ă͔ے�I�ԓx���Ƃ�A�g�R�ɂ̓Q������`���������悤���߂Ă����B�܂��y�n�v���ɂ����Ắu�n��ɂ͓y�n����ȁA�x�_�ɂ͈����y�n����v�Ƃ����K���H�����w�����Ă����B
��ꌎ��`�ܓ��A�����̎w���M���ѓO���邽�߁A�]���Ȑ����Ń\�r�G�g��}��ꎟ��\���i�R�E���c�j���Ђ炩�ꂽ�B�ё̎咣�́u�����o���_�v�u�x�_�H���v�u�E�X���a����`�v���Ƃ��肼�����A�����̋ɍ��i�U�H�����̑����ꂽ�B�����ő����ʌR���i�߁A�������ψ��̃|�X�g��p�~�������߁A�ё͒����\�r�G�g��g�R�ɂ�����w���I�n�ʂ��������B
��C�̗Վ������͎O��N�܌���Z���A�\�r�G�g�撆���ǂɈ��Ă��w���d��̂Ȃ��ŁA�Ăіё헪��ᔻ���������łȂ��A�����ɗ�������̎����������ᔻ�����B���킭�A�u���������u�̓\�r�G�g��ɗ��Ă��炢�ꕔ�̌��͐����������A��̍H���O��I�ɕς���H��͂܂����ʂ������Ă��Ȃ��v�B���̂悤�ɗՎ������͍ĎO�Ďl�A�\�r�G�g�撆���ǂ��i�U�H���A�ɍ��H���𐄐i����悤���͂������Ă����B
�����Ɩё̑Η��́A���܂�헪���x���̘_������A�g�R�̍s�����j�ɂ܂Ŕ��W���Ă����B�\�r�G�g�撆���ǂ͖ё̌��c��e��āA�R�E�]���݂���k�サ�āA�y���E�i�L�E�X���̓G����|���邱�Ƃ����߁A�ё��g����ʌR�������ψ��Ɍ��肵���B�O���ł͎���������ȂƂ��A�ёA�铿�A���ҏ˂��������u�ō��R����c�v������A�O���̈�̌R���s�����w�����邱�Ƃɂ����B
�������A�ёA�铿�A���ҏ˂�͔����ꎵ����������Ɋy���E�X���E��L�̎O�s�s���̂��A�ܐ�]�̕�����r�ł��A���B�E�쏹�E�����̍����}�R���ӂ邢�����点���B�����}�R�͒����ɓ��Ɉꎵ�R�A�����W�����A�Ԃ��ł߂��B�����œ��U���̐�������߂����đO���ƌ���Ƃ̖��C���\�ʉ������B
�g����ʌR�͔�����l���������ďo���������A��鑤�������ł߂����Ƃ�m���A�U�����~�̔��f���������A�����������̎|�A����̃\�r�G�g�撆���Lj����Ȃ��������B�������A�����ǂ͑O���̒��~���j�ɓ��ӂ��Ȃ������B�����őO���͂�ނȂ��㌎��Z���铿���i�߁A�ё����ς̖��Łu�P�߁v���o���A�ё̐헪�ɂ��������čs����W�J���悤�Ƃ����B��������ǂ͂���ɔ����A�s���̈ꎞ��~�����߁A�O���ƌ�����^������Η��������߁A�������s���ƂȂ����B
�Q�@���`��c�ł̋t�]
�i�]�̔J�s��c
�O��N��Z���O�`�����J�s��c�A���Ȃ킿�\�r�G�g�撆���ǑS�̉�c���Ђ炩�ꂽ�B�o�Ȏ҂͌�����痈���C�J���A���p�A�ڍ����A�g�E���ƁA�O���̎������A�ёA�铿�A���ҏ˂̌v���l�̃\�r�G�g�撆���ǃ����o�[�ł���A����������ɂ����B
���̉�c�ɂ��Ắu�\�r�G�g�撆���ǔJ�s��c�o�ߊȕ�v���c����Ă���݂̂ŁA�i�]�����������B���̂��߁A���̊Ԃ̎������Ɩё̊W�ɂ��Ă��܂��܂̉����������Ȃ��Ă����B�����Ƃ����z���ꂽ�̂́A���̉�c�Ŏ��������ё�r�˂����Ƃ������߂ł���B�ёƎ������̊W�����Ƃ���{���́A���̐^����Nj����Ȃ��킯�ɂ͂����܂��B
�V�����ɂ��ƔJ�s��c�̑��_�͂��̂悤�Ȃ��̂ł���B
?�B�U�����B
�J�s��c�O�̔��J���A���Ȃ킿�O��N�Ƀ\�r�G�g�撆���ǂ́A�����̒�N�����i�U�H�������s���A�g����ʌR��͂ɃR�E�B���U�����������A�ё͂��̍��ɓ������甽���Ă����B���̌�O���g�R���s�k�����̂�m���a�������đO���ɕ����A�g�܌R�c�̋N�p�����c���A�g�R��͂����S�ɓP�ނ������B�J�s��c�ł��̖��_���������A�ё�?�B�U�����s���ׂ��ł͂Ȃ������Ƃ��肩�������B����̒����Ǒ���?�B�U���͕K�v�ł���A�U�����s�̐ӔC�͖ё炪�i�U�H�������s���Ȃ��������Ƃɂ���ƒf�����B
?�B�U�����̕]���B
?�B�̖����I����Ă܂��Ȃ��A�ё͍g�R���H�R���w������?�B���U�����A�Ӊ�̐N�U�z�u�𝘗����A��ʂ̎����╨����D�����Ƃɐ��������B�����������́A��O�H����\���s�킸�A��̒��ӂ������D��Ɍ������A�Ɩё�ᔻ�������߁A�J�s��c�ł͂��̐�p�̓��ۂ��c�_�ɂȂ����B
���W�헪���B
�ё͎O�����{�Ƀ\�r�G�g�撆���lj�c�ŁA�G�����A��サ�Ƃ����F���̂��ƂŁA�����𒆐S�Ƃ��ׂ��Ǝ咣�������A����́A�G�̐N�U��҂�����̍��Ɣ��ꂽ�B�������͖ё́A�����𒆐S�Ƃ���l�����ɂ��ẮA���₩�ɔᔻ�����A����i�����j�̓��u�����ƈ���Ėёɑ���ߓx�̔ᔻ�ɂ����݂��Ȃ������B
�������́A�ё̐ϔN�̌o���͍��ɂނ��Ă���A�ނ̋������푈�ɂ���Ƃ̗��R����A�ё�O���ɂƂǂ܂点��Ǝ咣�����B������1)���������푈�w���ɑS�ӔC�������A�ё��⍲�Ƃ��đO���ɂƂǂ܂邩�A2)�ё��푈�w���ɑS�ӔC�������A���������s�����j�̊ēɑS�ӔC�������A�Ƃ�����Ă��o�����B
��c�͌��ǁA��������1)�Ă��̑��������̂́A�ё͕a�C�𗝗R�Ɍ���ɂ��ǂ����B�J�s��c�̐�����A�\�r�G�g�撆���ǂ͉�����Վ������̎w���ɂ��ƂÂ��ĉ�c�̌����ύX���A�ёɌ���Œ����Վ����{�̍H���������ƌ��肵�A�������̍g����ʌR�����ψ����C�𖽂��A�ё͂��̃|�X�g��D��ꂽ�B
��ꌎ�́u�R���H���ɂ��Ẵ\�r�G�g�撆���ǂւ̎w���v�́A�ё̐헪�������h��H���Ɣᔻ���A���̒ǐ��҂�����r�˂��Ō��������������A���̂Ȃ��ɂ͎Ⴋ�������������ё��H�Ȃǂ��܂܂�Ă���B�ё͕�����@�ɗH�����`�ƂȂ����B
���a��`�҂ւ̔ᔻ
�O��N��ꌎ�����A�C�J�����������Ǒ��́A��C�̗Վ������Ɉ��Ăēd���ł������A���̓d��̒��ŁA1)�������́u�O�����u�̑ҋ@��`�v���Ȃ킿�ё̌��Ɠ������A�����i�����j�̐ϋɐi�U�H���Ɏ^�����Ă��Ȃ��B2)�������͖ё����삵�Ă���B3)�������͒��a��`���A�Ɣᔻ����Ă���B�u����͎������̍ő�̎�_�ł���B��_�𗝉����������Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�B
�������͂��āA�����O�ɑ��Ē��a��`�̌���Ƃ����A�Ɣᔻ���ꂽ�B����͖ё����ɂ����ē�������Ƃ����Ɖ����炩��ᔻ���ꂽ�B���a��`�̗p�ꂪ�K�����ǂ����͕ʂƂ��āA����͎������̍s���p�^�[���̂��鑤�ʂ��悭���߂��Ă���B�̂��Ɂu�܂�߂��݉��v�Ɣl�|���ꂽ�̂��قړ����Ӗ����B
�������͗Վ������ɂ��ĂčR�ق����B1)�ёɑ��ĉ��a�ȑԓx���Ƃ������A����͒��a��`�ł͂Ȃ��B2)����̓��u���ёɑ��ĉߓx�̔ᔻ�������Ȃ����͎̂����ɔ�����B3)�ё�O���ɂƂǂ߂�̂́A�ё̌o�������ɓK���Ă���A�푈�ɗL���ł��邩�炾�B
������̗Վ������͎O�O�N���߁A�����}�ɂ���ď�C��ǂ��A�����\�r�G�g��Ɉڂ������A����ɂ���ĉ����ɍ��H���i�i�U�H���j�͂܂��܂��Ђǂ��Ȃ����B�O�O�N�Z����{�A���Â͔J�s�Œ��������lj�c�i��J�s��c�j���Ђ炢���B�ё͂���ɏo�Ȃ��A��ꎟ�J�s��c�̏����̌����咣�������A���Â�͂��肼���āA�ёւ̔ᔻ������������߂��B�ё͂ӂ����ѕa�ɂ����ꂽ�B
���`��c�ł̕���
�Q�����̍����n�͂��Ƃ��Ɩё���������J�������̂ł���B���Ƃ��獪���n�ɂ���Ă������X�N���A��̎w���҂������A�R�~���e�����̌��Ђ��P�ɂ��Č���̎���ɂ���Ȃ����߂��������Ȃ��ŁA�퓬�͔s�k�����肩�������B���ɍ����}�̕�͓��������ނł��Ȃ��Ȃ����B
���܂�]���\�r�G�g���̂ĂāA���̍����n�֓��S���邱�Ƃ�]�V�Ȃ����ꂽ�B�����߂������̂œ����͐����Ƃ�ꂽ���A�̂��ɒ����̖��ɓ��ꂳ�ꂽ�B�ё͔����̋@������������Ȃ���A�����̑���ɉ�������B
�����̉ߒ��Ŗё��}���̎w�������������̂��A���`��c�ł��邱�Ƃ͂悭�m���Ă���B���`��c�Ȍ�A�ё͂��̎����܂Œ��������̌��͂��ɂ���Â����̂ł��邩��A���̉�c�̏d�v���͖��炩�ł���B
���̋M�B�ȏ��`�ւ̓����w�������`�x�͂����`���Ă���B
�u�M�B�̓V�C�͂悭�g�V�ɎO������Ȃ��h�Ƃ�����B���`�i�R����r���A�������J���~�葱���A���͂ʂ���݁A���ɕ����ɂ��������B�������͊F�Ɠ��l�A��ɏ�������A�т���G��̈ߕ��𒅂āA�J��`���čs�R�����B�����̒n���͋N�����������A����z����Ƃ܂��₪�Â��Ă����B�����̎��ɁA������ƕs���ӂ��Ɗ����ē]�сA�l�X�݂͂ȓD�܂݂�ɂȂ����v�B
����������s��s�̋���A�O�ܔN�ꌎ�����A�g�R�͋M�B�ȑ��̓s�s�E���`���̂����B���`��c�͎O�ܔN�ꌎ��܁`�ꎵ���ɍs��ꂽ�B�Ȃ��G�̍U�������ނł��Ȃ������̂��A���̎w���̌������邱�Ƃ���c�̖ړI�ł������B�܂����X�N���A��̔��Ái�`�M���j������A��͓����ӂł��Ȃ������q�ϓI�������������邱�Ƃɂ���āA�݂�����̎w���̌����B�����Ƃ����B�������͕����s���A����͓��������s������Ȍ����͌R���w���ɂ�����헪��p�̌��ɂ���Ǝ��Ȕᔻ���A���ÁA�u���E���i�R�~���e��������h�����ꂽ�h�C�c�l�R���ږ�j��ᔻ�����B
���̂��ƒ����V���A�ёA���ҏ˂Ƌ����ŋN�������ɍ��R���H���ɔ�������s�����B�Â��Ėё����������ŌR���H���̌��̊j�S�P���A�v���푈�̐헪����_���A����̕������N�����B���ҏˁA�铿�A�������A���x�t�A��h�j��������Ŕ������A�ё̎咣���x�������B
�_�����`��c�̓`�B�̂��߂ɓ��������������ɂ��A���̉�c�ɂ����āu�������Ƃ��̑��̓��u�͒����V�A�ёA���ҏ˂̒�j�ƈӌ��Ɋ��S�ɓ��ӂ������A���Â͎��Ȃ̌������S�ɂ͔F�߂Ȃ������B�u���E���͎���ւ̔ᔻ�ɂ��Ēf�łƂ��Ĕ������v�B
��c�̌��_�͂����ł������B
1)�ё𐭎��Ǐ햱�ψ��ɑI�ԁi�ё͎O�Z�N�̘Z���O���S��Ō��ɂȂ�A�O�l�N�̘Z���ܒ��S��Ő����Ljψ��ɂȂ��Ă����B���`��c�����̏햱�ψ��́A���ÁA�����V�A�������A���p�̎l�l�ł���j
2)�����V�����c���N�����A�햱�ψ��̐R�����o�āA���_�̂��߂Ɏx���ɔ��o����B
3)�햱�ψ��̐E�����S�����炽�߂�B
4)���ÁA�u���E���A�������̎O�l�g�ɂ��w���̐�����߂�B�ō��R���铿�A���������R���w���҂Ƃ��A�������͌R���w���̍ŏI�I�ӎv����ӔC�҂Ƃ���B
��c�̂��ƁA�햱�ψ���c���Ђ炫�A�ё��������̌R���w����́u�ҁv�Ɍ��肵���B
�тƎ��̗���t�]
���`��c�̊֘A��������ނƈȏ�̂悤�Ȃ��Ƃ��킩�邪�A�������͂ǂ̂悤�Ɍ���F�����A���Ȕᔻ���A�ё̑��ɓ]�����̂��B
�������������̉ߒ��ŌR���w���̌���Ɋ�����悤�ɂȂ����̂́A�Í]����i�O�l�N��ꌎ���{�j�ŕ����̔����������Ȃ��A���O���]�ɋ}�������Ƃ��ł���B���̂��ƁA������ɌΓ�Ȓʓ��ŁA�ꔪ���M�B���t���ŁA�Â��ĎO�ܔN�ꌎ����M�B�ȉG�]��݂��ˏ�ōg�R�̐i���Ƃ����������S�̕��������߂邽�߂̌����c�����̂ǂЂ炢�Ă���B�����̉�c�ɂ�����ё̎咣�̑Ó������V�A���ҏ˂�ƂƂ��Ɏ��������݂Ƃ߂�悤�ɂȂ����悤�ł���B
�����A�������̓}����эg�R�ɂ�����n�ʂ́A�ږ�u���E�����̂����A���ÁA�����V�ɂ��i���o�[�X���[�ł���A���]���炢���Η��҂ɕ���ł����B���������n�ʂ��炵�āA��������������A��c�̐i�s���Ƃ߂邱�ƂɂȂ����B�������݂͂��������肵����c�Ŕ��Â̐�p�̌���ᔻ���A�݂����炪����ɒǐ��������Ƃ����Ȕᔻ���A�ё��w�����̈���Ɉ����������̂ł������B
���������̎��_�ł́A���Â̑��ӔC�҂Ƃ��Ă̒n�ʂ���C����ɂ͎��炸�A�R���w�����Ǝw�����ɂ��Ă̂ݎ����������Âɑ�ւ���ɂƂǂ߂��B�ё͂����Ŏ�������⍲�����������������ꂽ�ɂƂǂ܂�B
�����ĉ�c��A�O�Ȃ̌��E�i�l��A�M�B�A�_��j�ŁA���ӔC�҂̒n�ʂ��甎�Â����肽�̂Œ����V������ɑ���A����ɒ����V�̒�Ăɂ��ƂÂ��ĖёA�������A���ҏ˂���Ȃ�O�l�g���R���w���̑S�������悤�ɂ��߂��B�����ŏ��߂ĖёƎ������̊ԂŁA����ƕ⍲�̊W�������Ƃ��ɋt�]�����B
���̂悤�ɂ݂Ă���Ǝ������̌���I�����������т������Ă���B���������������ÁA�u���E���Ƃ̎O�l�g�ɌŎ����A�R�~���e�����̌��Ђ𗘗p���āA�ё̒���ɑR�����Ƃ���A�ё̒D�������͂���߂č���ɂȂ�A�g�R�͌�����w���ɂ��ƂÂ��đS�ł��Ă����\��������B
���̌���I�ȕ���ɂ��Ď������͂̂��ɂ����q�ׂĂ���B�u�ю�Ȃ̎w���I�n�ʂ͐�����ċ�����A�ł���B��R���n�̂Ȃ��Ŗю�Ȃ̎w�������m�ł��邱�Ƃ͎������ؖ����Ă���v�B�܂��u�ю�Ȃ��q�H��ς����̂ŁA�����v���͗��̂Ȃ��Ŋ댯����̂���A�s�k�������ɓ]���邱�Ƃ��ł����v�Ƃ��q�ׂĂ���B
�����A���̓�
�O�ܔN��Z�������A�g�R�͌��N���ɒ�����蟊É����̐l�X�̔M�����}�������A��E�ܖ��L���̒������I������B���̒����̂��т����ɂ��ẮA�l�X�̃G�s�\�[�h���c���Ă���B
�������n�܂�ƁA�����n���͔x���j�œf���������߁A�x�{�����ɕғ�����A�������ƕʂ̍s�R�ɂȂ����B�ёA���������x�{�����Ƃ���Ⴄ�Ƃ��A�l�X�́u�т���ƃq�Q������Ă���v�Ƌ��Ԃ̂��킾�����B�������͓����A�S�q�Q��L���Ă������߁A�q�Q����i�ӌ��j�Ƃ��Ă����B�������̓g�E�n���̂��Ƃɋ߂Â��A�A�O���b�������ŗ����������B����Ƃ������}��s�@�̔����ɂ���ċx�{��������\���l�̎����҂��o���B�������͐^�钆�ɂ����������A�����Ԙb���������ł����������B
�O�ܔN�����A�������̕a�C���d���Ȃ�A�悤�₭���n�����ނ����ɗ����B�������͈ӎ��s���Ŗؔ̃x�b�h�ɐQ������Ă����B���n���͒n�ʂɈ�m��~���ĐQ���B�ޏ����������̒E�����r�т̃`���b�L�����Ă݂�ƁA����킢���A�Ȃ�ƈꎵ�Z�C�̃V���~�������B���n���̎w�̒܂́A�}�j�L���A�ł������悤�ɐ^���ԂɂȂ����Ƃ����B
�ё͒����̂Ƃ��A�֔�ɔY�܂��ꂽ�B�s�K���Ȃ��R�����H���̂��߁A��T�Ԃ���ւ̂Ȃ����Ƃ����������B�����Ŗё���ւɐ��������j���[�X�ɎO�R�����Ă��A�������̑���ɂ��Ċ��t�������Ƃ����������B
�q�m���⋴�́A蟖k�]����ɖё̗p�ւ̂��߂ɁA�悭���@��𖽂���ꂽ�B�u��ȁA�ǂ����ĕ֏��ɍs���Ȃ��̂ł����v�u�������̂��������B�]���X�ɂ悭�Ȃ��v�Ɩё̓����B�u�ł��A�_���Ɛ��Ԙb������Ƃ��A�����ӂ��āA���̎���|���Ƃ������āA�����������Ă邶�Ⴀ��܂��v�Ɨ��⋴�����Ԃ���B�u����͂���A����͂��ꂾ�v�ƖёB�u�Ƃ���ŁA�N�͂����m���l���邩�ˁv�Ɩё��₤�B�u�x�b�h�̏�Łv�Ɠ�����ƁA�u�����Ă�낤�B�p�ւ̂Ƃ������A�����l���������Ԃ̂��B�֏�������Ȃɂ������āA�����l���������Ԃ��ˁv�B
�k���ւ̐i����A�앳���ł��Ȃ��Ȃ�A���⋴�͌��@��̎d�����Ȃ��Ȃ����B���̑���ɖёɟ������{�����Ƃ����⋴�̑厖�Ȏd���̈�ɂȂ�A�܋�N�܂ő������B���̍��ɂȂ�ƁA�ё̐H�������P����A�֔邪����A�����̎d�����Ȃ��Ȃ�������ł���B
���������[�[�̏o�G�W�v�g�ɂ��Ƃ����_�҂�����B���̓��ۂ͕ʂƂ��āA���̗����z����₷����̗��ł��������Ƃ͗e�Ղɑz���ł���B���Ƃ��A�H�ׂ���̂��Ȃ��Ȃ�A���ɍr�ꎛ�̔j�ꑾ�ۂ̔���ς���ŐH�ׂ��b�Ȃǂ́A���̈��ł��낤�B�@���u�͂̂��ɁA����͂ق�Ƃ��ɔ��������Ȃ������Əq�������B�l���̂��̂Ȃ�e�[�u���ȊO�͂��ׂāA����Ԃ��͔̂�s�@�ȊO�͂��ׂĐH�ׂ�̂������l���̐H�����Ƃ����邪�A�����̖Ҏ҂����ۂ̔炾���́A�h�������炵���B
�R�A�ю�Ȃ̓o��
��������̊J�n
���l�ܔN�A�����푈����������B�܂��Ȃ��R���������͂�Ԃ�A���Y�}�R�ƍ����}�R�Ƃ̊Ԃɓ��킪�ĊJ���ꂽ�B�l�Z�N�Z���A�����}�R�������ɑ���U�����͂��߁A�������킪�͂��܂����B���N�����������Ă����Ȃ�ꂽ�������E�}�[�V������k���l�Z�N���ɂ͕��ʂ�ɂ�������B
�l���N�O���A�����}�R�͉����ɂ��܂����B�O�����������̈ꖜ�]�̌R�����R���̏������ʼn����h�q�̓������ɂ��܂����B���̎��A�������͐����A�R���A�o�ς̊e���ʂ���Ӊ�ΐ��{�̌���͂������ƁA�����ނ��B�u�����ɂ͖ю�Ȃ̒��ڎw��������A���Ȃ炸�����킳���ł���B������h�q����A�ю�Ȃ�h�q����I�v�����ɂ͖ё_�b�̐����ɂ����Ď������̂͂����������̈�[����������ɂ���Ă���B
�O�������A�������ɍ����}�R�Ɍق�ꂽ�A�����J�������@��������A����R�����������ɑ�^���e�𗎂Ƃ������A���̂Ƃ��ёA�������A�d�����͌R�p�n�}���Ђ炢�āA�}�������������Ă����B���̓��A�铿�A�C�J���A�t���p�͈ꕔ�̋@�֗v���ƂƂ��Ɋ��~�ƂɈړ]�����B�ёA�������͉����ɂƂǂ܂������A������a���牤�ƒɂ�����Ă�������R�����Ɉړ������B
�O����O�����ŁA�����}�R�ӏ@��̈�l���c�͋X��A���삩�牄���ɂނ����ĖҍU�����͂��߂��B�d�������ёɉ�����P�ނ���悤�����߂��Ƃ���A�ނ͂����������B�u���͍Ō�ɉ�����P�ނ��悤�B�ӏ@��̕����ǂ����ǂ�ȋ�Ȃ̂��A���̖ڂŌ���������ˁv�B
�O���ꔪ���[���A�ёƎ����������c���i�߈����k�Ƙb���Ă���Ƃ��ɁA����������傫�ȏe�����������A�����}�R�̐擪���������ƞ����܂Ői���������Ƃ��킩�����B�@�ւ��A�Q�O�����ׂēP�ނ������Ƃ��m�F�����A�ё͂킴�Ƃ������H�������āA���ꂩ��W�[�v�ɏ�����B�u���u���N�A������낤�I�@�����͂��Ȃ炸���ǂ��Ă���I�v�B�}�b�J�[�T�[���ɂ����A�A�C�E�V�����E���^�[���Ƃ������Ƃ��납�B�}�b�J�[�T�[�͂����Ĉ�l�̂����ɂ������A�ё̂����́u�����v�ł���B
������P�ނ��Čܓ��ڂɖё�͊��~�Ƃɂ��A��x�݂����B�O����ܓ��������A���w���ō����}�R�l�Z�Z�Z�l�r�ł̏���ɐڂ����B�Â��Ďl����l���r�n�͐���A�܌���`�l��崗�����ł���������������B
�V�����̞��эa�œ}�����͏d�v��c���Ђ炫�A�ёA�������A�铿�A������A�C�J���珑�L�ܐl�̐ӔC���S�����߂��B�ё��S���̌R���w���ɐӔC�������A�������������⍲���邱�ƂɂȂ����B�铿�͓}�̊Ď@�H��A������͓}���Ɣ���H��A�C�J�����y�n���v�ɁA���ꂼ��ӔC���������ƂɂȂ����B
�ё͂����Ōӏ@��̌R����ܖ���|�M�����Ă��������ł͂Ȃ��B���c����i�l���N��`��ꌎ�j�̂��߂ɁA�d������Ȃ��Ƃ������ʂ����āA��p���w�����Ă����B�ё͎������̋��͂āA�S���̉���푈���w�������̂ł���A���҂ٖ̋��ȋ��͎͂l���`�l��N�̉���푈�̑S�ߒ���ʂ��ĊѓO���ꂽ�B
�����ɖё������ꂽ
���l���N�����ꔪ���̂��ƁA�����˂Ă̔s�k�Ɍ��{�������A�́A�����c���Ђ����Ėё璆���@�ւ̐��S�l��nj����A�V���A�Ď����o�āA�ь��i�����j�ł��ɉ��͉݂͊܂Œǂ��߂��B��J�������A���͂͑������Ă����B�O���ɂ͑����Q�������́A�������͍����}�R�̒nj��A�ёA��������͐i�ނ���܂����B���͂͌x�q�������Z�Z�]�l�A�G�R�͐����l�B���͂�n�͂��ׂ����ۂ��B
�ё͒��T�Ȋ�œ�{�w��ˏo���A�������z����������āA�u����������v�Əd�������Ђ炢���B�q�m�����ɂ͏������Ȃ��B�����������F�����������A�悤�₭�n���̌����ɕ��ő�ɂ��܂��Ă��������̂��Ă�������B�ё͂��̈ꕞ��[�X�Ƃ����B�����c�����S�l�̖��^�́A���̎����̍s���̂��Ƃ��ł���B
�e���͂܂��܂��������Ȃ�B�ё͋z�k�����Ă�ƁA�����ς�f�����B�u���͓͂n��Ȃ��I�v�@�����ēG�R�����̏e���̑O�������������������B�ё͉��͂�n��͖̂k������̂Ƃ��A�ƕ��ɂ��߂��̂ł��낤�B���k�̐�ǂ������I�ȏ̂��ƂŁA�i�ߕ����s�����͂��߂��̂ł͑�������ɂȂ�B�����͑�o�N�`��ł��āA���C�̃p�t�H�[�}���X���K�v�ł������Ƃ�������B�Ȃɂ���������E�C�Â��邽�߂ɁB
��ւ��N�������̂́A���̂Ƃ����B�����̓G�R�͓ˑR�ˌ����~���C�nj����~�߂��B�����}�R���ёA��������������܂Œǂ��߂Ȃ���A�Ȃ��r�ł̋@����킵���̂��A�悭�킩��Ȃ��B�ё͋u�����A�����_�ň�x�݂��A�ꑧ���ƓˑR�����u���v�v�����Ȃ����B�u���̂ڂ�ё̌�p�����߂Ȃ���A�C�J�������S�[���ɂԂ₢���B�u�����ɖё������ꂽ�v�B�ё]�́u�����g�v�̉̎��͂����ł���B
�u���͐Ԃ��B���z������B�����ɖё������ꂽ�B�ނ͐l���̂��߂ɍK����d��B�ނ͐l���̋~���̐����v�B�v���́u�C���^�i�V���i���v�̒������ɂ́u���̐��ɋ~����͂��Ȃ��v�Ƃ�����傪����B���̉̂��̂��Ȃ���v���������߂Ă�������̂Ȃ�����A�u�ё͋~���̐��v�Ƃ����̂������܂���悤�ɂȂ����̂́A���̂Ƃ��ł���B
�ё͉��˂�����
�l���N�����ꔪ�`��Z���A���k��ǂɌ���I�ȓ]���������炷���͓X��������ꂽ�B�ё͎������̋��͂̂��Ƃɍ������A���k���R�i�ߜd�����ɓ͂����B���̎O�����A�ё͕������o���A�֏��ɍs�����A�x�b�h�ɐQ�Ȃ������B���͂悭���B���t�ɂ͎O�𒍂��A�Ō�ɂ͒��t��H�ׂ��B���̏K���͎Ⴂ�Ƃ�����̂��̂ŁA�I���ς��Ȃ������B���ւ͕֊��p���Ă����Ȃ��A���⋴����������Ă��B
�ё͉��˂ł���A����������t�������ŁA�炪�^���ԂɂȂ����B�����łقƂ�Lj��ދ@��Ȃ��������A��O���������B����͐������ꂽ�Ƃ��A�퓬�w���⎷�M�̂��߂ɐ��ӓO�邷��Ƃ��ł������B���͓X����̂����ɐ������ꂽ�̂ŁA�q�m�͎���p�ӂ����B
�������߂�ёɗ��⋴��������B�u�ǂ�Ȏ����悢�ł����B�����i���r�E�o�C�`�E�j�͂ǂ��ł����v�B�u�����͂��₾�B�G�̏ߏ����R�́A����قǐh���Ȃ��v�B�u�ł͕������́H�v�B�ё͂��Ԃ���ӂ�A�u����͓G�͏\�����A�������݂����Ɏキ�͂Ȃ��B�e�ՂȂ���������Ȃ��B�c�c�E���A�u�����f�[�͂��邩�ˁv�B�u����܂��B�O�����̂ł��v�Ɨ��⋴�B
���ǁA�ё͉������ܔ������A���𐔏\�t�̂݁A�d�����ɖ����ďߏ��̎O�Z�t�c��r�ł����A�Z�Z�Z�Z�l��ߗ��ɂƂ�퓬���w�������B�퓬�������ɂ�����A�ё͜d�����̂��߂Ɂu�N���������n�A�B��d�叫�R�v�i�N�������ē����������n�𗧂Ă�A�����킪�d�叫�R����̂݁j�̈�������āA���������������B
���̎��̑O���́u�R���H���B�[�A��R�c���y�z�v�i�R�����H�����B�[���A��R�͏c���ɒy���z��v�ł���A�����͈��O�ܔN�㌎�A�d���������R�X�q���̓G�R����c�����j���A�g�R�����̍Ō�̕ǂ�˔j�����Ƃ��A�d�������������Ă��������̂ł���B
�d�����͒����ƁA�����h�q��ł����˂đ劈�A�ё͂�������܂����̂ł������B���̂悤�Ȍo�܂����������炱���A�d�����͌�������ё�Γ��ɓ��u�Ƃ��Ă������ԓx��ۂ��A�u��ȁv�Ƃ�т����邱�Ƃ����Ȃ������B�����Ȃ��ɖёɒ������A��Ɍ܋�N�̜I�R��c�Ō��˂��邱�ƂɂȂ�B
���͂��z����
���l���N�O����O���A�ё璆���@�ւ͂��ɉ��͂�n�����B�ݕӂɂ͏\���z�̖ؑ��D�������A�ё͍ŏ��̑D�ɏ��A�������A�C�J�������̑D�A�����ƌӋ��炪��O�̑D�ɏ�肱�B��@���̖ё͏㗬�߂Ȃ����l�������B�u�N�����≩�͂̐��A�V���痈����B�z���C�ɓ���ĕ����A�炸�c�c���͂������Ȃ��H�v�i�����u���i���v�j�B�ё͔������L�ł���A�����������������ڂ��Ă����B�܂��@���̂悢�Ƃ��́A���̏ɉ����������̈�߂��������ރN�Z���������B
�l���N�܌��A�ё璆���@�ւ͐W�@�b�R��i�ߕ��̏��ݒn�֕�������쑑�ɂ��A�����Œ����H���c���Ђ炢���B�������A�铿�A�C�J���A�B�A���T�A����O�A���ۏt�A�����炪�o�Ȃ��A��Z���ԂЂ炩�ꂽ�B��c��̖ё͏�@���ŁA��ʎR�̗������A�������ɒ����d�����������A�S������������c�J�Â̒ʒm���N�������肵���B
���l���N�㌎���`��O���A�������̋@�֏��H���Ő����NJg���c���Ђ炩�ꂽ�B�����̐����Ljψ��i�ёA�������A������A�铿�A�C�J���A�d�^�A���K���j�̂ق��A���������܂ވ�㖼�̒����ψ��A���A����ɉؖk�A�ؓ��A�����A���k�̓}�ƌR���̎�ȐӔC�҂��o�Ȃ����B
�����ʼn���R���Ō�̏������l�����邤���ŁA����I�Ȑ킢�ƂȂ����O�����i���c����A�̊C����A���Ð���j�Ɨg�q�]�n�͍��i����R�͓��k�A�ؖk������������ƁA�g�q�]�������āA�ؓ�A����A���k�ɐi���������A���̐헪�̂Ȃ��ŁA�g�q�]�n�͍��͑傫�ȃJ�x�ł������j�ւ̓����߂����߂��B
�}�����͑O�q�̂悤�Ɍܑ发�L�̕��S�����߂Ă���A�S���̌R���w���͖ё��������̕⍲�čs�����ƂɂȂ��Ă����B�������A���̂Ƃ��͖ё͂������ӂ�������B�u���܂�Ō�̌���̒i�K�ɂȂ����B�킢�͂��悢��傫���Ȃ�A�S���S�ǂɂ�������푈�ɂȂ��Ă����B����l�Ō��肷��킯�ɂ͂����Ȃ��B�d��Ȉӎv����͏W�c�Ō������Č��肵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�B�������ď��L���͖�����c���Ђ炭���ƂɂȂ����B�����ł̖ё͏W�c�w���̒��Ƃ��Ă����ւ�I�ł���A�ӔN�̓ƍقƑΏƓI�ł���B
�O��Ŏd�����s���A���ɖ��邱�Ƃ͖ё̒��N�̏K���ł��炽�߂ɂ����B�����ő��̏��L�������ё̏K���ɍ��킹�āA��^�ɂ��邱�ƂɂȂ����B蟖k��]�킵�������͎������A�C�J�����ёɍ��킹�Ė�^�ɂȂ��Ă������A����͎铿�Ɨ����������ɂ����������B
�铿���i�߂͒��N���A���Q���N���̏K��������Ă���A���Z���ɂ͏A�Q���A�����ɋN�����A�U���⑾�Ɍ������K���ł��������A���łɊҗ�������Ă������̘V�i�߂���^�ɂ��炽�߂��B�ё��C�Â����Ă��킭�u���i�߂�A���Ȃ��͍������A�����x��łق����v�B�铿�������Ă��킭�u�厖�Ȏ����B���ǂ��Ă��Q�����v�B�Ƃ͂����A��c������������܂Ői����A�铿�͂������肱�������邱�Ƃ����������B
�C�J���͍������Ȃ̂ŁA�ߓx�ɋْ�����Ɠ�������ށB�֎q�ɂ�肩�����Ėڂ���Ă����B�ёA������A�������͌��C�ɂ��ӂ�A�Ƃ�킯�������͌R���ψ���Q�d���Ƃ��āA�ё�⍲�������w�������B�钆�ё̂��𗣂ꂸ�A���͊O���A�؋���A�������A�V����`�Ȃǂ̎d�����ʂɏ��������B�������̐��͓I�Ȏd���Ԃ�A�����\���̍����ɂ݂͂Ȃ��������ꂽ�B
������{�ŎO�����̏���
���k�n�������������c������n�܂�ƁA���������ْ������B�ё͂����Ŕ�}�ȋC鮂��������B��͋яB�U���ł���B�яB�U���͏����̕��͂ňꋓ�Ɏl�Z���̑�R�Ɛ키�`�ł���A�e�ՂɌ��f���ɂ��������B
�ё͍����}�̑�R��ɂ��邾���łȂ��A�ѕV�̈٘_�����������Ȃ���Ȃ�Ȃ������B�ѕV�͌R���ɗL�\�ŁA�ёɖʂƂނ����Ĉ٘_�������邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ������B���������ԓx�������_�ŁA�d�����ƗѕV�͓ˏo���Ă����B�����炱���ё͗ѕV��M�����Ă����̂��Ɨ��⋴�͏،�����B
�яB�U���̏ꍇ�A�ѕV�͋ѐ����c�z�̓G�ɋ��������̂����ꂽ�B�����ς瓌�k���ɂ�����헪�I�ϓ_����A�k�����֒nj���������e�Ղ��Ɣ��f���Ă����B�������ё͑S���I�헪��������l���A�֊O�̓G���֓��ɂ���Ă͂Ȃ�ʂƌ��ӂ��Ă����B�ё͒P�Ȃ鏟���킳�ł͂Ȃ��A�O�㖢���̑�r�Ő���l���Ă����B�ё͏\���ʂ̓d���ł��ėѕV��������A���t��P�ނ��Ėk�J����쉺���A�яB���U�����A���k�̓G��S�ł���悤�w�������B
������A�ё����ڂ�������ɏ݂��ׂĂ����B�Ӊ���c�z�ɔ��ł����A�����Ȃ�Ƃ����̏����ɓW�]�������Ă����B��������������Ă����B�Ӊ������Ƃ���A�킢�₷���Ȃ�B�����f�^�����w������邩��ˁB�܂��Ȃ��яB����̃j���[�X���Ƃǂ����B
���c������n�߂��Ƃ��A������̑厖�͍����}�ؖk�n��̐ӔC�ҁE����`�̏\�����̑�R�ł������B�Ӊ���c�z�֔��œ�����r���A����`�ɋً}�ɂ����āA���k�x���𖽗߂����B����`�͊֊O�֏o�邱�Ƃ�]�܂��A�u鰂��͂������~���v�̎����l���A�ΉƑ���������͂�ŁA�c�z���~�����Ƃ����B�����R�͖k���ȓ삩��ΉƑ��܂Ŏ�͕��������Ȃ��̂ɑ��āA����`�̋R�������͍s���̐v���Ȃ��Ƃŋ����Ă����B�������͟������ƒ����x�q�c�����̂Ђ��������������R������h�����Čx�������A�ёƓ}�����̈��S��}��ƂƂ��ɁA�����e�@�ւ̑a�J���v�悵���B
�ё͂����ŐV�؎Ђ̂��߂ɕ]�_�������ă��[���A������ɘ���`�Ɍx�������B�u�����͂��łɏ\���ȏ������o���Ă��邩��A���Ȃ����i�ΉƑ��Ɂj����Ă��Ă�����Ƃ���͂Ȃ��B��͂���������^�ʖڂɍl���������悢�v�B���̕�����������`�͖k������̂��S�z�ɂȂ�A�ے蒓�Ԃ̕����܂Ŗk���Ɉڂ����B
�������Ĉ�т̕]�_�Ř���`�̑�R�����ނ����ё́A���Ƃ̂ق���@���ŋ����w���v�x���Γ��a��ł��Ȃ����B�u��܂��ɏ�O����R�i���ς�ɁA�����܂���O�̗������B�Պ��͂��߂��A�c�͋�Ȃ�B�����͎i�n�̔����镺�Ȃ��c�c�v�B���Ȃ肨���ƁA���x�́w�O�ڊ��I�x�̏������̒i�ł���B�u��͂��Ɖ痳���ɂ��肵���c�c�v
���c����������ɂ����A�c�z��������ꂽ��A�����͏j�t�����������A�ё͑傢�����̌�͎��g�́u�g�ē��v�����ׂĔ]���X�ɉh�{��₤�̂���ł������B���̖�͂ق��Ƀr�[�t�����Ǝ_���u�����A�R���͂̋��A�x�q���m�̑������������������B
���c����A�̊C������畽�Ð���܂Ŏl�J���]��A�����͖ё̓�Z���đ��炸�̎������ʼn߂����A�O�������w�������̂ł������B
�����ё͌܌܍A�g�̂͑s���Ŕ��͍��X�Ƃ��Ă����B�ё͔����Ƃ����͈̂��̈��Ō��t�z���悭���A��J���Ƃ�Ƃ������Ƃŗ��⋴���Ƃ������Ƃ���ƁA��{�̔����ɋC�Â����B���⋴�������łʂ��܂����ƕ��������ƁA���S���X�ƁA�������͂����߂Ăʂ��B������ዾ�z���ɒ��߂��ё̈ꌾ�B�u������{�ŁA�O�����̏����Ƃ́I�@���������ȁv�B
�P�D �ё̌Γ실�a���^��
�w�ёW�v����ѓ��w�⊪�x�i�����ЁA �P�X�W�R�`86�N�B�ȉ��w�ѕ⊪�x �Ɨ��́j�̕ʊ��u�ё���N�\�v���Ђ��ǂ��ƁC 1919�N����20�N�ɂ����āC�ё�ᨌn�R���̌Γ�ȓR�C�Ȓ����h�Ă̒Ǖ��^���ɔM�������o�܂��悭������B�ёƐV���w��C�Γ�w��������Ȃǂ̉^��������t���āC�Q�O�N�U���C���h�Ă͌Γ������C�u�쒣�^���v�͐��������i�w���C�x���j�����C��������j�Q�Łj�B
���̉^���̂Ȃ��ŁC�ё́u�Γ�����v���N���C�u�Γ쎩���v�u�Γ샂�������`�v�C�����āu�Γ실�a���̌��݁v�������C�ϋɓI�ɉ^����g�D�����B���Ƃ��Ζё́u�Γ����������v�̖��Łu�Γ����������N�錾�v���N�����āC��C�́w�\��x�i1920�N�U��14���t�j���C�w��������x�i���U��15���t�j�ɔ��\���Ă��� �i�w�ѕ⊪�x �X���C�X�V�`99�Łj�B
���œ��N�V�������u�����x�i�U������тV���t�j�ɂ́C�u�Γ����������v�̖��ŏ������u�Γ�����̎咣�v���f�������C���̈�߂ɂ����q�ׂĂ���B�u�����l��N���̐����͂��ׂċ�ˎq�́C��K�͂ȁC����@�ł������B���̌��ʁC�O�͋��������͊�����сC��͎������C���͋��C�O�ʂ͓��X�Ƃ����h�����C���͖������s���B�����ȗ��C���m�̐l�����@�C����C�哝�̐��C���t���Ƒ呛�����Ă������C���̌��ʂ͂܂��܂��f�^�����ɂȂ�̂݁B����̘O�t�Ɏ��āC�����̊�����҂������Ă��łɓ|��Ă���v�i�w�ѕ⊪�x�P���C199�Łj�B
�ё͂����ŌΓ�Ȃ̐l��3000���͖����ېV�����̓��{�̐l���Ɠ����ł���C�u�[���̖M�v���{�Ɋw�сC�Γ�����Ɏ��g�ނ悤�Ăт����C�����̑��`�́u������`�v�C���`�͖�����`���Ƃ��Ă����B
�����w�����x�i���N�X���R���t�j�ł́u�Γ실�a���v�̌��݂��Ăт����Ă���B
�u���͑咆�ؖ����ɔ����C�Γ실�a�����咣����B�Ȃ����B�ȑO�́C����̐��E�Ő������Ă�����̂͑卑�Ƃ��Ƃ���T�_���������B���̗��łɂ���Ē鍑��`���g�債�C�����̎㏬������}���C�C�O�ɐA���n�𑈂��C���J������z�ꉻ���Ă����B�����ȗ�́C�p�E�āE�ƁE���E�I�E�I�[�X�g���A�ł���B�ނ�͍K���ɂ������������C���͐��ʂȂ������ł������B�ق��ɒ��������̗�Ɋ܂܂�邪�C������͐��ʂȂ������ɂ��������Ă��Ȃ��B�����������̂́C���F�l�����ł����C�����S���l�C��l�C�`�x�b�g�l���C���������炵�߁C�P�W�Ȃ����`�����`���ɂ��C�R�̐��{�����C�R�̍�������C�Q�O�ȏ�̓R���C���g���C���i�߉������C�V�S���͓��X�E����C���Y��D���C�O�͎R�̔@���ł���B���a�������̂��Ă�����̂́C���a�Ƃ͉������������Ă��鍑���͂���������Ȃ��B�S���l�C���Ȃ��Ƃ��R��9000���l�͎莆���������C�V����ǂ߂��C�S���ɂP�{����Ƃ����O�̓S�����Ȃ��v�u�X�N�Ԃ̓��a�̑�헐�̌o����ʂ��āC�S���̑����݂͓��ʂ͊��S�Ɋ�]�̂Ȃ����Ƃ����������B�ŗǂ̕��@�͑����݂������ς�f�O���邱�Ƃł���B�v�����ĕ����C�e�Ȃ̕����݂�}�邱�Ƃł���B�Q�Q�ȁC�R����C�Q�̔˒n�C���v27�n�����e�Ȑl���̎�����`�����s���邱�Ƃ��B�ŗǂ�27���ɕ����邱�Ƃł���v�u�Γ�͂ǂ����B3000���l��l�ЂƂ肪�o�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�Γ�l�ɂ��ʂ̓��͂Ȃ��B�B��̕��@�͌Γ�l�̎��������ł���B�Γ�l�͌Γ�n��ŌΓ실�a�������݂��邱�Ƃł���v�i�w�ѕ⊪�x�P���C217�`218�Łj�B
�����w�����x�i���N�X���U���t�j�ł́u�Γ샂�������`�v���Ăт����Ă���B
�������̒�N�����u�Γ샂�����[��`�v�ɂ��āC �݂�����̎�������邱�ƂɈӂ�p���邱�ƁC���l�̎����ɂ͐�Ɋ����Ȃ����ƁC���l�������̎����Ɋ����邱�Ƃ��ɋ����Ȃ����ƁC�̎O�������Ɖ�����C����Ɂu��Ύ^���v�̈ӂ�\�����Ă���i�w�ѕ⊪�x�P���C223�`224�Łj�B
�����w�����x�i���N�X���U���t����тV���t�j�ł́C�Γ삪�����̗݂��Ă����Ǝw�E���Ă���B
�u���������܂�Ă��̂����C�Γ�͑��݂����B�Â��͔ؒn�ł���C����ɂ͑^���ł������B����ɂ͒������ł���C����ɂ͐ߓx�g�̒n��ł������B�v��͌t�Γ쓹�ł���C����͍s�Ȃ����Ă�ꂽ�B�����͂�����p�����C���̌���ς���Ă��Ȃ��v�u�Γ�̗��j�͂����Í��̗��j�ł���C�Γ�̕����͊D�F�̕����ł͂Ȃ��̂��B����͎l��N���Γ삪�����̗݂��C���R�Ȕ��W�𐋂����Ȃ��������ʂł͂Ȃ��̂��v�u�Γ�l��I�����̎g���͎��ɏd��ł���B�܂��Γ실�a����ڕW�Ƃ��C�V���z���������C�V������n�����C�Q�V�̏������̎句�҂���˂Ȃ�Ȃ��v�i�w�ѕ⊪�x�P���C225�`227�Łj�B
�����w�����x�i���N�X��26���t�j�ł́u�Γ쎩���^���v���Ăт����Ă���B
�����w�����x�i���N�X��30���t�j�ł́u�Ðl���Áv���Ăт����Ă���B�u�Ðl���Áv�̕\���͌��݂́u�`�l���`�v��z�N�����邪�C�O�Ȑl�ł͂Ȃ��u�Ðl�����v���咣����̂́C�u�����v�ɑウ�āu�����v���s�Ȃ����߂��Ƃ��Ă���i�w�ѕ⊪�x�P���C235�`236�Łj�B
�����w�����x�i���N10���R���t�j�ł́u�S�����v���Ăт����Ă���B���Ȃ킿�u�Γ썑�v���咣����̂́C�P�ɌΓ�Ȃ́u�ȁv���u���v�ɕς�����̂ł͂Ȃ��C�u�S�����v���l��������̂ł���B�u�������v�Ŗ������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂��Ǝ咣���Ă���i�w�ѕ⊪�x�P���C 237�Łj�B
�����w�����x�i���N10���T���t����тU���t�j�ł́C�u�Γ쌛�@�v�̐���ɂ�� �u�V�Γ�v�̌��݂��Ăт����Ă���B
�u�Γ쎩���̍��{�@�̋N���ɂ��āC�P�������c�_���s�Ȃ��Ă����B����҂͏Ȑ��{���N������悤�咣���C����҂͏ȋc��N�����ׂ����Ƃ��C����҂͏Ȑ��{�Əȋc��������ċN�����ׂ����Ƃ��C����҂͏Ȑ��{�C�ȋc��C�ȋ����C�Ȕ_��C�ȍH��C�ȏ���C�Γ�ٌ�m����C�Γ�w��������C�Γ�������Ȃǂ��������ċN�����ׂ����Ƃ����B�����̎咣�ɂ����͎^���ł��Ȃ��v�u�����̎咣�́C�Γ�v�����{���Γ�l�����@��c�����W���C�Γ쌛�@�𐧒肵�C�V�Γ�����݂��悤�C�Ƃ������̂ł���B���̎咣���������_�I�ɋ��ʂ�C���ۓI�ɂ����܂�������̂ł���v�i�w�ѕ⊪�x �P���C239�`241�Łj�B
���@����̌Ăт����́C���i�t�C�d�i�����j�C�錕�}�C��������376�l�̘A���ɂ��Ăт����ł���C�ё͂��̂P�l�ɂ����Ȃ����C���̍l�����Ɋ�Â��C�u�Γ�l�����@��c�I���@�̗v�_�v����сu�Γ�l�����@��c�g�D�@�̗v�_�v���N�������̂́C�ёC�d�i�����j�C�������ł������ƁC���������g���Q�N��ɒ����w�����x�i22�N10���X���t�j�ŏ،����Ă���i�Ȃ��C�u�v�_�v�͒����w�����x�i10���W���t�j�ɔ��\����C�̂��w�ѕ⊪�x�X���C103�`105�łɏ����j�B
�Q�D ���ؗ��M���a���\�z
�ё͒������Y�}�̂Q����ɂ́u�J�Ïꏊ��Y�ꂽ���߂ɎQ���ł��Ȃ������v�ƃG�h�K�[�E�X�m�E�Ɍ�����L���ȃG�s�\�[�h�����邪�C ���̑��ō̑����ꂽ�u�������Y�}��Q����錾�v�ɂ́u���M�v�\�z����N����Ă����B�ߔN�̏����J�̂Ȃ��ŁC�����}�j�̊�{�I�������I���W�i�����邢�͂���ɋ߂��`�ŗ��j�����Ƃ��Č��\�����悤�ɂȂ������C���̈�ł���w�������������I�W�x�i�������ĊٕҁC���������}�Z�o�ŎЁC1991�N�j������p���Ă݂悤�B
�i�P�j�����{���e�Ȃł͗��M�����Ƃ�Ȃ��k�����l�{���e�Ȃ́i���R�Ȃ��܂߂āj�o�Ϗ�ɍ��{�I����͐₦�ĂȂ��ɂ�������炸�C�����̗��j��10�N���̕��l�����ɂ���ĉ��o���ꂽ�������ۂ������ďȂ�M�ƂȂ����Ƃ��咣���C�e��������ɔe���ƂȂ��邱�Ƃ������Ēn���������邢�͗��Ȏ����̔����ŏ��낤�Ƃ��Ă���B����͂܂��������R�̂Ȃ����̂ł���B�Ȃ��Ȃ�10�N���C���ׂĂ̐����͊��S�Ɋe�ȕ��l�̎�ɂ���C��������ɕ������咣����Ȃ�C�Ȃ����Ə̂��R�����Ə̂���݂̂����炾�B����䂦�C���M�̌����͒����{���e�Ȃł͍̗p�ł��Ȃ��B
(2)�ÁC�����C�V���͎����M�𑣐i���C���ؗ��M���a��������B�ÁC�����C�V���Ȃǂ̒n���͂����ł͂Ȃ��B�����̒n���͊咎��َ햯�����v�����ڋ����Ă������ł������łȂ��C�o�Ϗ㒆���{���̊e�Ȃƍ��{����قȂ�B�Ƃ����̂́C�����{���̌o�ϐ����͏��_�Ǝ�H�Ƃ��炵�����Ɏ��{��`���Y���ɐi�ޗc�t�Ȏ���ɂ���̂ɑ��āC�ÁC�����C�V���Ȃǂ̒n���͂܂��V�q�̌��n��Ԃɂ���C�����Ē����{���ɓ��ꂷ��Ȃ�C�R���̒n�Ղ��g�傷�錋�ʂƂȂ�C�ÂȂǂ̖��������C�����̐i����j�Q���邩��ł���C�{���l���ɂƂ��Ă��������̗��v�ɂ��Ȃ�Ȃ�����ł���B����ł͌R�����̖͂c������Ƃ�C�����ŕӋ��l���̎���d���C�ÁC�����C�̂R�����M�𑣐i���C���ꂩ��������Ē��ؗ��M���a���ɂȂ��Ă����^�̖����`�I����ł���i��P���C111�Łj�B
�������đ�Q��}���̂V���ڂ���Ȃ�X���[�K���̑�R�`�S���͂����ł������B
(3)�����{���i���R�Ȃ��܂ށj�ꂵ�C�^�̖��勤�a���Ƃ���B
(4)�ÁC�����C�̂R���Ŏ��������s���C���厩���M�Ƃ���B
�i5�j���R���M����p���Ē����{���C�ÁC�����C�ꂵ�C���ؗ��M���a������������i����C115�`116�Łj�B
�ё̌Γ실�a���\�z�ƍ��킹�čl����ƁC�����̒������Y�}�̍l�����́u���M�āv�ł��������Ƃ�������B���V�A�v���Œ�N���ꂽ�������̉�����́C���O�I�C���z�I�Ȍ`�̂܂܂Œ������Y�}�Ɉ����p����Ă����Ƃ݂Ă悢�B
�R�D ���ؗ��M���a������̗��E��
��Q��}���炨�悻10�N��C�ё�͍]���\�r�G�g�ŃQ���������ɏ]�����Ă������C�P�X�R�P�N11���V���C���\�r�G�g��P��S����\���ō̑����ꂽ���\�r�G�g���a�����@��j�i�S17������Ȃ�j�̑�l���́u�\�r�G�g���a���̌����v�̓��e��������߂Ă����B
�u�\�r�G�g�����̈���̘J���ҁC�_���C�g�R���m����т��ׂĂ̘J�����閯�O�Ƃ��̉Ƒ��͒j���C�푰�C �@���ɂ������Ȃ��C�\�r�G�g�@���̑O�ňꗥ�ɕ����ł���C�������\�r�G�g���a�������ł���v�B
�����Łu�푰�v�̊��ʓ��ɋ������Ă���̂́u���C���C�ցC��C���C�c�C�t�C����ђ����ɂ����p�C����C����l�Ȃǁv�ł���B
��14���ł͏��������̎������C���M�ւ̉����E���E���������錾�����B
�u�����\�r�G�g�����͒��������̏��������̎����������F���C�e�㏬�������������痣�E���C���Ȃ��Ɨ��̍��Ƃ𐬗����錠������т��ď��F���Ă����B�ÁC��C���C�c�C�t�C����l�ȂǁC���悻�����n����ɋ��Z����҂́C���S�Ȏ������C���Ȃ킿�����\�r�G�g���M�ɉ������C���邢�͗��E���邩�C���邢�͎��Ȃ̎��������������錠�������B�����\�r�G�g�����͂��܂����̎㏬�������鍑��`�����}�R���C�����C���}�C�y�i�Ȃǂ̈����������犮�S�Ȏ����悤�w�͂��Ă���C�\�r�G�g�����͂����̖����̂Ȃ��ŁC�ނ炪���Ȃ̖��������Ɩ�������W�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�i�w�������������I�W�x��V���C�V�V�R�ŁC775�`776�Łj�B
�����ł́C���M�ւ̉����C���E�������܂߂āC���������̎����������S�ɔF�߂闧��ɗ����Ă������Ƃ�������B
�S�D���Ȃ̎��������Ȃ��Ǘ����錠��
�ё͉�����1943�N�ɊJ���ꂽ���������Z���Z���S��i10��12�`14���j �̕u�V�i�K��_���v�̑�S�́u�S�����̓��ʂ���ً}�C���v�̑�13���u���ؖ�����c�����C��v�Γ�����v�̂Ȃ��ŁC�����q�ׂĂ���B
�G�����łɐi�߂Ă���킪�����́u�e�����������悤�Ƃ����k�v�v�ɑ��āC���ʂ̑��̔C���͊e������c��������̂ƂȂ��C�����œ����ɑΏ����邱�Ƃł���B���̖ړI�̂��߂ɁC�ȉ��̊e�_�ɒ��ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
���C�ցC��C���C�c�C�i�P���m�ւ�ɗw�̃c�N���j�k�̂�����ƕ\�L�l�C�C�Ԋe�����Ɗ����������̌����������C�����œ��{�ɑ��錴���̂��ƂŁC���Ȃ̎��������Ȃ��Ǘ����錠���������C�����Ɋ����Ɨ������ē��ꂵ�����Ƃ��������邱�Ƃ������B
���ɁC�e���������Ɗ������G������n���ł́C���n�̐��{�͓��n�̏��������̐l������Ȃ�ψ����ݒu���C�Ȍ����{�̈ꕔ��Ƃ��āC�ނ�Ɗւ��̂��鎖�����Ǘ����C�e���Ԃ̊W�߂��C�Ȍ����{�ψ��̂Ȃ��ɔނ�̈ʒu����������ׂ��ł���B
��O�ɁC�e���������̕����C�@���C�K���d���C�ނ�Ɋ���⊿�����w�Ԃ悤�������Ȃ������łȂ��C�ނ炪�e���݂�����̌��ꕶ����p������������W������悤�^�����ׂ��ł���B
��l�ɁC���݂��Ă���势����`�����C���l�������ȑԓx��p���Ċe���ƐڐG���C�������ɐe�P�𖧐ڂɂ��C�����ɔނ�ɑ��ĕ��J�I�C�y�̓I�Ȍ���C�����C�s�����֎~����悤����i�w�ёW�x�U���C�����ЁC1983�N�C219�`220�Łj �B
�T�D 蝊ÔJ�Ӌ掞��
1941�N�C蝊ÔJ�Ӌ�{���j�̂ł́C���������̌����Ɉˋ����āu�։��̎�����v������������j�ցC��ނ������Ɍ��������C�ё͎l�ܔN�ɂ͎��̂悤�ɁC�����R�̖����u�������v���Ċm�F���Ă���B
�ё͑�V��}���Łu�������{��_���v�Ƒ肵�����s�Ȃ������i1945�N�S��12���j�C���̎l�́u�������Y�}�̐���v�́u�����̋�̓I�j�́v��X�������������ł����q�ׂĂ���B
�����}���l���W�c�͒����ɑ����������݂��邱�Ƃ�۔F���C�ցC��C���C�R�i�j�C�c�C��k�P���m���牤�ɕω��l�C�e�����������u�@���v�Ə̂��Ă���B�ނ�͊e���������ɑ��Ė������{����іk�m�R���̔�����������S�Ɍp�����C������悵�C���炴��Ƃ���Ȃ��ł���B1943�N�̈ɍ������֑��l����j�E���������C1944�N���猻�݂Ɏ���܂ŐV�����������͒���������������ыߔN�̊Ïl��j�E���������Ȃǂ͂��̖��炩�ȏ؋��ł���B����̓t�@�b�V���I�势����`�I�Ȍ���������v�z�ƌ������������ł���C�����R�搶�ɂ܂������w���Ă���B1924�N�ɑ����R�搶�����������������}��P����錾�ł����q�ׂĂ���B�u�����}�̖�����`�ɂ͂Q�̈Ӌ`������B�P�͒����������݂������������߂邱�Ƃł���B�Q�͒����Ǔ��̊e�������ꗥ�ɕ����ł��邱�Ƃ��B�����}�͊����ēA�d�ɂ����錾����B�����ȓ��̊e�����̎����������F����B�鍑��`����ьR���ɔ�����푈�ɏ����������ƁC���R�ȓ��ꂵ�� �i�e���������R�ɗ��������j���ؖ�����g�D����C�Ɓv�B�������Y�}�͑��搶�̂��̖�������Ɋ��S�ɓ��ӂ���B���Y�}���͊e���������̍L�͂Ȑl����O�����̐�����������邽�� �ɕ�������̂�ϋɓI�ɉ������ׂ��ł���B�e���������̍L�͂Ȑl����O���i���O�Ɍq����������ׂĂ̗̑����܂߂āj�C������C�o�Ϗ�C������̉���Ɣ��W�������Ƃ�C���O�̗��v��i�삷�鏭���������g�̌R���𐬗�������悤�������ׂ��ł���B�ނ�̌���C�����C�����C�K���C�@���M�͑��d����Ȃ���Ȃ�Ȃ��i�w�ёW�x�X���C�����ЁC1983�N�C 255�`256�Łj�B
�����ĂV����}�K��ł́C�u�Ɨ��C���R�C����C����C�x���́C�e�v���K���̓����Ɗe�����̎��R�ȗ�������Ȃ�V�����`���M���a������������v�ƋK�肵���B
���̂悤�ɁC�v�����̒������Y�}�́C(1)�����������̏��F�C�i2)���M���̎��s�C (3)������掩���̎��s�A�Ƃ����O�̎咣���s�Ȃ��Ă����B
�����������Ƃ͊e���������Ȃ̉^�������肷�錠���������Ƃł���C�����I�p�x���炢���ΓƗ����ł���B���Ȃ킿��}���������}���������玩���ŗ���錠���ł���B�����̒����̏����̂��Ƃł́C�����������Ƃ́C���������̏��������͑势����`�̍��҂Ɨ}���҂���C�����R���ƍ����}�����h���玩�R�ɕ������錠�����Ӗ����Ă����B
���̓_�ɂ��āC�ŋ߂̘_�ҁi�����j �͎��̂悤�ɂ��̈Ӑ}�����߂��Ă���B
�u�킪�}�͈�̖��������̗v�������Ɏx�����Ă����킯�ł͂Ȃ��B�킪�}�͊O���鍑��`�҂����������U���F���C�U���������{�C�U�g���L�X�^���C�X�������a���C�����̔����I��w�l���̓Ɨ������ɂ͒f�łƂ��Ĕ����Ă����v�i�����u�}�̖�����掩������̌`���Ɣ��W���T�v�w������藝�_�_���W�x�C�l���o�ŎЁC1987�N�C�V�V�`79�Łj�B
�������������R���푈���ɂ����āC���������C���M���C������掩���̂R�̕��j�Ɋ�Â��āC1936�N蝊ÔJ�ȗa�C���ɉ������{���������ꂽ�B1941�N�ɂ�蝊ÔJ�Ӌ�Ɉ�Q�̋惌�x���C�����x���̖Ñ��C�̎����������������ꂽ�B
�S�T�N����46�N�ɂ����āC�}�����͓��ÂŖ�����掩���̕��j�����s���������łȂ��C�u�a�������j�́v�̂Ȃ��Łu���������n��ł́C�e�����̕����Ȓn�ʂƂ��̎����������F���Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�ƒ�N�����B�S�V�N�T���P���ɐ����������Î������{�͏ȃ��x���Ƃ��Ē������߂Ă̖��������n���ł������B
![]()
�P�A�P�X�Q�V�N�A�ƏG���w���I�n�ʂ�Ǖ�����A�Q�X�N���������B
�Q�A�P�X�Q�V�D�R���A��T���\�҉�c�ŁA�ё��ƏG�ɂ��w������r�������B
�R�A�P�X�Q�V�N�A�ё��u�Γ�_���^�����@�v������āA�ƏG�ƈӌ��Η��B
�S�A�P�X�Q�X�N�A�ё��A�R�~���e�����̎w�߂ɔ����A�����Ċe�n�Ƀ\�r�G�g�n���n�݁B
�T�A�P�X�Q�X�N�A�ƏG����������A�����O�R�[�X���n�܂�B
�U�A�P�X�R�P�N�A�����O�R�[�X�ɑ����āA�Гe�i�����j�R�[�X���n�܂�B
�@�P�X�R�Q�D�P�O���A�J�s�i�˂��Ɓj��c�ŁA�������h���A�ё�O��ᔻ���A�R�����D����B
�@���傤�]�ŁA�����R�������}�R�ɎS�s����B�ё̕��A���v�������B
�V�A�P�X�R�T�D�P���A���`��c�ŁA�ё��w�������m���B
�W�A����������n���Ǐ��L�A�����Ǐ��L�A�ؒ��Ǐ��L�����C���A�}�����̏����ɓ�����A�}�������y�ѓ}���ɂ��Ę_�����̂́A��Ƃ��āA�P�X�Q�W�N����R�V�N�Ɋ|���Ă̑�����v���푈�̎���ł������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�y��1��}���z
�@
1921�N7��23������31���܂ŁA�������Y�}�͏�C�ő�1��}�����J���A�}�������ɐ����������Ƃ�錾�����B�o�Ȃ�����\�͖ёA���f�t�A���K���A���K�H�A���B�A�����r�A���m�ÁA����?Z�A���s���A?������A�����A�����C��12�l�B�ނ�͑S����50�����̓}�����\���Ă����B
�@
���́A���ʂ̐�����͂��A�}�̊�{�I�C���̓v�����^���A�ƍق̂��߂ɓ������Ƃł��邪�A���ʂ̓u���W���A�����`�v���ւ̎Q�����v�����^���A�[�g�ɌĂт����˂Ȃ�Ȃ����Ƃ��m�F���ꂽ�B�}�̑g�D�ɂ��ẮA���V�A�̃{���V�F�r�L�}��͔͂Ƃ��邱�Ƃ����肳�ꂽ�B
�@
���́A�������Y�}�́w���j�́x�Ɓw��ꌈ�c�x���̑����A�������Y�}�̐�����鍐�����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�y��2��}���z
�@
1922�N7��16������23���܂ŁA�}�͏�C�ő�2��}�����J�����B�o�Ȃ�����\�́A12�l�ŁA�}��195�l���\���Ă����B�ƏG����c����ɂ����B
�@
���͒ƏG�A����?��A��a�X�A����?Z�A���N�F�𒆉��ψ��ɑI�o���A�ƏG���������s�ψ����ƂȂ����B���͕��A�w����}���錾�x�\�����B
�@
���́A�����v�����K�i�ɕ����čs���悤�w�������B�����ߑ�j��͂��߂āA�鍑��`�ƕ�����`�ɓO��I�ɔ����閯���`�v���̍j�̂��N�����B����͒����v���ɑ��A�傫�ȈӋ`�������̂ł������B
�@
���������̑��ł́A�����`�v���̒��ɂ�����v�����^���A�K���̎w�����̖���A�����`�v���ƎЉ��`�v���Ƃ̊W�ɑ��ĔF�����܂��\���łȂ������B�܂��A�J�_������_���̓y�n����O��I�ɉ������邱�ƁA����јJ�_��������������Ȃǂ̖��ɑ��Ă��A�F�����Ȃ������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�y��3��}���z
�@
1923�N6��12������20���܂ŁA�}�͍L�B�ő�R��}�����J�����B�o�Ȃ�����\��30���l�A���̂�����\���������̂�19�l�ŁA420�l�̓}�����\���Ă����B�ƏG��������ɂ����B
�@
���̒��S�I�c��́A�S�Ă̋��Y�}����J���҂������}�ɎQ�����邩�ǂ����������B���_�̒��ő����̑�\�́A�����}�Ƃ̍���ɐϋɓI�łȂ�����?Z��̌�����ӌ���ᔻ����ƂƂ��ɁA
�R�~���e�����̒������ݑ�\�̃}�[������ƏG����N�����w���ׂĊ����������}�ɋA���x�Ƃ����E���I�Ȋϓ_�ɂ��^�����Ȃ������B
�@
�ŏI�I�ɑ��́A���Y�}�����l�̎��i�ō����}�ɉ������A����ɂ���Ė���I�Ȋe�K���̓����������グ�A�����ɋ��Y�}���g�D�I�ɂ������I�ɂ��Ɨ�����ۂ��Ƃ����肵���B
�@
����9���̐����ψ��A5�l�̌��ψ�����Ȃ�V�����������s�ψ����I�o�����B�������s�ψ���́A�ƏG�A�ёA���͗��A��a�X�A杕��R�̂T�l����Ȃ钆���ǂ�I�o���A�ƏG���ψ����A�ё��鏑�ɁA���͗�����v�ɔC����ꂽ�B
�@
���͊v���̓������̕��j�Ɛ�����m�肵�āA��������̌`���𑣂������A�v�����^���A�K���̎w�����̖���_�����A�R�̖��ɂ��āA�\���d�����Ă͂��Ȃ������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�y��4��}���z
�@
1925�N1��11������22���܂ŁA�������Y�}�͑�4��}������C�ŊJ�����B�o�Ȃ�����\��20�l��994�l�̓}�����\���Ă����B
�@
���̒��S�I�c��́A�����Ƃɍ��܂�v���^���ɑ��A�}���ǂ̂悤�Ɏw�����������邩�A�����Đ�`�H��A�g�D�H��A��O�H��̖ʂɂ����đ�v���̍��܂���}���鏀�����ǂ̂悤�ɍs�����A�ł������B�ƏG����c����ɂ����B
�@
���́A�O�N�T���̒����g���c���s�����}�H��̒��́A�E�̌��ɑ���ᔻ���m�肵�A���߂Ē������Y�}�������}�ƍ��삷�邱�ƁA�J���^���A�_���^���ȂǂɊւ��������̕��j���߁A�v�����^���A�K���̎w�����ƘJ�_�����̏d�v�����w�E�����B
�@
���͒ƏG�A����?���14�l�ɂ��V�����������s�ψ����I�o�����B�����ĊJ���ꂽ�������s�ψ���ŁA�ƏG�����������L�ɑI�o����A�ƏG�A�d�q�V�A����?Z�A��a�X�A�؏H���̂T�l����Ȃ钆���ǂ��g�D���ꂽ�B
�@
���̑��̎�v�Ȍ��ׂ́A�w�����̖����N�����ɂ�������炸�A�w�������ǂ̂悤�Ɋl�����邩�ɂ��āA��̓I�Ŗ��m�ȕ��j�Ɍ����A��O�^���ɑ���w����������_���āA�����ƕ����͂ɑ���w���������S�ɖ��������Ƃ���ɂ���B�_�����v���̓����R�ł��邱�Ƃ��N���Ă��̂́A�y�n�v���������_��������������Ƃ������{�v�z���N�ł��Ȃ������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�y��5��}���z
�@
1927�N4��27������5��9���܂ŁA�}�͑�5��}�����ŊJ�����B�o�Ȃ�����\��80�]�l�A5��7900�]�l�̓}�����\���Ă����B
�@
���̎�ȔC���́A�R�~���e�������s�ψ����7��g���c�ɂ����钆�����Ɋւ��錈�c�Ă�����A�ƏG�̓��a����`�̌������āA�}�̏d��ȕ��j�Ɛ�������肷�邱�Ƃł������B�ƏG���J��������ɂ����B
�@
���ł́A��\�������ƏG�̉E���̓��~��`�ɑ��Ĉ��̔ᔻ���s�����B��a�X�́u�v�����^���A�K���̐��}�������A�v����O��I�Ɏw�����A�������������鎖���ł���v�Ɣ������A�ё́A�ƏG�̔_���̖��Ɋւ������ᔻ���A�_����g�D���A���������A�_���̓�����v���ɋ������邱�ƂƎ咣�����B
�@
����29�l�̐V���������ψ����I�o���A���ɑ����ĊJ���ꂽ�ꒆ�S��ŁA�ƏG��V�l�̒��������Ljψ��A��������S�l�̐����nj��ψ���I�o�A����ɒƏG�A����?Z�A��a�X�A�؏H���̂S�l�𐭎��Ǐ햱�ψ��ɁA�ƏG���L�ɁA��������鏑���ɑI�B
�@
���̑��́A�ƏG�̉E���I�Ȍ���ᔻ�������̂́A�����̍����}�ƍ������{�̉����A�v�������͂ɑ���}�̎w����g�D���A�g�傷�邱�ƂȂǁA�v���̎w�����D��̂��߂ɉ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��ؔ������d����ɑ��āA���ۓI�ɓ������o�����Ƃ��ł��Ȃ������B�ƏG�̉E���I�ȓ��~��`�̖{���Ɗ�Q�ɑ��Ă��A�[���F���Ɍ����Ă����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�y��6��}���z
�@
1928�N6��18������7��11���܂ŁA��6��}�����X�N���ŊJ���ꂽ�B�o�Ȃ�����\��142�l�������B
�@
��c�͐����A�R���A�g�D�A�y�n���A�_�����ƘJ���^���Ɋւ���14���ڂ̌��c���̑������B�����̌��c�́u�����Љ�̐����͈ˑR�Ƃ��Ĕ��A���n�A�������̎Љ�ł���A���i�K�ɂ����钆���v���̐����́A�u���W���A�����`�v���ł���B���݂̐�����́A�v���̍������ƍ������̒J�Ԃɂ���A�}�̑S�̓I�C���͐i���ł͂Ȃ��A��O���l�����A�\�����������邱�Ƃł���v�Ǝw�E�����B
�@
��c�͂܂������v���̌��i�K�ɂ�����\�吭���j�̂𐧒肵���B���̍j�̂ł́A�}�̌��݁A�J���^���A�_���̉^���A�g�R�A�����n�̌��݂ɂ��Ă̊e���̐���𐧒肵�A"��"�ƉE�̓��a����`�̌��A�Ƃ��ɖӖڎ�`�̌���ᔻ�����B
�@
��c�͂܂��A�ψ�23�l�A���ψ�13�l����Ȃ钆���ψ����I�o�����B�����Ē��������Ǐ햱�ψ���͌������A��������W�l�ō\������A��ȂɌ��������I�ꂽ�B
�@
���̑����肵���H���͊�{�I�ɐ������A��̒����v���̔��W�ɑ��ĐϋɓI�Ȗ������ʂ������B���������ׂ��������B�������Y�K���̖����┽�����͓����̖����ɑ��Đ����������Ɛ���Ɍ����Ă����B�Ƃ��ɒ����v���̒������Ɣ_���v�������n�̏d�v�ȈӋ`�ɑ���F�������肸�A�ˑR�Ƃ��ēs�s�H���S�}�̊����̒��S�ɐ������B����́A�����v���̔��W�ɏ��ɓI�ȉe�����y�ڂ����B
�@���ƏG�@����ǂ����イ
�@1879�`1942�����C�����̎v�z�ƁB�������Y�}�����̎w���ҁB���J�ȉ��J���̐l�B���͒���B���͎����B�R�B�������@�C���������t�͊w�Z�Ɋw�сC����V���̔��s�C�x����̑g�D�Ȃǔr���v���^���ɏ]���B���J�s�{�鏑���Ƃ��Đh��v���ɎQ���������C��2�v������{�ɓ��ꂽ�B1915�N�i����4�j��C�Łu�N�G���v�i���N�u�V�N�v�Ɖ��́j��n���B�ᔻ�E���w�v��������V�����^���̊���ƂȂ�C�N�w���ɑ傫�ȉe����^�����B1917�N�i����6�j����͖k����w���Ȋw���Ƃ����ӓK�Ȃǐi���I�l�ނ����W���邪�C1919�N�i����8�j�ߕߓ������ꎫ�C�B��C�ŋ��Y�}�̑g�D�ɒ��肵�C1921�N�i����10�j�̑n�����ł͑����L�ɑI��C�Ȍ�}�̍ō��w���҂ƂȂ����B��������Ȍ�̓R�~���e�����̎w���ɂ��C�E�X�����鍑���}�Ƃ̒�g�ێ��ɂƂ߂����߁C1927�N�i����16�j�E�����a����`�҂Ɣᔻ����C1929�N�i����18�j�g���c�L�X�g�Ƃ��ē}���������ꂽ�B1932�N�i����21�j�����}�ɑߕ߂���C1937�N�i����26�j�Ɏߕ��B1942�N�i����31�j�l��Ȃŕa�������B
�@�@
������(1873�`1928)
�ɔJ�ȊC��̐l�B�n�����g���N�����A���ɋA���B1916�N�ɂ͕�V�R�ƂȂ�A���k��V�R���̎�̂ƂȂ����B1920�N�ɂ͒���h�Ƒg��ŁA���J�h�̒i�Q���𒀂����i�����푈�j�B1922�N�A����h�̑�?�E���Λt��Ƒ�ꎟ�푈�𑈂��A�s�k���ĕ�V�ɑނ��A���k�O�Ȃ̎�����錾�����B1924�N�A��푈���N�����ď������A�i�Q����Վ������ɏA�����B���{�̎x�������āA1927�N�ɂ͖k���ő匳���ƂȂ�B�����}�̖k���R�ɔs��A��V�ւ̋A�H�ɁA���{�R�ɂ���Ԕ��j�̂��ߎ��B
�D�v(1881�`1936)
�{���͎����l�B���͘��ˁB���]�ȏЋ��̐l�B�c���̂���A�Ƃ͖v�����ĕn���������B1902�N�A����œ��{�ɗ��w���āA����w���w�Z�ɓ��邪�A���ށB���w�ɓ]���āA�����ŕ��w�������͂��߂��B�A�����ċ����ŋ��������Ă������A�h��v����ɖk���ɈڏZ�B1918�N�ɏ�����u���l���L�v�\���Ĉ���L���ƂȂ�A�����E���E�]�_�E�|��Ȃǂ̒��슈���Ŋ����B�w���p���`�x�A�w���������j���x�ȂǑ����B
�ӊ���(1886�`1936)
���͓W���B�L���Ȕ��[�̐l�B1902�N�A���{�ɗ��w���A�@����w�ɓ������B1905�N�A����������̌����ɎQ�����A�]�c���E���s�����L�ƂȂ�A�w����x�̕ҏW�ɂ��������B1907�N�A�����ɏ]���āA�����E����ւ̖I�N�ɎQ�������B���s��A�V���K�|�[���ɓn��A�w��������x�̎�M�ƂȂ�A������̓�����x�����ƂȂ����B�_��͌��̖��A�L�B�V�R�̖I�N�A���ԛ��̖I�N�ɎQ�������B1911�N�A�h��v�����N����ƁA������čL���ȓs�ƂȂ����B���N�A�싞�Վ����{�̑����{�鏑���ƂȂ����B�������ޔC����ƁA�L���ɋA��A�L���s�E�������B���N�A�͐��M�ɂ���C���ꂽ�B1914�N�A���؊v���}�ɎQ�����A���������ƂȂ�B�G���w�����x�̎�҂��Ƃ߂��B1917�N�A��@�R���{�Ō�ʕ����B1924�N�A�����}���g�Œ������s�ψ��A�L���ȏȒ��B�������k������ƁA�匳���̐E�����s�����B�����̎���ɖK�\�B1927�N�A�싞�������{����������ƁA�������{��ȁB���N�ɂ͍������{���@�@���ɏA�����B1931�N�A���ӂ̒��S�l���Ƃ��ĐE��ǂ�ꂽ�B1933�N�A���`�Łw�O����`�����x��n�������B1936�N�A�L�B�ŕa�v�����B�w���u�W�x�B
��?(1862�`1938)
���͒��X�B����ȓV�Â̐l�B�k�m�����w���𑲋Ƃ����B�͐��M�̖k�m�V�R�ɓ���A��O�������E��O�t�t���ɏ�����B�͂̎���A����R�ƂȂ�A�����Œ���Ȓ��ƂȂ��āA����h�R���̎�̂̒n�ʂ��ł߂��B1920�N�A��V�h�ƌ���ň����i��ᨁj�푈��킢�A���J�h�̒i�Q���𒀂����B1922�N�A��ꎟ�푈�𑈂��A��V�h�̒������𒀂����B���N�A�A�����J�̎x�����A����h�̔e�����m�����A�c�������I���i�d�I�j���s���A�k�����{�̑呍���̒n�ʂɏA�����B���@�����z�����B1924�N�A��푈���N����A���̂Ƃ��g�ʏ˂ɓ�ւ���A�����O�p�����ɔs��Ď��r�B�̂��V�ÂɉB�ނ��A���̒n�Ŗv�����B
���ЋV(1860�`1938)
���͏���B�L���ȍ��R�̐l�B1874�N�A����ŕĂɗ��w���A�R�����r�A��w�Ɋw�B�A����A�V�ÂŐŖ��ɖ�ɂƂ߁A�܂����N�ɔh�����ꂽ�B�͐��M�̒m���āA�ÊC�֓��E�O�����E���Y�E�����S�H���E�X�B�������Y�E��V�����Ȃǂ��C�����B�h��v���̂Ƃ��A�͐��M���t�̑S����\�Ƃ��Čޒ�F�Ə�C�Œk�����A��k�u�a�����B1912�N�A�͐��M�呍���̂��Ɠ��t�������Ƃ߁A����������ɂ����������B�͂������̐E����N�����̂ŁA���S���Ď��C�B�͂ƑΗ����đ����ƌ��B1917�N�A��@�R���{�ɎQ�����A���������B1919�N�A����R���{����\�Ƃ��āA�k�����{�Ƙa�c�k�������B�̂����E�����ށB1931�N�����}���{�ψ��ƂȂ�A��C�ɏZ�B����h�̗v�l�Ƃ��Ċ������A�Ӊ�ƑΗ����č����}�����ɂ��ÎE���ꂽ�B
���Λt(1872�`1939)
���͎q�ʁB�R���ȖH���̐l�B�ے�R���w�Z�Ɋw�ԁB�g�����̎���A�k�m�R������h�̋����B1920�N�A��V�h�ƌ���ň����i��ᨁj�푈��킢�A���J�h�̒i�Q���𒀂����B1922�N�A��V�h�̒������Ƒ�ꎟ�푈�𑈂��A���������B���N�A����h�̔e�����m�����āA��?�ɑ呍���̒n�ʂɏA�������B���̂��ƂŒ��D�����{�g�ƂȂ�B1924�N��푈�ɔs��āA�����v���R�ɌΓ�E�Ζk��N����āA���r�����B�����푈�ł͓��{�R�ɋ��͂��A1939�N�ɗՎ����{�V���ψ��ƂȂ������A�a���B
������(1855�`1939)
���͖m�܁A���͋e�l�B����ȓV�Â̐l�B1879�N�A�͐��M�ƒm�荇���A���̉������ď㋞�����B1886�N�A�i�m�ɋy�悵���B�˗щ@�ҏC�ɔC�����A���j�ً��C�E���p�a���C�Ȃǂ��Ƃ߂��B�����푈�̂Ƃ��A�͐��M�̖����ɓ����ČR���ɂ����B�͐��M�̖k�m�R�������������A���̖d�m�ƂȂ����B1903�N�A���t�w�m�E�������ƂȂ�B���N�A���������Y�ƂȂ�A�R�@��b�E���x�������ɔC�����A�܂��Ȃ������������ɂ������B1907�N�A���O�ȑ��ƂȂ�B1911�N�A�������E�Q�d�����ɏ�����B����������A1914�N�ɖk�m���{�̍��������ƂȂ�B1918�N�ɑ呍���ɑI��A�k�m�R���̑Η��ɘa��}�������A���s�����B1922�N�A��ꎟ�푈�ŕ�V�R���s�ꂽ���߁A���E��ނ����B�V�ÂɉB�����A1939�N�ɕa�������B�w����w�āx�A�w�吴�E���N�x�B
�K����(1887�`1939)
���͒��G�A�܂��͓����A���͋^�ÁB���]�Ȍ����̐l�B1906�N�ɗ������đ���c��w�Ɋw�B����������ɎQ�������B�w���������x���������A1914�N�ɂ͖k����w�����ƂȂ����B������̃��[�}�����E��������̕��y���͂������B�܂�����́w�Îj�فx�̕Ҏ[�A�w�V�N�x�̕ҏW�������A���w�v���̐��i�Ɍ��т��c�����B
��|(1868�`1940)
���͒ߋ��A�̂��ɛr���B���]�ȏЋ��̐l�B1892�N�ɐi�m�ɋy�悵�A�͂��ߊ˗щ@�ɓ��������A����̐V���̎��s�����Ď��E�B�A�����ĐV������ɐs�͂����B����������g�D���āA���̉�ƂȂ�B1905�N�A�����v��������ɉ������A��C����ƂȂ����B1907�N�A�Ƃɗ��w�B�h��v����ɋA�����A1912�N�ɂ͋��瑍���B�͐��M�̓ƍقɔ����Ď��E�����B1916�N�ɂ͖k����w�w���ƂȂ�A�ƏG�E�ӓK����}���Ď��R�����̊w���������B���b�^���ɂ��͂���ꂽ�B�������{���ƍق����߂�ƁA����E����ނ��A���������@���ƂȂ����B�����V�����̕��Ƃ����B�w�����ϗ��w�j�x�B
�ƏG(1879�`1942)
���Ƃ̖��͊����B���͒���A���͓ˈ��B���J�ȉ��J�̐l�B�ȋ��������ĐV�w�ɑł����݁A���E���ɗ��w�����B�̋��̈��J�ȂŐh��v���ɎQ���B1915�N��C�Łw�N�G���x��n�����Ď�ɂ��A���N�w�V�N�x�Ɖ��肵���B�V�����^���̊���ƂȂ����B1917�N����k����w�����A�����ȕ����B�ӓK��ƕ��w�v������āA���b�^�����句�B�܁E�l�^�����w�������B1921�N�������Y�}�̌����ɎQ���B�}�����ϑ����L�ƂȂ�B��������ɂ͔ᔻ�I���������A�R�~���e�����̎w���ł���𐄐i�B�}���͊g�債���B1927�N�ɂ́A�����N�[�f�^�[�̐ӔC��Njy����A�E�����a����`�҂Ɣᔻ���ꂽ�B�Ȍ�A�X�^�[������ᔻ���āA�g���c�L�Y���ɌX�����B1929�N�ɋ��Y�}���������ꂽ�B1932�N�������{�ɑߕ߂���A�̂��ߕ����ꂽ���ǓƂ̂����ɕa�v�����B
�g�ʏ�(1880�`1948)
�������́B���J�ȑ����̐l�B����Ȑ��ɐ��܂ꂽ�B��������̌R�ɎQ���B�����̌R�����Ƃ߂��B�h��v���ł͖I�N�R�̎Q�d�����Ƃ߂��B�̂��A�͐��M�Ɍ��o����ČR�E��ݐi�B�͂̎���́A����h�ɑ����ē]�킵���B��\��t�t���E蟐��R�E�͓�R�E���R���{�g�E���n��O�H�R���i�߂Ȃǂ��C�����B1924�N�A��푈�̂Ƃ��A�ӌi����ƂƂ��ɖk�����̂��āA����h��Ǖ��B�����R���i�߁E���R�R���ƂȂ����B1926�N�A����A���R�ɔs��ĉ���B���X�N���֍s���A�A����ɍ����}�ɉ��������B���k�R�𗦂��A�k���ɎQ�������B�����v���R���W�c�R���i�߂ƂȂ����B�����A�s���@���@���E�R���������ƂȂ����B1929�N�A�Ӊ�Ɣ��ڂ��ċ~���R���i�߂ƂȂ�A���Ӑ푈���N�����č����}�����Ђ��ꂽ�B���N�A腎��R�ƘA�����čĂє��Ӑ푈���N���������A�������ɔs��ĉ��삵���B���F���ό�ɓ싞�ɖ߂�A�}�Ђ��B�R�����咣�������ӂɗe����Ȃ������B1933�N�A�@�V���O�R�������R�̑��i�߂ƂȂ邪�A�ӂ̝y�I�������ߑR�ɉB�������B1937�N�ɍR���푈���J�n�����ƁA��O���i�ߒ����E��Z���i�ߒ������C�����B�R���푈��́A��������̈ێ����咣���ē���ɔ������B1946�N�ȍ~�A�č��ق��̏����ɊO�V���A�����a�����哯���⍑���}�v���ψ���̌����ɂ���������B1948�N�A���r���ɍ��C�ŋq�D�Ђɑ������Ėv�����B�����̊v���v�z�̉e�����A�܂��L���X�g����M���Ă������߁A�N���X�`�����E�[�l�����Ə̂��ꂽ�B
�A���_�[�\��(1874�`1960)
���̓��n���E�O���i���B�����͈������B�X�E�F�[�f���̐l�B1914�N�A�k���ɂ����蒆���n���������̌ږ�ƂȂ����B1921�N�A�͓��?�r������ŐV�Ί펞��̈�Ղ@���A��ʂ̍ʕ��y��������B�܂��A�k���s�����X�̋��Ί펞���Ղ����A�Y�_���X�L�[��ɔ��@���ς˂Ėk�����l�̔����̂��Ƃ�z�����B��N���܂�������Ċ���E�C�E�����S���E�`�x�b�g�����A��j����̈�Ռ\�]�������B1925�N�A�A�������B�X�g�b�N�z�����̋ɓ������يْ����Ƃ߂��B
腎��R(1883�`1960)
���͕S��B�R���Ȍܑ�̐l�B1904�N�A���{�ɗ��w���A���R�m���w�Z�Ɋw�B���N�A����������ɎQ���B�h��v����A�͐��M�̖��������ĎR���s�ɔC����ꂽ�B�Ȍ�A�R�����Ƃ��ĎR���Ȃ��x�z�B���_����E�h�������������čR���^����W�J�����B���{���~������ƁA�����{����p���āA���Y�}�R�Ɛ�����Ƃ����}�b���c����Ă���B1949�N�A���Y�}�ɔs��đ�p�ɓn�����B�������{�̍s���@���E���h�����Ȃǂ��Ƃ߂��B1952�N�ɌR�E��ނ����B1960�N�A��k�ŕa�v�����B
�����q(1889�`1970)
���͖��n�B�Γ�ȓ����̐l�B1912�N�A�ے�R���w�Z�ɓ��w�B1914�N�A���ƌ�ɌΓ�ÌR�ɑ����A���͂̌썑�푈�ɎQ�������B1923�N���t�z�ɒ��Ԃ��A�ÌR�̍ő���͎҂ɐ���オ�����B�����i���E�Γ�ȑ㗝�Ȓ��ƂȂ�B1926�N�A�����v���R�̑攪�R�R���ƂȂ�A�k���R�̐��H���w���E��l�W�c�R���i�߂Ȃǂ��Ƃ߂��B1929�N�A���Ӑ푈�ɂ����ďӑ��ɂ��A�g�ʏ˂����B�̂��ɟ������ƘA�����A腎��R�ƒʂ��Ĕ��ӑ��ɗ����A��}�~���R���i�߂ƂȂ������A�s��Ĉꎞ���삵���B1932�N����R���Q�c�@�@���E�R���ψ���s����C�Ȃǂ��Ƃ߂��B�R���푈�̂Ƃ��A�싞�q���i�ߒ����ƂȂ������A�싞��ɍۂ��ē��S�����B���펞�ɂ͉B�����Ă����B1949�N�A�Γ�l�����~�ψ����C�ƂȂ�A�V����������A�Γ�Ȑ��{����ȁE���Ȓ��Ȃǂ��Ƃ߂��B1970�N�A�����Ŗv�����B