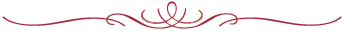
| 別章【レーニン考】 |
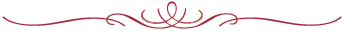
更新日/2020(平成31→5.1栄和改元/栄和2).5.8日
| レーニンについて、ロシア十月革命の第一指導者としての史的地位は定まっているが、ロシア十月革命とレーニンの指導をどのように評すべきか未だ定まっていない。肯定的評価と否定的な評価との間を今も行きつ戻りつしているところであるといえる。れんだいこの見解を述べる前に、どのような評価論が為されているのか羅列整理してみたい。「学べ!学べ!そして学べ!」(出典不明) 2005.11.24日 |
| レーニン論序章 | れんだいこ | 2004/05/06 |
| まーしさんちわぁ。レーニン論をやってみたくなり、こちらに振ります。 > どこかで読みましたが「レーニンは革命を維持するために強力な手段もとらざるを得なかった」。私はそうは思いません、ロシア帝国をレーニン帝国にしようとしただけで正義の旗の下にもっとひどいことをしたと思います。 れんだいこのレーニン理解は、マルクス主義の忠実な実践者として非常に有能な指導者であった、という評価は基本的に変わりません。そのレーニンの限界はどこにあったのかという点での研究こそしてみたいと思っております。その一つが、それまでのマルクス主義の公式的見解であったいわゆる国有化理論を疑問の余地なく信奉しており、革命後愚直なまでにこれを強行的に導入しようとした。しかし、この政策を押し進めれば進めるほど困難に遭遇し、建国革命はぎくしゃくしたものになった。これがレーニン主義の限界その一と考えております。 そのレーニンの偉大なところは、マルクス主義のいわゆる国有化理論的理解の間違いに気づき、ネップ政策で対応しようとしていたところにあります。しかし時既に遅く気づいたときには晩年のレーニンであり、もはや闘う気力に欠けていた。この時期がレーニンの最盛期ならもっと精力的に闘い、違う社会主義実験を見ることができたと思っております。 レーニンのもう一つの欠点は、マルクス主義そのものの欠陥でもあるのですが、ルネサンスの史上の意義を継承し損ねているように思えることです。いわゆるブルジョア民主主義とみなすことで、思想の中で流産させているように思えてなりません。 れんだいこの理解するルネサンス精神とは、「自由、自主、自律」の精神の称揚ということになりますが、これは中世と近世を分かつ大きな指標であり、経済・政治・文化の面で子供から大人への脱皮を遂げたほどに大きな価値があったと認めております。この洗礼を受けた諸国は国力も民力も向上した。受け損ねた諸国は歴史の流れに乗り損ねた、と観ております。これは今日にも見立てることができる指標のように思います。いわゆる議会制民主主義は、この観点から捉え返される必要がある、と思っております。 ところが、マルクス主義は、マルクス段階ではそうでもないのですが、それを受け継いだ後世のマルクス主義者はこのルネサンス精神においてからきし理解を持たなかった。階級闘争史観の押し出しすぎで、むしろ意識的に却下させてしまった。そういう史観の必然的な結果、中世的支配体制を生み出し、下級党員はそれを崇め奉るといういわゆる封建的秩序を良しとしてしまった。 この二点でレーニン主義の限界は認められるものの、運動体の指導者としては比類ない優れた方であると思っております。彼の情況分析力、実践力、課題解決能力は当代随一のものであり、我々は大いに学ぶべきであり、これに比べればトロツキーのそれは書斎的だとさえ考えております。 付言すれば、レーニンは、スターリンとトロツキーの比較で云えば、両者それぞれに欠点が認められるものの、共同戦線組むとすればトロツキーの方だったという史実があるようです。ということは、トロツキーの限界は我慢できるそれで、スターリンのそれは闘う以外になかったそれということになります。ところが、史実は、そういうスターリン派の社会主義が実践されていった。これがマルクス主義運動であったのかなかったのか。その結果どうなったか。 今日では自明です。この自明さを1950年代半ばの頃よりつとに早く指摘していたのが革共同でありブントの皆様でした。この時、日共党中央は、そういう気づき派に対してステレオタイプ的なトロツキズム批判を繰り返し、スターリニズム万歳を説いていた。 このことを何ら自己批判せず、スターリニズム万歳路線が破綻するや、口を拭ったまま科学的社会主義なる手前味噌用語を造語し、得々として語り続けているのが不破を指導者としていただく我が日共指導部です。こったら連中が議会専一主義運動を取り組んできましたが、一時期までは一定の成果を見せていたものの今日でも何ともはやの惨状を呈しております。その敗北責任取ることなく、駄々っ子的な言い訳と方針そのものは何ら間違っていないという居直りで捲土重来を繰り返しております。 あまりに無能過ぎる。全てが馬鹿げている。誰かがこのウソを衝かねばならない。いつしかうねりにせねばならない。この道中を難しく語り続ける者も又同罪。喧々諤々の左派運動ルネサンスを創出せねばならない。形あるものを欲するのではなく、常に流動情況に置き、その重みに耐えられる運動体を突出させていかねばならない。とかいろいろ考えております。思いつくままの乱文ですが意のあるところお汲み取りくだされば幸いです。 2004.5.6日 れんだいこ拝 |
||
![]()
| 目次 | |
| コード№ | 中項目 |
| 革命指導者としてのレーニンの史的地位論、レーニン主義評 | |
| 生涯の概略履歴 | |
| 哲学理論 | |
| 組織論、規約論 | |
| レーニンの「プロレタリア民主主義」 | |
| レーニンの「新経済政策(ネップ)」への転換考 | |
| 帝国主義論 | |
| 右翼日和見主義、社民主義批判論 | |
| 労働組合論 | |
| レーニンの議会論及び利用の観点論 | |
| レーニンの日本及び日本人論、明治維新論 | |
| 各界人士のレーニン評価論 | |
| レーニン著作集年次リスト | |
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)
他方、レーニン主義の特質として、党中央への権限集中制が同居していた。