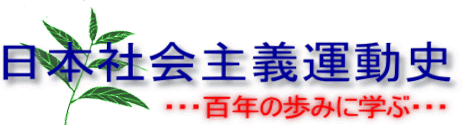
|
�P
�Վ��A�����{�ƃ��C�E�u�����̖���
���P�W�S�W�N�̃t�����X�Q���v���̌o�� |
�@���Y�}�́A�u����v���͂Ƃ̓��������u����A�������v�́A���a�I�A�Q���I�Ɏ��{�̎x�z���@������A�J���҂̗��z�ł���Љ��`�ւ̓����J���Ă����Ǝ����グ�Ă���B�ނ�͂��̂��߂ɘJ���҂̏��u���W���A���͂Ƃ̋����A�Ë���i���Ă����B�ŋ߂ł́A�u���W���A���R��`���͂Ƃ̋���������ł��o���Ă���B�������A���E�̊K�������̗��j�I�o���́A�u����A�������v��������鋤�Y�}�̐�p�������ɔ����I�ł��邩�𖾂炩�ɂ��Ă���B���̘A�ځi�P�Q���\��j�Ő��E�́u����A�������v�̗��j��U�肩����A���̐��i�A�ʂ����Ă����������������悤�B
�������v���ƗՎ����{�̐���������
�@�K�������̗��j�ŁA�u����A�������v�����߂ēT�^�I�Ȍ`�Ō���ꂽ�̂́A�P�W�S�W�N�̃t�����X�̓v���ł������B
�@�v���ȑO�̃t�����X���x�z���Ă����̂́A�u���W���A�W�[�̈�h�ł����s�ƁA��������A�S�����A�Y�z�A�S�z�A�X�т̏��L�ҁA�ނ�ƌ��Ԉꕔ�̒n�����Z�M���ł������B�ނ�́A���C�E�t�B���b�v�������ō��ƍ����Ɋ��ċ������ނ��ڂ��Ă����B�����̑I���@�́A�c��ւ̑I�����i�͔N�Q�O�O�t�����ȏ�̔[�Ŏҁi�Q�O�����̗L���ҁj�Ɍ��肵�Ă������A���{�͂�����\�����b��c���ɑ��Ă͍s����̃|�X�g�◘����^���邱�Ƃɂ���āA���{�x���h���m�ۂ��A���Z�M���̗��v��}�����������s���Ă����B���̂��߁A���ƁA�H�ƁA�_�ƁA�C�^�ƂȂǁA�Y�ƃu���W���A�W�[�̗��v�͐₦����������A���Q�������ނ��Ă����B
�@���C�E�t�B���b�v�̎��������̂��Ƃł̋��Z�M���̎x�z�ɔ����āA�u���オ��̐��{�v���f���āA�Y�ƃu���W���A�W�[�́A�S�V�N�̍�����u�o���P�v�i�����v����j���J�Â��A�I�����x�̉��v�^����S���I�ɓW�J���Ă����B�I���@���v��ʂ��āA�c��ő������Ƃ�A���Z�M���̓Ɛ��ł��j�낤�Ƃ����̂ł���B
�@����A�S�T�`�S�U�N�̔_�Ƃ̋���Ə��H�Ƃ̋��Q�́A�J���ґ�O�̐�����j���B�o�ϊ�@�̂��Ƃŕn���ɋꂵ�ޘJ���ґ�O�ɂƂ��āA���Z�M�������̐ꐧ�x�z�͂��͂�䖝�ł��Ȃ����̂ɂȂ����B
�@���{�Ƃ̏Փ˂��n�܂�ƁA�J���҂̓����́A�Y�ƃu���W���A�W�[�̑I�����x���v�Ƃ������v�f���щz���Đi�B�������ăt�B���b�v�̎��������͂Q���̃p���J���҂����̖I�N�ɂ���ē|�A�Վ����{�����������B
�@���������Վ����{�́A���̏����������������ꂼ��̓}�h�f���Ă����B���a��`�I�u���W���A�W�[�A�I�����A���������Δh�A���a��`�I���u���W���A�W�[�A�Љ���`�I�J���ҁB�Վ����{�t���̑命���̓u���W���A�W�[�̑�\����߂����A���̂ق��ɋ��a�h�I���u���W���A�W�[�̑�\�Ƃ��ă��h�����E�������ƃt���R���炪����A�����ĘJ���ҊK������͂킸���Ƀ��C�E�u�����ƃA���x�[���̓�l�����t�����B�Վ����{�͎Љ���`�h���͂��ߋ������ăt�B���b�v������|�����e�X���Q�̂��ƂȂ�}�h����Ȃ���́u����A�����{�v�ł������B
�@�Վ����{�͘J���҂̈��͂̂��Ƃɋ��a�����������Ƃ�錾�����B
���������C�E�u�����̋�����`������
�@�J���҂̓u���W���A�W�[�ƂƂ��ɓv���𐋍s�����B�v���̓����A�J���҂̉e���͂͑傫���A�u���W���A�W�[�͂�������邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B�J���҂͗Վ����{���炳�܂��܂ȏ������l�������\�\�u�J���̌����v�̕z���A�J�����Ԃ̍팸�A�J����蒲���ψ���̐ݒu���X�B
�@�Վ����{�́A�J���ґ�O�̈��͂̑O�ɁA���₢��J����蒲���ψ���A�����郊���N�T���u�[���ψ���̐ݗ���F�߂��B����͘J���҂̉��P�̂��߂̎�i��������Ƃ����C������������݂̋@�ւŁA���̋c���Ƀ��C�E�u�����ƃA���x�[���E�g�}���C�����ꂽ�B�����A����́A���ۂɂ́A�u�\�Z�����s�����Ȃ��v����Ȃ钲���E�����̋@�ւł����Ȃ������B�u���W���A�W�[�́A���͂ȋ@�ւł����Ȃ��ψ���ւ̌��z���ӂ�܂��A�Վ����{���J���̖����ł��邩�ɐ�`�����B�������A�ψ���̉��Ƃ��Đ��{�̏��ݒn���痣�ꂽ�����N�T���u�[���ɂ��������Ƃ́A�J���҂̑�\�ł��郋�C�E�u�����ƃA���x�[���E�g�}�𐭕{����u�����A�u���W���A�W�[�����ƌ��́A�s���̎�j��Ɛ肷�邱�Ƃ��Ӗ������B
�@�������A�����N�T���u�[���ψ���̋c���ƂȂ������C�E�u�����ɂƂ��ẮA���̈ψ���́A�Љ���v�̂��߂̐��i�@�ւɂȂ�͂��ł������B
�@���C�E�u�����̃����N�T���u�[���ψ���́A�u�Љ�v�����������A���X�ɁA���a�I�ɁA�v�����^���A�K�����Ȃ������߂̓��ʂ̔C�����������v�J���Ȃ̐ݒu��\�肵�Ă����B�ނɂ��Ύ��{��`�̈��̍����͋����ɂ���A���ꂱ���������o�c��v�������A�J���҂̒����̒ቺ�A�n���������炷�����ł������B�����Ă��̋������Ȃ����Ă������߂ɂ́A���Ƃ̉����ɂ��u�Љ��Ə�v�i���c��Ɓj������A��������I��ƂƋ��������Ă����B���I��Ƃ��₪�ċ��������邾�낤�B���{�Ƃ͎��{����āA���Ɨ\�Z���痘�q�����A�܂������̘J���ɑ��Ă͑g�����ɔz������������������x������B�������ď��X�ɋ����̂Ȃ��Љ�A���̂Ȃ��Љ���������͂��ł������B
�@���C�E�u�����̎Љ�����v��́A���{��`�̌�������ڂ����ނ������u���W���A�W�[�̋�z�ł����Ȃ������B���ہA�����N�T���u�[���ψ���̒�ĂŁA�d���H�A�a�эH�Ȃǂ̂������̋����g�����ݗ�����A�ꎞ�I�ɉ���l���̘J���҂ɐE��^���͂������A���{��`�I�ȋ����ɂ���Ėv���A���ł��Ă��܂����̂ł���B
�@�}���N�X�́A���C�E�u�����̘J���̑g�D�A���̂��߂̘J���ȂƂ����v���̖��͂��Ɣ������ɂ��Ă����q�ׂĂ���B
�@�u�J���҂́A�u���W���A�W�[�Ƌ������āA�v���������Ȃ����B�ނ�́A�u���W���A�W�[�ƂȂ��ŁA�����̗��v���ѓO���悤�Ƃ����B���傤�ǁA�Վ����{���̂��̂̂����Ƀu���W���A�I�����h�ƌ����Ȃ�ׂāA��l�̘J���ҁi�A���x�[���j����t�������Ɠ����悤�ɁB�J����g�D����I�@�ƁB����ǂ��A���J���A���ꂱ�����ɂ���u���W���A�I�J���g�D�Ȃ̂��B���ꂪ�Ȃ���A���{���A�u���W���A�W�[���A�u���W���A�Љ���Ȃ��B�Ǝ��̘J���ȁI�@�ƁB�����A���ƁA�������Ƃ̏��Ȃ����u���W���A�I�ȘJ���Ȃł͂Ȃ����H�@�����ł����ƂȂ��ő��݂���v�����^���A�I�J���ȂƂ����Ȃ�A����͖��͂ȏȁA���Ȃ�ʊ肢�̏ȁA�܂胊���N�T���u�[���ψ���ƂȂ�ق��͂Ȃ������̂��v�i�u�t�����X�ɂ�����K�������v�j�B
�@���C�E�u�����̉��ǎ�`�I�{���́A�J���^���ɑ���ނ̑ԓx�̒��ɂ������Ă���B�ނ͘J���҂̉^�������{�̑̐��̒����̂Ȃ��ɕ����߂悤�Ƃ����B�ނ́A�J���҂ƃu���W���A�W�[�Ƃ̑Η��͌���̌��ʂł����āA�����I�ɂ͘J���҂ƃu���W���A�W�[�͋����̓���i�ނ��Ƃ��ł���ƍl���Ă����B
�@�Վ����{�̃u���W���A�����Ƃ́A���R�A�����A�F���ɂ��āA�l���̓���ɂ��ČJ��Ԃ����������B�u�����A���ׂẲ��}��`�҂͋��a��`�҂ɂ����A�p���̂��ׂĂ̕S�����҂͘J���҂ɂ�������B���̋�z��̊K���W�̔p�~�ɑ������Ă����퓅���傪�F���A�܂�A�S�ʓI�Ȑe�r�Ɠ��E���ł������B�K���Η��̂��̂悤�ɂ��������Ȓ��ۖ@�A��������K�����Q�̂��������Z���`�����^���Ȓ���a���A�K����������̂����������z�I�Ȓ��z�A���Ȃ킿�F���A���ꂪ�v���̖{���̍����t�ł������B�K���́A����Ȃ����ɂ���ĕ����ɂ����Ȃ��B���}���e�[�k���A�Q���S���A�Վ����{���w�قȂ������K���Ԃɑ��݂���A���낵��������Ȃ������{�x�Ɩ��t�����v�i����j�B
�@�u���W���A�W�[�́A�J���҂�������`�̌��z�ł܂�ߍ��݁A����̎x�z�������߁A�J���҂ւ̔������������Ă����B�������A���C�E�u�������u���W���A�W�[�ƂƂ��Ɂu���ՓI�F���v�ɂ��Ă�����ׂ肵�Ă����̂��B
�@�ނ́A�J���҂ƃu���W���A�W�[�̊Ԃ̒���҂Ƃ��ĐU��܂��A�u���W���A�W�[�̔����̏������������̂��B
�@�u���W���A�W�[�͘J���҂ւ̔����̏����𐮂����B���̐헪�̊�b�́A�J���ҊK�����A�J���҂̈ꕔ���c��̕����ɑΗ������邱�Ƃł������B���̈�͌R���̑����ł������B�Վ����{�́A�p���ɂ��鍑���R�����ł͘J���҂ɂ��Ȃ�Ȃ��Ƃ��āA�V���ɂQ���S��l�̗V���x������g�D�����B�ނ�̑啔���̓����y���E�v�����^���A�[�g�ł������B
�@������́A������Ə��̐ݗ��ł������B����́A���C�E�u�����́u�Љ��Ə�v�Ƃ͂��ƂȂ�A�������ƏȂ̓����̂��Ƃɏ\���̎��Ǝ҂����e���A�P���ŕs���Y�I�ȓy�؍H���Ɏg�p���邱�Ƃł������B�Վ����{�́A�ނ��J���҂̑�O�I�^���ɓG�ΓI�Ȃ��̂ɑg�D���悤�Ƃ����B
�������J���҂̔s�k������
�@�v���̏����ɂ͘J���҂̓��C�E�u������̌f����Љ�����v���M���I�x�������B�����܂��Ȃ��ނ�͎�����������z�̐��E�ɂ��邱�Ƃ��v���m�炳��邱�ƂɂȂ����B
�@�l���ɂ́A���ʑI���ɂ�錛�@����c��̑I�����s��ꂽ�B�W�W�O�l�̋c�����I�o���ꂽ�B���̓}�h�̓���́A���悻�u�i�V�I�i���v�ɏW�܂�u���W���A���a�h�T�O�O�A�u���{�����������h�P�O�O�A�I�����A���h�Q�O�O�ŁA�Љ��`�h�͂P�O�O�ł������B�}���N�X�͑I�����ʂɂ��āA�u�u���W���A�����̐����I�Č��ł���A�u���W���A�Љ�ł̐����Ċm���v�ł������Əq�ׂĂ���i����j�B
�@�u���W���A�W�[�ɂƂ��āA���͂�J���҂̑�\�𐭕{�ɎQ��������K�v�͂Ȃ��Ȃ����B�J���҂���̑�\�Ƃ��ă��C�E�u�������l��Վ����{�̊t���ɓ��ꂽ�̂́A�܂����������̐����x�z�̊�b���ł܂炸�s����ł���������ł���B�������A���܂�J���҂ɋC���˂���K�v���Ȃ��Ȃ����B�����c��͘J���҂̉e���̔r���ɂƂ肩�������B
�@�����c��͂������ɁA���������̔C�������t�����烋�C�E�u�����ƃA���x�[������ߏo�����B���͂�C�E�u�����̓u���W���A�W�[�ɂƂ��Č�p�ς݂ƂȂ����̂��B�����ĘJ���Ȃ�����Ƃ�����Ă����ۂ����B
�@�u���W���A�W�[�͂�����ׂ��J���҂Ƃ̑Ό����������Ă����B�U���A�����c��͍�����Ə��̉��U�����肵���B
�@������Ə��̑n�݂ɂ͎Љ��`�I���v�Ƌ��ʂ̂��͉̂��ЂƂȂ������B�ނ��낻��́A�J���҂̈ꕔ���u���W���A�W�[�̖����ɂ���ړI�ł���ꂽ�̂������B�������A����ł��J���҂ɂƂ��Ă͂���͎Љ���v�̃V���{���ł������B
�@������Ə��̉��U�́A���Ƃɂ��J���҂ւ̒���ł������B������Ə������U�������Ƃ́A�J���҂ɂƂ��Ă͑��ނׂ����ƂƂȂ����B
�@�J���҂͗����A�o���P�[�h��z���Đ��{�ɔ������Ђ邪�������B�������A�J���҂̖I�N�͐��{�̌R���ɂ���đł��ӂ��ꂽ�B
�@�J���҂͔s�k�̒��ŁA���ʑI���ɂ�鋤�a�����l���̍��Ƃł���]�X���U��ł��邱�ƁA���������̂킸���ȉ��ǂ��u���W���A���a���̓����ł͕s�\�ł��邱�ƁA�����������҂����z�ł��������ƁA�J���҂������������邽�߂ɂ̓u���W���A�W�[�̎x�z��ł��|���A����̊v���I���͂��������A���{�̑̐��̍��{�I�ϊv�ɐi�܂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����Ƃ𗝉����Ă������̂ł���B
�@�v���ƘJ���҂̔s�k�̌o���́A����A�������̔��������a����`�I�ł���A�����ł��邩�Ƃ������ƁA�J���҂̊K���I�c���Ɠ�������̂��A�u���W���A�W�[�̎x�z����������̂ł��邱�ƁA�J���҂͎��{�̎x�z�̑œ|�Ɍ����Ēc�����A���������˂Ȃ����Ƃ������Ă���B
|
�Q
�t�����N�t���g�����c��݂̂��߂Ȕs�k
���P�W�S�W�N�̃h�C�c�R���v���̋��P |
�������E�B�[���A�x�������O���v��������
�@�P�W�S�W�N�̃t�����X�v���́A���[���b�p�e�n�ɑ傫�ȏՌ���^�����B�s�s�Ɣ_�����܂߂ă��[���b�p�e�n���A����������_���̔����ɗN���������B
�@�p���̊v���̉e�����ŏ��ɋy�̂́A����h�C�c�̏��̖M�ł������B�Q���ɂ́A�}���n�C���ŊJ���ꂽ��O�W��ł́u�m���̑I�����Ƃ��Ȃ��l���̕����A�o�ł̎��R�A�C�M���X���̔��R���A�h�C�c����v�̎l�̗v�������c�����B�����A�h�C�c�͎l�̎��R�s�s���܂ގO��̗̖M����������ɂ₩�ȘA���̂ł��������A����h�C�c�̎��R��`�҂⋤�a��`�h���f�����ڕW�́A�̎傽���̃h�C�c�A�M���s�������̃h�C�c�A�M�Ɉڍs�����邱�Ƃł������B
�@�R���T���A�n�C�f���x���N�ɏW�܂������R��`�҂�T�P���́A�h�C�c�����̐��{�ɂ������č����c��̌������Ăъ|���A�V�l�̑�\��I�o�����B���l�ψ���́A�h�C�c�S�y���\���鍑���c������邽�߂́u������v���R�����ɁA�t�����N�t���g�E�A���E�}�C���ŊJ�Â��邱�Ƃ����c�����B�������A���̊ԃE�B�[���i�P�R���j�ƃx�������i�P�W���j�Ɋv�����N�������B
�@�E�B�[���v���̔��[�ƂȂ����̂́A�t�����X�v���Ɏh�����ꂽ�w���𒆐S�Ƃ���f�����ƌR���̏Փ˂ł������B�B�c��c�������͂����f�����ɑ��ČR�������C�������Ƃ����������Ƃ��āA�E�B�[���͑�����ԂƂȂ����B�s���ɂ̓o���P�[�h���z����A�x�O�ł͖��O���x�@��H����P�������B���O�I�N�̒��ŁA�I�[�X�g���A�̍ɑ����b�e���j�q�͓��S�����B�c���{�̓��b�e���j�q�Ɉ�̐ӔC�킹�邱�ƂŃn�v�X�u���N��������уI�[�X�g���A�̐����̐����~�����Ƃ����̂ł���B
�@�����ăv���C�Z���̃x�������ł́A�c��̊J�݂�o�ł̎��R�����߂�s���W����R�����e���������Ƃ����������Ƃ��āA���O�ƌR���̏Փ˂��J��Ԃ��ꂽ�B�������s�X��̌�A���Ǎ����̓x����������R���������グ�邱�Ƃɓ��ӂ����B���O�̓{���������Ēe���̐ӔC�ҁE���탔�B���w�����̓C�M���X�ɓ��ꂽ�B�����͎s���̕�����F�߁A���O�̑����̂܂ƂƂȂ��Ă������t��ސw�������B
�@�E�B�[���ƃx�������̊v���ŁA���R��`�҂⋤�a��`�h�̉^���͂������������ƂȂ����B���̎����̓����́A�n�C�f���x���N�W��ɂ݂���悤�Ɏ��R��`�҂Ƌ��a��`�h�Ƃ͈ӌ��͑Η������A������c�̏��W�Ƃ����_�ł͈�v���A��Ύ�`�I�N��₻�����芪���ێ琨�͂ɔ����ċ��͂��Ă����B�����āA�����̐��������͕����I���x�ɔ������O�̉^���ƌ��ѕt���Ă������Ƃł���B
�������t�����N�t���g�����c�����
�@�R�����ɂ́A�n�C�f���x���N�W��ł̑I�o�ɂ�鎵�l�ψ���̌v��ɂ�鏀����c���J���ꂽ�B������c�́A������ׂ��u�h�C�c�����c��v�̂��߂̋c���̑I�o���@�A���@�̊�{�\�z���߂����ċc�_�����B�c���̑I�o�ɂ��ẮA�u�����I�v�s���ɂ�镁�ʕ����I������߂�ꂽ���̂́A�I�����Ⓤ�[���̐ݒ�ȂNj�̓I�Ȏ��{���@�͊e�̖M���{�Ɉς˂�Ƃ����Ë��I�ȕ��j���Ƃ�ꂽ�B���̂��ߕϊv��j�~���悤�Ƃ���̖M���{�̉����������ƂɂȂ����B���łɃu���W���A���R��`�҂�̑Ë��I�p����������n�߂Ă���B
�@�����c��́A�T���Ƀt�����N�t���g�ŊJ���ꂽ�B�o�Ȃ����T�O�O�l��̋c���̂����Ŏ��R��`�I�Ȕ����⌟�����̑��̍����������ł������A��w������ٌ�m�Ȃǂ�����ɑ������B
�@�e�̖M�c��ɂ����Ă��A�R�����ɂ́A���C���B�̑古�l�̃J���v�n�E�[�����ɁA�n���[�}���𑠑��Ƃ���v���C�Z���ōŏ��̎s�����t���g�D���ꂽ�ق��A�o�C�G�����A�o�[�f���A�������e���x���N�Ȃǂł��N��̏����ɂ���āu�O�����t�v���g�D���ꂽ�B
�@���̎����A�v���̐i�s�ƃh�C�c����̊��҂��L�����Ă��������A�͂₭���J���҂̓����������u���W���A�W�[�̑Ë��I�ԓx���v���̐i�s�ɉe�����Ƃ��Ă���B
�@�t�����N�t���g�����c��͊v���̖ړI�ɂ������Ė����o�ł������B����́u������ׂ�̏�v�A�u�����c��v�Ƃ���ꂽ�悤�ɁA��_�I�ȋc�_�ɖ������A��������Ɏ��Ԃ�Q��A����ɂ���Ĕ������̐��𐮂������Ԃ��ɏo��̂��������̂ł���B�}���N�X�A�G���Q���X�͍����c��̓��a����`�ɂ��Ď��̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�@�u���̃h�C�c�����c��́A�����镴���������������A�h�C�c�A�M�S�̂̂��ߍō����@�@�ւƂ��čs��������̂ƁA���O������҂���Ă����B�c�c�����c��́A�������ꂪ�����킸���̐��͂ł������Ă����Ƃ���A�������ɘA�M�c��i�̖M�c��̘A���\���p�ҁj�\�\����ȏ�ɕs�l�C�Ȓc�̂̓h�C�c�ɂ͂Ȃ������\�\�����U���āk���̋c�����l�{���ɂ����肩�����A���ꎩ�g�̋c���̂Ȃ�����I�o�����A�M���{�������Ă���ɂ������͂��ł���B����́A��ꂱ���h�C�c�l���̍ō��ӎu�̗B��̍��@�I�\���ł���Ɛ錾���A�������邱�Ƃɂ���Ă��̈�X�̋c���ɖ@���I���͂�t�^�����͂��ł���B�Ȃ����A����́A���M���{�̑��ɂ����锽�����������邾���́A�g�D���ꂩ�������ꂽ���͂��A�����ɂ����Ċm�ۂ������͂��ł���B����������炷�ׂĂ̂��Ƃ́A���̊v���̏����ɂ����Ă͗e�Ղ��e�Ղ���߂ėe�ՂȂ��Ƃł������B�c�c�i�������A�����c��́j�A�M�c��̊Ď��̂��Ƃɕ]�c�����A���ȁA����́A���̋c���ɑ���A�M�c��̍ى��قƂ�Ǎ��������������A�������A�����ōŏ��ɋc�����ꂽ���Ƃ́A���̂��Ƃ��ׂ��c�̂ɂ���Č��z����˂Ȃ�Ȃ���������ł���B����͎��Ȏ��g�̎匠���咣���邩���ɁA�Ƃ߂Ă��������댯�̂��邢�������̖��̓��c����������v�i�w�v���Ɣ��v���x�j
�@�����c��͐l���́u�v���I�s�����Ƃ邾�낤�v�Ƃ������҂ɔw���A�������]���̂܂܂ɂ��Ă������B�u���W���A���R��`�҂�́A�u�����I�Ȑ����I�A�d�����A���ׂȖ��O�^��������Ă����v�i����j�̂ł���B�ނ�́A�����I���͂Ɉˑ����Ȃ���A���O�̓�����}�����悤�Ƃ��Ă����B
�@�U���̃p���J���҂̔s�k�ɂ���āA�h�C�c�ł͔����h�̊����Ԃ��������J�n���ꂽ�B�v���C�Z���ł́A�C�M���X�ɖS�����Ă������탔�B���w�����l�����A�������B���v�������ꂽ�J���҂͔����Ɉڂ�ׂ��x�������̕���ɂ��P���������e�����ꂽ�B�������͂��̎����������ɌR�����x�������ɓ������邱�Ƃ����肵���B�ނ�ɂƂ��Ă��͂�J���v�n�E�[�����t��K�v�Ƃ��Ȃ������B���t�͎��E���A�����ăn���[�}��������������A�E�G���X�o���g���t���a�����A�R���͍Ăуx�������ɌĂі߂��ꂽ�B�A�E�G���X�o���g�E�n���[�}�����t�͊v���𐄂��i�߂�̂ł͂Ȃ��A�J���҂̊v���I����������ĕ����I���͂ɂ܂��܂��ˑ�����悤�ɂȂ��Ă������B
�@�t�����N�t���g�����c����h���d�˂Ă���ԂɁA�P�P���I�[�X�g���A�̃E�B�[���́A�����ɂ��R���ɂ���Ē������ꂽ�B����Ɍە�����āA�v���C�Z���ł́A���@�ɂ���Đ������Ă����u���G�����t����Ƃ���A�����̃u�����f���u���N�����ɔC�����ꂽ�B�V���t�́A�v���C�Z�������c����x����������Ǖ��A�s���R�������������߂��������B�v���C�Z�������c��͔[�ŋ��ۂȂǂŒ�R���������ʂȂ��A�P�Q���ɂ͍����c��͉��U�ɒǂ����܂ꂽ�B����ɂ������ăt�����N�t���g�����c��́A�������Ăъ|����̂ł͂Ȃ��A�����v���C�Z�����{���Ȃ����܂܂ɂ����Ă��������ł������B
�@�P�Q���悤�₭�t�����N�t���g�����c��́A�u�h�C�c��{�@�v�����\�����B����́A�u���W���A�����`��\�������̂ŁA�S�Ă̍����Ɏs������^���A�c�ƁE�M�E�o�ł̎��R��搂����B���̊�{�@�����ƂɂS�X�N�R���A���@�����z���ꂽ�B
�@���̈���ō����c��́A�����Ɍ��z���������B���w�����l�����h�C�c�c��ɐ��Ղ������A���ۂ��ꂽ�B���͂�A�����h�ɂƂ��č����c���u���Ă����K�v���Ȃ��Ȃ����̂ł���B
�@�t�����N�t���g�����c��͐��{�ɑ��čR�c��Q����J��Ԃ��ȊO�ɂ͂Ȃɂ����Ȃ������B�������āA�ŏ��ɃI�[�X�g���A�̋c���������A���ɂ̓v���C�Z���A����ɂ͉E�h�A���Ԕh�Ƃ�����Ɏ��X�Ɠ��S���Ă������B�Ō�Ɏc�����S�l���炸�̋c���́A�V���g�D�b�g�K���g�Ɉڂ�u�c�]�c��v����������������e������āA�����c��͏��ł̉^�������ǂ����B�������āA�v���œ����u���W���A�����`�I�Ȋl��������|����Ă��܂����B
�������v���̋��P������
�@�S�W�N�̃h�C�c�v���̔s�k�́A�u���W���A���R��`�h�̔s�k�ł������B�h�C�c�̃u���W���A�W�[�́A�Ȃɂ����J���҂�����Ă����B�ނ�̓u���W���A�����`���l�����邱�Ƃł́A�J���҂ƈ�v���Ă������A�v���̏u�Ԃ��玩�������ɑΗ�����ł��낤�J���҂̓���������A�J���҂ɑR���邽�߂ɕ����I���͂Ɉˑ������̂ł���B�܂����u���W���A�����`�h���s���f�Ɠ��h���J��Ԃ����B
�@���R��`�I�u���W���A���t�́A�u����ɂ�������A���ꋤ�a���Ƃ������i�������i�K�ɐi�ނ��A�܂��͂ӂ邢�����I�������I�A�����I�x�z�̐��ɂ��ǂ邩�A�����ꂩ�v�́u��̋x���_�v�i����j�ł����Ȃ������̂ł���B
�@�}���N�X�A�G���Q���X�́A�h�C�c�̊v���Ɣ��v������d�v�ȋ��P�������o���Ă���B����́A�J���҂͎���̐��}���������A�Ǝ��̓����𐄂��i�߂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃł���B
�@�h�C�c�v���̔s�k�̌�A�V���ȘJ���҂̓����̍��g�����҂��ď����ꂽ�u���Y��`�ғ����ւ̒����ψ���̌Ăт����v�͎��̂悤�ɑi���Ă���B
�@�u���u���W���A�I����}�ɂ�������v���I�J���ғ}�̊W�͂������A�\�\���Ȃ킿�A�v���I�J���ғ}�͂��̑œ|���߂����Ă��镪�h�ɑR���āA���̏��u���W���A�I����}�ƒ�g���邪�A����}�����ꎩ�g�̗��v�ɂȂ�悤�Ɏ����̒n�ʂ��͂�����ł́A���Ƃ��Ƃ����̖���}�ƑΗ�������̂ł���B�����`�I���u���W���A�́A�v���I�v�����^���A�̂��߂ɑS�Љ��ϊv���悤�ȂǂƂ͖ѓ��l�����A���݂̎Љ���ł��邾��������ɂ��܂�ł���A�����ĉ��K�Ȃ��̂ɂ���悤�ȁA�����������x�̎Љ��Ԃ̕ύX���߂����ēw�͂���v�B�����`�I���u���W���A�́u���I���L�̕ύX�v��v�����邾���ł��邪�A�J���҂ɂƂ��Ė��Ȃ̂́A�u�i���I���L�́j�p�~�ł���A�K���Η��̂��܂����ł͂Ȃ��ĊK���̔p�~�ł���A���݂̎Љ�̉��P�ł͂Ȃ��ĐV�����Љ�̌��݂ł���v�B
�@�����āA�J���ғ}�̏��u���W���A����h�ɑ���ԓx�͂ǂ�����ׂ����ɂ��āA�u�Ăт����v�͑����ďq�ׂĂ���B
�@�u�����`�I���u���W���A�́A�ނ炪������Ƃ���ŗ}������Ă��錻�݂̏u�Ԃɂ����ẮA�v�����^���A�ɂނ����Ĉ�ʂɒ�g�Ƙa��������Ă���B�ނ�̓v�����^���A�Ɏ�������ׁ̂A����}���̂�����F�������ӂ��ވ�唽�Γ}�����낤�Ɠw�͂���B���Ȃ킿�A�ނ�͘J���҂���̐��}�g�D�\�\���̂Ȃ��ł́A�ނ�̓���ȗ��Q�����̔w��ɔ�߂��Ă����ʓI�Ȗ����`�I�������͂��������A���a���������߂Ƀv�����^���A�[�g�̓���̗v�����咣���邱�Ƃ͂�邳��Ȃ��\�\�̂Ȃ��Ɉ����������Ɠw�͂���̂ł���B���̂悤�Ȓ�g�͔ނ�̗��v�ɂȂ邾���ŁA�v�����^���A�[�g�ɂ͂܂������s���v�ɂȂ낤�B�v�����^���A�[�g�́A���������Ă����������̓Ɨ��̒n�ʂ̑S�̂������Ȃ��A�ӂ����ь��F�̃u���W���A�����`�̕t�����ɐg�����Ƃ��Ă��܂����낤�B���������Ă��̂悤�Ȓ�g�͒f�Ő˂����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�܂����Ă��g�������āA�u���W���A�����`�҂ɔ���������鍇�����̂킫�����Ƃ߂��肹���ɁA�J���ҁA�Ƃ�킯�����́A���F�̖����`�҂ƂȂ��ŁA�J���ғ}�̓Ɨ��̔閧�g�D�ƌ��R�̑g�D�Ƃ����肠���A�e�ǂ��A�v�����^���A�[�g�̒n�ʂƗ��Q�Ƃ��u���W���A�I���e�����͂Ȃ�ċc�_�����J���ҋ���̒��S����ђ��j�ɂ���悤�ɁA�Ƃ߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��v
�@�J���҂͎���̊K���I����ɗ����A�Ǝ��̓����𐄂��i�߂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ����w�E�́A���R��`�I�u���W���A�}�h�⏬�u���W���A�}�h�Ƃ̒�g�A�u����A�������v�����������Ă��鍡���̋��Y�}�ɑ���s���ᔻ�ɂ��Ȃ��Ă���B
|
�R
�鍑��`�푈�ւ̋��͂ƃu���W���A�x�z�̕⊮
���P�X�P�V�N���V�A�Վ����{�̌o�� |
�������Վ����{�ƃ\���F�g�̐���������
�@��ꎟ���͐��E�ɑ傫�ȉe����^�������A�Ƃ�킯���V�A�̎��e���͐[���ł������B�푈�͑�O�ɖ��\�L�̋]�����������A���̕s���͘J���҂̃X�g���C�L�A�f���ƂƂȂ��Č���ꂽ�B�P�X�P�V�N�Q���A��s�y�e���O���[�h�̃p����v������J���҂̃f���A�X�g���C�L�͂����܂��̂����ɑS�s�ɍL����A���m���������N�����ĘJ���҂ɍ��������B�J���ҁA���m�̖I�N�ɂ���ăc�A�[���ꐧ�͑œ|���ꂽ�B
�@�J�f�b�g�}�i��������}�\�\���R��`�I�A�N���`�I�u���W���A���}�j�ƃI�N�`���u���X�g�}�i�P�O���P�V�������\�\�Y�ƃu���W���A�W�[�Ƒ�n��̐��}�j�ɑ�\�����u���W���A�W�[�̐��͂́u�ӔC���t���v��v������u�i���h�u���b�N�v���`�����Ă������A�ނ�́A�v����~���Ă��Ȃ��������A����ɎQ�������Ȃ������B�ނ�͘J���ҁA�_���̊v��������A���������悤�Ɠw�߂��B�ނ�ɂƂ��Ă͘J���ҁA�_���̊v�������c�A�[���ꐧ�̕����܂��ł������B�c�A�[���ꐧ�́A�J���ҁA�_���̊v������u���W���A�W�[�̗��v������Ă������ł���A�h�ǂł������B�y�g���O���[�h�̊v�������������Ƃ��A�J�f�b�g�̃~�����[�R�t��I�N�`���u���X�g�̃O�`�R�t�́A�N�吧���~�����Ƃ��������̂ł���B��������͂��͂�s�\�ł��邱�Ƃ����炩�ɂȂ����B
�@�R���A�c�A�[���ꐧ�ɑ����Ēa�������̂́A�@���P�����X�L�[�������Ύ������̃����H�t���͂��߂Ƃ��đS�����u���W���A�̑�\�ł������B
�@�Վ����{�ƕ���Ń\���G�g���������ꂽ�B�y�e���u���O�J���҂���ѕ��m��\�\���G�g������ł���B�\���G�g�͑S���ɑg�D����l���̌��͂Ƃ��ėՎ����{���p�������������͋@�ւƑΗ����Ă����B�Վ����{�͒��ڑ�O���������邱�Ƃ��ł����A�\���G�g��ʂ��Ă������̎x���邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ��������܂ꂽ�B������u��d���́v�ł���B�������A���R�����I�ɐ��܂ꂽ�\���G�g�́A�u���͂̋@�ցv�Ƃ��Ă̎��Ȃ̖��������o���Ă��Ȃ������B���܂ꂽ����̃y�e���u���O�E�\���G�g�̎��s�ψ���́A�鍑��`�푈�̌p����F�߂郁���V�F���B�L�Ȃǂ̉E�h�Љ���`�h���������߂��B
�@�y�e���u���O�E�\���G�g����́A�����I���R�̕ۏ�A���@�����c�̏��W�Ȃǂ������Ƃ��āA�Վ����{�����F���邱�Ƃ����|�I�����Ō��肵���B�����V�F���B�L�́A�u���W���A�v���ł��邩��J���҂͎Q�����ׂ��ł͂Ȃ��A���{�ɊO���爳�͂������A�J���҂ɗL���Ȑ���i�����܂Ńu���W���A�����`�̘g���Łj�����s������ׂ����ƁA�P�X�O�T�N�̊v���̎��Ɠ����咣���J��Ԃ����B�������̏������x�����t�O���͘_�́A���ۂɂ̓u���W���A���{�Ƃ̋����ȊO�̂Ȃɂ��̂ł��Ȃ������B
�@�Վ����{�̓\���G�g�Ƃ̋���Ɋ�Â��āu�����Ƃ̎ߕ��A���_�E�o�ŁE���ЁE�W��E�X�g���C�L�̎��R�A���ʁE�����E�閧�E���ڑI���Ɋ�Â����@�����c�̏��W�v�Ȃǂ�����B�����ē����ɁA�Վ����{�͐푈�̌p����錾�����B�u���W���A���{�ɂƂ��āA�A�����Ƃ̓������ێ����h�C�c�Ƃ̐푈�ɏ������邱�Ƃ͎���̉ۑ肾�����B�������ėՎ����{�́A�u���W���A�I���R�Ɛ푈�̐��{�Ƃ��ēo�ꂵ���̂ł���B
�@�O���~�����[�R�t�͘A�����ɑ��āA���V�A���{�͘A�������ɗ����čŌ�̏����܂Ő푈���p������A�c�A�[�̐��{�ɂ���Ē������ꂽ�S�Ă̏��𒉎��Ɍ��炷��Ɩ���o���𑗂����B
�@����ɑ��ĘJ���҂╺�m�́u�N���푈���v�A�u�~�����[�R�t�œ|�v�Ȃǂ̃X���[�K�����f�����f���Ŕ����ɗ����A�\���G�g���u���v�̑ԓx�𖾂炩�ɂ��钆�ŁA�~�����[�R�t�Ɨ����O�`�R�t�͎��C�ɒǂ����܂�A�Վ����{�͕����B
�������A�������ƒ鍑��`�푈������
�@�����V�F���B�L��͂����鐭�}�̑�\�ɂ���đg�D����A������K���ɂ���Ďx������鏔�K���̋����ɂ�鐭�{��ڎw�����B
�@����A�\���G�g�̈��͂ɔY�܂���Ă����u���W���A�W�[�́A�A��������g�D���邱�Ƃ�L���ƍl����悤�ɂȂ����B�ނ�̓\���G�g�̑�\�ł���g�Љ��`�ҁh�𐭕{�Ɉ�������邱�Ƃɂ���āA�\���G�g�Ɍ��W����J���ҁE�_���ɑ���x�z��ł��ł߂悤�Ƃ����̂ł���B
�@�T���A�������čŏ��̘A�����{���a�������B����ɂ͂W�l�̃u���W���A�̑�\�̂ق��ɃG�X�E�G���i�Љ�v���}�\�\���u���W���A���}�j�A�����V�F���B�L�A�i���[�h�j�L����e�X��l�����t�����B
�@�����A�u���W���A�W�[�Ƌ������A���a�I�ɐi�����Ƃ��郁���V�F���B�L��͂����܂��T�����B���{���ɂ�����J����O�̑�\�Ƃ��čl�����Ă����ނ�́A�J����O�̗v�������邱�Ƃ��ł��Ȃ���������ł���B�ނ�̔w��ɂ́A�J���ҁA���m�A�_�������W����\���G�g���������B
�@���{�����̑Η��̑��̖��́A�y�n�̖��ł������B�y�n�̕��z��v������_���͓y�n�Ɋւ���_����֎~���A������y�n��y�n�Ǘ��ψ���̊Ǘ��̂��ƂɈ����n���悤�ɗv�������B�����A���̗v���͎��L���Y�̐N�Q�Ƃ��Ēn���u���W���A�W�[�̔����������N�������B�_�Ƒ�b�`�F���m�t�i�G�X�E�G���j�́A�_���̈��͂ɂ���ė��@�����͂��낤�Ƃ������A�u���W���A��b�̔��ɂ����č��܂����B�܂��ގ��g�A���{���̕s�a������Ă��̗v�����т����Ƃ͂��Ȃ������B
�@�y�n���ɏے������悤�ɁA���{�͏d�v�Ȗ��ɂ��Ĉ�v���邱�Ƃ��s�\�ł��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ����B
�@�푈�Ɋւ�����ɂ��Ă��ӌ��̕s��v��\�I�����B
�@���t���������V�F���B�L�A�G�X�E�G���̑�b�́u�c���i��v�̗���ł���A�h�C�c���푈����߂Ȃ�������A�푈�̌p�����咣���Ă����B����ɑ��ĘJ���ҁA�_���͂Ȃɂ����푈�̏I����]��ł����B�������A�A�����{�́A�A�����̗v���ɂ���ăh�C�c�ւ̐N�U�̏������J�n�����̂ł���B���̐擪�ɗ������̂͗��E�C���P�����X�L�[�ł������B�ނ́A�����������ĕ��m��퓬�ɂ��藧�Ă��B
�@�������������͘A���������u���W���A�W�[�̂��߂̐��{�ł���A�J���ҁA�_���̗��Q�ƑΗ����Ă��邱�ƁA�g�Љ��`�g��b���J���ҁA�_���̑�\�ł͂Ȃ��A�u���W���A�W�[�ɗ��p����Ă��鑶�݂ł����Ȃ����Ƃ𖾂炩�ɂ����B�������āA�J���ҁA�_���̓���Ǝx���́u�S���͂��\���G�g�ցv�ƌĂъ|�����{���V�F���B�L�ւ܂��܂��W�܂��Ă������B
�@�J����O�̘A�������ւ̕s���ƕs�M�́A�U���̎�s�ŘJ���ҁA���m�̑�K�͂ȃf���Ƃ��Ĕ��������B�ނ�̊��ɂ́u�S���͂��\���G�g�ցv�u�閧���𑒂�v�u�N���푈�𑒂�v�Ə�����Ă����B����̓{���V�F���B�L�̊v���I���J���ґ�O�̒��ɐ[���Z�����A�e�����L���Ă��邱�Ƃ������Ă����B
�@�J����O�̍��g�Ƃ͋t�ɁA�����V�F���B�L��G�X�E�G���͂܂��܂����������A�u���W���A�W�[�Ƃ̋��������߁A�A�������͘J���ҁA�_���Ƃ̑Η���[�߂Ă������B
���������v���ւ̓���|�����߂遟����
�@�U���f���̓u���W���A�W�[��k���オ�点���B�u���W���A�V���i�����ă����V�F���B�L�Ȃǂ��j�́u�����{��ԁv�̖�����j�~���A�{���V�F���B�L�̐i�o��j�~������u���łȂ錠�́v�̌��݂����B�u���W���A�W�[�́A�u��d���́v��Ԃ��I��点�A�K���x�z�̊m���̂��߂ɍ��������߂Ă������B
�@�U���f���̗����A�P�����X�L�[���C���́A�O���ł̑��U�����J�n�����B������`�����A�ɂx�z���ł߂悤�Ƃ����̂��B�����A���U���͎��s���A�܂��܂����m�̔���ӎ������߁A�R���̊���𑣐i���錋�ʂɏI������B�N�����V���^�b�g�̕��m��J���҂�͕������A�푈���̃f�����s�����B
�@����ɑ��Đ��{�́A������琭�{�ɒ����ȌR�����Ăъe�������B�{���V�F���B�L�́u�c���̗���ҁv�Ƃ��Ēf�߂���A�w���҂͑ߕ߂���A���̋@�֎��̔��s�͋֎~���ꂽ�i���������j�B
�@�V�����{�ɂ́A�P�����X�L�[�������C���Ƃ�����t���a�������B�P�W�l�̊t���̂����P�P�l���g�Љ��`�ҁh�ł������B�J�f�b�g����͂T�l�����t�����B�J�f�b�g�́A���t�̏����Ƃ��ă\���G�g�ƈ�����悷�邱�Ƃ��������B
�@����Ɋ�Â��āu���ƕ]�c��v���J���ꂽ�B����ɂ́A����c���A����A�s��A����g���A���Z�c�A���{�ƒc�́A�J���g���Ȃǂ̑�\���W�܂����B�u���ƕ]�c��v�́A�J�f�b�g�A���Z�c�A���{�ƒc�̂Ȃǔ����h�̃f�����X�g���[�V�����̏�ƂȂ����B�ނ�́A�{���V�F���B�L�̊v�����烍�V�A���~�ς��邱�Ƃ����R�Ƒi�����B
�@���̑�\�Ƃ��đI�ꂽ�̂̓R���j�[���t���R�ł���B�ނɂ́A�\���G�g��j�A�u���W���A�ƍق̂��߂̓����J���C�����ۂ���ꂽ�B���̉A�d�̒��S�̓J�f�b�g�̃~�����[�R�t�������B�����āA���̉A�d�ɂ��ăP�����X�L�[���g���܂��������W�ł͂Ȃ������B
�@�����A�R���j�[���t�̔��v���������̉^���ɂȂ�ƁA�P�����X�L�[�̓R���j�[���t�i�ߊ������C�����B�P�����X�L�[�͎���A�d�v��ɉ��S���Ȃ�����A�R���j�[���t�ɔ������̂́A���v���̔g���{���V�F���B�L�݂̂Ȃ炸�A�����ɂ��P���������Ă���댯������������ł���B�R���j�[���t�̓P�����X�L�[���{�ɑ��ĐV���Ȑ��{��g�D����Ƃ��đS�Ă̌��͂������n���悤�v�������B�R���j�[���t�̏����́A�P�����X�L�[�̔j�ł����Ӗ������B
�@���藈�锽�v���̊�@�ɑ��āA��s�̕��m�͐v���ɔ����ɗ����A�J���҂͕��������B�S���J���҂̓X�g�ɓ������B�J���ҁA���m�̐V���ȍ��g�ɂ���Ĕ��v���͑|�����ꂽ�B
�@�R���j�[���t�̔����̎��s�ŁA�J�f�b�g�͐��{���狎�����B����̓}���v�悵�����v�����ق����{�ɂ͂����Ȃ��Ȃ�������ł���B�������A������_�@�ɃP�����X�L�[�����͓ƍٓI���i�����߂Ă������B�P�����X�L�[�́A�c�A�[����̏��R�Q�l�A�����H���A�����V�F���B�L�̂S�l���������T�l����Ȃ�u�������t�v��g�D�����̂ł���B
�@�R���j�[���t�̔����͋}���ɘJ���ґ�O��ڊo�߂������B�����V�F���B�L��G�X�E�G����̋�����`�ɏ]���A�A���������x�����Ă����O���[�v��J���҂́A�u���W���A�W�[�Ƃ̋����A���������������炷�������o�����B�������ď\���v���͏�������A�������Ă������B
���������V�A�v������������́�����
�@�P�V�N�̃��V�A�̌o���́A�u����A�������v�i���R��`�҂�Љ���`�}�h�Ƃ̘A�������j�ɂǂ�Ȋ��҂⌶�z�������Ƃ͂ł��Ȃ����ƁA�K�������W������̂͘J���ҊK�����g�̓����ł����āA�u���W���A���R��`�҂⏬�u���W���A�}�h�Ƃ̓����⋤���ł͂Ȃ����Ƃ������Ă���B�������K�������̋�̓I�Ȑ����I�ǖʂł̔ނ�Ƃ̋�����Ë��͂��肦�邾�낤�B����������P�v��������A���ȖړI������Ƃ���A����͘J���҂̊K���I�c���Ɠ�������̂��A�s�k�ɓ������낤�B
�@�����V�F���B�L�̓\���G�g�̑�\�Ƃ��āA�u���W���A���R��`�҂Ɓu�A�������v���������B�������łɌ����悤�Ɂu����A�������v�́A�J���҂�_�����v�����Ă��������̈������P�������炷���v���s�����Ƃ͂ł��Ȃ������B�u���W���A�W�[�̍��{�I���Q�Ɋւ��悤�Ȗ��ł́A�����܂��[���Ȉӌ��̑Η��������N�����A�J���҂�_���̗v���͋��ۂ��ꂽ�B�����A�J���҂̗v�����ѓO���悤����i�����V�F���B�L�͂��Ƃ��Ƃ���Ȉӎu�͂����Ă��Ȃ������̂ł��邪�j�A���{�͂��ɕ������Ă��܂������낤�B���ہA�E�N���C�i�̎�����F�߂����Ƃ�s���Ƃ��ău���W���A��b�͎��C���i��ꎟ�����H�t���t�j���{��@���������B
�@���{�̈ێ����͂��邽�߂ɂ́A���ǂ̓����V�F���B�L��G�X�E�G���������悤�ɘJ����O�𗠐�A�ł��E���I�ȓ}�h���u���W���A�W�[�ɕ��������킹�Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ������B�u���W���A�W�[�������V�F���B�L��g�Љ��`�ҁh�����ꂽ�̂́A�u���W���A�W�[�ɑ���J����O�̓����ւ̏��Ƃ��邽�߂ł���A���z��U��܂����{�̎x�z�̂��ƂɘJ����O���Ȃ��Ƃ߂Ă������߂ł������B�������ău���W���A�W�[�͊�@�̎�������z���悤�Ƃ����̂ł���B
�@�������J����O�̗v�������������Ȃ��u�A�������v�ƘJ����O�Ƃ̑Η��͔������Ȃ��B�K���Η�����������Ȃ��Łu�A�������v�͂܂��܂����͉����Ă������B�������Ă�肠���炳�܂Ȗ\�͂ɂ���ĘJ����O�̉^����}�����悤�Ƃ��锽�v�������܂ꂽ�B�R���j�[���t�̔����́A�u����A�������v�̖��������݂��������̂ł������B�����V�F���B�L��̊K��������`�͔��v���̑䓪���������̂ł���B
�@�������Y�}�́A�J���҂Ǝ��R��`���͂⏬�u���W���A�Ȃǂ���������u����A�������v�́A�������͂��Ǘ������A���{�̑̐��́u���a�I�ϊv�v���s���Ă������Ƃ��\�Ƃ���ƌ����Ă���B����������͂܂������̌��z�ł���B���Y�}�̎咣����u����A�������v�Ƃ́A����́u�P�����X�L�[�����v�ł���B�J���҂͂���ɂǂ�Ȋ��҂������Ƃ��o���Ȃ��B�J���҂͎���̊K���I�������W�����A�ѓO���Ă����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
|
�S
�v���̎���ɓ��a����`�҂Ǝ��g��
���n���K���[�E�\���B�G�g�����̐����ƕ��� |
���������a�����{�̎���������
�@�n���K���[�̊v���́A��ꎟ���̌o�ϓI��@��w�i�Ƃ��āA���V�A�v���̋����e���̂��ƂŎn�܂����B
�@��ꎟ���ł̓n���K���[�̓h�C�c���Ƃ��ĎQ�킵�����A���т����Ȃ�R���I�s�k�Ɛ푈�ɂ��o�ϊ�@�́A�����̊K���Η�����w�����������B�_�Ƃ͍r�p���A�s�s�̐H������͈������A��O�͋Q���ɋꂵ�B��O�̔���A���a�����߂鐺�͋}���ɍ��܂�A�e�n�ŘJ���҂ɂ��R�ɑ��锽�R���N����A����ł͕��m�̔��������������B
�@�P�W�N�P���A�I�[�X�g���[�S�y�ɋN�������X�g���C�L�̓n���K���[�ɔg�y�A��s�u�_�y�X�g�ł͑����u�a��v������R�O���̑�O�W��s��ꂽ�B�����ĘJ���҂͎Љ��}�̒��~�̌����U����ă[�l�X�g�����s�����i������_�@�Ƃ��āA�Љ��}���ɍ��h���������ꂽ�j�B
�@�T���ɂ̓y�[�`�łQ�疼�̕��m�����ɂ�苒�A�v�����^���A�v���̃X���[�K�����f�����B�����ĂU���ɒ��グ�X�g���s��ꂽ���A�R���̔��C���_�@�Ƃ��ă[�l�X�g�ɔ��W�����B���̊ԁA��s����эH�Ɠs�s�ŘJ���ґ�\�^�i�[�`�i���\���F�g�j���������ꂽ�B�܂��W���ɂ͍ŏ��̕��m�^�i�[�`���������ꂽ�B
�@�P�O�����A�E�B�[���Ŋv�������������u�_�y�X�g�ɓ`���ƁA���h�Љ��}��v���I�Љ��`�҂ɂ���Ďw�����ꂽ�����J���҂ƕ��m�́A�u�_�y�X�g�s���̓S���A��s�Ȃǎ�v�{�݁A���{������苒���A�����Ƃ��ߕ����͂��߂��B�����͍�����c�̗̑��ł���J�[���C�����Ɏw�����A���͂̓u���W���A�}�i�}�A�J�[���C�}�A�Љ��}�O�}�ɂ�鍑����c�ɈϏ����ꂽ�B�\���u���W���A�v���́A���m�^�i�[�`�A�J���҃^�i�[�`�ƘJ���ґ�O�̗͂���b�ɂ��Đ��s���ꂽ�̂ł���B������c�́u�l�����a���v��錾�A�n���K���[�́A�����I�ɂ킽��n�v�X�u���N�Ƃ̎x�z�ɏI�~���������A���ƓI�Ɨ����l�������B
�@�������A���{�͘J���҂̎Љ�ϊv�̗v���A�_���̓y�n�z���v�������������Ȃ����Ƃ����炩�ɂȂ����B�O�}�̂Ȃ��ŗB��g�D�J���҂Ɋ�Ղ������Ă����Љ��}�́A�}�i�������J���҃^�i�[�`�̑̐����ւ̎�荞�݂���B�������A����͍������Δh�̔��������˂��A�s�s�ɂ����Ă��n���ɂ����Ă��A����ɐ��{�ƃ^�i�[�`�Ƃ̑Η����\�ʉ����Ă������B�܂��y�n���v�����s���Ȃ����{�ɔ_���͂������������A����Ă������B
�@���������̂��ƂŁA���h�Љ��`�҂ƃ��V�A�A��̋��Y��`�҂ɂ���ċ��Y�}���ݗ����ꂽ�B���Y�}�̓^�i�[�`���͂̎����A�y�n�̒D���i���A��O�̎x�����g�債�Ă������B
�@���{����̘J���ҁA�_���̗����A���Y�}�̉^���̊������A�N���A�`�A�l�A���[�}�j�A�l�A�X���o�L�A�l�̕����E�Ɨ��錾�ɂ���ĘA�������͊�@���}�����B
�@�Љ��}�ł́A�P�Ɛ������A����������̗��E�_�����_���ƂȂ����B�E�h�͐��{����̗��E���A�����h�A���h�͒P�Ɛ������咣�������A�ŏI�I�ɂ͒����h�N���t�B�ɂ���Ăɂ���āA�Љ��}�t���������ĘA�����{���ɂƂǂ܂邱�ƂɂȂ����B
�@�������ĂP�X�N�P���ɂ́A�J�[���C�}���h�A�u���W���A�}�i�}�A���_�Ɠ}�A�Љ��}�̎l�}����Ȃ�x�����P�C�V���t�����܂ꂽ�B�Љ��}�͂P�P�̊t�����R����b�͂��߂S�t�����߉e���͂傳�����B�_�Ƒ�b�ɂ͏��_�Ɠ}�}��i�W���^�[�f�B�E�T�[�{�[���A������b�ɂ͋��Y�}�ɔᔻ�I�ȃi�W�E���B���c�F���o�p���ꂽ�B����́A�_���̕s�����ɘa���A�}�i������J���ґ�O�Ɉ��̏����������A�����ł͋��Y�}�A���h�ɑ��Ă͑Ό�����p���𖾂炩�ɂ������̂ł������B
�������Ћ������Ɗv�����{�̎���������
�@�x�����P�C�����̂��Ƃœy�n���z�@���悤�₭���z���ꂽ�B�Q�S�z���h�i�P�P�T�����j�܂ł̓y�n���L���F�߂��A������镔���͔����グ���A�y�n�̂Ȃ��_���ɂT�`�P�O�z���h�i�Q.�X�`�T.�W�����j�����z����邱�Ƃ��K�肳��Ă����B�������A���v�͎��{����Ȃ������B
�@�܂����{�̌����u�Ɛ��Ƃ̎Љ�v�����L�҂̋�����R�ɂ����Ē��~����A�J���҂̗v���͂W���ԘJ�����ȊO�ɂ͂ȂɈ�������Ȃ������B����ɑ��ĘJ���҂́A���͂Ŋ�Ƃ���o�c�҂�ǂ������ĎЉ�𐋍s�����B���Y�}�́u�J�[���C�́g�l�����a���h�͎��{�̎x�z�̕ό`�ɂ������A���Ƃ͈ˑR�Ƃ��ėL�Y�K���ɂ��J���ҍ��̓���ƂȂ��Ă���v�Ƃ��āA�J���ҁA���m�A�_���^�i�[�`�����͋@�ւƂ��đg�D���邱�ƁA�v�����^���A�[�g�̊v�����͂��������邱�Ƃ�i�����B
�@�Љ��}�w�����͋��Y�}���ɍU�������B�����h�̃N���t�B�́A�c��ɂ����鉉���ŁA�u�����́A�K���I�����ƊK�������Ƃ�����i��p�������͂Ȃ��B�c�c�����́A���ׂĂ̐l�X���A�K���I���Q�𗣂�Ă������x�����邱�Ƃ����҂���v�i�֓����A�u�n���K���[�E�\���F�g���a���v���j�w�����Q�S�S�����j�ƍ����Z�a��i�����B�����ĎЉ��}�͍H��苒����т����鋤�Y�}����A�J���g���ƃu�_�y�X�g�J���҃^�i�[�`���狤�Y�}����r������悤�w�߂����B�������A�ő�̘J�g�ł���S�|�A�����J�g�Ȃǂ��狑�ۂ��ꂽ�B
�@���������̂��ƂŁA���{�͋��Y�}�̉e���͂̊g���j�~���邽�߂ɖ\�͓I��i�ɑi�����B���{�̓x�[���E�N�����͂��ߋ��Y�}������ߕ߁A�@�֎��ւƂ����B
�@�������A���{�̋��Y�}�e���̓n���K���[�S�y�ɍR�c�̗����ĂыN�����A�����e�n�ōR�c�̃f����W����������B�u�_�y�X�g�ő�̃`�F�y�������H��̈ꖜ�l�W��ł͋��Y�}�����ߕ���v������ƂƂ��ɁA�S�H���\�҉�c�J�Â��Ăъ|�����B����͎�����A�I�N�̌Ăъ|���ł������B���ƘJ���҂͊č����P���A���Y�}���̎ߕ���v���A����J���҂̓X�g���C�L�ɓ˓������B���Y�}�������S�Ă̐V���̔��s�͎~�܂�A���Y�}�n�̕����J���҂͌��W���n�߂��B
�@���{�ɂ��͂�J���҂̓�����j�~����͂͂Ȃ������B���t�͑����E���ĎЉ��}�ɐ�����������B�������A�Љ��}�͒P�ƂŐ�����������l���͂Ȃ������B�ނ�͐��{����̑ސw���咣����E�h�Ƌ��Y�}�Ƃ̘A����v�����鍶�h�̑Η��̒��ŗh�ꓮ���Ă������A�ŏI�I�ɂ͍��h�̗v��������āA���Y�}�Ƃ̍����ɂ��V�������������邱�Ƃ����߂��i�A���A�E�h�̎w�����̈ꕔ�͍����ɂ�鐭���ɔ����ė��}���A�S�����邢�͔����Y�}�^���𑱂��邱�ƂɂȂ�j�B�����Ƀu�_�y�X�g�J���҃^�i�[�`����������F���A�Љ��}�����h�̃K���o�C���c���Ƃ���V���{���u�v�������]�c��v����������A�n���K���[�E�^�i�[�`���a�����錾���ꂽ�B
�@�v�����{�̓}�h�ʍ\���́A�Љ��}�P�X���i�E�h�U�A�����h�W�A���h�T�j�A���Y�}�P�R�A���}�h�Q���ł���A�Љ��}���������߂��B���Y�}����̓x���E�N�[�����O���l���ψ��ɂȂ������l���ψ��㗝�����������B�i���J�[�`�͋���l���ψ��㗝�A���R�[�V�����H�l���ψ��㗝�A�T�[���g�E�x�[���͌R���l���ψ��㗝�Ȃǁj�B
�@�������Ċv�����{�́A�u���W���A�}�i�h�̖v���ƎЉ��}�̋��Y�}�ւ̐ڋ߂ɂ���ĕ��a�I�Ɏ��������B�������A���x�z�K���͊��S�ɑœ|���ꂽ�킯�ł͂Ȃ��������A�E�h�𒆐S�Ƃ���Љ��}�͈ꎞ�I�Ɍ�ނ����ɂ����������̋@������������Ă����B�܂��鍑��`�����͕��͊����J�n�����B
�@�v�����{�͒����ɎY�ƁA�y�n�̍��L���A�ԉq���̑g�D���ȂǘJ���ҍ��ƌ��݂ɒ��肵���B�Y�Ƃ̍��L���ɂ��ẮA�R������S���ɂ����ĂQ�O�l�ȏ�̘J���҂�L����H�ƁE���Ƃ������ō��Ƃɐڎ����ꂽ�B�����̊�Ƃ͘J���ҁA�E���̒�����I�o���ꂽ�o�c�]�c��Ɛ��{�C���̐��Y�ψ��Ƃɂ���Čo�c����邱�ƂɂȂ����B�y�n���L���ɂ��ẮA�y�n�Љ�@�����z����A�P�O�O�z���h�i�T�V�����j�ȏ�̓y�n�͉ƒ{�E�_��Ƃ������Őڎ�����A�n��I�y�n���L�҂͈�|���ꂽ���A�������n�_�i�P�O�O���l�ȏ�𐔂����j�͓y�n�����Ȃ������B�y�n�́A�_���ɕ��z���ꂸ�ɍ��c�_��ɂȂ����_�Ɛ��Y�����g���Ɉ����n���ꂽ����ł���B
�@���[�j���́A�n���K���[�̎w���҂ɑ��āA���}����摖������Ȃ��悤�ɒ��������B�ނ́A�Љ��`�̌��݂́u���Ȃ蒷���ߓn����K�v�v�Ƃ��邱�ƁA�Ȃ��Ȃ�A�u���Y��g�D�������邱�Ƃ͍���Ȃ��Ɓv������ł��邾���łȂ��A�u���u���W���A�I����уu���W���A�I�o�c���@�Ɋ��ꂽ�K���̑傫�ȗ͂́A�����́A�˂苭��������ʂ��āA�͂��߂č����ł��邩��ł���v�i�u�n���K���A�̘J���҂ւ̈��A�v�j�Ƒi�����B�������A���̒����͌ڂ݂��Ȃ������B
�@�����A�Љ��}�����Y�}���n���K���[�����V�A�Ɠ��l�ɒx�ꂽ�_�����Ƃł���Ƃ������l�������ɋ@�B�I�Ɂu��K�͌o�c�v���Ɏ������悤�Ƃ����B�ނ�͂܂���y�n���L��苒�������g����g�D���Ă������_�ƘJ���҂̓������ߑ�]�����Ă����B�ނ�́A�y�n�̍��L���������Ĕ_�Ɛ���ł̓��V�A�̃{���V�F���B�L�̂�������i��ł���ƕ]�����Ă����̂ł���B�����A���̐���͏��_���̊v�������ւ̔�������ыN�����A�����h�֑���v���ƂȂ����B
�������Љ���`�҂̓��h�Ɗv�������̕�����
�@�鍑��`�����͊v���������֔g�y���邱�Ƃ�����A�n���K���[�ɑ��Čo�ϕ������s�����B�t�����X�̓`�F�R�A���[�}�j�A�����������ĕ��͊��ɏo���B���{�͐ԌR���ĕҐ����Ċ��R�̕�͖Ԃ�ł��j��A�X���o�L�A�ɐi�������B�n���K���[�ԌR�̐i�U�Ɍĉ����ăX���o�L�A�ł͊v�����������܂ꂽ�B
�@�����������g�̎����ɎЋ�������̏��߂Ă̑S�����J���ꂽ�B�������A���͎Љ���`�҂Ƌ��Y�}�Ƃ̑Η��𖾂炩�ɂ����B�E�h�A�����h�̎Љ���`�҂́A���[�j���́u���̂������ƂȂ����Љ��`�҂̂�������A���u���W���A�W�[�̊Ԃɓ��h�����ꂽ��A�e�͂Ȃ����h��������ׂ��ł��v�i����j�Ƃ����莆���������ɏo���āA���Y��`�҂͐��{�̕�����A�Љ���`�҂��U�����Ă���Ɣ����B�ނ�́A�u���W���A�����`�̊�b�̂����ɁA�t�����X��C�M���X�ȂNj��������ƌ����āA���ƍĕ҂��s�����Ƃ��Ă����B���ǁA���҂̑Η��͉������Ë��ɏI������B����́u�n���K���[�Љ��`�E���Y��`�J���ғ}�v�Ƃ������̂ɏے�����Ă���B������@�ɉE�h�͓Ǝ��������߂Ă����̂ł���B
�@��͋}���Ɉ������Ă������B�������͐ԌR�̋��E���ւ̓P�ނ�v�����Ă����B�n���K���[���{�͂�������ꂽ���i�P�ނɂ���ăX���o�L�A�v�����{�͕����j�A���R�̓n���K���[�����ɋ��������B��������ł́A�����h�ɂ�锽�v�������������ƂȂ�A�ނ�͕x�_�̔����A�n�����s�ʼn����h��m���̊����Ȃǂ��Ăъ|�����B
�@���Ԃ���]�I�ƂȂ钆�ŁA�Љ���`�҂͘J���g���w���҂���Ȃ�Վ����{�Ɍ��͂�����悤�ɔ������B�x���E�N�[���A�����h���[��͖S�������B�������ĂW���P���A�n���K���[�E�^�i�[�`�����́A�P�R�R���ɂ킽����j������B
�@�v�������ɑւ���ĉE�h�Љ���`�҂̃y�C�h������ǂƂ���u�J���g�����{�v�����������B���{�́u�����Ɓv���ߕ����A���Y�}���̑ߕ߂��w�������B��Ƃ̍��L����p�~���A���L���Y�̕�����錾�����B���������������̏��F�邱�Ƃ��ł����A���[�}�j�A��̌R�Ɏx�����ꂽ�����h�̃N�[�f�^�ɂ���đœ|���ꂽ�B�Љ���`�҂̒P�Ɛ����́A�����h�ɑ��ĉ��̒�R�������A�킸���S���ŕ���A���̌�̃z���e�B�̌R���ƍقւƂȂ����Ă����̂ł���B
�@�v����������𑣐i�����̂́A�}�i�I�_�Ɛ���̌�����ł͂Ȃ��A�g�D�I�ɋ��Y�}����̂ł��������Ƃ��傫�ȗv���ƂȂ����B�Љ��}�Ƃ̍����́A���Y�}���Љ��}�̒��ɋz�������������錋�ʂƂȂ����B�P�X�N�̂͂��߂ɋ��Y�}�̉e�������債�����ł��}���͂킸���ɂP���`�R�A�S���l�ɂ����Ȃ������B����ɑ��ĎЉ��}�̓}�����͐�O�ɂ��łɂP�O���l�ɒB���Ă����̂ł���A�������O�ɂ͂W�O���𐔂����i�H��v�ݎq�A�u�n���K���[�v���j�����v�j�B�����ĘJ���g���͉E�h�̉e�����ɂ������B
�@�܂��A�}�ƃ^�i�[�`�Ƃ̊W�ɂ����Ă��A�}�ƃ^�i�[�`�̊W�͂����܂��Ȃ܂܂ɂƂǂ܂����B�Ƃ�킯�_���ł́A�}�̑g�D�̓^�i�[�`�Ɍ����肳��A�Ǝ��̑g�D���Ȃ��A�������s���Ă��Ȃ������B���Y���Ǘ��A�w������������������E��̘J���҃^�i�[�`���A�J���҂̖��n���Ȃǂňꕔ�͋��Ǘ��҂⋌���L�҂����Y�Ǘ���Y�ψ���̃����o�[�Ƃ��ĂƂǂ܂������߁A�J���ҊǗ��͌`���I�ɂ����@�\���Ȃ������B�J���҃^�i�[�`�A�_���^�i�[�`���v���I�Ȏw�����������Ȃ������̂ł���B����́A���V�A�v���Ń{���V�F���B�L���\���F�g���ł̂˂苭�������ɂ���āA��O�ւ̉e���͂��g�債�A�x�����l�����Ă��������ƂƑΏƓI�ł���B
�@�n���K���[�v�������́A�鍑��`�̌R���I���A�_���̗����A����ɂ͎Ћ��̓��a����`�ɂ���ĕ����B�R�~���e����������́A�u���Y��`�҂͂���ł��n���K���[�E�\���F�g���a���̋��P���킷��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�n���K���[�̋��Y��`�҂Ɖ��ǎ�`�҂��A���������߁A�n���K���[�̃v�����^���A�[�g�͑傫�ȋ]�����͂�����v�Ǝw�E���Ă���B���̋��P�́A�u���ǎ�`�y�сw�����h�x�̐���Ɗ��S�ɁA��ΓI�ɐ≏����K�v������v�Ƃ̃R�~���e�������������ɔ��f���ꂽ�B�������A�n���K���[�v���̍��܂̋��P�͐�������邱�ƂȂ��A��ɃX�^�[�����̐l�������p�̂��ƂŌJ��Ԃ����̂ł���B
|
�T
�Ж��Ƃ̋�����`�ɓM��A���v���ɔs�k
���ƃU�N�Z���A�`���[�����Q���̘J���Ґ��{�̌o�� |
�������U�N�Z���J���Ґ��{�̐���������
�@�P�X�Q�R�N�A�h�C�c�����̃U�N�Z���A�`���[�����Q�����B�ō��h�Љ��}�Ƌ��Y�}�A���ɂ��u�J���Ґ��{�v���������Œa�������B�h�C�c�͏��B�̘A�M�Ƃ����`�Ŋe�B���Ƃɒn�����{�������A���Ȃ�傫�Ȍ����������Ă����̂ł���B���̎ЁA���A���ɂ��u�J���Ґ��{�v�̐���ƍs���́A�u����A�������v�̓����������Ă���B
�@�Q�R�N�̏t����Ăɂ����ăh�C�c�̊K���Η��͐�s�������B�A�����ɂ��Ս��Ȕ����̓h�C�c�����ɑ傫�ȕ��S�������炵���B�܂��A�t�����X�̃��[����̂��߂����āA�h�C�c�ƃt�����X�ْ̋��������������A�����ł͔����I������`�I�g�D��R����`�I�g�D�̊����������ƂȂ��Ă������B
�@�X�����ɂ̓X�g���C�L�^���������ƂȂ����B�x���������̑��̓s�s�̋Q��s�i�͌x�����Ƃ̏Փ˂ɔ��W�����B�����A�j�������x���N�ł͕����t�@�V�X�g�Ɩ�����`�c�̂��f�����s���A�L���X�g�����ł͔@�́u�������h�R�v�̔������N�����B���̎��������������Ƃ��ăG�[�x���g�哝�͔̂�펖�Ԃ�錾���A�S�s�������Q�X���[���h���Ɉς˂��B����͘J���җ}���̔����ϔC����R�����[�[�N�g���R�ɗ^�������Ƃ��Ӗ������B
�@�������������܂�Ȃ��A�P�O���A�U�N�Z���B�ŎЉ��}���h�̃c�@�C�O�i�[����ǂƂ���ЁA���A�����{�\�\�T�l�̍��h�Љ��}���ƂQ�l�̋��Y�}���\�\�����������B�U�N�Z���B�ł͂��łɎЉ��}�Ƌ��Y�}���c��ő����h���߂Ă������A���Y�}�����t�ɓ��ݐ�������ł���B
�@���Y�}�̓��t�́A�J���҂��t�@�V�Y���I�������͂Ƃ̓����Ɉ�������邽�߂��Ƃ��ꂽ�B���Y�}�w�����ł������u�����h���[�͌�ɏq�ׂĂ���B
�@�u�U�N�Z�����{�ւ̂����̓��t���A�����̃t�@�V�X�g�ƍق̑ς�����Ƃ���łȂ����Ƃ͖��炩�ł������B�����́A��̊ϓ_������t����Ă��B���́A�������ɂ���邽�߂ɁA���́A���̒n�ʂ����̎��s������ɂ���āA�܂�t�@�V�Y���ɂ���čU�����ꂽ�ꍇ�A���̒n�ʂ̗i���ʂ��āA�]���A��蓱����Ă����Љ��}�n�J���ґ�O��ނ�̎w���҂���藣�����ƁA����э��@�I�ɐ��������U�N�Z���ƃ`���[�����Q�����{��i�삷�铬���Ƃ��Ďn�܂������̓����ɔނ����������邱�ƁA�Ȃǂ̉\���ݏo�����߂ɁA������̌��͓I�n�ʂ���肾�����Ƃł������v�i�u������Ɠ}�̎��̔C���v�A������v�ҁA�w�}���N�X��`�v���_�j�E�R�x�j
�@�c�@�C�O�i�[���{�́A��������a����h�q����u�}�����ꂽ���ׂĂ̋ΘJ�ґ�O�̐��{�v�ł���Ɛ錾�����B
�@�c�@�C�O�i�[�͔������R���ƍقɑR���ׂ��A���C�}�[���u���@�i���ړI�Ƃ������a���h�q�ً}�R��n�݂���v�Əq�ׂ��B
�@����ƂƂ��Ɍ��肳�ꂽ���Ƃ́A�W���ԘJ�����ȂǘJ���҂̌�������邱�ƁA�o�ϓ����ψ���𐭕{�@�ւ����F���邱�ƁA���ׂĂ̐��N�Ɋw�K�̌�����F�߂铝��I�P���w�Z���x�̌p���A�E�Ɗw�Z��n�����邱�ƂȂǂł������i�㐙�d�O�Y�A�w�h�C�c�v���^���j�E��x�j�B
�@�������A�c�@�C�O�i�[�́A�ً}�R�̑n�݂͂��Ƃ��A���{�̍��{�I�ȗ��Q�ɐG���悤�ȉ��v�͍s��Ȃ��������A��������J���Ґ����h�q�̂��߂̐����ȂɈ�{�C�Ő��s���Ȃ������B
�@�U�N�Z���ɑ����āA�`���[�����Q���ł��Љ��}�Ƌ��Y�}�ɂ��J���Ґ��{���������ꂽ�B���{�͘J���҂̕�������g�D���āA�n���x�@�ƌ������͂���A�G�[�x���g�哝�̂́u��펖�Ԑ錾�̓P��v�u���ׂẴt�@�V���c�̂̕��������v���f�����B
�������R���I�e���ɂ�鐭�{������
�@����ɑ��āA�u���W���A�W�[�̓U�N�Z����`���[�����Q���̎ЁA���A�����������܂��Č��߂����C�͂Ȃ������B���h�R�͓��v���C�Z���ƃV�����[�W�F������̂��Ⴊ�����̔��o���֎~���A�U�N�Z�������ċQ���Ԃ����肾�����B
�@�U�N�Z���̍��h�R�i�ߊ��~���[���[�̓U�N�Z�����{����B�x�@�R�ɑ���w�����D�������A�t�@�V�X�g��N���`�҂���Ȃ锽�v�������̑����������Ȃ����B
�@�����Ē������{�ƌR���́A���͂ɂ���ăU�N�Z���A�`���[�����Q���̎ЁA��������œ|���邽�߂ɌR���𗼏B�ɔh�������B
�@�������c�@�C�O�i�[�́A���h�R�̐i���̖ړI���u�����I�ȁv��Ԃ����邽�߂ł���Ƃ����ʍ����Ă����ɂ�������炸�A�R���ւ̃U�N�Z���i�U�̓o�C�G�����̋ɉE�����h�̐i����j�~���邽�߂ł��邩�ɋU�����B�������{�A�R���ɂ�锽�v���ɑ��āA�c�@�C�O�i�[�Љ��}�����͓����ӎu�ȂǏ������������킹�Ă��Ȃ������̂ł���B
�@�R�����U�N�Z���ɐi�����J�n�������ɃU�N�Z�����{�̏��W�ŊJ���ꂽ��c�i�P���j�b�c��c�j�ł��A���̂��Ƃ͖��炩�ɂȂ����B���̉�c�́A�o�c���c��A�o�ϓ����ψ��̂ق�����g���A���t�@�b�V���s���ψ���A���Ǝ҂̊e��\�A�J���g���������Q�������B�����҂͌R���ƍقɔ����铬�����ɊJ�n����K�v�����������A�U�N�Z�����{���A�����߂ƍ��h�R�̋����ɔ����A�[�l�X�g���Ăт�����悤�v�������B
�@�������A�Љ��}�̘J����b�̓[�l�X�g���c��ɂ��邱�Ƃ����ۂ��A��������Ɋւ��ē��c�𑱂���Ȃ�Αޏꂷ��ƈЊd�����B����ɑ��ċ��Y�}�̃u�����h���[�́A�[�l�X�g�͑S���v�łȂ���ΈӖ����Ȃ��Ɣ����������A���Ƃ��Ƌ��Y�}���^���ɔ������͂Ɠ����C�ȂǂȂ������̂ł���B�������ă[�l�X�g�͑��肳��ꂽ�B
�@�U�N�Z���ɐi�������R���́A�U�N�Z�����{�ɑސw�𔗂����B�c�@�C�O�i�[���{�͂�������ۂ����B����ɑ��đ哝�̃G�[�x���g�́A���@�̋K��Ɋ�Â����{�̉����𖽗߂��A�����Ĕ����Ƃ��Ēm��ꂽ�l���}��c�m���U���Z���B�����ٖ����ɔC�������B����ɑ����ă`���[�����Q�����{�����Y�}�̑�b�̎��E�����v��������B��̐��{�͒�R���Ȃ��ɔs�k�����̂ł���B�����{�����A���Y�}�͔@�����ꂽ�B
���������Y�}�̎Љ��}�Ƃ̋���������
�@�u�����h���[�́A�����̔s�k�̌����͎Љ��}�̗���ƘJ���ґ�O�̈ӎ��̗����x��ɂ������Ƒ��������B
�@�u�Љ��}�\���Y�}���{�ւ̍U���́A�v�����^���A�[�g�ƍق̂��߂̓����̎n�܂�ƂȂ�͂��ł������B�����͂����B�����邽�߂ɁA�}�Ƃ��Ă����鎎�݂��������A���̎��݂͍��܂����B�Ȃɂɂ���Ă��H�@�U�N�Z���ɑ��鍑�̎��s���͂��ʍ����ꂽ����I�u�ԂɁA�Љ��}�w�����Ɍ�蓱���ꂽ�Љ��}�n�J���҂��܂��A���̍��̎��s���͂ɑ��Č��R���镐���������s���p�ӂ��Ȃ������Ƃ������Ƃɂ���č��܂����̂ł���B�L���Ȃ������������P���j�b�c��c�́A���̂��Ƃ��܂�������R�Ǝ������B���̉�c�ł͎��̂悤�Ȃ��Ƃ��N�����B�o�c���[�e�A�܂�o�c�̃v�����^���A�̂X�O�p�[�Z���g�́A�Љ��}�}���ǂ������\�t�I�g���b�N�������邳�܂�Â��ɌX�����A�U�N�Z���ɑ��鍑�̎��s������́A�U�N�Z���Ɍ�����ꂽ���̂ł͂���Ȃ��A�o�C�G�����ɑ��铬�����U���������̂ɂ����Ȃ����̂Ɖ����ׂ��ł���Ɣނ�͌�邱�Ƃ��ł����v�i���O�j
�@�Љ��}���������͂ƓO��I�ɓ������Ȃ��Ƃ������Ƃ͖��炩�ł������B�c�@�C�O�i�[�Љ��}���{�̉��ł̊Ǘ��ψ���͎��{�̒f�ł���K�����s�킸�A�܂��J���҉�c����������ׂ�̋@�ւɂ����Ȃ������B���{�͌���ł͘J���҂̂��߂̐�����搂��Ȃ�����ۂł͌x�@�����Ǝ҂̃f�����ɑ��Ĕ��C����ȂǁA�J���҂̑�O�^���ɑ��Ēe�����������Ă����̂ł���B
�@�J���҂̊v���I�����������c�@�C�O�i�[�Љ��}���A�������͂̍U���Ɠ������ѓO�����Ȃ����Ƃ͕����肫�������Ƃł������B
�@�u�����h���[�͘J���ґ�O���܂��Љ��}�̓��a����`�̉e���̉��ɒu����A����̊K���I�C�������o���Ă��Ȃ������Ƌ������Ă���B�������A�c�@�C�O�i�[�Љ��}������J���҂̂��߂̐��{�Ƃ��Ĕ������Ă����̂͋��Y�}���g�ł������B�ނ�͘J���҂Ɏ��{�̎x�z�̑œ|�Ɍ������������Ăт����A�g�D����̂ł͂Ȃ��A���{�̂��Ƃł̔����ԘJ�����̖h�q�Ȃǂ́u���ԓI�v���v�ɂ��āA���̂��߂̎Љ���`�҂Ƃ̓������ɂ��J���Ґ��{�ɂ��Ă�����ׂ肵�Ă����B
�@���Y�}�͘J���Ґ��{�̂��߂̓����ɂ��Ď��̂悤�ɏq�ׂ��B
�@�u�J���Ґ��{�́A�v�����^���A�[�g�ƍقł��Ȃ���A�܂�����ɂ����镽�a�I�A�c���`�I�Ȓi�K�ł��Ȃ��B����͘J���ҊK�����v�����^���A�I���@�ւƃv�����^���A�I��O�^���Ɏx�����Ȃ���A�u���W���A�����`�̘g�̂Ȃ��ŁA�܂��Ȃɂ����܂��������i�Ƃ��āA�J���ғI����𐋍s���悤�Ƃ��鎎�݂ł���B�c�c
�@���Y�}�͘J���Ґ��{���A���݂̒i�K�ł̓v�����^���A�[�g�̐����̂��߂̓����������ł���B��̐��{�Ƃ��āA�u���W���A���{��A�����{��Љ���`���{�ɑΒu���邪�A�u���W���A�W�[�ɍ~�������Ƀv�����^���A�[�g�̗��Q���\�ł��鐭�{�́A���ꂵ�����肦�Ȃ��B�c�c�B
�@�J���Ґ��{�ւ̎Q�������Y�}�ɂƂ��ĈӖ�������̂́A�v�����^���A�[�g�̊v���I�ڕW���]���ɂ�������ł��Ȃ���A�k�v�Ȃ�����p�I�ȃ}�k�[���@�[�ł��Ȃ��A���ǎ�`�I�J���ҏ��}���u���W���A�K�����番�����A�v�����^���A�[�g�̓���I�v���̂��߂ɋ��Y��`�҂ƂƂ��ɓ������Ƃ�e�F���閾�m�Ȉӎu�������ꍇ�ɂ͂��߂Đ������邻���̏��}�Ƃ̋��������ւ̗p�ӂȂ̂ł���v�i�h�C�c���Y�}�攪����ō̑����ꂽ�e�[�[�A�w�}���N�X��`�v���_�j�E�R�x�j
�@���Y�}�̓u���W���A�����`�̘g���Ńu���W���A���ƂɈˑ����Ȃ���A�u����I�v���v�̂��߂̓�����i�������̂ł���B�J���҂ɑ��āu����ꂪ�ӔC�������Ă���̂́A�B�c��̑����h�Ɩ@�ɂ������Ăł���v�ȂǂƂ���u���W���A�����`�ɂ��Č��z������Ă����Ȃ���A�J���҂̊K���I�ӎ��������x��Ă������߁A�U�N�Z�����{������������Ȃ������ȂǂƂ����̂́A�܂������̋\�Ԃł������B���Y�}�̓��a����`�����J���҂̊K���I��������̂��Ă����̂ł���B
���������a����`�I�ȘJ���Ґ��{�j�́�����
�@�u�����h���[�́u�U�N�Z�����{�ւ̋��Y�}���̓��t�́A�u���W���A���a������E�p���āA�v�����^���A�[�g�x�z�̂��߂̓����Ɉڂ邽�߂̈���ł������v�ƌ�Ɍ�������A���t�̕��j�̓R�~���e�����̎w���ł��������B
�@�R�~���e�����̓U�N�Z���̌o�������A�u���t�̈Ӗ��́A����ɌR���I�E�����I�ȔC���v�ɂ������Əq�ׂĂ���B�R�~���e�����́u�x���Ƃ��S�Ȃ����U�T�Ԍ�Ɍ���I�Ȏ��_������Ƃ�����]���̂��ƂɁA���ږ𗧂Ă��邠����w�n���ɐ苒�v���A�T�Ȃ����U���l�̕������������邱�Ƃɂ���ĖI�N���A�S���I�ȖI�N�ɔ��W�����Ă����ƓW�]���Ă����̂ł���B
�@�U�N�Z���̌o���������R�~���e�������c�́A�u�}���̂܂��Ȃ��ׂ����Ƃ́A�J���҂̕����̖���e�͂Ȃ���N���邱�Ƃ������B�J���Ґ����Ɋ֗^�������̎�����A�v�����^���A�[�g�̕����ȊO�̃e�[�}�́A�}���ɂ����Ă͂Ȃ�Ȃ������v�Ƃ��āA�U�N�Z���́u�����v�̔s�k�̓h�C�c���Y�}�w�������J���҂̓����̈ӗ~��]���ł��Ȃ��������ƁA����̏����A�J���҂�I�N�Ɍ����đg�D�����銈����ӂ������߂ł���Ɣᔻ�����i�u�U�N�Z���̎����ƃn���u���O�̓����v�j�B
�@�����A�����̃U�N�Z�����{���v���I�I�N�̏o���_�ɂȂ�Ƃ����̂́A�R�~���e�����̎�ϓI��]�ł������B�[�l�X�g��ے肵���P���j�b�c��c�̓̕������x�ꂽ�n���u���O�̋��Y�}�͖I�N�������A�킸���R�S�l���炸�̌Ǘ����������ɏI������B
�@�U�N�Z���̔s�k�̓h�C�c���Y�}�w�����̖I�N�����Ɍ���ꂽ�g�D�I�Ȍ��Ƃ��������Ƃɂ͂Ȃ������B����̓c�@�C�O�i�[���{��J���҂̂��߂̐��{�ł��邩�ɔ������A�ނ�Ƌ������A��ꂠ���Ă������ƂɎ��������a����`�I�����̌��ʂł������B
�@�����Ă��̓��a����`�́A�Y��`���}�Ƃ̘A�����u�J���Ґ��{�v���f�����R�~���e�����i�g���c�L�[�A�W�m�r�G�t���哱�I�������ʂ������j�̓�������p�ƌ��ѕt���Ă����B�R�~���e�����̓u���W���A���}�ƎЉ��}�̘A���ɑR����u�����E�o�ς̕���ɂ�����S�J���Ґ��}�̈��A���v�Ƃ��Ă̘J���Ґ��{�̂��߂̓����́A�L�͂ȘJ���҂��v���I�����Ɍ��W���Ă��������ł���Əq�ׂ��B
�@�����A���{�ƈ�̓��a����`��O��I�ɖ\�I���A�J���҂��v�����}�ɑg�D���Ă����Ƃ������{�I�ȔC����������A�Љ���`�҂Ƃ̓������A�A����Nj�����Ȃ���̐��{�́A���ǎ�`�I�ȁA���邢�͎Љ���`�I�Ȑ����ɂ����Ȃ肦�Ȃ��ł��낤�B�v�����}�ɂ��J���ґ�O�̊l����ʂ��Ċv�������{�I�ɏ�������Ƃ����ۑ���A�Y��`���}�Ƃ̘A���ɘc�Ȃ�����������p���u�����h���[��̓��a����`�ݏo�����̂ł���B
|
�U
�u���W���A�Ƃ̋��������i�ߍ���
���t�����X�l��������{�̌o�� |
���������t�@�V�Y���l������̌���������
�@�P�X�R�O�N��̐��E���Q�ƃt�@�V�Y���̑䓪���錃���̎���ɁA�t�����X�ł́u���R�ƕ��a�ƃp���v���X���[�K���Ƃ��āA���I���E�u��������ǂƂ���Љ�}�l��������{���a�������B�t�@�V�Y������̖h�q�ƃp���l���̂��߂̋��Q�̍�����ڎw�����u���������́g�����h�̔j�]�́A�u���a�Ŗ���I�ȖL���ȓ��{�v�Ƃ������Y�}�̖���A�������̈�̏����̎p�������Ă���Ƃ����悤�B
�@�u���������݂�������̂ƂȂ����̂́A���t�@�V�Y���̉^���ł������B���Q�̂��Ƃł̍����̋��R�A��ʎ��Ƃ�w�i�Ƀt�@�V�Y�����䓪�A�h�C�c�ł̓q�g���[�����͂����������B�t�����X�ł��u�̏\���c�v�Ȃǃt�@�V�Y���I�E�����͂��e���͂��L���A�����Ƃ̏Փ˂��J��Ԃ����B���������̂��ƁA�l������^���́A�E���I���͂ɑR���āA���a�Ɩ����`�A���������h�q���f�������t�@�V�Y���^���Ƃ��č��g�����B�R�T�N�V���A�u�p���ƕ��a�Ǝ��R�v�̃X���[�K���̂��ƂɁA�Љ�}�A���Y�}�A�}�i�Љ�}�A�J���������A���t�@�V�X�g�m���l�Ď��ψ���ȂǂT�O�ɋ߂��c�̂̂��ƂɂT�O���l���Q�����āA���ĂȂ���K�͂ȃf�����p���ŌJ��L����ꂽ�B
�@���̃f���̒���ɊJ���ꂽ�R�~���e�����掵����ŁA�f�B�~�g���t�́u�T�O���̐l�X�̎Q�������V���P�S���̃f���Ƃ��̑��̃t�����X�s�s�ɂ����邨�т��������f���̈Ӌ`�́A�͂���m��ʂقǑ傫���B����͂���ɘJ���҂̓������^���ł��邾���ł͂Ȃ��B����̓t�����X�ɂ�����t�@�V�Y���ɔ�����L�ĂȐl������̎n�܂�ł���v�Əq�ׂ��B
�@�E���̃f���ɑR�����O�s����g�D���邽�߂ɐݗ����ꂽ�u�l���A���S���ψ���v�͂��̌�������𑱂��邱�ƂƂȂ�A�₪�ĎЉ�}�A���Y�}�͂��ߍ����e�}�h�𒆐S�ɕS�߂��c�̂����W�����u�l���A���v���l��������������ꂽ�B
�@�l����������ɂ������čj�̂����ꂽ�B
�@�j�̑O���ł́A�u�p���ƕ��a�Ǝ��R�v�̃X���[�K���̈Ӌ`���Ċm�F����ƂƂ��ɁA�u���̍j�͈̂Ӑ}���đ����K�p�\�ȕ��@�Ɍ��肳���v���Ƃ�搂����B�����I�v���ł́A�t�@�V�X�g�c�̂̕��������A���U�A���_�A�g���^���̎��R�Ȃǂ��f�����B�o�ϓI�v���Ƃ��ẮA���Q�ɂ�莸��ꂽ�w���͂̉A�J�����Ԃ̒Z�k�A��K�͂Ȍ������ƁA���Ɗ���̐ݗ��Ȃǂł���B���L���ɂ��Ă͕���Y�Ƃ����̑ΏۂƂ��ꂽ�����ł������B���Y�}�̃g���[�Y�̓R�~���e�����̉�c�ŁA�L�ĂȔ��t�@�V�Y���l���A���̌����ɐ����������R�́A�u�u���W���A�����`����т��Ď���Ă����v���߂ł������Əq�ׂĂ���B
�@�j�̂����{�̑̐��̘g���ł́g���v�h�ɂƂǂ߂�Ƃ����悤�ɁA�l���A���͌������_�ɂ����Ă��łɖ����Ɍ����Ă̔��W�̌_�@�������Ă����̂ł���B
�@�����������Ō}�����R�U�N�T���̑��I���́A�����̐l���A���h�ΉE���𒆐S�Ƃ��锽�l������h�Ƃ̓����ƂȂ����B���I���̌��ʂ́A�l������h���R�V�R�c�Ȃ��l���A���l������̂Q�S�W�c�Ȃ�傫�����菟�������߂��B
�@�l��������{�́A���}�ƂȂ����Љ�}�Ƌ}�i�Љ�}�𒆐S�Ƃ��đg�D���ꂽ�B���}�ƂȂ������Y�}�͓��t�̗v�������Ƃ�����B����́A�J���҂̊v�����}�Ƃ��Ă̗��ꂩ��ł͂Ȃ������B�ނ�́A���Y�}�̐��{�ւ̎Q�����v�`�u���W���A�����������A�l��������痣���̂����ꂽ�̂ł���B���̂����t�O�ł́u���S�ŋ��łȎx���v�����߂��B
�������l������ɂ��X�g�̗}��������
�@�u�������t�����������Ƃ��A�t�����X�S�y�ł͑�K�͂ȃX�g���C�L�������Ă����B
�@�S���ɂ͒n���ōH��苒���Ƃ��Ȃ����K�͂ȃX�g���C�L���N�����Ă������A�T���P���A�p���n���̃��m�[�����ԍH��̂Q���T��l���͂��߂P�Q���l�̋����J���҂���Ƃ��~�����B�{�i�I�ȃX�g���C�L�̔g�́A���E�A�[�����̍q��@�H��Ń��[�f�[�ɋx�J���҂̉��ُ����̓P������Ƃ߂ăX�g���C�L���s��ꂽ�̂Ɏn�܂����B�X�g���C�L�́A�H��苒���Ƃ��Ȃ��Ȃ���܂������ԂɑS���ɔg�y�����B�X�g�����͂P���Q�O�O�O�A�Q���҂͖�Q�S���l�ɏ�����B
�@�J���҂̓����̍��g�̂Ȃ��ŁA�Љ�}�ō��h�̃s���F�[���́u��͉\�ł���v�A�u���{��`���E�͎��̋�Y�ɕm���Ă���B���܂����V�������E������ׂ��ł���v�Ƌ��B�s���F�[���́A�u�������������{�ɔ�����v���I�Ȑ����ɂȂ肤��Ƃ������z�������Ă͂������A�l�������h�q�I�ȉ^������U���I�ȉ^���ɁA����Ɏ��{�ɔ����铬���ɔ��W�����Ă������Ƃ��āu����\�ł���v�Ǝ咣�����̂ł���B
�@�Љ�}�A�J���������͘J���҂̓����̔��W���Ȃɂ�������Ă����B�X�g���C�L�����̔��W�͎Љ�������������A�}�i�Љ�}���h�����Đ�����������̃u�������{�����ɓ������˂Ȃ��A�ƁB
�@���{���������������A�u�����͘J���҂ɃX�g���C�L�̌����������悤�ɌĂъ|���A�X�g�����E���邽�߂ɘJ���������Ǝ��{���̒���ɏ��o�����B�������đg���^���̎��R�A�����̂V�`�P�T���̈����グ�A�X�g���C�L�Q���҂��������Ȃ����ƁA�J���҂ɂ��@�̑��d�Ȃǂ���ȓ��e�Ƃ���}�e�B�j�������肪���ꂽ�B
�@�Љ�}�����Y�}����������炵�������Ƃ��������B�������A���{�ɂƂ��ċ���́A�J���҂̍U�����������߁A�����̑̐����������邽�߂̈ꎞ�I�ȏ����ł������B
�@�X�g���C�L�����̔��W�����ꂽ�͎̂Љ�}����ł͂Ȃ������B���Y�}���܂��J���҂ɃX�g���C�L����������悤�Ăъ|�����̂ł���B�g���[�Y�͎��̂悤�Ɍ������B
�@�u�����Ȍ��ʂ�����ꂽ��A�������ɃX�g���C�L���I��点�邷�ׂ�m��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B���܂��v���̂��ׂĂ��ʂ����Ƃ����Ȃ��Ă��A�v���̖{���I�ȕ����ɂ����ď��������߂Ă���ꍇ�́A�Ë����邱�Ƃ����m��K�v������̂��B����\�ł���Ƃ����킯�ł͂Ȃ��v�B����ɔނ́A�H��苒�œ����Ă���J���҂ɑ��āA�u�H���苒���A���Y��J���҂̊Ǘ��ɒu���v�ɂ͂���Ȃ��Əq�ׂ��B
�@�g���[�Y�̔������ċ��Y�}�����ψ���͎��̂悤�Ȍ��c�������B�u���̊댯�Ȍ����i��͉\�ł���j�ɂ������āA�����ψ���́s����\�ł���Ƃ����킯�ł͂Ȃ��t�Ƃ������Y�}�̐�����Βu������B�}�̎�v�ȃX���[�K���́A�ˑR�Ƃ��ās���l������̂��߂ɁA���l������ɂ���āt�Ȃ̂ł���v�ƁB
�@���Y�}�ɂƂ��āA�l������͑̐����̉^���ł���A��������z���O�i���Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ł���B�ނ�͘J���҂̓��������{�̑̐��ɔ�����v���I�ȓ����ւƔ��W�����Ă������Ƃ���҂ɑ��āA�J���҂���������Ǘ������钧���ҁA�����`�҂Ƃ��Ĕ����̂ł���B���Y�}�͘J���҂̓����̖W�Q�҂Ƃ��Č��ꂽ�̂ł���
�������j�Y�����w���͊g�吭����
�@���肪���ꂽ��A���{�͗L���x�ɖ@�i�N�ԂQ�T�ԁj�A�c�̋���@�A�T�S�O���Ԗ@�����Ő����������B
�@�u�������{���ł��d����������͌o�ϐ���ł������B�ނ�ɂ��A�o�ϋ��Q�͉ߏ萶�Y�̌��ʂł͂Ȃ��A�ߏ�����̌��ʂł���A��O�̍w���͂̑����ɂ���ċ��Q������������Ƃ����̂ł���B�l������j�̂ɂ��������ău�������{�͑�O�̍w���͂������邽�߂ɁA�S�����Ɗ���̐ݗ���A�_�Ə����������邽�߂̏������c�̑n�݁A�������ƁA�����̌��z�Ȃ��̘J�����Ԃ̒Z�k�����{�����B�u�������{�̐���̓A�����J�̃��[�Y�x���g�̃j���[�f�B�[�����O���ɂ������ƌ����Ă���B�������A�A�����J�̂悤�ȑ�K�͂Ȍ������Ƃ͎��{���ꂸ�A����̒��S�͘J�����Ԃ̒Z�k�ł������B
�@�Љ�}�́A�������Ȃ��̘J�����ԒZ�k�͏A�Ƃł���d�����Ĕz�����邱�Ƃɂ���Ď��Ƃ��������邱�Ƃ��ł��邵�A�����v�傳���Čo�ς����C�Â���Ǝ咣�����i����͌��݁A���Y�}��S�J�A�������グ�Ă��郏�[�N�V�F�A�����O���j�B
�@�����A���̐���́g���Y�R�X�g�h�����������ėA�o������ɂ����B���͊C�O�ɗ��o���A���Y�͒ቺ�����B���{�͗A�o�g��̂��߂ɕ��ݐ艺�������{�����i���łɐ��{�������ォ�瑠���͗A�o�g��̂��߂ɕ��ݐ艺�����s�����Ƃ����Ƃ�����B����ɑ��Ď����̎s�ꂪ�r�����̂������ăC�M���X�͔������B���ǁA�C�M���X�A�A�����J�̍��ӂ̂��Ƃɂ͂R�J����̂X���Ɏ��{���ꂽ�̂����j�B
�@���ݐ艺���ɂ���ď�����͍������A���������͒ቺ�����B�J���҂͂킸���R�J���O�Ƀ}�e�B�j��������œ������v�̔������������B
�@�܂��A�ٗp���g�傳����͂��ł������J�����ԒZ�k���A���̑����ߍ��킹�邽�߂Ɏ��{�͐V���ȘJ���҂��ق������A��l����̐��Y���𑝂₻���Ƃ����B���̂��߂ɐ��{�����҂����悤�Ȍٗp�g��������炳�Ȃ������B
�@�J�����ԒZ�k�ɂ��w���͑��������s�ɏI������̂́A�����̊l���Y�̗B��̖ړI�Ƃ��鎑�{�̑̐���O��Ƃ��Ă������߂ł���B��Ƃ̖ړI�������̊l���ɂ���ȏ�A�����̊g���W����J�����ԒZ�k�̕��S�����܂��Ď����͂��͂Ȃ������B���{�̍w���͑�������͉�݂ɏI������̂ł���B
�@�������āA�킸���ȊԂɃu�����̌o�ϐ���̖��͂��͖��炩�ɂȂ����B
�������u���������̕�����
�@���Ƃ��ƃu���������ɂ͎��{�ƓO��I�ɓ����Ƃ����ӎu�ȂǂȂ������B�u�����͑g�t���O�̓}���Ŏ��̂悤�ɏq�ׂ��B�u��̎Љ�̐��́A�悩�ꂠ������A���̓����Ől�������Ă��鉽���ł���B�����͂��łɌ��̐��̖����A���ׂ�\�I�������A�̐��̓������瓭�������邱�ƁA���ꂪ�����̎����̖ڕW�ł���B�g���N�̓u���W���A�Љ���Ǘ����A�~�����悤�Ƃ��Ă���̂��h�Ƃ����l�����邩���m��Ȃ��B�������A���݂̎Љ�����悫���̂ɕς����邩�ۂ����ŏd�v���ł���v
�@�ނ́A�u���W���A�W�[�ɑ��āu�킪���t�́A�����̎��{��`�I���L�`�Ԃ̊v���I���p�ɂ̂肾���������Ȃ����A�܂����̈Ӑ}���Ȃ��c�c�����̎Љ�̐��Ə��L���x�̘g���ŁA�ǂ̒��x�܂ŁA�ǂ̒i�K�܂ŁA���̎Љ�I�O�i�Ɛl�ԓI���������������邩�A������ؖ����邱�ƂȂ̂ł���v�i�c��ł̉����j�ƁA���{�̍��{�I���v�Ȃ����ƂȂǖѓ��l���Ă��Ȃ��ƕى����A���{�̋��͂�i���Ă���B
�@�����A�u�����̗���͂܂������������Ă���B���{�́g�����v�h�����{�̗��v���������Ă���Ƃ��ɁA�ނ�̋��͂ȂǓ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ�����ł���B���{�́A���{�ɑ��āA�C�O�Ɏ��{�������A���Y���T�{�^�[�W�����邱�Ƃɂ���Ē�R�����B���Y���k���A�ቺ����Ȃ��ŁA���{�̌i�C��͍s���l�܂�A�j�]�����B
�@����A�X�y�C���l��������{�x�����߂����Đ��{���̋T��͊g�債���B
�@�t�����X�Ǝ��������ăX�y�C���ł��l��������{���a���������A�h�C�c�A�C�^���A�̃t�@�V�X�g�����͐l��������{�ɔ����ĖI�N�����t�����R�̔��v�����x�������B�u�����͓����X�y�C���l������x����ł��o�������̂́A�}�i�Љ�}�̋��d�Ȕ��A�C�M���X�̔����ɂ����āA�����ł̓���ƍ��ۋ����̂��߂Ɂg�s������h�ɓ]�����A�X�y�C���̐l�������E���ɂ����B
�@�ΊO�I�ɂ��Γ��I�ɂ����{�̐���͍s���l�܂�A�킸���R�J���ɂ��Ă��͂�u���������́A�O�i����C�͂��������Ă����B�u�����́u�Љ�A�o�ϐ����ɂ����炵��������ȕω��̌�ł́A���̔ɉh�A���N�ɂƂ��ď\���Ȉ���ƃm�[�}���Ȏ�������ɕK�v�ł���v�Ɛl�X�ɒ����ւ̕��A��i�����B����́A�܂��܂������h��u���W���A�W�[�𐨂��Â����邱�ƂƂȂ����B
�@�������Ă��ɂR�V�N�Q���A�ǂ��߂�ꂽ�u�����͐l������̎Љ�A�o�ϐ���́u�x�~�v��錾����Ɏ���̂ł���B�����ĘJ���҂̍w���͂̑����Ƃ���������������Ă������B
�@���̌�A�}�i�Љ�}�̃V���[�^�����t�A��u�������t�ƌ`���I�ɂ͐l������͂R�W�N�S���܂Ōp�����邪�A�J���҂̃X�g�͖����ł������͂��̐��{�ɂ���Ēe������Ă������B���ۓI�ɂ́u�x�~�v�錾�̎��_�Ől��������{�͎��̂ł���B�����đ�u�������������ɒa���������Ă̐l������̖��F�}�i�Љ�}�_���f�B�G�����̂��ƂŁA�l������̃V���{���ł������T�S�O���ԘJ�����͔p�~���ꂽ�B�����Ĕ��v�����t�@�V�Y�����͂��Ăѐ�����Ԃ��Ă���̂ł���B
�@�l������̖��������̌�������a������������Ȃ������B�J���҂��l�������L���x�ɐ��A�J�����ԒZ�k���J���҂̑�O�I�ȓ����̍��g�̌��ʂł������B�����A�J���҂̓����͔��W��������̂ł͂Ȃ��A�t�Ɏ��{�̒����̂Ȃ��ɉ������߂�ꂽ�B�Љ�}�����Y�}���̐����́g���v�h��i���A�J���҂̊K��������}�������B���������Ћ��A�l��������{�̓��a����`�A���ǎ�`�����A�J���҂̒c���Ɠ�������̂��A�����I���͂̔��U���������̂ł���B
|
�V
�u���W���A�����ێ������v�����������
�����Y�}�ƃX�y�C���l����� |
�������l��������{�̐����ƃt�����R�̔���������
�@�P�X�R�U�N�Q���A�X�y�C���̐l��������{���a�������B�����Ă�����_�@�Ƃ��ĘJ���ҁA�_���̓����͋}���ɍ��g���Ă��������A���ǂ͊v���ɂ܂Ŕ��W�������邱�ƂȂ��u���W���A�����̘g���ɉ������߂�ꂽ�B�u���W���A���R��`�h�Ƌ����ɏI�n���A���v���̏������������X�y�C���l��������{�̌o���́A�v�`�u���W���A�}�h�⎩�R��`�I�u���W���A�}�h�Ƃ̘A����搂����Y�}�̖���A�������̏��������Ă���Ƃ����悤�B
�@�Q���̑��I���́A���h���a�}�A�Ћ��Ȃǁu�l������v�ƉE�h���͂́u��������v�Ƃ̑Ό��ƂȂ����B
�@���I����O�ɂ��āA���h���a�}�A�Љ�}�A���Y�}�A�t�f�s�i�Љ�}�n�J�g�j�A�o�n�t�l�i�g���c�L�X�g�n���}�j�𒆐S�Ƃ��āu�l���u���b�N����v�����ꂽ�B���̎�ȓ��e�́A�����Ƃ̎ߕ��A���@��̎��R�̉A�_���ւ̍��Ɖ����A�������H�Ǝ҂ɑ���ł̌y���A�������ƌv��̎��{�Ƃ��������̂ŁA�{���I�ɂ̓u���W���A���ǎ�`���Ȃ����̂ł������B
�@�I���̌��ʂ́A��������̂Q�O�T�c�Ȃɑ��āA�l������h�͂Q�U�W�c�ȁi���h���a�}�P�T�W�A�Љ�}�W�W�A���Y�}�P�V�j���l�����ď��������B����͂���܂őI���ɔے�I�ł������A�i�[�L�X�g�n�J���҂����[�ɎQ���������ʂł������B
�@�������ċ��a�h�ɂ��A�T�j�����{���a�������B�Љ�}�⋤�Y�}�͊t�O�x���ɂƂǂ܂����B
�@�I���̏����Ƌ��ɓs�s�ł͘J���҂͑ҋ����P��v�����ăX�g���C�L�ɗ����オ��A�_���ł͔_���͒n��̓y�n��苒���͂��߂��B����ɑ��āA���{�̓X�g���C�L��s�@�Ɛ錾���A�J���҂̃f����W���e�������B�܂����{�͓y�n�̕��z�v������ۂ��A�y�n�̊l�����߂����_���̉^���͒������ꂽ�B�����n��̕x�͂قƂ�ǎ�����̂܂܉������ꂽ�B
�@�u����v�́A�R���l�̐����Ƃ̎ߕ��A�R���ɂ��J���҂ւ̎c�s�s�ׂ̐ӔC�҂̏�����搂��Ă������A�����Ƃ͈ꕔ���ߕ����ꂽ�ɂ������A�J���҂�e���������R�͈�l�Ƃ��čق���Ȃ������B�J���Ґ��}��J���g���̎x���Ēa�������A�T�j�����{�ł��������A���{�͋������j�ł������u�l���u���b�N����v���ȂɈ�܂��߂Ɏ��s���悤�Ƃ��Ȃ������̂ł���B
�@���{�́u����v���������ł́A�A�ʼnE�������h�Ƃ̑Ë������Nj����Ă����B
�@�V���A�t�����R�̕����I�N�����}�ɁA�E�������h�͊e�n�ň�Ăɔ������N�����B�S���̂T�O�̎�����̂قƂ�ǂ����X�ƃt�����R�x����\�������B�J���Ґ��}�A�J���g���͐��{�ɕ����v�������B�������A���{�͔����̎�����ŏ����A�J���҂ɕ�����x�����邱�Ƃ����ۂ����B���{�͘J���ҁA�_���ɓn�������킪�₪�Ď��������Ɍ������邱�Ƃ�����Ă����̂ł���B���������댯��Ƃ������t�����R�h�Ǝ�����ق����܂��ł���Ƃ��āA���{�͍Ō�܂Ŕ��v���h�Ƃ̑Ë��ɂ���@��肫���Ɋ�]��������B���{�͔��v���h�Ƃ̑Ë��̐��{��g�D���邱�ƂɌ��߁A�E���Ɋt���̈֎q��^�����Ă��s���������ۂ��ꂽ�B
��������d���͂Ɛ��{�ɂ��e��������
�@���v���̖I�N�ɑ��Ĕ����ɗ����オ�����̂͘J���҂ł������B���{�����v���ւ̔������S�O���A�A�őË����Nj����Ă���ԁA�ނ�͏e�C�X��x�@����e���A�����ꂩ��_�C�i�}�C�g�B���A���ɂ��P�����A�����I�R�l��ߕ߂���ȂǁA�R�������v���ɍ�������̂�h�����B�J���҂̂��₢�v���I�ȓ����Ȃ��ɂ́A���a�h���{�͂ЂƂ��܂���Ȃ����v���ɂ���đœ|����Ă������낤�B
�@������Ƃ���ɘJ���҂Ɣ_���́g���́h�����܂ꂽ�B
�@�H�ƒn�т����J�^���j�A�B�i�L�ĂȎ������������{���F�߂��Ă����j�ł́A�b�m�s�i�A�i�[�L�X�g�n�J�g�j�Ƃt�f�s�i�Љ�}�n�J�g�j�̋����ψ���^�A�ƍH�Ƃ����������B�Љ�}�A���Y�}�A�o�n�t�l�A�J���g���̑�\����Ȃ�u���t�@�b�V���s���R�ψ���v���g�D���ꂽ�B�_���ł͔_���ψ�������A�������g�D�ɑ������B�s�s�̍H��ɂ͍H��ψ���g�D����J���҂ɂ��H��Ǘ����s��ꂽ�B���t�@�b�V���s���R�ψ���̎���ɂ́A�H��A�H�ƁA�x�@�A�_���e�ψ���Ȃǂ��܂��܂Ȉψ���g�D���ꂽ�B�J�^���j�A�ŁA�B�ꌠ�Ђ������Ă���̂͏B���{�ł͂Ȃ��Ĕ��t�@�b�V���s���R�ψ���ł���A���̕z���͎����I�ɂ͖@���Ƃ��ċ@�\�����B�B���{�͎s���R�ψ���̕z����ǔF���Ă����ɂ����Ȃ��B
�@�������{�������s�}�h���[�h�����l�ł���A���t�@�b�V�������s���R�ψ���A�J���҃p�g���[���A�H��ψ���g�D���ꂽ�B�������āA�X�y�C���̖��̓y�n�Ƒ�s�s�̂قƂ�ǂ͊v���I�J���҂̌��͂̂��Ƃɂ������B���V�A�̂P�V�N�̓v���̎��Ɠ��l�Ɂu��d���́v�̏�Ԃ����܂ꂽ�̂ł���B�{���ɗ͂������Ă����̂́A���R�����I�ɐ��܂ꂽ���t�@�b�V���ψ���ł��������A�J���҂͏\���ɂ�������o���Ă͂��Ȃ������B
�@�Ë��I�ȋ��a�}���{�ł͔��v���Ɠ����������Ƃ��o���Ȃ����Ƃ����炩�ɂȂ�Ȃ��ŁA�X���ɂ͍��h�Љ�}�J�o���F�����Ƃ��āA���E���Љ�}�A���Y�}�A���a�h�ɂ��A�����{������ꂽ�B
�@���{�̊�{����ɂ��ăJ�o���F���͎��̂悤�ɏq�ׂ��B�u�{���{�́A���t�@�V�Y�������ɂ�����X�y�C���̖h�q�Ƃ����B��̊�]�ɂ�铝����ێ������߂ɁA�䂪�}�̎咣��Ǝ��̕��j��i�삷�邱�Ƃ𐳎��ɕ���������ŁA���̓}�h�̎Q�������̂ł���v
�@�ނ͎ɑI���O�܂ł͐푈�Ɗv����藣�����Ƃɔ����Ă����B���ۂɁA�u���W���A�̐��ɂƂǂ܂�̂ł͂Ȃ��A�J���ҁA�_���ɂ���Ďn�߂�ꂽ�v����[�߁A���W�����邱�Ƃ͓����ɔ��v���Ƃ̐푈�ɏ������铹�ł������B�Ƃ��낪�A���܂�푈�ւ̏����̂��߂ɘJ���҂͊v���I�����͍T���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ǝ咣���A�u���W���A���ƍČ��̂��߂̎w���҂ɂȂ����̂ł���B�������āA�J�o���F�����{�̉��ŘJ���ҁA�_���̓����͈�������Ă������B
�@�u���W���A�����ێ��̐擪�ɗ������̂́A���Y�}�ł������B���Y�}�͓���u���ȗ��A�B��̉������\�A�̌㉟���ɉ����A�J���ґg�D����̒E�����q��v�`�u���W���A�̑�ʂ̉����ɂ���ē}�����g�債���B�ނ�̊�{�I����̓u���W���A���a���ێ����������������̂ł͂Ȃ������B�������Y�}�@�֎��͎��̂悤�ɏq�ׂ��B
�@�u���݂̘J���^�����푈�I����Ƀv�����^���A�ƍق�ڎw���Ă���Ƃ����̂͐�Ό��ł���B����ꂪ�푈�ɋ��͂���͎̂Љ�I�ȓ��@�����邩��Ȃǂƌ�����͂��͂Ȃ��B�����R�~���j�X�g�͂��̂悤�ȉ�����^����ɕ����̂���B�����͂����ς疯���`���a���h�q�ւ̔O��ɂ���ē��@�Â����Ă���̂ł���v�i�t�F���b�N�X�E�����E���A�w�X�y�C���̊v���Ɣ��v���x���j
�@�t�����R�̔��v���ɏ������邽�߂ɂ́A���R��`�I�u���W���A��v�`�u���W���A�Ƃ̓������������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��A�J���҂͖����`�̖h�q�̂��߂ɓ����Ă���̂ł���A�v�����������Ƃ͔ނ��G�ɒǂ����A���{������锽�v���ł���A�Ƌ��Y�}�͎咣�����̂ł���B�\�A�̉�����w�i�ɐ��{���Ŕ����͂����߂����Y�}�̍U���̂ق���́A�J���ҁA�_���̊v���I�����Ɍ�����ꂽ�B
�@���Y�}�́A����ɏ����߂ɂ͌R����x�@�𐭕{�̓����̂��Ƃɒu���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ��āA�u���W���A���ƌ��͂��������Ă������B
�@�J���Ҏs���R�͉�̂���āA���������~���ꂽ�B�R�����ł͈ʊK�������������B�J���ҁA�_���̌R���͉�̂���A�m���̖��߂̂܂܂ɓ����K���I�R�������������̂ł���B�����ŁA�J�^���j�A��}�h���[�h�ōs���Ă����J���҃p�g���[���͋֎~����A����ɑ����Đ��{�̌x�@�������A�������ꂽ�B�x�@�����̘J���g���A���}�ւ̉������֎~����A�W��A���_�������K�����ꂽ�B�K���I�R���ƌx�@�̕�������̎d�グ�́A�J���҂̕��������ł���B�J���҂��畐�킪���グ���A���{�̋��Ȃ��ɂ͕���������Ƃ͏o���Ȃ��Ȃ����B
�@���̈���ł́A���{���������A���{�ɔᔻ�I�ł������b�m�s��o�n�t�l�ɑ���e��������ƂȂ��Ă������B�b�m�s��o�n�t�l�̑�O�W��͋֎~����A�ނ�̋@�֎��͔��s��~����A���W�I�ǂ������ꂽ�B�o�n�t�l�͔@������A���̎w���ҁA�����Ɗ����͑S���������ꂽ�B���Y�}�ɂ��閧�x�@���̂���A�����A����A�ÎE�A�ߕ߂Ȃǁg�ԐF�h�e�������r�ꋶ���̂ł���B�o�n�t�l�̎w���҃j�����t�@�V�X�g���v���������������A����̂����閧���ɋs�E���ꂽ�B
�������l��������{�̔s�k������
�@���{�ƘJ���҂̋T�[�܂�A�J���҂̐��{�ւ̕s�M�����܂�Ȃ��ŁA�R�V�N�T���ɁA�J�o���F���͎����C�A�����ĎЉ�}�E�h�̃l�O�������Ƃ��鐭�{�����������B���Y�}�͂�����u�����̓��t�v�ƌĂB�������A���a���́u�����v�̖��̂��ƂɘJ���҂̊l���������ʂ͎��X�ƒD���A����܂łȂ���Ђ��߂Ă����u���W���A���q�������̕\����Ɍ���Ă����B
�@�_���ɂ��W�Y���_��͉�̂���A�y�n�͌��̒n��ɕԂ��ꂽ�B�H��ł͘J���҂̊Ǘ����͔��D����A����͍��Ƃ̎�Ɉڂ���A�H��̋����L�҂ւ̕⏞���F�߂�ꂽ�B
�@�l�O�������{�̂��ƂŁA�l��������{�͔s�k�Ɍ������ē˂��i��ł������̂ł���B�t�����R�̔��v���̏��������͂�N�̖ڂɂ����炩�ƂȂ����i�K�ŁA�l�O�����͋��Y�}�r���ɏ��o�����B
�@���Y�}�͂�����u�l�O�����̗���v�Ƃ��Ĕ����B�u�P�X�R�W�N�̂R������A����ɑ��������̒�R�̎x���҂ł������l�O�����ƁA���̐퓬�̍Ō�̎����̃l�O�����Ƃł͂����ւ�ȑ��Ⴊ�������B���̓����̃l�O�����́A�l���Ə����ƂɊm�M�������A�����B������ӎu�����߂��A��O�̎x�������Ƃ߁A���������ē}�̎x�������Ƃ߂��B���܂̎����̂�����l�̃l�O�����́A�}�̎x���������A���Y�}�̒�ĂɎ��������ނ����Ƃ����ۂ����B�l�O�����͂��͂⓬�����Â��悤�Ƃ��Ȃ������B�����č~����`�҂̎v���ǂ���ɂ����Ă����̂ł���v�i�X�y�C�����Y�}�A�w�X�y�C���l������j�x�j
�@�����A�s�k�̐ӔC���l�O�����ɋA�����Y�}�̑����͓O�ꂵ�ċ\�Ԃł���B�l�O�������g�ώ��h�����킯�ł͂Ȃ��B�l�O�����⎩�R��`�u���W���A�W�[�́A�J���҂̊v������u���W���A�̐�����邽�߂ɋ��Y�}�𗘗p�����̂ł���B�J���ҁA�_���̔s�k������I�ƂȂ������A���Y�}�͂��͂�ނ�ɂƂ��Č�p�ς݂ƂȂ����B�������čŌ�ɂ͔ނ�͋��Y�}���痣��A�G����悤�ɂȂ��Ă������B
�@�l������̔s�k�́A�A�i�[�L�X�g�A�ЁA���A�o�n�t�l�̓��a����`�̔j�]��\�I���Ă���B
�@�J���҂̊v���I���͂��������邱�Ƃ����A���v���ӂ���ƂƂ��ɘJ���҂̉����������邱�Ƃł������B�������A�u�Љ�}�A���Y�}�̒��ځi�t���Ƃ��āj�Q���ɂ��ƂÂ��^���̐l��������{�v���v���𑣐i���邽�߂̐��{�Ƃ��ėv�������o�n�t�l�̐���́A�J���ҁA�_���ɏ����̓W�]��^���邱�Ƃ͂ł����A�M���������Ă������B�܂��J���҂̍��Ɓ����͂�ے肵���A�i�[�L�X�g�̉^���͍s���l�܂�A���ǂ̓u���W���A���ƂɈˑ����Ă������B�A�i�[�L�X�g�̓��a����`�̓u���W���A�����̉A���������ԎЋ��⎩�R��`�I�u���W���A�W�[���������B�A�i�[�L�X�g��ЁA���A�o�n�t�l�̓��a����`�̓u���W���A���́A�������q����������̂������A�J���ҁA�_���̊v���I��������̂��A���v���̏����ɓ����J���Ă������̂ł���B
|
�W
���{��`�I�����Ɏ��݂����Ћ�
�����C�^���A�́u�������{�v�̌o�� |
�@���햖������I���ɂ����āA�t�����X��C�^���A�ł̓u���W���A���}�ƎЉ�}�A���Y�}�Ƃ��A�������u�������{�v���������ꂽ�B����̓R�~���e�����̕��j�̓]���f���Ă���B�l��������{���s�k���A�t�@�V�Y������������Ȃ��ŃR�~���e�����́A����܂ł̎Љ�}�A���Y�}�𒆐S�Ƃ������������玩�R��`�I�u���W���A���}�Ƃ́u�����I�v�������ɓ]�����Ă������B�����Ă��͂�Љ��`�͉��������̖ڕW�Ƃ��ĒI�グ����A�u�����`�Ǝ��R�v�̂��߂̓������������ꂽ�̂ł���B�t�����X�̌o���ɂ��ẮA�w�v�����e�E�X�x�R�Q���Ř_�����̂ŁA�����ł̓C�^���A�́u�������{�v�ɂ��Ď��グ�邱�Ƃɂ���B
�������o�h���I�����̐���������
�@���풆�̂S�R�N��������̂S�V�N���܂ł̂S�N�Ԃ́A�u���W���A���}���L���X�g������}�i�ȉ��L���}�j�ƎЉ�A���Y���}�𒆐S�Ƃ���A�������̎���ł������B���̘A�������̓t�@�V�X�g�����㒼��̌����̎����ɂ����āA�u���W���A�x�z�����̊m���Ǝ��{��`�I�o�ύČ��̊�b��z���������ʂ������B
�@�C�^���A�ł̓h�C�c����{�ƈقȂ��āA�t�@�V�Y�������̕���͂��łɑ�풆�Ɏn�܂����B�t�@�V�Y���ɑ��铬���́A�S�R�N�́u�t�B�A�b�g���~���t�H���I�v�H��̑�X�g���C�L���͂��߂Ƃ���J���҂̃X�g���C�L�����Ƃ��Ĕ��W�����B���グ�A�H�ƁA���a��v������J���҂̓����́A�����܂��g���m�A�~���m�Ƃ����ߍx�̊�Ƃɔg�y���A���{�͏�����]�V�Ȃ�����A�J���҂͑����̌o�ϓI�v��������������B����̓t�@�V�X�g�x�z���J���ґ�O�̓����ƌR���I�s�k�ɂ���Ă�����͂��߂����Ƃ��������炩�Ȓ���ł������B����A�S�Q�N�ɂ͋��Y�}�A�Љ�}�A�L���}�Ȃǂɂ��u�����������ψ���v����������A���W�X�^���X���J�n���ꂽ�B
�@�J���҂̓����ƃ��W�X�^���X�^���̍L���肪�t�@�V�X�g������h�邪���Ȃ��ŁA�x�z�K���̓��b�\���[�j�̐������痣�����Ă������B
�@���̌���I�_�@�ƂȂ����̂͘A���R�̃V�`���A�㗤�ł������B�S�R�N�R���A�����̓��b�\���[�j���Ƃ��A�V���ɃG�`�I�s�A�̐����҃o�h���I�����ɑg�t�𖽂����B����̓t�@�b�V���}�����Δh�A���{�ƁA�ێ�I�����Ƃɂ��N�[�f�^�ł������B�ނ炪�ł�����Ă����̂̓t�@�V�Y���̌R���I�s�k�Ƌ��|��ɂȂ邱�Ƃł������B�t�@�V�X�g�����̔s�k���Z���ƂȂ�Ȃ��ŁA���b�\���[�j��r�����ĘA���R�Ƙa�����s���A����̑̐��̈ێ���}�낤�Ƃ����̂ł���B�o�h���I�����́A�t�A�V�X�g�}���]�c������U�������A���t�@�V�X�g�����Ƃ��ߕ������B�������A����͓O�ꂳ�ꂸ�A���Y�}�����Ƃ̎ߕ��ɂ��Ă͍ĎO���������ꂽ�B�Ƃ͂����Љ�}�A���Y�}�Ȃǔ��t�@�V�X�g�����}�͂���܂ł̔@��Ԃ�E���āA�����㍇�@�I�ȑ��݂ƂȂ����B
�@���{�̓t�@�V�X�g�}�g�D�̉��U�𖽂��͂������A�t�@�V�Y���̐��{�@�\�ɂ��Ă͂��̂܂܂ɂ����B�ނ�̓t�@�V�Y���̓����@�\�����̂܂܉������A���t�@�b�V�����͂̐����I�e���͂�D���A���������̎x�z���m�����悤�Ƃ����B
�@���b�\���[�j�̔�Ƃƃo�h���I�����̐��������\���ꂽ���A�ނ�̗\���ɔ����āA�t�@�b�V���}�ƃt�@�V�X�g�`�E�R�̒�R�͂قƂ�ǂȂ������B�ނ���t�@�V�Y���ɔ������O�s�����S�������B�Ƃ�킯�k���ł́A�f�����z���ĘJ���҂͐����Ƃ��ߕ������B��@�I���Ԃ����ꂽ�����́A�J���҂̓�����}�����ނ��߂ɉ����߂�~�����̂ł���B
�@�����ƃo�h���I�́A�����ɘA���R�Ƃ̘a���H����s�����B�X���A�x�틦�肪���\�����ƁA���ɘA���R�̎x�z���ɂ������T�����m�ȓ�̒n��������āA�C�^���A�̓h�C�c�̐�̉��ɂ����ꂽ�B���̂��߁A�o�h���I�����͂��̎x���ł������R�������̂Ăă��[�}����암�ɓ��S���A�A���R�̐�̒n�u�����f�B�W�ɐ��{���ڂ����B����A�h�C�c�R�ɋ~�o���ꂽ���b�\���[�j�́A�q�g���[�̂Ќ�̉��ɖk���T���H�Ő��{�����������B�������āA�C�^���A�͋x�틦�蔭�\���琔���̂����ɓ���邱�ƂƂȂ����B
���������Y�}�̓��t������
�@�A���R�Ƃ̋x�틦�萬���Ǝ��������āA���t�@�b�V�����}�͍�������ψ���i�b�k�m�j�Ɍ��W���A�������������������ꂽ�B�������A�o�h���I�����ւ̎Q�����߂����āA�����ł͕��Ă����B
�@�s���}�A�Љ�}�A���Y�}�̎O�}�́A�o�h���I�����̃t�@�V�Y���Ƃ̋��Ɛ�����A�b�k�m����b�Ƃ������a���̎����ň�v�A���͂�����L���}�A���R�}�A�J������}�O�}�Ɛ^��������Η����Ă����̂ł���B
�@�����A�o�h���I���������咣���鋤�Y�}�̐���̓]���𔗂����̂́A�R���̃\�A�ɂ��o�h���I�����Ƃ̊O���W�̎����ł������B�\�A�ɑ����ĕĉp���o�h���I�����Ƃ̊W������搂����B
�@�S���A�\�A����A�������g���A�b�e�B�́A���Y�}�S����c�Ŏ��̂悤�ɒ�Ă����B���Ȃ킿�A���ʂ̉ۑ�͑S�͂������ăi�`�X�̎x�z����|���邱�Ƃł���B���̂��߂ɂ͐��{�Ɣ��t�@�V�X�g���}�Ƃ̊Ԃ̕���͎��}��������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B���̕���̎���ƂȂ��Ă���N�吧�̖��́A�����܂ŒI�グ���āA���ׂĂ̔��h�C�c�E���t�@�V�Y�����͂��u�����I����v�̂��ƂɌ��W����K�v������A�ƁB
�@����ɑ��āA���[�}��~���m�̋��Y�}�g�D����͔��_�����o�����B�X�R�b�`�}�����́A�o�h���I�����̘J���Ғe���������A����Ƃ̋��͂ɔ����Ď��̂悤�ɏq�ׂ��B�u�͊W�����łȂ��A����̐����I���������K�v������B�͂��傫���Ă��A������I�Ȃ炻��ƌ��Ԃ��Ƃ͕s���B�i���������āj�o�h���I�̉ߏ��]�������R���B�ނ̔�����I����́A���̔��ƓI����������A�ΓƐ�킻�̂��̂��ɂ����v
�@�܂��Z�b�L�A���g���A�b�e�B�ɔ������B
�@�u�����A�T���E�t�@�V�X�g�ȊO�ɔ������I���͂��Ȃ��ƍl����̂͌�肾�B�h�C�c�ɋ��͂��Ă���Y�ƉƁE���������E�o�h���I�h�Ȃǁc�c�B�����I����́A�E�̕��Ɋg�債�Ă��������ł͎����ł��Ȃ��B�c�c�����̓X�g���w�����A�p���`�U������������Ă���B���ꂪ�����̐���̍��{�������v�i�ɓ�����Y���w�C�^���A���Y�}�j�x�j
�@�������A�g���A�b�e�B�͓}���̋��d�Ȕ����������āA�o�h���I�����ւ̎Q�������肵���B
�@�g���A�b�e�B�́A���Y�}�͂��܂�u�J���ҊK���̓}�v�u�O�q�}�v����E�炵�āA�L���u������O�̓}�v�ɂȂ�Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��A�����āu�ᔻ�Ɛ�`�̓}�v����A�u�����̐ӔC��S������}�v�ɂȂ��Ă����˂Ȃ�Ȃ��Ƌ��������B�u�����͘J���ҊK���̓}�ł���B�c�c�������J���ҊK���͍����̗��Q�ɂ������Ė����ł͂Ȃ��B�c�c�t�@�V�Y�����D�y�̒����Ђ�����A�����������I���v�̊����A�����͏E�������A�킪���Ƃ���B�c�c���V�A�ł����Ȃ�ꂽ���Ƃ������Ȃ��Ƃ����ۑ肪�A�C�^���A�̘J���҂Ɍ��݉ۂ����Ă���̂ł͂Ȃ��B�c�c�C�^���A�J���ҊK���́A�C�^���A���������肱���܂̔j�ǂ���̏o����S�����Ɏw���������߂ɔ������A���j���o���ׂ��ł���B�c�c�����̐���́A�����̐���ł���A����̓���ł���v�i���j
�@���Y�}�͂��܂▯���̓}�A�����̓}�Ƃ��Č��ꂽ�̂ł���B�K�����}���獑�����}�ցA�o�h���I����������x���ւ̋��Y�}�̐����]���́u�T�����m�̓]���v�Ƃ��Ă��邪�A����͎��{�̎x�z��œ|���ĎЉ��`���������Ƃ����J���ҊK���̉ۑ��������āA�t�@�V�Y�������ɔ����ău���W���A�̐��̉�����}�낤�Ƃ���ێ琨�͂ւ̒ǐ��A�������Ӗ������B�������č����̐��{�ɔ����Ă����Љ�}�A�s���}���Q�����ăo�h���I�����́A�g���������h�Ƃ��Ĕ��������B���Y�}����̓g���A�b�e�B�ƃO�������t�A�g���A�b�e�B�͕��̒n�ʂɏA�����B
�������u�����̓}�v�Ƃ��Ă̋��Y�}������
�@�S�S�N�U���A���[�}�͘A���R�ɂ���ĉ�����ꂽ�B�o�h���I���t�͎��E���A�b�k�m�̗v���ɂ���Ă��ׂĂ̔��t�@�V�����͎Q���̂��Ƃŕێ�I�����ƃ{�m�[�~�̐V���t���g�D����A�����ăC�^���A�������ɂ̓��W�X�^���X�̎�v�Ȏw���҂̈�l�ł������s���}�̃o�b�����Ƃ��鐭�{���a�������B�S�y�����ɒa���������̐��{�͂Ȃ��`���I�ɂ͂b�k�m�Ɋ�b���������{�ł������B�������A�t�@�V�Y���Ƃ̓����Ƃ����ڕW���B�����ꂽ���܁A�b�k�m�̓����ł͂��łɃo�b����������߂����Č������Η����W�J����Ă����B
�@���Y�}�́g�����I����h�������Ȃɂ����D�悳���ׂ����Ǝ咣�����B�g���A�b�e�B�́A�L���}�A���Y�}�A�Љ�}�́u�O���O���}�v�ɂ��A���������咣�����̂ł���B���Y�}�̓L���}�Ƃ̓�������Ƃ��đ��������[�}�������̂S�S�N�V���ɂ͍s�����ꋦ��̒�Ă��s���Ă���B�������āA���S�T�N�R���ɂ̓L���A���Y�A�Љ�O�}�ɂ��s�����ꋦ�肪����A�P�Q���ɂ́A�L���}�̃f�E�K�X�y������ǂƂ���O�}�A�����������������B
�@���{�ƊK����ێ�̐��͂��K�X�y�������ɑ��������Ƃ́A�u���W���A�������m�����A�푈�Ŕj�ꂽ�o�ς��̋O���ɏ悹�邱�Ƃł������B�K�X�y�����Љ�A���Y�}���}�𐭌��ɉ������̂́A���W�X�^���X�̉e���������Ȃ���������ł���B�ЁA������t�Ɏ�荞�ނ��Ƃɂ���ĘJ���҂����_���悤�Ƃ����̂ł���B
�@�u�����I����v��搂������Y�}�ɂƂ��āA����ɂЂт������̖��͔r������˂Ȃ�Ȃ������B
�@���̍ő�̖��͂b�k�m�̏����ł������B���Y�}�́u���卑�Ƃł͑Η������̌��͂͑��݂����Ȃ�����A�b�k�m�͌��͂�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ǝ咣�����B�k���A�����ł͘J���҂𒆐S�Ƃ��郌�W�X�^���X�͘A���R������O�Ɏ��͂Ŏ�v�ȓs�s��������Ă������B�����Ă��̒n��ł͒m���A�s�������A�x�@�����Ȃǂ�C�����A���W�X�^���X�w�����ł������u�㕔�C�^���A��������ψ���v�́A�����I���͂Ƃ��Ă̗l����悵�Ă����B�������Y�}�͓����̒��Ő��܂ꂽ���̊v���I���͂�ے肵�A�u���W���A���ƌ��͂̊m����i�����̂ł���B
�@�������������́A�o�ϖ��ł��Nj����ꂽ�B���ɂ���Ĕj��A�敾�����o�ς̍Č��͘J���҂��ϋɓI�Ɏ��g�ނׂ��C���Ƃ��ꂽ�B�g���A�b�e�B�͂S�T�N�W���̓}���o�ϖ�蓢�_��c�Ŏ��̂悤�ɏq�ׂ��B
�@�u�Ȃ����ׂ����̂��Ƃ́A���ɂ��A�J���҂ɑ��A�ނ炪�����Ƃ���ł͂ǂ��ł��A�J���\������̕K�v�����A�s�[�����邱�Ƃł���B�c�c�J���ҊK���́A�J�����Y���̑��傪����̐����C�^���A�ɂ���̂ɐ������邽�߂̏����̈�ł��邱�Ƃ�m��˂Ȃ�Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A����ꂪ�o�ϖ��A����ѓ����Ȃ��Ƃ����ꎞ�̗��s�����������邱�Ƃɐ������Ȃ��Ȃ�A�����`�ւ̓����̉^���Ȃ����낤����ł���v
�@�����āu�����́A�Ⴂ���Y�R�X�g�A�����J�����Y���A�����č������ɂ��ƂÂ��������Y�̂��ׂĂ̍đg�D�Ɍ�����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��v�i����j�Ƃ����B
�@���Y�̍ĊJ�A�����̂��߂ɐ擪�ɂ����ē����Ƃ������Ƃ��A�u�Ȃ����ׂ����̂��Ɓv�Ƃ��ĘJ���҂ɉ�������ꂽ�B�����āu�J���҂Ɛ��Y�u���W���A�W�[�Ƃ̓�������v��搂��A���̂��ƂōH��]�c���b�k�m�ɂ�鐶�Y�Ǘ��͐��Y�����̖W���ɂȂ�Ƃ��Ĕr������A���̈���ł͊�Ƃ̋���]�����X�ƕ��A���ʂ������̂ł���B
�@���Y�}�̓u���W���A�I�����̐ӔC��S���u�����̓}�v�Ƃ��Č��ꂽ�B�K�X�y�����{�ɖ@���Ƃ��ē��t�����g���A�b�e�B�i���ɃX�R�b�`�}�������������A�O�����_���j�͕p�����鑛���̂Ȃ��ŁA�u�����͂ւ̔��R�v�ɑ��Ắu�ő�̐v���ƍő�̌������v�������đΏ����邱�Ƃ𖽂����B
�@�t�@�V�X�g�̐��قɂ��Ă����l�ł���B
�@�S�S�N�A�S�T�N�A�S�U�N�̊e�N�Ƀt�@�V�X�g�̑�͂��s��ꂽ���A�S�U�N�̂���̓g���A�b�e�B�̒�Ăł������B
�@�܂��K�X�y�����{�͔�����Ԃ��Ȃ��S�U�N�R���ɂ́A�t�@�V�Y�����ٍō��ψ�������U�����B����Ɠ����ɁA���ق����҂ً̈c�\�����Ă�F�߂��B���̌��ʁA�t�@�V�X�g�ɋ��͂����Ƌ@�ւ���Ǖ����ꂽ�҂̂قƂ�ǂ����߂Ƃ���A���ƂƎЉ�̗v�E�ɕ��A�����B�t�@�V�X�g�Ƃ��̋��͎҂ɑ��鐧�ق���ނ������ł́A�u���W���A�W�[�ɂ���ăt�@�V�X�g�ɑ��ĉʊ��ɓ������p���`�U���i�J���ҁA�_���𒆐S�Ƃ����V�����j���E�l�A�����A���D�҂Ƃ���L�����y�[�����J�n���ꂽ�B����͊v���I���q����Ƃ⍑�Ƌ@�\����Ǖ����A�u���W���A�̊K���x�z��ł������߂Ă������߂̍U���ł������B�p���`�U���ɑ��ẮA�Ǖ���Ƃꂽ�ٔ����ɂ���Č����������������ꂽ�B�܂��x�@�ɕғ����ꂽ�p���`�U�������́A�u�Z�N�g�I�ł���A�������s�\�͂Ɍ�����v�Ƃ��đ�ʂɒǕ�����Ă������̂ł���B
�@�����ĂS�V�N�ɂ̓L���}�͎ЁA����r��������l���K�X�y���������������B���Y�}�̃L���}�Ƃ̋�������́A���{�����̊�@����肫��A�J���ґ�O�̎��{�ɑ���{���s�������点��𗋐j�ƂȂ�A���{��`�̍Č����x����������ʂ������̂ł���B
|
�X
��㎑�{��`�̍Č��ƈ���ɕ�d
�����Y�}���u����v�����ЎR�u�Љ�}�v���� |
�������Љ�}��Ǔ��t�̐���������
�@�O���悤�ɑ��풼��̌������ɂ́A�C�^���A��t�����X�ł͎Љ�}�A���Y�}�����t�����������A�������{���a�������B���{�ł��V���@�̂��Ƃł̏��̑��I���ŎЉ�}����ǂƂ��鐭�������܂ꂽ�B�A�������Ƃ͂����g�J���҂̐��}�h�𖼏�鐭�}�̐��������܂ꂽ�̂́A���{�ł͂��ꂪ���߂Ă̂��Ƃł������B
�@�P�X�S�V�N�S���̑��I���ŎЉ�}�͂P�S�R�c�Ȃ��l���i���[���Q�T.�V���j�A���}�ɖ��i�����i���̓}�̋c�Ȃ́A���R�}�P�R�P�A����}�P�Q�S�A���������}�R�P�A���Y�}�S�A���h�Q�O�A�������P�R�j�B�������c�Ȃł͂R���̂P�ɖ����Ȃ���r���}�ł������B����͕ێ�̕[�����R�}�A����}�ɕ������߂ł������B
�@�Љ�}�̕ЎR�N�ψ����͎��̂悤�ȏ����̒k�b�\�����B�u�䂪�}�����}�̉h�_���l���������Ƃ́A�����͂ɑ���v�V���͂̑䓪�̂�����A���Ȃ킿�g����̗́h�̂�����ł���B�ێ琨�͂̐�����������M�����Ȃ��Ƃ������Ƃ����炩�ɂȂ����ȏ���̐����́A���{��`����Љ��`�ֈڍs���鐫���������������łȂ���Ȃ�Ȃ��v
�@�����A���ۂɂ͎Љ�}�ɂƂ��đ��}�͐V�����̂ł������B�I�����ʂ��ĕЎR�́u������v�ƌ����A���L���̐������L�i��ɖ��Г}����ψ����ƂȂ�j�́u�����A���炢��������v�i�������Ƃ����Ӗ��j�Ǝv�킸������A�Ƃ܂ǂ����B���Ȃ������悤�ɁA�Љ�}�͖{�C�Ō�������̂��߂ɓ����o��ȂǂȂ������̂ł���B
�@�U���P�����������ЎR���t�́A�Љ�A����A�����O�}�A�����t�ƂȂ����B�������A����ɂ��ǂ���܂łɂ́A�Љ�}���ł͎��R�}���܂߂��l�}�A�����߂����E�h�ƁA���R�}���������O�}�A�����咣���鍶�h�̑Η����������B
�@�����A�ЎR��E�h�w�������߂������̂́u���R�}���܂ދ�����v�̐��v�ł���A���̍\�z�͂���܂ʼn��x������Ԃ��Ă������R�}�Ƃ̘A���H��̉����ȊO�̂Ȃɂ��̂ł��Ȃ������B
�@�������Ďl�}�̐��肪���������B���̓��e�́A�o�ϊ�@�˔j�̂��߂̌o�ϓ����A���Y�����̂��߂ɒ��d�_�Y�Ɛ���̓����Əd�v�Y�Ƃɑ��Ă͕K�v�ɉ��������ƊǗ��A�C���t�������̂��߂̌��S�����̌�������ы��Z�����A�����y�щ��i�̓����A�Ŏ���̖o�łȂNj㍀�ڂł������B�o�ύČ����ő�̉ۑ�Ƃ������̐���́A��̌R�i�ߊ��}�b�J�[�T�[���g�c�Ɉ������ȂƁA����ɑ���g�c�̉��u�ӂƌ[���̂悤�ɓ��ɕ����ׁv���i�����j�̂���ɍ쐬���ꂽ���̂ł������B
�@����ɂ��āA���R�}���u����͂قƂ�ǎЉ�}���킪�}�̐�����̂�œ��������̂ŁA�܂�����ő听���v�ƌ��A����}���u�킪�}�̐����S�ʓI�Ɏ����ꂽ�̂ɁA����͖���}���S�̓��t���v�ƍ��������悤�ɁA����́u�قƂ�ǖ��C���v�ŏ��F���ꂽ�B�����ē����Ɏl�}�̊t���̔z�������߂�ꂽ�B
�@���������R�}�͂�������͘A���ɓ��ӂ������̂́A�Љ�}���h�̔r����v������g�c�̔��ŎQ�����Ȃ����ƂƂȂ����B���̂��ߐ����玷�s���͎O�}�A���ɐ�ւ����B����}�͎O�}�A�����l�}�A�������߂����Ĉӌ�������A���ǂ͎O�}�A���h���������邱�ƂɂȂ邪�A���̉ߒ��Ŗ���}�̒�ĂŁA���̎O�J�����A���̏����Ƃ��Ēlj����ꂽ�B�@�ɉE�A�ɍ���`���̌����B�A�d�v�@����R�k���Ȃ��B�B�Љ�s�����N��������̂���s�������Ȃ��B�ᔽ����}���ɑ��Ă͊e�}���ӔC�������ď��u����B�O�����́u�ɉE�v����搂��Ă��邪�A�Љ�}�̍��h���ӎ��������̂ł��邱�Ƃ͖��炩�ł���B����}�͍��h�̍s�����K�����悤�Ƃ����̂ł���B
�@����A�E�h�w�����ɒ�R���Ă�����ؖΎO�Y��������\�獶�h���l�}����A�O�}�����ɑ債���������Ȃ������B�ނ�͎��R�}�ƒ�g���邱�Ƃɔ������Ă����ɂ������A�ێ琨�͂Ƃ̘A���ɔ����Ă����킯�ł͂Ȃ���������ł���B��������A�����͋��Y�}�Ƃ́u�≏�錾�v���s���A������ɒǐ����Ă����̂ł���B�ނ�͓�E��X�g���֎~������̌R�̋��d�p���ɂ������蓮�h���Ă����B
�@�l�}����ɂ���Č������������Љ�}�́A����ɂ��̎O�J���ɂ���Ă��̍s���������邱�ƂɂȂ����B�������ĎЉ�}�́A�ێ琨�͂��������y�U�̂Ȃ��ŕЎR���t�������Ă����̂ł���B�A���ɎQ�����Ȃ��������R�}���t�O���͂��邱�ƂɂȂ�A������́u������v���{�v�ł������B
�������Ɛ莑�{�̕���������������
�@�g�t���I���������A�ЎR�̓��W�I�ō����Ɋ�@�˔j�̊o���i�����B�ЎR�́u���ɍ������N�ɂ��肢���������Ƃ́A��@�˔j�̂��߂ɁA���ꂼ�ꕪ�ɉ����āA�]�����ÎĂ������������Ƃ������Ƃł���B���Ȃ킿�C���t�������A���Y�����̂��߂ɁA���̏�Ƃ��A�ϖR�����𑱂��Ă������������Ƃ������Ƃł���v�Əq�ׂāA�J���҂̊��҂ɗ␅�𗁂т����̂ł���B�ЎR���t���N�̂��߂̐��{�ł��邩�͖��炩�ł������B
�@�����Đ��{�͂W���ڂ���Ȃ�u�o�ϋً}��v�����肵�����A����́u���͂������Čo�ψ���̂��߂ɂł��邩����̎{����s���v�K�v���������A�Ăсu�ϖR�ƁA���͂ƁA�����Č��Ɗ��̘J���v��i����ȂǁA�A�C����̍����ւ̑i���ƕς��Ȃ����e�ŁA�Љ�}���������Ă����J���҂̐��}�Ƃ��Ă̓Ǝ����ȂǂقƂ�ǂȂ������B
�@���̒��S�͂P�W�O�O�~���ϒ������e�R�Ƃ���u�V�����̌n�v�ł������B
�@����͂قڎ��̂悤�Ȃ��̂ł������B�܂���b�I�����i�S�|�A�ΒY�A�엿�A�\�[�_�Ȃǁj�̌��艿�i���P�X�R�S�`�R�U�N����Ƃ��āA���̂U�O�`�U�T�{�̌��x�i����сj��݂���B����͓����̎s��ł̉��i�ɂقړ����������ł������B�����Ċ�b�����̌��艿�i����Ɍ����v�Z���đ��̏��i���i�̌��艿�i���߂�B�����A�����͊�b�����̐��Y�����Ƃ̍̎Z�������猈�߂�Ƃ����̂ł���B
�@��̓I�ɂ́A�ŏ��ɓS�|�̌��艿�i�i����҉��i�j��ݒ肵�A���̉��i�ŕ⋋�����v�Z�ɓ����ΓS�|���{�̍̎Z���Ƃ��悤�ɐΒY�̌��艿�i�����߂�B�����Ď��ɁA���̉��i�ŐΒY���{����������悤�ɁA�ΒY�̃R�X�g�̔����߂�Y�z�J���҂̒������߁A�������Ƃ��Ĉ�ʘJ���҂̒��������߂�Ƃ��������ł������B���ꂪ�P�W�O�O�~�̃x�[�X�����ł������B����͊�N���̂Q�W�{�ł������B��Ƃ̐��Y���ɂ��Ă͌����v�Z��`���Ƃ����A�J���҂̒����ɂ��Ă͐����̎��Ԃ͖������ꂽ�̂ł���B
�@�u�V�����̌n�v�͘J���҂̒����̎����I�艺�����s����b�����̌��艿�i�����߁A���̌��艿�i�������Ă��Ă��̎Z���Ƃ�Ȃ��ꍇ�́A���{�������I��i�ɂ���ė�����ۏႵ���̂ł���A���ꂪ���i���⋋���ł������B
�@�P�W�O�O�~�x�[�X�����������ɘJ���҂̎��������炩�����ꂽ�Ⴂ�����ł��������́A�J���Ȃ́u�s�s�ƌv�����v�ɂ���Ă��S�V�N�U���̑S���\�s�s�̉ƌv�x�o���A�S�V�O�O�~�]�ƂȂ��Ă������Ƃ�������炩�ł���B
�@�������Đ��{�́A�ΒY�Y���A�����S�|���Y�ɂ܂킵�A����ɂ����ΒY�̌@�ɍē�������Ƃ����u�X�ΐ��Y�����v���Ƃ�A�Y�Ƃ̊g��Đ��Y��ڎw�����̂ł���B�����̐��Y�ڕW�͐ΒY�R�疜�d�A�S�|�V�\���d�ł������B�⋋���́A���̑��̎Y�Ƃ��܂߂ĂS�V�N�V������N�x���܂łɂP�Q�O���~���v�サ�A���̈�ʉ�v�ɐ�߂銄���͖�ꊄ�A�P�P.�P���i���N�͂P�R.�Q���A�S�X�N�x�ɂ͂Q�S.�Q���j�ɂ��B�����B
�@�Љ�}���J���ғ}�Ƃ��Ă̐���Ƃ����Ă����Y�z�̍��ƊǗ�������A���ۂɂ̓u���W���A�I�Ȃ��̂ł����Ȃ������B���Ƃ��ƁA�}�b�J�[�T�[���u�Y�z�͂�����o�ϊ����Ɩ��ڂɊ֘A���Ă���A���������č��L���̒�Ă͌������闝�R���\������v�i�Γ�������ւ̊o���j�Əq�ׂĂ������A�܂����R�}���ꎞ�́u���ƊǗ��v��F�߂Ă����̂ł���B
�@�Љ�}�͒Y�z�̍��ƊǗ��@�Ă�������B�Љ�}�͂��̗��R�ɂ��āA���̂܂܂ł͐V�Y�z�̊J�����s�\�ł���A�Y�z�����̕s���A���肠�鎑�ނ�Y�z�ɗD��I�ɂ܂킷�A���{�͒Y�z�̓��e���\���ɊǗ�����K�v������A���Y�\���A�o�c�����������邽�߂ɘJ����̂̊W�����グ�Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��A�Əq�ׂ��B����͌��ǂ͎Y�ƕ����̂��߂Ɂu�R�疜�d�̐��Y���m�ہv���邱�Ƃ��K�v�ł���A���̂��߂ɍ��ƊǗ����s���Ƃ������Ƃł���A���͂�Љ�ϊv��ڎw���ďd�v�Y�Ƃ́u�Љ�v���s���Ă����Ƃ�������܂ł̎咣�͉e���`���Ȃ������̂ł���B
�@�����������������ƊǗ��ł��疯��}�⎩�R�}�̔�������сA�@�Ă͂���Ɍ�ނ����B���Ȃ킿�A���̌���Ǘ��͔ے肳��{�Ќo�R�̊Ǘ��ɁA�J���ҎQ���̌o�c���c��͋c���@�ւł͂Ȃ�����@�ւɂȂ����B�������A���ƊǗ��̑Ώۂ͌o�c������ȒY�z�Ɍ��肳�ꂽ�B
�@�����A����R�c�͕������d�˂��B���R�}�͍��ƊǗ��͍��Y���̐N�Q�ł���Ƃ��Ĕ������B����ɑ��Đ��{�͖@�Ă͎Y�Ƃ̕����ƌo�ς̈���ɂ�����܂łً̋}�[�u�ł���A���̖ړI�͐��{�A�o�c�҂���јJ���҂���̂ƂȂ��ĐΒY�̑��Y��B�����邱�Ƃɂ���B���ƊǗ��͐ΒY���Y�ً̋}��Ƃ��ė��Ă������̂ł����āA���̎Y�Ƃɋy�ڂ��l���͂Ȃ��ƕٖ��ɂ���w�߂邠�肳�܂ł������B�����Ă���Ɛ����������̂̂��̎��{�͂S�W�N�S���܂ʼn������ꂽ�i���ǁA���c���t�̂��ƂŎw����������ŁA���ۂɂ͉��̌��ʂ��Ȃ��T�O�N�ɂ͔p�~���ꂽ�j�B
�@���ƊǗ��@�݂͂��߂Ȍ�����H�������A���R�}�͂�����_�@�Ɋt�O���͂���߁A����ɗ^�}����}�̈ꕔ�����R�}�ɓ������Ĕ��ɉ��A�}���番�V���ȓ}�h�����������B�������ĕЎR�A�����t�͕������n�߂Ă����B
���������{�̕�����
�@�ЎR���t�̃u���W���A�I�{���͖��炩�ɂȂ�A�J���ґ�O�̐��{�ւ̊��҂͋}���ɂ��ڂ�ł������B�����Ď��]�͐��{�ւ̔����A����ɂ͑œ|�ւƒZ���Ԃ̂����ɐ�ւ���Ă������B����ɂ�ĎЉ�}���̍��E�̑Η����A�S�V�N�����痂�N�ɂ����Č������Ă������B�����Ă��ɂP���A�Љ�}���́u�l�}����v�̔j�������肷��B
�@���t����̌_�@�ƂȂ����̂͊����J���҂̐����⋋���x���̂��߂̕�\�Z�Ă��\�Z�ψ���Ŕی����ꂽ���Ƃł������B���{�͐����⋋���x���̍�����S���^����X�֗����̒l�グ�ɋ��߂����A���h�͐��{�Ǘ������̕��������Ɛ펞���̗�������~�ɍ��������߂�ׂ����Ƃ��Ĕ��A�\�Z�ψ���Ŕی��B�S�W�N�Q���A���t�͂��̐ӔC���Ƃ��đ����E�ɒǂ����܂�Ă������̂ł���B�������ĕЎR���t�͒a�����Ă킸���W�����]�ŕ����B
�@�ЎR���t�͘J���ґ�O�̂��߂̐��{�ł��邩�̌��z��U��܂��A�J���ґ�O�ɑϖR������v�����A�J���҂̊K�������ւ̖h�g��̖������ʂ������B�����ČX�ΐ��Y�����A���i���⋋���A���艿�i�̌n�Ȃǂ̏d�v�o�ϐ�������R�}�������炻�̂܂܈����p��������łȂ��A�����̏����������ɋ��������B�����̐���͕m���̐��ˍۂɂ��������{���{��`����@����~�������A�Ɛ莑�{�̍Č��Ɍ����Ė{�i�I�ɓ����o���Ă������߂̂��̂ł������B���Ƃ̎���������ɂ���ė�����ۏႳ�ꂽ�Ɛ莑�{�͗�������A���C���Ƃ���ǂ��Ă����̂ł���B
�@�����Ȃ̉�̂ƒn���������x�̊m���A�i�@�Ȃ̉�̂ƍĕҁA�J���Ȃ̐ݒu�A�����{�@�ȂLj�A�́u���剻�v�������A�Љ�}�����ł��������炱���u���剻�v�͐i�̂ł����āA�����ێ琭���ł������疯�剻�̓T�{�^�[�W������Ă����Ƃ���]��������i�����p�v�u�A���������������v�j�B�������A�����́g���v�h�͊�{�I�ɂ͐��̃u���W���A���匛�@�̘g���̂��̂ł����Ȃ������B
�@�ЎR���t�́A���{���{��`�����̊�@����肫��A�{�i�I�ɕ����A�������Ă����̂������������S�������A���������������ʂ��������̂́A���c����}���ق��u�J���U�����Ƃ����������̂Ă��ǂɂƂǂ߂����͕̂ЎR���t�̌��тł���v�Əq�ׂ��悤�ɁA�ꎞ�I�ɂ���J���҂����{�Ɋ��҂��悹�Ă�������ł������B�Љ�}�́g�Љ��`�h�̊Ŕ��f���J���ґ�O�̐��{�ł��邩�̌��z����܂��A���{�Ƃ̋�����J���҂ɉ��������̂ł���B
�@�Ō�ɂ��̎����̋��Y�}�̑ԓx�ɂ��Č��Ă������B
�@�����ł͋��Y�}�́A�ЎR�������u�������]���ɂ��A�Ɛ莑�{�̕������������v�i�}�j�j�Ɣᔻ���Ă���B���������A�ނ�͕ЎR�����ɑ��āA���҂�U��܂��Ă����̂ł���B
�@���t���������A���́A�A���H��̂Ȃ��Ŏ��R�}�▯��}�ɏ����������Ƃ�ᔻ�����A�u�ΘJ��O����b�Ƃ��A�Љ��`��W�Ԃ�����{�Љ�}�����[���b�p�̎Љ��}�̃e�c���ӂ܂Ȃ����Ƃ��A�킪���Y�}�͗F�}�Ƃ��Đؖ]����v�A�u�Љ�}���ڑO�̊�@�ƍ����ŊJ���A����ɏ���������ێ����邽�߂ɂ́A�c�c�����I�J�P�q�L�ɂ����̂ł͂Ȃ��āA��O��M�����A��O�̎x���ɂ�肩���邱�Ƃł���v�ƌ��サ���B�܂����Y�}�̉e�����ɂ������Y�ʉ�c���A�Љ�}��Ǔ��t�����́u����w�c�̑O�i�v�ł���Ɗ��}���A�ۑ�͑I������̎��s���Y�ʉ�c�ƘJ���҂��x�����Ă������Ƃɂ���Ƒi�����B���Y�}���܂��ЎR���t���J���҂̂��߂̐��{�ɂȂ肤�邩�̂悤�Ȍ��z��U��܂��A�J���^���̂Ȃ��ɍ������������̂ł���B
�@���Y�}���ŏI�I�Ɂu�ЎR���t�œ|�v��ł��o���̂͂���ƂS�W�N�Q���ɂȂ��Ă���A���Ȃ킿�ЎR�����̔����I�������N�̖ڂɂ������ƂȂ�A�J���҂������ɗ����������Ȃ��ł���B�C���t���̍V�i�̂��ƂŐ����h�q�A�P�W�O�O�~�x�[�X�����Ŕj���߂����ĘJ���҂̓����͏H����N���ɂ����ĔR���オ�����B�J���^���͍Ăя㏸�ɓ]�����̂ł���B���Y�}�͘J���ґ�O�����͂邩�ɒx��Ă����̂��B
|
�P�O
���R�Ɉˑ������ł̓���i��
�����܂����`���l���A���́g�����h |
�@�P�X�V�O�N�ɐ��������`���̃A�W�F���f�l���A�������́A�u���W���A�c���ʂ��č��@�I�A���a�I�ɎЉ��`��ڎw�������{�ł������B�`�����Y�}�́A�u�l�����{�̑̐����ł��A���̌�̎Љ��`�̏������ł��c�c������@����̐M���͑��d����A�v�z�I�E�����I������`�����݂��A���ꂼ��̗��O�̂��߂ɓ������Ƃ͖W�����Ȃ��v�Əq�ׂ��B�l���A�������̓����͎Љ��`�ւ́u���a�I�ȓ��v�́g�����h�Ƃ��Ē��ڂ��W�߂��B
�@�Ƃ��낪�l���A�������́A�a����킸���Q�N�P�O�J���ŁA�R���N�[�f�^�[�ɂ���ĕ����B�C�^���A��X�y�C���̋��Y�}�̓`���̌o�������A�����̑��������W���邽�߂̓w�͂�z���������Ă����Ƃ��āA���̌�A�����炳�܂ȃu���W���A���}�Ƃ̋������u���j�I�Ë��v�H���ɐi��ł������B�`���̌o���͂��̌_�@�ƂȂ����B
�������A�W�F���f�����̐���������
�@�V�O�N�P�P���A�ЁA���𒆐S�Ƃ����l���A���������a���������A�`���Љ�͐[���Ȋ�@�̒��ɂ������B
�@�l���A�������ɐ旧�t���C�E�L���X�g������}�����́A���{��`�I�Ȍo�ϔ��W�𐄂��i�߂邽�߂ɏd���w�H�Ƃ̔��W�A�y�n���v���f�����B�O�����{�̓����ɂ��d���w�H�Ɖ�����́A�ΊO���̑����A���O�̑厑�{�̌o�ώx�z�̋����������炵���B����A�y�n���v���n��̒�R�ɂ���ĕs�O��ɏI������B�����Đ��������ɂ́A�o�ς͒���A�ΊO���͋���Ȋz�ɂ̂ڂ�A�C���t���͍��i���A���Ƃ̕s�����J���ґ�O�̐������������Ă����B����A�_�Ƃ̐��ނ��i�݁A�H�����͂��߂Ƃ��鐶�������͕s�����A�_�����n���ɂ������ł����B
�@�o�ϓI��@�̐[�܂�̒��ŁA���̊Ŕł������u���R�̒��̊v���v�̌��z�͉_�U�������Ă��܂����B��O�̕s���͍��܂�A�J���҂̃X�g���C�L��y�n���v��v������_���̓��������W�����B
�@�����������Ō}�����X���̑哝�̑I���́A�E�h�̃u���W���A���}�E�����}�A�L���X�g������}�i�ȉ��L���}�j�A�l���A���̎O�b�̓����ƂȂ����B
�@�I���ł́A�l���A���̃A�W�F���f�����ʂƂȂ������A���̓��[���͂R�U.�Q���i�����}�̃A���N�T���h���͂R�S.�X���A�L���}�̃g�~�b�`�͂Q�W.�W���j�ƎO���̈ꋭ�ɂƂǂ܂����B�ߔ������Ȃ��ꍇ�́A�哝�̑I�o�͏㉺���@�̍�����c�̎w���ɂ�邱�ƂɂȂ��Ă����B�������A�l���A���̋c�Ȃ͗��@�c�������Q�S�̂����̂W�O�i��@�T�O���Q�R�A���@�P�T�O���T�V�j���߂�ɂ����Ȃ������B
�@�L���}�́A�����l���A�������@��̏C���������Ȃ�A�A�W�F���f�A�C�ɓ��ӂ���ƕ\�������B���@��̏C���Ƃ́A�V���{�͐V���A�����A����A�i�@�ȂǂɊ����Ȃ��A�R�̏��Z�͎m���w�Z�o�g�҈ȊO�ɂ͔C�����邱�Ƃ��ł����A�R��x�@�̋K�͂�ύX���Ȃ��A�Ȃǂł������B�����́A�哝�̂̌������K�����A�u���W���A���Ƌ@�\���ێ����悤�Ƃ�����̂ł������B�l���A���̓L���}�̎x������t���邽�߂ɂ����̏��������ꂽ���A����͎���̌�����������A�u���W���A�����⍑�Ƌ@�\�Ɏ��G��Ȃ����Ƃ��u���W���A�W�[�ɑ��Ė������Ƃ��Ӗ������B
�@�u���W���A�W�[�̎x�������㏞�Ƃ��āA�A�W�F���f�͉ߔ����i�P�T�����W���j�̊t�����l���A�����̃u���W���A���}����Ȃ鐭�{��g�D�����B����珔�}�͋c�Ȃł͂킸���ł������ɂ�������炸���������̂ł���B�c��̂V���͎Љ�}����S���A���Y�}����R�������t�����B
�������j�]�����l���A�������́g���v�h������
�@�A�W�F���f�����͔����Ɠ����ɐ���̎��{�ɒ��肵���B�R�N�ԂɎ��s������ȓ��e�́A�g�����̍Ĕz���h�A�Y�Ƃ̍��L���A����є_�n���v�ł������B
�@�Ƃ����Ă��A�A�W�F���f�����̓Ǝ��̐���Ƃ�ׂ���̂͏����̍Ĕz�����炢�ł����Ȃ������B
�@�Y�Ƃ̍��L���ɂ��ẮA�܂��P�l�R�b�g�A�A�i�R���_�Ȃǂ̕Čn��Ƃ����L����ܑ哺�R�̍��L�������{���ꂽ�B�������A�O�t���C�����̉��ł��A�`���̑��A�o�̂W�����߂铺�Y�Ƃ̍��L���͖����I�ۑ�Ƃ���Ă����̂ł���A�����}�����L���@�Ɋ��������ȊO�͂��ׂĂ̐��}������Ɏ^�������B�����ď��A�S�|�A�ΊD�i�����͂قƂ�ǃ`���̎��{�ł������j�Ȃǂ̎����Y�Ƃ����L�����ꂽ���A������u���W���A�I�Ȍ��E���z������̂ł͂Ȃ������B�����Y�Ƃ̍��L���́A���{��`�I���W�ɂƂ��ĕK�v�Ƃ���Ă����̂ł���B
�@�_�n���v�ɂ��ẮA�V�Q�N���ɂ͂W�O�������z�����y�n���L�͍��ɐڎ�����A�_���ɕ��z���ꂽ��A���邢�͐V���ɓ������ꂽ�����g���ɓ]�����ꂽ�B�������A���̓y�n�̉��v�́A�O��������̈��p���ł����Ȃ������B��n��͖��`�U����Ȃǂ����肵�Ď����I�ȓy�n�̐ڎ���Ƃꂽ���̂����Ȃ��Ȃ������B
�@���v���I��������_�ŁA�����̓y�n�������Ȃ��_�����c���ꂽ�B�y�n�������Ȃ��_�ƘJ���҂͂P�V���A���ƁE�Վ��J���҂͂P�S���A�Ƒ��̐����̈ێ�����������ȂT�����ȉ��̗�ה_�͂R�U�������݂����̂ł���B
�@����A�V�Q�N�̎��_�ł́A�Ȃ��Q�O�������z���钆�E�x�_�w�͔_�n�ʐς�Y�z�̖����߂Ă����B�������n��͋ߍx�̏��_�⏬��ɑ��Ĕ_�n���v����傫�ȉe���͂��s�g���邱�Ƃ��ł����B
�@�������̍Ĕz��������͑I������Ɋ܂܂�Ă������̂ŁA�Ǖw�A�V��ҁA�ސE�҂̂��߂̊e��N���̈����グ�A��Ô�̌��ƁA�P�T�Έȉ��̑S�����ɑ����������b�g���̃~���N�̖����x���A�Ƒ��蓖�̈����グ�A�X�����X�̏Z����P�A�f�Ï���w�Z���݁A���グ�Ȃǂł������B
�@���グ�͎�Ƃ��ĒᏊ���҂̈����グ��_���Ƃ������̂ł��������A�����ɂ��ׂĂ̘J���҂ɂ��āA�����㏸�ɑ��ĂP�O�O���̃X���C�h�i��R�T���̒��グ�j���������B
�@������A�́g�����Ĕz���h����́A������h�����o�ϊg��������炵�����ɂ݂����B�������A�����̂�܂��ɂ��Љ���̏[���Ƃ���������́A�P�C���Y��`�I�Ȑ���̏Ă������ɂ����Ȃ������B�����̖c���̓C���t�������i�����A�����܂��s���l�܂��Ă��܂����̂ł���B
�@�V�P�N�㔼��蕨���͏㏸���͂��߁A�����̕s�����ڗ����n�߂��B�C���t���ɂ�镨�����M���i�݁A�܂����Ԋ�Ƃ͐��Y���T�{���A���@�ɑ������B����A�č��̇��o�ϕ������̉e��������n�߂��B
�@�o�ς�����������ƂŁA�u���W���A���͔͂����{�U�����J�n�����B�ނ�̓}�X�R�~�������đ�X�I�Ȕ��l���A���L�����y�[�����s�����B�V�P�N���ɂ́A�H�ƕs���ɍR�c����u���W���A�����ɂ��u��Ȃ׃f���v���s��ꂽ���A����͐l���A���ɑ��鏉�߂Ă̊X���s���ł������B����ȍ~�A���u���W���A����������ʼnE���A�ێ琨�͂ɂ��e����f�����}���Ɋ����ƂȂ��Ă������̂ł���B
�������R���ւ̈ˑ��Ɛ����̕�����
�@�V�Q�N�X���ɂ͉E���e���g�D�ƌ��ꕔ�R���̃N�[�f�^�[�v�悪���o�A�����đS���I�ȁu���{�ƃX�g�v���s��ꂽ�B
�@���̃X�g�̔��[�ƂȂ����̂́A�g���b�N�A���Ǝ҂̃X�g�ł������B�S���Ԃ������B�ȃ`���ł͗A���̓g���b�N�i�قƂ�ǂ��Q�A�R������L�����Ǝҁj�Ɉˑ�����Ƃ��낪�傫���������A���{�͗A���̈���m�ۂ̂��߂ɓ암�̏B�ɖ��Ԃƍ����ō��ي�Ƃ����邱�Ƃ��v�悵���B����ɑ��ē암�̃g���b�N�Ǝ҂̑g���͌o�c���������Ƃ��Ĕ����A�v��P������߂ăX�g�ɓ˓������B�X�g�͑S���̃g���b�N�Ǝ҂ɔg�y�A����Ɏ��R�ƎҁA�����A��t�A�w���A���_�Ȃǂ��A�т��ăX�g��錾���A������u���{�ƃX�g�v���n�܂����̂ł���B
�@�S���̗A�����}�q�������X�g�̍Œ��A����ł̓L���}�A�����}���}�ɂ��l�t���̕s�M�C���������B����ɑ��ăA�W�F���f�哝�̂͐��{���E�����A�V���Ƀv���b�c���R���i�ߊ���O�R�̑�\����t�������R�����t��g�D�����B�A�W�F���f�͌R���̗͂�����č����������Ԃ̎��E��}�낤�Ƃ����̂ł���B����͐l���A�����{����������\�͂̂Ȃ����Ƃ�����\�I����ȊO�̂Ȃɂ��̂ł��Ȃ������B
�@�����V�R�N�R���̑��I���ł́A�l���A���h�͋c�Ȑ��ɂ����Ă����[���ɂ����Ă��x��������₵�����A�K���Η��͈�w�������Ȃ��Ă������B�I����A���v���h�̍U���́A�o�ϓI�h���Ԃ肩��R���ւ̍H��A�e�������ւƑ��ʓI�ƂȂ��Ă������B
�@�R�����ɂ́A�R���̈��͂Ő��{�ɋ��͓I�ł������v���b�c���R��R�l�̌R�l�t�������C�ɒǂ����܂ꂽ�B�����U���ɂ́A�R���ɂ��N�[�f�^�����������N�����B����܂ŌR�l�ɂ��N�[�f�^�v��͊��x�ƂȂ����o�������A���ۂɎ��s���ꂽ�̂͂��ꂪ���߂Ă̂��Ƃł������B
�@����A���{�Ɛ��͂ɂ�鐶�Y�T�{�^�[�W���A���@�A�Ŏs��ւ̕����̉������Ȃǂ́u���{�ƃX�g�v�ȗ������Ƒ����Ă���A�o�ς̍����ɔ��Ԃ��������B
�@�G���e�j�G���e���R�Œ������߂����ăX�g���N�����̂́A���������o�ς�����n�̏�Ԃɂ������S���̂��Ƃł������B�Q�J���ɋy�ԃX�g�͈ꎞ���̎x���Ŏ��E�������A��������������Ƃ��āA�S���ʼnE���e���������ƂȂ�A����ɑR���鍶���Ƃ̏Փ˂��J��Ԃ����B
�@����̊�@�����X�Ɣ���Ȃ��A���{�͘J���҂ɑ��Ĕ������Ăъ|���A�g�D����̂ł͂Ȃ��A�t�ɃL���}�ɑ����L������̌����A�H��E�y�n�苒�̒�~�A��ɍ��v���Ȃ����L����Ƃ̖��Ԃւ̕Ԋ҂ȂǁA�g���v�h���~�Ȃ����͌�ނ����邱�Ƃ���邱�Ƃɂ���ċ��͂����t���悤�Ƃ����̂ł���B
�@�����������{�̑Ë��I�ԓx�́A�����{�h���܂��܂������Â����邱�ƂɂȂ����B�L���}�͐��{�̗v�������ۂ����B�����āA���R�X�g�̂قƂڂ���܂����߂��ʂV�����{�A�Ăуg���b�N�Ǝ҂��X�g�ɓ������̂��_�@�Ƃ��āA�S���I�ȑ�K�͂ȁu���{�ƃX�g�v���J��Ԃ��ꂽ�B
�@����Ɍ������𑝂��Ă����K���Η��ɂ���Čo�ς��}�q����Ȃ��ŁA�{�肭��������u���W���A�͎��X�ƉE���A�ێ琨�͂ɂ�锽���{�U���Ɋ������܂�Ă������B���Y�}�͏��u���W���A�����������Ƃ����ĉ��v�����߂炢�A�����߂����������B�ނ�͔_�n���v��O�i�����邱�Ƃ����߂Ĕ_�n��苒�����_���̓�����A���Y���T�{�^�[�W�����鎑�{�Ƃ̍H��苒���s�����J���҂̓������u�ɍ��ϓ��v�Ɣ��A�u���W���A�W�[�ɑ��ĉ��v�́g�����h������̂ł���B
�@�����A�E���A�ێ琨�͂����u���W���A�v���I�ȍs���ɓ����������̂́A�l���A�����{���g���v�h�����߂炢�A�u���W���A�Ƃ̑Ë��I�ȑԓx�ɏI�n��������ɂق��Ȃ�Ȃ��B���{�̑Ë��I�A���a����`�I�ȑԓx���������v�����͂𐨂��Â����A�o�ς��}�q�����A��]�������u���W���A�v���̑��ɒǂ�������̂ł���B
�@���{�͓����ɍ��܂鐭���I�A�Љ�I�s���ɏI�~����ł��߂ɁA�ĂьR�����t��g�D�����B�����A�A�W�F���f������t���ɔC�������s�m�`�F�g���R��ɂ��R���̃N�[�f�^�[�ɂ���Đl���A�������͑œ|���ꂽ�B�N�[�f�^�[�̂��̓�����l���A���̊����Ƃ̑�ʑߕ߂��s���A�����������s�E�ŎE���ꂽ�B�ȍ~�A�\���N�ɓn��R���ƍق̎��オ�n�܂�̂ł���B
�@�Ћ��͌R�����x�z�K���́u�]���ȏ��g�Ƃ݂Ȃ����Ƃ͂ł��Ȃ��v�Ɣ������Ă����B���Y�}�͎��̂悤�ɏq�ׂ��B�`���̌R���́u�E�ƈӎ��ƁA�����I�ɐ����������{�d���悤�Ƃ��鐸�_���x�z�I�ł���B���킦�āA���R�ƊC�R�́A�Ɨ����߂��������̂Ȃ��Ő��܂ꂽ�B�O�R�̈�ʕ��m�Ǝm���͕n�����Љ�K�w�̏o�g�҂ł���A���Z�̂قƂ�ǂ��ׂĂ����ԑw�̏o�g�҂ł���v�B
�@�����A�`���̌o���͋��Y�}�̎咣���܂������̓��a����`�I���z�ł���A�u���W���A���Ƃ̌R�������{�̂��߂̊K���I�\�͋@�ւł��邱�ƁA�J���҂̓u���W���A�̌��͋@�\��ł��ӂ��A����̊K���I���͂�ł����ĂȂ邱�ƂȂ��ɂ͊v�������������邱�Ƃ͏o���Ȃ����Ƃ����߂Ď������B
�@�J���҂̊v���I�����Ɉˋ����Љ���v�W������̂ł͂Ȃ��A�u���W���A���͂Ƃ̑Ë��ɂ͂���A����ɂ͔����I�ȌR���Ɉˑ����Ă������l���A���̓��a����`�������s�k�����������̂ł���B
|
�P�P
�t�O�^�}�Ńu���W���A���{�x����
���ɋ��Y�}�́u���j�I�Ë��v�H�� |
�������`���l���A������Ɓu���j�I�Ë��v������
�@�u���j�I�Ë��v�H������N���ꂽ�_�@�ƂȂ����̂́A���O�N�̃`���l���A�������̕���ł������B�A�����{�͂Ȃ��R���N�[�f�^�ɂ���đœ|���ꂽ�̂��A���̌������߂����Đ��E�I�ɂ��傫�Ș_�c�ƂȂ������A�x�������O�F�������P�Ƃ��Ĉ����o�������̂́A���Y��`�ҁA�Љ��`�ҁi�Љ���`�ҁj�A�J�g���b�N�Ƃ����u�O���O���́v�̓����Ƃ����V���ȘH�����u���j�I�Ë��v�ł������B
�@����́u�`���̎��ό�̃C�^���A�ɂ��Ă̍l�@�v�Ƒ肵�Ĕ��\���ꂽ�B�����Ńx�������O�F���͎��̂悤�ɏq�ׂ��B
�@�u����I�Ȋv�V�̐����̎����v�̂��߂ɂ́A�L�͂ȎЉ�I�����̐���Ƃ��������ł͕s�\���ł���A�u�S���吨�́E�S�l�����͊ԂŁA�����I�������ł�������قǂ܂łɁA�����̐��͊Ԃ̈�v�Ƌ��͂��A�i�����邱�Ƃ���邷�悤�ȁA������̐����W�̑̐����K�v�ł���v�A�Ȃ��Ȃ�A�u�l���̂Ȃ��Ɋ�Ղ������A�l���̏d�v�ȕ������\����悤�ȏ����}���A���������ɓG������A�������U�����������肷��悤�ł́A��������A�����ʂ�A�����܂��Ղ��ɕ��邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B����͖����`�ɂƂ��āA�v���I�ł���A����I���Ƃ̉����̊�Ղ��̂��̂����A�Ƃ菜�����˂Ȃ��v����ł���B
�@�u�ΘJ�҂̏����}�ƍ�������́A��������ɉE�ɂ�����n�ʂ��������}�̃u���b�N�ƑΒu�����ꍇ�ɂ́A�����`�̖h�q�Ɛi����ۏႷ�邽�߂̏\���̏����ɂȂ�Ȃ��v���A�u���������}�ƍ������͂��A���[�Ƌc���̐��łT�P�����Ƃ�������Ƃ����āA�����̈����ێ����ۏႳ��Ƃ����̂͑S�����z�ł���B�����炱���A�����́A�w�����I���x�Ƃ͌��킸�A�ނ���w����I�Ȍ��x������Ă���̂ł���B�w����I�Ȍ��x�Ƃ́A���Y��`�I���O�E�Љ��`�I���O�����l�����͂ƁA�J�g���b�N�I���O�����l�����́A�����Ė����`���u������c�̂Ƃ̊ԂŁA�ЂƂ̋��͂ƂЂƂ̑��ݗ������������Ă�A�Ƃ��������I�ȓW�]�̂��Ƃł���v�i�x�������O�F�����w��i���v���Ɨ��j�I�Ë��x���j
�@�`���l���A���͍������͂̓������ՂƂ��Ă������߂ɁA�L���X�g������}�̉e�����ɂ����O�����W���邱�Ƃ��ł����ɁA�E�������h�̔��v�����������B�u����I�Ȋv�V�����v���������Ă������߂ɂ́A�L���X�g������}�Ƃ́g�a���h�������i�ȉ��A�L���}�j���K�v�ł���Ƃ����̂ł���B
�@�������A���u���W���A���{�s���ɂ��藧�āA�E�������h�ɒǂ�������̂́A���{�̎x�z�̊�b�Ɉ�w���G��悤�Ƃ����Ȃ��l���A�����{�̉��ǎ�`�ł������B�l���A�������́A�u���W���A���Ƌ@�\�ɏ��������t���悤�Ƃ��Ȃ��������A�E�������h�̍����������ɂ����B����͂܂��܂������h�A�ێ�̐��͂����オ�点���̂ł���B�J���҂̊v���I�����W�����Ă������Ƃ������A���u���W���A��J���҂̖����Ɉ����t�����邢�͍D�ӓI�����̗�����Ƃ点�邱�Ƃ��\�ɂ������낤�B
�@�܂��x�������O�F���̓L���}�����̂܂����킯�ł͂Ȃ��B�u����̓L���X�g������}�̐���������w���H���̕ω����܂ނ̂��v�A�L���}�̓����̕ێ�I�A�����I�X���⎎�݂��Ǘ������A���̐l���I�v�f�̔�d����Ɋm�F������悤�Ȏ����I�Ȏh���A���ꂪ�u���j�I�Ë��v�̒�ĂȂ̂��Ǝ咣�����B�����A����̓u���W���A���}�ւ̒ǐ����B���f�}�S�M�[�ɓ������B
�@�x�������O�F���́A�`���̌o������J���҂̒f�ł���v���I�����̕K�v�ƕK�R���Ƃ������P���w�Ԃ̂ł͂Ȃ��A���ɐ��{�������̑命���̎x�������邽�߂Ƀu���W���A���}�Ƃ̓������K�v���Ƃ������a����`�I���_���������̂ł���B
�������C�^���A�̊�@�ƍ����I�g�A�сh�̑i��������
�@�V�R�N�H�A�Ζ���@�͌o�ς������B�G�l���M�[�̂W����Ζ��Ɉˑ����A���������̂X���ȏ��A���ɂ������ł���C�^���A�ɂƂ��āA�������i�̈����グ�͑�Ō��ł������B�C���t���͂܂��܂����i�����B�C���t���ƕ����㏸��}�����邽�߂Ɉ������ߐ����{���ꂽ���A����͊�Ɠ|�Y�Ǝ��Ƃ̑������������B���̂��߂V�S�N������ɘa����ɐ�ւ���ꂽ���A����͍ĂуC���t���A���������������Ƃ������悤�ɁA�C�^���A�́u�j�Y��ԁv�Ƃ�����ɂ������B
�@�o�ϓI��@�͐����I�A�Љ�I�����������N�������B�o�ϔ��W�ɂƂ�c����A�S���̂R�̕n���w���W������암�̓l�I�E�t�@�V�X�g�̍ő�̉����ƂȂ��Ă������ɉE�A�l�I�E�t�@�V�X�g�̃e���́A�܂��܂������ƂȂ����B�����ĂV�O�N�ɑ����āA�V�S�N�ɂ��E���R�l�ɂ��N�[�f�^�v�悪���������Ƃ���ɔ��������B�哝�̂͌R�ɍ��Ƃւ̒��������߂鐺�����A���Y�}��J�g�̊����͈��S�̂��߈ꎞ�g���B���˂Ȃ�Ȃ��Ƃ����ł������B
�@���������Ȃ��ŁA���Y�}�́u����v�Ɍ������g�~���̓}�h�Ƃ��ēo�ꂵ���B�u���j�I�Ë��v�́A��@�Ɋׂ����u���W���A�x�z���~�o���邽�߂̐���ł������B
�@�V�S�N���A�x�������O�F���́A��@�𐭎��A�o�ρA�����̂����镪��ɂ킽����̂Ƃ��ĂƂ炦�A����ɑΏ����邽�߂ɂ̓L���}�₻�̑������}�̐ӔC��ᔻ����ɂƂǂ܂��Ă͂Ȃ�Ȃ��A�����́u�ْ������w�́v���K�v�ł���A�Ƒi�����B
�@�u�ْ������w�́v�Ƃ����̂́A�u�����Ƒ������Y���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃ��Ӗ����Ă���A�����鎑����Q����A�ߖA���p���Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ��Ӗ����Ă���A�c�c���݂̐����l���Ƃ͈�����l���ł̂��悢�����l���̓���T�����邽�߂Ɏ�̏K����ς��Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ��Ӗ����Ă���v�B�J���҂ɂ͐��Y�ւ̓w�͂Ɛߖ�ł���B
�@�����Đ����Ƃ�������ɑ��Ắu��������э��Ƃɂ������錣�g�I�ȕ����v���A���t�Ɗw���ɑ��Ắu�w�K�ɂ�������^�����ƋK���v���A�m���l�ɑ��Ắu���̐i���̂��߂̔C���̎��o�v���A�����čŌ�Ɂu��s��s�����A�ɒ[�ɂȂ������Ȏ�`��l��`�v�ɔ����鍑���̘A�т�i�����B
�@�����A�C���t���̍��i�ɂ��o�ϔj�]�A�����Ƃ�������̕��s�A���A���Ȏ�`��l��`�̖������X�A�C�^���A���ׂ��Ă���o�ϓI�A�Љ�I�Ȑ[���Ȋ�@�̓u���W���A�Љ�̖����Ƃ������p�̌����ł������B���p���A���s�������{�̑̐������̂܂܂ɂ��āA��@�����̂��߂́u�����I�v�c���ƘA�т�i���鋤�Y�}�̎咣�́A���͂ł��蔽���I�ł������B����͊�@�̍����ł��鎑�{�̎x�z����ڂ点�A���{�Ƃ̋��́A�u���W���A���Ƃ́u�Č��v��J���ґ�O�ɑi������̂ł���������ł���B�x�������O�F���́u�߂��ڕW�Ƃ��ĎЉ��`�̖ڕW���N���邱�Ƃ͂Ȃ��v�ƁA�u���W���A�W�[�ɐ����������B
�@���Y�}�̒�ẮA�L���}��Љ�}�ɖ������ꂽ�B�������A�I���ł͋��Y�}�����i�����B�V�T�N�̓���n���I���ł́A���Y�}�͂R�R.�S���̕[���l���A���}�̃L���}�ɂP.�X���ɂ܂Ŕ������B�����V�U�N�̑��I���ł��A���Y�}�͂R�S.�S�����l���A�c�Ȃł��Q�Q�V�i�U�R�O���j�ƃL���}�ɓ��[���łS.�R���A�c�ȂłR�U���܂Ŕ������B�L���}�ɂƂ��đI���Ŗ��i�������Y�}�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ȃ����B
�������u��펞���t�v�Ƃ��̍��܁�����
�@���ɑI���̊��Ԓ��A���Y�}�́u���j�I�Ë��v�ً̋}�łƂ��Ắu������v���t�v��������A�I����A�c����}�Ƃ��ĉ��@�c���ƂU�̏�C�ψ������l���������Y�}�̗^�}���͋}�s�b�`�Ői�B
�@��O���A���h���I�b�e�B�E�L���}�P�Ɠ��t�ł̐V�C���[�ł͋��Y�}�͊����������A����͎�����A���{�̐M�C���Ӗ������B���ہA�I����͐��{�Ƌ��Y�}�̒�����c��������A��Ȑ���ƕ��j�͂��炩���ߘb�������Ă����̂ł���B
�@�����ċ��Y�}�͑g�D�A�V�V�N�͂��߂ɂ́u��펞���t�v�������āA�L���}�Ƃ̐�������ъt�O�^�}�ƂȂ����B
�@�o�ϊ�@��������ƂƂ炦�A�o�ύČ�������̉ۑ�Ƃ������Y�}�́A���{�̑ϖR����\�\�e����������̒l�グ�A�����̈ꕔ�����A�����̕����X���C�h���̗}���A���グ�̗}���A�x���̍팸�A�Љ�ۏ�̍팸���X�\�\�����X�Ǝ���A���͂𐾂����B
�@�x�������O�F���́A�u�ϖR�v�̈Ӌ`�ɂ��āA�u�����ɂƂ��đϖR�́A����Ɍi�C���I�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A���{�I�ȍ\����@�Ɋׂ����̐��̍����Ƀ��X������A��������������邽�߂̎�i�ł���B�c�c�ϖR�́A�V�������l�̘g�g�������炵�A�܂��������ƌ����A�^�����ƌ������Ӗ�����v�i�w�ϖR����ƍ��̕ϊv�x�j�Əq�ׂ��B
�@�������A�u���W���A���Ƃ̌R���⊯���g�D�̖c���A���̑����X�̕s���Y�I�Y�Ƃ����p�I�Y�ƁA����ɏ]������s���Y�I�K����I�K���ɂӂꂸ�ɁA�Q��◔�����A��O�́u�ϖR�v�̔�����������Y�}�̎咣�́A�܂������̋\�Ԃł������B
�@�C���t���ɔ����ė����オ�����J���҂ɑ��āA���Y�}�́u�C���t���ɑ��铬���́A�J�����Y���̌����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�A�u�]���Ȃ����Ċ�@����̒E�o�Ȃ��v�Ɛ������Ă܂�����B
�@����I�ɘJ���ɋ]������������̂Ƃ��āA�J���҂̕s����{��͍��܂����ł������B�V�U�N�̂P�O������P�Q���ɂ����āA�ϖR����ɍR�c���ăC�^���A�ŋ��̘J�g�̈�g���m�E�t�B�A�b�g�H��̘J���҂����Y�}�̎s����݂邵�������̂��͂��߁A�ϖR����ɔ����č��S�A�X���̘J���҂Ȃǂ̂S�O���l�̃X�g�A���[�}�J���҂̂P�O�O���l�X�g�A�����J���҂̓���f�����s��ꂽ�B
�@���Y�}��^�}�Ƃ���u���j�I�Ë��v�̐��{���J���҂̔������Ǘ���[�߂�Ȃ��A�V�V�N�ɂ́A�}�i�h�́u�Ԃ����c�v�ɂ�郂���E�L���}�}��U�������i�̂��E�Q�j���N�������B������_�@�ɃL���}�͋��Y�}�ɑ��ė�W�ȑԓx���Ƃ�悤�ɂȂ��Ă������B����̓L���}�̎w���҂̂����ōł����Y�}�Ƃ̘A�g�ɐϋɓI�ł������������������Ƃ������Ƃ����A�ő��A�L���}�����Y�}�̋��͂̕K�v��F�߂Ȃ��Ȃ������ʂł������B�L���}�ɂƂ��ċ��Y�}�Ƃ̘A�g�́A�J���҂ɋ]���𐄂����Ċ�@�����邽�߂̈ꎞ�I�Ȑ���ł������B
�@����͑��풼��̂S�T�`�S�V�N�̌J�Ԃ��ł������B�������Y�}�̓L���}�𒆐S�Ƃ��釀�����I�����t�ɓ��t���A�푈�Ŕj�ꂽ�o�ς̕����ɕ�d�����B���Y�}�͘J���҂ɃX�g���C�L�̎���������A���Y�ւ̋��͂�i�����B�������ĘJ���Ґl�����]���ɂ��Ď��{��`�I�Č��̊�b���z���ꂽ�B�S�V�N�A�L���}�͐��{���狤�Y�}��Ǖ������B�u���W���A�W�[�́A���̎x�z���s����ł���J���҂̍U���ɂ��炳��Ă���Ƃ��́A�J���҂̍U�������炷���߂̏��Ƃ��ċ��Y�}�̑�b��K�v�Ƃ������A�ő��K�v���Ȃ��Ȃ�������ł���A�u���W���A���}�����̂ق�������w���ʓI�Ɏ��{��`�I�Č����o���錩�ʂ�����������ł������B���Y�}�͒x���ꑁ����A���p�ς݂Ƃ��ĒǕ������^���ɂ������̂ł���B
�@�J���҂ɋ]�������v���鐭�{�ɑ���J���ґ�O�̕s�M��{�肪���܂�Ȃ��A�x�������O�F���͂V�W�N�T���ɂ́A�}�́u����I�ȃC�j�V�A�e�B�u�������߂��A�F�������v�ƌ��킴������Ȃ������B�����ė��N�P���ɂ͋��Y�}�͂��ɗ^�}���E�����肵���B
�@�V�U�N�����R�N�ɂ킽��u���j�I�Ë��v����́A��@�Ɋׂ����L���}�x�z�̕⊮�I�������ʂ������B����́A���A�L���}�ƘA����g��Ńu���W���A�x�z�������Ă����������}�̖��������Y�}��S�����Ƃ��Ӗ������B
�@�u���W���A���}�ƂƂ��Ɏ��{��`�̖���I���v���������Ă����Ƃ������u���j�I�Ë��v�̐��{�́A�\�����v�H���̈�w�̐i���̌��ʂł������B�\�����v�H���ł́A�Љ��`��W�]�����g����I���v�h��搂������A�u���j�I�Ë��v�H���́A�Љ��`��I�グ���u���W���A���Ƃ́u�Č��v��i�����̂ł���B�V�O�N��́u���j�I�Ë��v���u�����I���{�v�̌o���́A�������Y�}�����Ă���ێ琨�͂��܂߂��u�b�萭�{�v���邢�́u���܂����{�v�ɘJ���҂͐M�����邱�Ƃ��ł��Ȃ����Ƃ������Ă���B
|
�P�Q
���ނ��鎑�{�Ƀe�R����
�����A�~�b�e�����哝�̉��́u�����A�����{�v |
�@�P�X�W�P�N�T���̑哝�̑I���퓊�[�ŁA�ێ�̃W�X�J�[���f�X�^����j���āA����������̎Љ�}�~�b�e�������哝�̂ɓ��I�����B�����̏����͂R�U�N�̎Љ�}�u�����l��������{�ȗ��S�O���N�Ԃ�̂��Ƃł������B�C���t���̍��i�A���Ƃ̑����ȂǎЉ�I�������[�܂�Ȃ��ŁA�N��J����O�͍������~�b�e�����Ɋ��҂����B�Ћ��́A�u�����A���v�ɂ��u�Љ���v�v������B��������͋�ł����Ȃ������B�u�����A���v�����̓u���W���A�����ɍs���������B
�������Ћ��A�������̒a���Ƃ��̐�����
�@�哝�̑I�Ɉ��������čs��ꂽ�U���̍����c��I���́A�Љ�}�i�}�i�Љ�}�����܂ށj�������A�P�Ɖߔ������l�������B�ɂ͎Љ�}�̃��[�������C������A���Y�}������S�l�����t�A�Ћ��A�����t���a�������B
�@������������ɂ́A���ƁE�ٗp��Ƃ��ĂQ�P���l�̌������i�n�������́A�X�ցA�a�@�A�����E�Љ�{�ݓ��j�̑����A�U�O���N�̌ٗp�v������肵���B�܂��J����ł͒������Ȃ��ɏT�S�O���ԘJ������R�X���ԂɒZ�k�i�W�T�N�܂łɂ͏T�R�T���ԘJ���Ɂj�A�L���x�ɂ��P�T�Ԃ̑����i�S�T�Ԃ���T�T�ԂɁj���ꂽ�B
�@����ɎЉ�ۏ���g�傳�ꂽ�B�Œ�����P�O�������グ���͂��߁A�Ƒ��蓖�A�Z��蓖�Q�T���A�V��N���̂Q�O���A�����蓖�Q�T���A�g�̏�Q�Ҏ蓖�Q�O�������グ�������{���ꂽ�B�����Ă����̑[�u�̍����̈ꕔ�Ƃ��ĂR�S���t�����ȏ�̏��������l�ɑ���x�T�ł̓����A�Ζ���ƁA��s�ւ̑��ł��s��ꂽ�B
�@�V�Q�N�̎Ћ��������{�j�̂Ɋ�Â��āA�S�|�A���w�A�d�@�A�R���Y�ƂȂǍH�ƕ���ЁA��s����ѕی��̓�Ђ�ΏۂƂ��č��L�������{���ꂽ�B
�@���[�����͍��L���@�Ă̎�|�����Ŏ����̂悤�ɏq�ׂ��B�u���ɏグ����̂́A���含�E���́E�����͂ɕx�݁A�V�����_�C�i�~�Y���ݏo����Ƃ���\������鋭�͂Ȍ�������̊g��ł���v�u���̖@�Ă��w�肷���Ƃ̃R���g���[������������c�c������v�Y�Ƃ𒆐S�ɂ��āA�L�x�ȋZ�p�͂ɒ��킷�鋐��Y�ƕ�����m���ɔ��W�����邱�Ƃ��ł���v
�@���[���������͂���獑�L�������{�̎x�z���������Ă��������Ƃ��Ĉʒu�t���Ă����̂ł͂Ȃ��A�ړI�́A�Y�Ƃ̍Đ��A���ۋ����͂̋����ł������B���L���ɂ���ē����Ɛ��Y�̌����I�^�p��}�낤�Ƃ����̂ł���B��s�A�ی��̍��L�����A�������������v��ւ̏d�_�I�Ȏ����Z���𑣂����߂ł������B���풼��A�t�����X��C�^���A�ł̓u���W���A�����̂��ƂŃh�C�c�ɋ��͂�����Ƃ𒆐S�ɍ��L�����s���A�o�ς̕����̖�����S���Ă������A���[���������ɂ�鍑�L�������������u���W���A�I���L���ł������B
�@���[�����́u�����x�o����A����g��ɂ��i�C�h���A����������Ƃ�A���ƂƂ̂�����������̉ۑ�Ƃ��A�C���t����͑�I�ۑ肾�Ƃ��Ă����v�Əq�ׂ����A�����̐���́A�����x�o�Ə���g��ɂ��i�C��}�낤�Ƃ���P�C���Y����ł������B�����A����ɍ��������Ƃ��ēƎ������������߂ɎЉ�ۏ�Ƃ��J�����ԒZ�k�Ȃǂ̘J������������ꂽ�ɂ����Ȃ��B
�@�������A���L��Ƃ͕s�U������߁A�V���ɍ��L�����ꂽ��Ƃ̐Ԏ��͂W�Q�N�ɂ͖�P�U�O���t�����ɒB�����B�܂����L���ɔ����⏞�����������������B��O�̏����̑���ɂ���ď�����v���g�債�A��Ƃ̐��Y�E�����������ɂ��i�C��}���Ă����Ƃ����̂����{�̖ژ_�݂ł������B�����A�����c���ɂ��P�C���Y����̓C���t���������A�A�����g�債�f�ՐԎ����U�W�N�ȗ��̍ň����L�^�����B���Ǝ҂͂Q�O�O�����A�킸���P�N�Ő��{�̐���͔j�]�����B
�������I���ȃu���W���A�Y�ƍČ�����
�@�W�Q�N�T���A�h���[�������́u�����Ə����}���ɂ��C���t������d�_�ɂ����A�ϖR�A�����A�сA�w�͂��K�v�ł���v�Ƒi���A�����c������ُk����ւ̓]���𖾂炩�ɂ����B
�@�܂��U���ɂ͒ʉ݂̐艺���ƁA��������S�J���Ԃ̕����ƒ����̓������s��ꂽ�B�����āA�W�R�N�R���ɂ́u�ُk�v�����v�i�h���[���E�v�����j���ł��o���ꂽ�B���̎�ȓ��e�͎��̂悤�Ȃ��̂ł���B�Љ�ی����̂P�������グ�A��ŁA�����ł̈����グ�A�K�X�A�d�C�A�d�b�����A���S�^���̂W���l�グ�A���~�̋`���Â��A�O�ݐߖ�̂��߂̊O�����s�̐����B
�@����́A����܂ł̐��{�̌��������ے肷�邱�Ƃł������B�Ћ��͕ێ琭���̂��ƂŁA�J���ґ�O�̐������j��Ă����Ɣᔻ���A�ނ�̐��������Ƃ��Ȃ����A����������������Ă������ł���ƌ���Ă����B�������A���{�͘J���ґ�O�ɑ��āA�o�ϊ�@���������Ă������߂ɂ́A�]����ς����̂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ����̂��B�u�ϖR�v�����߂��Ă���̂��J���ґ�O�A�Ꮚ���҂ł���A�������K���⎑�{�łȂ����Ƃ́u�ُk�v�����v�̊K�����𖾂炩�ɂ��Ă����B
�@���{�͘J���҂ɋ]���������������ł́A��Ƃɑ��ẮA���Ɛł̌��ŁA�Љ�ی����Ǝ啉�S���̓����Ȃǂ�����B�J���ґ�O�̋]���ō������肫�낤���Ƃ���u�ُk�v�����v�͂��肫����̂��̂ł������B
�@�Ƃ��낪���Y�}�́u�����̓}�v�Ƃ��āA�u���ʂً̋}��@����E�o���ϊv�̓�������Ђ炭���߂́w�K�v���x�ł���v�Ƃ��Ă��̔����I�ȃu���W���A�����F�߂��B�ő�̘J�g���Y�}�n�̘J���������i�b�f�s�j������ɂȂ�����B
�@���Y�}�i����тb�f�s�j�ɏ������āA���{�͂���ɘI���Ȏ��{�Č������ł��o���Ă������B
�@���[�����̌�A�V���ȎɔC�����ꂽ�̂̓t�@�r�E�X�ł��������A�ނ͂��łɍH�Ƒ��̎��ɁA���ۋ����ɂ����ăt�����X�̎Y�Ƃ͎x�z�I�n�ʂ��m�ۂ��čs���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��A���L��Ƃ��s��o�ςƍ��ۋ����ɑg�ݍ��܂�Ă���ȏ�A�o�c�҂͐v���Ɉӎv���肷��K�v�����邵�āA���Ƃ̉���̊ɘa�������A����ɍ��L��Ƃ��Ԏ��𗝗R�ɍ��Ɨ\�Z�ɏ������邱�ƂȂǘ_�O�ł���Əq�ׁA���L��Ƃ̍ĕҁE�������v��𖾂炩�ɂ����B
�@����́A�Ő�[�Z�p�ƃG���N�g���j�N�X�Y�Ƃ̈琬�ƓS�|�A�����ԁA���D�A�ΒY�Ȃǂ̋@�֎Y�Ƃ̃��X�g���ł���B�������āA�t�@�r�E�X���t�̂��ƂŁA�����Ԃ̃v�W���[�łQ��l�̎�肪�s��ꂽ�̂��͂��߁A�ΒY�i�R���l�j�A���D�i�T��l�j�A�S�|�i�Q���T��l�j�ȂǑ�K�͂Ȑl���팸�E�����������s����Ă������̂ł���B
�@���Y�}�͂��̃t�@�r�E�X���ɂȂ����̂��@�ɁA�A���������痣�E�����肵���B�J���҂��]���ɂ��Ď��{�̂��߂̎Y�ƍĕҁE�������𐄐i����t�@�r�E�X�����ɑ���J���҂̓���������Ă̂��Ƃł���B��荇�����ɔ����ĘJ���҂̓X�g���C�L�����ɗ����������B
�@���Y�}�́A�~�b�e�����Љ�}�͘J���҂𗠐����Ɣ����B�����A�ނ�Ƀ~�b�e�����Љ�}��ᔻ���鎑�i�Ȃǂ��炳��Ȃ������B�~�b�e�����Љ�}�������グ�A�Љ�}�ƘA��������g�݁A�x���Ă�������ł���B�ނ�́A�Љ�}�ƂƂ��ɃP�C���Y��`�ɂ������x�o�Ə���g��ɂ��i�C������ł����B�����A����͔j�]���A���[���������ُ͋k����ɓ]�����Ă������B�ُk����́A���Y�}���i�삵�Ă�������g��̃P�C���Y�I����̔j�]�̕K�R�I�Ȍ��ʂł������B�t�@�r�E�X�̐���������ł���B���{��`��O�邩����A���{�̗i��Ƃ������u���W���A�����ɍs����������Ȃ��B
�@���Ƃ��ƃ~�b�e�����Љ�}�Ɏ��{�Ɠ����ӎv�ȂǂȂ������B�哝�̑I�̔N�̏��߂ɔ��\���ꂽ�}�̑I���j�̂́u�Ɨ����[���b�p�̒��̋��͂ȃt�����X�v�Ƃ��āA�u�����Њ�ƁA�A�����J����ѓ��{���i�̐Z���y�ѐZ�����牢�B�����̂����v���Ƃ��f�����B�~�b�e�����́A���B���������͂ɐ��i�����B���̖ړI�́A���B�ɂ����鋭�͂ȃ��C�o���Ƃ��ēo�ꂵ���h�C�c����荞�݁A�č�����{�ɑR���ĉ��B�������������A���̖���Ƃ��ăt�����X�������邱�Ƃł������B����̓t�����X�Ɛ莑�{�̖�]���ق�����̂ł������B
�����������j�̂Ƌ��Y�}�̘A��������
�@�W�T�N�ɊJ���ꂽ���Y�}���́A�V�Q�N�̎Ћ��E�����j�̂Ƃ���ɂ��ƂÂ������A������ɂ��āA�u�ے�I�����v���ʂ������Ƒ��������B�u�Љ�}�������A���ɑ������̂́A�l���^���f���A���̐퓬�\�͂����킹�A�킪�}�̉e���͂����ނ����邽�߂ł������v
�@�����ă}���V�F���L���͒����ϕŋ����j�̂ɂ��Ď��̂悤�ɏq�ׂ��B�u�����j�̂́A���܂��܂ȍS���������ɉۂ����B���ɁA�����j�̂ɂ��ƂÂ��������}�̘A�����������v�ɗB��ŗǂ̎�i�Ƃ���ꂪ�m�M�����Ƃ�����A���N�ɂ��킽��A�ϊv���߂������������A���̂悤�ȋ�������Ԃ��߂̂���������D�悳�����B�c�c���ɁA�����j�̂���������A�d�v�ȉ��v�����̍j�̂ɂ��肱�ނ��Ƃɐ������Ĉȗ��A��@����̒E�o�̂��߂Ɏ������ׂ�������̐��i�Ƃ����ł��d�v�ȉۑ���������ɉ������ꂽ�Ƃ݂Ȃ��X�����������v�u�����́A�����j�̂ɁA���{�̎x�z�ɔ�����[�u���܂܂��邱�Ƃɐ��������A�������A���̂��Ƃ͓����ɁA�Љ�}�����{��`�Ƃ̌��ʂ����肵�����̂悤�Ȍ��z���L�߂錋�ʂƂȂ����v�B�������đ��́u�����A���v�ɂ�����āu�V���������h�̐l���A���v��ł��o�����B
�@�u�����A���v���Љ�}�Ƃ̘A���ł͂Ȃ��āu�V���������h�̐l���A���v���Ƃ����Ă��A�����������{�I�ȈႢ�����邾�낤���B�����A���Y�}�̘A���̑��肪�Љ�}�ł͂Ȃ��Ȃ����Ƃ������Ƃɂ����Ȃ��B�Љ�}�Ƃ̘A�����j�]��������A�u�l���A���v�Ƃ����͎̂���́u�A�������v�A�Љ�}�Ƃ̓�ꍇ�������̔j�]�����܂����\�Ԃł����Ȃ����낤�B�t�����X�̎Ћ��A�������́A���Y�}�́u�A�������v�̔j�]�𖾂炩�ɂ��Ă���B
�@�u�����A���v�����������̂́A�Z��N�Ɂu���{��`���\���鐭���I���͂Ƃ̓����v�̋֎~�����c���A���ׂĂ̍������}�Ƃ̘A����i�������Ƃ��_�@�Ƃ��Ă���B�V�P�N�ɎЉ�}�̍Č����J�Â���A���́u�����A���v�̕��j�������Ɋm�F����A�~�b�e��������ꏑ�L�ɑI�ꂽ�B���������o�߂��o�āA�V�Q�N�Љ�}�Ƌ��Y�}�Ƃ̊Ԃŋ������{�j�̂����ꂽ�B����Ɋ�Â��āA�V�S�N�̑哝�̑I�ł̓~�b�e����������������Ƃ��ē����Ă���B
�@���������̌�A�Ћ��͂��̍j�̂̉�����߂����đΗ������B���̎�ȓ_�́A���L�������Ƃ͈̔͂ł���A���Y�}�͐��𑝂₷���Ƃ��咣���A�Љ�}�͂���ɔ����A���͌����B����ȍ~�Ћ��́A�ᔻ������s���B���Y�}�́A�~�b�e�����Љ�}���u�w�Q���j�[���������A�����ɏA�����߂̕⏕���͂Ƃ��ċ��Y�}�𗘗p���Ă���v�Ƃ��u�ێ��蔽���I�v�ȂǂƔ����J��Ԃ��Ă����B
�@�����W�P�N�̑哝�̑I�ł́A���Y�}�͌��I���[�ō������Ƃ��ă~�b�e�����ւ̓��[���Ăъ|�����B�����ċ��Y�}�͂���܂ł̎Љ�}�ւ̔ᔻ�ɂ��đ������邱�ƂȂ��Љ�}�����ɓ��t�����̂ł���B
�@�~�b�e�����͋��Y�}�̓��t�ɂ��āA�u���͐�����f�����B���̐��������鐨�́A����I�Ԃ��ׂĂ̐��͂����͌��W�����B�������̐��͂��Ȃ���̂Ă邱�Ƃ��ł��悤���B���Y�}�͂�����ƈقȂ鐭��������Ă��邪�A���Y�}�t���͋��Y�}�̐�������s������̂ł͂Ȃ��v�Əq�ׂ��B�~�b�e�������Η����Ă������Y�}�̓��t��F�߂��̂́A���Y�}�̎x���ҁA�Ƃ�킯�b�f�s���l���Ă̂��Ƃł������B���Y�}�ɑ�b�̈֎q��^���邱�Ƃɂ���āA���̔w��ɂ���J���҂���荞�����Ƃ����̂ł���B�����ċ��Y�}�͓��t���邱�Ƃɂ���āA�~�b�e�����Љ�}�̃u���W���A�����������Ă����B
�@���Y�}�͎Љ�}�Ƃ̘A���Ŏ��{�̑̐������v���A���̎x�z�����ɑO�i���Ă����邩�̌��z��U��܂����B�������u���W���A�I�}�h��u���W�A�}�h�Ƃ́u�A�������v�ɂ���ẮA���{�Ƃ̓������ѓO���Ă������Ƃ͂ł��Ȃ��B����́A�J���҂̊K���ӎ������������A��������̂�������̂ɂ����Ȃ�Ȃ��B���{�̑̐����������邱�Ƃ��ł���̂́A�J���ҊK���̊v���I�����ł���B
|
�P�R�@�ŏI��
�g����h���͂Ƃ̘A��������R����u���W���A�A����
���g����A���h�H���̗��j�I���� |
�@����i�l���j�A�������̗��j�́A���ꂪ�J���ҊK���̓Ǝ��̓�����������A�u���W���A���R��`���͂⏬�u���W���A���͂Ƃ̋����ɘc�ߓ�����s�k�ɓ������a����`�ł��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��Ă���B���Y�}�͍ŋ߂ł͔ނ炪�g�v�V�h���ǂ����́g�����h�Ƃ܂ł����Ă������ۏ��j���܂ŒI�グ���āA�u���W���A���}�Ƃ̘A�������i�u�b�萭���v�j���f����ɂ��������B����i�l���j�A�������́A�u���W���A���}�̌��R����A�������ɍs���������̂ł���B
���������u���W���A���͂Ƃ̓�����������
�@���{���Y�}������A�������\�z��ł��o�����̂́A�P�X�V�R�N�̑�\�����ł���B����A�������\�z�̍ő�̓����́A���̐����̐��i���Љ��`�ڂ߂������̂ł͂Ȃ��A�u���������h�q�Ɩ����`�I���v�v�̂��߂̐����ƋK�肵�Ă��邱�Ƃł���B
�@���Y�}�́A����A���������o�����Ƃ��Ă��A���������̖ڎw���Ă���u�������哝�������{��ڎw���ċ����ɂЂ��ς��Ă����v���Ƃ͂��Ȃ��A�v�V�������ɎQ�����鐭�}�A�������͂̊Ԃ̏����̐����I�W�]�〈���̕s��v�ȓ_�͕ۗ����A��v�_�ŋ������鐭�{�ł���Ɛ������Ă���B
�@���Y�}�̖���i�l���j�A����p�̊�b�ƂȂ��Ă���̂́A�����҂̌��W�Ƃ������Ƃł���B�厑�{�̎x�z�ɋꂵ�߂��Ă���̂͘J���҂���ł͂Ȃ��A�_���⒆�����ƂȂǂ̏��u���W���A�������ł���B���u���W���A�W�[�▯��I�E���R��`�I�u���W���A�W�[���܂߂������̑��������W����L�͂ȓ������������A�厑�{�̎x�z��ł��j���Ă������߂ɕK�v�ł���A���̂��߂ɂ͘J���҂̊K���I������i���āA�ނ���������ׂ��ł͂Ȃ��A�ނ�Ɏ�����閯���`�I�A���ǎ�`�I�ȁg���v�h�ɂƂǂ܂�ׂ��ł���Ƃ����̂ł���B
�@���݂̋��Y�}�̖���i�l���j�A������́A�P�X�R�O�N��̐l������ȗ��̐�p�ł���B�����̐l�������p�́A�t�@�V�Y���ɑR�������ł��j���Ă������Ƃ��\�ɂ���Ƒ�X�I�ɐ�`���ꂽ�B���̗��R�͒P���ł���B�J���ҊK�������ł͖��͂ł���A���u���W���A�W�[�⎩�R��`�I�u���W���A�W�[��J���҂Ƃ̓������Ɍ��W���邱�Ƃ��K�v�ł���Ƃ������Ƃł������B�C�^���A��h�C�c�̃t�@�V�Y���͓Ɛ莑�{�̎x�z�ɂ���Ėv�����A�j�ł������u���W���A��g�D���A�J���҂̓�������ł����邱�Ƃɐ��������B�������ď��u���W���A��J���҂̑��Ɋl�����邱�Ƃ��t�@�V�Y���ɏ������铹�ł���Ƃ��ꂽ�̂ł���B
�@�t�����X��X�y�C���Ől��������{���a�������B�����Đl��������{�̓t�@�V�Y�����疯���`�⍇�@�I���{��h�q���铬���Ƃ��Ĕ�������A����͂V�O�N��̃`���́u�l���A���v���{�Ɏp���ꂽ�B�l��������{�ł̓t�@�V�Y�����v���ɑ���h�q�I�Ȑ��i���������ꂽ�̂ɑ��āA�l���A�����{�́A����������ՂƂ��ĎЉ��`�ւ̓����J�������Ƃ��Ĉʒu�t����ꂽ�B�l���A�������ł́A�厑�{�ɂ���č��A���D����Ă��鏬�u���W���A��J���҂̑��Ɍ��W���đ����h���`�����A���a�I�A�K�@�I�ɎЉ��`�Ɍ����đO�i���邱�Ƃ�搂�ꂽ�B�����A�l��������{�ł���l���A�����{�ł���A���u���W���A�W�[�Ƃ̘A���̕K�v���������Ă���_�ł͓����ł���B
�@�厑�{�̐��͂͌���I�ɏ����ł���A���u���W���A�W�[�Ȃǂ����W���āu�����̑����h�v�����W����Δ����h�̍����ӂ��A�厑�{��ǂ��߂邱�Ƃ��o����Ƃ������Y�}�́u�����ҁv�v���̎咣�́A�J���҂̊v���I�����̈Ӌ`��ے肷����a����`�ł���B
�@���R��`�I�u���W���A�W�[�⏬�u���W���A�W�[�Ƃ̘A���Ƃ����l�������p�̖��͂��́A�X�y�C����t�����X�̌o�������炩�ɂ��Ă���B
�@�u���W���A�I�����ɑ����O�̔����̒��ŁA���R��`�I�u���W���A�⏬�u���W���A���͂͘J���҂ƂƂ��ɓ�������g�ݐ������l�������B�������A����i�l���j�A�������̏����͈ꎞ�I�Ȃ��̂ł����Ȃ������B�u���W���A���R��`�h�́A�t�@�V�Y����u���W���A�����h�ɑ��ēO�ꂵ�ē������Ƃ͂����Ë���������ɏI�n�����B�ނ炪�ł�����Ă����̂͘J���҂̊v���I�����ł������B
�@�Ⴆ�A�X�y�C���ł͎Ћ��̌㉟���Ő��������u���W���A���a�h�����́A�t�����R���I�N���Ă�����Ƃ̓������S�O�����B���v���ɑ��Ă��₢������g�D�����̂͘J���҂ł���A���{�łȂ������B�ނ炪�l������̐����ɎQ�������̂́A����ɂ���ĘJ���҂̊K���I�����̔��W�������Ƃǂ߁A�u���W���A�x�z�̐����~�����߂ł������B�u���W���A���a�h�͘J���҂̊v���I�����ɔ����A�}�������B
�@�����Ă�����������̂͋��Y�}�ł���B�ނ�͂܂��t�@�V�X�g�ɏ������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��A���̂��߂ɂ͓������𗐂��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ǝ咣�����B�J���҂͖����`�̖h�q�ɂƂǂ܂�ׂ��ŁA�u���W���A�Љ�������z����悤�ȓ����́A���a�h�������痣�������锽�v���I�s�����Ɣ��A�J���҂̊v���I������e�������̂ł���B
�@�t�����X�̐l������A�`���̐l���A�������l�ł���B�`���̏ꍇ�́A�Љ��`�������̓W�]�Ƃ��Ă������A���Y���T�{�^�[�W���������{�Ƃ̍H����n��̓y�n��J���҂�_�����苒���邱�Ƃ́A�������{�Ƃ�G�̑��ɒǂ���萭��������邱�Ƃ��Ɣ������B
�@����t�����X�̏ꍇ�́A���Y�}�̃g���[�Y�́A�}�i�h���u����\�ł���v�Ƃ������̂ɑ��āA�u����\�ł͂Ȃ��B���ׂĂ�l������̂��߂Ɂv�Ƌ��сA�J���҂̃X�g���C�L�����ɔ����A�����}�������B���ꂱ������i�l���j�A��������p�̓��a����`�I�{�����������t�ł���B
�������A�����{���܂̌���������
�@���Y�}�́A����i�l���j�A�������̍��܂̌������A�A�������̕s����A�Ƃ�킯�}�i�h�̂����ɂ��Ă���B�X�y�C���l��������{�ł́A�A�i�[�L�X�g��g���c�L�X�g�i�o�n�t�l�j���A�`���ł͋}�i�h�i�l�h�q�j���J���҂�_�������������čH���_�n���u���W���A�W�[��n�傩����D�������X�B
�@�����A����i�l���j�A�������̍��܂̌����́A�}�i�h�ɂ������킯�ł͂Ȃ��B
�@�`���l���A�������́A�����͘J���ґ�O�̌o�ϓI�n�ʂ̉��P�������炵���i���グ�A�J�����ԒZ�k�A�����Ȃǁj�B�������₪�ĘJ���ґ�O�̊��҂͌��łɕς����B���{���J���ґ�O�ɗ^�����o�ϓI�ȉ��P�́A���{�̐��Y�T�{�^�[�W����C���t���ɂ���Ă����܂��D�������Ă��܂�������ł���B�Ћ��ɂƂ��ĘJ���҂̉���͂͂邩���������̂��Ƃł����Ȃ������B���{�Ƃ̑Ό���������鐭�{�Ɏc���ꂽ��i�́A�P�C���Y��`�I�ȍ����c������ł������B���̌��ʂ͕����̓��M�ł���B�J���ґ�O�͈ȑO�̃u���W���A���������������C���t���ɋꂵ�߂�ꂽ�B
�@�o�ς����A���{�̐���̖��͂����\�I�����Ȃ��ŁA�����h��u���W���A���}�͏��u���W���A�W�[����������Ő��{�œ|�̍��������߂��B���u���W���A�́A���͂�{�ɍ����������o���Ȃ������B�ނ�̓C���t���ƌo�ύ����̌����́A�J���҂̐��{���l���A�����{�ɂ���A����������j�ł����悤�Ƃ��Ă���Ƃ��āA���{�ɓG����悤�ɂȂ��Ă������̂ł���B
�@���{�̐��s���l�܂����̂́A�v���I�������肦���A���L���Y��ۏ���Ȃǂƃu���W���A�W�[�Ƌ������Ă�������ł���B�J���҂̊v���I�����W�����邱�Ƃ������A���h�I�ȏ��u���W���A�W�[�𖡕��ɂ��A���邢�͒��������āA�������͂⎑�{�̍�����ł��j��A�J���҂̉���̓W�]���J���Ă������ł������B�����A���Y�}�͘J���҂̊v���I�����W������̂ł͂Ȃ��A�t�ɂ���ɔ������̂ł���B
�@���Y�}�͏��u���W���A�W�[���厑�{�ɂ���Ďx�z����A��悳��Ă��邱�Ƃ����o���āA�J���҂Ƃ̘A��������B�������A�ނ炪�厑�{�ƑΗ����Ă���Ƃ����͈̂�ʂɂ��������Ȃ��B�ނ�͑����ł͑厑�{�Ɩ����̎��Ō���Ă���̂ł����āA����Ɉˑ����Ă���̂ł���B�ނ�̓����̂ق���́A�����ΘJ���҂Ɍ�������B�ނ�̒n�ʂ��̂��̂������̓_�ŘJ���҂̗��v�ƑΗ��������Ă��邩��ł���B�ނ炪�J���҂̊v���I�����ɎQ�����Ă���̂́A���͂�v�����������Ȃ��Ȃ������Ƃ����o���A����̒n�ʂ��̂ċ��鎞�ł���B
�@���{�̎x�z�̊�b�Ɉ�w���ɐG�ꂸ�A���{�̐��͂Ƃ̋����ɏI�n�����l���A�������̉��ǎ�`�A���a����`�����A���̍��܂Ɣs�k�̌����ł���B�J���҂̎x�������������{�͘J���҂̊v���I�����ɂ���ď��z�����邩�A���邢�͓��������̂��邩�i�t�����X�l������j�A���v���ɂ���đœ|�����i�`���l���A�����{�j�����Ȃ������̂ł���B
����������A�������̐i���Ƃ��Ă̎b�萭�{������
�@���Y�}�͍����ł́u�b�萭���v�����o���Ă���B�ނ�ɂ����̐��{�́A�u�����̍��̗��v�ɂ��Ȃ��v��������s���邽�߂̐��{�ł���B�u���̗��v�v�Ƃ͉����B���Y�}����̓I�ȉۑ�Ƃ��Ă������̂́A����ŗ��̈��������ł���A�������s�̑Ŕj�Ȃǂł���B�ނ�͂��Ă͓��Ĉ��ۏ����u�����̍����v�Ƃ����Ă����B�����āA���Ĉ��۔p���������Ȃ��Љ�}�Ȃǂ́u���܂������v����a����`���Ɣ��Ă����B�Ƃ��낪���݂ł́A�u�����̍����v�i�Ƃ����Ă����Y�}�̃h�O�}�ł����Ȃ����j��I�グ���āA�u���̗��v�v���������邽�߂̐��{�������Ă���̂ł���B�����Ă��̂��߂ɂ́A��}�ł���Εێ琭�}�ł����Ă��ꏏ�ɐ��{��g�D����Ƃ����̂��B
�@�����u�����̍����v�̍����̂��߂ɓ���Ȃ��ŁA�����I�グ�ɂ��āu���̗��v�v���]�X���邱�Ƃ͋\�Ԃł͂Ȃ��̂��B���Y�}�͂���₱���̉��ǂ��u�����̐؎��ȗv���v�ƋU��A�u���W���A���ǐ����ɂǂ��Ղ�����Ă���̂ł���B
�@����́A����A�����{�������グ�Ă������a����`�����̓��I�i���̕K�R�I�A���ł���B���Y�}�͌���ł͈�̍���}����p�₵���Љ�i�Љ��`�j��ڎw���ƌ������A����������́u�����̑I���v�̖��Ƃ��ĒI�グ���A���{��`�́u����I���v�v�ɂ��Č���Ă����B
�@�u���W���A���}�Ƃ̘A�����������������炷���́A�C�^���A�́u���j�I�Ë��̐��{�v�̌o�������炩���Ă���B
�@�u���W���A���}�Ƃ́u���j�I�Ë��̐��{�v�́A�C�^���A���Y�}�̍\���I���v�H���̈�w�̐i���ł���A�Ћ��𒆐S�Ƃ����l���A�����{����u���W���A���}���܂߂��u�����A�����{�v�ւ̓]���ł������B���Y�}�́A�}�͂���Ȃ�ᔻ���́A����Ȃ锽�ΐ��͂ɂƂǂ܂��Ă͂Ȃ炸�A�ϋɓI�A���ݓI�����ɂ���č��������ɉ�����Ă����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Əq�ׁA�u���W���A���}�Ƃ̘A���𐳓��������B
�@�������A�J���҂̊v�����}�͂���Ȃ�ᔻ�Ɛ�`�̓}�ł͂Ȃ��B���̔C���͘J���҂̊v��������g�D���A���{�̎x�z��œ|���A�v���I���͂��������A�Љ��`�����݂��Ă������Ƃł���B�Ƃ��낪���Y�}�͊v�����}�̍��{�I�C����c�Ȃ��āA�o�ρA�Љ�ɉ�����ăC�^���A�Љ���~�ς��邽�߂ɐϋɓI�Ɋ������ׂ����Ǝ咣�����̂ł���B
�@�u���j�I�Ë��̐��{�v�́A�C���t�������A�o�ύČ��A�������s�A�E���e���Ƃ̓�����搂����B�����A�����͂܂��Ɏ��{��`�̖����̌���ł������B���{�̎x�z�����̂܂܂Ƀu���W���A���}�Ǝ����荇���āA��@�̍����ɂ��Ă�����ׂ肷�邱�Ƃ́A���{�ւ̋����ł���A�ǐ��ł����Ȃ������B���ہA���Y�}�́u���j�I�Ë��v�H���́A���ŁA�����艺���A�����k�����X�J���҂ɋ]�����������邱�ƂŁA���{�������蔲���邱�Ƃ��������̂ł���B
�@�J���҂̊K���I�A�v���I�����W�����A�����i�߂�Ȃ��ŁA���{��`�̌o�ϓI�A�Љ�I�Ȗ������������悤�Ƃ���̂ł͂Ȃ��A���{��`�̑̐��̘g���ł́u����I���v�v��搂����Y�}�̖���i�l���j�A�������́A�����炳�܂ȃu���W���A���}�Ƃ̋����ɍs���������B���݁A���{���Y�}�͎����}�Ƃ̘A���܂ł͍s���Ă��Ȃ��B�����A�����ނ炪�����}�Ƃ̘A���ɍs�������Ȃ��ƒN���ۏł��悤���B�ނ�̂����u�b�萭���v�́A�����ے肷����̂ł͂Ȃ�����ł���B
�c���u��Y
�u�C�߁v684���i1998.7.5�j�`731���i1999.6.27�j
|


![]()
![]() (���_�D����)
(���_�D����)