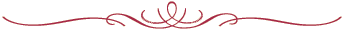
| 元号「令和」字義考 |
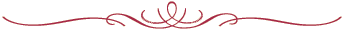
更新日/2019(平成31→5.1栄和元).6.4日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここで、「元号「令和」字義考」をものしておく。今はスケッチ段階であるが追々精緻にして行くことにする。
2019(平成31).4.5日 れんだいこ拝 |
![]()
| 【張 衡 87-139 /帰田賦】 | ||||||
| 新元号「令和」の出典は万葉集の「初春の令月、気淑しく風和らぐ」。この句は文選の句を踏まえていることが新日本古典文学大系「萬葉集(一)」の補注で指摘されている。 張衡(78〜139)は後漢の役人・学者。その張衡が残した「帰田賦」(きでんのふ)は6世紀の文選に収録されている。後漢・張衡「帰田賦・文選巻十五」に「於是仲春令月、時和気清」(「仲春令月、時和し気清らかなり」)とある。万葉集の成立は8世紀とされるが、当時は漢文・漢詩の教養が当たり前であり、「帰田賦」を参考にしたのは確定的。 | ||||||
| 遊都邑以永久 無明略以佐時 徒臨川以羡魚 俟河清乎未期 感蔡子之慷慨
感蔡子之慷慨 従唐生以決疑 諒天道之微昧 追漁父以同嬉 超埃塵以遐逝 ★於是仲春令月 時和気清★ 原隰鬱茂 百草滋栄 王睢鼓翼、鶬鶊哀鳴 交頸頡頏 関関嚶嚶 於焉逍遥 聊以娯情 于時曜霊俄景 係以望舒 極般遊之至楽 雖日夕而忘劬 感老氏之遺誡 |
||||||
| 田園に帰ろう 張 衡 87-139 (書下し文と和訳) | ||||||
| 都邑に遊びて永く久しきも 明略の以って時を佐くる無し。徒らに川に臨みて魚を羡い、河の清むを未だ期せられざるに俟つ。 都住まいも久しくなるが、世をよくする功績なく、網も持たず、川岸で魚を得たいと望むばかり。黄河の澄むよい時世を待つも、何時のことか 計られぬ。 蔡子の慷慨にして 唐生に従いて疑いを決せるに感ず。諒に天道の微昧なる、 漁父を追いて嬉みを同じうせん。埃塵を超えて遐に逝き 世事と長く辞さん。その昔、思いあぐねた蔡沢は、唐挙の占いに賭けて、迷いの霧をはらしたが、まこと人の運命は見通し難く 漁父をさがし求めて楽しみをともに分ちたいものだ。いざ、この世の塵芥から抜け出て遥かな彼方に去り、生臭い俗事との縁を永遠に絶とう。 是に於いて 仲春の令月 時は和し気は清む 原隰し鬱茂し 百草 滋栄す。 おりしも今は 春も半ばのめでたい月よ。時節はなごやか 大気は澄んで 岡も湿地も鬱そうと 百草は繁り花さく。 王睢翼を鼓し、鶬鶊哀しげに鳴く 頸を交えて頡り頏り 関関たり嚶嚶たり。焉に於いて 逍遥し 聊か以つて情を娯しましめん。 爾して乃ち龍のごとく方沢に吟じ 虎のごとく山丘に嘯く。 仰ぎては繊繳を飛ばし 俯しては長流に釣る。矢に触れて斃れ、餌を貪りて鉤を呑む 雲間の逸禽を落し、淵沈の魦鰡を懸く。 睢鳩(みさご)は羽ばたき、倉庚(うぐいす)は悲しげに鳴き、頸すりよせて、上に下にと飛びかけり。仲睦まじく伴を求めて呼び交わす。いざやこの地に遊び歩き、しばらく情を楽しませよう。そうして私は、大きな沢で龍の如く吟じ 山や丘で虎のように嘯き、仰いで細い繳(いぐるみ)を放ち、俯し見ては長い流れに釣り糸を垂らすのだ。鳥は矢にあたって斃れ、魚は餌を貪って鉤(はり)を呑む。かくて雲間を飛ぶがんも射落され、深い淵にひそむ魦鰡も釣りあげられる。 時に曜霊は景を俄け 係ぐに望舒を以ってす。般遊の至楽を極め、日の夕なるも劬るるを忘れる。老氏の遺誡に感じ 将に駕を蓬蘆に廻らさんとす。五絃の妙指を弾じ、周孔の図書を詠ず。翰墨を揮いて藻を奮い 三皇の軌模を陳ぶ。苟くも心を物外に縦にせば 安んぞ栄と辱の如く所を知らんや。 いつしかに 日は西に傾き、月さし昇る。心ゆくまで遊び楽しみ、暮れがたになるも疲れを覚えぬ。しかし、狩を戒めた老子の遺訓に気づき、車駕を草蘆(いおり)に帰すことにする。すぐれた五絃(こと)の調べを奏で、周公・孔子の書を口吟み、筆走らせては詩文を綴り、時には三皇の功業を書きしるす。執らわれぬ境に 心を解き放つならば 此の世の栄誉(ほまれ)も恥辱(はじ)も 問うところではない。 | ||||||
| 「帰田賦」を口語訳すれば「田舎に帰ろう」といったところだが、「遊都邑以永久、無明略以佐時」(都暮らしも長くなるが、世を良くする功績もない)で始まる内容は、安倍首相がアピールする「ひとりひとりが輝く新しい時代」とは程遠く、政治の腐敗を嘆き、中央政府に愛想を尽かして故郷に帰る喜びをつづる厭世的な独白である。 張衡は、「後漢書」によれば、年少時から文才にたけた秀才で、天文学、数学、地理学などに通じていた。地方の役人だったが、6代皇帝の"安帝"に都に呼ばれ、中央政府の官僚になる。その治世は宮廷官僚の宦官が幅を利かせ、忖度や賄賂の横行を招いた。嫁の閻后も、側室の子を殺したり、縁故政治を増長させるなど、やりたい放題だった人物として評判が悪い。中央政府の腐敗に我慢できなかった張衡は順帝(8代皇帝)の時代に朝廷を辞し、「帰田賦」を書いた。135年に書いた「思玄賦」には、朝廷の腐敗やそれに媚びる役人を厳しく糾弾する記述がある。こちらも『文選』におさめられている。
張衡はこの腐敗と忖度にまみれた朝廷で官吏として働くことの苦悩をこう書いている。
張衡は実権力者であった宦官勢力に睨らまれ、136年に首都・洛陽から河間(現在の河北省あたり)へ移り行政官を務めた。『後漢書』によれば、2年後に辞職願いを上書するも徴され、再び都の官職に就いたのち引退する。139年、62歳で没。その頃に書かれた隠居の書が「帰田賦」だ。張衡はこのなかでその心情をこう語っている。
|
||||||
| ■主な参考文献 『新釈漢文大系』81巻(明治書院) 『後漢書』列伝7(岩波書店) 鈴木宗義「張衡「帰田賦」小考」(「国学院中国学会報」2005年12月号所収) 富永一登「張衡の「思玄賦」について」(「大阪教育大学紀要」1986年8月号所収) |
| 「嘉徳、文長…新元号は未採用案から? 「元号」「日本年号史大事典」から(8)」、「久礼旦雄・京都産業大准教授と京都府教育庁の吉野健一・文化財保護課副主査」その他参照。 「令」の文字は、これまで日本の元号に使用された72字の中にない。昭和の「昭」、平成の「成」に続いて、元号の文字にニューフェースが加わった。中国の漢から清までの元号354に使われた148字の中にも入っていない。昭和の「昭」、平成の「成」に続いて元号の文字にニューフェースが加わったことになる。「令」は過去の改元論議で提案された元号未採用案の中ですらも、ほとんど見られない。1回の改元時に、学識者らから提案される元号案は10を超えることも少なくない。その中から1つが選ばれ、あとは有力な元号候補として温存される。江戸時代以降では、こうした未採用案の中から正式な元号に登用されるケースが約8割を占める。これまでに約500の元号候補が確認されている。令を使ったケースは、幕末に論議された令徳だけ。 「令和」で初めて元号に使われた「令」の字は、これまでに案の段階で2度挙がったことがある。漢文学者の高辻修長から提出された。同じ人物が同じ元号を続けて提案したが採用には至らなかった。高辻家は、平安時代の右大臣菅原道真の流れをくむ名家の一つで、修長は元治の直後の元号「慶応」(1865~68年)改元時には、平成を提案している。しかし、延べ24案を提出したものの、存命中に自らの案が採用されることはなかった。「令徳」初登場は14代将軍・徳川家茂の文久(1861-64年)で、京都の朝廷は「文久、令徳、明治、建正、萬保、永明、大政」の候補を江戸幕府に送り、幕府からの返答で文久が内定した。2度目は尊皇攘夷の動きが全国に広がっていた元治改元(1864-65年)。朝廷は令徳、元治を候補として示した上で、特に令徳が孝明天皇のお気持ちに沿うと伝えた。しかし幕府は「令徳は徳川に命令すると読める」として嫌い、様ざまなルートで朝廷への政治工作をはかり元治に落ち着いた。 「和」はこれまでに19回使われ(上で使うのは和銅のみ)これで20回目。1文字目に使われたのは「和銅」(708~15年)だけで、今回や「昭和」を含め残り19回は2文字目。元号では「永」(29回)、「元」(27回)、「天」(27回)、「治」(21回)に続いて「応」(20回)と並び5番目に登場回数が多い字となった。中国でも「元」(46回)、「永」(34回)、「建」(26回)のベスト3に続いて「和」(21回)が多い。しかし昭和で長期間使われていたので、平成の後にすぐ再登用され難いのに採用された。近世で元号の字が重なるケースは、元治(1864年)と明治(68年)がある。ただ元治は1年1カ月で慶応へ再改元したから、印象は薄い。それ以前は、寛保(1741)から延享を挟んで寛延(48年)、文化(1804年)から続けて文政(1818年)としたケースが目に付くくらいだ。享和、明和、天和、元和……「和」を後ろに持ってくると、落ち着きのある元号になる。第3のサプライズは、「万葉集から採用されたこと」(久禮氏)。日本の古典からの採用される場合は、日本書紀などが有力で、万葉集のような歌集からの引用は難しいとされていた。政府案は国書・漢籍からそれぞれ3候補づつ挙げていた。日本の古典からの採用というアイデアは以前から一部で考えられており、1960年代初めの国学者の坂本太郎・東大教授を中心とした日本書紀研究会では、聖徳太子の十七条憲法や嵯峨天皇の漢詩などが具体的に挙げられたという。万葉集や古事記を推すメンバーもいたという。 新元号の出典となった「初春(しょしゅん)の令月(れいげつ)にして、気淑(きよ)く風和(やわら)ぎ、梅は鏡前(きょうぜん)の粉を披(ひら)き、蘭は珮後(はいご)の香(こう)を薫(かお)らす」は漢文による歌の序文。久禮氏は「書聖・王羲之の代表作『蘭亭序』を基にしており、漢籍を日本の古典に取り入れた」と指摘する。これまで漢籍から採用してた元号の伝統も、新元号の中に引き継ぐ形となった。 |
|
「元号」(文春新書)、「日本年号史大事典」(雄山閣)などの著者である所功・モラロジー研究所教授説参照。「明治は天皇のくじ引きで決まった。それまでに10回落選していて、やっと日の目を見た。明治が最初の候補になったのは室町時代の正長改元の時(1428年)で、正式採用まで480年かかったことになる。江戸時代末期に何度もノミネートされていた。有力案の場合、何度も提案される。平成も、幕末の慶応(1865年)の際に検討されていた。2度目で早くも昇格した。源頼朝が鎌倉幕府を開いた建久3年(1192年)から今日まで約930年間に元号は140あり、初出の候補がそのまま起用されたケースは38回。江戸時代からの約400年間では元号39に対し8回で、最も新しい初出採用の元号は昭和(1926年)。ひとつ前は元治(1864年)まで遡る。逆に言えば、近世から現代までで未採用候補からの登用は約8割。中国の古典を基にして考案する。これまでの年号は約80種類の漢籍から出典されている。一番多かったのは書経からの35回(未採用案は85回)という。248番目の今回は日本の古典からの候補もありそうだが、
聖徳太子の十七条憲法などをみても、元号にふさわしい語句の出典は漢籍に由来するケースが多い。これまでの大化から平成の247元号は、典拠がわかっているものはすべて五経や史記など中国の古書(漢書)からとられてきたとされる。各元号は、平成は『地平天成』、昭和は『百姓昭明・協和萬邦』。大正は『大亨以正』。明治は『嚮明而治』。日中で共通して使われたことのある元号は少なくとも貞観、建武、弘治の3つがある。中国稀代の名君と謳われる唐の太宗の時代に使われた貞観が日本でも859~877年に使用されている。 近世の元号で、最も多く候補に挙げられたのは天保(1831年)の15回。最初は平安中期の正暦(990年)。用いられるまで約840年待ったことになる。朝廷は7つの元号案を徳川幕府に送り、特に天保を推していることを伝えたところ、幕府も同意したという。幕末に近づくと朝廷が主導権を握って元号を決めたケースが多い。未採用の元号案で最も落選回数が多いとみられるのが嘉徳。春秋左氏伝にある『上下皆有嘉徳、而無違心』のほか、史記などにも『群臣嘉徳』といった表現がある。28回以上の改元時に論議されながらいま一歩及ばなかった。学識者が別々に答申したり、異なる漢籍からの引用で提案されたケースも重複して数えると40回提案されたことになる。嘉徳は延久(1069年)から文久(1861年)まで登場した。惜しかったのは弘化(1845年)の改元時。朝廷は弘化、嘉徳、万安、万延、文久、嘉永、嘉延を幕府に提示し、弘化か嘉徳を選ぶように伝えた。嘉の字を使った3案のうち嘉徳がトップ候補だった。しかし結局、弘化が採用された。嘉徳ファンとしては字画数の多い点が気になる。 「主な元号未採用候補」(日本年号史大事典などから)は次の通り。
落選24回の文長も惜しい元号案のひとつ。史記に『文武両用、長久之術也』といった記述がみえる。南北朝時代から幕末の万延(1860年)まで候補に挙がった。文も長も、たびたび元号に使われている縁起の良い字である。文政(1818年)改元では最終2候補のうちの1つにまで残った。さらに黒船来航などを理由にした安政改元(1855)では、朝廷は文長、安政、和平、寛裕、寛禄、保和を幕府に送り、文長を第1候補とした。しかし幕府が推薦したのは安政だった。ほかにも寛安、建正、大応、貞正などが数多く候補に上っている。未採用案のいずれもが、良い時代を表象しようという希望が込められている。今後の元号に採用されても不思議ではない。(松本治人) |
| 【元号「昭和」命名時の新元号スクープ誤報事件考】 |
| 河西秀哉/名古屋大学大学院准教授「皇室タイムトラベル11、光文事件」(2019.2.10日づけ山陽新聞)参照。 明治以来、日本は「1世1元の制」(一人の天皇に対し一つの元号だけにする)を敷いている。それまでは、天皇の即位、天変地変などがあると改元されるのが通例だった。この改元を巡る事件を確認しておく。 1926.12.25日午前1時過ぎ、大正天皇が逝去した。これを受け、東京日日新聞(後の毎日新聞の前身)は号外や朝刊最終版で、新元号が「光文」とスクープ報道した。ところが、その日の午前11頃、宮内庁が発表した新元号は「昭和」だった。社長は辞意表明したが、最終的に編集局主幹が辞任することで決着した。 新元号の選定は、現在は宮内庁が関係せず政権中枢が極秘裏に進めているが、当時は宮内庁が中心となって行われていた。この時も、宮内大臣の一木喜徳郎(いつききとくろう)の命令を受け、図書寮編修官の吉田増蔵が案を作成していた。図書寮は、皇室に関係する史料の管理保存、歴史の編纂などを行う部局である。この部局が元号の策定に大きく関わっていた。吉田案の中に「光文」はなかった。 この宮内庁の動きとは別に、内閣の策定もあった。首相の若槻礼次郎の命令を受けた内閣官房嘱託の国府犀東(こくふさいとう)が新元号案を作成していった。こま国府案の一つに「光文」があった。 大正天皇死去直後、東京日日新聞の社会部長から「政治部の特ダネで元号が『光文』に決まったそうだ。宮内省で確認してくれ」と云われ、皇室担当記者だった藤樫準二(とがしじゅんじ)が宮内庁で打診したところ「報告がない」と云われ、社へ報告した。ところが既に印刷に回っており報道済みだった。 新元号「昭和」は25日午前6時45分から9時25分まで枢密院審査委員会・本会議が開催され諮問された。枢密院議長であった倉富勇三郎の日記によれば、既に大正天皇死去前の12.8日には「昭和」を最終候補にすることが決まっていた。 |
| 【「令」の字義、語源】 |
| 会意文字。(亼+卩)。亼(シュウ,會ー集まる)と卩(セツ、割り符)の合字。上に立つ人の下命・戒告の意。「頭上に頂く冠の象形」と「ひざまずく人」の象形から、人がひざまずいて神意を聞く事を意味し、そこから転じて、「お告げ」、「命ずる・いいつける」を意味する「令」という漢字が成り立った。立命館大の白川静名誉教授の名著「字通」によると、「令」とは、「礼冠をつけて、跪いて神意を聞く人の形。神官が目深に礼帽を著けて跪く形。神意を承ける象」(日本においては、八百万の神々に日々、世界の恒久平和と繁栄を祈っておられる神官の最高位・天皇陛下を意味している)という。なお、鈴も初めは「令」に従って鈴に作り、神を降ろし、神を送るときに用いる。 「令」の読みが「りょう」と「れい」の二通りある。 |
| 名前(音読み・訓読み以外の読み):「なり」、「のり」、「はる」、「よし」 |
| 画数/「5画」 |
| 明朝体の「令」の下の部分「刀」を、小学校では教科書体と称して「マ」として書くように教え、筆記体として許されるとしている。一方、文化庁では常用漢字表として「刀」を採用し、「鈴木」性などの「令」の表記方法については、既に戸籍照合をする実務においてトラブルを招いている。 |
| 「令」はアとへを組み合わせたもので「ア」、「ヘ」が紛れ込んでいると指摘されている。 |
2019.4.17日、西日本新聞配信「新元号「令」の字のナゾ “点スタイル”と“線スタイル”両方ある理由」。
|
| 【「和」の字義、語源】 |
| 『和』◆成り立ち
形声文字です。「口」の象形と「穂先が茎の先端に垂れかかる」象形(「稲」の意味だが、ここでは、「會(か)に通じ、「会う」の意味)から、人の声と声が調和する「なごむ」を意味する「和」という漢字が成り立ちました。和らぐとか争わずの意。和ぎ=凪、風がやむ。 |
| 【「令和」の出典】 | ||||||||||||||||
| 奈良時代の公卿にして一流の歌人にして漢籍に明るい大伴旅人は、隼人の乱の鎮圧に成功して朝廷の評価を受けていたが、太宰府長官として左遷された。その父親である大伴安麻呂は、壬申の乱では大海人皇子(天武天皇)の側に立って天武のクーデター成功に寄与した人物である。 新元号「令和」の出典となった葉集第五巻梅花歌卅二首は、730(天平2)年正月の春、その大宰府の邸宅で催した庭に咲く梅を詠み比べる歌宴を催した時のもの。招かれたのは対馬や鹿児島など九州一円の役人や医師、陰陽師(おんみょうじ)ら31人。「梅」をテーマに1人1首歌を詠んでいる。その「梅花(ばいか)の宴(えん)」で詠まれた32首の序文に記されている「初春の令月(れいげつ)にして、気淑(きよ)く風和(やわら)ぎ」から「「梅花(ばいか)の宴(えん)」から採られている。「令月」とは、1 何事をするにもよい月。めでたい月。「嘉辰(かしん)令月」、2 陰暦2月の異称。新暦では2月下旬から4月上旬ごろに当たる。 2月の別名は如月(きさらぎ)である。辞には続きがある。「天空を覆いとし、大地を敷物として、くつろぎ、ひざ寄せ合って酒杯を飛ばす。さあ園梅を歌に詠もうではないか」。旅人が、酒席で述べた挨拶(あいさつ)。 大伴旅人の有名句は「なかなかに人とあらずは酒壺(つぼ)に成りにてしかも酒に染みなむ」(いっそ人間をやめ、ずっと酒に浸れる酒壺になりたい)。60余年の大伴旅人の生涯に、元号は驚くほど頻繁に代わっている。吉兆の亀が発見されたと言って「神亀」。奇跡の水が見つかったと「養老」。ほかに「朱鳥」「大宝」「慶雲」「和銅」「霊亀」「天平」。 歌は万葉仮名で序文は漢文。作者は旅人や山上憶良などと推測されている。宴の開かれた前年、時の左大臣が自死に追い込まれる「長屋王の変」が発生している。その緊張した雰囲気の中で催されたのが梅花の宴だった。 「武都紀多知 波流能吉多良婆 可久斯許曽 烏梅乎乎都々 多努之岐乎倍米[大貳紀卿」
初出は、“中国屈指の政治家・天文学者・数学者・地理学者・発明家・製図家・文学者・詩人である後漢時代の張衡(78-139)の「帰田賦」にも 「於是仲春令月時和氣清 原隰鬱茂 百草滋榮」とある。万葉集の編纂者は、張衡の漢詩「帰田賦」も読んでいた。これを踏まえて(新日本古典文学大系『萬葉集(一)』岩波書店の補注で指摘)『万葉集』巻5(集歌815から集歌852まで)の詞書(ことばがき)として 于時初春令月 氣淑風和梅披鏡前之粉 蘭薫珮後之香 加以 曙嶺移雲 松掛羅而傾盖 夕岫結霧鳥封縠而迷林 庭舞新蝶 空歸故鴈 於是盖天坐地が記述された。こうなると純然たる正式な漢文ということになる。国文学が専門の山崎健司・明治大学教授も〈「令和」に使われた万葉集の第5巻の序文は中国の六朝時代の政治家で、書家として名高い王羲之の書「蘭亭序」や同時代の詩文集の「文選」を参考にしたのではないか〉(NHKニュースより)と指摘している。 当時、日本には平仮名がなく漢字文化圏漢詩が貴族の嗜み。元号、令和の由来は、中国にあった。「令和」は『万葉集』からとってきたといっても、万葉仮名である歌の部分ではなく漢文調の序文が出典。「梅は鏡前の粉を披き」の部分の梅の木も、中国から日本列島に輸入された樹木といわれている。 |
| 【「令和」の評価】 |
| 「令和」は日本最古の和歌集「万葉集」巻五の『梅花の宴』の序文は漢文で、しかも変体漢文ではなく中国語そのものの純漢文。「初春の令月にして、気淑(よ)く風和らぎ、梅は鏡前の粉を披(ひら)き、蘭は珮後(はいご)の香を薫らす」との一文から取られたもので、初めて日本の古典から選ばれたという。しかし、万葉集の『令月』は中国古典からの引用。儀礼の『士冠礼』などに見える。万葉集の当該部分は後漢の張衡『帰田賦』の『於是仲春令月、時和氣清』を踏まえたものであり中国古典からの孫引きが明らかである。 「令の字は中国語で美や謙遜といった意味を持ち、和の字は柔らかいという意味を持つことがあるため、一見して柔和な感じのする元号だと思いました」。 元号としては失格だ。理由は2つ。『令』が人に与える“直観的”なイメージの悪さ。そもそも、「令」という表意文字には、言いつける、命ずる、掟、規則といった「権力の冷たいイメージ」しかない。「令嬢」も「令夫人」も所詮は、格式・形式的尊称・建前美称であり、もはや“死語”である。“死語”を元号にして良いのか? |
|
2019.4.18日、令和の考案者であると有力視されている国文学者・中西進さんが朝日新聞編集委員・塩倉裕の取材に応じ次のように語った。(「議論しても、たぶん令和が一番いい 中西氏が語る元号」参照)
|
| 【「令和」解釈考】 | |
| 新元号【令和】 は「倭に命令す!」。日本民族に従属強制。令なんて政治的或いわ支配的な字を入れて来る。不吉でしかない。 これは、征倭会による隷倭宣言とみた。清和会は実は“征倭会”(日本人を征服する勢力という意味)と言われている。清和会議員を主体とする議員の大半は帰化人(半島系)ではないかと言われている。“令”と言う漢字から連想するのは、召集令状(赤紙)の“令”であり、この清和という漢字自体にも、和(日本)を制するという意味が含まれている。今回の新元号「令和」も、和人(日本人)を律するという意味が含まれる。徳仁天皇には「ご愁傷様」と言う他にない。 初めて、中国から脱して日本の古典を典拠にしました、と宣伝しまわって、結局は、その古典も、それ以前の中国古典を典拠にしてましたって、どう見てもお笑いだろう。 「『しょせん、日本人にとって漢字はわが国からの借り物。漢字のなんたるかをわかっていない。その証拠がこの元号だ』。まず、『令』という字は、中国人からすると『零』と音が同じで、どちらも中国語では『リン』と発音するため、『令和』すなわち『零和』(平和ゼロ、平和な日はない)という極めて縁起のよくない元号ととらえられます。これは「諧音(シエイン)」という同音異義語のことで、避けるべき用法です。中国人であれば常識中の常識、安倍はそんなことも頭が回らないのか、というわけです」(中国在住ジャーナリスト)。『日本人は教養がない』『センスがない』という意見も相次いでいる。 4.3日、本郷和人氏「「令和以外の5つはケチのつけようがない」東大教授が指摘する『令』が抱える3つの問題」。
|
| 【「令和」の和訳考】 |
| 外務省は、平成に代わる新元号「令和」について外国政府に英語で説明する際、「Beautiful Harmony」(美しい調和)という趣旨だと伝えるよう在外公館に指示した。新元号発表後、「令」を「order」(命令、秩序など)と訳す外国メディアがあったのを受けた措置で、外国メディアにも個別に説明している。「令和」の発表後、国際的に影響力が大きい英BBC放送が「order and harmony」と表すと報道。「令」については「Command」(指令)を意味すると報じる欧米メディアもあった。外務省の担当者は「令和の意味を正確に訳すのは難しいが、全く異なる解釈をされるのを避けるため、趣旨を伝えることにした」と述べた。外務省内では「令」が律令など法律の意味で使われることがあることから、「『令和』は『法の支配に基づく平和』とも解釈でき、日本の外交姿勢になじむ」といった声も出ている>(以上「毎日新聞」より引用)。 |
| 【「令和」商標登録考】 |
|
AbemaTimesの報道によれば、中国で「令和」が既に商標登録されている。2017年11月16日に出願され、本出願は2018年10月21日に登録され、既に商標権が発生している。権利者は河北省の個人の方。指定商品は(日本酒を含む)酒類。新元号選択時に商標登録されていないものという条件があるが、外国の登録までは調べていなかったことになる。商標権の効力は基本的にその国の中だけなので、この商標登録が日本国内でのビジネスに影響を及ぼすことは基本的にありえない。
|
| 「★阿修羅♪ > カルト20 」の氏の日付け投稿「はちま・令和にアベの文字、ゲン・元ネタは腐敗政治を嘆く内容の漢籍。と医学書と清史と酒名で圧巻は和坤に自尽を迫る内容である」。 |
| 正月十四,嘉慶(帝)說:「朕若不除和珅,天下人只知有和珅而不知有朕」。下令判和珅死刑。 https://zh.wikipedia.org/zh/ 「和珅下獄時作了絕命詩一首」。 |
2019年05月04日、「自民党的政治のパンツを剥ぐ」の「令和の令 という字は えらぶべき字ではない」、「」。
|
「「令和」の時代を考える」の日付け「「令和」が専門家を驚かせた3つの理由 「元号」「日本年号史大事典」から(9)」。
|
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)