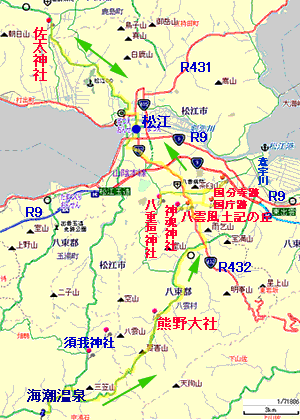大庭(おおば)大宮とも云ひ、出雲国造の太祖・天穂日命(アメノホヒミコト)が、この地に天降し創建したという。国造就任の神事・神火相続式(おひつぎしき)を代々行ってきている。出雲国造家は意宇の首長としての勢力を有していた。斉名天皇の勅令で出雲大社が創建され、国造家は杵築に移住したが、神火相続式では現在も神魂神社と熊野大社とに参向している。大和朝廷に出雲が恭順する事情・時代を彷彿させる。
祭神としては、イザナミ大神とイザナギ大神が合祀されている。出雲国風土記には神魂神社の社名は見当たらないが、神魂(かもす)はカミムスビである。カミムスビの神はもともと出雲の古い霊格であり、出雲国風土記にもしばしば出て来る。カミムスビの神は造化三神のひとつ(他の二神は、アメノミナカヌシとタカミムスビ)として、後世に宮廷神話や祭祀に取り入れられた。
この近辺は、奈良時代に国庁、国分寺が置かれ、鎌倉時代まで政治・経済・交通の中心であった。現在もすぐ近くに文化庁の協力の下に「八雲立つ風土記の丘・郷土博物館」が建てられ、出雲文化発祥の転移を紹介している。
拝殿につづいて御本殿がある。室町時代に建造されたものである。現存する大社造りとして最古のものである。境内は余計なものは何もなく、簡素である。全国の八百万の神々が集う10月には「神在祭」が行われている。御本殿は国宝であり、天地根源造りの形態をもつ大社造りで屋根は栃葺きである。女神イザナミノミコトあるいは女神カミムスビを祀ることからか先端を水平に切る女千木(めちぎ)で、本殿内部は二間の右側から入り、心柱を左に見て左奥の神座に至る女造(めつくり)とする。