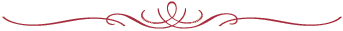| 「近代とはデイアレクテイクだといふことは出來ます。近代史の進展、近代人の生成、近代人の支配形式、權力樣式、陰謀霸道、それらはすべてデイアレクテイクです。デイアレクテイクによつて説明されます。人智の不安定、人力の空しさの證です。(中略) 近代は弁証法的であり、それは永遠と絶対のうちに存在しない。具体的にいえば権力と財貨を所有せんとする『物質に基づく世界』の原理が近代である。たとえば、共同体と共同体のあいだ(マルクス)、単線的な時間における技術革新(シュムペーター)によってそれがつねに発展してきたことを想起すればよい」。 |
| 「一言につゞめて申しますと、その生活からは戦争の実体も心もちも生れない、平和しかないといふ生活、さういうふ生活の計画を先とする平和論といふ意味です。その生活からは戦争する余力も、必要も、さういふ考へも起つてこないやうな、さういふ生活をまづ作らうといふ考へ方です。これをもう少し説明するために、我々は二つの命題を立てることが出来ます。一つは近代とその生活の不正を知り近代生活を羨望せぬこと。次に(第一の命題の確立のために)近代文明以上に高次な精神と道徳の文明の理想を自覚すること。この第二の命題を別の言葉で申しますと、アジアの自覚とアジアの理想の恢復といふことです。このアジアの理想は、アジアの本有生活の道の指すものであります」。 |
| 「無関心といふのは、近代を生きてゆくといふ上で無関心といふ意味でありません。つまり自衛手段は講ずるといふ関係で、本質の精神や理念上では無関係だといふことです」。 |
「改正憲法の眼目の一つは第九条の戦争の抛棄で、一切の武力を保持せず、自衛のための戦争をも抛棄するといふものである。これについては、自衛権や自衛戦争は否定してゐないといふ解釈があったけれども、草案審議のときに、共産党の野坂参三議員が、「自衛戦争は正義の戦だ。この案において自衛戦争まで抛棄してゐるのは行きすぎではないか」と質問したとき、吉田首相は「国家の正当防衛権による戦争は正当なりとせられるやうであるが、私はかくのごとき之とを認むることは有害であると思ふ」といふ趣旨の答弁をした。
外交官出身の吉田茂に、戦争抛棄についての何らかの信念があったわけではなく、自衛戦争であらうがなからうが、他国の疑惑をすこしでも招く条文はよくないといふ外交官的配慮が優先したのであらう。ともかく、占領の早期終結と講和の実現が吉田茂の頭を占めてゐた使命観であつた。
第九条は、その考へ方の根本において、前文の「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」といふ部分に立脚する。これも奇妙な日本語である。平和であれ何であれ、およそ「崇高な理想を深く自覚する」者が、自分の「安全と生存」を他人にゆだねようと「決意」するなどといふことは、正常な人間精神の本来からすればありえないことである。理想の「自覚」といふものはさういふ他力本願を拒否するものである。さういふおめでたい他力本願を抱くことは、ことさら「決意」といふ悲痛な心のはたらきを必要としないのである。
戦争か平和かといふ二者択一の論議は、すぺて情勢論であって、これがやがて東西二大陣営の対立の激化といふ情勢にうながされて、アメリカにつくかソ聯につくかといふ国際政治論議に横すべりした。平和といふものが、戦争の休止状態であるといふ認識の地平では、それは理想たりえないものである。あるいは、平和が人間生活の相対的な幸福をもたらすといふ観念は、理想の名にあたひしないものである」。 |
「それも「近代」といふものに対して何らの懐疑も表明しなかった十九世紀的観念です。そして近代の繁栄と幸福の維持拡大といふ考へ方を根本にしてゐると考へられます。この点でその平和論は非常に不安定です。おそらくその点からくづれる可能性があります。それは分離した政治的結論の羅列に終わってゐるのです。原則の思想と分離した、政治的もしくは政策論的結論を羅列してゐるからです。
そこで一番問題になる第九条ですが、それには「日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇又は武力の行使は国際紛争を解決すり手段としては、永久にこれを放棄する。前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」とあります。この項目は「正義と秩序を基調とする」とある前提が、実に暖昧な表現であります。不安定であります。
これは憲法前文中の「日本国民は恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」とあるのと同じ考へですが、いづれも不明確な表現で「公正」と「信義」に対し、当然アジアの発言を予想すべきです。さらに念願するとか信頼するといふことは具体的な手段でなく、又具体的な生き方の指示とはなりません。要するに世界に文明の理念はただ一つしかないといふ軽率な考へ方に立脚し「近代」の考へ方を唯一のものとして考へた思想の表現です。これは実に困ったことですが、結局は事大主義の現れなのであります。これは実に困ったことですが、結局は事大主義の現れなのであります」。 |
| 「日本の生民に絶対的な世界に於て、天皇はいつも、「知ろしめす」と云ふのです。旧い時代、将軍は「領(うしは)き」天皇は「知ろしめす」と、その二つの世界を別ったのです。それは本居ら国学者の思想上でした仕事です。「領く」形式を一排し「知ろしめす」形一つに変革せねばならぬと唱へて、明治御一新に、不抜の方法論を与へたのです。それが復古の意義です、つまり国家体制を基本の一つにかへす
( 滅んだ昔にかへすのでない意味はわかるでせう ) 、決して主権と支配権の奪取を意味したのでないのです。しかし以前は愛国者と云った連中が、このけぢめを理解せず、本居らは幕府に妥協してゐたと云ひました。彼らは御一新時に、天皇を将軍の位置におきかへる工作をした野望家たちのエピゴーネンだったのです。維新後は、本末軽重を間違った人々によって「知ろしめす」天皇を「領く」将軍の地位へ下さうとしたのです」。 |
| 「十九世紀ヨオロッパの人文思想の最高良質のものが古代ギリシャへの郷愁に根をもつことを思へば、極東の敗戦国の窮乏の中で一文人が古代日本の伝説と神話を機縁に抱いた絶対平和の生活実体といふ思ひを、はかないユートピアとして無視することはできないであらう。ひるがへって思ふに、その念願に別の方法をあたへるとき、それは日本の『国民的抵抗線』になるであらう。別の方法とは、絶対平和の理想である。生活の瞬間が永遠であり、最悪事態の予想の上に安心を得てゐる精神である。現にもし我々が、侵略国の軍隊を迎へたやうな場合、反抗しない、共(ママ)力しない、誘惑されないといふ形を守るには、戦車のまへに横臥して、なすにまかせるといふ、大勇猛心を振ふ位の夢のやうな決心が必要なのです。これは日本国憲法を作ったすべての人々が、もし彼らが正気だったなら、それをよみ上げた日にした決心だと思ふのです。さういふ理想に殉ずる聖者らは、武器をとる勇士に比べて、比較にならね大きい勇気のある人々です。しかし彼らは夢のやうな人々と云はれるかもしれません。だからさういふ聖者らは、かういふ無惨さをみかねて、武器をとって代りに侵略者をこらしめ、代りに防いでやらうといふ人々を、心からの感謝をもちつゝも、拒絶するだらうと思ふのです」。 |
| 「日本はもともと平和な『くに』であった。東洋における『くに』とは、ある一定地域と人口が、平和の基礎となる生活に入った時に、これを『くに』が生れたという。(中略)三千年の歴史に於て、『文化』の実体は、つねに『くに』の『盛典』が表現した。(中略)文化が人にあらわれる前に、国として現れることを彼らは誤解した。米作は水に従い、天候に従い、そうして個人のつつましい力の限度に従ってきた。そこに神に委任を受けて耕作するという「事依さし」の思想が生れる。神と人々がつねに共同に働いている。大祓詞の罪状の中にも天つ罪として規定されたものは所有権上の罪でなく生産妨害の罪。わが古制においては、この所有権という考え方がなかった。『事よさし』に則ることを主張した。(中略)日本の本質社会は、一から始まって末広がりに国になったのです。維新後は、本末軽重を間違った人々によって、『知ろしめす』天皇を、『領く』将軍の地位へ下そうとした」。 |
| 「我々は偽瞞や脅迫や煽動といった、すべての近代の政治的運動に付随した必要のものを、我々の原理から否定した。(中略)それが日本の本質。(中略)つねに良心を緊縛しています。覚醒せしめます。一度道徳を知った人は、つねに良心を意識して、日常性の中に生きることでしょう。それで十分なのです。(中略)どんな不幸と危険がきても、決して滅びないのです。(中略)近代国際社会の「完全主権」というものの表象する国という観念の寿命は、もう一般的にその先が見えています。この運命を防ぐ方法も防げる人もいないでしょう。(中略)我々の道徳と生活が、そのありのままに行われていた日の「くに」という観念は、生活と道徳を共通にした集団の意味でした。しかもその生活と道徳は即身一体でした。近代が衰亡する日は、我々の『くに』の恢弘する日です」。
|
| 「日本の近代史への反省を、我々は『文明開化』を否定するという形で現したのです。大久保、福沢の系統をひく日本こそ、所謂『軍国主義』として、今日の列強から否定された日本の根本思想だと云うた。(中略)日本は「近代」を最も正しく懸命に学びました。己を零としてヨーロッパを学ぼうとした結果がこの敗戦となったのです。(中略)しかし日本には「東洋の理想を了解した多数の人々が生きていた。(中略)彼らは「近代」を文明の理想と考えていません。(中略)我々の精神上の先人とはそういう人々をさします。彼らはそういう自衛は第二義的である。第一義の理想を忘れるなということを懸命に唱えたが、文明開化派のために受け入れられなかったのです。彼らは攘夷家と呼ばれました。(中略)彼らの考え方は本質上で、道徳の見地から東西文明の優劣をのべたのです。彼らへの誤解の原因は、ものごとを知らない小説家と活動写真の脚本家が作ったのです。活動写真の影響をそのままうけて歴史観と立てている者らが、この国ではインテリゲンチヤと称しています。(中略)この系統の人々の気分に思想の言葉と方法を与えたのが、岡倉天心です。しかしこの系統の思想を持しつつ、世間を隠遁せず、時務を論じて説をなした人々は、戦時中戦後を通じてあくまで理解されず、簡単に反対のものに誤解されています。慨(なげかわ)しいことですが、現状から考えると当然のことでしょう」。
|
| 「日本人は平和を守るべきです。しかし新憲法の基本思想に立脚しては、その第9条を守れません。日本の中立を持することは、平和の本質論に徹し、本質的平和生活を敢行した場合にのみ可能です。これが絶対平和論です。敗戦によって日本は近代の高度工業と、その高度産業組織を一挙に禁止された。(中略)「近代」に逆行させられた。絶対平和生活をなすためには、近代人は大きい犠牲を払わねばならない。困苦欠乏に耐える必要がある。ちょうどよい。(中略) 強いられてなす状態となったということはいささか残念。自覚がないから、くづれ易いが、これを機に、絶対平和生活に入るべき。(中略) 何が入ってきても表から裏へつきぬけさせる、むこうのほうで抵抗を予想するところで、何の障害もなくて、結局つきぬけてしまうような生活。 アジア的農耕の生活の中にある、道義、倫理、勤労観、永遠などの恢弘。この道義の中には、近代観の、所有権、政治、主権はありません。(中略) 戦争に介入する気持が起らぬ生活、介入する必要ない生活」。 |
| 「『やはら』という術は、守ること攻めることを、つとめて外に示さぬ術です。すたすたと歩いている時の、不意の攻撃を、身体も動かさずに反撃し、相手に致命傷を与え、そのままゆきすぎるような状態を理想にしています。(中略)現にもし我々が、侵略国の軍隊を迎えたような場合、反抗しない、共力しない、誘惑されない、という形を守るには、戦車の前に横臥して、なすにまかせるという、大勇猛心を振う位の夢のような決心が必要なのです」。 |
| 「我々は作られた憲法に殉じるのではない。我々の伝えを守るのです。 国全体として絶対平和の道を歩む必要がある。(中略)我々が戦争に介入せぬ生活を国全体の計画として立て、一切の戦争介入の危険を勇気をもって拒絶する以外にない。(中略)一人でも戦争に介入して利益を得ようとすれば、百事瓦解の前兆となる」。 |
| 「吉田首相は講話後も米軍の日本駐屯を希望する、、、。(中略)それは希望でなく自棄です。理論追求上の自棄です。日本人は今こそ、父祖より遠い代々の理念に生きねばならぬのです。(中略)日本人の立場が極めて希薄。日本の同胞についての思いやりがありません。これが第一の致命的欠点。それに彼らは近代生活も今のまま楽しみたい、戦争もさけたいといった、虫の良い考えの間をゆききしている。
今のままの近代生活を維持し、出来れば少し向上させたい。「文化」を愛し、学者の俸給を増し、戦争はさけたい。そういう考え方は、植民地的なものを何かの形で保持せねば不可能なのです。平和の保障とならぬ。彼らは実際生活の上での思想と感情は、必ず戦争の一つの陣営に属さねばならぬものをもちつつ、口さきでは平和を唱えるのです。そうして後になって、新聞やラジオで、瞞された瞞されたとわめくのはみな彼らです。しかし彼らは自分の抽象的平和論が、内容と方法をもたないことをさとり、形勢非となると、多分に共産主義の陣営に近付く傾向があります。日本を謬った者は左や右のものでなく、日本の官僚組織の中枢にいて、官僚に対し最も因縁深い影響力をもった彼ら自由主義者たちこそ最も重いものでした。
彼らは戦争に対しても平和についても、本気で実践的に考えた例がないのです。それが最もよくないところですが、彼らは巧みさと器用さによって、世渡りすることに慣れて、思想というものを極めて甘く考えて了ったのです。彼らはその政治的平和論が論理的にゆきづまると、平和を守るためには国が亡んでもよい、などと平気で云います。確信をもたないもの、現実性をもたない、観念的なものは、口を閉すようにしむけるのがよいのです」。 |
| 「誰でも権力を持ちうる社会か、誰でも金持ちになりうる社会かを作ることが、近代の動きの二つの方向。故にアジアの最もすぐれた者は、みな近代から落伍した。アジアのすぐれた頭脳と精神は、そういう近代の発想を全然しないから、無関心だった。(中略)今の社会のそういう進行に必要な学問が生まれ、学者がでるのです。戦争に関係無かったり、殺戮に重宝でない文化学術は注目されないのです。(中略) 我国の西洋史家というものは、近代の枠を超えられない。(中略)独自な思想家が出ても、岡倉天心のように外国でみとめられぬ限り、日本の学者はこれを黙殺した(彼らは、外国で認められた後も、天心を理解できなかったのではないだろうか) 人間を大量に消耗したり、大量に殺戮する機械と事物の発明に於て、アジア人はヨーロッパ人に敗けたのです。(中略) 「近代」の生活と思想は、戦争の母胎です。それは「植民地」−「市場」がなくては成立しない「時代」です。(中略) 近代において「人間はすべて奴隷です」、「近代とは人間を人間以下にする機構です」。 |