私の中の二十五年間を考へると、其の空虚に今さらびつくりする。私は殆ど「生きた」とはいへない。鼻をつまみ乍ら通りすぎたのだ。
二十五年前に私が憎んだものは、多少形を變へはしたが、今もあひかはらずしぶとく生き永らへてゐる。生き永らへてゐるどころか、おどろくべき蕃殖力で日本中に完全に滲透してしまつた。其れは戰後民主主義と其処から生ずる僞善といふおそるべきバチルスである。
こんな僞善と詐術は、アメリカの占領と共に終はるだらう、と考へてゐた私はずいぶん甘かつた。おどろくべきことには、日本人は自ら進んで、其れを自分の體質とする事を選んだのである。政治も、經濟も、社會も、文化ですら。
私は昭和二十年から三十二年ごろまで、大人しい藝術至上主義者だと思はれてゐた。私はただ冷笑してゐたのだ。或る種のひよわな青年は、抵抗の方法として冷笑しか知らないのである。其のうちに私は、自分の冷笑・自分のシニシズムに對してこそ戰はなければならない、と感じるやうになつた。
此の二十五年間、認識は私に不幸をしか齎さなかつた。私の幸福はすべて別の源泉から汲まれたものである。なるほど私は小説を書きつづけてきた。戲曲も度くさん書いた。然し作品を幾ら積み重ねても、作者にとつては、排泄物を積み重ねたのと同じことである。其の結果賢明に成る事は斷じてない。さうかと云つて、美しいほど愚かに成れるわけではない。
此の二十五年間、思想的節操を保つたとひふ自負は多少あるけれども、其のこと自體は大して自慢に成らない。思想的節操を保つたために投獄された事もなければ大怪我をした事もないからである。又、一面から見れば、思想的に變節しないといふことは、幾分鈍感な意固地な頭の證明にこそなれ、鋭敏、柔軟な感受性の證明にはならぬであらふ。つきつめてみれば、「男の意地」といふことを多く出ないのである。其れは其れでいいと内心思つてはゐるけれども。
其れよりも氣にかかるのは、私が果たして「約束」を果たして來たか、といふことである。否定により、批判により、私は何事かを約束して來た筈だ。政治家ではないから實際的利益を與へて約束を果たすわけではないが、政治家の與へうるよりも、もつともつと大きな、もつともつと重要な約束を、私はまだ果たしてゐないといふ思ひに日夜責められるのである。其の約束を果たすためなら文學なんかどうでも好い、といふ考へが時折頭をかすめる。此れも「男の意地」であらふが、其れほど否定してきた戰後民主主義の時代二十五年間、否定し乍ら其処から利益を得、のうのうと暮らして來たとひふことは、私の久しい心の傷になつてゐる。
個人的な問題に戻ると、此の二十五年間、私のやつてきた事は、ずいぶん奇矯な企てであつた。まだ其れは殆ど十分に理解されてゐない。もともと理解を求めてはじめた事ではないから、其れは其れでいいが、私は何とか、私の肉體と精神を等價のものとする事によつて、其の實踐によつて、文學に對する近代主義的妄信を根柢から破壞してやらうと思つて來たのである。
肉體のはかなさと文學の強靱との、又、文學のほのかさと肉體の剛毅との、極度のコントラストと無理強いの結合とは、私のむかしからの夢であり、此れは多分ヨオロッパのどんな作家もかつて企てなかつた事であり、若し其れが完全に成就されれば、作る者と作られる者の一致、ボオドレエル流にいへば、「死刑囚たり且つ死刑執行人」たる事が可能に成るのだ。作る者と作られる者との乖離に、藝術家の孤獨と倒錯した矜持を發見したときに、近代がはじまつたのではなからうか。私の此の「近代」といふ意味は、古代に就いても妥當するのであり、萬葉集でいへば大伴家持、ギリシア悲劇でいへばエウリピデスが、既に此の種の「近代」を代表してゐるのである。
私は此の二十五年間に多くの友を得、多くの友を失つた。原因はすべて私のわがままに據る。私には寛厚といふ徳が缺けてをり、果ては上田秋成や平賀源内のやうに成るのがオチであらふ。
自分では十分俗惡で、山氣もありすぎるほどあるのに、どうして「俗に遊ぶ」といふ境地に成れないものか、われとわが心を疑つてゐる。私は人生を殆ど愛さない。いつも風車を相手に戰つてゐるのが、一體、人生を愛するといふことであるかどうか。
二十五年間に希望を一つ一つ失つて、最早行き着く先が見えてしまつたやうな今日では、其の幾多の希望が如何に空疎で、如何に俗惡で、然も希望に要したエネルギイが如何に厖大であつたかに唖然とする。此れだけのエネルギイを絶望に使つてゐたら、もう少しどうにかなつてゐたのではないか。
私は此れからの日本に大して希望をつなぐことが出來ない。此のまま行つたら「日本」はなくなつてしまふのではないかといふ感を日ましに深くする。日本はなくなつて、其の代はりに、無機的な、からつぽな、ニュートラルな、中間色の、富裕な、拔目がない、或る經濟的大國が極東の一角に殘るのであらふ。其れでも好いと思つてゐる人たちと、私は口をきく氣にも成れなくなつてゐるのである。 |
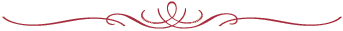
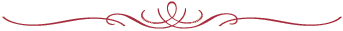
![]()
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)