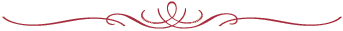「恋とはどういう人間がするべきものかということを、松枝清顕のかたわらにいて、本多はよく知ったのだった。それは外面の官能的な魅力と、内面の未整理と無知、認識能力の不足が相俟って、他人の上に幻をえがきだすことのできる人間の特権だった。まことに無礼な特権。本多はそういう人間の対極にいる人間であることを、若いころからよく弁えていた。」(332頁)
「死を決したころの勲は、ひそかに「別の人生」の暗示に目ざめていたのではないだろうか。一つの生をあまりにも純粋に究極的に生きようとすると、人はおのずから、別の生の存在の予感に到達するのではなかろうか。」(34頁)
「最高の道徳的要請によって、阿頼耶識と世界は相互に依為し、世界の存在の必要性に、阿頼耶識も亦、依拠しているのであった。 しかも現在の一刹那だけが実有であり、一刹那の実有を保証する最終の根拠が阿頼耶識であるならば、同時に、世界の一切を顕現させている阿頼耶識は、時間の軸と空間の軸の交わる一点に存在するのである。」(161頁)