七、石上中納言の巻(燕の子安貝を取らんとすれども)
石上の中納言様には、燕(つばくらめ)の子安貝を取るようにとのお題が与えられた。この人は、自分で決めることができぬ右顧左眄型の優柔不断な質(たち)にして、加えて人の云うことを真に受けては失敗する癖がある御方であった。
(石上家は歴代神事を司どっている名家の一つである。中納言とあるから大納言よりは下位の身分と云うことになる。これにどういう意味が隠喩されているのかは分からないが以下の如く描写している)
或る時、屋敷の使用人の許(もと)へ行き曰く、「燕(つばくらめ)が巣を作るのを見つけたら直ぐに知らせよ」。使用人曰く、「なぜそんなことを望むのですか」。中納言曰く、「燕が持つ子安貝を取りたいのじゃ」。使用人曰く、「これまでに燕をたくさん殺して見ましたが、腹の中にもそのようなものを見たことはありません。ひょっとして、燕が子を産む時に出るのかも知れません。しかれども、人が燕を見てしまうと飛び去ってしまうやに聞いております。どうやって取れば良いのでせう」。
こうして、どうやって取るべきかの談議が始まったが、そうこうしているうちに或る人がやって来て曰く、「大炊寮の飯炊屋の棟の上の穴に燕の巣があります。壯夫(ますらお)に命じて梯子(はしご)を架けて子燕を窺わせませう。この時に上手に取るのです」。これを聞いて悦び中納言曰く、「これは妙案じゃ。私は気がつかなかったが、汝の提言はもっともなことと思う」。そこで、壯夫(ますらお)廿(二十)人ばかりが集められ、高い梯子を架け登り、燕の巣の中を窺わせた。中納言見守り、しばしば訊(たず)ねて曰く、「子安貝取れたかや」、「何か探り当てたかや」。巣の中には何もなかった。,燕は恐れて近寄らなくなった。
ここに翁が登場して来た。寮官人の倉津麿と云う。曰く、「子安貝を取るには計略が必要ぞな.」。 中納言の御前に進み出でて、額を寄せて密談する。倉津麿曰く、「燕の子安貝を取るのに、そのようなやり方では拙(まず)い。結果は非を見るより明らか。梯子を架けるようでは驚くばかり。大勢の者が巣に近づけば燕が寄りつかなくなるでせう。高架を毀(こわ)し人を退けなさい。熟練の男子を一人荒籠に乗せ、綱で縛(しば)って掛けるのが良い。その上で、燕が子を産む間際に綱を引き釣り上げるじゃ。そうすれば子安貝を見事に取れるというものじゃ」。中納言曰く、「なるほど」。そこで、高架を毀し人払いを命じた。しかる後、倉津麿に訊ねて中納言曰く、「しかし、燕が子を産まんとするそのタイミングをどう計るのじゃ」。倉津麿曰く、「燕が子を産む時、必らずその尾を七度振ります。燕が尾を七度振った時に綱を引き揚げるのじゃ。そうすれば、籠の中に子安貝が取れようというもの」。中納言曰く、「なるほどなるほど」。
そこで、寮の男を物色し、昼夜なく貝を取るに相応しい者を探し始めた。倉津麿のアイデアがよほど気に入ったと見え、褒めて曰く、「汝は私の使用人ではないが、我が願いめでたしの暁には望みのものを与えよう。しばし協力せよ」。こう云って、とりあえず中納言が着ていた羽織を与えた。倉津麿、これを貰って曰く、「有り難いお言葉です。お任せください。今夜必ず寮に参るつもりです」。こう述べて帰って行った。
日が暮れた時分になって子安貝取り作戦を開始した。中納言と倉津麿は使用人に指示した。下から見上げながら曰く、「燕が尾を振る時、荒籠を引き綱を釣り上げる。その時、手をすっと伸ばして巣の中の子安貝を探すのじゃ」。使用人はその時を待った。燕が尾を振ったのを合図に、さっと巣の中に手をれた。しかしながら曰く、「それらしいものが見当たりません」.。これを聞いて怒って中納言曰く、「汝の探し方が下手なのじゃ」。人を替えて試したが、これも失敗した。改めて曰く、「このへたくそめが。私が登って探そう」。
そこで籠に乘り登って穴を窺った。その時、燕が尾を振り廻り始めた。その刹那(せつな)、手を差し伸べると平たいものに触れた。喜んで曰く、「握ったぞ。さぁ私を降ろせ。倉津麿よ、遂に子安貝を取ったぞ」。大声で使用人を呼び寄せ曰く、「早く私を下せ」。使用人が籠を降ろそうとして綱を引いたが、大慌てで引き過ぎたためプツンと切れてしまった。中納言はそのまま八島鼎(かなえ)の上に落下した。.驚いた使用人急ぎ抱きかかえて曰く、「大丈夫ですか。お気を確かになされませ」。中納言は両の白目をくるくると廻していた。水を口にふくませると漸(ようや)く正気(しょうき)に戻った。幾分か苦しそうにしていたので、鼎の上で手足を揉みさすった。
少々息を荒げながら中納言曰く、「降りるときに失敗した。腰が痛くて動けない。しかし痛さもなんのその子安貝を握っているのでこれに勝る悦びはない。心配ない。それより私が握っている貝を早く見たい。が、起き上がれない。みんなで確認してくれ」。中納言が手を開くと、使用人どもが見たのは何と燕の古糞(ふるくそ)だった。これを見て嘆じて曰く、「ああ、貝を取るのにこんなに苦労したと云うのに」。これより世人、願い事違う時には、「貝なし(甲斐なし)」と云うようになった。
子安貝を取り損ない、唐櫃に入れてかぐや姫に見せに行く夢を叶えられなかった中納言は、腰を痛めて立つこともできぬようになり、氣病みも加わった。弱った両目は相変わらず貝を取りそこなったことを恨んでいるようだった。世人の笑いを懼(おそ)れ、日々鬱々になりとうとう病死してしまった。
(石上の中納言のみ気弱になり日日鬱々のまま死んでしまったとあるのも何らかの裏意味があると窺うべきであろう。中納言は他の方に較べて物入りしなかったが一番慘(むご)い目に遭ったことになる。中納言の様は石上家のそれでもあるように思われる。そういう隠喩が込められているように思われる)
かぐや姫、このことを聞いて慰め歌って曰く、
| 「年を經て浪立たず 住江(すみのえ)の松は何処にあらむ 子安貝得ずと聞き思う」 |
| (經年浪不立 訊杳住江松不待 聞是不得子安貝) |
| (「年を經て浪立たちよらぬ住江(すみのえ)の 末(まつ)貝無しと聞くは真ことか」) |
かぐや姫の慰めを聞いた中納言は、身体(からだ)は弱り床に伏し頭を上げるのも難しかったが、紙を取れと命じ、心中の苦悶を詠んで曰く、
| 「労したものの貝を得ず 今かぐや姫の一言を得 慰みの良薬とぞ けだし身の救い難しのみ恨み残る」 |
| (徒勞不得貝 得汝一言如良藥 只恨殘身難為救) |
| (「かひは斯くありけるものを侘び果てて 死ぬる命を救ひやはせぬ」) |
中納言は、書き終えるやそのまま死んでしまった。こうして石上の中納言が五番目の撃沈者となった。これにより五人衆は皆な思いを遂げられなかったことになる。かぐや姫は、これを聞き少し哀しんだ。かぐや姫の哀しみを貰った中納言は甲斐を得た。これにより歓びごとを甲斐ありと云うようになった。
(石上の中納言は、前四者と違い自ら本物を得んとして危険を冒し、転落して腰の骨を折り、これが元で病に伏し、未練のまま病没したことになる。このことにどういう寓意があるのかは分からない) |
|
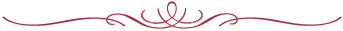
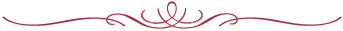
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)