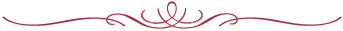
| 桃太郎伝説考 |
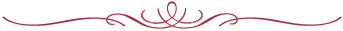
(最新見直し2008.8.29日)
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここで、鬼、天狗、サンカ伝説を確認しておく。それぞれに興味がわくが一朝一夕にはできない。 2008.4.10日、2010.4.17日再編集 れんだいこ拝 |
![]()
|
「谷田茂・氏の「古代出雲王国-スサノオの光と影-53 被差別民の真実-彼らは出雲族だった!!」(2009.5.29日)は次のように記している。
関裕二「修験道がつくった日本の闇」(ポプラ社、2009.2.16日初版)の39P鬼の烙印を押されし者」の一文を転載する。
|
| 【桃太郎の鬼退治伝説考】 |
| 2018.5.24日、岡山県の岡山市、倉敷市、総社市、赤磐市の4市が申請した「『桃太郎伝説』の生まれたまち おかやま~古代吉備の遺産が誘(いざな)う鬼退治の物語~」が、日本遺産に認定された。「日本遺産」とは、文化庁が、地域の歴史的魅力や特色を通じて我が国の文化、伝統を語るストーリーに対して認定したものを云う。2020年までに100件程度の認定を予定している。2019.3月現在の認定数は67件。年に一度の公募審査がある。2018年度は76件の申請があり、認定されたのは13件の難関になっている。 |
| 桃太郎伝説に登場する桃は、古代中国では桃源郷にある不老不死の果実、日本でも魔除けの果実として知られている。桃神話は古事記に次のように記されている。イザナギ、イザナミの夫婦神様が現れ、日本の国土を造り、これを支配する神々をお産みになられた。ところが女神はまもなく黄泉(よみ)という国へ去ってしまわれた。男神は大変悲しみ後を慕って黄泉の国まで訪ねて行き、女神と会った。暫く待つように云われたのに構わず女神の居所へ入っていくと、女神は見るも気味の悪い姿に変っており、男神はびっくりして逃げ出した。みにくい姿を見られた女神は怒ってシコメ軍という黄泉の国の鬼共を呼び集めて男神を追いかけて捕えよと命じた。男神は十拳(とつか)の剣を抜いて後手にふりつつ黄泉比良坂(よもつひらさか)とう所まで退いた。見るとそこに大きな桃の木があって桃がたくさんなっていたので男神はその桃の実をとって鬼共めがけて投げつけるとどうしたことか鬼共は頭をかかえて一目散に逃げ帰っ。男神は桃の実のおかげで思わぬ危難をまぬがれることができた。桃の実に大神実命(おおかむづみのみこと)という御神名を賜ると同時にこれから後の世の人々が、若し私の様なめにあって苦しむことがあったらお前行って助けてやってくれよとお頼みになられた云々。 桃太郎の鬼退治伝説では、ある日のこと、いつものようにお婆さんが岩の上で洗濯していると大きな桃が流れてきた。「おお珍らしい大きな桃じゃわい。お爺さんと二人で食べましょう」と持ち帰った。しばらくして柴を背負ったお爺さんがやっこらさと帰って来た。お婆さんは「お爺さんさぞ疲れやんしたろう、さあ、きょうはいいものがあるぞえ」と云いながら先程の桃を出してきて切らうとしたところ、これは不思議、突然、桃の中で声がしたと思うと桃はひとりでに割れて中からまるまる太った男の子が生れ出た。腰を抜かさんばかりに驚いた二人はやがて神様がお授けくださったのに違いないと、手をとり合って喜びあい桃から生れたので桃太郎と名づけて大事に育てた。 桃太郎は年とともにぐんぐん力もちになった。或る日、お爺さんの柴刈りの手伝いをしながら山奥へ入って行くと、子供をふところに抱いた女達が肩を寄せ合ってシクシク泣いていた。桃太郎がやさしくわけを尋ねると、「私達は山向うの百姓ですが、川の中の鬼ケ島にすむ鬼共が近郷近在を荒し廻り、女・子供をさらって行きますのでこうして可愛い子供を抱いてかくれております。今に見つけ出されてひどい目に合わされるのではないかと思うと恐ろしくて生きた心地もしません。どうか助けてください」と話した。そこで桃太郎は鬼征伐の決心をしてお爺さんお婆さんに話すと、大賛成して早速、土地の名物きびだんごを兵糧(ひょうろう)として沢山作ってくれた。桃太郎はそのきびだんごを網袋(あみぶくろ)に入れて腰にさげ、日本一と書いた小旗を立てて勇んで家を出掛けた。日本一の旗をひらめかして進む姿は実に勇ましく見えた。 桃太郎の出陣を知って息せき切って三匹の供がいた。最初に馳けつけたのが日頃仲よしのイヌ。桃太郎から吉備団子を貰ってお供になった。すこし行くと今度は崖から大きなサルが現われた。 さらに先へ進むと、今度は山のてっぺんから一匹のキジが船へ舞い降りてきた。桃太郎はこれにもきびだんごをやり、お供になった。 吉備津彦命の優秀な三人の家臣。犬は、犬飼健(いぬかいたける)で忠実。猿は、軍師の楽々森彦(ささもりひこ)で知恵。雉は、留玉臣(とめたまおみ)で情報。吉備津彦命は、この三人の家臣を従え、和歌や枕草子などで知られる吉備の中山に鬼退治の陣を構えた。 現在の岡山市、総社市、倉敷市の一帯は、その昔「吉備の穴海」と呼ばれる海だった。桃太郎伝説で桃太郎が向かった鬼が島は、総社市にある鬼の城辺りと考えられる。鬼の城は、正規の歴史書には登場しない謎の城で、2.8kmに及ぶ城壁が山を取り巻いており、古代山城随一のスケールを遺している。見せている。いるろ。当時、温羅(うら)は鬼の城の山域に住んでいた。桃太郎伝説では、村人たちに悪さをする鬼として描かれているが、追いやられた原住民とも考えられる。桃太郎伝説では、吉備津彦命と温羅の放つ矢が不思議なことに全て空中でぶつかり、矢喰宮(やくいのみや)に落ちた。そこで吉備津彦命は同時に二本の矢を放つと、一本は温羅の矢とぶつかり、もう一本が温羅の左目を刺した。温羅の目から流れ出した血が血吸川を赤く染めた。温羅は雉や鯉に化け逃げた。吉備津彦命も負けじと鷹や鵜となり追いかけ、遂に鯉を捕らえた。温羅は元の姿に戻り力つきた。こうしてさすがの鬼共は降参した。もう決して悪いことはしませんと改心したしるしに宝物を全部さし出した。桃太郎の一行は宝物を車に積んでめでたく帰路についた。途中の村々では大喜びで倉から酒を出して凱旋(がいせん)を祝った。 かく鬼退治されめでたしめでたしとなっているが、続きがある。吉備津彦命に退治された後も夜になるとうなり声をあげ続け、温羅の首は吉備津神社の御釜殿のかまどの下深くに埋められた。しかし不気味な声はおさまらなかった。ある夜、吉備津彦命の夢に温羅が現れ、「この釜の火を炊く役目を私の妻にさせてくれ。そうすれば、釜の音で世の吉凶を占おう」と告げた。温羅の云う通りにするとうなり声はおさまり、この地の吉凶を告げる使いになった。この神事は今も続いている。神官と共に阿曽女(あそめ)という女性が奉仕するのは、温羅の妻に由来している。 |
| 「桃太郎伝説は古事記から始まる」その他参照 |
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)