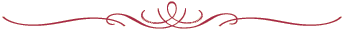
| 別章【聖武天皇前後考】 |
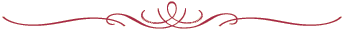
更新日/2023(平成31.5.1栄和改元/栄和2).4.22日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここで、「別章【聖武天皇前後考】」をものしておく。 2008.8.2日再編集 れんだいこ拝 |
![]()
| 43代、元明天皇の御代 |
| 【元明天皇即位】 |
| 707(慶雲4).6.25日、文武天皇が25歳で崩御。首皇子が当時7歳と幼少であったので、遺詔により文武天皇の母、即ち首皇子の祖母(天智天皇皇女、文武天皇の母親)にあたる阿閇(あべ)皇女が元明天皇として即位。母の宮子も心的障害に陥りその後は長く皇子に会う事はなかった(物心がついた天皇が病気が平癒した宮子と対面したのは天皇が37歳のときのことであった)。 |
| 【元明天皇の詔勅】 | ||
708(和銅元)年、続日本紀によれば、正月11日の条に詔勅「山沢に亡命して禁書をきゅう蔵し、百日にして首(いで)ずば、罪を初の如く復す」(山中に亡命して禁書を秘蔵する者が百日たっても自首しなければ本来の罪に問う)が発令されている。
|
708(和銅元)年、3.13日、従四位上の中臣朝臣意美麻呂を神祇伯に任じ、右大臣・正二位の石上朝臣麻呂を左大臣に、大納言で正二位の藤原朝臣不比等を右大臣に任じる。
708(和銅元)年、7.15日、二品の穂積親王、左大臣の石上朝臣麻呂、右大臣の藤原朝臣不比等を御前にお召しになって、天皇は次のように詔した。(以下略)
708(和銅元)年、続日本紀によれば、2月の条に「始めてさい鋳銭司を置く」、5月の条に「始めて銀銭を行う」、8月の条に「始めて銅銭を行う」とある。
709(和銅2)年、5.27日、(新羅使)の金金信福らを朝堂でもてなされ、地位に応じた禄を賜った。(中略)この日、右大臣の藤原朝臣不比等が、新羅使を弁官の庁内に招き、次のように語った。「新羅国の使節は、古くから我が国に入朝しているが、今まで使節が執政の大臣と語り合うことはなかった。しかし今自分が直接対面するのは、二国の好(よしみ)を深めて、親しく往来しようと思うからである」。使節らは座をおりて拝礼し、席にもどって答えて言った。「自分らは本国の卑しい地位の人間です。けれども新羅の王臣の命を受け、聖朝に入ることができました。下位にあるにも拘わらず、この幸いは言い尽くせません。まして椅子席にかけて親しく対面が許され、温情の言葉を承り、深く喜んでおります」。
| 【平城京遷都】 |
| 710(和銅3).3.10日、元明天皇の時代に藤原京から平城京への遷都。 |
| 【古事記献上】 |
| 711(和同4).9.18日、元明天皇の御代、元明天皇が、大安万呂(おおのやすまろ)に命じて稗田阿礼詠みまとめていたところの歴史書の編纂の詔を下す。 712(和同5).正月28日、元明天皇の御代、大安万呂は、天武天皇の命を受けて始めた国史として古事記3巻を編纂し、持統、文武の時代を経て元明天皇に献上した。物語風に編纂されているところに特徴がある。これが我が国初の国史書となった。実際には古事記以前の国史書の存在も推定できるが残存しておらぬ為、古事記が史上最も古い国史書と云う歴史的地位を獲得している。 |
712年、「隼人の乱」。大和朝廷の追討・掃討で全壊滅。
| 【風土記編纂】 |
| 713(和同6)年、.5.2日、元明天皇の詔「畿内七道諸国郡郷の名は好字を著けよ。其の郡内に生ずる所の銀銅彩色草木禽獣魚虫等の物はつぶさに色目を録せ。及び土地ノ沃項、山川原野の名号の由る所、また古老の相伝ふる旧聞異事は史籍に載せて言上せよ」によって各地の風土記が撰集された。その多くはその後散逸したが、出雲国風土記のみが完本として残され、一部伝存しているのは、播磨、常陸、豊後、肥前の四風土記である。その他各国別の風土記逸文がある。出雲風土記の勘造の日付は733(天平5).2.30日、編纂責任者は出雲国造家の祖・出雲臣広島である。広島は秋鹿郡の人で、神宅臣金太理(みやけのおみかなたり)の支援協力を得てこれを完成したと明記している。こうした事情の明瞭にわかるのは五国の古風土記の中で出雲風土記のみとなっている。 |
| お触れ「諸国の郡名、里名を、好い字の二文字に改めて定着させよ」により「粟国」は「阿波国」、「木国」は「紀伊国」、「泉国」は「和泉国」となった。 |
714(和銅7).6.25日、首皇子はこの年、14歳で立太子式を迎えられ、皇太子となる。
714(和銅7)年頃、藤原不比等が中心になって養老律令の成文化が始まる。
| 44代、元正天皇の御代 |
| 【元正天皇即位】 | |
715(霊亀元).9.2日、元明天皇55歳の時、健康上の理由もあって、元明天皇の娘にして文武天皇の姉にあたる氷高内親王(ひたかのひめみこ)に天皇の位を譲られ、元正天皇として即位する。年号を霊亀と改元している。元明天皇が譲位に際して下した詔はこう記している。
|
716(霊亀2)年、首皇子(16歳)は藤原不比等の娘(母は橘宿禰三千代)の安宿媛(後の光明皇后)を夫人とされる。
717(養老元).4月の条、続日本紀は次のように記している。
|
719(養老3).6.10日、首皇子、初めて朝政を聴く。
| 【日本書紀献上】 |
| 720(養老4)年、編纂に約40年を費やして、古事記献上から8年後、元明女帝の皇女元正女帝の御代、天武天皇の第3皇子である舎人親王等が日本書紀30巻、系図1巻を上宰し、元明女帝の皇女・元正女帝に献上した。大安万呂(おおのやすまろ)の子孫である多人長(おおのひとなが)の著書「日本紀弘仁私記」の序文には、大安万呂が日本書紀の編纂に加わっていたと明記している。つまり、古事記を編纂した大安万呂が、古事記完成の僅か8年後にそれと異なる日本書紀を正史として新たに作り上げた、ということになる。日本書紀が、我が国における初の官選正史の歴史書となった。中国の歴史書・史記、漢書、後漢書、三国志魏志、三国志呉志、梁書、隋書、文選、芸文類聚、最勝王経、北堂書鈔から3、191字の章句を借用している。
古事記も日本書紀もいわゆる神代時代から始まって、古事記は第33代推古天皇まで、日本書紀は第41代持統天皇(在位690~697)までの事跡を扱っている。共に編年体と云われる時系列で記されているところに特徴がある。古事記は前半部分の方が詳しく、日本書紀は後半部分の方が記事が詳しい。読み比べればどこを訂正しているか歴然とするのであろうが、れんだいこにはその能力も時間もない。又、古事記の方が古くからの言葉をそのまま残そうとしている。現在では母音はあいうえおの五つしかないが、古事記は当時八つあった母音を異 なる漢字で書き分けている。 ともかく、それぞれ研究の対象に選べば、それだけで一生費やせそうな内容を持った重要な文献である事は間違いない。 日本書紀の完成を最も喜んだのは藤原不比等であったと思われる。701年に「大宝律令」を制定、710年に平城京遷都を主導し、我が子の宮子を持統天皇の孫にあたる文部天皇に嫁がせた不比等は、先行した古事記を踏まえつつ皇室の万世一系の系譜と由来を完成させ、現王朝の正統性を引き出すことに腐心していた。 日本書紀には、壬申の乱で敗北した天智天皇の娘でありながら勝者の天武天皇の后となった持統天皇の秘めた願いが込められていた。天武天皇の死後、皇太子である子の草壁皇子のためにライバルと目された天武系の大津皇子を抹殺したが、草壁皇子が若くして病死するという悲運に見舞われた。そこで自ら即位し持統天皇となった。持統天皇は、その後継者として孫の軽皇子の擁立を藤原不比等とともに図って文部天皇として即位させ天智系の復活を実現させた。その勝者の立場で書かれたのが日本書紀であった。 |
|
|
| 古事記、日本書紀の編纂は、日本の国家ないしは民族の主体性を示して余りあると云えるだろう。この点がもっと指摘され注目されても良いだろう。 |
| 続日本紀は、720年に「日本紀」が撰上されたと記し、日本書紀については言及がない。「日本紀」が先にあり、それが修正、改編されて日本書紀になったと考えられる。 |
720(養老4)年、3.12日、勅を出して、特別に右大臣正二位の藤原朝臣不比等に、授刀資人30人を加えた。
| 【藤原朝臣不比等が薨じる】 | |
720(養老4)年、8.1日、右大臣・正二位の藤原朝臣不比等が病気になった。平癒を祈るため、得度する人30人を与えられ、次のように詔した。
720(養老4)年、8.3日、右大臣正二位の藤原朝臣不比等が薨じた。天皇はこれを深く悼み惜しまれた。ためにこの日は政務はみず、内殿で悲しみの声をあげる礼を行ない、特別に手厚い天皇の勅があった。大臣は近江朝廷の内大臣・大織冠であった鎌足の第二子である。(後日本紀の養老四年(720年)八月一日の条) |
721(養老5年).12.7日、元明太上天皇崩御。
722(養老6)年頃、藤原不比等が中心になって成文化させた養老律令が完成する。但し施行は757年頃となる。
| 45代、聖武天皇の御世 |
| 【聖武天皇即位】 |
|---|
| 724(神亀元).2.4日、首皇子(おびとのみこ)が24歳で、元正天皇より位を譲られて第45代天皇として即位した(聖武天皇)。尊号(諡号)を天璽国押開豊桜彦天皇(あめしるしくにおしはらきとよさくらひこのすめらみこと)、勝宝感神聖武皇帝(しょうほうかんじんしょうむこうてい)、沙弥勝満(しゃみしょうまん)。 聖武天皇は、文武天皇の第一皇子。母は藤原不比等の娘の・宮子。皇后は、やはり藤原不比等の娘の光明子。夫人として安宿媛(あすかひめ)との間に阿倍内親王・基親王をもうけ、夫人県犬養広刀自(のち皇后)との間に井上内親王・安積親王・不破内親王をもうけた。他に橘古那可智(佐為王の女)・藤原武智麻呂の女・藤原房前の女も室とした。 この日、長屋王を左大臣とする。聖武天皇の愛用品は、今日、正倉院()の宝物()として天平文化の粋をつたえている。 聖武天皇の生没年は、701(大宝元)-756( 天平勝宝8).5.2叉は6.4日。在位は724(神亀元).2.4(3.3日-749( 天平勝宝元).7.2(8.19)。在位中の元号は、神亀が724.2.4(3.3)日-729.8.5(9.6)日。 聖武天皇は積極的に唐の文化をとりいれる一方、仏教を深く信仰して全国に国分寺と国分尼寺をつくり,都には東大寺をたてて大仏をまつった。天皇の治世を中心に,仏教中心の天平文化がさかえた。 |
| 【「長屋王の変」】 |
| 聖武天皇の治世の初期は皇親勢力を代表する長屋王が政権を担当していた。この当時、藤原氏は自家出身の光明子の立后を願っていた。しかしながら、皇后は夫の天皇亡き後に中継ぎの天皇として即位する可能性があるため皇族しか立后されないのが当時の慣習であったことから、長屋王は光明子の立后に反対していた。 729(神亀6年、天平元年).2.10日、漆部(ぬりべの)造君足等、左大臣長屋王の謀反を密告した。「続日本紀」には密告の内容を、 「左大臣正二位長屋王私(ひそか)に左道を学び国家を傾けんと欲す」と続日本紀に記している。これにより、三関を固守させ六衛府の兵に長屋王の宅を囲ませる。2.12日、長屋王自尽。その室、吉備内親王も自殺した。これを「長屋王の変」と云う。 後に、これは讒言であった事が発覚する。長屋王の変は長屋王を取り除き光明子を皇后にするために不比等の息子で光明子の兄弟である房前ら藤原四兄弟が仕組んだものといわれている。変後、不比等の長子武智麻呂を大納言に任命する。 |
| 【光明子は非皇族として初めて立后される】 |
| 反対勢力がなくなったため光明子は非皇族として初めて立后された。 |
| 【一切経を書寫】 | |
734(天平6)年、この年、聖武天皇、一切経を書寫させる。詔(東大寺要録)は次のように記している。
|
| 【藤原不比等四兄弟相次いで没す】 |
| 737(天平9).4.17日、諸国で疫瘡に倒れる者が多く、参議藤原朝臣房前(ふささき、藤原不比等次男)薨る。7.13日、参議藤原朝臣麻呂(藤原不比等四男)薨る。7.25日、左大臣藤原朝臣武智麻呂(藤原不比等長男)薨る。8.5日、参議藤原朝臣宇合(うまかい、藤原不比等三男)薨る。藤原不比等の子の房前ら4兄弟が相次ぐ死。急遽長屋王の実弟である鈴鹿王を知太政官事に任じて辛うじて政府の体裁を整える。 |
| 【光明皇后が、法華寺を建立】 |
| 聖武天皇皇后光明子は立て続けに兄たちを亡くした為、法華寺を建立して兄たちの菩提を弔った。法華寺は天平時代、光明皇后の勧めにより日本総国分尼寺として創建されたが、正式な寺号は「法華滅罪寺」である。光明皇后の生家、藤原不比等の邸が寄進されて寺となった。皇太子を満一歳前に亡くし、また天然痘で兄弟の藤原四卿を失った皇后の悲しみが、「滅罪寺」という名前を付けさせたのかもしれない。 皇后官職に施薬院を置き、天平9年大流行した疫病(天然痘)の難病者たちを自ら法華寺の風呂に入れ介護したと伝えられる。 |
| 【聖武天皇の行幸彷徨】 |
| 聖武天皇は、738(天平10)年あたりから頻繁に行幸を繰り返し、都も「平城京」を出て、「恭仁京」「難波宮」「紫香楽宮」と遷都を繰り返した。しかし人臣にはすこぶる不評で、「紫香楽宮」などは奈良へ帰りたい臣下達が放火を繰り返したとされている。会議を開いて臣下に「都は何処がよいか」などと聞いたことが文献に見え、聖武天皇の優柔不断、或いは情緒不安定とも評される。 |
| 【藤原広嗣の乱】 |
| 740(天平12).8.29日、藤原広嗣(参議藤原朝臣宇合(藤原不比等三男)の子)が、橘諸兄の主導する政治を批判し、僧正玄昉、下道朝臣吉備真備を除こうとする。「天変地異を招き、朝政を壟断する玄昉、吉備真備ら一部の政治家を朝堂から追放せよ」とする上表を送った。同9.2日、藤原広嗣が兵を起こして反す(藤原広嗣の乱)。 聖武天皇は大野東人を大将軍に任じて節刀を授け、副将軍には紀飯麻呂を任じた。東海道、東山道、山陰道、山陽道、南海道の五道の軍1万7千人を動員するよう命じた。4日、朝廷に出仕していた隼人24人に従軍が命じられる。5日、佐伯常人、阿倍虫麻呂が勅使に任じられた。 朝廷からは伊勢神宮へ幣帛が奉納され、また、諸国に観世音菩薩像をつくり、観世音経10巻を写経して戦勝を祈願するよう命じられた。9月21日、長門国へ到着した大野東人は、同地に停泊している新羅船の人員と機器の採用の許可を求めた。 9月22日、勅使佐伯常人、阿倍虫麻呂が隼人24人、兵4,000人を率いて渡海して、板櫃鎭(豊前国企救郡)を攻略。登美、板櫃、京都三鎮の兵1767人と兵器多数を鹵獲した。 広嗣は企救郡の隣の遠賀郡に到着して烽火を発して国内の兵を徴集。広嗣が大隅国・薩摩国・筑前国・豊後国の兵5000人を率いて鞍手道を進軍、弟の綱手は筑後国・肥前国の兵5000人を率いて豊後国から進軍、多胡古麻呂が田河道を進軍して三方から官軍を包囲する作戦であった。9月25日、豊前国の諸郡司が500騎、80人、70人と率いて官軍に投降してきた。9月29日、「広嗣は凶悪な逆賊である。狂った反乱を起こして人民を苦しめている。不孝不忠のきわみで神罰が下るであろう。これに従っている者は直ちに帰順せよ。広嗣を殺せば5位以上を授ける」との勅が九州諸国の官人、百姓にあてて発せられた。 10月9日、広嗣軍1万騎が板櫃川(北九州市)に至り、河の西側に布陣。勅使佐伯常人、阿倍虫麻呂の軍は6,000人余で川の東側に布陣した。広嗣は隼人を先鋒に筏を組んで渡河しようとし、官軍は弩を撃ち防いだ。常人らは部下の隼人に敵側の隼人に投降を呼びかけさせた。すると、広嗣軍の隼人は矢を射るのをやめた。常人らは十度、広嗣を呼んだ。ようやく乗馬した広嗣が現れ「勅使が来たというが誰だ」と言った。常人らは「勅使はわれわれ佐伯常人と阿倍虫麻呂だ」と応じた。すると、広嗣は下馬して拝礼し「わたしは朝命に反抗しているのではない。朝廷を乱す二人(吉備真備と玄昉)を罰することを請うているだけだ。もし、わたしが朝命に反抗しているのなら天神地祇が罰するだろう」と言った。常人らは「ならば、なぜ軍兵を率いて押し寄せて来たのか」と問うた。広嗣はこれに答えることができず馬に乗って引き返した。この問答を聞いていた広嗣軍の隼人3人が河に飛び込んで官軍側へ渡り、官軍の隼人が助け上げた。これを見て、広嗣軍の隼人20人、騎兵10余が官軍に降伏してきた。投降者たちは3方面から官軍を包囲する広嗣の作戦を官軍に報告し、まだ綱手と多胡古麻呂の軍が到着していないことを知らせた。その後、広嗣軍は板櫃川の会戦に敗れて敗走した。広嗣は船に乗って肥前国松浦郡値嘉嶋(五島列島)に渡り、そこから新羅へ逃れようとした。ところが耽羅嶋(済州島)の近くまで来て船が進まなくなり、風が変わって吹き戻されそうになった。広嗣は「わたしは大忠臣だ。神霊が我を見捨てることはない。神よ風波を静めたまえ」と祈って駅鈴を海に投じたが、風波は更に激しくなり、値嘉嶋に戻されてしまった。10月23日、値嘉嶋に潜伏していた広嗣は安倍黒麻呂によって捕らえられた。10.29日、聖武天皇、伊勢国へ行幸。11月1日、大野東人は広嗣と綱手の兄弟を、肥前国唐津(現・佐賀県唐津市)で斬った。11.5日、大野東人等、1日に肥前国松浦郡において藤原広嗣を斬りし事を報ず。 741(天平13).1月、乱の処分が決定し、死罪16人、没官5人、流罪47人、徒罪32人、杖罪177人であった。藤原式家の広嗣の弟たちも多くが縁坐して流罪に処された。 |
| 【諸国に国分・国分尼寺を建立】 |
| 741(天平13).2.24日、聖武天皇は、「国分寺・国分尼寺建立の詔」を発令し、国家の隆昌・安寧を祈らんが為として、諸国に国分・国分尼寺を建立せんとする。(「続日本紀」天平19年11/7に載せる詔に国分寺建立の願を発した日を「天平13年2月24日」とする) 光明皇后が創建したこの法華寺も総国分尼寺となる。 |
10.16日、山城国賀世山の東河の架橋成る。よって従事せし諸国の優婆塞等に得度を許す。
| 【盧舎那大仏像の造顕を発願】 | |
743(天平15).10.15日、聖武天皇が、三宝の威霊に頼り、乾坤相泰かならん事を欲し、「盧舎那大仏像の造顕を発願の詔」を発布する。
10.19日、聖武天皇、信楽(紫香楽)宮にて、盧舎那の仏像を造り奉らんが為に始めて寺地を開く。行基、弟子を率いて勧進をはじめる。 東大寺大仏の造営のきっかけは天平7年の疫病の大流行であった。さらに飢饉が襲い、宮廷内の政局も不安定であった。聖武天皇はこうした災いを神仏に祈祷することでくい止め、人臣の不安を和らげようと考えた。その方策として僧・玄肪の意見をいれ考えられたのが毘廬舎那大仏の金銅仏の造営だった。大仏造営は資金難によりいったんは中断するが、行基の勧進などにより再開された。帝は、この仏をみなが一丸となって造営する事で団結し、同様に利益を分かち合おうとする主旨の誓願を立て、天皇も自ら土を運んだので、皇后以下、臣下の者もこれに従った。天平15年(743)の着手から、大仏開眼まで10年の年月を費やし、動員された人員は延べ200数十万人、資材は銅、錫、金、水銀など合わせて15万貫にものぼったと言われる。 |
| 【八幡宮創建】 |
|
(古代史研究会の佐伯剛/氏の所説参照)
富山県の奈呉の浦は、能登半島によって日本海の荒波から守られ、穏やかな内海になっている。ここは、江戸から明治にかけて北前船の寄港地として栄えたところだが、現在でも、内川の両岸には漁船が係留され、風情のある民家が軒を連ねている。この地に、放生津八幡宮が鎮座している。この八幡宮は、万葉歌人で政治家でもあった大伴家持が、746年に創建したとされる。 八幡神を祀る神社は、今でこそ日本でもっとも数多いが、八幡神は、古事記(712)や日本書紀(720)に登場せず、745年から752年にかけて行われた東大寺大仏の造立の際、国家の守護神として歴史に華々しく登場した。(それまでは九州の豊前の一地方神だった)その歴史背景として、天然痘の大流行と、九州で起きた藤原広嗣の乱があり、この緊急事態に、聖武天皇は、それまで宗教的に弾圧されていた行基の力を頼り、律令制の縛りをゆるめ、人々が自分の土地を離れ、自ら進んで大仏造立の仕事にくわわることを認めた。奈良の大仏の造立は、よく言われるように人民を搾取して強制的に使役することで成し遂げられたのではなく、行基集団が信仰心に基づいて行っていたボランティアの社会活動の延長にあった。聖武天皇は、この民力を、天然痘で人口の半分から三分の1が失われた社会の立て直しに生かそうとした。
同じ頃、大伴家持は、越中国守として富山に赴任した。その任務は、東大寺の寺領を占定し、開墾を進めることだった。正倉院に保管されている東大寺墾田地地図の24枚のうち17枚までが、大伴家持の赴任した越中国のものである。さらに、この奈呉の地は、古代から海人の拠点であり、海産物や、海上交易による富も、重要だったのではないかと思われる。そして大伴家持は、この奈呉の浦に、豊前の宇佐八幡宮から勧請して放生津八幡宮を創建した。石清水八幡宮(860年創建)より100年以上も古く、国家の守護神としての八幡神を祀る聖域としては、日本最古級となる。奈呉という地名は、大伴氏が拠点としていた大阪の住吉神社周辺の古代の地名でもあり、ここも、瀬戸内海から大陸へと向かう海上交通の玄関口であった。
そして、伊豆半島の伊豆の国市にも、”なご”の名がつく奈古谷集落があるが、ここは、鎌倉時代の執権政治の基礎を築いた北条時政が治めていたところで、伊豆に配流されていた源頼朝と邂逅したところだった。この地も水上交通と関わりが深く、この場所を流れる狩野川流域は、古代から、船の建造に適したクスノキの産地であり、古事記のなかにも、応神天皇が、この地で船を作らせたという記録がある。また、この地に鎮座する奈胡谷神社の敷地からは、古代住居跡や土器片・玉類の祭祀遺物が出土しており、ここが古代の祭祀場だったことが分かっている。また、当社の御神体の石捧は、縄文時代以來、伝存されたものだという。そして、北条時政は、鎌倉時代、富山の奈呉の浦の放生津八幡宮を再興した。北条時政というのは歴史上に名を残す人物であるが、父が不明確で兄弟の存在もわからない謎の人物だ。しかし、母親は、大伴氏の伴為房の娘であり、伴為房を伴善男の後裔とする系図が存在している。伴善男というのは、平安時代、応天門の変で藤原氏との権力争いに敗れて失脚し、伊豆に配流された大伴氏の代表的人物である。
大伴氏は、奈良時代中旬まで朝廷内で大きな力をもっていたが、長岡京の変(785年)で藤原氏によって多くの大伴氏の有力者が死罪となり、その時、すでに亡くなっていた万葉歌人の大伴家持まで、陰謀の罪があったとされた。この長岡京の変によって朝廷内で力を失った大伴氏にとって最後の一撃となったのが応天門の変(866)だとされる。これを機に、藤原氏の独裁的な権力が確立されたというのが歴史の教科書で習う内容だ。しかし、藤原氏によって歴史から抹消されたように語られる大伴氏は、明治時代の前まで鶴岡八幡宮の神職を世襲し続けた。また、長岡京の変で、大伴氏の共犯とされた佐伯氏(大伴氏と同族)は、広島の厳島神社や、福岡の住吉神社の神職を世襲し続けた。いずれも海上交通と非常に深い関係のあるところだ。
そして不思議なことに、北条時政が伊豆を治めていた頃、福岡の住吉神社の神官だった佐伯昌長が、中国貿易をめぐる平清盛との軋轢で伊豆に配流されており、彼の占筮(ぼくぜい)によって、源頼朝は、1180年8月17日を平氏打倒の挙兵の日と決めたと吾妻鏡に記録されている。伊豆に流されていた源頼朝による平氏打倒のための挙兵の背後に、藤原氏によって歴史から抹殺された大伴氏や佐伯氏が関わっている。( NHKの大河ドラマではスルーされているだろうが)。そして、平氏打倒の一歩を踏み出した源頼朝は、神奈川県真鶴付近で石橋山の戦いで敗戦するが、真鶴岬から船で安房国(現在の千葉県南部)へ脱出し、この地の豪族、上総氏と千葉氏に加勢を要請した。滅亡寸前の源頼朝が海を渡れるよう支援した海人がいなかったら歴史が変わっていただろう。
安房国の房総半島最南端部には、安房神社が鎮座する。ここは古代からの海人の痕跡が多く残るところで、神話時代に徳島県から渡ってきた忌部氏による創建とされるが、この地に郡司職や祭祀者として忌部氏の名はほとんど見られず、『先代旧事本紀』で「大伴直大瀧」が初めて国造に任じられたとする記録をはじめ、ここでも大伴一族が国造を担っていた。この房総半島で力を盛り返した源頼朝は、鎌倉入りをし、鶴岡八幡宮を守護神に位置付けるわけだが、鶴岡八幡宮の初代の神官は、大伴氏の伴忠国であり、その後、鶴岡八幡宮の神職は、明治維新まで大伴氏が世襲してきた。
京都で藤原氏との政争に敗れた大伴氏は、どうやら東国において、海人ネットワークを掌握し続けていたのではないかと思われる。さらに、源頼朝を支え続けた北条時政は、大伴家持が創建した富山の奈呉の放生津八幡宮を再興し、この神社の神職は、今日まで、大伴氏が世襲しているのだ。このように見て行くと、平安時代、朝廷内の権力争いで藤原氏によって葬られたかのように伝えられる大伴氏は、違うかたちで歴史の中を生き延びており、その影響力を行使した期間は、藤原氏よりも長いということになる。
私たちは、都の中心にいることが権力の中心にいることだと思いがちだが、それは城壁都市の発達した大陸の国にあてはまることで、城壁都市の発達しなかった日本という国は、ネットワーク型の世界だったのではないかと思われる。だから、日本の天皇は、中国の皇帝やヨーロッパの王のような絶対権力者ではなく、どちらかというと、各地を結ぶネットワークを機能させる祭祀の要にある権威的存在だ。そして、そのネットワークは、日本列島内を網の目のように張り巡っている川と海の交通が重要な鍵を握っていた。特に、潮の流れが読みにくく座礁もしやすい瀬戸内海や、荒れやすい日本海は、大陸との交流においても重要な場所でありながら、エンジンを持たない船で航海することは簡単でなかったはずで、その専門集団は、歴史的に大きな役割を果たし続けていたことは間違いない。
|
天平21年、東大寺に行幸した天皇は「三宝の奴」と称して「天平感宝元年」と改元し、同年皇太子・阿部内親王(孝謙天皇)に譲位して再び天平勝宝元年(749)と改元した。
6.21日、聖武太上天皇の七七日にあたり、光明皇太后、遺品を東大寺に施入し、また種々の薬を盧舎那仏に奉る。
| 758年、天武系でかつ天智系(持統系)でなく、母親も藤原氏の娘ではない淳仁天皇即位。 |
|
760(天平宝字4).6.7日、光明皇太后崩御(60歳、又は56歳)。「天平応真仁正(にんしょう)皇太后」。「続日本紀」皇后崩御の條には「東大寺、及び天下国分寺を創建する者は、本太后の勧むる所なり」とあり、光明皇后が聖武天皇に、東大寺及び国分寺の建立を勧められた可能性のあることを窺わせる。ちなみに法華寺の十一面観音像のモデルは皇后の光明子とも言われる。 |
| 藤原不比等の娘で聖武天皇の皇后となった光明子(こうみょうし)は、不比等の死後、その邸宅を「滅罪」と云う名の寺に改造している。ここで、ライ病患者を風呂に入れたり、貧しい人々に食事を提供している。現在の奈良県奈良市の法華時がそれである。 |
| 藤原不比等の娘で聖武天皇の皇后となった光明子(こうみょうし)は、不比等の死後、その邸宅を「滅罪」と云う名の寺に改造している。ここで、ライ病患者を風呂に入れたり、貧しい人々に食事を提供している。現在の奈良県奈良市の法華時がそれである。 |
756年、藤原仲麻呂に思惑により大炊王(おおいおう)に皇位を譲渡している。これを淳仁天皇と云う。藤原仲麻呂は、淳仁天皇から「恵美押勝」の名を貰い受ける。これに対して、孝謙上皇が道鏡を登用する。
756(天平勝宝8)年、聖武天皇は56歳で崩御し、佐保山南陵(さほやまのみなみのみささぎ)に葬られた。
| 46代、孝謙天皇の御世 |
757(天平字元).3.20日、聖武天皇と藤原不比等の娘・光明子の子供の後の称徳天皇が、聖武天皇の禅譲により即位、孝謙天皇となる。藤原仲麻呂は、叔母の光明皇后の信任を得て、大納言・紫微令・中衛大将に任じられるなど次第に台頭し、孝謙天皇が即位すると、孝謙と皇太后となった光明の権威を背景に事実上の最高権力者となった。3月、当時皇太子だった道祖王を廃位に追い込み、翌4月、ひそかに孝謙に勧めて息子真従の未亡人粟田諸姉と結婚して仲麻呂の私邸に居住していた大炊王を皇太子に立てることに成功する。
同7月、橘奈良麻呂らは道祖王らと共に謀叛を企てたとして芋づる式に捕らえられる。首謀者の処刑や流刑が行われ、400名に登る人々が処罰された。大伴の古麻呂が拷問死させられている。これを「橘奈良麻呂の変」と云う。
| 47代、淳仁天皇の御世 |
758(天平宝字2)年、大炊王(淳仁天皇)が即位する。藤原仲麻呂は大保(右大臣)に任ぜられ、恵美押勝(藤原恵美朝臣押勝)の姓名を与えられる。760(天平宝字4).1月、人臣として史上初の大師(太政大臣)に登りつめる。押勝は子弟や縁戚を次々に昇進させ要職に就けて勢力を扶植していった。
760(天平宝字4).6月、光明が死去。藤原仲麻呂の権勢はかげりを見せはじめる。
760(天平宝字4)年、淳仁天皇が、藤原不比等の功績を古代中国の諸侯・斉(せい)の太公(たいこう)になぞらえ、周朝が太公に対して為したように追贈として亡き藤原不比等を淡海公(あふみのきみ)に封じた。淡海とは近江国のことを云い、その12郡をもって封地とした。朝廷をして顕彰せしめた主導者は不比等の孫の仲麻呂であった。
| 【道鏡の登用】 |
|
761(天平宝字5)年、道鏡(どうきょう)が、平城宮改修のため都を一時近江国保良宮に移した際、病を患った孝謙上皇(後の称徳天皇)の傍に侍して看病して以来、その寵を受けることとなった。孝謙天皇に寵愛された理由として、平安時代以降の学者によって天皇と姦通していたとする説や巨根説などが唱えられ、日本霊異記や古事談など説話集の材料にされている。但し、具体的な史料には乏しい。こうした説が流布された背景には、称徳天皇が天武天皇系の皇統であり、称徳天皇没後、この系統が断絶して天智天皇系の皇統が復活した事から、天智天皇系の皇位継承を正当化するために天皇と道鏡を不当に貶めるために創作されたという指摘がある。 道鏡の台頭は藤原仲麻呂の勢威を殺ぐことになった。藤原仲麻呂は、淳仁を通じて孝謙に道鏡への寵愛を諌めさせたが、これがかえって孝謙を激怒させた。 |
| 【淳仁天皇と孝謙上皇が決定的に対立】 |
|
762(天平字6).5月、淳仁天皇と孝謙上皇が決定的に対立。6月、孝謙上皇は朝堂に五位以上の役人を集め、淳仁天皇を弾劾する宣明を読み上げる。「淳仁天皇には恭しく従う事はない。政治の小事は任せるが、国家の大事については、私が行う」。6月、孝謙は出家して尼になるとともに「天皇は恒例の祭祀などの小事を行え。国家の大事と賞罰は自分が行う」と宣言する。孝謙の道鏡への信任はしだいに深まり、逆に淳仁と押勝を抑圧するようになった。 |
763(天平宝字7).9月、道鏡が少僧都に任じられる。
| 【藤原仲麻呂の乱(恵美押勝の乱ともいう)】 |
|
764(天平宝字8).9月、太政大臣の藤原仲麻呂は「道鏡の朝廷に仕える様子を見ると、先祖の大臣として仕えていた過去の一族の栄光を取り戻そうとして躍起になっている故、排斥してしまえ」と述べ、軍事力により孝謙と道鏡に対抗し始めた。新設の「都督四畿内三関近江丹波播磨等国兵事使」に任じられた。諸国の兵20人を都に集めて訓練する規定になっていたが、600人の兵を動員するよう大外記高丘比良麻呂に命じた。都に兵力を集めて軍事力で政権を奪取しようと意図していた。この時、太政官印の確保に成功している。 孝謙は勅して、仲麻呂一族の位階・官職を奪い、藤原の氏姓の剥奪・全財産の没収を宣言した。さらに三関の固関を行わせている。その夜、仲麻呂は一族を率いて平城京を脱出、宇治へ入り、仲麻呂が長年国司を務め、彼の地盤となっていた近江国の国衙を目指した。孝謙は当時造東大寺司長官であった吉備真備を召して従三位に叙し仲麻呂誅伐を命じ、ただちに討伐軍が仲麻呂の後を追った。真備は仲麻呂のため久しく逆境にあった人物で、この年正月に70歳になっていたが、軍学の知識を買われた。 仲麻呂の行動を予測した真備は、山背守日下部子麻呂と衛門少尉佐伯伊多智の率いる官軍を先回りさせて勢多橋を焼いて、東山道への進路を塞いだ。仲麻呂はやむなく子息辛加知が国司になっている越前国に入り再起をはかろうとし、琵琶湖の湖西を越前に向い北進する。淳仁を連れ出せなかった仲麻呂は、自派の貴族中納言氷上塩焼(新田部親王の子)を同行して「今帝」と称して天皇に擁立し、自分の息子たちには親王の位階である三品を与えた。また、奪取した太政官印を使って太政官符を発給し、諸国に号令した。ここに、2つの朝廷ができたことになる。孝謙側は、仲麻呂を討ち取った者に厚い恩賞を約束するとともに、北陸道諸国には、太政官印のある文書を信用しないように通達している。 官軍の佐伯伊多智は越前に馳せ急ぎ、まだ事変を知らぬ辛加知を斬り、授刀舎人物部広成らに愛発関(近江と越前の国境の関所)を固めさせた。仲麻呂軍の先発隊精兵数十人が愛発関で敗れた。辛加知の死を知らない仲麻呂は愛発関を避け、舟で琵琶湖東岸に渡り越前に入ろうとするが、逆風で舟が難破しそうになり断念して、塩津に上陸し陸路、愛発関の突破をはかった。佐伯伊多智が防戦して、仲麻呂軍を撃退する。仲麻呂軍は退却して三尾(近江国高島郡)の古城に籠もった。討伐軍は三尾を攻めるが、仲麻呂軍は必死で応戦する。 9.18日、討伐軍に討賊将軍に任ぜられた備前守藤原蔵下麻呂の援軍が到着して、海陸から激しく攻めたので、ついに仲麻呂軍は敗れた。仲麻呂は湖上に舟を出して妻子とともに逃れようとするが、軍士石村石楯に斬られ、その一家も皆殺しにされた。塩焼も同時に殺されている。これを藤原仲麻呂の乱(恵美押勝の乱)と云う。(「ウィキペディア藤原仲麻呂の乱」参照) |
| 48代、称徳天皇の御世 |
仲麻呂の勢力は政界から一掃され、淳仁は廃位され淡路国に流された。代わって孝謙が重祚する(称徳天皇)。以後、称徳と道鏡を中心とした独裁政権が形成されることになった。
道鏡が太政大臣禅師に任ぜられた。翌年には法王となり、仏教の理念に基づいた政策を推進した。道鏡が関与した政策は仏教関係の政策が中心であったとされているが、彼の後ろ盾を受けて弟の浄人は8年間で従二位大納言にまで昇進し、一門で五位以上の者は10人に達した。これが藤原氏等の不満を高め確執することになる。
| 【称徳天皇発願で「西大寺」、「西隆寺」の建立始まる】 |
| 765(天平神護元)年、奈良時代後半の称徳天皇(孝謙天皇、718~70年)の発願で、平城京の宮域(平城宮、奈良市)のすぐ西側で「西大寺」の造営が始まった。父の聖武天皇が平城京の東郊に創建した「東大寺」に対し、「西のおおでら」として知られる。外国からの知識や技術を取り入れたそれまでにない伽藍(がらん)が展開されていた。同様に尼寺「西隆寺」が称徳天皇の発願で西大寺の隣に造営された(その後、廃絶)。「寵愛(ちょうあい)する僧の道鏡を重用し、二度即位するなど個性的な女帝が営んだ寺院」として知られる。 称徳天皇は、道鏡が権勢を強めていく中で起きた藤原仲麻呂(恵美押勝=えみのおしかつ)の乱(764年)の平定を祈願し、鎮護国家の守護神とされる四天王像を造立することなどを誓願。それに勝利したことで西大寺の造営が決まった、という。奈良時代の財産目録「西大寺資財流記帳」(しざいるきちょう)(資財帳)によると、創建時の西大寺は寺域が約48ヘクタール。中心伽藍は「院」で区画され、薬師・弥勒両金堂のある「金堂院」、東西の塔が並ぶ「塔院」、四王院、食堂(じきどう)院、十一面堂院、政所院などで構成されていた。平城京内では興福寺や薬師寺を上回る最大規模の寺院だったが、平安時代に著しく衰退。鎌倉時代に戒律復興に尽くした叡尊が入って再興した。現在の寺域は、鎌倉時代のものがベースになっているという。 |
| 【宇佐八幡宮神託事件】 | |||
| 769()年、大宰府の主神であった習宜阿曾麻呂は、豊前国(大分県)の宇佐神宮より天皇の位を道鏡に譲れとの神託があったと道鏡に伝え、道鏡はこれを信じて皇位に就く志を抱く。これに対し、称徳天皇は、神意を確かめるために信任の厚い法均尼を宇佐へ下がらせようとしたが、病身であったので、代わりにその弟の和気清麻呂を勅使として参向させた。 これにつき次のように疑問されている。
宇佐から帰った清麻呂は、「皇位には皇統の人を就けよ」という全く反対の内容を神意として言上した。称徳天皇は「嘘を申した」と激怒され、清麻呂を大隅に追放した。この遣り取りで、道鏡が皇位に就くことができなかった(宇佐八幡宮神託事件)。 この事件の背景として、称徳天皇が、天皇を傀儡にして支配する藤原氏に嫌気がさし、反藤原勢力の後継者として道鏡を重用していたことにある。これを権力基盤の危機と受け取った藤原百川が謀略を開始した。まず、道鏡の弟を誘惑して、「道鏡を皇位に就けよ」という[最初の神託]を出させた。すぐに乗って来れば、「皇位奪取の意志有り」として処罰するワナであったが失敗した.。そこで二の矢として、[和気清麻呂]に神託の偽造を命じた。神託により道鏡への譲位を阻んだ。
ある夜、百川の館に泊まった女帝は、激しい腹痛に見舞われた。道鏡は、女帝が倒れてから100日あまり、度々訪れ治療を申し出るが門前払いを食らい、そのまま称徳天皇は崩御した。道鏡は、戒律の指導的立場を持つ日本三戒壇の一つ、下野薬師寺に左遷された。 百川は、称徳天皇の姉・甥にあたる井上内親王母子を[光仁天皇呪詛事件]の捏造により失脚させ、新たな[皇太子]を立てた。 熊本市にある弓削神社には「道鏡が失脚した後この地を訪れて、そこで藤子姫という妖艶華麗な女性を見初めて夫婦となり、藤子姫の献身的なもてなしと交合よろしきをもって、あの大淫蕩をもって知られる道鏡法師がよき夫として安穏な日々を過ごした」との俗話がある。 |
|||
| 日本三大悪人・弓削道鏡の汚名を晴らすサイト http://www.kawachi.zaq.ne.jp/ishii/doukyou.htm 今日の…「道鏡事件と桓武天皇」のはなし http://ameblo.jp/eiichi-k/theme2-10013483725.html#main 朱雀の洛中日記 弓削道鏡 http://suzaku62.blog.eonet.jp/default/2010/01/post-00b1.html 道鏡の真実 http://www.melma.com/backnumber_136539_2241164/ もう一つの神託「道鏡」事件 http://www.ten-f.com/doukYoujiken.html 道鏡って悪い人だったんですか? http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1048394595 闇に葬られた皇族(1) ー 井上内親王 http://miburo.blog6.fc2.com/blog-entry-449.html 井上内親王 他戸親王 http://sendo.fc2web.com/flame01/katudoukiroku/igaminaisinnnou/ gojousi.htm まんがで見る五條市史 井上内親王 編 http://www.gojo.ne.jp/yamayoh/manga/ig1.htm |
|||
|
和気清麻呂(わけのきよまろ、733-799)が、奈良の仏教を嫌い、山岳修行の道場として高雄に開山したのが高雄山寺。息子の真綱(まつな)らが、父の遺志を継ぎ、空海さんや最澄さんを招き、新仏教を試みる中で整え、再スタート(824)させたのが神護寺。紅葉に彩られた大伽藍は、この時期の高雄の一番人気。北山杉の美しさも見逃せない。 |
770(神護景雲4)年、称徳天皇が病死する。
| 49代、光仁天皇の御世 |
770(神護景雲4)年、称徳天皇崩御により、光仁天皇が即位する。光仁天皇は聖武の第一皇女・井上内親王(いのえのひめみこ)の夫(婿)であり、称徳女帝崩御による天武-聖武直系皇統の嫡流断絶を受けて推戴された。
| 光仁天皇は皇位を手中にすると、井上内親王とその子の他戸親王(おさべのみこ)が光仁天皇を呪詛したとして皇后・皇太子を廃嫡し、異母系の山部親王(やまべのみこ、後の桓武天皇)を皇太子に指名した。二人は大和国の没官の邸に幽閉され、翌々年、幽閉先で同日に薨去した(続日本紀)。これは、100年ほど続いた天武天皇系の皇統が廃されて天智天皇系皇統に戻ったことを意味する。いわゆる皇統交替であり、いわば宮廷革命に他ならない。 |
| 【道鏡逝去】 | |
道鏡は葬礼の後も僥倖を頼み称徳天皇の御陵を守った。同年8.21日、造下野薬師寺別当(下野国)を命ぜられて下向し、赴任地の下野国で没した。龍興寺(栃木県下野市)境内に道鏡の墓と伝えられる塚がある。「道鏡を守る会」が墓所に設置した掲示板には次のように記されている。
|
772(宝亀3).5.13日、道鏡死去の報が下野国から光仁天皇に言上された。道鏡は長年の功労により刑罰を科されることはなかったが、親族(弓削浄人とその息子広方、広田、広津)4名が捕えられて土佐国に配流された(続日本紀)。
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)