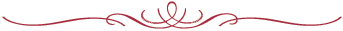
| 役行者考前知識 |
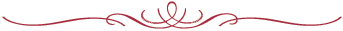
(最新見直し2008.7.24日)
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここで、役行者考に入る前の予備知識として、日本神道のついて考察しておくことにする。 2008.7.24日 れんだいこ拝 |
| Re:れんだいこのカンテラ時評420 | れんだいこ | 2008/07/24 |
| 【れんだいこの役行者論予備知識、日本式古神道の秀逸考その1、神道とは】 「れんだいこの役行者論」は、日本式古神道の秀逸性を語るところから始まる。関係ないと思う勿れ。これから追々明らかにしていくが、これにより新たな役行者像が生まれることになるだろう。 世界の宗教圏識別によれば、日本は仏教国と云われる。間違いではないのだが、れんだいこはこの捉え方に若干の異議を持っている。日本は仏教国ではあるが、実のところは日本はその前に世界に誇るべき世にも稀な神道国として自己形成していたのではなかろうか。 もう10年ほど前になるだろうか。森首相が「神の国」発言した。これにマスコミと左派、サヨ陣営が批判のボルテージを上げた。どういうセンテンスの「神の国発言」であったか忘れたのでなんとも云いようがないが、れんだいこが思うに、これはマスコミと左派、サヨ陣営の方が分が悪いのではなかろうか。日本史の底流を見ずに、幕末以来の西欧史観に呑み込まれた挙句、さほどメクジラするほどのことでもない批判の為の批判をしたに過ぎない。れんだいこは、あの当時も今もそう思っている。 今日、仏教も神道も日本社会にすっかり根づいている。だから日本を仏教国と見なして差し支えはない。だが、詳細に見ると、神道の方こそ真に底流で根づいているのではなかろうか。神道の発展バージョン系として仏教、道教、儒教その他諸々が取り入れられているのではなかろうかと思っている。 これを過度に心酔すれば日本国粋主義になるのだろうが、根拠がない訳ではないと思う。排外主義的な国粋主義を除いて日本耽美浪漫主義に転換させれば、「神の国発言」はあながち的外れではあるまい。但し、この場合、日本国、日本神道のどこをもって評価するのかが肝腎だろう。これについては後述する。 現代日本はこれら東洋系思想の切磋琢磨とは別に既に西欧的なキリスト教、ユダヤ教、イスラム教の各派を抱えている。日本神道がありながらこれを知る事もなく、西欧宗教を受容した者に於いては、日本社会に伝統的に根づいている神道的精神、価値基準は幼稚なものに見えたのであろう。 しかし、れんだいこは逆に考えている。日本神道の方こそ本来最も優れた思想ないしは宗教ではなかろうか。日本神道には、世界の四大宗教の如くな精緻な教義、経典がどうやら意図的なようであるのだが、ない。故に、何か劣等なもののように受け止められているのだろうか、日本人自身が日本神道を世界に冠たるものとして位置づけ称揚しようとしない。実にそういう在り方が神道的なのではあるが。 かといって、日本神道の真価を貶めるのは大いなる誤りではなかろうか。日本神道に教典がないのは、ないことにより却って教条主義から解放されると云う功の面がある。これによりいつでも情況即応的な開放的柔構造になっている。この功をも知るべきではなかろうか。れんだいこはそのように捉えている。 今後、日本社会の精神界は、近現代史の主潮である国際金融資本の植民地化政策及びそのイデーとバッティングし、日本神道を廻るせめぎあい時代を迎えるかも知れない。そんな予感がする。こうした時代にあっては特に、在来の伝統的精神、価値基準、日本神道、日本精神を学んでおき且つ重んじたいと思う。 2008.7.24日 れんだいこ拝 |
||
| Re:れんだいこのカンテラ時評421 | れんだいこ | 2008/07/25 |
| 【れんだいこの役行者論予備知識、日本式古神道の秀逸考その2、神道と仏教の関係】 日本への仏教伝来は、6世紀頃の蘇我氏の台頭時代に始まった。聖徳太子がこれに関わり推進派として活躍した。蘇我氏が渡来氏族なのか、高天原王朝天孫系なのか出雲王朝国津神系なのか分からない。ただ深く韓国ルートと絡んでいるのは間違いない。 この時期、仏教の受容を廻って伝統的神道派の物部氏派と革新的仏教派の蘇我氏派が大いに争い、最終的に仏教派が勝利し、物部氏派の主流は壊滅させられ叉は逃亡を余儀なくされ地下に潜ったことは衆知の通りである。こうして、天皇家は、「上からの革命」式にそれまでの神道とは別に新たに仏教的祭祀制を取り入れ、全国各地に積極的に寺院建立に向かう等手厚く保護し、氏族系神社と拮抗させ、仏教国日本の創建に向かった。これを仮に「国策仏教」と命名する。 しかし、このことを知ることは単なる知識であり、問題は仏教の受容の仕方され方に対する認識の方にこそある。仏教の伝来、普及により神道が滅びたのではない。政治の表向きを仏教が、裏向きを神道が司るようになると云うイニシアチブの交替が起こったが、そういう体裁で両者が鼎立共存したことにこそ嗅ぎ取るべき意味があるのではなかろうか。そうなると、世界史的に見ればかなり珍しい「仏教と神道の鼎立共存」は何ゆえにもたらされたのであろうか、ここが問われねばならない。 結論的に述べると、れんだいこは、先行して存在していた神道の方の優秀性こそがキーワードではないかと考えている。これは丁度、言語学も同じで、漢字の輸入にも拘らず原日本語は滅びず、否むしろ原日本語の方が漢字を咀嚼吸収し、その結果平仮名、カタカナを創造し、新たなる日本語を創造していった例に似ていると考えている。してみれば、注目すべきは、日本語同様に在来文化及び精神としての神道の共生能力及び器量の広さの方ではなかろうか。 仏教もまた共生能力及び器量の広さを有していた故に併存が可能になったのであろう。少なくとも、神道と仏教は鼎立共存できる関係を互いが持っていた。こういう観点を持ちたい。両者のこの共生構造が、国策仏教を次第に大衆仏教へと生育させていくことになる。それは同時に仏教の土着化であり、神道との混淆化の道のりでもあった。即ち日本仏教化であり、これは極めて日本的現象であった、そう考えるべきではなかろうか。 この竿頭に立ち、仏教の真髄を的確無比に捉え、それを日本神道と格闘させ、これを取り込み練り合わせる形で日本仏教化の先鞭を付けたのが役行者であり、その意味で特筆に価するのではなかろうか。結果的に汎神論的神仏習合が編み出されたが、この役行者式神仏習合がその後の日本仏教の在り方を定式化させた。最澄も空海もこの路線に沿って日本仏教化を促進させた気配が認められる。その後の法然、親鸞、日蓮、道元、栄西その他然りとすれば、元一日を打ったてた役行者の果たした役割は大きいと認めるべきではなかろうか。 日本文化は練りの文化ないしは発酵文化だと云われる。そのことは、日本宗教史の中にも見て取れる。れんだいこはそのように考えている。この柔軟な仕組みが、仏教受容の時にも働いたと受け止めている。国策的に導入された仏教がやがて日本社会に根づき、今度は神道と仏教が共存的に併存する道を見つけていくことになった。これにより日本は仏教国と云われるようになっているが、注目すべきは、日本語同様に在来文化及び精神としての神道の共生能力及び器量の広さの方ではなかろうか、ということになる。 だが、これは自然にそうなるのではない。何事も、時代のテーマを嗅ぎ取った能力者が死に物狂いの格闘の末に活路を見出し、これが伝授受容されることにより新たな発酵文化が形成すると云う経緯を見せる。役行者は、宗教史の面でこれに取り組み為し遂げた稀有の超能力者であった。かく観点を据えたい。 補足すれば、日本神道が唯一相容れないものがあるとしたら、史上いわゆるユダヤ教と呼ばれる、特にネオシオニズム系の選民主義思想ではなかろうか。そのネオシオニズムの襲来が著しい今、日本史上初の未曾有の椿事が起こっている。明治維新以来、欧化知識人が、この思想史的意味を弁えぬままネオシオニズムの尖兵としてあるいは御用聞きとして立ち回ってきている姿はあさましい。 彼らは本質的に低脳インテリなのではなかろうか。故に何を遣らせても上手く漕げない。ただひたすら気難しく語り、徒に規制に夢中になり、権利病に侵され、何食わぬ顔で利権にありつき、仮に口先で良きことを云っても裏では利権に手を突っ込んでいる。総じて虚学派であり無責任を習性とする。この連中を大目に見ながら結果的に円く治めてきたのが伝統的な実学派のインテリであった。そろそろ我慢にも限界はあろうが。こういう観点を持ちたい。 2008.7.25日 れんだいこ拝 |
||
| Re:れんだいこのカンテラ時評422 | れんだいこ | 2008/07/25 |
| 【れんだいこの役行者論予備知識、日本式古神道の秀逸考その3、伊勢神道と出雲神道の関係】 上述で日本神道が如何に優れているか、その構造の柔軟性について記したが、未だ漠然と結論的に指摘したに過ぎない。もう少し細部に立ち入って確認してみる必要がある。日本神道は内部で自己変革を遂げており、興味深いことに、神道と仏教の共生関係と同様なものが既に神道内部で経験されていたという史実がある。 これを分かり易く確認すれば、後に伊勢神道として結実する新神道と出雲神道に結実した古神道の関係にも共生関係が見て取れるということである。両者を神道と云う名目で一括りするならば、神道は多重構造ということになる。これを別物として見るならば、伊勢神道と出雲神道双方の共生能力及び器量の広さ問題になる。 現代の自称インテリ達が一口に神道と云う時、そういう風に教育されてきたからでしかないのだが、決まって伊勢神道を指している。ここで止まっており、出雲神道には目もくれないと云うか記紀神話の記述をそのまま鵜呑みにして邪教扱い叉は顧慮しない。 彼らは、明治維新以来の天皇制を眼前に置いて、その王朝系譜を古代まで遡り大和王朝まで辿り着く。大和王朝は、高天原王朝譚、国譲り譚、神武東征譚と続いて創建に辿り着く。この歴史を正統御用化し、先行して存在していた出雲王朝の古神道をも一部ミックスしながら新神道を創ったのが、いわゆる伊勢神道である。 明治維新以降の自称インテリ達は、御用系も批判系もここを始発としており、それ以前を顧みない。これを仮に「新神道」叉は「伊勢神道」叉は「弥生神道」叉は「天皇制神道」と命名する。ここでは「伊勢神道」と表記することにする。これが一般に認識されている神道であり流布されている神道である。 付言すれば、左翼は、この伊勢神道を批判して神道問題を解決したかの手前味噌に陥っている。記紀神話的天地創造譚の荒唐無稽性、皇統譜の連綿性、八紘一宇観、神州不滅観を批判なり否定して事足れりとする習性がある。しかし、その程度の批判は子供騙しの類いでしかない。 史実はもっと奥行きが深い。伊勢神道以前に、古代日本には既にれっきとした出雲神道が先行的に確立されていた。ここに着目しないと古代史の秘密の扉が開かない。その出雲神道を遡れば更に先行的に縄文神道が形成されており、これを更に遡ればアイヌ神道まで辿り着く。これを仮に「古神道」叉は「出雲神道」叉は「縄文神道」叉は「部族連合制氏族神道」と命名する。ここでは「古神道」と表記する事にする。 神道と云うとき、この流れを押えなければ正しい理解にならない。かく構図を構えなければ神道問題の入り口を潜れない。左翼が、神道問題に対して理論的に解決済みと嘯くなら、この古神道まで視野に入れて批判せねばならない。果たしてうまくできるだろうか。察するに、伊勢神道以前の神道は仮にあったにせよアニミズム段階のものであり、論評するに足らないとでも云うのだろう。その言で納得できるものは幸せであるが、れんだいこのように納得できない者も現に存在する。 れんだいこの見立てるところ、日本神道は、古神道と新神道である伊勢神道が綾なしてきた多重構造的生成発展型宗教である。日本神道を理解せんとするならば、この軟構造を無視しては神道の何たるかが理解できない。世上の神道認識はこの点で大雑把過ぎており、学問的に堪えられない。「神道の共生能力及び器量の広さ」を云うとき、このことを認識していなくては全く役に立たない。 付言すれば、日本神道の構造式は世界に誇る開放系教説の宗教であり、行き詰まることがないと云うすぐれものとなっている。対照的に、ユダヤ−キリスト教的教義は一見精緻に見えるが、完結系の為に却って危ない。論の前提が崩れれば収拾が尽かない。現在、地球環境問題がクローズアップされつつあるが、ユダヤ−キリスト教的教義に基く「神言による自然支配命令」の結果であり、その論理の破綻であろう。日本神道は、その他の良質的な宗教も然りであるが、支配と云う概念を持ち込まない。むしろ、諸氏族、民族間の共生は無論のこと、自然摂理、環境との共生をも指針させている点で、例えアニミズムと云われようともむしろ奥が深いと云うべきではなかろうか。 |
||
| Re:れんだいこのカンテラ時評423 | れんだいこ | 2008/07/25 |
| 【れんだいこの役行者論予備知識、日本式古神道の秀逸考その4、日本神道の多重構造、三極構造考】 もとへ。そういう訳で、日本神道の何たるかを知る為には古神道にまで至らねばその秘密が解けない。こうなると必然的に日本神道の原基としてのアイヌ神道こそが探られるに値する事になる。但し、河川の上流を尋ねれば源流はとある地点の一滴の水に過ぎなかった例に似てアイヌ神道はアイヌ神道として形成されている訳ではない。否形成されていたのかも知れないが文書としては残されていない為に口伝に拠るしか捉えようがない。その口伝も断片的なものしか残されていない。故に、アイヌ神道なるものを無理矢理に想定して確認しようとしても無為に終わってしまう。 と云う訳で、神道を知るためには、はるけきアイヌ神道から縄文神道、縄文神道から出雲神道までの長い道のりの間に発酵醸造形成された古神道を知らねばならない。その古神道の精華が出雲神道であり、伊勢神道が伝来してきた時既に在来土着系の氏族宗教が生まれており、その氏族宗教の連合型宗教の粋として国津神系王朝御用神道即ち出雲神道として確立されていた。このことが確認されねばならない。 この出雲神道の内実を問うと紙数を増やすばかりなので、別途「出雲神道考」で確認する。(ttp://www.marino.ne.jp/~rendaico/rekishi/nihonshinwaco/izumoootyoco/izumotaisyaco.htm) 驚くことに、出雲神道の智恵は今日なお連綿と日本精神の根底に息づいていることが確認できよう。早い話が、各種各様の神事、地鎮祭、厄除け、正月初詣で、七五三、神前結婚式、奉納相撲、奉納芸能等々がこれ皆な出雲神道時代に確立されていた儀式である。 その出雲神道は、古代史上の最大政変である国譲りにより、「記紀神話」説話によれば主流の大国主系が幽界に隠れることになり、裏世界即ち非政治的宗教的世界でのみ活動が許容されると云う手打ちで生き延びることとなった。これにより、表舞台としての神道を渡来系の高天原王朝御用神道即ち伊勢神道が支配し、国譲りの際に功のあった出雲神道の事代主系が伊勢神道を補完するという体裁で三者が共存的に棲み分けすることになった。この構図が確認されなければ古代史の流れが読めない。 冒頭の話に戻るが、「神道の共生能力及び器量の広さ」がここで確認できる。古代史上最大政変である国譲りにより登場した伊勢神道は、先行する出雲神道を駆逐できず、結果的にむしろ共生共存した。あるいは共生共存的新神道を醸造したと見なすべきかも知れない。 ここで問われねばならないことがある。伊勢神道はなぜ、世界の諸文明勃興史の如くに先行する出雲神道を一掃駆逐できなかったのか。ここに日本史の秘密がある、とれんだいこは考える。それは、アイヌ神道から発する縄文神道、出雲神道が偏に有能であり、天地自然の理に叶っていたから否定しようにもしきれなかったと云わざるを得ない。 つまり、潰すに潰されず、それをうまく利用した方が賢明と云う裏事情があったのではなかろうかと考える。これを逆に云えば、先行する文明がそれほど優秀であったと考える。それを許容した伊勢神道も共生的であったということにもなろう。 2008.7.25日 れんだいこ拝 |
||
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)