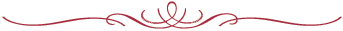
| 修験道の歩み |
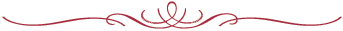
更新日/2020(平成31→5.1栄和改元/栄和2).9.7日
| 【役行者昇天後の修験道の歩み】 |
| 役行者の入寂によって修験道は滅びなかった。役行者を慕い続く山伏が続々列なりますます盛んになり、吉野、熊野を拠点とする金峯山寺(きんぷせんじ)を主霊場として参集するようになった。この当時は、仏教派ばかりではなく、道教的な神仙術派、日本古神道派も修業していた。 |
| 【行基の修験道活動】 |
| 奈良時代の名僧として知られる行基(668-749.2.27日)が役行者と深く関っている。これを確認する。681年に出家し、官大寺で法相宗などの教学を学び、集団を形成して関西地方を中心に貧民救済・治水・架橋などの社会事業に活動した。704年、生家を家原寺として居住した。 ところが、民衆を煽動する人物であり寺外の活動が「僧尼令」に違反するとし、養老元年.4.23日詔をもって糾弾されて弾圧を受けた。731(天平3)年、禁圧が緩まり、741(天平13).3月、聖武天皇が直々に会見し、同15年、東大寺の大仏造造営の勧進に起用されている。745(天平17)年、朝廷より日本最初の大僧正の位を贈られた。 日本全国には、行基が発見したとされる温泉が数多くある。ただし、これらの中には開湯伝説を作った際に名前が使われただけのものもあるとされる。めぼしいところは次の通りである。作並温泉、東山温泉、芦ノ牧温泉、草津温泉、藪塚温泉、野沢温泉、渋温泉、湯田中温泉、山代温泉、山中温泉、吉奈温泉、谷津温泉、蓮台寺温泉、三谷温泉、木津温泉、関金温泉、塩江温泉。他にも、有馬温泉、湯河原温泉などにも行基にまつわる伝承が残っている。 この行基が、役行者修験道を行じ、役行者が山上蔵王堂を建立したのに対し、下山の吉野の蔵王堂に三世三体の蔵王を造り安置したと伝えられている。金峯山寺の寺伝では、山下蔵王堂は役行者が開基し、行基が増修したとされている。 |
| 【道鏡の修験道活動】 |
| 道鏡(700-772.5.13日)も然り。物部氏の一族の弓削氏の出自で、俗姓が弓削連であることから、弓削道鏡(ゆげのどうきょう)とも呼ばれる。奈良時代の法相宗の僧で、葛城山に篭り、苦修練行の末に密教的宿曜秘法を習得したとも云われる。 |
| 【平安時代、密教と習合】 |
| 平安時代に入ると、唐から帰朝した空海(弘法大師、真言宗開祖、比叡山)、最澄(伝教大師、天台宗開祖、高野山)の日本仏教上の二大開祖が出現し、即身成仏と鎮護国家の二面から日本仏教を開花せしめていく事になる。空海も最澄も修験道と深く関わり、山岳仏教を護持した。 空海(774-835)は、讃岐国の出身で、青年期に阿波の大滝岳、土佐の室戸岬、入唐前の791(延暦10)から数年間、大和の金峯山で修行し、さらに勤操の下で虚空蔵求聞待法を修得する。31歳で入唐し、恵果から密教の潅頂を受け、秘法を授けられて帰国する。816(弘仁7)年、高野山を開く。823(弘仁14)年、東寺を勅賜される。この間、真言宗を創始し、その教義を真言密教(東密)と云う。 最澄(767-822)は、近江国の帰化人を祖としており、入唐して天台の付法を受け、帰国後、比叡山で天台宗を興した。818(弘仁9)年、「山家学生式」を定め、比叡山の大乗戒の受戒者に12年間の籠山修行をさせた。空海から密教を学び、弟子の円仁(794-864)を入唐させ密教を習得させた。この天台密教(天密)はその後、義真の弟子・円珍(814-891)により確立される。教内が次第に円仁派と円珍派に分かれてきたところから、円珍は再興させた旧大友氏の氏寺であった円城寺(三井寺)に移り、寺門派を樹立する。 帰朝した空海、最澄は密教を持ち帰り、大日如来思想、金剛界・胎蔵界の曼荼羅思想(両界曼荼羅教)を導入した。曼荼羅は宇宙そのものを大日如来の圏域として捉え、これにより吉野から熊野に至る大峯山系の吉野側が金剛界曼荼羅、熊野側が胎蔵界曼荼羅になぞられることになった。 |
| 【平安時代、修験神道】 |
| 役行者式修験道が仏教系密教修験道化して行った他方で、神道系修験道化も始まる。大神大社信仰周辺に三輪流修験神道が生まれ、伊勢神宮信仰周辺に両部修験神道(御法流神道)が派生する。 |
| 「美濃禅定道〜修験の道〜」。
『白山長瀧寺』の裏山からは、一般の登拝道とは異なる、修験者が【行を行う為の登拝道】があり、【長滝十宿】と呼ばれた。今でも裏山には『一の宿』、『ニの宿』、『三の宿』跡があり、境内にはその当時の面影を残す跡地や、お堂が残されていました。(鎮座地:白山長瀧寺/長滝白山神社境内) |
| 【修験道に対する規制】 | |||||
| 修験道に対する規制も頻繁に出されている。これを確認しておく。 702(大宝2)年、大宝律令が制定され、僧尼令は、吉凶を占ったり、「小道巫術(ふじゅつ)」にを用いて治病したり、妄りに罪禍を説く僧尼を還俗させるとしている。 元正紀の717(養老元).4月、次のように詔したている。(「優婆塞役小角」参照)
この間、大和朝廷は度々禁止令を発布している。元正紀によると、718(養老2).9月、太政官が僧綱に対して次のように告示している。(「優婆塞役小角」)
720年、仏教本来の教えから外れて勝手に法を編み出す事を禁ずる。 聖武紀の729(神亀6、天平元).4月、次のように詔した。(「優婆塞役小角」参照)
833(天長10)年、令義解の僧尼令の禅行条に、山居をする僧尼の規定が示されている。それによると、僧尼は朝廷の厳重な統制下に置かれ、山林修行は奨励されたものの、官の許可が必要であり、修行の場を自由に変更することができなかったことが判明する。 |
| 【平安時代、末法思想、浄土信仰と習合】 |
| 平安時代中期、源信(942-1017)の「往生要集」が著された。この頃、1052(永承7)年から末法に入るとされ、浄土信仰が盛んになった。浄土に往生して弥勒下生を待つ弥勒信仰が盛んになった。吉野の金峯山が弥勒下生の地とされ、吉野参りが盛んになった。 修験道も含む日本仏教は、末法思想、浄土信仰などを更に融合させて行き弥勒菩薩教義を生み出し、平安時代末までに体系化されることになる。修験道は次第に、神道的な鎮魂帰神、道教的な修法、方術、仏教の密教的な加持祈祷術を編み出し、薬草医学、鉱山学、温泉湯治学等をも生み出していった。 修験者はこれらを身につけることにより、除災招福、怨霊退散等々衆生の要請するままに霊能を使い身すぎ世すぎとするようになった。 峰入り修行を終えた修験者は、峰中で獲得した験力を示すために火渡り、刃渡り、護法や動物霊を操作するなどの験術を行った。これを「験競べ(けんくらべ)」と云う。羽黒山の烏とび、吉野の蛙飛びなどがその例である。またその験力を用いて小祠の祭、加持祈祷、卜占、巫術、調伏、憑きものおとしなどの多様な現世利益的活動を行っていくことにもなった。 |
| 【皇家、尊顕の参詣】 |
| 平安時代に入ると、皇族、貴族などの金峯山参詣が相次いだ。900(昌泰3)年、905(延喜5)年の宇多法皇。1007(寛弘4)年の関白の藤原道長。藤原道長は、自ら筆写した法華経三部経、阿弥陀経、弥勒経などを金剛蔵王権現に献じ、山上の蔵王堂付近に金峰山経塚を造営した。日本最古の経塚として知られている。1049(永承4)年の関白左大臣の藤原頼通、1088(寛治2)年、1090(寛治4)年の関白左大臣の藤原師通、1092(寛治6)年の白河上皇などがいる。この時、左大弁・大江匡房らが随行している。 |
| 【当山派と本山派に分流する】 |
| 平安末期、修験道は二派に統制されるようになった。熊野側では本山派が形成された。天台宗系で、園城寺(三井寺)の智證大師・円珍(814-891、天台の第5代座主)を開祖とする。これが三井修験道の始まりとなる。総本山は天台宗寺門派(園城寺傘下)の聖護院(京都市左京区)である。本山派は、熊野から大峯へ入るを通例とし、これを順峰と云う。「伊勢へ七たび 熊野へ三たび 愛宕まいりは月まいり」と言われるほど、熊野詣は盛んになった。 これに対し、吉野の大峰山の金峯を主要な修行場として当山派が形成された。金峯山の奥に位置する小笹に拠点を置く。真言宗系で、理源大師・聖宝(832-909)を開祖とする。聖宝は、天智天皇の皇子・施基(しき)王の子孫である。総本山は聖宝が創建した醍醐寺三宝院(京都市伏見区)であった。当山派は、大峯から熊野へ入るのを通例とする。これを逆峯と云う。 聖宝は、宇多天皇の勅令により長らく廃れていた役行者修行の旧跡を再興して修験道を大いに鼓吹した。金峯山寺は山上・山下に多くの子院をもち、多くの僧兵(吉野大衆と呼ばれた)を抱え、その勢力は南都北嶺(興福寺と延暦寺の僧兵を指す)にも劣らないといわれた。 このほかに全国各地の例えば羽黒山、日光、白山、立山、富士、木曾御岳、伯き大山、石鎚山、彦山などでも修験グループが生まれ全国に群居した。 このニ派が主流で、地方的組織として備前児島の五流滝尊院、出羽三山、日光ニ荒山、彦山などをはじめとして霊山と呼ばれている全国各所で修験道の各派が生まれた。 |
| 奈良県大和郡山市にある真言宗醍醐派「大和松尾寺(やまとまつおでら)」。松尾寺は養老2年(718)に、舎人親王(とねりしんのう)が日本書紀の完成と、自らの42歳の厄除けを祈願するために創建したと伝わり、厄除けの寺としては日本最古と言われている。例年「松尾山修験道まつり・柴燈大護摩奉修行」が日本最古の厄除霊場・松尾寺で行われる。本堂の御本尊は千手観音(厄除観音)。 |
| 【南北朝時代】 |
| 南北朝時代、後醍醐天皇が吉野に移り、南朝を興した。南朝政権は金峯・大峯・能野一帯に立て籠った。北朝との間にしばしば山岳戦が繰り返され、そのため修験者もこれに動員され、劣勢な南朝側に立って活躍した。南北朝時代を経て山伏の活動は一段とさかんになり、修験道の組織化が進んだ。この頃、「役行者俵末秘蔵記」、「役君形生記(えんくんぎようしようき)」、「役行者講私記」、「役行者本記」をはじめ、役行者に関する数々の書が修験道の教典として作られている。 |
| 【室町時代】 |
| 修験道は、室町時代末になって、定式化された教義、儀礼、組織を持つ教団として確立された。修験道の遥拝する全国各地の霊山の縁起が作られ、起源、開山の伝承、山中の霊所などが整備された。 |
| 【戦国時代】 |
| 現存する本堂の蔵王堂は、1592(天正20)年頃に再建されており、重層入母屋造りの桧皮葺きの建物で国宝になっている。東大寺大仏殿に次いで大きい木造の大建築物檜で、皮葺の建物としては世界一の大きさを誇る。秘仏本尊・金剛蔵王権現が3体安置されているほか、多くの尊像がある。堂内は自然木をそのまま使った柱が68本林立していて豪壮。金箔張りの化粧柱や須弥壇は豊臣秀吉が吉野の花見の際に寄進したものといわれ、桃山建築の美しさを伝えている。 |
| 【徳川政権の修験道法度】 |
| 1603(慶長8)年に刊行された「日葡辞書」には、「五鬼。役の行者という名前のある山伏が打ち負かし服従させた五匹の悪鬼」とある。 1613(慶長18)年、幕府は広くは宗教統制、直接的には修験道統対策として修験道法度を定め、諸国の修験者を聖護院を本山とする本山派と醍醐三宝院が統括した当山十二正大先達衆を中核とする当山派の両派に分属させた。この段階で、役行者の修験道の開祖という地位が確定した。 1614(慶長19)年、徳川家康の命により、天台宗の僧である天海(江戸・寛永寺などの開山)が金峯山寺の学頭になり、金峯山は天台宗(日光輪王寺)の傘下に置かれることとなった。 |
| 【真言宗醍醐派別格本山/龍泉寺再建】 |
| 1711-16(正徳年間)年、時の住職・英尊が、聖護院、三宝院、当山十二先達、本山二十七先達の協力を得て、真言宗醍醐派別格本山である洞川(どろがわ)の里にある龍泉寺を再建した。 |
| 【登拝講の隆盛】 |
| 江戸中期の頃、大峯山、出羽三山、富士山、木曾御岳、英彦山などで庶民の登拝講が輩出し、盛行し始めた。 |
| 【役行者の復権】 |
| 役行者が国難期に復活する。 1799(寛政11)年正月、役氏正統の聖護院宮盈仁親王が、光格天皇へ役行者御遠忌(没後)1100年を迎えることを上表した。同年、正月25日、光格天皇は、烏丸大納言を勅使として聖護院に遣わして、役行者の偉大な功績を称賛し、「神変大菩薩(じんべんだいぼさつ)」の諡を贈った。菩薩とは、上求菩提下化衆生の菩薩道を実践し、六波羅蜜行、自利利他円満の修行徳目を行じる人を云う。勅書は全文、光格天皇の御真筆による。聖護院に寺宝として残されている。 |
| 【幕末期】 | |||
| 「しばやんの日々」の「明治5年の修験道廃止で17万人もいた山伏はどうなった」参照。
仏教学者・五来重氏の著「山の宗教 修験道案内」p.9、角川ソフィア文庫)が次のように記している。
和歌森太郎氏の「山伏」(中公新書)が次のように記している。
厳しい自然をともに克服しながら、地域の人々とともにみんなが豊かで幸せに暮らせることを祈る山伏が、地域の人々同志の連帯感を強めて、地域を住みやすくすることに役立っていたといえば言い過ぎであろうか。明治維新以前には全国で17万人もの山伏がいたと云う。内閣統計局が昭和5年に公表した『明治5年以降我国の人口』によると、明治5年の人口数は3480万6千人だという。山伏は全員男性なので、単純に考えると、当時のわが国の男性のうち約100人に1人が山伏であったという計算になる。江戸時代のわが国においては、山伏は地域の人々の生活に欠かせない存在であったことは確実だ。 http://hiyoshikami.jp/hiyoshiblog/?p=66 http://www.ipss.go.jp/syoushika/bunken/data/pdf/14167501.pdf |
| 【明治政府の修験道弾圧】 |
| 近代に入って修験道の信仰は大きな打撃をこうむることとなった。これを確認しておく。次のURLに神仏分離に関するすべての布達等の原文が掲載されている。 http://www7b.biglobe.ne.jp/~s_minaga/s_tatu.htm |
| ◎慶応4年(1868)3月17日 神祇事務局達 神社において僧形で神勤している別当・社僧は復飾せよ。つまり僧侶の身分を棄てて還俗することを命じて、その際に差支えがある場合は復飾のうえで神職となり、浄衣を着て神勤すること。 |
| ◎慶応4年(1868)3月28日 神祇官事務局達 ○○権現・牛頭天王などといった神仏混淆的な神号を一掃し、神号の変更を行なうこと。また、仏像を神体としている神社は、仏像を取り除いて神体を取り替えること。また神社から仏具である鰐口や梵鐘などをすべて取り除くこと。 |
| 1868(明治元)年、神仏分離令が発布され、長年吉野山で行われてきた神仏習合の信仰が禁止され、寺院は廃寺になるか、神社に名を変えて生き延びるほかなかった。これは修験道にも受難であった。修験道絡みの建物や文化財の多くが破壊された。中でも石上神宮の神宮寺であった内山永久寺や、琵琶山白飯寺(現天川弁財天神社)が徹底的に破壊された。 |
| 1872(明治5)年、9.5日、神仏分離令に続いて太政官布達第273号をもって「山伏の道、修験道は今後いっさい廃止する」とする修験道廃止令が発布された。本山派修験、羽黒修験は天台宗に、当山派修験は真言宗に所属するものとした。「修験道廃止令」以降、公には山伏は存在しなくなり、真言宗、天台宗のいずれかに属するか、神官となるか、帰農するしかなくなった。さらに追い打ちをかけるように明治政府は、山伏の収入源であった行為を禁止する命令を相次いで出している。これにより、修験道は一宗としての活動が禁止された。明治政府は、このように山伏修験道を弾圧した。これにより凡そ17万人とも18万人とも云われる山伏たちは帰俗を促され、あるいは天台、真言の僧侶、神職に転ずることを余儀なくされた。 |
| ◎明治6年(1873)1月15日に出された教部省達第2号 狐憑きを落すような祈禱をしたり、玉占いや口寄せを業としている者が庶民を幻惑しているので、そのような行為を一切禁止する。 |
| ◎明治7年6月7日 教部省達第22号別紙教部省乙第33号 禁厭、祈祷等を行ない、医療を妨げ、湯薬を止めることの禁止。 |
| 1874(明治7)年、中心寺院の金峯山寺が廃寺に追い込まれた。熊野 ,羽黒,白山,立山,英彦山などの修験霊山は神社化させられた。修験者や僧侶は強制的に還俗させられ農民や氏神鎮守の神職となった。本山派は天台宗に、当山派は真言宗に組み込まれるかたちとなった。富士講は扶桑教、実行教に、御岳講は御岳教と云うように教派神道として公認された。 その背景には、修験道が「文明開化」の流れにもっともなじまない抵抗勢力であったことによるものと思われる。 |
| ◎明治13年7月17日 太政官布告第三十六号 … 旧刑法第427条第12号 妄りに吉凶禍福を説き、又は祈祷、符呪等を為し、人を惑わして利を図る者を拘留または科料に処す |
| ◎明治15年7月10日 内務省達乙第42号別紙戊第3号 禁厭、祈祷等を行なって病人の治療、投薬を妨げる者がいれば、そのことを当該省に報告すること |
| 1886(明治19)年、修験道側からの嘆願により、「天台宗修験派」として修験道の再興が許され、金峯山寺は寺院として存続できることになった。但し、山上の蔵王堂は「大峯山寺」として、吉野の金峯山寺とは分離され現在に至っている。 |
| 1890(明治23)年、11.29日、帝国憲法が施行された。帝国憲法第28条で「信教の自由」が「安寧秩序ヲ妨ゲズ」、「臣民タルノ義務ニ背カザル限ニ於イテ」認められた。 |
| 1941(昭和16)年、政府が、一宗祖一派の建前による仏教諸宗派の合同を促した。これにより、天台宗三派は天台宗に、真言宗八派は真言宗に一括された。 |
|
|
| 知られていないことだが、明治政府は山伏修験道を徹底的に弾圧している。なぜここまで叩いたのか。その理由、事情を考察せねばならないのではないのか。政治運動で事足り派には理解不能であろうが、精神界の抗争も実は立派な政治運動である。と云うか、最も根源的な政治運動と云うべきかも知れない。と云う観点から、明治政府の山伏修験道弾圧事情を解析しておく。本稿は現代政治に何がしか有効と思われるからである。 明治政府の山伏修験道弾圧事情に、明治新政府に忍び寄った国際ユダ邪の陰を見て取るべきではなかろうか。明治維新政府とそれ以降の日本政治には国際ユダ邪に操られている線が窺われる。巧妙に隠されているが、それは国際ユダ邪の統治手法としてのスティルス術によるものであって、我々はこの線を手繰り寄せて洗うべきではなかろうか。明治維新政府が、「中央集権的国家の確立を目的として、天皇を中心とした祭政一致国家の建設をはかろうとした」のは、実は近代化でもなんでもなく、実際は日本の国際ユダ邪植民地化上に都合の良い政体だったからではないのか。そういうもの以外の何物でもなかった。これに合わせて形成された近代天皇制国家神道も然りで、表見は幕末の国学や尊王思想の流れで生み出されたもののように見えるが、その実は国際ユダ邪の好む政策物でしかない。国学や尊王思想の流れを逆手取りして生み出した狡知術によるものではないのか。山伏修験道排撃も然りである。山伏修験道排撃は、山伏修験道が日本神道、日本精神形成に奥深く食い込んでおり、これを排撃せずんば彼らの統治が首尾よく進展しないことを熟知してのものではなかったか。してみれば、国際ユダ邪の正面の政策が記紀神話にも依拠する近代天皇制国家神道であり、裏のそれが山伏修験道排撃であると、こう構図すべきではなかろうか。近代天皇制国家神道と山伏修験道排撃とはかように裏合わせの関係になっている。 思えば、明治維新政府による廃仏毀釈運動の本質は、山伏修験道をターゲットにしていた感がある。しかもそれは、戦国期に侵入したキリスト教イエズス会の宣教師バテレン活動によるキリシタン大名を唆(そそのか)しての神社、寺院の焼き討ち史と重なっている。戦国期の神社、寺院の焼き討ちが明治初期にも起り、これが「廃仏毀釈運動」の正体であったと解するべきではなかろうか。なぜなら、幕末の国学や尊王思想の線から仮に近代天皇制国家神道が生まれたとした場合に、神仏分離令までは出しても、日本神道、日本精神からは寺院や仏像等の破壊焼却までは起り得ないからである。「廃仏毀釈運動」はそれとは別の奥の院指令と窺うべきではなかろうか。なぜなら、本来の日本神道は、自然現象を敬い、その摂理から学ぶ八百万の神を見出す多神教であり、神仏共生で一向に構わないからである。あのような暴力は、それをやらせた司令塔が別に居たと考えるべきではなかろうか。 近代天皇制国家神道は、現天皇を現人神として崇拝し、天皇による祭/政/軍を一体化した国家体制を目指したが、その理論構図が奇しくも国家による一神教化となっている。こういう一神教化は八百万の神々の共存共生を前提としている日本神道、日本精神と合致していない。近代中央集権国家も近代天皇制国家神道はやはり外来物でしかない。正しくは、国際ユダ邪好み中央集権国家、国際ユダ邪好み近代天皇制国家神道と見なすべきだろう。ここをこう捉えないような学問や政論ばかりが流され、その理解が宜しければ人材登用される道筋が確定しているが、それによって出てくるのはいつも決まって「地位に不似合いなお粗末権力者」ばかりである。 2015.11.5日 れんだいこ拝 |
| 【戦後の修験道】 |
| 1946(昭和21)年、真言宗醍醐派別格本山である洞川(どろがわ)の里の龍泉寺の本堂が焼失した。1960(昭和35)年、再建される。 |
| 1948(昭和23)年、天台宗から独立して大峯修験宗が成立した。1952(昭和27)年、金峯山修験本宗と改称、金峯山寺が同宗の総本山となっている。 |
| 一時は歴史の隅に追いやられてしまったが、現在でも奈良県吉野山の金峰山修験本宗、旧本山派は京都市左京区の聖護院を中心とする本山修験宗、当山派は京都市伏見区の醍醐寺を中心とする真言宗醍醐派の三派を主流として信仰が行われている。他にも羽黒山修験本宗、石槌本教など数多くの修験道教団が独立した。更に真如苑、解脱会など修験系の新宗教も成立した。叉、出羽三山神社、英彦大神宮など修験霊山の神社においては峰入りなどの修験道的な行事を行っている。 |
2019.7.28日、「民衆信仰「修験道」の過去・現在・未来(中)」。フォーサイト編集部/森休快。
|
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)