
| 日本神道の歴史6、諸氏の神道論 |

更新日/2019(平成31).1.20日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここで、「諸氏の神道論」を確認しておく。 2005.7.8日 れんだいこ |
![]()
|
|
|
日本に古来から伝わる本来の神道の教え、つまり古神道の流派に属するこの一派は、代々「神祇伯」という、古代日本の律令制度の下に設置された神祇官の長官職を世襲する一族に伝えられてきた。
伯家神道の口伝「2012年、日本大混迷説」 |
| 霊的エコロジストの先駆者・梅辻規清 | |
| 梅辻規清は古神道の中に《生態系》と《食物連鎖》考えを取り込んだ神道説を展開させた霊的エコロジストの先駆者である。しかし、その先駆者ゆえに彼の神道説の中に“政道之批判”の契機を読み取った幕府神道方と寺社奉行は規清を逮捕して島流しにしたのである。そして、明治以降、近代化を急いできた日本の社会は彼を無視続け、歴史の中に埋没させてきたのである。そのため、彼は長い間、“忘れられた神道家”として、その先駆的業績は闇に葬られてきたのである。正当な評価すらされてこなかったのである。しかし、地球的規模での環境破壊が進んでいる今こそ、偉大なる神道家・梅辻規清と烏伝神道は甦るときが到来したのである。 彼は京都上賀茂の賀茂別雷神社の社家の出身で、正式の名を賀茂懸主梅辻飛騨守規清という。十一歳のとき父の報清を亡くしたことから、梅辻家は困窮艱難の状況に見舞われた。しかし、規清は上賀茂と下鴨の両社を合わせた賀茂神道の学頭的存在だった曾祖父・岡本清茂の「希なる血脈」に生まれたことを誇りに、あえて自ら清貧の道を選んだ。そして、彼自身を語るところによれば、十二カ年にわたって東国三十三カ国の深山幽谷で遍歴修行し、その間に富士山にも登拝した。その一方で、彼は神道・国学ばかりでなく、天文・暦学・数学・医学・薬学・建築学・・・等々を幅広く、そして有る程度まで奥深く研究した。 こうした知識を蓄積した規清は、三十代前半のころ江戸へ出て、曾祖父・岡本清茂ゆかりの賀茂神道の伝統の上に、神武東征のさい天皇の軍を熊野から大和国へ導いた遠祖・賀茂建角身命(八咫烏)に由来する《烏伝神道》を創唱した。その違いは《賀茂神道》が賀茂氏の社家神道であったのに対し、《烏伝神道》は民衆救済のための《大衆神道》であった、という点である。そして、烏伝神道の布教のため、奇席を借りて神道講釈を行う一方、池之瑞という名の神道教場を開設した。梅辻規清の主著で、烏伝神道のエッセンスの解説書でもある『烏伝神道大意』は、この瑞烏園での講義録として著されたものらしく、もちろんテキストとしても使用された。かれはその版刻の費用を捻出するため、医学・薬学の知識を活かして万病に効くという「神敵退治散」なる漢方薬を製造・販売し、また糊口をしのぐ糧とした。 規清は『烏伝神道大意』の上巻で、その独自の神道的概念ともいえる「神とは火水則 噛なり」との神道思想を展開している。ちなみに、こうした考えは、現在、真光系の神道系新宗教では、“常識化”しているが、梅辻規清は今から百五十年前、この概念を教義の中心に据えていたという点でも先駆的なのである。すなわち彼は上巻で「神は火水といふの訓にして火水則噛みなり」と指摘し、「神道は火水道といふ事にして、其の火水道とは天地総べて行ひの自らなる道をとふなり」と説いている。 いうなれば、規清によれば、森羅万象は火と水とが動くこと、すなわち陰陽二気が噛み合うことで生じるのである。さらに、かれは、人間にも《火水》の理があるとし、火は熱で天の霊を、水は体(身)で地の霊を意味していると考えた。そして、この二つを結びつけるのが、《呼吸》であるとした。 実際、規清は《森羅万象》を《八百万の神》として据えていたが、その子細について『神道烏伝禊除抄』の中で、つぎのように述べている。
すなわち、規清によれば、イザナギとイザナミの二神は「万物の祖神」なのである。つまり、かれは自然の摂理の中に、神々の作用を見出していたのである。そして、そうした観点に立って、当時の一般庶民にたいする神道的信仰心を喚起したものである。 |
|
| 現五大陸が沈み、新五大陸が浮上する? | |
| さらに規清は(上巻)だけでなく『烏伝神道大意』の全編を《火水開噛の活用》の視点から説いている。そして、かれは天然自然の諸現象を《火水開噛の活用》の視点から捉えるのだ。 たとえば、規清は(下巻)の中で、暦学・天文学の知識を駆使し、数学的演繹を加えながら、世界(地球)の寿命は三億七千二百五十五万六千三百二十二年で、天と地は一万二千七百五十年ごとに呼吸している、結論するのである。そして、その半分の六千三百七十五年ごとに、潮の千満のように呼気と吸気に入れ換わり、そのとき現在の五大陸が海中に沈み、新しい五大陸が出現する、という《盛衰浮沈》理論を展開する。ちなみに、ムー大陸の研究に半生をささげたイギリスのジェームス・チャーチワードによれば、ムー大陸は一万三千年前に沈んだとされており、これは、規清のいう年代とほぼ照合する。 梅辻規清はその証拠として、かつて深山幽谷で修行したさい、高い山々で見た貝の化石の存在をあげている。 この盛衰浮沈論は、幕府にとっては許すことの出来ない危険思想であった。それは幕府の盛衰浮沈を意味していたからである。梅辻規清は弘化四年(一八四七)八丈島への流刑を申し渡されたが、そのときの裁判の《判決書》によれば、この盛衰浮沈論も罪状の一つとされたのであった。なお、この盛衰浮沈論は、世界救世教や真光などの神道系新宗教における《夜昼転換論》の理論的先駆であった。 |
|
| 「火水開噛の活用」の奥義 | |
| 一方、この《神=噛》から《食》を大切にする想が出てくる。というよりも、衣食住全体を大切にする考えが生じてくる。規清が《火水=神=噛》と一見、語呂合わせのように捉えながらも、《噛》の上に《開》の上に字を冠して《開噛》にしたのは深い理由があった。すなわち、それは単なる食養思想からきたのではない。宇宙剖判、天地開闢の神妙があったのである。 すなわち、何もまた生じていない「元始め」のタカアマハラ(高天原)に、火と水の気が潜在し、その二つの気が交み合うことによって神が生じ宇宙が始まったのである。つまり火と水の気が出会うと、神が鳴り生り成るのだ。このとき、音(音霊→言霊)が生じ、光(稲妻)が走るが、これがカミナリ(神鳴り・雷)である。賀茂別雷神社のワケイカヅチとは、若いカミナリの義である。また、上賀茂も訓みようによっては、カミカミである。すなわち、烏伝神道のキーワードともいうべき《火水開噛》というコトバは、宇宙剖判の神妙とともに、梅辻規清の出目が隠されていたのである。 もちろん、宇宙の始めは、《音》だった。『旧約聖書』の「創世記」の冒頭に「神光あれと言いたまひければ光ありき」とか、『新約聖書』の「ヨハネ伝」の冒頭に「太初に言葉あり」 とあるのは、このことを指していたようだ。当然、そのとき生じた音(音霊)は宇宙の《息吹》でもあった。そして、この《息吹》は地球が誕生し、地球上に始めて《産み》の親たる《海》が発生したときにも生じている。もちろん、このときにも神が鳴り生り成っているのである。すなわち、水蒸気を多量に含んだ雲の中で雷鳴とともに稲妻が走り、雨が天から降ってきて《海》が形成され、そこから生命が誕生したのである。梅辻規清の烏伝神道の天然自然の諸現象の視点から捉えられるのは、じつは、ここから発していたのである。 ちなみに、梅辻規清は『烏伝神道大意』の中で、口語訳すれば、「国常立尊に『造化妙用』という著述があり、その中の人間の部をみると、すべてのことがわかる。ただし、この書籍は肉眼では見えず、胸中にある天目一命という神のはたらきがなければ詠むことはできない」と述べているが、かれはクニトコタチの造化妙用(すなわち天地開闢)の過程を、《火水開噛》のコトタマの活用による霊的視点で読み取ったのである。 要するに、《火水=神=噛》とする神道の神道の中で、規清は神が鳴り生り成るときの、火水のコトタマ(言霊)を重視することによって、そのコトタマが躍動する祝詞を霊魂の《食物》として捉えたのである。 実際、かれは『生魂神供次第記』の中でそうした考えを展開している。つまり、霊魂の食物(ケ)であるコトタマ(本来は宇宙に充満しているから、我々にたいしていつも開かれた状態にある。)をよく噛む、という意味で《開噛》という字を当てたようなのだ。また、人間が、そして天地が《呼吸》することになって、火と水とを放出している状態にあることも、《開》の字を冠している理由の一つになっているようである。なお、規清は「神道き火水道である」ということから、火と水を使う台所と、その台所を守る主婦の役割についても重視し、『三宝荒神真向鏡』の中で神道の日常生活化を提示している。 いずれにせよ、人間の呼吸と天地の呼吸を結びつけた発想は、十分に注目されてよい。 規清は、烏伝神道の、こうした考えは賀茂氏の先祖である建角身命(八咫烏)から伝来したと称しているが、おそらく十二カ年、三十三カ国にわたる深山幽谷での、彼自身の宗教的体験にもとづくものも含まれていたに違いない。その意味で『烏伝神道大意』は規清の《気》と《呼吸》にかんする霊学思想を展開した書であったといえる。 「古神道とエコロジー」菅田正昭・著より |
霊学中興の祖・本田親徳 一般的に古神道とは「自然の中に神(霊)性を観て、自然即宇宙という認識のもと、万物に霊魂が宿ることを感じ、それら総ての生命に畏敬を払う“自然発生的アニミズム信仰”」である。そして、その起源は縄文以前にまで遡ります。 古墳時代から飛鳥時代にかけて、天皇家を始め各氏族はそれぞれの古神道を創設しました。物部神道、中臣神道など多数あります。しかし、大陸からの様々な宗教の伝来などによって、平安時代頃には既に古神道の秘儀が埋没しそうになってしまいました。そこで1025年、各古神道が結集、統合したかたちで白川神祇伯王家(しらかわじんぎはくおうけ)が創設されることとなりました。明治時代に廃止それるまでの約800年間、その行法によって天皇の霊性を守ることを第一の目的として継承されました。 明治期に入り、この伯家の神道と地下水脈ではつながりを持つ、古伝復興派と呼ばれる人たちが活躍します。その中の一人が本田親徳(1822~1889)です。薩摩の氏族(典医)の家に生まれ、18歳で上京し、水戸学の相沢正士斎に入門。平田篤胤の家にも出入りしました。諏訪神社の神官を務めたこともあります。 天保14年秋のこと、親徳が京都の藩邸にいるときのことです。狐憑きの少女が和歌を詠むという憑霊現象を実見することになったのでした。この事件を契機に親徳は、本格的な霊学研究の志を立て、古社を訪ね、深山幽谷に分け入ること40年、ついに霊学体系を樹立したといいます。 伯家神道の鎮魂行における「審神者(サニワ)」の役割 さて伯家神道の霊的修行、つまり鎮魂行がおこなわれる場合の説明をしますと、まず、仲介者として魂の階梯(レベル)を見極め、神業を取り立てていく指導者が必要となります。これを「審神者と呼びます。修行者が座していると、様々な霊動が出てきたりします。審神者はその際、“手かざし”や“手当て”によって神気を送り、修行者の霊的障害を祓います。(手かざしを行う多くの神道系教団がありますが、これがもとになっているようです。)一時的に邪気を代替わりしてあげることもあるといいます。これが伯家の「審神者」の定義です。 本田親徳が復活させた「鎮魂帰神法」 神懸かりの歴史は非常に古いものと思われます。ちなみに『古事記』中巻 仲哀天皇の条には神宮皇后を神主にし、天皇が琴を弾き、建内宿祢が審神者を努め「帰神法」を執り行った旨が記されている。 本田親徳が復活させた「鎮魂帰神法」では、「神主(霊媒)」と「審神者」が二人一組になり、「神主」に憑ってきた神(又は霊)が正神(又は霊)か邪神(又は霊)か、また、その由緒来歴を問い質して判断する役を「審神者」と定義しています。 鎮魂帰神法という場合は、「鎮魂」は自己の霊位を上げる行法であり、「帰神法」がいわゆる神憑り法と考えたらよいでしょう。 神伝により幽冥界には正神(霊)界・邪神(霊)界があり、上・中・下の品位がそれぞれにあるという。この帰神法は良質の神主と審神者が必要で、未熟だったり、自己の利益のために行うと、それに相応した低級霊が降りてくる。低級霊はもっともらしいことを言って騙すことが上手である。よほどの技量がないと憑ってきた神霊に振り回されることになるという。 多くの神道系教団でも同様で、教団初期の段階では帰神法的なものを行っていたが、その障害が出てしまうため、後には帰神法だけにとどめるようにしているところが多いと言います。 ●帰神法 鎮魂とは、(1)日常的な霊魂の訓練のようなものとし、(2)帰神=憑霊のための準備的行法であり、(3)自他の霊魂を外部の物体に憑依集中させることとしており、(4)自己の霊魂が天御中主神のもとに至ることによる神人感応としても説かれている。 (が、これは憑霊よりもむしろ脱魂に近いものに表現される) ※神が自分の霊魂を草木に付けることも鎮魂であるとしている。 ◆鎮魂石 直径五、六分くらいから一寸内外の活き石に自分の霊魂の集中することを凝念すること二、三〇分の鍛錬を行うとよい。(霊的)病気治しや、審神にそれなりの力がついてくるという。 ●霊界の区分 ・正神に181階級あり、邪神もまた同じ181階級あるという。 ・「精神正しければ即ち(正霊)に感合し、邪なれば即ち邪神(邪霊)に感合す。精神の聖者賢愚は直ちに幽冥界に応ず。最も戒慎すべし。」としている。 ●帰神法 ①自感法-自分一人で神霊に感合する。 ②他感法-審神者がいて、神主(霊媒)がいて琴師(本田はこの琴師を略し、審神者が石笛を吹くをもって代用した)がいる。 ③神感法-人の意志に係わらず、神の意思で忽然と憑かってくる。 ・この三法がさらに有形、無形、上中下に十八法に細分されているという。 ◆審神者(さにわ) 帰神法を一人で行うことは未熟な人の場合、邪霊などが憑ってくるので危険であり、そのため、その憑かりきたるものの正邪高下などを判断し、場合によってはその霊を祓うことのできる力をもつ審神者がいて行う他感法を親徳は重視し、「帰神に重要なるは審神者とす。その人に非ざれば即ちあたわざる者なり」とし、審神者は「注意周到にして胆力あり、学職ありて、理非を明らかにするに速やかなる」人でなければならぬと記している。 ★帰神の実際 婦女を台の上に座せしめ、指を組み合わせ、その眼口を閉じ、一心に神々を念思せしめて、然して後に、貴君は石笛(いわぶえ)にて「ヒト、フタ、ミ、ヨ、イツ、ムユ、ナナ、ヤ、ココノ、タリ、モモ、チ、ヨロツ(一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、百、千、萬)と心に念じて吹かるべし。吹き様は、ヒーと長く吹きて、そのヒーの内に「ヒト」を含ませて、又ヒーに「フタ」を含ませて段々と「ヨロツ」まで吹き、吹き終わりて祈るなり。この百吹きにてその時は暫くやめて、又翌日にても翌晩にても修行するなり。かくの如くして日数を重ぬざる也。そこで神の御名たずね上ぐればよろしい。 つまり、審神者と神主が対座し、神主は“印”を組み、審神者が石笛を吹き、さらに神界から神気を神主に降下させるのである。すると神主に神霊が降下し、手を動かしたり、口を切って神言をかたりだすのである。この時に審神者は、憑かってきた神が、正神界の神であるか、邪神界の神であるかを審神する必要がある。また、正神界の神名をたとえ名乗っていても、真神であるか、偽神であるかを審神する必要である。その為には常に神典(『古事記』『日本書紀』)などを読んでその神徳、功業を記憶していることが肝心だという。 「祓いと占いの世界への導き」 http://www.michihiraki.org/michihiraki/honda.html |
スとはス(主)神、言い換えれば とうぜん、私は今、このス神と 出口王仁三郎がそうであったように、大本系のコトタマ学では、ヒト(人)を〈霊止〉として捉える。たとえば、大本→世界救世教の流れにある真光の岡田光玉(聖凰)も、「霊止(人)」と書き、霊止・人にそれぞれとヒトとルビを振っている。そして、「神魂に宿したるもののことを霊止」と申させしなり、などといっている。 ところが、ヒトには〈霊止〉のほか、〈霊交〉の義もあるのだ。つまり、〈霊止〉だけでは神理の一面しか語っていたいのだ。 ただし、岡田光玉の場合、「ミロク大神(主)は、霊成型(ひながた)火(タテ)と水(ヨコ)にて創りて肉身(にくみ)と現れしめん時、神魂を分け、大天津神の霊質(ひしつ)もヒキチギリて分け与え・・・・・」(『御聖言』)と書いてある。つまり、彼は人が〈霊交〉であることに気付いていたのである。 「言霊の宇宙へ」菅田正昭 著より 私の想像では、スガタというのは、古代、ス神を見ることができた人々に贈られた敬称ではなかったか、ということだ。つまり彼らは |
現代への応用と神道地政学 竹内睦泰 古神道本庁統理 第七十三世武内宿禰 武内宿禰の血をひく正統竹内家には かずかずの秘儀・口伝が残されている。 熱湯の中の小石を素手で取る「盟神探湯」、 空に浮かび飛行する「天之浮船之行法」など 特殊な行法から、現代人でも応用が 可能なものまで一挙、初公開する! 【はじめに】 古神道の秘儀は、今までの歴史のなかでことある事に使用されてきた。場合によっては悪用されたこともある。なにゆえ、悪用できるのかと疑問に思う方も多いだろうが、それは古神道に「悪」という概念が存在しないからである。局外者にとって、これは利用しやすいものはない。 古神道には「善」と「悪」といった二元論はありえない。「悪神」はあとから作り出されたもので、儒教・仏教伝来まではなかったと思われる。善か悪か、正か邪か、判断する術をもたない。とにかく、何をつけても「あいまい」なのである。この曖昧さが古神道の一つの大きな特徴である。 正統竹内家は、後醍醐天皇の南朝および武内宿禰の正孫であり、代々竹内宿禰を名乗って(鎌倉期に武内から竹内と書き替えている)、門外不出の秘授口伝、古神道の行法を現代に引き継いでいる。その概要については以前に述べた。竹内神道は秘密神道であり、当然、一般の目には触れることはないのだが、ここでは他の古神道と共通する行法も含めて、その代表的な秘儀を紹介していこう。 【反魂蘇生之行法】 古神道では「生」と「死」の境界も、きわめて曖昧で、人は死ぬと魂と霊体が「黄泉の国」といわれるところへ行き、そこから戻ってきて「甦る」(=黄泉国から帰る)人が、死後の世界を伝えることが多い。人為的に人を甦らす行法に竹内神道の「反魂蘇生之行法」がある。物部神道では「十種神宝之行法」と呼ばれる。段階をもってマスターしていき、最後には死者を甦らす能力を身に付けるのが目的だが、これが古神道の奥義の「死と再生」の修行の一つである。 死後の世界を見るというのは、「夢」の中で見るのとどこが違うのかというと、夢では魂が別の世界に行くだけであり、霊体と肉体と重なったままだ。霊体が肉体と離れるといわゆる「死体」になってしまう。よく「鏡を見て、姿を二重に写ると、もうすぐ死ぬ」というのはこのためである。 しかし「死」もまた「生」の始まりなのである。最後をしめくくることを「結ぶ」というが、「むすび」は「産霊」と書く。「霊」をむす(=生む)のが、生の最後なのだ。神道では「人」は霊が留まる場所「霊止=ヒト」と書く。 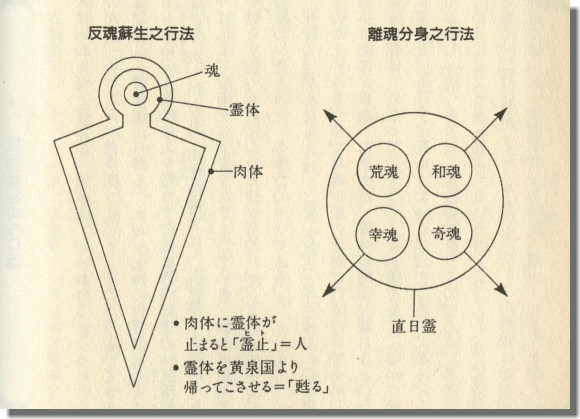 【離魂分身之行法】 魂だけを飛ばす技を竹内神道では「離魂分身之行法」という。魂が数日後の世界を見てくれば「予言」は可能になる。しかし、これは簡単にはいかないのだ。 人間は「一霊四魂」といって魂は四つある。飛ばせる魂は一つだけであり、自由にコントロールができるわけでもない。一つの魂だけでは、四つ揃っているときと意識が違うし、戻ってきたときの記憶が曖昧になるため、正確にはっきりと思い出せないのだ。さらにそのとき見た未来が状況の変化によって変わることもある。人の運命も同じで、運命とは、たえず動き続けるもの、すなわち運行している命なのだ。 そういう意味では自分自身の心がけで変えていくことが可能である。もしも何らかの「夢」があるのならば、その夢に向かっていくよう運命を創り出してほしい。 【御鏡御拝之行法】 自分自身を変えていくにはどうしてもきっかけが必要だろう。そのきっかけを作る小道具として「鏡」を使った修行法を勧める。「御鏡御拝之行法」は江戸時代に財政難でまともに神道の儀式ができなかった天皇家で細々と続けられてきた行法である。これは現代でも十分役に立つもので「人」が「神」になる方法の一つである。 まず鏡の前に立ってほしい。そこに何が写っているだろうか。おそらく普通は貴方の姿であろう。その姿を直視して心から頭を下げることができるだろうか。おそらく普通は無理だろう。しかし、たとえ一日でも命掛けでスポーツでも勉強でもいい、何かの努力をしたときに本当にこれ以上はできないというぐらい頑張ったときの己の姿を鏡で見たときに、自然と頭が下がるようなときがある。 そのときに鏡に写っているのは、いつもの自分ではなく「無私」の気持ちをもった別人であるはずだ。それもまた「神」なのである。鏡とは「神=カミ」の中に「我=ガ」を入れるものである。これもまた神社と共に人が神になる神聖装置なのだ。 【鎮魂帰神之行法】 人が神になる方法はほかにもある。「鎮魂帰神之行法」もその一つである。これは己の身体の中に「神」を入れる行法で、かなり高度なものである。 まず、神を入れるためには己の肉体をそれにふさわしい「真秀呂場」にする必要がある。簡単にいえば自分の肉体を「神社」にして神を迎えるのである。よくオカルト的神道系新宗教で軽く鎮魂帰神法などといっているが、実際は単なる「降霊」にすぎない。真の鎮魂帰神之行法は数多くの行法の中でもきわめて難しいものである。というのは霊媒になる人に霊媒体質の人が多いように、体質が少なからず関係してくる。体質はある程度は変えることもできるのだが、初めから鎮魂帰神に向いている人もいるし、迎える神「合う」かどうか個人差がある。 修行によって迎える神の格を高めていくことは、どの宗教も同じで、真言密教の奥義の大日如来と一体になる「即身成仏」の境地もこれにきわめて近いものと思う。 【真床男衾之行法】 だからこそ神道の奥義をマスターしていた後醍醐天皇は、かなり早いペースで真言密教の奥義を修めて伝法灌頂を受けることができた。 大日如来と一体になる即身成仏の秘儀は、天皇になるために、天照大神と一体となる日嗣の儀式と極めてよく似たもので、この一つの形として「真床男衾之行法」がある。 これは現在の北朝の天皇家には伝わっていないものだが、南朝の血を引く竹内宿禰家に伝わっており、武内宿禰の霊を体に入れる「霊嗣の儀式」では仮の「真床男衾」を使用することもある。歴代の竹内宿禰はすべて天皇家と武内宿禰の血を引いており、体質が遺伝しているからだろう。神主に親子相続が多いのもそのためである。 もっとも、長子相続ではなく一族の中から適任者が選ばれることになっている。あらかじめ占いで予言されていた人物と一族中の適任者が一致して霊嗣の儀式が執行される。体質は隔世遺伝の場合もあるので、途中で期間が空くこともあった。 【言霊之行法】 言霊については詳しい解説書が多く出ているので詳しく延べないが、弘法大師・空海が短期間で真言密教をマスターできたのは、真言(=マントラ)と言霊(ことだま)が共通したものであり、無意識のうちにすでに理解していたからであろう。 簡単にいえば一つ一つの言葉に「霊」が宿っているという思想で、日本人にとっては無意識のうちに身についているものである。この組み合わせにより古神道の行法を執行することもある。「アマテラスオホミカミ」と唱える「十言の神咒」や「トホカミエミタメ」から始まる「三種の祓詞」は有名である。 キリスト教でも言葉が重視されているのは、聖書の「初めに言葉ありき」にあらわれている。とくに神の名は大切な秘密でみだりに唱えてはいけないところも似ている。エホバの真の名は案外、竹内家口伝の最初の神の真の名と同じではないかと密かに思っている。 【息吹永世之行法】 神道の呼吸法は流派によってさまざまな方法を伝授しているが、武内宿禰は「息吹永世之行法」にとって当時としてはかなり長生きをした。一般に丹田呼吸法といわれるものがあるが、この方法に近いものから、呼吸を停止する行法まで十数種類ある。しかし、あまり難しく考えずに深呼吸の効能から理解していったほうがいい。焦っているとき、つらいときにまず、深呼吸してから思案するように勤める。 【禊之行法】 朝風呂に入ってから一日が始まるというのは気持ちのいいものである。女性なら朝、シャワーを浴びてから一日を始める人多いだろう。これは日本に限らず世界各国共通の習慣かもしれない。世界的共通性があるこの習慣は、古神道でも初期のアニミズムのころに作り出された。これこそ古神道でもかなり古い形態の行法「みそぎ」である。 竹内神道では大きく二種類に分けられている。「水」の禊と「火」の禊で、水の禊は文字通り、水で「自らの身」を清める肉体的なもの。火の禊は「霊=ひ」の禊であり霊体を清める霊的なものである。ともに神道の行法を行なう上でどうしてもマスターしておきたい基本的行法である。 【盟神探湯】 これはまさに竹内家の御家芸というべきもので、『日本書紀』にも武内宿禰が盟神探湯を執行したということは詳しく載っている。 熱湯の中に手を入れて、鍋の中にある小石を素手で取る業なのだが、嘘をついている人物なら火傷し、清廉潔白なら火傷しないという。いくらなんでも、これは無理だと思った。火傷をしないなんて化け物だ。ところができるのである。なんと二十通りの方法がある。といっても、裏十種といわれる十通りは超能力しいってもいいものなので、一般人には無理だ。私も恐くて試したことはない。 しかし、表十種といわれるものは一般人にも可能な業だ。物理的には可能な方法なのである。では、インチキかというと、そうではない。当時の人々の中では十分「神業」なのである。そこに秘伝がある。天皇族は太古より、征服した王朝の歴史と秘儀を奪ってきた民族なのだが、その尖兵となっていた武内宿禰はかなりの秘儀を授かっていたし、自分で開発していた。 【八雲村雲十握剣之行法】 剣によって邪霊を祓う「剣祓い」はよく知られているが、竹内神道の場合は、霊剣によって霊体を斬ってしまう行法がある。「八雲村雲十握剣之行法」である。 物質的な剣ではなく、霊体のみを持つ剣に入魂して執行する。たとえ肉体を鍛え上げていても、死後に霊体を斬られてはつらいだろう。剣は「武内宿禰」の称号とともに「神宮幽宮(幽界の伊勢神宮「皇祖之霊大神宮」)」に与えられる。 【天之浮船之行法】 一言でいえば、空に浮かび、飛行するのが「天之浮船之行法」である。しかし、あまりお勧めはできない。というのは、一度行っただけで一週間くらいは動けなくなるほど体力を使う上に頭痛が続く。私の場合、数センチは浮くのだが(錯覚かも知れない)、一ヶ月たっても限界を乗り越えるのが難しく、前へ進まない。結論からいって、その程度の移動なら立ち上がって歩いた方が速い。修行する気になれない行法の一つ。 【呪殺について】 人を呪い殺すという物騒なものだが、呪殺の行法はあることはある。しかし、実用されては困るし、かなりの精神的・肉体的苦痛が伴うのでやめたほうがよい。ナイフの方が手軽(?)だが、人を殺しておいて自分は捕まりたくないなんて考えが甘い。私が絶対やらない行法である。呪殺するくらいの精神力があれば、ほかに道があるはずだ。 【二上山について】 全国に二上山という山がある。これらはすべて竹内神道の祭祀を執行できる場所である。ほかに二塚・両神など頂上が二つある山は使用できる。低い山から高い山を望み、それを神体山として祭祀を執行する。もっとも、これは顕斎の場合で、通常は幽斎で行う。幽斎とは、物質的には存在しない神社を眼前に出現させる事である。はじめは目を閉じて社を想像するといいだろう。現在、幽斎を普及するため、人間一人一人の中に神社を創建する「心に社を」運動を準備中である。 【神とは何か】 古神道では「八百万神」というぐらいで、あらゆる事物に神が宿っているという考えがある。宗教学でいうところの「汎神論」である。 実はおよそ宗教と言われるものは、もともと汎神論的アニミズム=自然崇拝から発生したと思われる。日本の古神道はそれが古い形態のまま残った一つの例にすぎない。だから石や樹木も神だし、人も神である。ただ自然の事物や生物以外に、人間の力を超えた力、たとえば宇宙の運行などの動力、これを神と呼ぶのが竹内神道の神という用語のもっともポピュラーな使い方である。天照大神など、人が死んで霊となり神霊となった人格神も神と呼ぶが、山や石などの自然神は普段はあまり神と呼ばない。 【産土神と神道地政学】 しかし産土神といわれる土地の神については、はっきり神と呼ぶことが多い。その土地の風土と産土神の気性は同じであり、土地の霊であり、土地の地主である。この産土神の性格を踏まえた上で、「審神」をすれば、戦争や政治情勢などを判断することができる。実はこれこそが、歴代の武内宿禰の戦略の基本にあった「家学」というべきものである。これを私は「神道地政学」と命名した。 武内宿禰の称号を持つものにとって、「審神」は「盟神探湯」「禊」と共に御家芸といっても過言ではない。審神とは「審庭」とも書き、その土地を神の真秀呂場かどうかを占うことも大切な仕事である。 【神道地政学と戦争】 審神を使えば、戦争も政争もある程度の予測がつく。道教の奇門遁甲の法もこの審神が発達して実用されたものだろう。天武天皇が 奇門遁甲の術を使ったというのも、この土地の神の発送が、もとからあったからではないかと思う。 天武天皇は西暦六七五年に占星台という天文台造営しているが、これは明らかに星の運行を見て将来を占うためで、彼は「大王=オオキミ」の称号を「天皇」に変えたことでも有名だが、天皇を名乗る以上、十分に土地の皇帝たる「地皇」のことにも詳しかったと思う。しかし竹内家に伝わる兵法の極意は、「無の極」と「和」である。ここでは「和」について語ろう。なんといっても日本は「和(倭)」の国であり、「大和(邪馬台)」の国である。和といっても今の平和主義者のように何も考えずに平和を唱えるものではなく、どちらかといえば戦争のケースを考えた上での「和」である。このため情報収集を最重要としている。審神にしても膨大な諸神の情報をもとに判断を下すのである。情報収集の後に外交への戦いに移るが、このときは敵の情報を混乱させるため、偽情報を流したりの情報操作を行う。ここらへんは日露戦争以後の日本にない部分だ。 【外八州内八州観】 神道地政学が通常の地政学と違うのは、神道地政学は顕界の地政以外に、幽界の地政も参考にすることだ。「顕幽一如」といって顕界と幽界は合わせ鏡のようなもので、幽界に起こったことは、必ず顕界にも起こるといわれている。 これと似た合わせ鏡に「外八州内八州観」がある。すなわち日本が世界の雛形であるといった世界観である。例を挙げると、本州=ユーラシア大陸。九州=アフリカ大陸。四国=オセアニア大陸。北海道=北アメリカ大陸。次は書きにくいのだが、台湾=南アメリカ大陸。樺太=グリーンランドである。もう少し例を挙げると琵琶湖=カスピ海。大阪湾=黒海。エベレスト=富士山などである。 次は通常の外八州観と少し違うのだが伊豆半島=インド説だ。伊豆半島が南方より移動してきて本州にぶつかった半島だということは科学的にはわかっているのだが、実は、インドも南方より移動して大陸にぶつかったのである。これは知る人ぞ知る事実である。 【世界同祖説と万教帰一】 世界の大陸が元一つだったことはよく知られているし多くの人がみとめているが、世界の各民族がすべて同じ祖先だということは、民族主義の関係なのか認めない人が多い。この状況を何とかしないと民族対立による戦争が今後も引き続き行われてしまう。これは不毛だ。白人の先祖と黒人の先祖がまったく別の動物であると考えるよりは、ひとつの人種が移住した土地の風土や気候によって異なった容姿を持つようになったと考えるほうが自然だろう。 実は異なる宗教の神話や神もよくよく調べれば、もとは同じであるといえるようなものが意外に多い。それらを整理して原型(=プロト)の神話を浮かび上がらせることが可能ならば、宗教紛争も減るに違いない。強引に力で一つにするのではなく、一つのモデルを提示して納得し合うことができればどんなに素晴らしいだろう。これができるのは神社でクリスマスパーティを開催できる寛容さをもつ神社だけではないかと思う。 「古神道・神道の謎」 新人物往来社 |
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)