
(最新見直し2010.03.07日)
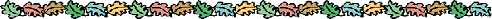
| たかまなるあや |
タカマ成る文 |
| やまくいの たかまおこえは くさなきて |
ヤマクイの タカマを請えば 草薙ぎて |
| こほしおまつる ゆきのみや |
九星を祀る ユキの宮 |
| あめとこたちと すきとのに |
アメトコタチと スキ殿に |
| うましあしかい ひこちかみ |
ウマシアシカイ ヒコチ神 |
| あわせまつれは なもたかま |
合わせ祀れば 名もタカマ |
| もろあつまりて ゆえこえは |
諸集まりて 故請えば |
| きみさほひこに みことのり |
君サホヒコに 詔 |
| これたまきねに われきくは |
これタマキネに 我聞くは |
| あめつちいまた ならさるに |
天地未だ 成らざるに |
| あめのみをやの なすいきは |
天の御祖の なす息は |
| きわなくうこく あもとかみ |
際なく動く 天元神 |
| みつにあふらの うかむさま |
水に油の 浮かむ様 |
| めくるうつほの そのなかに |
廻る空洞の その中に |
| あめつちととく みはしらお |
天地届く 御柱を |
| めくりわかるる あわうひの |
廻り分かるる 泡泥(あわうひ)の |
| あわはきよくて むねをかみ |
泡は清くて むね陽(を)神 |
| うひはにこりて みなめかみ |
泥は濁りて みな陰(め)神 |
| をはかろきよく あめとなり |
陽は軽ろ清く 天となり |
| めはおもりこる くにのたま |
陰は重り凝る 地の球 |
| うをせのむねは ひのわなる |
うを背のむねは 日輪なる |
| うめのみなもと つきとなる |
うめの源 月となる |
| あもとあらわれ うみてのる |
天元顕れ 生みて乗る |
| うつろしなとに はおめくり |
ウツロ・シナトに 地を巡り |
| ありさまなせは つきのみつ |
あり様成せば 月の水 |
| うみとたたえて ひにうめる |
海と湛えて 日に生める |
| うつほうこきて かせとなる |
空動きて 風となる |
| かせほとなれは つちもまた |
風火となれば 土もまた |
| みつはにとなる |
水埴となる |
| このゐつつ ましわりなれる かんひとは |
この五つ 交わり成れる 神人は |
| あうわあらわる みなかぬし |
ア・ウ・ワ顕わる 御中主 |
| くにたまやもに よろこうみ |
地球八方に 万子生み |
| はつにをうみの ゑとのこの |
果つにヲウミの 兄弟の子の |
| ゑみこあにつき をうみたす |
兄御子上に継ぎ ヲウミ治す |
| おとみこのすむ としたくに |
弟御子の統む トシタ国 |
| これいまはらの みやのなも |
これ今ハラの 宮の名も |
| としたといいて よよのなの |
トシタと言いて 代々の名の |
| ももはかりのち とのみこと ゑにうけをさむ |
百諮り後 弟の命 兄に受け治む |
| それよりそ かわるかわりに よおつきて |
それよりぞ 代る代りに 世を継ぎて |
| あめにかえれは みなかぬし |
天に還れば 御中主 |
| およひゑひため とほかみも |
およびヱ・ヒ・タ・メ ト・ホ・カ・ミも |
| あめにくはりて ほしとなす |
天に配りて 星となす |
| あめとこたちの かみはこれ |
アメトコタチの 神はこれ |
| のちそひのきみ きつをさね |
後十一の君 キ・ツ・ヲ・サ・ネ |
| あみやしなうも あにかえり |
ア・ミ・ヤ・シ・ナ・ウも 天に還り |
| さこくしろにて みことのり |
サコクシロにて 詔 |
| みなほしとなす このかみは |
皆な星となす この神は |
| はらわたいのち みけおもる |
腹腑(はらわた)命 食(みけ)を守る |
| うましあしかい ひこちかみ |
ウマシアシカイ ヒコチ神 |
| かれあめみこと わのみこと |
故天命 地の命 |
| くにとこたちの なよのかみ |
クニトコタチの 七代の神 |
| みなさこくしろ よりのほし |
皆なサコクシロ よりの星 |
|
|
| あにあらわるる ひのわたり |
天に現るる 日の径り |
| ももゐそとめち つきのほと |
百五十トメチ 月の程 |
| なそとめちうち ひのめくり |
七十トメチ内 日の廻り |
| なかふしのとの あかきみち |
中節の外の 赤き道 |
| やよろとめちの つきおさる |
八万トメチの 月を退る |
| つきのしらみち よよちうち |
月の白道 四万チ内 |
| くにたまわたり もそよちの |
地球径り 百十四チの |
| めくりみもむそ ゐとめちの |
周り三百六十 五トメチの |
| つきよりちかき ひはとおく |
月寄り近き 日は遠く |
| つきはなかはに ちかきゆえ ならへみるなり |
月は半ばに 近き故 並べ見るなり |
|
|
| もろほしは あめにかかりて またらなす |
諸星は 天に篝りて 斑(まだら)なす |
| つつゐはもとの いろつかさ |
連井は本の 色司 |
| ふそみかほしは よしあしお はらのにしめす |
二十甕星は 吉凶を ハラ野に示す |
| あまめくり ひはををきくて ひとおくれ |
天廻り 日は大きくて 一送れ |
| みもむそゐたひ ひととしの |
三百六十五度 一年の |
| はるたつひには もとにきて |
春立つ日には 元に来て |
| ひとたひもとの ほしにあい |
一度元の 星に合い |
| つきはおもくて そみのりお |
月は重くて 十三延を |
| おくれひにあふ ついたちそ |
遅れ日に合ふ 朔(ついたち)ぞ |
| ほしにそみあふ あめはゑな |
星に染み合ふ 天は胞衣 |
| ひつきひとみな あめのえな |
日・月・人皆な 陽陰の枝 |
| そとはたかまの はらまわり |
外はタカマの ハラ周り |
| ももよろとめち ほしまては |
百万トメチ 星までは |
| そゐやちとめち そのそとは |
十五八千トメチ その外は |
| なもとこしなえ やすみきは |
名もトコシナエ 八隅際 |
| やいろのにきて みなみあお |
八色の和幣 南青 |
| にしはくれない きたはきに |
西は紅 北は黄に |
| ひかしはしろく あいもいろ |
東は白く 間(あい)も色 |
|
|
| みをやのそはに やもとかみ |
御祖の傍に 八元神 |
| まもるとほかみ ゑひための |
守るトホカミ ヱヒタメの |
| ゑとのことふき あなれかみ |
兄弟の寿 天なれ神 |
| ねこえさつけて みそふかみ |
根こえ授けて 三十二神 |
| みめかたちなす したつもの |
見め形成す 親つモノ |
| そむよろやちと もりおゑて |
十六万八千と 守を得て |
| ひとうまるとき かみともの |
人生まる時 神とモノ |
| たましいむすひ たまのをと |
魂魄結び 魂の緒と |
| ゐくらむわたも そのかみの |
五臓六腑も その神の |
| そよたてそなえ ひととなす |
十四経備え 人となす |
| あめのみをやの ををんたけ |
天の御祖の 大御丈 |
| やもよろとめち みのひかり |
八百万トメチ 身の光 |
| もともとあけの あまめくみ |
元々明の 天恵み |
| ととくはしらは すきとほる |
届く柱は 透き通る |
| なかのくたより はこふいき |
中の管より 運ぶ息 |
| くるまのうてき ここのわの |
車の腕木 九の輪の |
| ひひきてめくる いきのかす |
響きて巡る 息の数 |
| よろみちむやそ ひとのいき ささなみもこれ |
万三千六八十 人の息 細波もこれ |
| |
|
| とめちとは めのみそむふむ |
トメチとは 女の三十六踏む |
| せはといき ももいきはまち |
畝は十イキ 百イキは町 |
| みそむさと さとみそやなり |
三十六里 里三十八なり |
| みをやかみ みてくらそむる |
ミヲヤ神 幣(みてくら)添むる |
| はるあきの いきはくたより さきりなす |
春秋の 息は管より 精霧なす |
| ゑにゆつるきり ひおまねき ふゆひをかえす |
ヱに譲る霧 日を招き 冬日陽反す |
| とはなつに つきのめかえす |
トは夏に 月の陰 反す |
| はるあきそ あめゆつるひは あのさきり |
春秋ぞ 天譲る日は 天のさ霧 |
| くにゆつるつき はのさきり |
地譲る月 地のさ霧 |
| てれはたたゆる みなかぬし |
てれば称ゆる 御中主 |
| あきりにのりて やもにゆき |
天霧に乗りて 八方に行き |
| ひつきのみちお ゆつりはに |
日月の道を 譲り地に |
| あかたのかみの いろくにと なつけあのみち |
県の神の 色国と 名付け天の道 |
| はのみちも あしのことくに たつゆえに |
地の道も 葦の如くに 立つ故に |
| よそこのかみは あにかえり |
四十九の神は 天に還り |
| もとのたかまの はらにあり |
元のタカマの ハラにあり |
| くにたまくわし さこくしろ |
地球細し サコクシロ |
| かれかみまつる はもたかま |
故神祀る 地もタカマ |
| すかのところは これにくらへん |
清の所は これに比べん |
| をおんかみ おりのみゆきに ききませは |
大御神 折の御幸に 聞きませば |
| こきみもみこと みちひこも |
九君百尊 三千彦も |
| みなつつしみて うやまいにけり |
皆謹みて 敬いにけり |
| なめことのあや |
嘗事の文 |
| つきすみの しかのみことか |
ツキスミの シガの命が |
| ゑとのかみ とよりののとの ゆえおとふ |
兄弟の神 弟よりの宣の 故を問ふ |
| かれにとよけの なめことそ |
故にトヨケの 嘗事ぞ |
| ゑのなめはねに しものなか |
ヱの嘗は北に 十一月の中 |
| ひうおまねけは かつめかみ |
一陽を招けば かつめ神 |
| かちおねにひき ひおむかふ |
舵を北に率き 日を迎ふ |
| このういなめは いまののと |
この初嘗は 今の宣 |
| こほしまつりて をめくりに |
九星祀りて 陽回りに |
| くろまめゐひの ちからそふ |
黒豆飯の 力添ふ |
| しわすはにみつ きはねさす |
十二月地に満つ 木は根差す |
| なおそらさむく つきすえは |
なお空寒く 月末は |
| かゐみなきそひ ややひらく |
殻漲ぎ聳ひ 弥々開く |
| またそらさむく うるおえす |
まだ空寒く 潤を得ず |
| ややなめつくる はにみつの |
弥々嘗尽くる 埴・水の |
| ゑにはしらたつ かみかたち |
上に柱立つ 神形 |
| としわけのよは まめおいり |
年分けの夜は 豆を煎り |
| みなおにやらふ かおひらき |
穢・鬼遣らふ 門を開き |
| しめひきふさき はゑゆつは |
〆引き塞ぎ ハヱ・ユヅ葉 |
| むきにとしこへ ひのなめは |
麦に年越え ヒの嘗は |
| つさにいなさの はつひより |
西南にイナサの 初日より |
| ふうおやわせて おけらたき |
二陽を和せて 朮(おけら)焚き |
| わかめみつくみ しときもち |
若女水汲み 粢(しとぎ)餅 |
| まかりかやくり うなところ |
まかり榧栗 海菜トコロ |
| かくいもかしら しむのより |
橘芋頭 シムの寄り |
| ゆみつきのよは ゐのみつに |
弓月の夜は 亥の三つに |
| ぬえあしもちか かたをゑお |
ヌエアシモチが 朽穢を |
| こけふはこへな いたひらな |
ゴゲフ・ハコベ菜 イタヒラ菜 |
| すすなすすしろ すせりなす |
スズナ・スズシロ スセリ・ナズ |
| なみそにのそく めをおえは |
七ミソに除く 陰陽合えば |
| もちのあしたは ひもろけの |
十五日の朝は 霊守食の |
| あつきのかゆに ゑやみよけ |
小豆の粥に 穢病除け |
| ささおけとんと もちやきて |
笹・オケ・ドンド 餅焼きて |
| かゆはしらなす かみありの |
粥柱なす 神現りの |
| かゆふとまにや きさらきは |
粥フトマニや 二月は |
| めをほほやわし きさしおふ |
陰陽ほぼ和し 萌し生ふ |
| たねかしまつる いなるかみ |
種浸し祭る 稲荷神 |
| のりゆみひらき もちまてに |
乗弓開き 餅左右に |
| そこにふきたつ はつひかせ |
底に吹き立つ 初日風 |
| これかみかたち |
これ神形 |
| たのなめは みうのあおうけ |
タの嘗は 三陽の天を受け |
| きさらきの なかよりみうお めにやわせ |
二月の 中より三陽を 陰に和せ |
| ひとくさそたつ いというそ |
人草育つ イトユウぞ |
| やよいのはしめ ももやなき |
弥生の初め 桃柳 |
| みきひなまつり ゑもきもち |
酒雛祭 蓬(ゑもき)餅 |
| たみなわしろに たねおまく |
民苗代に 種を蒔く |
| やよいなかより かけろひて |
弥生中より 影ろひて |
| なえおいそたつ わのなかに |
苗生い育つ 輪の中に |
| みひかりのあし なかにみつ |
三光の足 中に見つ |
| これかみかたち |
これ神形 |
| めのなめは うめのいもみつ |
メの嘗は 大陰の妹水 |
| うつきより うをおまねきて なつおつく |
四月より 大陽を招きて 夏を継ぐ |
| みはわたぬきて つきなかは さひらきまつる |
衣綿抜きて 月半ば 早開き祭る |
| ゐなるかみ すえはあおひの めをまつり |
稲荷神 末は葵の 夫婦祭り |
| さつきにもろは なるつゆお |
五月に両葉 乗る露を |
| なめんとゑもき あやめふく |
舐めんと蓬 菖蒲(あやめ)吹く |
| さつさはゐわた のりはゐゐ みなそこにふす |
サツサは五腑 乗りは五五 水埴底に伏す |
| めのなさけ これかみかたち |
陰の情け これ神形 |
| とのなめは はにみつうるふ |
トの嘗は 埴・水潤ふ |
| さつきなか ひかりとほれは かつめかみ |
五月中 光徹れば かつめ神 |
| みちおかえして ひおこえは |
道を返して 冷を乞えば |
| みひきおまねき しらみちの |
陰引を招き 白道の |
| ひめおくたして はにふせは |
一陰を降して 地に伏せば |
| きそひのほりて さみたるる |
競ひ昇りて 五月雨るる |
| あおはしけれは なからえの さのかおりうく |
青葉茂れば 長らえの 南の香り受く |
| みなつきは ややはにみちて たたかえは |
六月は 弥々地に満ちて 闘えば |
| かみなりあつく すえはなお |
上鳴り暑く 末は尚 |
| あつくかわけは ももまつり |
暑く乾けば 桃祭り |
| きそひやむれは ひめひらく |
競ひ止むれば 一陰開く |
| ほそちちのわに ぬけつくる みなのはらひそ |
熟瓜茅の輪に 抜け尽くる 皆なの祓ぞ |
| かたちけた あのまてのいの なかにたつ |
形方 天の左右の射の 中に立つ |
| くにたしなるる かみかたち |
地治し平るる 神形 |
| ほのかみきねに なめうけて |
ホの神東北に 嘗受けて |
| はのふめもりて あふみまつ |
地の二陰 盛りて 七月先ず |
| ふめにやわして かせとなす |
二陰に和して 風となす |
| ゆみはりにうむ いうとあさ |
七日に績む 木綿と麻 |
| をとたなはたの ほしまつり |
をと棚機の 星祭り |
| もちはみをやと いきたまに |
十五日は御祖と 生き魂に |
| ゑなのはすけの めをあえは |
胞衣のはすけの 陰・陽合えば |
| あおきおとりて いおうくる |
仰ぎ踊りて 気を受くる |
| ほつみはつひは うけまつり |
八月初日は ウケ祭 |
| ふめたつかせに かやおふす |
二陰立つ風に 萱を臥す |
| ふしあれのわき そろをゑは |
悉し粗れ萎わき ソロ衰えば |
| しなとまつりに のわきうつ ほをのはらゐぞ |
シナト祭に ノワキ討つ ほをの祓ぞ |
| かたちはに ふはしらたちて むつましく |
形埴 二柱立ちて 睦まじく |
| これかみかたち |
これ神形 |
| かのなめは あのあかりもる |
カの嘗は 天の明り守る |
| ほつきなか みめにとくつき |
八月中 三陰に磨ぐ月 |
| いものこの さわおいわいて |
芋の子の 多を祝いて |
| なかつきは おおとしつける |
九月は 大年告げる |
| ここのみは かさねここくり |
菊の御衣 襲菊・栗 |
| ひとよみき こもちつきには まめおそふ |
一夜御酒 小望月には 豆を供ふ |
| もちよりさむる をかまつり |
十五日より騒むる 生姜祭 |
| まとかのなかの みはしらは かのかみかたち |
円の中の 御柱は カ の神形 |
| みのなめは そのめたえにて |
ミの嘗は その陰妙にて |
| かみなつき うめしりそけて しくれなす |
十月 大陰退けて 時雨なす |
| ややそこにみち をおつくす |
弥々底に満ち 陽を尽くす |
| かれををなむち かなつきに |
故ヲヲナムチ 十月に |
| ぬるておたきて もろかみに もちゐほとこし |
ヌルテを焚きて 諸守に 餅飯施し |
| しもつきは ややめかのほる しもはしら |
十一月は 弥々陰が昇る 霜柱 |
| ひらきはつくさ つほみさす |
柊初草 蕾(つぼみ)差す |
| はによりかせの ひとゐたつ これかみかたち |
埴より風の 一射立つ これ神形 |
| ひとせこれ ゑとにはんへる みそのかみ |
一年これ ヱトに侍る 三十の神 |
| ひひにかわりて むそかもる |
日々に替わりて 六十日守る |
| むわのなめこと うつろゐの |
六還の嘗事 ウツロヰの |
| としこえせまえ おおみそか |
年越瀬前 大晦日 |
| はつむかそよか さのみそか |
初六日・十四日 五月の三十日 |
| すへひとせもる なめことそこれ |
総べ一年 守る 嘗事ぞこれ |
|
|
| かくゑとの とさきのゆえは |
かく兄・弟の 弟先の故は |
| あめみをや のりしてゑかみ ふゆおもり |
天の御祖 宣してヱ神 冬を守り |
| とかみはなつの そろおもる |
ト神は夏の 繁を守る |
| なかくひとくさ うるほせは |
長く人草 潤せば |
| かみになそらえ とのたまに |
神に擬え トの魂に |
| なつくやまとの のとなれは |
名付くヤマトの 宣なれば |
| いまさらかみの みことのり |
今新守の 御言宣 |
| うけてさたむる みちとけは |
受けて定むる 道説けば |
| しかおちこちの ももつかさ |
シガ遠近の 百司 |
|
|
皆な文染めて 帰るこれかな |
| はにまつりのあや |
埴政りの文 |
| やつくりの のりはあまてる |
屋造りの 法はアマテル |
| かみのよに あめのみまこの みことのり |
神の代に 天の御孫の 御言宣 |
| をこぬのかみの うなつきて |
ヲコヌの守の 頷きて |
| にはりのみやの みやつくり |
ニハリの宮の '宮造り |
| のりおさたむる そのかみは |
法 を定むる その神は |
| くにとこたちの かみのよに |
クニトコタチの 神の代に |
| むのたみめより むろやなる |
ムのタミメより ムロ屋成る |
| まつはおならし すきはしら |
先ず地を平らし 直き柱 |
| むねおかつらに ゆひあわせ |
棟を上面に 結ひ合わせ |
| かやふきすみて このみはむ |
萱葺き住みて 木の実食む |
| をしゑおたみに ならはせて |
教えを民に 習わせて |
| くにとこたちの かみとなる |
地床立の 神となる |
| これよりさきは あめつちの |
これより先は 天地の |
| なりてあれます みなかぬし |
成りて現れます 御中主 |
| ふそよにうめる たみくさの |
二十世に生める 民草の |
| あなにすまえは ひとならす |
穴に住まえば 人ならず |
| くにとこたちの むろやより |
クニトコタチの ムロ屋より |
| みやとのつくる はさらたみ |
宮殿造る ハサラ民 |
| ゐためたたるの おりあれは |
傷め祟るの 折あれば |
| これのそかんと おほすなり |
これ除かんと 思すなり |
|
|
| まさにしれ まつひきのりは はおならし |
正に知れ 先ずひき法は 地を平らし |
| かしきのゆうお なかにたて |
赤白黄の木綿を 中に立て |
| ましろのゆうお きねにたて |
真白の木綿を 東北に立て |
| かしろのゆうお つさにたて |
赤白の木綿を 西南に立て |
| あしろのゆうお きさにたて |
青白の木綿を 東南に立て |
| きしろのゆうお つねにたて |
黄白の木綿を 西北に立て |
| としのりたまめ やまさかみ |
トシノリタマメ ヤマサ守 |
| をころのかみも はにまつり |
オコロの守も 地に祀り |
| としつきひひの もりはこれ |
年月日々の 守はこれ |
| もしやよこまの さはいせは |
もしや汚曲の 障いせば |
| あらかねのはお うつろゐの |
粗金の埴を ウツロヰの |
| うをまさかみの まさかりや |
大将守の マサカリや |
| このはかまろは はひきなす |
この真黄磨は 地掃なす |
| なまろくろまろ あすはなす |
鉛磨・黒磨 あす地なす |
| あかまろゐくゐ しろまろは よものつなかゐ |
赤磨打杭 白磨は 四方のつなかゐ |
| きかまろは たるはおふきて ゐかすれは |
黄赤磨は 惰る地を奮きて 活かすれば |
| すへてふくゐの かなまろの |
総てふくゐの 金磨の |
| ななのきたひの いくしまや |
七の鍛の イクシマや |
| たるしまかみと ふきなする |
タルシマ守と ふき撫ずる |
| かとはくしとよ いわまとの |
門はクシ・トヨ イワマトの |
| かみのゆきすき すきとほる |
守の 活き繁き 優き徹る |
|
|
| をこぬのかみの ほつまのり |
ヲコヌの神の ホツマ法 |
| しきますきみお いかすれは |
敷きます君を 活かすれば |
| たとひきねまに さはなすも |
たとい東北魔に 障なすも |
| へらよりきたふ かたたかひ |
穢方よりきた傾ふ 方違ひ |
| あらかねのはお とくねれは |
粗金の埴を とく錬れば |
| かみのめくみに かなふなる |
神の恵みに 適ふなる |
| このやつくりの ほつまのり |
この屋造りの ホツマ法 |
| ゐくゐつなかゐ はひきして |
打杭つなかゐ 地掃して |
| あすはふくゐの はしらたて |
映地ふくゐの 柱立て |
| むろやみやとの たみのやも |
ムロ屋・宮殿 民の屋も |
| むねはたかまの はらまても |
棟はタカマの ハラまでも |
| ちきたかしりて さわりなし |
千木高知りて 障り無し |
| しもはちひろの いしすえの |
下は千尋の 礎の |
| はしらはちたひ ねつくまて |
柱は千度 根接ぐまで |
| しきますきみの なからえお |
敷きます君の 長らえを |
| まもるはさらの かみしつめ |
守るハサラの 神統め |
| これすみよしの ゐかすりお |
これ住吉の 活かすりを |
| をこぬのかみの とくのりと |
ヲコヌの神の 説く法と |
| まつりのふみに もうしてもうす |
祀りの文に 申して申す |
| としうちになすことのあや |
年内に為す事の文 |
| あるひこふ ゑおこのかみと をもひかね |
ある日請ふ ヱオコの神と ヲモヒカネ |
| いちゐたたせは たまきねの |
いちゐ質せば タマキネの |
| このなすことお のたまわく |
九の為す事を 宣給わく |
| ゑはねのみつの ひとをかみ |
ヱは陰の三つの 一陽神 |
| ひのみちささけ ねにかえす |
日の道繁々げ 北に返す |
| ひとをふせても あめわゆき |
一陽伏せても 天地幸 |
| とのかみおして うゐなめゑ |
トの神をして 初嘗会 |
| しわすれはやや つちにみち |
しわすれば弥々 土に満ち |
| よろきねうるひ うゑさむく |
万木根潤ひ 上寒く |
| すゑにひたけて そらさむく |
末に開けて 空寒く |
| かたちはゑみつ をのはしら |
形埴・合・水 陽の柱 |
| ゑもとのかみの わかるよは |
ヱ元の神の 別る夜は |
| ゐりまめうちて おにやらゐ |
煎り豆打ちて 鬼遣らい |
| ひらきゐわしは もののかき |
柊鰯は モノの垣 |
| ほなかゆつりは しめかさり |
穂長譲葉 注連(しめ)飾り |
| ひはつさかせの ふつをかめ |
ヒは西南風の 二陽神 |
| きたれはひらく はつひくさ |
来たれば開く 初日草 |
| はつひまつりは ふとまかり |
初日祭は ふと環り |
| やまのかやくり うみのめも |
山の榧・栗 海の布も |
| ところたちはな ゐもかしら |
トコロ・橘 芋頭 |
| しむのふしゑは たるむつみ |
シムの節会は 足る睦み |
| ゆみはりまつる みそのなは |
弓張り(7日)祭る ミソの菜は |
| ぬゑあしもちか かさくさお |
ヌヱアシ餅が かさくさを |
| こけふはこへら ゐたひらこ |
ゴゲフ・ハコベラ イタヒラコ |
| すすなすすしろ すせりなつ |
スズナ・スズシロ スセリ・ナヅ |
| このななくさに のそくなり |
この七種に 除くなり |
| もちのあさほき あつきかゆ |
十五日の朝祝ぎ 小豆粥 |
| さむさにやふる わたゑやみ |
寒さに破る 腑穢病 |
| さやけをけらに とんともち |
清掛朮に どんど餅 |
| ゑさるかみあり きさらきや |
穢去る神あり 二月や |
| こりゑこころみ むままつり |
こりゑ試み 馬祭り |
| よろきひいつる かみかたち |
万木秀づる 神形 |
| たはきそらてる みつをかみ |
タは東空照る 三陽神 |
| きさらきなかに みつをきて |
二月中に 三陽来て |
| あおひとくさお うるおせは |
青人草を 潤せば |
| いとゆふのとか やよゐきて |
いとゆふ長閑 弥生来て |
| ももさきめをの ひなまつり |
桃咲き女男の 雛祭り |
| くさもちさけに ひくゑもせ |
草餅酒に 祝く妹背 |
| やよゑなかすえ かけらうや |
三月中・末 陽炎や |
| めつたりおさむ たもとかめ |
三つ垂り収む タ元神 |
| めはつねにすむ みつのかみ |
メは西北に住む 水の神 |
| うつきはうめの をおまねく |
四月は大陰の 陽を招く |
| さなゑあおみて なつおつく |
稲苗青みて 夏を告ぐ |
| なかわたぬきて つきすえは |
中綿抜きて 月末は |
| あおひかつらの めをまつり |
葵・桂の 夫婦祭り |
| ふたはにのほる さつゆつき かつみのつゆや |
双葉に上る 栄露月 かつみの露や |
| のりくらへ ゐゐのつつたち めをのほき |
乗り競べ 五五のツツタチ 女男の祝ぎ |
| ゐわたちまきや めもとかみ |
五腑茅巻や メ元神 |
| とはさにゐます めやわかみ |
トは南に坐す 陰和神 |
| みつのひかりの はにとほり |
三つの光の 地に通り |
| ひのめちかきる さつきなか |
冷の充ち限る 五月中 |
| ひとめふしおき さみたるる |
一陰伏し置き 五月雨るる |
| よろのあおはの かせかほる |
万の青葉の 風薫る |
| みやにうくれは なからゑり |
身・家に受くれば 長らえり |
| めははにみてと うゑあつく |
陰は地に満てど 上 熱く |
| みなつきすえは いよかわき |
六月末は いよ乾き |
| ももにちまつる ちのわぬけ |
桃に繁まつる 茅の輪抜け |
| ゐそらおはらふ みなつきや |
ヰソラを祓ふ 六月や |
| かたちはくにの なかはしら |
形は地の 中柱 |
| まてにととなふ ともとかみ |
左右に調ふ ト元神 |
| ほはきねにすむ ふためかみ |
ホは東北に住む 二陰神 |
| あふつきふめお あにやわし |
七月二陰を 天に和し |
| あきかせつけて まをまゆみ |
秋風告げて 真麻・真弓 |
| ゐとおつむきて たくはたや |
糸を紡ぎて たぐ機や |
| あわのほきうた かちにおし |
陽陰の祝ぎ歌 かちに押し |
| しむのもちほき ゐきめたま |
シムの十五日祝ぎ 生霊魂 |
| おくるはすゐゐ ゑなかのり |
上くる蓮飯 胞衣が法 |
| あをきおとれは あゐうくる |
仰ぎ踊れば 天気受くる |
| はつきはしめは ふためさく |
八月初めは 二陰栄く |
| あらしくさふす うかほきの |
嵐草臥す ウカ祝の |
| ほつみならふる ほもとかみ |
果実並ぶる ホ元神 |
| かはにしそらの をあけかみ |
カは西空の 陽別神 |
| はつきなかより みめのとく |
八月中より 三陰の磨ぐ |
| にたこもちつき ゐもはつき |
熟小望月 芋果月 |
| なつきみつきの ここなさき |
九月満きの 菊(ここな)咲き |
| をほとしきくの ちりわたこ |
大年菊の 散り綿子 |
| ささけてまつる くりみさけ |
ささげて祭る 栗見酒 |
| もちまえまつる ほからつき |
十五日前祭る 朗ら月 |
| まめやかうたゑ かみおとり |
豆夜明宴 香味踊り |
| かたちあかるき かもとかみ |
形分るき カ元神 |
| みはきさにすむ そのめふり |
ミは東南に住む その陰ふり |
| をかみしりそく はつしくれ |
陽神退く 初時雨 |
| ややめもみちて なかころは |
弥々陰も満ちて 中頃は |
| をのかみつきて かみなつき |
陽の神尽きて 神無月 |
| ねのつきつゆも しもはしら |
十一月露も 霜柱 |
| こからしふけは きはみおち |
木枯し吹けば 木葉実落ち |
| ひらきはつくさ めはるなり |
柊初草 芽張るなり |
| かたちかせもつ みもとかみ |
形風没つ ミ元神 |
| かくめをおもる そのなかに |
かく陽陰を守る その中に |
| とはみなみむく ひとくさの |
トは南向く 人草の |
| ことほきのふる このゆゑに |
寿伸ぶる この故に |
| とはのとうたの はしめそと |
トは宣歌の 初めぞと |
| つねなすことに あめおしるなり |
常為す事に 陽陰を知るなり |
|
|
|
|
| つきしほうみて みかつきの のちのひまちや |
月潮終みて 三日月の 後の日待ちや |
| いさきよく たかゐにえませ たまいつつ |
潔く 互いに笑ませ 給いつつ |
| わかひにむかゐ おわします |
若日に向い 御座します |
| あめのはつひの みかけさす |
天の初日の 御影 射す |
| ふたかみおもゐ はからつも |
二神 思い 計らずも |
| ひかりおゐたく ここちして |
光を抱く 心地して |
| みたけうるおゐ はらみます |
満たけ潤い 孕みます |
| つきみつころも あれまさす |
月満つ頃も 生れまさず |
| こころつくしも やとせふり |
心尽しも 八年経り |
| はれわたる わかひとともに あれまして |
晴れ渡る 若日と共に 生れまして |
| おほよすからの ことほきも |
おほよすがらの 言祝ぎも |
| みたひにおよふ こゑよろし |
三度に及ぶ 声喜し |
| かねてたまもの いちゐのえ |
予て賜物 一位の枝 |
| ここりひめ みゆとりあけて |
ココリ姫 御湯取り上げて |
|
|
| あまねきかみの あれのとき |
遍き神の 生れの時 |
| あめにたなひく しらくもの |
天に棚引く 白雲の |
| かかるやみねの しらたまの |
架かる八峰の 白玉の |
| あられふれとも あめはるる |
霰降れども 天晴るる |
| みつのしるしお しらぬのに |
瑞の徴を 白布に |
| やとよのはたの よよにたつ |
八豊の幡の 代々に立つ |
| すへらのみこの はしめなりけり |
皇の御子の 初めなりけり |
| あなかしこあな |
あなかしこあな |
|
|
| ほつまきみ かつらきやまの やちくらの |
ホツマ君 葛城山の 八千座の |
| みそきもみちて かつらきの |
禊も満ちて 桂木の |
| てくるまなして むかえんと |
出車成して 迎えんと |
| はらみやまとに つたゑよる |
ハラミヤマトに 伝え寄る |
|
|
| たらちねのゆめ さめまして |
タラチネの夢 覚めまして |
| まみえあかつき ををきみの |
見みえ暁 太君の |
| みまこおいたき たてまつり |
御孫を抱き 奉り |
| てくるまにゑて みゆきなる |
出車に合て 御幸成る |
| ひおへてくにに いたります |
日を経て国に 到ります |
| みこのよそゐの ひたかみや |
御子の他所居の 日高見や |
| ひかりかかやく わかひとの |
光 り輝く ワカヒトの |
| をしてわみこの ゐむなのり |
ヲシテは御子の 斎名・乗り |
| たらちねかみわ おそれまし |
タラチネ神は 畏れまし |
| あわのみやにわ そたてしと |
「アワの宮には 育てじ」と |
| あめにおくりて かえります |
天に送りて 帰ります |
| あめつちさるも とおからつ |
天地離るも 遠からず |
| ひことにのほる とゆけかみ |
日毎に上る トユケ神 |
| あめのみちもて さつけます |
陽陰の道以て 授けます |
| わかひとふかく みおつくし |
ワカヒト深く 身を尽し |
| みこころととく ひさかたや |
御心届く 久方や |
| むそよつむちの おをひるめ |
六十万つ六千の 大日霊 |
| ふつくにうれは すへらきの |
悉くに得れば 皇の |
| よよのまつりお しろしめす |
万々の政りを 知ろし召す |
| くしたえとおる ひのくらい |
貴妙徹る 日の位 |
| ひるめとともに あまてらす |
日霊と共に 天照らす |
| うみはかりなき ひとくさの |
生み計りなき 人草の |
| ふつくにそたつ くしたまの のりもてうつす |
悉くに育つ 奇魂の 法もて写す |
| くにうとの あまてるかみと よろこひの |
地人の 天照神と 喜びの |
| まゆもひらくる ゐひならし |
眉も開くる 言ひ慣らし |
| たらちねかみわ たたひとり |
タラチネ神は ただ一人 |
| ゐもをせかみの ひおうみて |
妹背神の 霊を生みて |
| ねのくにの ゑひめさすらや |
根の国の 姉姫流離や |
| おとさすら |
妹(おと)流離 |
| たかまのはらの ををみやめ |
タカマの原の ヲヲミヤ姫 |
| とよはたすけや ここたえの さくらたに |
トヨハタスケや ココタエの サクラタニ |
| たきつせのめわ せおりつめ |
滾つ背の女は セオリツ姫 |
| おとわかさくら |
弟ワカサクラ |
| つきわうなはら やおあいの |
次は海原 八百会の |
| はやあきつめや ここたえの |
ハヤアキツ姫や ココタエの |
|
|
| ををなむち すくなひこなも ともともに |
ヲヲナムチ スクナヒコナも 共々に |
| くにくにめくる おりしもに |
国々廻る 折しもに |
| かてつくたみに うしのしし |
糧尽く民に 牛の肉 |
| ゆるすそのたに ゐなむしの |
許す稲の田に 厭虫の |
| おゑるなけきの ををなむち |
穢える嘆きの ヲヲナムチ |
| あめやすかわの わかひるめ |
天ヤスカワの ワカヒルメ |
| とえはこたえの をしゑくさ |
問えば答えの 教え草 |
| をしてあふけは たちまちに |
ヲシテ仰げば 忽ちに |
| はふむしいにて いなくさわ |
蝕虫去(い)にて 稲草は |
| やはりみのりて わかかえる |
やはり実りて 若返る |
| かみわたかてる したてるの |
神はタカテル シタテルの |
| としのめくみの おおんかみ |
歳の恵みの 大御神 |
| ひたるのときに たまふなわ |
ひたるの時に 賜ふ名は |
| あゆみてるめに したてると |
アユミテル姫に シタテルと |
| さたのたかめは たかてると |
サタのタカ姫は タカテルと |
| さつくるわかの たまつみや |
授くるワカの タマツ宮 |
| をしてのこして かくれます |
ヲシテ残して 隠れます |
| さたわいやます みこみまこ |
サタは弥増す 子孫 |
| ももやそとめる ををなむちかな |
百八十富める ヲヲナムチかな |
|
|
| かわりなけれは としよりて |
変わりなければ 年寄りて |
| そのたのしあり ここなしの |
その楽しあり 菊(ここなし)の |
| かるることくに かんはしく |
枯るる如くに 芳しく |
| よろとしふれは まかるみの |
万歳経れば 罷る身の |
| ここなのことく かほるなり |
菊の如く 香るなり |
|
|
| ひめなんち せなのみのたけ いくはくそ |
姫、汝 背なの身の丈 幾ばくぞ |
| ひめのこたゑは かねてしる |
姫の答えは 予て知る |
| そふたいゆひは あまてらす |
十二尺五指は 天照らす |
| かみのみたけと わかせこと |
神の身丈と 我が背子と |
| いとかけまくも おなしたけ |
いとかけまくも 同じ丈 |
| おほふうれしさ またあらし |
覚う嬉しさ またあらじ |
| たかえあわせし ゑみすかほ |
違え合せし 笑みす顔 |
| そのときあるし みあゑして |
その時主 御饗して |
| こもりもてなす ものかたり |
コモリ持て成す 物語り |
| わかみのたけは そむたあり |
我が身の丈は 十六尺あり |
|
|
| いかつちか ととろきとほる いさおしお |
雷が 轟き徹る 功を |
| よよのかなめの いしつつに |
揺の要の 石槌に |
| かふつつつるぎ たもふなり |
枯断剣 賜ふなり |
| みかつちの なりわたるなの ゆみとりの |
ミカツチの 鳴り渡る名の 弓取りの |
| もののへかみの かなめいし |
物部守の 要石 |
| ときわにまもる あまかみの |
常磐に守る 天神の |
| よよのみそきの さきかけは |
世々の禊の 先駆けは |
| ふつぬしかみも ならふなりけり |
フツヌシ神も 倣ふなりけり |
| かしまたち ひなふりのあや |
カシマ立ち ヒナフリの文 |
| きつくここのえ たまかきの |
築く九重 玉垣の |
| うちつのみやに くらへこし |
内つの宮に 比べ越し |
| あめのうたえわ かふのとの |
天の治えは 代の殿 |
| たたすわみこの おもゐかね |
直すは御子の オモヰカネ |
| かみはかりして ゑりたたす |
神議りして 襟正す |
| そのときに にしにさむらふ ひるこみや |
その時に 西に侍らふ ヒルコ宮 |
|
|
| ぬはたまの あかおはなるる みしおあひ |
ぬばたまの 垢を離るる 潮浴び |
| みことゑひすの たたしみて |
御子とヱビスの 直し見て |
|
|
タマキの作る 教え種 |
| あまかみまねく みはしらき |
天神 招く 御柱木 |
| にこころうつす うつわもの |
中心写す 器物 |
| そのみかたちに すすめこふ |
その神形に 進め乞ふ |
| ふかきむねある そめふたお |
深き旨ある 染札を |
| まかせたまわる にふのかみ |
委せ賜る 熟の守 |
| ここにひるこは ゐものしに |
ここにヒルコは 鋳物仕に |
| かなあやゐさせ あまねくに |
金紋鋳させ 遍くに |
| おしゆるみなも わかひるめ |
教ゆる御名も ワカヒルメ |
| にふのゐさおし ををいなるかな |
熟の功(ゐさおし) 大いなるかな |
| よつきふみ いきすのあや |
世嗣文 息為の文 |
| つついすす ももゑふそやほ ほつまくに |
二十五鈴 百枝二十八穂 ホツマ国 |
| かしまのみやの みよつきに |
鹿島の宮の 御世嗣に |
| つはやむすひの みまこなる |
ツハヤムスビの 御孫なる |
| こことむすひの わかみこの |
ココトムスビの 若御子の |
| あまのこやねの ひととなり |
アマノコヤネの 人となり |
| あめのみちゑて みやはせの |
陽陰の道得て 宮は背の |
| つきこほしさに かしまたち |
嗣子欲しさに 鹿島発ち |
| かとりにいたる ものかたり |
香取に到る 物語り |
| こたうふつぬし さほしかに |
応うフツヌシ 直御使に |
| むかふおりふし はかりしる |
迎ふ折節 計り知る |
| かよふなさけの おもひあり |
通ふ情けの 思ひあり |
| いまよりむちの ことなさは |
今より貴の 子となさば |
| われももふけの このことし |
我も儲けの 子の如し |
| ともにのほりて なかうとと |
共に上りて 仲人と<ならん> |
| あめのなかくに みかさやま |
天の中国 三笠山 |
| ととにかたれは ととのひて |
父に語れば 調ひて |
| あめにうかかふ このよしも |
'天に伺ふ この由も' |
| おかみよろこふ みことのり |
祝かみ喜ぶ 詔 |
| ましはりかえる ちなみあひ |
交わり帰る 因み合ひ |
| ことほきおはり むつましく |
言祝終わり 睦まじく |
| こやねはあめに つかえます |
コヤネは天に 仕えます |
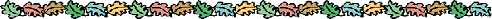



 (私論.私見)
(私論.私見)


![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)