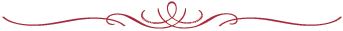
| 田中角栄の妻及び愛人との絆考 |
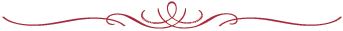
更新日/2018(平成30).6.19日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここで、角栄の妻及び愛人との絆について考察しておく。 2012.10.03日 れんだいこ拝 |
| れんだいこのカンテラ時評№1068 投稿者:れんだいこ 投稿日:2012年10月 3日 |
| 田中角栄の妻及び愛人との絆考 一般に、人を評するには、当人が言っていることよりも為していることに注目すべきだろう。しかもそれを凡そ10年ごとのスパンで長期に亘って追跡すれば、自ずとその人の人となりが浮き彫りになって来る。人の言説は平素の饒舌で測るものではない。ここ一番のいざ鎌倉の肝腎の時の言動で捉えるべきである。現代人は、昔の人が持ち合わせていたこういう秤(はかり)を忘れて、平素の無責任な饒舌で善人悪人、敵味方、能力を測ると云う貧困な知性を披歴している。 れんだいこも含めて或る人を測るには、昔の人の秤で天秤にかけた方が賢明であるように思われる。その上で、貫目を測る為の表ワザ、裏ワザを使うべきである。表ワザとは、対象とする人の本業としての仕事ぶり、その際の能力を観察することである。裏ワザとは、対象とする人の血筋(血統)、妻子関係、愛人関係を観察することである。付録ワザとして気質、人格、学歴、趣味、読書、性癖の傾向等を観察することである。 以上を前置きとして、ここで、田中角栄の妻及び愛人との絆について考察してみる。興味深い田中角栄の人となりが判明するからである。思いつくままに記すので、正確には今後書き直したり付け加えたりすることにする。只今はスケッチとして書き遺しておく。 角栄は、1942(昭和17) 年3月3日、24歳の時、家主の娘・坂本はな(八十子、以下「ハナ」と記す)と結婚している。ハナは当時31歳で、角栄より8歳年上であった。且つ離婚歴があり9歳になる女の子を連れ子として云わば出戻りしていた。角栄は、ハナのつつましやかな挙動と、内に秘められた芯の強さに惚れ結婚することになる。このハナが糟糠の妻となる。 興味深いことは、結婚時、次のような「三つの誓い」をさせられたと伝えられていることである。それは、「一つ、出て行けと云わぬこと。二つ、足蹴にしないこと。三つ、将来、角栄が二重橋を渡るときは彼女を同伴すること。その三つを守ってくださるなら、それ以外のことについては、どんなつらいことにも耐えてついていきます」。この約束が角栄夫婦の契りとなった。 何気なく見落としてしまうが、「三つの誓い」の中に、「将来、私が二重橋を渡るときは彼女を同伴すること」とあるのをどう理解すべきだろうか。当時、角栄は、飯田橋2丁目にあった建築業者坂本氏の家の一部を借り受け、田中建築事務所を開設して半年足らずの頃である。いくら新進気鋭の建築家として頭角を現しつつあったとしても、その角栄が将来「二重橋を渡る」などと発想すること自体、ハナ以外には誰も予想し得なかったであろう。 これを逆に云えば、ハナは、8歳年下の角栄に何を認めていたのだろうか。どこにそのような片鱗があったのだろうか。女性の直感が恐ろしいにしても、24歳の建築家の駆け出しを「将来、二重橋を渡る人」と見染めたハナの予知能力は異能過ぎよう。この予知能力が当るのだから歴史は面白過ぎる。 角栄夫婦の間には、この年の11月、長男・正法が誕生している。1944(昭和19)年、角栄26歳の時、長女真紀子が誕生している。こうして1男1女を授かったが、長男・正法は1947(昭和22)年、5歳で死亡している。この時、角栄は次のように述懐している。 「その時に俺はしみじみと考えたんだ。妹の時にしろ、長男の時にしろ、後に残った自分が、いつも十分なことをしてやれなかったという悔いを感じた。生きているうちに家族にも、友人にもできるだけのことをしてやりたいという気持ちが一層強くなった。人の為になるように生きたいと思った」(戸川猪佐武「君は田中角栄になれるか」)。 後に、幹事長時代の年少当選組の小沢一郎を見て正法を彷彿とさせ、以降、手塩にかけて育てたのは有名な話である。他にも当選組はあまたいたが、角栄は小沢一郎に何を見染めたのだろうか。こういうところも興味深い。 もとへ。角栄は、生涯この「三つの誓い」を守る。但し、気づくことがある。普通の夫婦がする如くの「浮気はしない」なる誓いがないことである。これもハナの凄いところであろう。ハナは、男の浮気については別の物差しを持っていたようである。事実、「三つの誓い」の中に浮気禁止項目がないこともあってか、角栄はこの方面でも約束を守る。それはあたかも男の甲斐性としていた感がある。ちなみに、ハナの連れ子の子育てについても角栄は十分な配慮を見せ隔てなく育て上げている。これについての詳細は略すが、この親ワザもできそうでできないのが世の常であることを考える時、立派と評すべきだろう。 角栄はその後、ひょんな機縁から政界入りする。建築家としての業績は順風満帆であり、以降暫くの間、二足のわらじを履くことになる。但し、次第に政界で頭角を現し始め、政治家稼業に一本化することになる。党の要職履歴は次の通りである。 1957年、39歳の時、岸内閣で郵政大臣に就任、戦後最年少大臣となる。1958年、40歳、自民党党紀委員、党新潟県連会長に就任。1959年、41歳、自民党副幹事長に就任。1961年、43歳、池田内閣で自民党政調会長に就任、初の党三役入りする。1962年、44歳、大蔵大臣就任。この時大平が外務大臣となり田中-大平コンビが誕生している。1963年、45歳、大蔵大臣留任。1964年、46歳、佐藤内閣で大蔵大臣留任。1965年、47歳、自民党幹事長(1期目)に就任。1966年、48歳、幹事長留任(2期目)。但し一連の政界黒い霧事件で川島副総裁と共に幹事長を引責辞任する。1967年、49歳、自民党都市政策調査会長に就任。1968年、50歳、自民党米価調査会会長に就任。日本列島改造論の原型である「都市政策大綱」を発表。自民党幹事長に再度就任(3期目)。1970年、52歳、自民党幹事長に留任(4期目)。自民党代表選で佐藤首相が4選され自民党幹事長に留任(5期目)。1971年、53歳、参院選敗北の責任を取り幹事長辞任。通産大臣に就任。1972年、54歳、田中派旗揚げ(衆院40名、参院41名)。「日本列島改造論」を発表。第64代内閣総理大臣に就任。1974年、56歳、2年余886日間の政権の座から降りる。 この間、角栄は、二人の愛人を囲っている。一人は元神楽坂芸者の辻和子、もう一人は越山会の女王と評された佐藤昭子である。辻和子は、「熱情ー田中角栄をとりこにした芸者」(講談社、2004年)、佐藤昭子は「私の田中角栄日記」(新潮社、1994年)、「田中角栄ー私が最後に伝えたいこと」(経済界、2005年)を著している。それぞれに何人の子がいるかと云う下世話な話しはさておき、注目すべきは、この二人の女性が、著書の題名からも窺えるように終生、田中角栄を支持し抜いて生を全うしたことである。 この角栄を取り巻いたハナ、辻和子、佐藤昭子の3人は、角栄の権勢絶頂期に奢り昂ぶる訳でもなく、角栄の失意期に手のひらを返す訳でもなく、終生、角栄との絆を大事にした。ロッキード事件以降の角栄バッシングの喧騒下、ハナは妻であるからともかく辻和子、佐藤昭子には相当の圧力が掛かり悪意の利益誘導があったと推定できる。 しかし見よ。この貴婦人は貴婦人たる誇りをも秘めてやんわりと峻拒し、返す刀で角栄との絆を大事に添い遂げた。こういう場合、この貴婦人が偉いのか、そもそもそういう女性を見染めていた角栄が偉いのか。恐らく双方が偉くて成り立つドラマであろう。くどくど述べないが世の社会事象とは一味違う絆を見る思いがするのは、れんだいこだけだろうか。 2012.10.3日 れんだいこ拝 jinsei/ |
| 【佐藤昭子の角栄評】 | |
|
| 【ハナの角栄との絆考】 | |
2019.5.4日、「執着しない田中角榮が唯一大事にしたモノ」を転載しておく。
|
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)