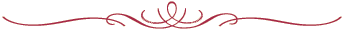
| 田沼意次の政治履歴考 |
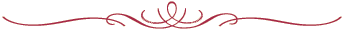
更新日/2022(平成31.5.1栄和元/栄和4).7.24日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここで、「田沼意次の政治履歴考」をものしておく。 2010.11.14日 れんだいこ拝 |
![]()
| 【田沼意次の政治履歴考】 | |
2022.7.23日、「田沼意次はワイロ政治家というより優秀な経済人? 評価の見直し進む」参照。
|
| 2021.4.25日、「田沼意知 暗殺!佐野政言が江戸城内で斬りつけて~まんが日本史ブギウギ200話」参照。 江戸時代に入って商工業やサービス業が発達し、人々の消費先は各種方面へ向かった。貨幣経済の発達。給料の基盤を【米】に頼っていた幕府や全国の大名は、それをいったんお金に換金するシステムに取り組まれている時点で不利であり、米の収穫高と物価や、税金などのコストを考えると、もはや限界に達しようとしていた。田沼意次と田沼意知の親子はそこにメスを入れ、商業での税収でもって幕府の財政を安定化させることに注力した。 商活動の活発化と、そこから上がる税収入――幕府や大名の財政安定化。【重商主義】と呼ばれる田沼意次の政策が、現代では評価が高まつている。田沼意次にとって不幸だったのは、この時期に【天明の大飢饉】が発生してしまったこと。日本は浅間山噴火、欧州はアイスランド噴火の影響で、全世界的に天候が悪化。幕府や諸藩の備蓄米対策は十分とは言えず、多くの死者を出した。田沼意知は愚人ではなかった。当時の在日オランダ商館長・ティチングが「父親の田沼意次は高齢だから、さすがにこれ以上の活躍は難しいけど、息子の田沼意知の時代に、改革を進められるんじゃない?」と『日本風俗図誌』に記している。その意知が非業の展開を迎える。 ◆ちょっと危ない人に見える、この佐野政言(まさこと)さん。 当時は旗本でしたが、そのご先祖様を辿ると佐野源左衛門常世に着きます。源左衛門とは、北条時頼を助けた人で、つまりは鎌倉時代から続く名門だったのですね。しかも、家系的に田沼親子は佐野政言の家来筋にあたるという、なかなか複雑な状況でした。 佐野政言は江戸城内で田沼意知を斬りつけ、重傷を負わせた。すかさず政言は揚座敷(あがりざしき・高位の旗本や僧侶などを収容する施設)へ送られ、田沼意知が亡くなると、切腹を命じられた。世間は、佐野政言を「世直し大明神」として称え、ついに田沼の心はポッキリ折れた。そして次にやってきたのが……田沼に代わって政治を担ったのが、家斉とは性格真逆のカタブツでした。ガチガチの倹約主義者・松平定信!せっかく田沼親子が進めた重商主義も、瞬時に瓦解。幕府も諸藩も財政が改善することなく幕末へと向かった。 |
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)