概要「思想とは、人々の営みを支える堅固な枠組みのこと。人間が考えついた物事のうち、時間や空間を隔てて、繰り返し使用に耐えるだけの耐久性を備えたものを、思想という。個々の人間の生き死にを越えて永続する文明の枠組み、それが思想であった。
近代以前の社会では、伝統や慣習や習俗が、このような枠組みを与えていた。
思想とは、思考の回路であり、専ら言語によって表明される。個々の利害関係を通関させて、それらを凌いだ価値や原理を見出し、人々を巻き込んでいく。時代を超え、時間を貫き、遠隔操作にも耐えうる。個々の人間の寿命は、思想の前には儚い。時間・空間を隔てた多数の人間達が、共通に帰属する言語で表明された思考の枠組みが、思想である。
法や宗教もその一種である。初めは民族的な出自と分かち難く結びついていた思想が、互いに競合していくうちに、多くの民族に共通な「大思想」に成長していく。ギリシャ思想、インド思想、中国思想、ユダヤ・キリスト教等々は、その代表例である。そのうち、ユダヤ・キリスト教は、史上最も力強く影響力を及ぼしつつ今日にいたって居る。
近代思想は、西欧の教会権力との闘いから生まれた。そういう意味では「宗教からの分離」が近代思想のメルクマールである。とはいえ、近代思想を生み出す母体となった面を軽視してはならない。
思想は、単なる知識ではない。思想を奉ずる者は、他の者から論争が仕掛けられた場合に、ちゃんと応答出来なければならない。これが思想に伴う責任であり、「responsible」とはそういう意味である。 |
| 「戦後日本は、GHQ権力を通じて「戦後民主主義」なるものを与えられた。憲法秩序を始めとする諸改革は、本国アメリカにも増した世界史上例の無い民主主義的諸権利を付与した。成年男女による投票制度、選挙による代議員選出、議会の常設、討論の奨励、多数決原理による意思決定、少数意見の尊重、決議に対する全員一致制、言論・思想・信条・結社・集会の自由、報道の自由、知る権利、人権諸権利の保障、憲法・法律による統治、多党政治等々。これらに貫く「手続き重視の思想」による「手続きによる正当化」主義、法の下の平等により不当な処罰、不利益を受けない。これらには、政治権力の暴力の抑止を狙っての、「政治の修羅場をくぐりぬけた現実的な大人の知恵が結晶」、「民衆が蒙る苦痛や悲惨を必要最小限に食い止めるための、ギリギリの工夫」が為されている」。 |
| 「実際に、民主主義を動かして見ると、あちこちでつじつまの合わない部分が出てくる。それを、めいめいが犠牲を払って、何とか体裁をつくろっていく。民主主義はポンコツ自動車のようなものだ。乗り合わせた乗客が、あちこち修繕したり、後ろから押したりしないと、動かないのである。かといって、これを乗り捨てようにも、他に適当な代わりが見つからない。そんなものだ」。「手続き上正しい決定であれば、それに従わなければならない、という過酷さも持つ」が、「たかが民主主義、されど民主主義」であり、「これよりましな政治の仕組みを、人類はまだ考え付いていないのではないか」。
|
| 「左翼は、体制の変革を目指す。政治・経済システムを現在のものと別なものに作り変え、されを自分達が動かして、もっとましな社会を実現しようとする運動のはずだ。実際にそういう大事業を為し遂げようというからには、今政治・経済を担当している人々と同等か、それを上回る実務能力や、現実感覚がなければつとまらないだろう。ところが、日本の左翼はなぜか、体制に反対することには熱心でも、社会の現実をトータルに受け止め、責任ある対応をしていこうという気迫や現実感覚が見受けられない。一体、政権をとる気があるのかと、疑いたくなってしまう。日本の左翼は、現実的な政治勢力である以前に、象徴的な反対勢力、現実性の無い空理空論を振り回すことに存在理由を見出す思想的・文化的反対派なのであった。大勢に反抗することだけで、自分のアイデンティティを保っている勢力は、結局のところ体制に依存していると言わざるをえない。そういう情けない存在が、日本の左翼だ」。 |
| 「体制に依存しているのに、体制を肯定しきれない−日本の左翼は、こういう中途半端な心理を基盤にしている。こういう心理からは、うまく理屈にならないが、とにかく体制は肯定しなければならない、とする現実主義者と、理屈からすれば体制を否定するしかないはずだというところにこだわる左翼の、二類型が生まれる。(その他興味深い類型として、もう一つ、右翼があるけれども、省略。左翼は、現実の片面だけを増幅するので、結果として、現実の全体像に向き合うことが出来ない。現在の体制からどれほどの人々がどれほどの抑圧を受けているのかを、理論的に指摘する(ということは、現実がどうなっているかということとあまり関係なしに)割に、実際自分達が政権をとったら、どういう政策体系を採用して、国家を運営していくのか、あまり熱心に論じない。それどころか、自分達が政権をとることなど、全く思いもよらないというのが、左翼の大部分の人々の実感であり、実態なのであった。結局、左翼の言説は、ささいな教条の違いや学理上の整合性をめぐる、神経質で際限の無い水掛け論に陥っていくことになりがちである」。 |
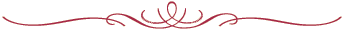
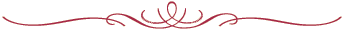
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)