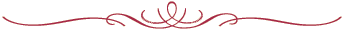|
2009. 3.10 「内憂外患」から 寄稿者は田中良紹氏です。
眉間にしわ寄せキャスターの番組は、昔から「もっともらしい嘘」を振りまくのが得意なのに何故か「報道番組」と称している。この前も某名誉教授が小沢秘書逮捕事件の感想を聞かれて、「政治に金がかかるのが問題だ。政治家はお金を使わずに節約をして生活することが出来ないのか」という趣旨の発言をしていた。そしてスタジオみんなが頷いた。「おかあさんといっしょ」程度の番組なら許される。しかし「報道番組」での発言である。これでは日本の政治は救われないと暗澹たる思いになった。
政治家の仕事は「国民の財産と安全を守る」ことである。日本人の財産を狙い、安全を脅かす他国から日本人を守るのが仕事だ。オバマ、プーチン、胡錦涛、金正日らと互角に渡り合って日本を守らなければならない。庶民のような生活を心がけるのも結構だが、そんなことを政治家に期待する感覚を他国の人間は持っているだろうか。それよりも政治には大事なことがあると思っているのではないか。オバマやプーチンや胡錦涛に庶民のような暮らしを期待する学者やジャーナリストが他国にいるとは思えない。
よく「選挙に金がかかりすぎる」と言う人がいる。そう言う人がいるために日本の選挙は民意を反映されない形になった。「金がかかりすぎるから」と言う理由で選挙期間は短くなり、お祭り騒ぎをやめさせられ、戸別訪問は禁止され、選挙カーで名前を連呼するだけの選挙になった。名前を連呼されて候補者の何が分かるのか。何も分からない。要するに「金がかかりすぎる」を口実に、国民に判断をさせない選挙になった。現職議員にとってその方が再選される可能性が高まるからだ。
選挙期間が十分にあり、戸別訪問を認めて候補者と有権者とが会話をし、国民を選挙戦に参加させるためにお祭り騒ぎをやれば、国民に政治に参加しようという意欲が生まれる。「それだと自分たちに不利になる」と世襲議員や年寄り議員は考える。より若く、情熱があって、意欲的な議員が選ばれる可能性が高まる。政権交代も起きやすい。それをさせないための仕掛けが「金のかからない選挙」という名目で行われた。
だから日本で選挙に金をかけるのは「悪」である。それに賛成したのが55年体制の野党だった。初めから政権交代を目指さない社会党にとって現状維持で何の問題もない。憲法改正をさせないために三分の一の議席だけを確保すれば良い。過半数は要らない。それが「金をかけない選挙」という思想と共鳴した。そして政権交代をさせたくない自民党と官僚とも利害が一致した。
学者などがよく言う「金のかからない選挙」とはイギリス型の選挙である。これは日本の選挙と全然違う。候補者が後援会を組織して金を集め、有権者に名前を売り込み、「選挙区のために働きます」と訴える選挙ではない。政党が選挙を行う。候補者は政党から選挙区を指定され、自分の名前ではなく政党のマニフェストを売り込む。戸別訪問で政党の政策を説明して歩く。「候補者は人間でなく豚でも良い」と言われるほど候補者は重視されない。だからお金はかからない。と言うか、すべてを党で面倒見る。日本共産党や公明党のやっている選挙がこれに近い。
しかし日本でやっている選挙はアメリカ型だ。アメリカ型はマニフェスト選挙ではない。候補者同士が競い合う。アメリカでは「選挙区のために働きます」と言って支持を訴える。支持者から献金を集め、多く集めた方が当選する。だから選挙は金集めの競争である。そのためにはお祭り騒ぎをやって有権者を政治に参加させる。選挙期間も勿論日本より長い。日本と違うのは選挙カーでの連呼ではなく戸別訪問が主体である。
大統領選挙は長期戦である。1年間の戦いを制するのは金の力である。候補者は企業からも個人からも団体からも金を集める。オバマはそれでヒラリーに勝った。ヒラリーは最後は私費まで投じたが、選挙を続けることが出来なかった。選挙民はその様子を見ながらリーダー足りうる素質を見極める。「政策の競争」などでリーダーの素質は見抜けない。資金集めとスキャンダル攻撃をどう乗り切るかの対応力でリーダーの素質を見分ける。
自民党の選挙はアメリカ型に近いのだが、日本で「金集め」は「悪」である。日本とアメリカ政治の何が一番違うかと言えば、政治と官僚の力関係である。アメリカは政治が官僚より優位に立ち、官僚をコントロールしている。日本では官僚が政治より優位にいて、政治が官僚にコントロールされる。官僚が最も嫌がるのは政治が力を持つことだ。そのため力の源泉になりかねない要素をことごとく封じ込めた。
メディアと野党を使って「政治が汚れている」キャンペーンを張り、自民党の力ある政治家を次々「摘発」した。今では自民党も官僚の言うことを何でも聞く「おとなしい子羊」になった。官僚の言うことを聞かない政治家を許さない。それが霞ヶ関の本音である。政権交代が近づいた今、その矢が民主党に対して放たれた。政治資金規正法と公職選挙法は警察と検察がいつでも気に入らない政治家を「摘発」出来る道具である。政治とカネの関係を見誤ると日本の政治は何時までも混迷を続けることになる。
以上 2年前に書かれたことが見事に的中している事に驚きますね。
|