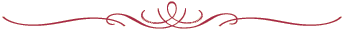
| 全日空の新機種選定への関与の問題 |
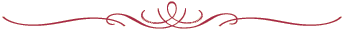
(最新見直し2007.3.19日)
れんだいこが下手に解析するより格好な以下の分析がある。新野哲也「角栄なら日本をどう変えるのか」には次のように書かれている。
この言は、次の「千葉大学教授・清水馨八郎教授談話」を下敷きにしている。
清水馨八郎教授は、「破約の世界史」(祥伝社、2000.7.21日初版)150Pの中で次のように述べている。
この言の確かさは、次の発言によって補強された。小山健一氏は、著書「私だけが知っている『田中角栄無罪論』」の中で、概要「関係者が生きているうちにどうしても言い残しておきたかった」との思いで「ロッキード社機購入前、全日空社長・若狭得治氏と約1時間半にわたる長電話をした時の会話」の内容を明らかにして、次のように記している。
これに関連して、池見猛・氏編著の「国益上、田中元首相の無罪を望む」は次のように記している。
|
| 【「まだ解けないロッキード事件」】 | |||||||||
200.02.29日付で「Mint/札幌/中山正志」氏が「時事問題、Mintインタネ街宣活動」の「まだ解けないロッキード事件」で、貴重な解析しているのでこれを転載しておく。
|
| 【徳本栄一郎氏の「国務省機密電8399」読みとり漫談考】 | |||||
相も変わらず「田中角栄有罪説」に凝り固まるジャーナリストの徳本栄一郎氏が、****.8.8日、「国務省機密電8399」をワシントンの公文書保管所で発見したと喧伝し回っている。同文書は、東京の駐日大使インガソルからワシントンの国務長官宛ての機密電報で、タイトル「日米貿易交渉のフォローアップ 日本による航空機購入の可能性について」とあり、「ジョンソン次官のみ閲覧のこと」、「担当者の許可なく複製を禁ず」と附されている。日本のANA(全日空)、JAL(日本航空)の大型航空機購入についての調査が、次のように報告されているとのことである。
これを受け、次のようにコメントしている。
|
| 【全日空の社歴】 |
| 1957.12月、前身となる日本ヘリコプター輸送株式会社と極東航空株式会社が合併して全日空(全日本空輸株式会社、All Nippon Airways(ANA))」が設立される。 1966年、羽田空港沖でのボーイング727型機の墜落事故、松山沖墜落事故と一連の連続墜落事故を起こす。遺族への慰謝料支払いによる出費など、経営面で苦境に立たされた。 経営不振に陥った全日空は、日本政府と大株主となった日本航空(JAL)の支援の元で、経営再建を進めることとなった。当時の日本航空は、ほぼ国営の航空会社と言っても良く、羽振りが良かった。政府と日本航空の支援を受けた全日空は、1970年代になると高度経済成長のおかげもあり業績を回復する。1972年に開催される札幌冬季オリンピックに向けて、大型旅客機を発注するまでに業績も回復した。 |
| 【全日空の新機種選定過程検証】 |
|
【ロッキード・ダグラス・ボーイング三社の航空機売り込み競争】 |
|
【ロッキード社の秘密対外工作】 この頃のロッキード社の経営状態を知っておく必要がある。橋本登美三郎運輸大臣がエアバス導入延期を発言した時期、その直前にはトライスターのエンジンを製造していた英国ロールスロイス社が倒産、国家管理に移されている。このためロッキード社は6500人の従業員を解雇、ニクソン大統領に緊急特別融資を直訴している。ロッキード社はニクソンの選挙区に本社を持っていたこともあってか、ニクソンはこの時異常とも言える熱意でロッキード社救援に動いている。ロッキード社に対する緊急融資陳情が「前例も制度も法律もない」ままに推し進められ、ニクソン政権のコナリー財務長官、パッカード国防次官はじめ米上下両院の有力議員への働きかけが功を奏し、その結果、上院で僅か1票差で緊急融資法が成立している。こうした流れが全日空の機種選定作業の一旦中止工作と並行しつつ進んでいた。つまり、ロッキード社の商戦勝ち抜きのお膳立てが日米合作で進められていたという背景が垣間見られる。 |
|
【サンクレメンテ会談】 |
|
【売り込み競争の結果】 |
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)