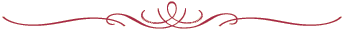
| 「嘱託尋問採用」問題考 |
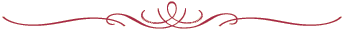
(最新見直し2008.8.19日)
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| 今日法秩序は根本のところで乱れに乱れている。その決定的嚆矢が、ロッキード事件の際に検察庁と最高裁判所が採用した「最高裁の不起訴宣明」と「反対尋問なき嘱託尋問による調書採用」ではなかったか。ここでは、「反対尋問なき嘱託尋問による調書採用問題」を採り上げる。 かの時、「嘱託尋問」の正当性を検察に代わって弁論しまくったのが立花隆であった。彼の言説を収拾し、俎上に乗せる必要がある。しかし、れんだいこは、ある種馬鹿馬鹿しくてその労を取らない。時間の無駄と思わぬどなたかがやってくれれば良いと思う。その必要は有る。誰もしなければ、追ってれんだいこがやる。 俵孝太郎氏の「田中裁判ーもう一つの視点」、秦野章・氏の「角を矯めて牛を殺すなかれ」その他を参照する。 2004.10.7日、2007.1.20日再編集 れんだいこ拝 |
| 【嘱託尋問採用の問題性】 | ||||
|
「ロッキード事件」を廻って、これほど司法当局の不法行為が露骨且つ満開された例はない。アンドリュー・ホルバート氏は、「田中角栄と日本人」の座談「田中角栄における日本的体質」の中で次のように述べている。
池見猛・氏編著「国益上、田中元首相の無罪を望む」は次のように批判している。
|
| 【嘱託尋問採用にまつわる問題点】 | ||||||||||||||||||||
「嘱託尋問問題」にまつわるいかがわしさは次の点にある。早くより俵孝太郎氏、石島弁護士が指摘し、渡部昇一も「角をしばるものは丸も三角も縛る」(「萬犬虚に吠える」、文春文庫p.160)と警句している。問題点を列挙しておく。
|
以上の疑問を持ちながら、以下、個別に考察する。
| その1、明文規定の無い法行為を率先履行 | ||||
|
東京地検と最高裁の連携プレーで「嘱託尋問」を米国裁判所に委託したが、嘱託尋問制は我が国の刑訴法に明文規定がない。こういう場合、「デューフロセスを守らなければ法治主義とはいえない」が、時の東京地検と最高裁が独断で「嘱託尋問」を推進した。こともあろうに法の番人ともあろう機関が明文規定のない法行為を平然とこれを犯したことになる。
|
| その2、「嘱託尋問の違法性その1、形式的是非問題 | ||
|
「嘱託尋問の形式的是非問題」について考察する。「嘱託尋問」の形式的是非とは、わが国の刑訴法に明文規定の無い「嘱託尋問」制度を導入することの違法性と合法性の問題である。つまり、「嘱託尋問の違法性問題」であり、我が国の裁判制度上、刑事訴訟法上、明文規定の無い「嘱託尋問」が認められるのかという問題である。「226条で証人尋問を請求された裁判官ないしは裁判所が、外国の裁判所に対し証人調べを依頼し証拠採集嘱託を出来るのか」、「公判裁判所が、外国の裁判所に証拠調べを嘱託する権限があるか」という議論になる。
このことに関しての法論争はかなり為されたようである。記録によれば、嘱託証人尋問調書が適法なのか、それとも違法なのか、の最も根源的な法律論争は、第一審の東京地裁においては3回に亘り、また 第二審の東京地裁においても3回行われている。つまり、この下級審においては6回に亘って、「日本の法に明文規定がない刑事免責を条件とする
嘱託尋問調書の法的正否」として複合的に争われることになった。
つまり、最高裁判決は、当時の検察の採用した手法を否定し、「嘱託証人尋問調書は違法」 と断じた。この間の法律論争となっていた 「刑事免責」 を完全に否定したものであり、検察側の非道・無法ぶりが暴かれた。こうして、後日になって、当時の手法の目的のために手段を選ばない手法に対して司法が決着させた。 |
||
| しかし、20年後のこの判決は、被告側にとって何の甲斐があろう。してみれば、角栄追討の為にのみ政治主義的に悪利用されたということになろう。これは法治精神ではない。しかも悪事例を作ったことになる。その後の司法は、この咎を負っていくことになろう。 |
| その3、嘱託尋問の違法性その2、内容的是非問題その1、「起訴免責」採用の是非 |
| 「嘱託尋問」そのものの形式的違法性に加えて、この時導入された「嘱託尋問」の内容的違法性問題もある。「嘱託尋問」手法を採用している米国では「刑事免責」(イミュニティ)と呼ばれて法律に規定もある。但し、特殊な規定であることによって厳重な制約が課せられている。「嘱託尋問」には、「起訴免責」(取引免責)と「証拠免責」(使用免責)の二通りがある。「起訴免責」(取引免責)の方が「証拠免責」(使用免責)に比べて包括的に免責される制度であり、証言者側優位であることになる。この時、検察が米国裁判所に依頼したのは「起訴免責」の方であった。よりによって「起訴免責」の方を採用した事にも大いに疑問が為されるべきである。 |
| その4、嘱託尋問の違法性その3、内容的是非問題その2、反対尋問無き起訴免責誓約の違法性 | |||||
| 驚くことにこの時、米国裁判所に委託された「嘱託尋問」は、「反対尋問権無き起訴免責による嘱託尋問」であった。こういうやり方は植民地法なら有り得るかもしれないとでも云うべき手法であり許されない。当然、アメリカの国内法にはこのような「反対尋問無き起訴免責誓約付き嘱託尋問」はない。「コーチャン証言」は、このような手法で引き出されたが果たして有効足りえるのかという問題がある。「反対尋問無き起訴免責誓約の違法性」という問題となる。
「起訴免責」の場合には、証言者側が包括的に免責されることが約束された上での証言引出し手法であるからして証言者側優位になり、被疑者側の不当な不利益発生を避けるための法の公平性の必要から、被疑者やその弁護人による反対尋問権を行使させるというのが要件とされている。ロッキード事件で採用された「反対尋問権無き起訴免責による嘱託尋問」という手法は凡そ法治国家に相応しくないものであり、なり振り構わぬやり方であった。後々のお笑いものである。 渡部昇一氏は次のように断言している。
この「刑事免責」に関して、元九州大学法学部教授の井上正治氏は、「田中角栄は無罪である」80Pで次のように解説している。ちなみに井上氏は、「不適法だが有効」説という立場に立っている。それにしてもとして次のように述べている。
石島泰弁護士は次のように断言している。
|
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)