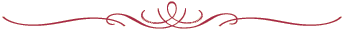
| 「不起訴宣明」、「嘱託尋問採用」問題考 |
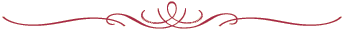
(最新見直し2007.1.20日)
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| 今日法秩序は根本のところで乱れに乱れている。その決定的嚆矢が、ロッキード事件の際に検察庁と最高裁判所が採用した「最高裁の不起訴宣明」と「反対尋問なき嘱託尋問による調書採用」ではなかったか。ここでは、「最高裁の不起訴宣明問題」を採り上げる。 俵孝太郎氏の「田中裁判ーもう一つの視点」、秦野章・氏の「角を矯めて牛を殺すなかれ」その他を参照する。 2004.10.7日、2007.1.20日再編集 れんだいこ拝 |
| 【最高裁の不起訴宣明書の違法性その1、検事総長による免責不起訴宣明書問題】 |
| ロッキード事件に関連して、検事総長は二回に亘って免責不起訴宣明書を米国の裁判所に提出している。免責とは、刑訴法248条の起訴便宜主義「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる」に基づいて、「コーチャンらが日本でどんな罪を犯していようと、自供すればその罪に就いて日本では起訴しない」というものであった。これは、贈収賄事件で「贈」の側を免訴にして「収」だけを罰しようとしており、日本法制史上初めての事例でもあった。 |
| 【最高裁の不起訴宣明書の違法性その2、最高裁による免責不起訴宣明書問題】 | |||
| 「最高裁による不起訴宣明書の是非」も問われねばならない。最高裁はこの時、米国裁判所の要請に従い「不起訴宣明書」を送付している。最高裁が「不起訴宣明書」を出すに至った経過にも問題が残されている。結果として、「反対尋問権無き起訴免責による嘱託尋問」を認可する「不起訴宣明書」を為しえる権限が果たして最高裁にあったのかどうか。 憲法第76条には、「すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される」と記されている。「世論を参考にせよ」とはどこにも書かれていないが、この時、最高裁は、「世論という名を借りたロッキード事件仕掛け人の意向」を聞き入れた。 「最高裁による不起訴宣明書問題」は、戦後憲法秩序としての三権分立制度、司法権の独立という観点に照らして汚点を残した。実際には、検事総長宣明書に対する最高裁長官の保証書簡という体裁を採っている。これに賛成したのは最高裁全員の13名対0、という数字だった。と同時に、何と署名者は藤村長官 只1人という曲芸といえるやり方で為されている。しかも、この時の藤村長官は第一審判決にもオーバーラン的コメントをして顰蹙を買っているというケッタイナ人物である。 この経過は次の通りであった。米国地裁の裁判官はコーチャンらを裁判所に出頭させたが、コーチャンらは、うっかりしゃべると贈賄側として日本で刑事訴追を受ける恐れがあることを理由に証言を拒否した。そこで、日本に「刑事免責」制度が無いことを踏まえた上で、「この不起訴の約束によるコーチャンらの証言調書の引渡しには、日本の最高裁のオーダー又はルールを必要とする、それがあるまで証言調書は引き渡さない」と対応し、東京地検に対し、「最高裁のお墨付きによる不起訴宣明書」を出すよう促した。 これに基づき、時の検察は、最高裁に対して「不起訴宣明書」を出すよう促している。ここでも最高裁は、その手法的是非を詮議するべきであったにも関わらず、論ずるよりも行動を先走らせることになる。その結果、「検事総長宣明書に対する最高裁長官の保証書簡」という「最高裁による不起訴宣明書」が全員一致で出されることになった。 こうした日本の検察と最高裁と米国裁判所の遣り取りは、全く「違法を正すべき職責を任務とする機関の対応としては自制すべきであった」が、結果的にこうした不当な手法を合意させ、これにより米国裁判所にコーチャンらの証人尋問をさせることになった。この「不起訴宣明」経過は、「アメリカと日本の司法官僚の出来レース」ぶりを物語っている。 ちなみに、逆の事例を考えてみれば分かりやすい。コーチャン等の嘱託尋問のようなことが仮にアメリカから日本に要請されて、日本の裁判官が日本にいる日本人に対して将来ともアメリカの法廷に出廷しなくても良いからと保障して尋問調書を作った場合に、アメリカの法廷がそのような調書を認めることは絶対にないように思われる。 かの藤原弘達氏にして、「角栄、もうええかげんにせんかい」の中で次のように述べている。
井上正治氏は著書「田中角栄は無罪である」(講談社、1985.6月初版.)で次のように述べている。
|
| 【「コーチャン証言の真偽性問題」(コーチャン証言の「真実性担保」の違法性)】 | ||
|
このようにして引き為された「コーチャン証言の真実性(真偽性)」が詮議されねばならない。 「コーチャンらがいかなる証言をしようとも免責となり、不利益に対して黙秘権を行使して証言を拒んだ場合であっても、同人らに対し『起訴しない』という約束をして証言させる」という「不起訴約束による供述誘引」策は、もともと真実を引き出すための便宜的な捜査手法として導入された筈であるが、これが逆に謀略的に使われるという可能性が無い訳ではない。否、はっきりと謀略に使われたという可能性がある。もし、これが意図的に為されたと想定した場合、この法理論そのものの危うさ、恣意的権力理論性が認識されねばならない。 新野哲也氏の「誰が角栄を殺したのか」は次のように指摘している。
|
| 【コーチャン証言の重大疑義】 |
| コーチャンは、証言の中で、「一体誰に支払うのか」という質問に対して、あるときは「リベラル・デモクラティック・パーティー(自民党)」、あるときはフ「プライム・ミニスターズ・オフィス(首相事務所)」、あるときは「セクレタリーアート(秘書官)」と述べ、相手先を替えている。このことは、誰に支払うか、支払ったのか明確でないことを意味している。 この発言と、児玉には成功報酬として直後に13億円が支払われており、角栄側には8ヶ月も経過して、秘書の榎本の強い催促により支払われることになったという検事調書経過と、実際の授受現場のフィクション性をあわせて考えれば、請託が無かったことを裏付けることになり、その意味で注目されるコーチャン証言の杜撰さを物語る重要証言内容である。より具体的には「コーチャン証言、クラッター証言をどう見るべきか考」で解析する。 |
| 【公判外の供述書面を証拠採用するという違法性】 |
| 憲法第37条第2項の権利を踏まえて,それに反する公判外の供述書面は原則として「証拠にすることができない」という原則が刑訴法320条にも謳ってあるという考えに立てば、当然これに抵触する。同法321条にいう除外規定は、憲法の趣旨からいってあくまで厳格に限定して解釈されなければならないということが当然の流れであろう。これが321条の解釈論についての基本的な姿勢とされるべきである。 |
| 【元最高裁長官の発言の越権発言の違法性】 |
| 【小森義久氏の「遥かなる日本」での指摘】 | ||
小森義久氏の「遥かなる日本」(毎日新聞社)は、この時の刑事免責問題について次のように記している。
|
| 【藤林元最高裁長官の政治的立ち回り考】 |
|
2007.4.24日、元最高裁長官の藤林益三(ふじばやし・えきぞう)氏が心不全のため東京都内の病院で死去した(享年99歳)。藤林氏は、1907(明治40).8.26日、京都府船井郡五ヶ荘村田原(現・南丹市日吉町)で誕生。父に3歳で死別。郷里の篤志家の援助で、園部尋常高等小、京都三中(現・京都府立山城高等学校)、第三高等学校、
東京帝国大学法学部を卒業。1932年に弁護士登録。協和銀行、日本興業銀行の顧問弁護士を務める。第1東京弁護士会副会長や司法研修所教官などを歴任した。 1976年、ロッキード事件の捜査段階で、米国の贈賄側関係者の調書を入手するために検事総長が確約した関係者の不起訴を、最高裁としても保証する異例の「不起訴宣明書」を出した。 |
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)